みんなで大家さんとは?仕組みと注目を集めた理由
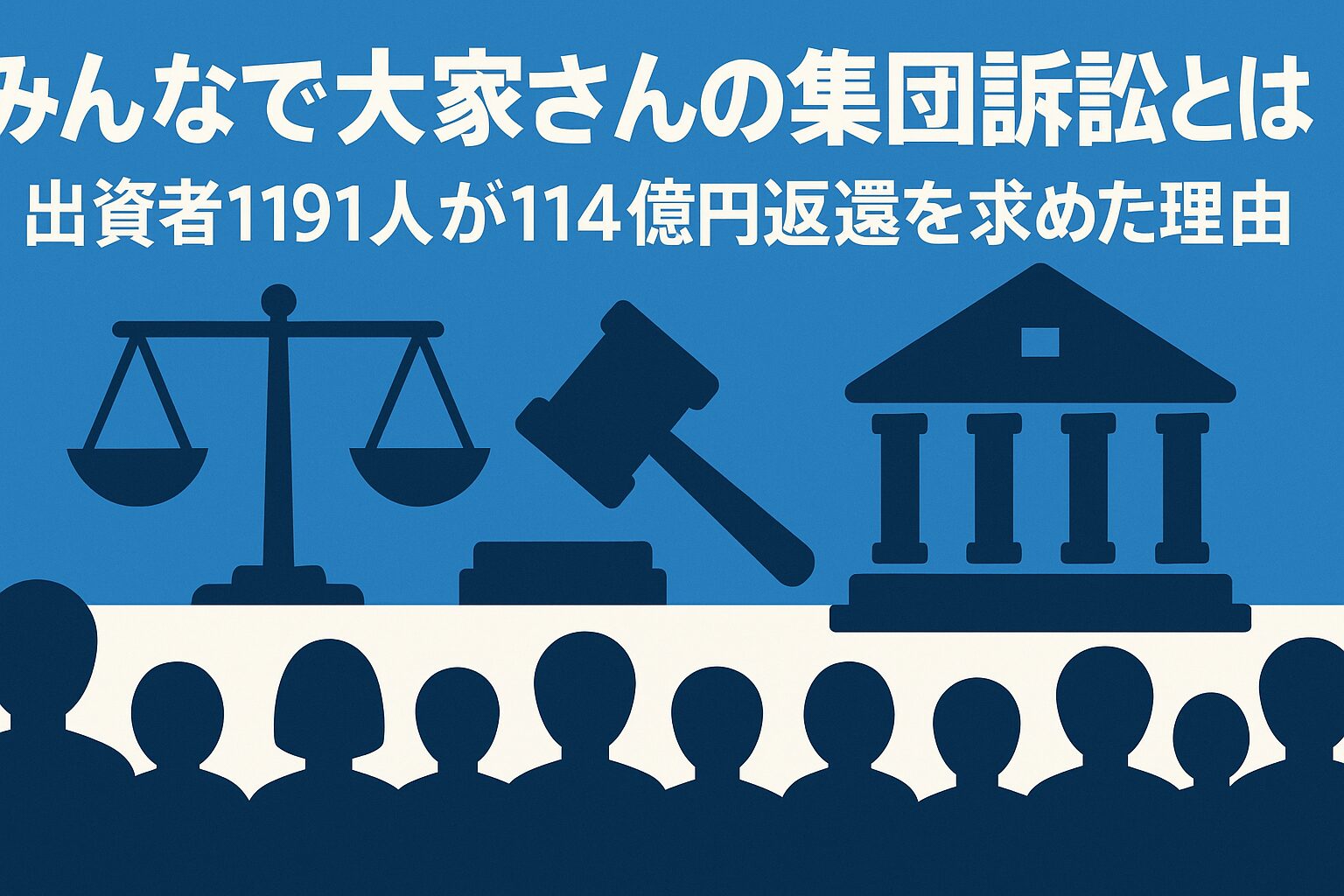
「みんなで大家さん」は、不動産投資を身近に感じられる仕組みとして多くの個人投資家から注目を集めてきた商品です。
運営会社は東京都に本社を置く都市綜研インベストファンド株式会社で、全国の商業施設やマンションなどを運用し、出資者に分配金を支払う「不動産小口化商品」として展開されています。
この仕組みの特徴は、少額から始められる“共同出資型不動産投資”です。
従来の不動産投資のように数千万円単位の資金を用意する必要がなく、1口100万円前後の出資で不動産の“大家”になれる点が大きな魅力でした。
投資家は運用期間中に賃料収入や売却益に基づく配当(分配金)を受け取る仕組みで、広告では「安定した利回り」「元本割れリスクが低い」などの文言が強調されていました。
また、みんなで大家さんは累計出資額1,000億円を超える人気を誇り、シニア層や主婦層、退職金を運用したい個人投資家から広く資金を集めてきました。
パンフレットやセミナーでは「実物資産に裏付けされた安心感」がアピールされ、
「銀行預金より利回りが高く、リスクも限定的」という印象を与える設計となっていたのです。
しかし、こうした“安定性”のイメージの裏で、
一部のファンドでは分配金の遅延や運用実態の不透明さが指摘され始めました。
これが後に、出資者からの不信感と、最終的に集団訴訟へとつながる引き金となります。
つまり「みんなで大家さん」は、
・誰でも簡単に始められる不動産投資として人気を集めた一方で、
・運用内容や資金管理の透明性に課題が残った投資商品でした。
投資そのものの構造を理解しておくことが、今回の「集団提訴」を正しく読み解くための第一歩です。
みんなで大家さん集団提訴の概要と経緯

2025年11月、全国の出資者1,191人が合計約114億円の返還を求めて大阪地方裁判所に集団提訴しました。
対象となったのは、不動産投資商品「みんなで大家さん」を運営する都市綜研インベストファンド株式会社(東京都千代田区)です。
この訴訟の中心にあるのは、出資金の返還が長期間にわたり滞っていること。
出資者の多くは「契約満了を迎えても元本が返ってこない」「分配金の支払いが停止している」といった問題を訴えています。
出資者の中には高齢者や退職金を運用していた人も多く、全国から被害弁護団に相談が相次ぎました。
弁護団によると、出資者が求めているのは単なる配当金ではなく、契約解除に伴う元本の返還請求です。
つまり「運用は終了しているのに返金がない」という構造的なトラブルが問題の核心にあります。
投資家の一部はすでに個別で提訴していましたが、今回は全国規模での集団訴訟として動き出した点が大きな特徴です。
背景には、2024年6月に大阪府が都市綜研インベストファンドに対して業務の一部停止命令を出したことがあります。
これは、同社が投資勧誘の際に「元本保証があるような説明」をしていた可能性や、
ファンド運用の実態が投資家に十分に開示されていなかった点を問題視したものでした。
行政処分以降、信頼が揺らぎ、資金返還の遅れが表面化していったとされています。
今回の訴訟では、契約解除・損害賠償・資金返還が求められており、
もし原告側が勝訴した場合、今後の不動産クラウドファンディング市場全体にも影響を与える可能性があります。
また、弁護団は今後も新たな参加者を募る方針を示しており、
「被害は氷山の一角。出資金が戻らないまま困惑している投資家は全国に多数存在する」と説明しています。
“安定した不動産収益”を掲げて多くの信頼を集めてきた「みんなで大家さん」。
しかし今、そのブランドは大きな岐路に立たされています。
分配金遅延と資金トラブルの原因

「みんなで大家さん」がここまで大規模な訴訟に発展した背景には、分配金の遅延と資金の流れの不透明さがあります。
本来、不動産投資ファンドでは、運用期間中に賃料収入などから定期的に分配金が支払われる仕組みです。
しかし一部のファンドでは、予定日に分配金が支払われない、あるいは支払額が当初より大幅に減少しているという事態が続いていました。
投資家の不安をさらに高めたのは、運営側からの説明不足でした。
分配金の遅れに関する通知は形式的なメールや曖昧な説明にとどまり、
「なぜ支払われないのか」「今後の見通しはあるのか」といった核心的な情報は十分に開示されなかったのです。
一部では、出資金が新たなファンドの運用資金に転用されていた可能性も指摘されています。
さらに問題を複雑にしたのが、物件売却や再投資のプロセスです。
本来、ファンドの運用期間が終了すれば、物件の売却や資金の精算を経て出資金が返還されるのが一般的です。
しかし、一部の案件では「次のファンドへ自動的に再投資される」形となり、
投資家が意図せず資金を長期間拘束されるケースが発生しました。
これにより、
- 契約期間終了後も元本が返還されない
- 分配金が数か月、場合によっては1年以上遅延
- 出資金の運用実態が不明瞭
という三重の問題が浮き彫りになりました。
こうした状況を受けて、出資者の中には「運営会社が十分な説明責任を果たしていない」として、弁護士を通じた法的手段に踏み切る動きが加速しました。
行政側もこの問題を重く見ています。
2024年6月には大阪府が都市綜研インベストファンドに対し、業務の一部停止命令を出しました。
この行政処分は、投資勧誘の際に「元本が保証されるような誤解を与える説明」を行っていた点などを問題視したものです。
つまり、「安全」「確実」といった訴求が、金融商品取引法上の適切な説明義務を逸脱していたと判断されたのです。
この一連の問題は、投資家の信頼を大きく損なう結果となりました。
行政処分と運営会社の対応
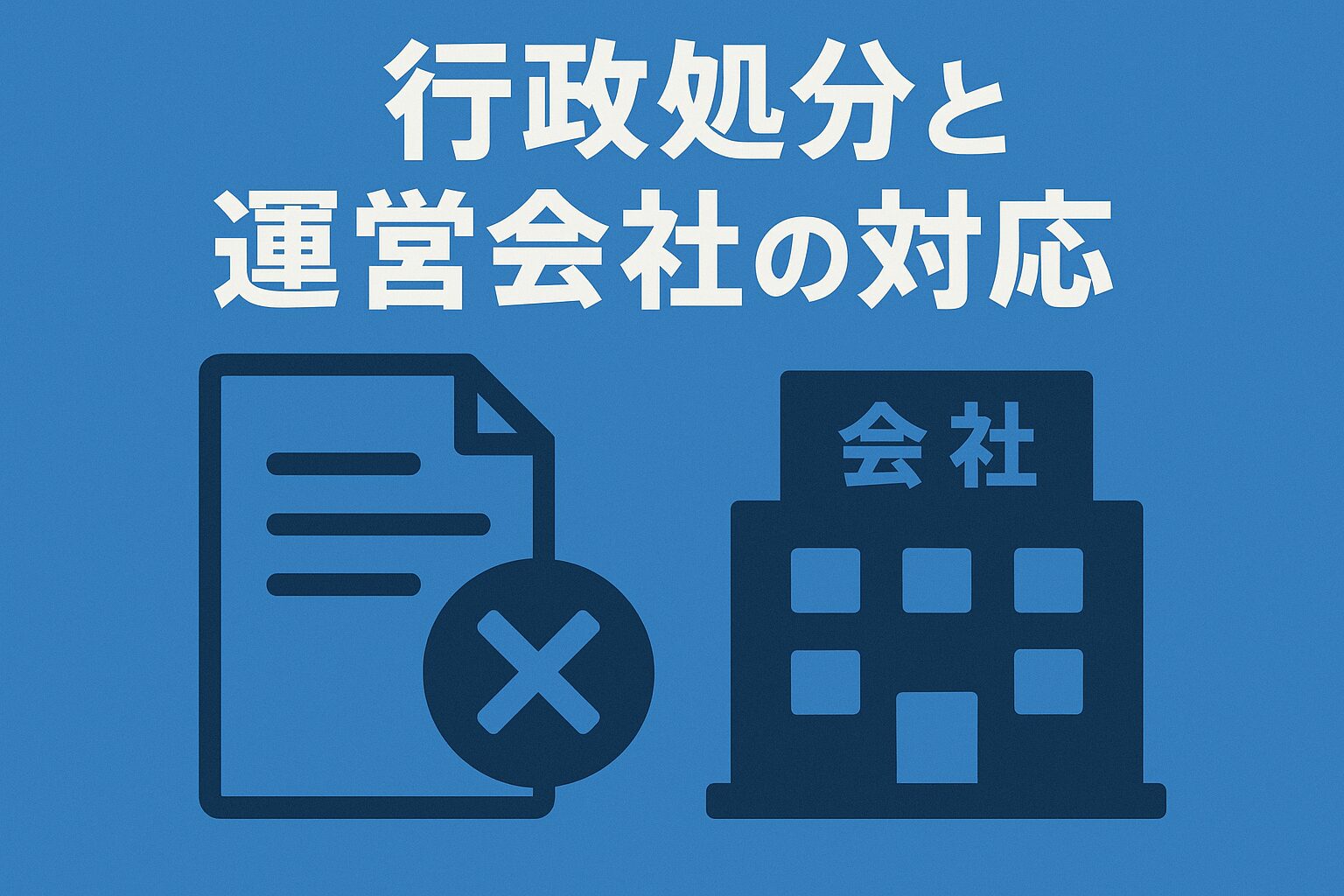
2024年6月、大阪府は「みんなで大家さん」を運営する都市綜研インベストファンド株式会社に対して、
金融商品取引法に基づく業務の一部停止命令(3か月間)を下しました。
この行政処分が、今回の集団訴訟へとつながる大きな転換点となりました。
処分の理由は、投資家への誤解を招く説明と情報開示の不備。
具体的には、出資勧誘の際に「元本保証があるような表現」や「安全で確実な利回りが得られる」といった内容が使われていた点が問題視されました。
金融商品取引法では、投資リスクを明確に説明しなければならない義務があり、
これに違反したと認定されたのです。
また、ファンドの運用状況や収益構造についても、投資家が十分に確認できない状態が続いていました。
「どの物件からどの程度の収益が出ているのか」
「なぜ分配金が遅れているのか」
といった基本的な情報が開示されず、出資者は不安を募らせるばかりでした。
行政処分を受けた後、同社は「改善計画書」を提出し、
投資家向け説明体制の見直しや社内コンプライアンス強化を公表しました。
しかし、現場レベルでの変化は限定的で、
その後も「返還請求への回答が遅い」「電話がつながらない」といった苦情が相次ぎました。
さらに、親会社である都市綜研グループも投資家対応に追われましたが、
具体的な返還スケジュールや資産状況を明確に示すことはできず、
不信感は拡大の一途をたどりました。
結果的に、行政処分から約1年後、
返還されない出資金を抱える投資家が全国的に団結し、
2025年11月の大規模集団提訴へと発展したのです。
この一連の流れは、
「法的規制の不備」と「投資家保護の限界」を浮き彫りにしました。
集団訴訟の争点と今後の見通し
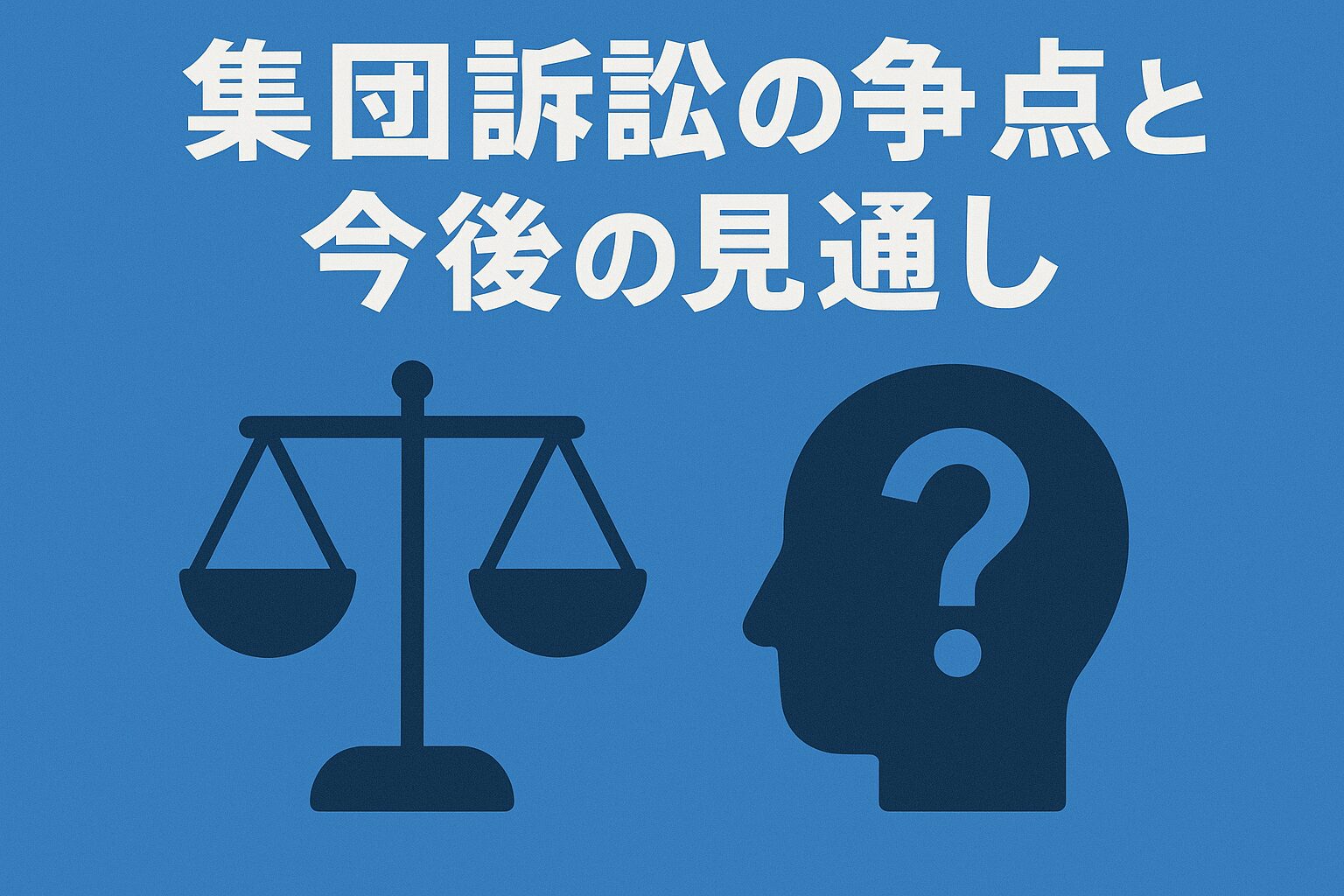
今回の「みんなで大家さん」集団訴訟では、主に3つの争点が注目されています。
それは、①契約の有効性、②運用実態の透明性、③説明義務違反の有無です。
これらは不動産クラウドファンディング全体にも影響を及ぼす、極めて重要な論点です。
① 契約の有効性と元本返還の義務
出資者側が主張している最大のポイントは、「契約が実質的に終了しているにもかかわらず、元本が返還されていない」という点です。
契約期間が満了した後は、本来であれば運用物件の売却や精算が行われ、出資金が返還される仕組みになっています。
しかし、実際には「運用継続」や「再投資」という名目で資金が拘束され続け、
出資者の意に反して返還が遅延しているケースが多数確認されています。
そのため、原告側は契約解除と元本返還を求める法的請求を行っているのです。
② 運用の透明性と資金の流れ
次に問題視されているのが、資金の流れが極めて不透明であるという点です。
どの物件にどれだけ投資され、どのように利益が分配されているのか――
これらの情報が投資家に十分に開示されていなかったことが訴訟の根幹にあります。
一部の弁護団関係者は、「新しい出資金が過去の分配金に充てられていた可能性もある」と指摘しており、
もしそれが事実であれば、金融商品取引法や資金決済法に抵触する恐れもあります。
③ 説明義務違反と誤認勧誘の問題
さらに焦点となるのが、投資勧誘時の説明義務違反です。
「元本保証がある」「損失の心配はほとんどない」といった説明を受けたとする出資者の証言が複数存在します。
こうした発言が事実であれば、投資判断に影響を与える「重要事項の不実告知」にあたる可能性が高く、
損害賠償請求の根拠となることが予想されます。
裁判の見通しと業界への影響
この裁判の行方は、不動産クラウドファンディング業界全体の信頼性を左右します。
もし原告側の主張が認められれば、同様の仕組みを採用する他社にも説明義務や情報開示の強化が求められるでしょう。
逆に、被告側が勝訴すれば「投資は自己責任」という原則が改めて強調される形になります。
現時点では判決の見通しは立っていませんが、
弁護団は「投資家保護の枠組みを問う象徴的な訴訟になる」とコメントしています。
投資家が学ぶべき教訓と再発防止のポイント
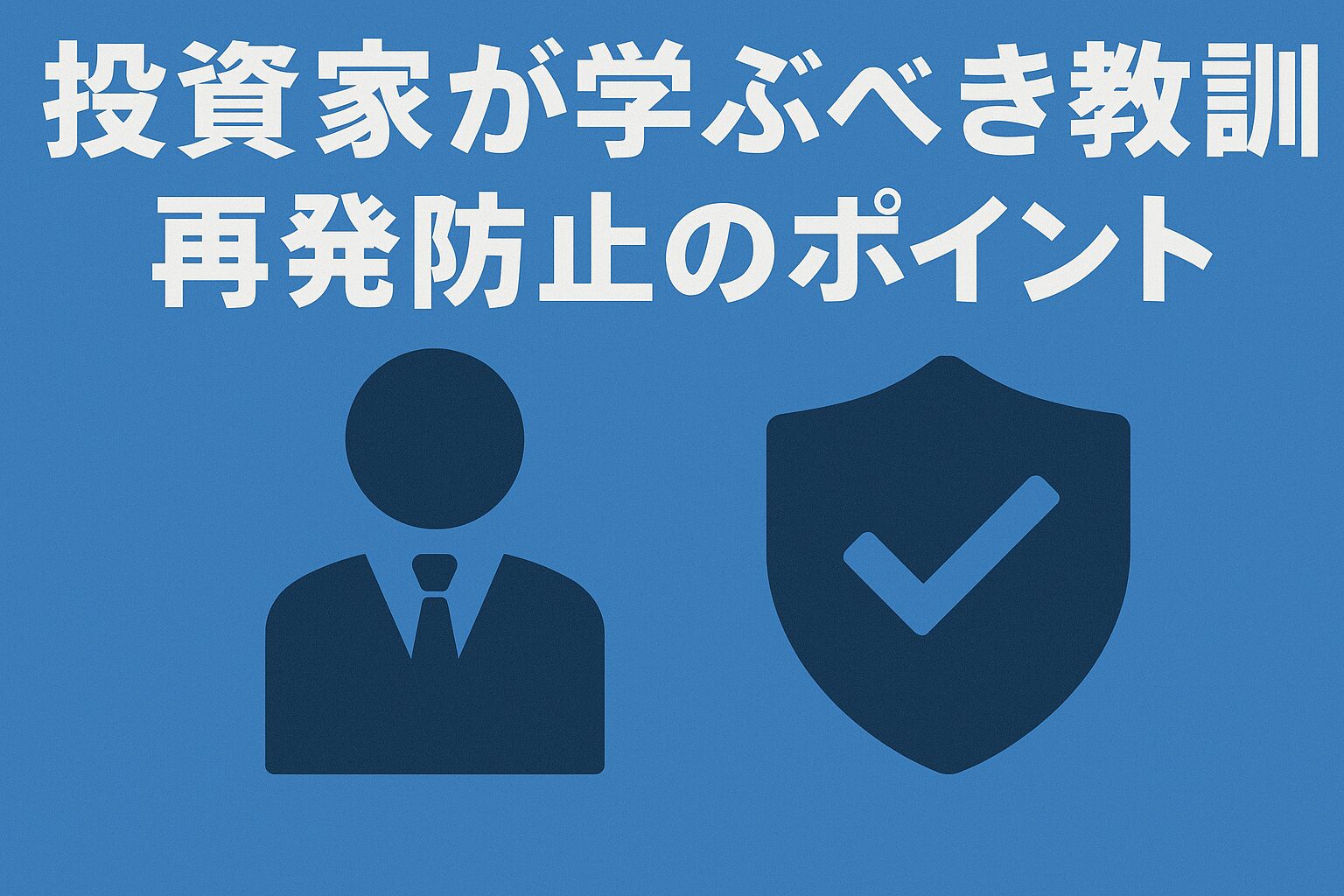
今回の「みんなで大家さん」集団提訴は、単なる一企業の問題ではなく、
投資家一人ひとりが“何を信じ、どう判断するか”を問う事件でもあります。
ここから得られる教訓は、今後の不動産クラウドファンディングや副業投資を検討するすべての人にとって重要です。
① 「元本保証」という言葉を鵜呑みにしない
最も大きな教訓は、“安全”を強調する宣伝文句ほど注意すべきという点です。
金融商品取引法では、元本保証をうたう投資商品は原則禁止されています。
にもかかわらず、「元本割れしない」「安定した利回り」といった表現を使う業者は後を絶ちません。
仮に悪意がなくとも、リスクを十分に理解せず契約してしまえば、損失は投資家自身が負うことになります。
パンフレットや説明会の言葉よりも、契約書とファンド規約を自分の目で確認することが不可欠です。
② 運用会社の“実態”を必ず調べる
投資前にチェックすべきは、運営会社の信頼性と財務状況です。
公式サイトや広告だけではなく、行政処分歴・登記情報・監査報告書などを調べましょう。
今回のように、業務停止命令を受けた企業が再び投資募集を行うケースもあり、
「大手グループだから安心」と思い込むのは危険です。
金融庁の登録業者リストや監督当局の公示を確認する習慣を持つことで、リスクを減らせます。
③ 分配金の“仕組み”を理解する
不動産ファンドの分配金は、物件の運用益から支払われるものです。
もし収益が出ていないのに分配金が支払われ続けている場合、
その原資が“新規出資者の資金”になっていないか注意が必要です。
これは「ポンジ・スキーム」と呼ばれる典型的な資金循環構造で、
長期的には破綻リスクが非常に高いモデルです。
④ 契約終了後の返還条件を確認する
出資前に「運用期間終了後にどう資金が返ってくるのか」を明確に理解することも大切です。
今回のケースでは、契約期間満了後も「再投資」扱いで資金が返還されない例が多発しました。
契約書に「自動継続」「再投資条項」といった文言がある場合は要注意です。
出資金の返還条件や解約手続きが不明確な場合は、契約前に必ず書面で確認しましょう。
⑤ 「口コミ」よりも「公式資料」を信じる
SNSや口コミサイトには多くの投資体験談が投稿されていますが、
中には広告目的や誇張された情報も含まれています。
信頼すべきは目に見える数値と公式資料。
利回りや資産残高、運用報告の公開状況など、
“第三者が確認できる情報”をもとに判断することが重要です。
この事件は、投資をする上での「信頼」と「自己防衛」のバランスを私たちに突きつけました。
そして同時に、投資教育や法的保護の必要性も再確認させる出来事でした。
まとめ 今回の提訴が投資市場に与える影響
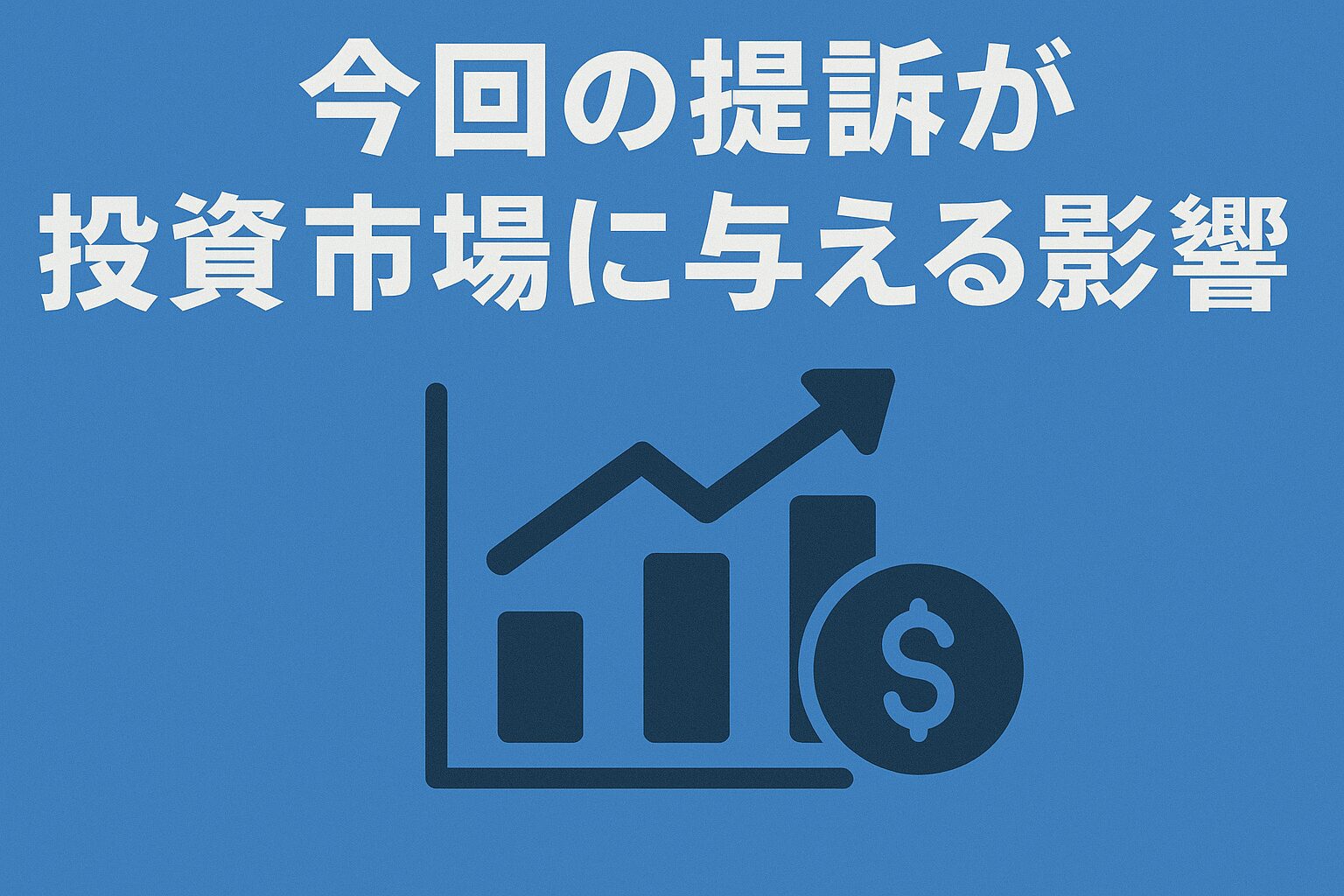
「みんなで大家さん」の集団提訴は、日本の不動産クラウドファンディング市場にとって歴史的な分岐点です。
これまで“手軽で安心”“元本割れしにくい”と宣伝されていた投資商品が、法廷で信頼性を問われる事態となりました。
この訴訟が示すのは、単に一企業の問題ではなく、投資家と事業者の情報格差という構造的課題です。
資金の流れが不透明なまま、出資者がリスクを正確に把握できない投資スキームが広がれば、
市場全体の信頼が失われ、健全な投資文化の育成にも悪影響を及ぼします。
同時に、この事件は「投資を自ら守る力」が求められる時代に入ったことも意味します。
法規制や金融庁の監督にも限界がある中で、
私たち個人投資家が情報を精査し、リスクを見極める力を持たなければなりません。
投資の本質は“リスクとリターンのバランス”にあります。
安易に「安全」「高利回り」といった言葉に飛びつかず、
仕組みを理解し、資金がどのように運用されているかを常に確認する姿勢が必要です。
この提訴をきっかけに、不動産投資型クラウドファンディングの制度見直しや情報開示の強化が進む可能性もあります。
しかし最も大切なのは、投資家自身が“学び、疑問を持つ姿勢”を忘れないことです。
「みんなで大家さん」事件は、信頼と透明性を欠いた投資がどれほどの混乱を生むのかを示す象徴的な出来事となりました。
これを他人事にせず、次の投資を考えるきっかけに変えること――
それこそが、この出来事から私たちが得るべき最大の教訓です。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。