※本ページはプロモーションが含まれています。
第一章 JEPQとは何か/基本情報と仕組み
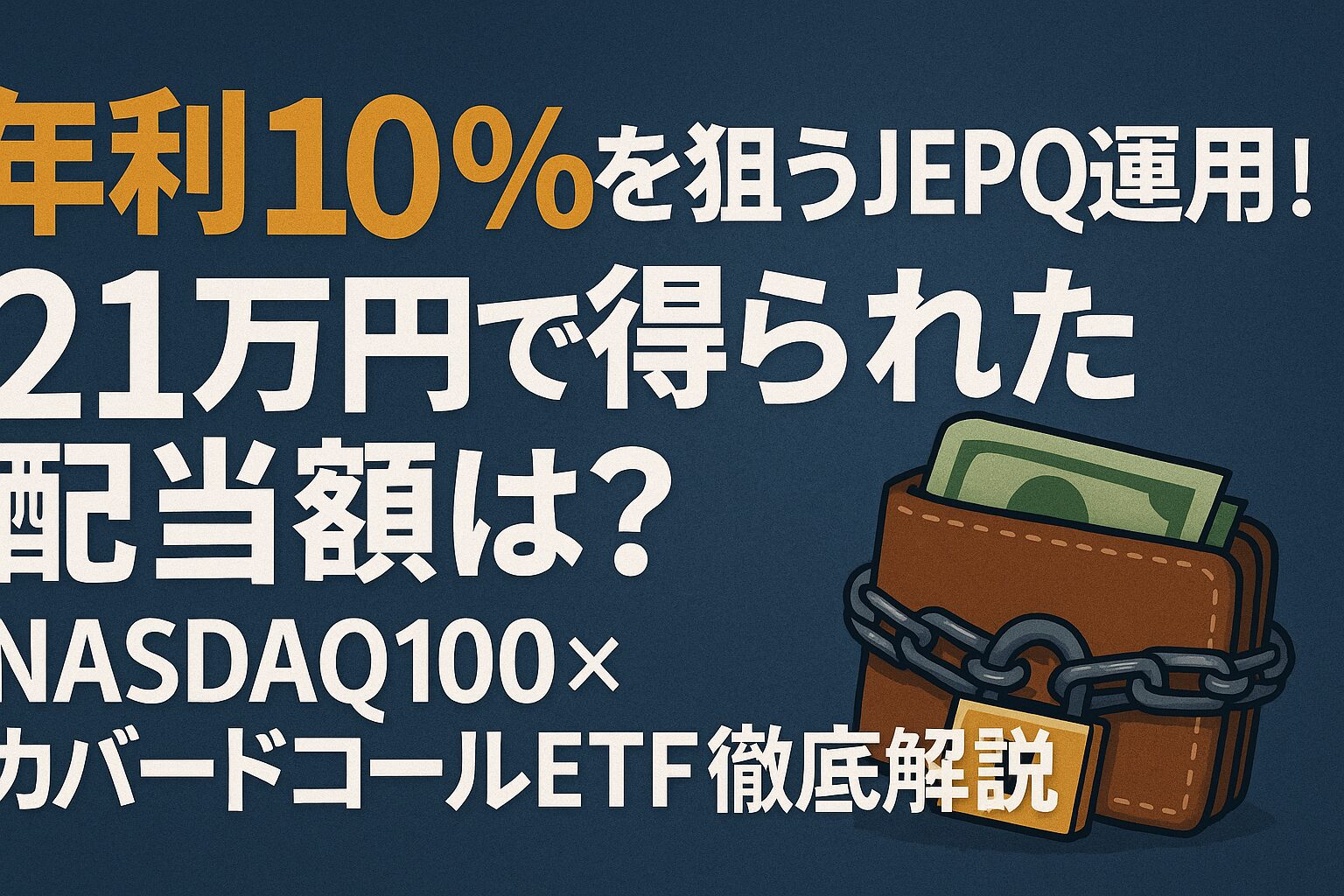
JEPQは、正式名称を「JPモルガン・NASDAQエクイティ・プレミアム・インカムETF」といい、米国の大手金融機関JPモルガン・アセット・マネジメントが運用するETF(上場投資信託)です。
2022年に登場して以来、「年利10%超の高配当ETF」として注目を集めています。
ちなみに最近、日本でも登場しました!
詳しくはこちらをご覧ください👇
このETFは、米国の代表的な株価指数「NASDAQ100」に連動しつつ、カバードコール戦略を活用して毎月の分配金(インカム収益)を投資家に還元する仕組みです。
つまり、ハイテク株の成長性を取り込みながら、オプション取引による安定的な収入を得るという「攻守のバランスを取ったETF」といえます。
JEPQの投資対象は、NASDAQ100指数に採用されている企業の株式です。
Microsoft、Apple、NVIDIA、Amazonなど、世界をリードする巨大テック企業が中心で、米国株の成長をけん引してきた名だたる銘柄が組み込まれています。
そのため、単なる高配当ETFとは異なり、テクノロジー株の値上がりも一部享受できる点が大きな魅力です。
さらに特徴的なのは、毎月分配型ETFであるということです。
多くのETFが年1回または年4回の分配を行う中、JEPQは毎月配当を受け取れるため、キャッシュフローを重視する投資家や、配当生活・セミリタイアを目指す層からの人気が非常に高まっています。
2025年時点の主要データを見てみると、以下のようなスペックです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
| ベンチマーク | NASDAQ100 |
| 信託報酬 | 年率0.35% |
| 分配頻度 | 毎月 |
| 分配利回り | 約10〜11%(2025年初頭時点) |
| 総資産額 | 約300億ドル(約4兆円) |
| 運用戦略 | カバードコール戦略 |
| 為替 | 米ドル建て(円安時に影響あり) |
この数値からも分かる通り、JEPQは規模・流動性ともに十分で、短期間で世界有数の資金流入を記録したETFのひとつです。
特に「高配当×テック株」という珍しい組み合わせが、投資家の関心を集めている理由です。
まずはこちらをご覧ください👇
第二章 JEPQの運用戦略:カバードコールとは何か

JEPQの最大の特徴は「カバードコール戦略(Covered Call Strategy)」を採用している点です。
これは、ETFが保有している株式を担保に、あらかじめ決められた価格でその株を買う権利(コールオプション)を売ることで、プレミアム(オプション料)を受け取る手法です。
このプレミアムが、投資家に分配される「毎月の配当金(分配金)」の原資となります。
一見難しそうに聞こえますが、仕組みを分かりやすく言えばこうです。
- JEPQはNASDAQ100の株を保有します。
- 同時に「将来、一定の価格で株を買う権利」を他の投資家に売ります。
- その権利を売った代わりに得た“手数料”のようなもの(オプションプレミアム)が、安定的な収入になります。
つまり、株価が急激に上がらなくても、保有しているだけで現金収入を得られる構造を持っているのです。
これこそが、JEPQが「毎月高配当を実現している理由」です。
ただし、当然デメリットも存在します。
株価が大きく上昇した場合、コールオプションを買った投資家が権利を行使すれば、JEPQは保有株をあらかじめ決めた“安い価格”で売らなければなりません。
つまり、株価上昇の利益(キャピタルゲイン)を逃すリスクがあるのです。
そのため、カバードコール戦略は「急上昇相場では利益が伸びにくい一方、横ばいや下落相場では強い」という特徴があります。
実際、NASDAQのようなボラティリティの高い市場では、価格変動を抑えながらインカムを安定的に得るという戦略が非常に有効に機能します。
また、JEPQはすべての保有株に対してカバードコールをかけているわけではありません。
オプション比率を100%にしていない点も特徴的です。これにより、一部の銘柄については株価上昇の恩恵も受けられる構造になっています。
つまり、完全に「防御型」ではなく、「収益+成長」のバランスを狙ったETFといえるのです。
まとめると、カバードコール戦略とは――
- 安定収入(オプションプレミアム)を得られる
- 株価急上昇時は利益を取り逃がすリスクがある
- 横ばい〜下落相場で安定性を発揮する
という、まさに“安定型の高配当戦略”です。
第三章 JEPQのメリット・魅力ポイント

JEPQは「NASDAQ100に連動しながら毎月10%超の利回りを狙える」という、他のETFにはない独自の強みを持っています。
ここでは、投資家から支持される理由と具体的なメリットを整理します。
1. 毎月の分配金でキャッシュフローが安定
JEPQの最大の魅力は、毎月分配金を受け取れることです。
年に一度の配当ではなく、毎月安定したインカムが得られるため、生活費の一部として活用したり、再投資に回すことで複利効果を高めたりすることが可能です。
2024年〜2025年のデータでは、分配利回りはおおむね10〜11%台を維持しており、米国ETFの中でも高水準。
例えば21万円を投資した場合、1年間でおよそ2万円強の配当を受け取る計算となります。定期収入型のETFとしては極めて魅力的です。
2. NASDAQ100の成長性を部分的に享受できる
JEPQはNASDAQ100を投資対象としているため、構成銘柄にはMicrosoft、Apple、NVIDIA、Amazonなど、世界を代表するハイテク企業が並びます。
カバードコールを100%ではなく部分的に行っているため、株価の上昇分も一部取り込むことが可能です。
つまり、完全な守りではなく「守りながら攻める」ETFなのです。
3. オプションプレミアムで下落相場にも強い
カバードコール戦略により、株価が横ばいまたは下落してもオプション料(プレミアム)による収入が得られる点が強みです。
実際、2024年のNASDAQ調整局面においてもJEPQは高い分配利回りを維持しており、価格下落の影響を緩和する役割を果たしました。
4. 高い流動性と安定した運用規模
JEPQは登場からわずか数年で純資産総額約300億ドル(約4兆円)を突破しました。
世界的に見ても、ETF全体の中で資金流入額がトップ10に入るほど人気があります。
流動性が高いということは、売買がスムーズに行えるだけでなく、運用の安定性と信頼性にも直結します。
長期保有を前提とするETFでは、この点は非常に重要です。
5. 米国ETFの中では信託報酬が低コスト
JEPQの信託報酬は年率0.35%。
同じカバードコール型ETFである「QYLD」の0.6%と比較すると、運用コストが抑えられていることがわかります。
高配当を維持しながらも低コストという点は、長期投資家にとって大きな魅力です。
6. 投資モチベーションを維持しやすい
高配当ETFのもう一つの魅力は、定期的にリターンを実感できる点です。
JEPQの場合、毎月の分配金が振り込まれるたびに「投資している実感」が得られ、モチベーションの維持につながります。
特に、セミリタイアを目指す層やFIRE志向の投資家には、心理的リターンの面でもメリットがあります。
第四章 JEPQのデメリットと注意すべきリスク
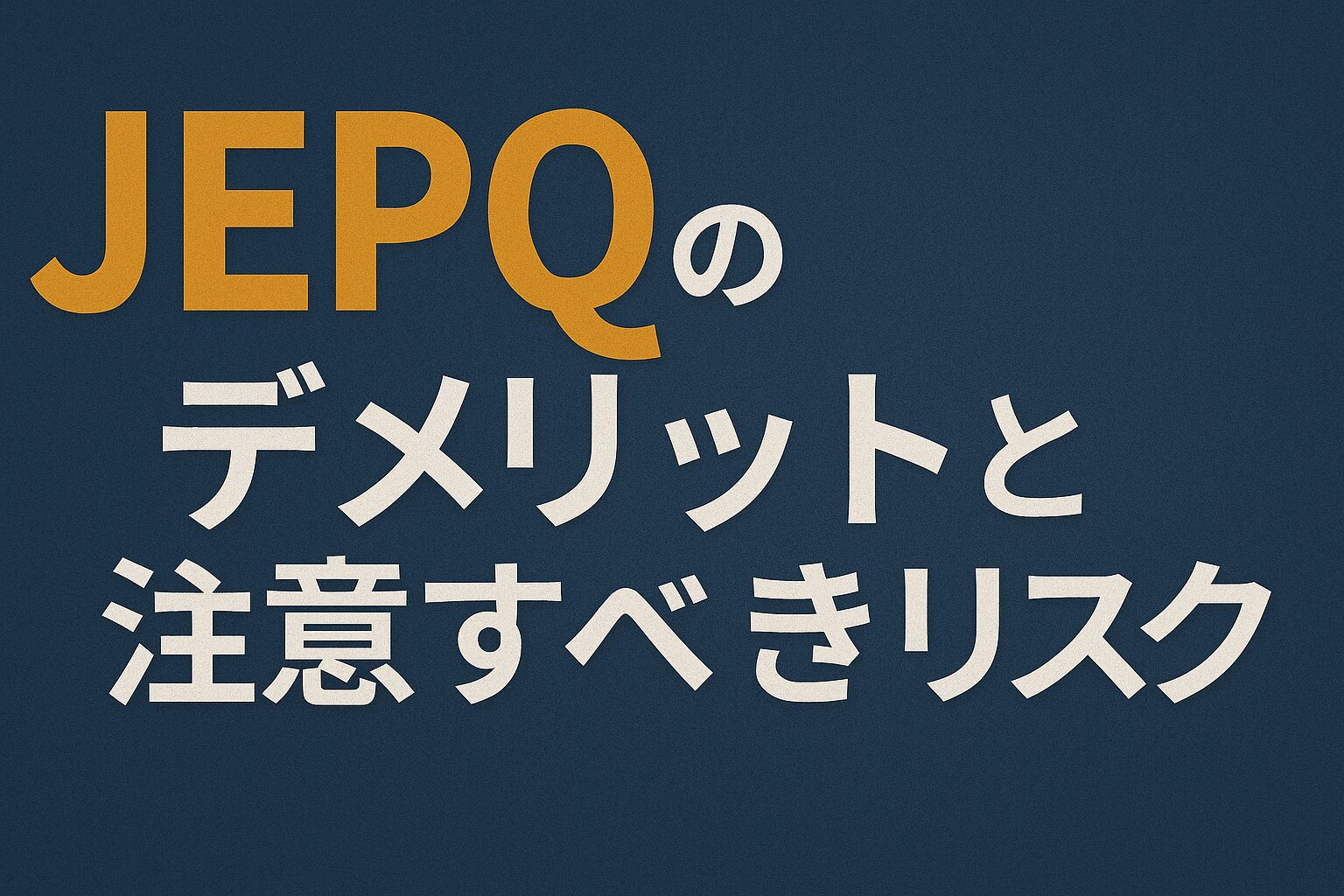
高配当・安定運用が魅力のJEPQですが、当然ながら万能ではありません。
特徴を正しく理解せずに購入すると、期待したリターンを得られないどころか、資産運用の足を引っ張る可能性もあります。
ここでは、投資前に押さえておくべき主なデメリットを整理します。
1. 株価上昇局面で利益が伸びにくい
カバードコール戦略の最大の弱点は、株価が大きく上昇したときにキャピタルゲインを取り逃がす点です。
コールオプションを売っているため、一定の価格を超えると保有株を安値で売らなければならず、急騰局面では値上がり益が限定されます。
実際、同じNASDAQ100をベースにした「QQQ」と比較すると、2023年以降の上昇局面では価格差が大きく開く結果となりました。
株価上昇を狙う成長型の投資家には不向きなETFです。
2. 分配金が変動する
JEPQは毎月分配型ですが、その金額は固定ではありません。市場環境やオプションプレミアムの収益によって配当額が上下する仕組みです。
特にNASDAQが強い相場ではプレミアム収入が減少する傾向があり、配当額も減る可能性があります。
安定収入を目的に投資する場合でも、「毎月一定ではない」点を理解しておく必要があります。
3. 為替リスクがある
JEPQは米ドル建てのETFです。そのため、円高・円安による為替変動の影響を受けます。
円安時に購入すると円換算の評価額は有利になりますが、円高に転じると配当や評価額が目減りします。
円で配当を受け取る場合、為替の影響を考慮した上で、長期視点でのリスク分散が重要です。
4. 二重課税が発生する
米国ETFの宿命ともいえるのが二重課税です。
JEPQからの分配金には、まず米国で約10%の源泉徴収がかかり、その後、日本国内で約20%の課税を受けます。
結果として配当の約3割が税金で差し引かれる計算になります。
外国税額控除の手続きを行えば米国分の税金は一部取り戻せますが、確定申告が必要になるため手間がかかります。
5. 信託報酬はインデックスETFより高め
JEPQの信託報酬は年率0.35%。
QYLDなどの同系統ETFよりは低いものの、S&P500やVTIといった一般的なインデックスETF(0.03〜0.1%前後)に比べるとやや高コストです。
ただし、毎月の高配当を得られることを考慮すれば、コストに見合う価値があるといえるでしょう。
6. 株価下落リスクは回避できない
カバードコール戦略は下落相場での損失を“やや緩和”する程度であり、株価の下落そのものを防ぐわけではありません。
NASDAQ100はハイテク企業が多く、ボラティリティ(価格変動)が高い傾向があります。
そのため、JEPQも一定の下落リスクを常に抱えていることを理解する必要があります。
これらのデメリットを踏まえると、JEPQは「株価の成長を狙う投資」よりも、「安定的なインカムを得たい投資」に向いている商品といえます。
第五章 JEPQの実績と配当利回りの現実

実際にJEPQへ投資した場合、どの程度の成果が得られるのか──ここでは、リアルな運用データをもとに、その実力を具体的に見ていきます。
1. 投資額21万円で得られた配当額
ある投資家の実例では、投資金額21万円(約26株)に対して、10ヶ月で受け取った配当総額は95.3ドル(税引後68.53ドル)でした。
年利換算するとおよそ10〜11%の実質利回り。
これは一般的な米国株ETFと比べても圧倒的な水準です。
しかも、この投資家は配当金を再投資することで、手出しなしで1株を追加購入することに成功。
配当が配当を生む“複利の力”を実感しています。
2. 配当推移と安定性
JEPQは2024年以降も毎月分配を継続しており、4月以降は年利換算で11%を超える高水準を維持しています。
ただし分配金は一定ではなく、市場のボラティリティに応じて上下します。
特にNASDAQの上昇が続く局面では、カバードコールのプレミアムが減少し、配当がやや下がる傾向があります。
それでも、過去1年間の平均分配金は1株あたり毎月約0.45〜0.55ドルと高水準をキープしており、安定したインカム源として優秀な実績を見せています。
3. 株価推移とトータルリターン
JEPQの株価は、2023年以降じわじわと上昇を続け、2025年時点では基準価格55〜57ドル台を推移しています。
一方で、同じNASDAQ連動型ETF「QQQ」と比較すると、価格上昇率では見劣りします。
これは、前章で述べた通りカバードコール戦略の特性によるものです。
しかし、JEPQは値上がりよりも配当収入を中心にリターンを積み上げる設計であり、長期のトータルリターンでは十分に競争力があります。
4. 配当金をどう活用するか
JEPQの分配金は、再投資と生活資金への活用のどちらにも向いています。
再投資すれば複利で資産が増え、長期的には効率的な資産形成が可能。
一方、セミリタイアやFIREを目指す層にとっては、毎月の安定キャッシュフローとして活用するのも有効です。
特に、投資モチベーションを維持する目的で少額から始める人には、「配当が届くたびに投資を実感できるETF」として好評です。
5. 楽天・JEPQ投資信託版の登場
2024年には「楽天・JEPQ(投資信託版)」が登場しました。
信託報酬は0.658%とETF版よりやや高めですが、
- 円建てで購入可能
- 100円から積立できる
- 確定申告不要(二重課税調整済み)
といった利便性が特徴です。
ETFに抵抗がある初心者でも、気軽にJEPQの仕組みに触れられる選択肢として人気が高まりつつあります。
6. 実績から見える結論
運用実績を踏まえると、JEPQは「安定した高配当を得たいが、リスクは抑えたい」投資家に最適なETFです。
毎月の分配金は精神的な安心感を与え、再投資すれば着実に資産が増えていく。
一方で、大きな株価上昇を狙うタイプの投資家には向かない──このバランスを理解することが、JEPQを使いこなすカギになります。
第六章 JEPQが向いている人・向いていない人
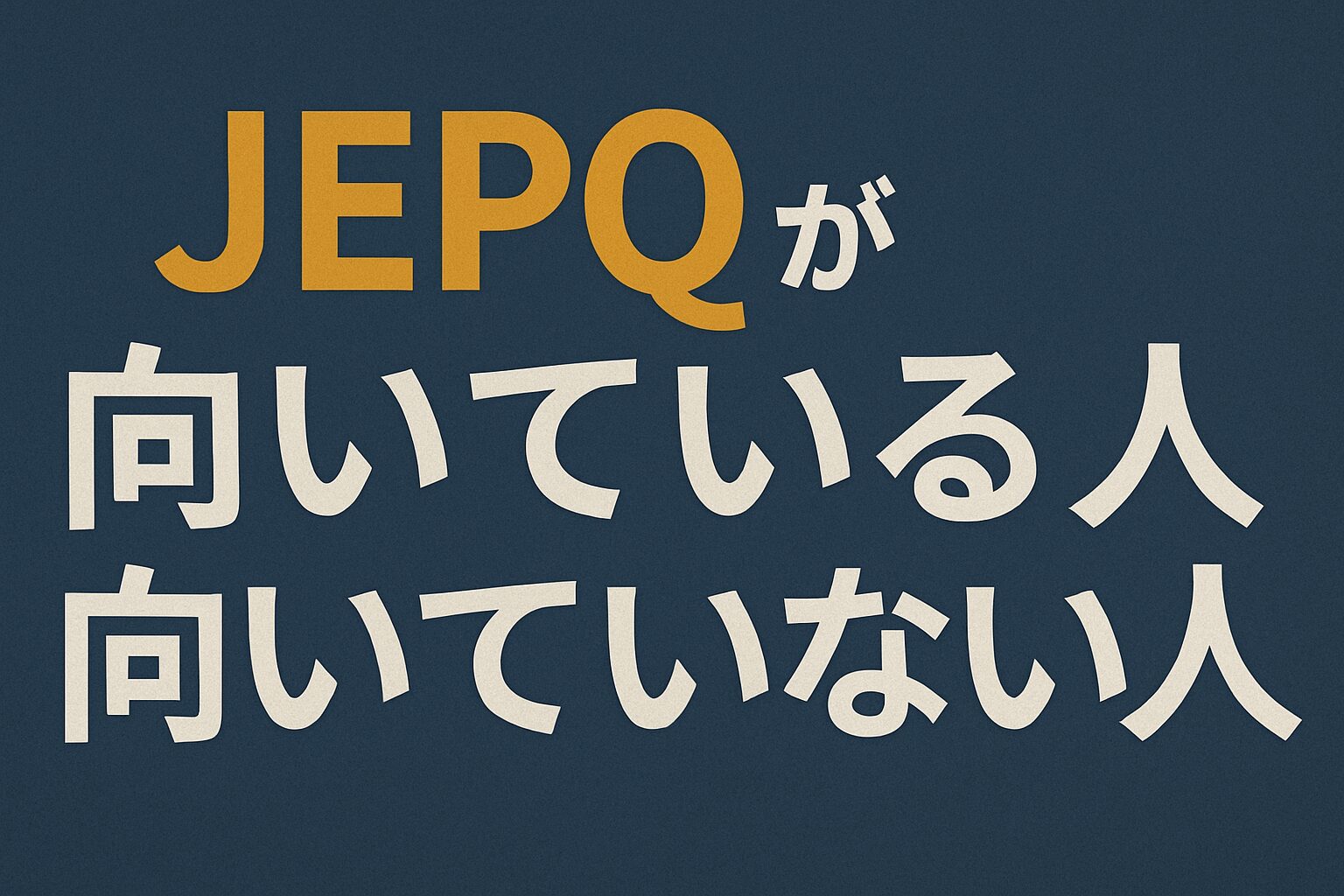
JEPQは「年利10%超の高配当ETF」という強烈な魅力を持ちつつも、投資家のタイプによってはメリットとデメリットが逆転します。
ここでは、どんな人がJEPQに向いているのか、そしてどんな人にはおすすめできないのかを具体的に整理します。
1. JEPQが向いている人
✅ 毎月の安定収入を重視する人
JEPQは毎月分配型ETFであり、安定的なキャッシュフローを求める投資家に最適です。
「配当を受け取りながら生活費の足しにしたい」「FIRE後の固定収入を確保したい」といった人には、JEPQの仕組みが非常にフィットします。
✅ 大きな値上がりより安定を求める人
株価の急上昇を狙うよりも、「下落に強く、価格変動を抑えたい」という安定志向の投資家にも向いています。
カバードコール戦略によりボラティリティ(価格変動)が小さくなる傾向があるため、資産が減りにくい安心感が得られます。
✅ 資産がある程度育っている中・上級者
JEPQは“配当生活を支えるETF”であり、資産形成の「守り」に強い商品です。
そのため、すでに投資経験があり、元本を減らさずに運用益を取りたい中〜上級者に向いています。
セミリタイア層や、老後の生活費補填を目的にした投資家にも好相性です。
✅ 投資モチベーションを維持したい人
毎月の配当が「投資の実感」として可視化されるため、長期投資を続けやすくなります。
「コツコツ積立が退屈」「成果を実感できずに挫折しそう」という人には、精神的にも良い刺激になります。
2. JEPQが向いていない人
⚠️ 株価上昇益を狙う人
JEPQはキャピタルゲイン(値上がり益)を狙うタイプのETFではありません。
カバードコール戦略の性質上、大きな上昇相場では利益が限定的になります。
長期的な値上がり重視の投資家は、QQQやVOOなど、純粋なインデックスETFの方が適しています。
⚠️ 投資初心者・少額投資の人
JEPQは癖のある構造を持っており、カバードコール戦略や税金の仕組みを理解せずに購入すると、思わぬ損失を抱えることもあります。
また、分配金に30%近い税金がかかるため、少額投資では税引き後の手取りが少なく感じる場合もあります。
⚠️ 円高リスクを避けたい人
JEPQは米ドル建てで運用されるため、円高局面では評価額が目減りする可能性があります。
為替リスクを避けたい人や、円建てで安定的に投資したい人は、「楽天・JEPQ(投資信託版)」の方が適しています。
3. 運用ポートフォリオでの立ち位置
JEPQは、「コア資産」ではなく「サテライト資産」として活用するのが理想です。
全体資産の10〜20%程度をJEPQに充てることで、リスクを分散しつつ、毎月の配当収入を楽しむことができます。
資産形成初期の人にとっては“育てる投資”よりも“守る投資”の位置づけで考えると良いでしょう。
第七章 JEPQとQYLDの比較と使い分け
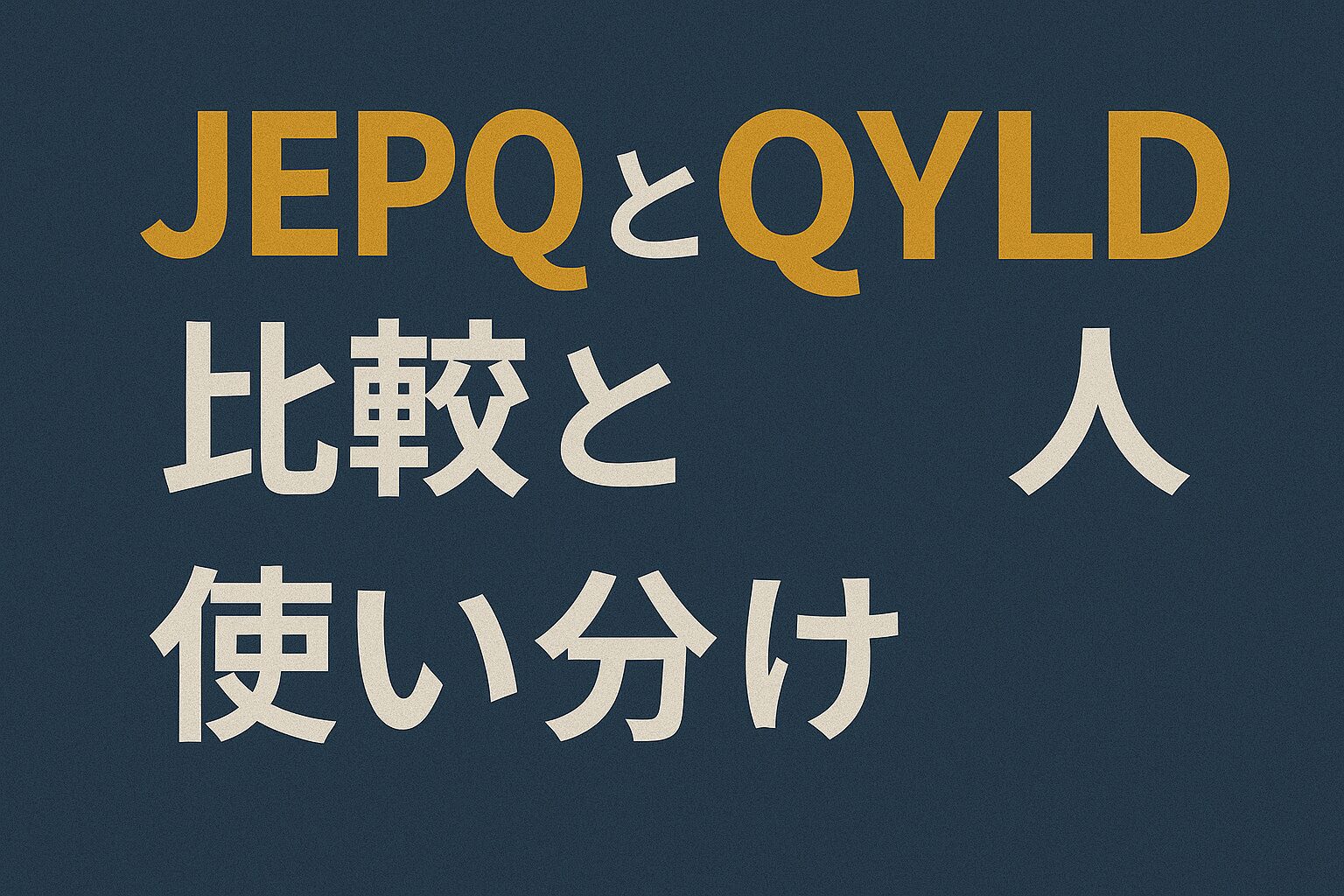
JEPQとよく比較されるのが、グローバルX社が運用する「QYLD(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)」です。
どちらもNASDAQ100を対象にしたカバードコール型ETFですが、戦略の違いによってリターンやリスクの性質が大きく異なります。
ここでは、2つのETFを徹底的に比較し、それぞれの特徴と使い分け方を解説します。
1. 基本スペック比較
| 項目 | JEPQ | QYLD |
|---|---|---|
| 運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント | グローバルX社 |
| 投資対象 | NASDAQ100 | NASDAQ100 |
| カバードコール比率 | 約70〜90% | 約100%(全額) |
| 信託報酬 | 0.35% | 0.6% |
| 分配頻度 | 毎月 | 毎月 |
| 分配利回り(2025年時点) | 約10〜11% | 約11〜12% |
| 値上がり益の余地 | 一部あり | ほぼなし |
| 運用方針 | キャピタル+インカムのバランス重視 | インカム最大化型 |
この表から分かる通り、JEPQはQYLDよりもやや攻めの姿勢を持っています。
カバードコールの比率を100%にしていないため、株価上昇時の利益を一部享受できます。
その分、分配金は若干少なめですが、トータルリターンではJEPQの方が優れている傾向があります。
2. パフォーマンスの違い
過去のチャートを比較すると、2023年以降、株高局面ではJEPQの方が明らかにパフォーマンスが良好です。
QYLDはオプション比率が100%のため、株価上昇をほとんど享受できず、横ばい〜下落局面での安定収益に特化しています。
一方、JEPQは上昇局面の恩恵を一部取り込めるため、株価上昇時でも置いていかれにくいバランス型ETFとして機能します。
3. 配当水準と安定性
QYLDの分配利回りは平均11〜12%と、JEPQよりやや高い水準です。
しかし、QYLDは「配当を出すために元本を削っている」ケースも多く、長期的にはトータルリターンが劣る傾向があります。
一方で、JEPQはオプション収入と株価成長の両方から配当を生み出すため、より持続的な分配金構造を持っています。
4. 税金・為替・運用コストの観点
どちらも米国ETFのため、分配金には米国課税(約10%)+日本課税(約20%)=約30%の二重課税がかかります。
ただし、JEPQは信託報酬が低く、長期運用時のコスト負担が少ない点で優位です。
また、円建て投資を希望する場合は「楽天・JEPQ投資信託版」を利用すれば、為替や確定申告の手間を軽減できます。
5. どちらを選ぶべきか
結論としては、投資目的によって使い分けるのが最適です。
| タイプ | 向いているETF | 理由 |
|---|---|---|
| 安定した高配当を重視 | QYLD | キャピタルを犠牲にしても毎月の収入を最大化 |
| 株価上昇も取り込みたい | JEPQ | 成長性とインカムの両立を狙える |
| セミリタイア・FIRE層 | JEPQ+QYLD併用 | 毎月配当+リスク分散のバランス最適化 |
| 投資初心者 | 楽天・JEPQ投資信託版 | 円建て・100円単位で始められる簡易版 |
6. 実践的な活用法
多くの投資家は、JEPQとQYLDを組み合わせて「安定+成長のハイブリッド運用」を実践しています。
たとえば、ポートフォリオの比率を
- JEPQ:60%(成長+安定)
- QYLD:40%(高配当重視)
とすることで、インカムを確保しつつ値上がり益も狙える構成が可能です。
第八章 JEPQを最大限に活かす運用戦略

JEPQは、単に「高配当ETFだから買う」ではなく、戦略的に運用してこそ真価を発揮する商品です。
ここでは、買い時・保有戦略・再投資のタイミングといった実践的なポイントを整理します。
1. 買い時は「株価調整×円高」のタイミング
JEPQはNASDAQ100をベースにしているため、米国市場全体の影響を強く受けます。
株価が調整局面に入ったとき、あるいは為替が円高方向に振れたときが最適な買い時です。
円高局面では同じドル建てETFでも日本円換算価格が安くなるため、割安で購入できます。
高配当ETFであっても、エントリーポイントを工夫するだけで長期の利回りを数%押し上げることが可能です。
2. 基本は「長期保有+放置」でOK
JEPQは毎月の分配金で成果を感じやすいため、頻繁に売買する必要はありません。
市場環境によって配当額は変動しますが、1年以上の長期保有で平均利回り10%前後を維持しています。
相場の上下に一喜一憂するより、「配当を受け取りながら再投資する」スタイルが理想です。
3. 再投資で複利を最大化
JEPQの魅力は、受け取った分配金をそのまま再投資することで複利効果を得られる点です。
たとえば年利10%で運用し、配当を再投資した場合、10年後には元本が約2.6倍に成長します。
配当金をそのまま使うのではなく、「再投資 → 保有株数を増やす → 分配金も増える」という好循環を作ることが重要です。
4. 為替と税金を意識したリバランス
米国ETFはドル建てのため、為替レートによって実質リターンが変わります。
円安が続いている間は、配当金を円転せずドルのまま再投資する方が効率的です。
また、年末には配当課税の影響を考慮し、外国税額控除の申請を行うことで手取りを増やせます。
手間を避けたい場合は、「楽天・JEPQ投資信託版」を使うのも賢い選択です。
5. サテライト運用でリスク分散
JEPQは高配当かつボラティリティが比較的低いETFですが、1本に集中投資するのは避けましょう。
全体ポートフォリオの10〜20%程度をJEPQに割り当て、残りはS&P500(VOO)や全世界株(VT)などのインデックスETFに分散することで、リスクを抑えながら安定したインカム収入を得ることができます。
6. 利用者が陥りやすい落とし穴
JEPQは「高配当=安定」というイメージで購入されがちですが、株価が下落すれば元本も減る点を忘れてはいけません。
また、配当利回り10%という数値に惹かれて短期売買を繰り返すと、為替差損や税金でリターンが削られます。
本来の魅力は「安定的なキャッシュフローと複利成長」にあるため、短期ではなく長期スパンで“育てる”投資として向き合うことが大切です。
7. モチベーション維持のコツ
毎月届く分配金を「自分へのご褒美」として捉えるのもおすすめです。
金額が少なくても、「投資でお金が生まれている」という実感は継続の原動力になります。
SNSなどで運用実績を記録する投資家も多く、モチベーション維持の習慣として有効です。
第九章 JEPQ投資のまとめと今後の見通し

JEPQは、米国市場のテック株成長力と安定したインカム収入を兼ね備えた、新時代の高配当ETFです。
ここまで見てきたように、リスクを理解した上で長期的に保有すれば、非常に魅力的なリターンをもたらす可能性があります。
1. まとめ:JEPQの本質は「安定×効率」
JEPQは「株価が上がらなくても稼ぐ」ETFです。
カバードコール戦略により、株式保有から得られるプレミアム収入を毎月の配当として投資家に還元します。
NASDAQ100という成長力のあるインデックスを基盤にしているため、守りながら攻めるという絶妙なバランスを実現しています。
また、分配金の高さだけでなく、信託報酬の低さ(0.35%)や高い流動性、JPモルガンという信頼性も大きな魅力です。
高配当ETFの中でも「実用性」「持続性」「安定性」を兼ね備えた優等生といえるでしょう。
2. JEPQがもたらす投資スタイルの変化
これまで高配当投資は「地味」「長期前提」と言われがちでしたが、JEPQの登場によって、配当を楽しみながら投資を続ける時代へと変わりつつあります。
毎月届く分配金は単なるリターンではなく、投資へのモチベーションを高める“心理的リワード”としても機能します。
特にFIRE志向や副業投資家の間では、JEPQを「配当で生活をデザインする道具」として取り入れる動きが加速しています。
3. 今後の展望
2025年以降も米国のテック企業はAI・クラウド・半導体といった分野で世界を牽引する見通しです。
その恩恵を受けるNASDAQ100の成長とともに、JEPQも安定的な運用成果を継続する可能性が高いと考えられます。
ただし、インフレ再燃や金利上昇が起きた場合、株価調整による一時的な下落も想定されるため、短期ではなく中長期視点での運用が求められます。
4. 今から始めるなら
もし初めてJEPQに投資するなら、まずは毎月の分配金を実感できる少額からスタートするのがおすすめです。
円高局面で購入し、得た配当を再投資することで、複利の力が雪だるま式に効いていきます。
慣れてきたら、ポートフォリオ全体の10〜20%程度をJEPQに割り当て、残りをVOOやVTなどのインデックスETFでバランスを取るのが理想です。
5. JEPQは「配当で生きる」時代の象徴
資産形成の目的は、単にお金を増やすことではなく、お金に働いてもらう仕組みを作ることです。
JEPQはまさにその第一歩を実現するETFといえます。
少額でも毎月お金が入ってくる体験は、投資を“数字の世界”から“実感のある収入”へと変えてくれます。
6. 最後に
JEPQは、
- 高配当
- 毎月のキャッシュフロー
- NASDAQの成長力
- 安定性と再現性
をすべて兼ね備えた「次世代の高配当ETF」です。
短期の値動きに惑わされず、“安定して増やす”投資の本質を理解できる人ほど報われる銘柄です。
今後も米国市場の動向とともに進化を続けるこのETFは、長期投資家にとって心強いパートナーになるでしょう。
🌱 結論:JEPQは「働かなくても毎月お金が入る」未来を現実にするETFである。
日本でも登場したJEPQを始めたい方は、こちらもご覧ください👇
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。


