第1章 ラブブとは何か?起源と特徴

近年、SNSを中心に爆発的な人気を誇るキャラクター「ラブブ(Labubu)」は、単なるトレンドを超えた“文化現象”として注目を集めています。
TikTokやInstagramのハッシュタグ「#labubu」は世界的に拡散し、日本でも若年層を中心に急速に浸透しています。
では、この不思議な存在はどこから生まれ、なぜこれほど多くの人々を惹きつけているのでしょうか。
アーティスト・Kasing Lungが生んだ“奇妙で愛しい世界”
ラブブの生みの親は、香港出身のアーティスト Kasing Lung(カシン・ルン) です。
彼は絵本作家としても知られ、代表作『The Monsters』シリーズに登場する小さな妖精「Labubu」を中心に、独自のアート世界を築いてきました。
ラブブは、うさぎのような耳・ギザギザの歯・いたずらっぽい表情を持つ一方で、どこか寂しげな眼差しをしています。
そのアンバランスな魅力が、「可愛い」と「奇妙」の境界を曖昧にし、Z世代の“個性重視の美意識”に強く響いています。
Kasing Lungは、ラブブを通して「人間の不完全さ」や「愛と孤独の共存」をテーマに描いており、キャラクターの造形に哲学的な深みを与えています。
これは単なるマスコットではなく、“感情を投影できるアートピース”としての存在でもあるのです。
世界展開の立役者「POP MART」の戦略
ラブブの人気を世界に広げたのは、中国・北京のトイブランド POP MART(ポップマート) です。
POP MARTは、アートトイ(デザイナーズトイ)市場をリードする企業で、ブラインドボックスという独自の販売方式で知られています。
購入者は箱を開けるまで中身が分からず、どのキャラクターが出るかは“運次第”。
この“ガチャ的”要素がコレクター心理を刺激し、特にZ世代の購買体験を「ワクワクするゲーム化された行動」に変えています。
POP MARTはラブブを中心に、シーズンごとの限定シリーズや有名ブランドとのコラボレーションを展開。
これにより「希少性 × SNS拡散力」という、現代的なトレンド構造を作り上げました。
また、パッケージから展示用フィギュアまで統一されたビジュアルデザインにより、“集めて飾る”カルチャーを確立した点も成功要因のひとつです。
“可愛い”の再定義 Z世代が共感する理由
ラブブの人気を支えるもう一つの要素は、「かわいい=整っている」から「かわいい=個性的」への価値観の変化です。
Z世代の若者たちは、完璧さよりも「欠点を含めた可愛さ」や「感情のグラデーション」を重視します。
ラブブの表情は笑顔でありながらどこかアンニュイで、見る人によって「怒っているよう」「泣いているよう」にも見える。
その曖昧さこそが、“自分を重ねやすいキャラクター”として共感を呼んでいます。
SNS上では、ラブブを撮影した「ぬい撮り」や「Labubuの日常」動画が数多く投稿されており、ユーザー自身が“ラブブの感情”を演出することでキャラクターが拡張的に成長しています。
つまりラブブは、「ファンが共創するキャラクター」として進化を続けているのです。
グローバル人気の背景にある文化的要素
2024年以降、ラブブは中国・タイ・日本・韓国・アメリカなどで同時多発的にブームを起こしています。
特にアジア圏では、「ブラインドボックス開封動画」や「ぬい活写真」がSNSトレンドを牽引し、BLACKPINKのリサや台湾の人気俳優など、著名人の愛用によってさらに拡散しました。
日本では、原宿・渋谷・心斎橋などの若者エリアでラブブグッズ専門ショップが急増。限定イベントでは数時間待ちの行列ができ、オンラインでも抽選販売が行われるほどの人気です。
これは単なるキャラクター消費ではなく、“個性を表現するアイテム”としてラブブが浸透していることを意味します。
まとめ
ラブブは「アート × トイ × SNS」を融合した新時代のカルチャーです。
その背景には、アーティストの哲学、POP MARTの戦略、そしてZ世代の価値観変化が複雑に絡み合っています。
可愛いだけではなく、“自分の感情を映し出す存在”として愛されるラブブは、今後も世界中のSNSを舞台に進化し続けるでしょう。
第2章 流行の背景 ブラインドボックスと限定性

ラブブの人気を語る上で欠かせないのが、「ブラインドボックス」という販売手法です。
これは、購入時に中身が分からない“開けて初めてわかる”サプライズ型のパッケージで、コレクターズ心理を巧みに刺激します。
POP MARTがこの方式を採用したことで、ラブブは「買う行為そのものがエンタメ化」するブランドへと進化しました。
ブラインドボックスがもたらした“体験の価値化”
従来のキャラクターグッズは「好きなものを選んで買う」ものでした。
しかし、ラブブは「何が出るかわからない」という偶然性を設けることで、“購入=開封体験”を価値の中心に置きました。
購入者は箱を開ける瞬間にドキドキを感じ、SNSではその“開封の瞬間”を動画として投稿します。
TikTokで「#labubu開封」「#ブラインドボックス」などのハッシュタグが急上昇し、1件の購入が「視聴・共感・拡散」という波及効果を生む構造が生まれました。
このように、ブラインドボックスは「消費を共有する文化」を作り出し、ラブブの人気をブーストさせています。
コレクター心理をくすぐる希少性の演出
POP MARTは、ブラインドボックスの中にごくわずかな確率で“シークレット(超レア)モデル”を仕込んでいます。
たとえば12体のうち1体だけが特別仕様の「限定Labubu」。
この「出るかもしれない」という期待感が、ギャンブルではなく“運を試す遊び”として若者の購買意欲を掻き立てています。
さらにSNS上では、レアモデルの自慢投稿が大量に拡散され、未入手者の“FOMO(取り残される不安)”を刺激。
「自分も手に入れたい」「次こそ出るかも」という心理がリピート購入を生み出し、持続的な話題性を確保しています。
“限定”がブランドの熱狂を生む
ラブブシリーズは、季節や地域、イベントごとに限定版コレクションを展開します。
「春の妖精Labubu」「ハロウィンナイトシリーズ」「サンタLabubu」など、テーマ性のあるデザインが定期的にリリースされ、SNS上では「推しシリーズ」が形成されます。
特に限定イベントでは、販売初日に完売することも多く、POP MART原宿店では開店前から数百人規模の行列ができるほどです。
こうした希少性 × 即時性 × コミュニティ感の三位一体構造が、ラブブブランドの“熱狂的支持”を維持しています。
開封文化とSNSの相乗効果
ブラインドボックスの開封体験は、SNS時代の「自己表現」の一形態でもあります。
TikTokでは開封動画のリアクションを通じて、「どのLabubuが出るか」で喜びや落胆を表現し、視聴者はその感情に共感します。
特にZ世代にとっては、“開ける瞬間を共有する”こと自体がコミュニケーションです。
Instagramのリール投稿やYouTubeショートでは「開封×BGM×反応」のテンプレートが確立しており、POP MARTはそれを意識した公式キャンペーンも展開しています。
結果として、個人の購入行為がSNS上で一種のエンタメコンテンツ化しているのです。
まとめ
ラブブの流行は、ブラインドボックスという単純な仕掛けから生まれたわけではありません。
そこには、「心理的報酬設計」「SNS連動」「限定性マーケティング」という現代的な戦略が緻密に組み込まれています。
ラブブは単なるキャラクターではなく、“ユーザー参加型の体験ブランド”として進化を続けているのです。
第3章 SNSでの拡散と若者文化

ラブブが世界的に認知を拡大した最大の理由は、テレビCMや広告ではなく、SNSによる自然拡散にあります。
Z世代が「可愛い」をシェアし、「開封」を投稿し、「推し」を表現する。
この“日常の可視化”が、ラブブを単なるキャラクターから「文化のシンボル」へと押し上げました。
TikTokが作り出した“発見の連鎖”
TikTokでは、ラブブをテーマにした開封動画や“日常系ショート”が急増しています。
ハッシュタグ「#labubu」や「#ラブブ開封」は、合計再生回数が数億回を超え、特に10〜20代のユーザーに圧倒的な支持を得ています。
その仕組みは非常にシンプルです。
- ブラインドボックスを開ける瞬間を撮影する
- 期待と落胆、喜びと驚きを“リアルに演出”する
- コメント欄で「私も欲しい!」「推し出たのすごい!」と共感が生まれる
この“リアクションの連鎖”こそが、TikTokにおけるラブブの爆発的拡散を生み出しています。
アルゴリズムが感情反応の多い動画を優先表示するため、ユーザーが「可愛い!」とコメントするたびにラブブ動画の露出が加速していくのです。
Instagramが作る「美しい所有欲」
Instagramでは、TikTokと異なり「美的表現」としてのラブブが注目されています。
フィギュアを机に並べて撮影したり、屋外で“ぬい撮り”をしたりと、アート的な構図が人気を集めています。
中でも特徴的なのは、“整列写真”と“陰影撮影”。
Z世代のクリエイターは、同じラブブを異なる光や角度で撮り、「#labubustyle」「#monstersart」などのハッシュタグで投稿。
それを見たフォロワーが「この撮り方かわいい!」と真似することで、美的模倣によるトレンド連鎖が起きています。
さらに、ストーリーズでは「開封→飾る→投稿」の3ステップが定着し、ラブブを通して“生活の中に美を見出す”文化が形成されています。
このように、Instagramでは「シェア=自己表現」であり、ラブブは“所有するアート”から“見せるアイデンティティ”へと進化しています。
X(旧Twitter)での共感拡散
Xでは、トレンドワードとして「ラブブ届いた」「ラブブかわいすぎ」「POP MART行列」が頻繁に上位入りしています。
投稿内容の多くは、「抽選で当たった!」「シークレット出た!」といった体験共有や、“戦利品報告”です。
中でも特徴的なのは、画像よりも“感情の言語化”。
「今日もラブブに癒された」「仕事終わりに開封して元気出た」など、キャラクターを通して自分の感情を言葉で表す投稿が多いのです。
これはZ世代特有の「感情共有文化」に基づいており、
他者との比較ではなく「同じ気持ちを感じる」ことでつながるSNS行動と言えます。
結果として、ラブブは「共感でつながるキャラクター」という位置づけを確立しました。
SNS拡散を支えるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の力
ラブブのマーケティングは、企業主導ではなくファン主導です。
POP MARTが提供するのは“舞台”にすぎず、物語を作るのはファン自身。
- ファンが作るアニメーション風ショート動画
- ラブブを主役にした「1日密着Vlog」
- 推しLabubuのファッションコーデ投稿
これらUGC(ユーザー生成コンテンツ)が爆発的に増え、
「企業が広告を出す前に、ファンが宣伝している」という理想的な拡散構造が完成しています。
POP MARTはこの現象をさらに後押しするため、TikTokやBilibiliで公式の“#LabubuChallenge”を開催。
ファンの創作をリポスト・紹介する仕組みを整え、UGCを公式文化に昇華させています。
SNSが作り出した「デジタル共感圏」
SNS上のラブブ人気は、単なるバズではなく、“共感経済”の象徴です。
若者たちは「かわいいから買う」のではなく、「共感できるから共有する」。
その結果、ラブブはブランドではなく「共感でつながる存在」になりました。
SNSでの投稿が「所有の証」から「所属の証」に変わりつつある今、
ラブブは“個人の小さな居場所”を提供する存在となり、ファン同士の繋がりがコミュニティ化しています。
まとめ
ラブブのSNS拡散は、偶然ではなく“構造的必然”です。
TikTokでの感情共有、Instagramでの美的発信、Xでの共感文化。
それぞれが相互に作用し、ラブブは「自分を映す鏡」として、SNS時代の若者の心に深く根付いています。
第4章 コミュニティ形成とファンカルチャー

ラブブの人気は、単なるキャラクターブームでは終わりません。
その背後には、ファン同士の“つながり”を基盤にした文化の生成があります。
ファンが作品を創り、共有し、互いに支え合うことで、ラブブは「一方的に消費される商品」から「共創されるカルチャー」へと進化しました。
ファン同士が生み出す“共創経済”
Z世代を中心に広がるラブブのファンコミュニティでは、個々のファンが自らコンテンツを生み出しています。
TikTokではラブブを主人公にしたショートドラマが数多く投稿され、YouTubeでは「My Labubu Life」というファンメイドのVlogシリーズも人気です。
こうしたUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、企業の宣伝を超えて自然発生的に拡散されており、ファンが広告主の役割を担うという新しい構造を生み出しています。
さらに、フリマアプリやSNSマーケットでは「Labubu コレクターズマーケット」が活発化。
限定フィギュアや非売品を売買する小規模経済圏が形成され、希少モデルの相場が数万円に達することもあります。
このように、ラブブはファン活動自体が経済価値を持つ“二次創造経済”を構築しているのです。
「かわいい」を共有する感情共同体
ラブブのファンコミュニティには、年齢や国籍を超えた“共感の絆”があります。
SNS上では「今日のラブブ」「#LabubuMood」など、日常の中で感じた気分や出来事をラブブの写真とともに投稿するユーザーが増えています。
そこでは「かわいい」の基準が外見ではなく、“感情を共有できる存在”へとシフトしています。
たとえば、疲れた日にラブブのぬいぐるみを抱えて「今日も一緒に頑張った」と投稿する人もいれば、旅行先でLabubuを撮影して「この景色を一緒に見た」と共有する人もいます。
このように、ラブブは人と人をつなぐ感情の媒介者として機能しているのです。
オフラインイベントが育むリアルなつながり
オンラインだけでなく、リアルイベントの熱量も圧倒的です。
POP MART JAPANは、東京・大阪・名古屋などで「Labubu POP UP Store」を定期開催しており、整理券配布の行列ができるほどの盛況を見せています。
来場者同士がコレクションを見せ合ったり、限定グッズを交換したりと、リアルな“推し活”コミュニティが自然発生。
イベント内ではフォトスポットやスタンプラリーなど、SNS投稿を促す仕掛けも用意されており、オンラインとオフラインがシームレスに連動しています。
このように、ラブブのファン体験は「デジタルで広がり、リアルで深化する」双方向モデルで成立しているのです。
国境を越えたグローバルファンネットワーク
Labubuは中国・タイ・韓国・日本・欧州・米国で同時多発的にブームとなっており、ファン同士の国際交流も活発です。
Redditの「r/LabubuCollectibles」やDiscordの「Labubu World」では、限定商品の交換・情報共有・コレクション展示が行われています。
言語の壁を超え、「Labubuを愛する」という一点でつながるグローバルな共同体が誕生しており、POP MARTはこの動きを公式に支援。
NFT アートやメタバース空間「POP LAND」では、デジタルフィギュアの展示・販売を通じて世界のファンをつなげています。
このように、ラブブはリアルとデジタルを越境する国際的カルチャーとして進化を続けています。
ファンダム文化の進化モデル
ラブブ現象は、従来の「キャラクタービジネス」とは異なり、“ファンが作り、ファンが拡張する”モデルを体現しています。
これは、K-POPファンダムやゲーム実況文化とも共通する「参加型経済圏」の一形態です。
ファンは受け手ではなく創り手。
POP MARTはその動きを制御せず、むしろ“ファンの創造性”を尊重するオープン戦略をとることで、ラブブの世界観を自然に拡張しています。
この柔軟さこそ、ブランドが長期的に成長する最大の要因といえるでしょう。
まとめ
ラブブのファンコミュニティは、単なる「ファングループ」ではなく、感情・創造・経済が循環するエコシステムです。
SNSで出会い、リアルで交流し、再びオンラインで共有する。
この循環構造が、ラブブを“Z世代の象徴的カルチャー”へと押し上げています。
第5章 日本と世界でのトレンド比較
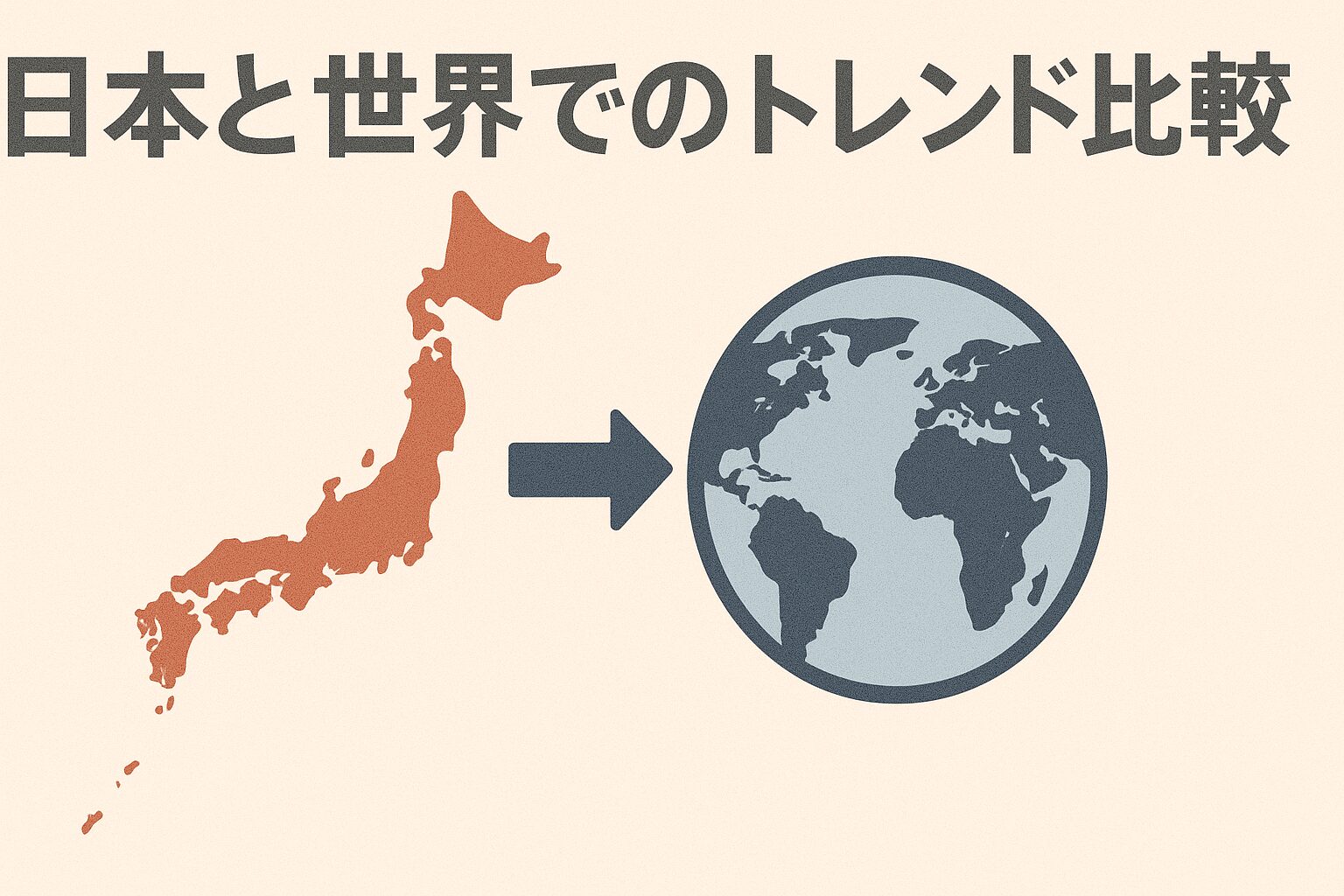
ラブブの人気はもはや一国の現象ではありません。
中国、タイ、韓国、日本、アメリカ、ヨーロッパ──
SNSというグローバルな舞台で同時多発的にブームが起き、各国で異なる“意味”を持って受け入れられています。
この章では、世界のトレンド構造を比較し、ラブブがどのように「文化を横断するキャラクター」へと進化しているのかを紐解きます。
中国 ブームの震源地としての熱狂
ラブブが最初に社会現象化したのは、中国本土です。
POP MARTの本社がある北京では、2020年代初頭から「アートトイ文化」が急成長。
若年層の間で“自分の世界観を表すオブジェ”として人気が高まり、「ラブブを飾る=センスの証明」という認識が広がりました。
中国では特に、コレクター文化とデジタル拡散力の融合が特徴的です。
Weibo(微博)や小紅書(RED)では、「#Labubu系列」「#盲盒開箱」などのタグが億単位の再生数を記録。
さらに、開封動画やコレクション写真を共有することで、同好の士がつながり、“二次流通市場”が巨大化しています。
ラブブはここで単なる玩具を超え、ステータスシンボル × SNS映えの象徴として社会的価値を確立しました。
タイ アジアカルチャーとポップアートの融合
タイでは、ラブブがポップアートとファッションの中間点に位置付けられています。
特にバンコクの若者文化圏では、ストリートブランドとのコラボやアーティスト展示会が頻繁に行われ、
「Labubu × Culture」ムーブメントが形成されています。
また、タイのクリエイターは自身のLabubuをカスタマイズしてSNSに投稿する「#MyLabubu」文化を牽引。
ラブブを“個性を表現する素材”として再構築しており、創造性を競うカルチャーへと発展しています。
このように、タイではラブブが「かわいい」よりも「かっこいい」文脈で語られているのが特徴です。
日本 “癒しと共感”のキャラクター文化としての定着
日本におけるラブブ人気の特徴は、他国とは異なり感情共感型にあります。
Z世代・ミレニアル世代の間で、「ラブブに癒される」「気分を表現してくれる」といった心理的なつながりが強調され、
“可愛いの多様化”の象徴となっています。
日本では特に「ぬい撮り文化」との相性が良く、カフェや旅行先でラブブを撮影し、
「#ラブブとお出かけ」「#今日のラブブ」といったタグで投稿する習慣が広がっています。
さらに、日本のキャラクター市場はすでに飽和状態にありますが、
ラブブは「癒し×不完全美」という独自の世界観で新しいポジションを確立しました。
つまり、“整っていないかわいさ”が新しい共感軸となったのです。
韓国 ミニマル美学と共感SNSの融合
韓国では、ラブブが「ライフスタイルアクセサリー」として受け入れられています。
インテリアに馴染むカラーリングや質感が評価され、
カフェ文化や雑貨ブランドと組み合わせた投稿が人気を集めています。
特にInstagramとPinterestでは、「#LabubuHome」「#SoftRoomStyle」などのタグが拡散。
美しい部屋の一部にラブブを置くことで、自分らしさの象徴として機能しています。
韓国のトレンドは“整う美学”がベースにあるため、
ラブブの「混沌としたかわいさ」が新鮮に映り、若者の心を掴んでいます。
欧米 サブカルチャーとしての再解釈
アメリカやヨーロッパでは、ラブブが「アートトイコレクション」の一環として受け入れられています。
アメリカのトイ展示会「DesignerCon」ではLabubuシリーズが高く評価され、
“ポップアートの進化形”として紹介されました。
欧米市場では、“キュート&クレイジー”という相反する魅力が「東アジア的感性」として受け止められ、
ファッションやNFTアートの領域にも波及しています。
特に米国の若年層は、ラブブを「自分の内面を具現化するキャラクター」と捉え、
感情をビジュアル化するアイテムとしてコレクションしています。
文化ごとに異なる「意味の再構築」
| 国・地域 | 主な受け入れ方 | キーワード |
|---|---|---|
| 中国 | ステータス×SNS映え | コレクター・社会的象徴 |
| タイ | アート×ファッション | 創造性・自己表現 |
| 日本 | 癒し×共感 | 感情の共有・可愛いの再定義 |
| 韓国 | ミニマル美学×ライフスタイル | 洗練された混沌 |
| 欧米 | サブカル×ポップアート | 個性・自己投影 |
このように、ラブブは国や文化によって異なる価値を与えられています。
それでも共通しているのは、「自分を表現するための媒介」であるという点です。
ラブブはもはやキャラクターではなく、“感情を翻訳するグローバル言語”なのです。
まとめ
ラブブ現象の本質は、「可愛い」の輸出ではなく「感情の輸出」にあります。
各国の若者たちが、文化や言語を超えてラブブを“自分の分身”として受け入れている。
その普遍性こそ、ラブブがグローバルブランドとして確立した最大の理由です。
第6章 今後の展望とマーケティングへの示唆
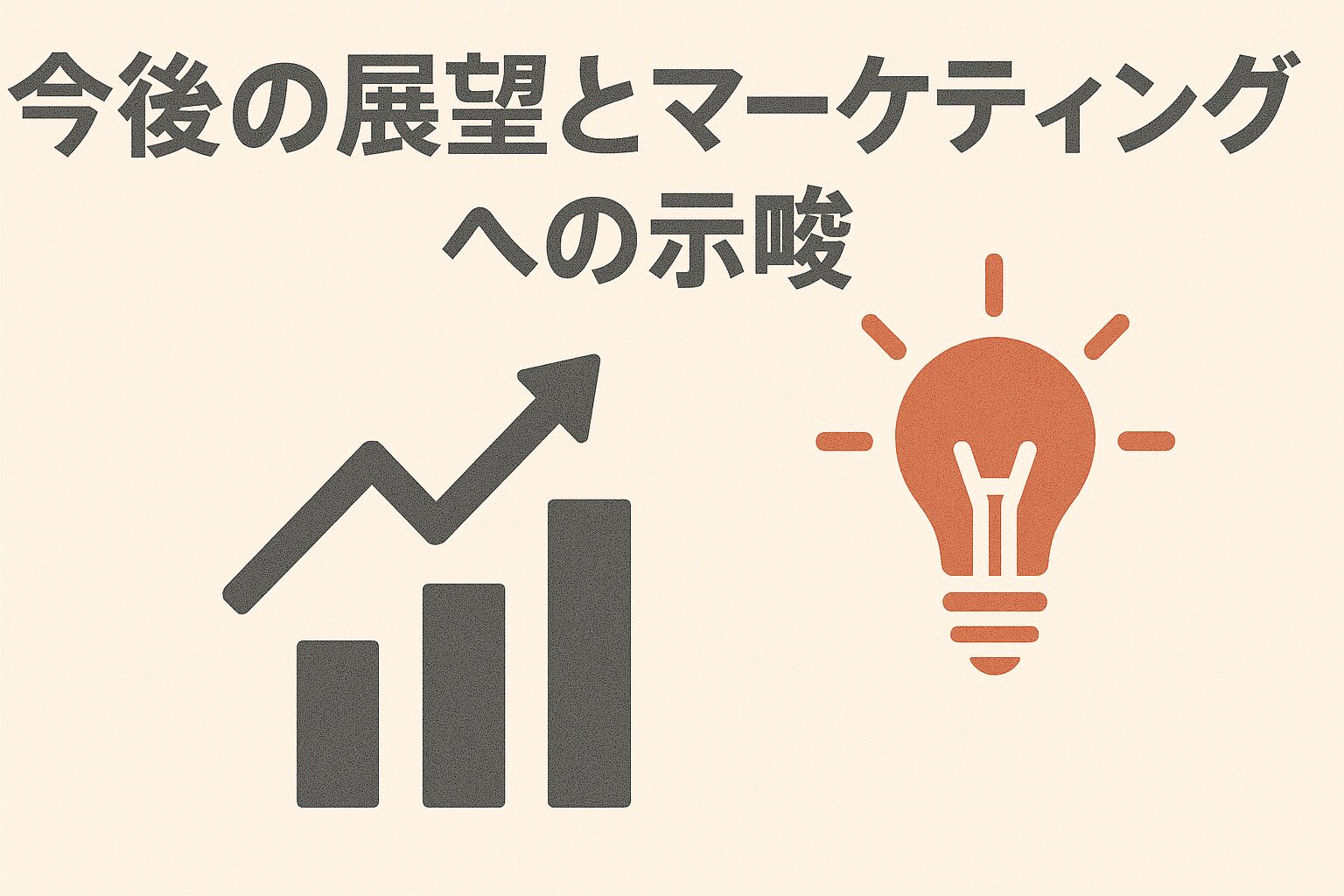
ラブブの世界的ブームは一過性のものではありません。
それは、“商品としての可愛さ”ではなく、“文化としての共感”を軸に成立しているからです。
ここでは、ラブブ現象の今後の方向性と、企業がこのムーブメントから学ぶべきポイントを整理します。
ラブブが築いた「共感経済」の未来
ラブブの成功は、Z世代を中心とする“共感経済”の象徴です。
従来のマーケティングは「認知 → 購入 → 利用」という直線的な構造でした。
しかしラブブの場合、消費の流れは「共感 → 共有 → 拡散 → 所有 → 再共感」という循環構造を描きます。
つまり、“好きだから買う”のではなく、“共感できるから広めたい”という動機が購買を促しているのです。
この構造は、商品やサービスに対して“感情の帰属”を求める現代の若者心理を象徴しています。
ラブブが今後も支持され続ける理由は、この感情の循環モデルを持続可能な形で構築している点にあります。
「体験設計」がブランドの競争力を決める時代へ
POP MARTのブラインドボックス戦略は、単なる販売方法ではなく、体験設計(CX Design)そのものです。
ユーザーが“箱を開ける瞬間”をコンテンツ化し、その体験をSNSで共有する流れを完全に計算しています。
今後、ブランド価値を高める企業が成功する鍵は、
「買う瞬間」ではなく「シェアする瞬間」をデザインできるかどうかにかかっています。
ラブブのように、
- 「驚き」や「運試し」などの感情トリガーを仕掛ける
- ファン同士の“つながり”を促す設計を行う
- 限定性を高めつつ、入手体験を“イベント化”する
このような体験の設計こそが、ブランドの持続的成長を支える要素になるでしょう。
メタバースとAIが拡張する“デジタルラブブ体験”
2026年以降、POP MARTはデジタル領域における新たな展開を加速させると予測されます。
実際に同社はメタバースプラットフォーム「POP LAND」を構築し、ラブブの3DアバターやNFTアートの発行を進めています。
この動きは、リアルのフィギュアとデジタル所有権をつなぐ「デジタルツイン戦略」の一環であり、
今後はAI生成コンテンツや仮想イベントでの参加型体験も拡張していくでしょう。
たとえば、
- AIを使って「自分だけのラブブ」をデザインできる機能
- メタバース空間でラブブ同士が“交流する”バーチャル展示会
- 現実の購入履歴と連動するデジタルコレクション
といった仕組みが現実化しつつあります。
これにより、ラブブは“所有するキャラクター”から、“体験し続けるキャラクター”へと進化します。
ブランドがラブブから学ぶべき5つのマーケティング原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| ① 共感設計 | 商品の機能ではなく「感情価値」を中心に設計する |
| ② 参加型体験 | ファンを受け手ではなく“共創者”として巻き込む |
| ③ 限定性と希少性 | 手に入れる過程そのものをストーリー化する |
| ④ SNS同化型戦略 | 拡散の起点を「ブランド」ではなく「ユーザー投稿」に置く |
| ⑤ デジタル拡張 | 現実と仮想をつなぐ双方向体験で熱量を維持する |
これら5つの原則は、ラブブが単なるヒット商品にとどまらず、“文化としてのブランド”に進化した理由を説明しています。
今後の展望 “ポストキャラクター時代”の象徴へ
2025年以降、キャラクタービジネスは新しい段階に入ります。
重要なのは「どんなキャラクターか」ではなく、「そのキャラクターが人にどんな体験をもたらすか」です。
ラブブはこの新時代の象徴であり、企業にとっては“広告ではなく共感を設計する存在”としての手本になります。
POP MARTが掲げる理念「Collect Joy, Spread Love(喜びを集め、愛を広める)」は、単なるスローガンではなく、
SNS時代のブランド哲学そのものなのです。
まとめ
ラブブの未来は、単なるキャラクタートレンドの延長ではありません。
それは、“感情と体験を中心にした新しい経済の形”を提示する現象です。
ファンが創り、共感で広がり、テクノロジーで拡張する──
そのすべてがラブブというひとつの世界に凝縮されています。
企業がこの構造を理解し、自らのブランドに応用できたとき、
次のラブブ現象は、あなたの手によって生まれるかもしれません。
✅ 総括メッセージ
「ラブブはキャラクターではない。人々が自分の感情を託す“鏡”である。」
最新トレンドを掴みたい方はこちらからご覧ください👇
\登録たった1分!キャンペーンが終わる前に/
※特典が受け取れるのは、当リンク限定