日本の公的年金制度は、老後の生活や万一の障害・死亡に備えて国民全員が加入する社会保障制度です。
この制度では、現役世代が納めた保険料を財源として高齢者世代などに年金を給付する世代間の支え合いの仕組みになっています。
個人では対応しにくい老後の収入減少や障害・死亡による収入途絶といったリスクに対し、みんなで支え合って備えるために公的年金制度が設けられています。
本記事では、この公的年金制度の概要から、未支給年金の手続き、年金生活者支援給付金制度、さらに公的年金に関する税制上の優遇措置まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。
制度を正しく理解し、漏れなく給付を受け適切に活用するための知識を身につけましょう。
まずはこちらをご覧ください👇
公的年金制度とは
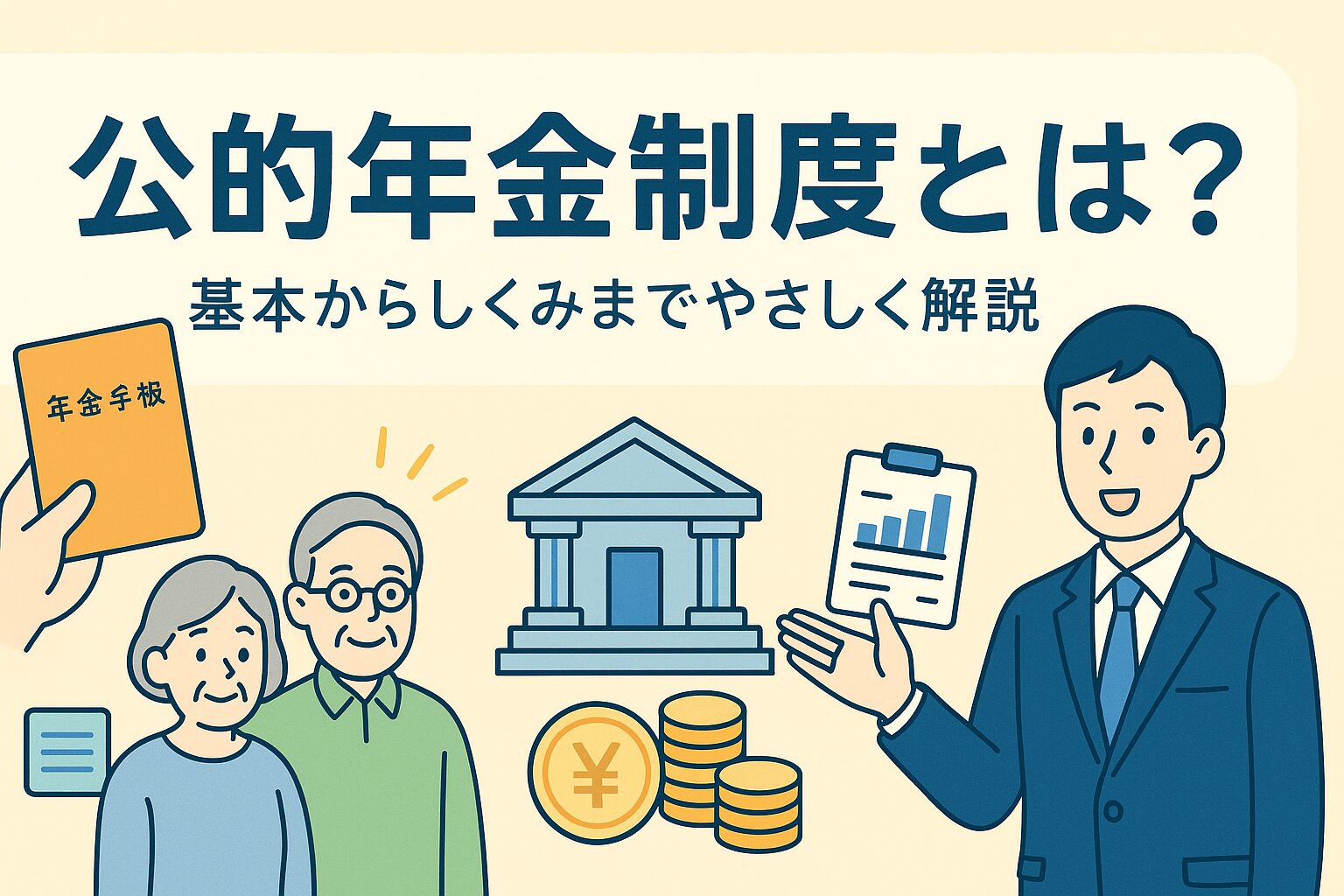
公的年金制度とは、日本に住むすべての人が加入する強制加入の年金制度です。
20歳から60歳までの全国民が国民年金(基礎年金)に加入し、保険料を納めることになっています。
さらに会社員や公務員など給料を得て働く人は厚生年金保険にも加入します。
公的年金制度はこの国民年金と厚生年金の二階建て構造になっており、自営業や学生・無職の方は基礎年金部分のみ、会社員等の方は基礎年金に加えて厚生年金の上乗せ給付を受けられる仕組みです。
公的年金は賦課方式(世代間扶養)と呼ばれる方式を採用しており、現役世代が支払う保険料と国の財源によって、現在の高齢者などへの年金給付がまかなわれます。
特に国民年金(基礎年金)の給付費用の約2分の1は国庫負担(税金)で賄われており、公的年金は公的資金も投入された社会全体で支える仕組みです。
これにより、自分が若いときは高齢世代を支え、自分が高齢になったときには次の現役世代から支えられるという相互扶助が成り立っています。
公的年金制度の仕組み(二階建てと加入区分)
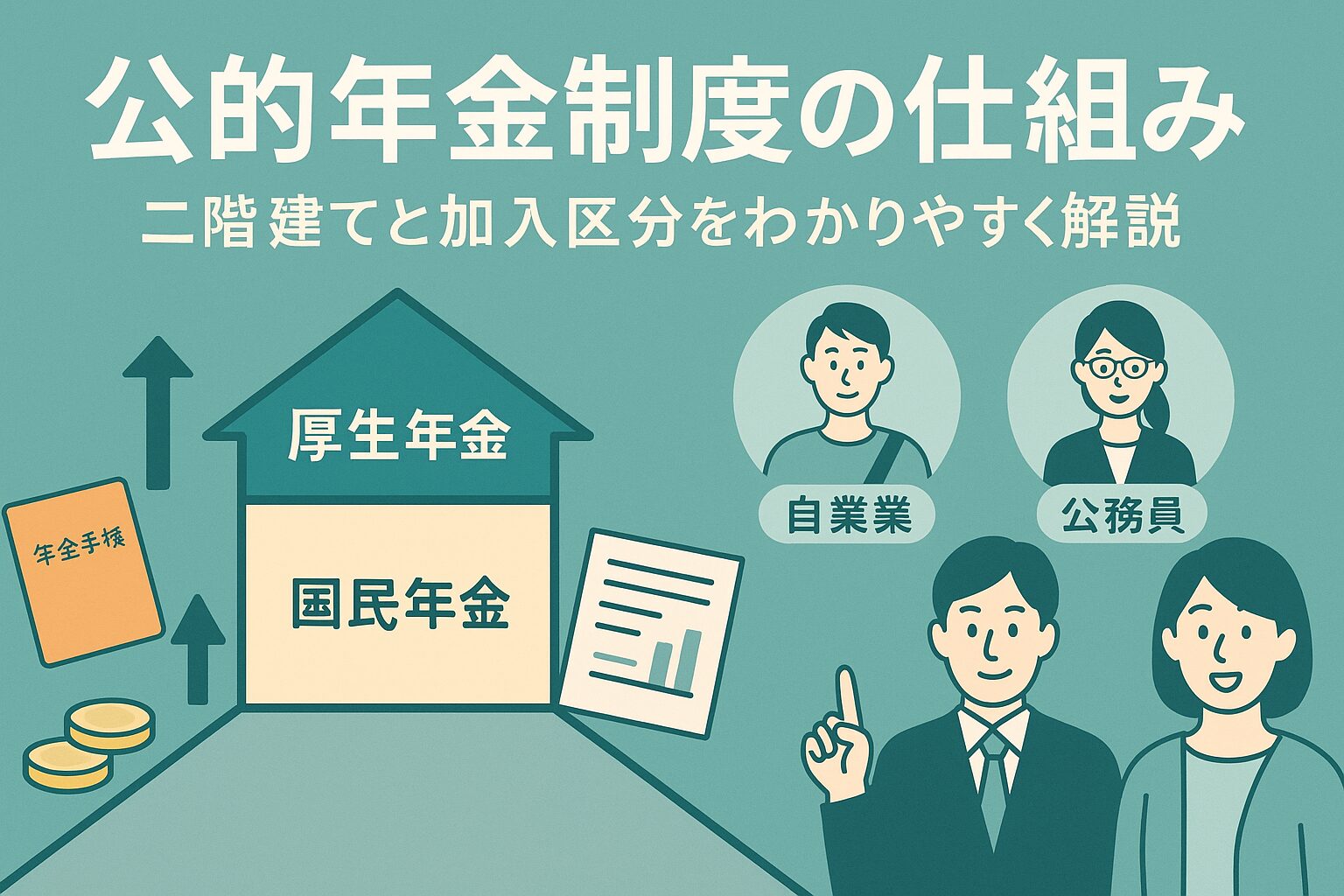
日本の公的年金は、全員が加入する1階部分の国民年金と、会社員・公務員などが加入する2階部分の厚生年金という二階建てになっています。
この2つの制度に誰がどのように加入するかは、その人の働き方や属性によって区分されています。
以下に被保険者区分と加入する年金制度をまとめます。
| 被保険者区分 | 該当する人(例) | 加入する年金制度 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職の人など | 国民年金のみに加入 |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 厚生年金(国民年金を含む) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 国民年金のみに加入(保険料負担なし) |
第1号被保険者は自営業者やフリーランス、学生、無職の方などで、自分で国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者は企業や官公庁に勤める会社員・公務員で、勤務先を通じて厚生年金保険料を納めます(厚生年金保険料には国民年金分が含まれます)。
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、自身で保険料を支払わなくても国民年金に加入したとみなされます。
つまり、専業主婦(夫)などは配偶者の厚生年金の扶養範囲で基礎年金を保障される仕組みです。
国民年金の保険料は定額で、2025年度(令和7年度)時点で月額約17,510円です。
この保険料を20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて納めると、将来受け取る老齢基礎年金は満額で月額約6万9千円(2025年度価額)になります。
厚生年金の保険料は給与や賞与に比例した額で、現在の保険料率は報酬の約18.3%(労使折半)となっており、会社員等は給与に応じた年金額を将来受け取ることができます。
厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入している扱いとなり、基礎年金部分と給与比例部分の両方を将来受給します。
なお、公的年金にはこの二階部分までが法律で義務付けられた範囲ですが、さらに任意加入の第三の支柱(3階部分)として企業年金(企業が従業員のために用意する年金制度)や個人型年金(例:国民年金基金やiDeCo〈個人型確定拠出年金〉)などの私的年金を上乗せして老後資金を準備することもできます。
ただし公的年金だけでも老後・障害・死亡に一定の保障を得られるよう設計されており、日本に住む人は原則として何らかの形で公的年金に必ず加入することになっています。
公的年金の主な給付内容(老齢・障害・遺族)

公的年金制度は単に老後資金を受け取るためのものではなく、老齢・障害・死亡という三つのリスクに対する保障を一体的に提供しています。
具体的には、以下のような給付を受けることができます。
- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金):
所定の保険料納付期間を満たし原則65歳に達すると受け取れる年金です。
老齢基礎年金は全員共通の基礎部分で、満額の条件を満たした場合に定額の年金が支給されます。
厚生年金に加入していた人はこれに加えて報酬比例の老齢厚生年金が支給され、現役時代の収入に応じた年金額となります。
老齢年金は高齢者の生活を支える柱であり、受給開始年齢は原則65歳ですが、希望により繰上げ受給(60歳以降に早めて減額受給)や繰下げ受給(最大75歳まで遅らせ増額受給)も選択可能です。
※受給資格期間(保険料納付や免除期間の合計)は原則10年以上必要です。 - 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金):
公的年金に加入中の病気やケガが原因で所定の障害等級(一般に1級・2級程度の重度の障害)に該当した場合に支給される年金です。
障害基礎年金は全国民共通で、障害の程度に応じて定額の年金が支給されます。
厚生年金加入者で障害等級に該当した場合は、障害基礎年金に加えて報酬比例の障害厚生年金(厚生年金の等級3級や一定条件下の障害手当金など)が支給されます。
障害年金は働けなくなった場合の生活を支える重要な給付です。 - 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金):
年金加入者や受給者が亡くなったとき、残された遺族の生活を守るために支給される年金です。
遺族基礎年金は主に死亡した方に生計を維持されていた子どもがいる配偶者(典型的には子のいる妻)または子どもに支給されます。
遺族厚生年金は厚生年金加入者が亡くなった場合に、その配偶者(主に妻)や子など一定の遺族に支給され、加入者の報酬に応じた年金額となります。
遺族年金は一家の働き手を失った場合に、残された家族の生活を下支えする公的年金からの給付です。
条件を満たせば老齢年金の代わりに遺族年金を受け取ることで、遺族の生活保障に役立てることができます。
以上のように、公的年金は老齢・障害・死亡の三つの事態それぞれに対して年金給付が用意されています。
若いうちは老後の年金だけが注目されがちですが、公的年金制度は現役世代にも万一の保障を提供する大切なセーフティネットとなっています。
いざというときに備え、障害年金や遺族年金の制度についても理解しておくことが重要です。
未支給年金とは何か

未支給年金とは、本来年金を受け取るはずだった人が亡くなった際に、その人に支払われるはずだった未受領の年金額を指します。
年金受給者が死亡すると、その人自身の年金を受け取る権利はその時点で消滅します。
しかし、例えば偶数月支払いの年金で支払日前に亡くなった場合など、亡くなった月までの年金でまだ支給されていない分が発生します。
これが「未支給年金」であり、一定の範囲の遺族が請求することによって受け取ることができます。
未支給年金は本来故人が受け取るはずだった給付であるため、法律上は故人から相続する財産ではなく、故人と生計を同じくしていた遺族固有の権利として位置づけられます。
そのため未支給年金として受け取る金額は故人の遺産ではなく遺族が新たに取得する給付であり、相続放棄をしていても受け取れるほか、所得税や相続税の課税対象にも基本的になりません(公的年金の未支給分については非課税扱いです)。
例えばご高齢の年金受給者がお亡くなりになった場合、死亡した月分までの年金は振り込み停止になりますが、所定の手続きをすれば後日その月までの分を遺族が受け取れる仕組みです。
なお、未支給年金と遺族年金は別の制度です。
未支給年金はあくまで亡くなった方が受け取っていなかった年金の清算払いですが、遺族年金は加入者が一定の条件を満たして亡くなった場合に遺族に支給される継続的な年金給付です。
両者は別立ての制度なので、対象となる場合は未支給年金の請求と遺族年金の請求をそれぞれ行う必要があります。
未支給年金の請求方法と手続き
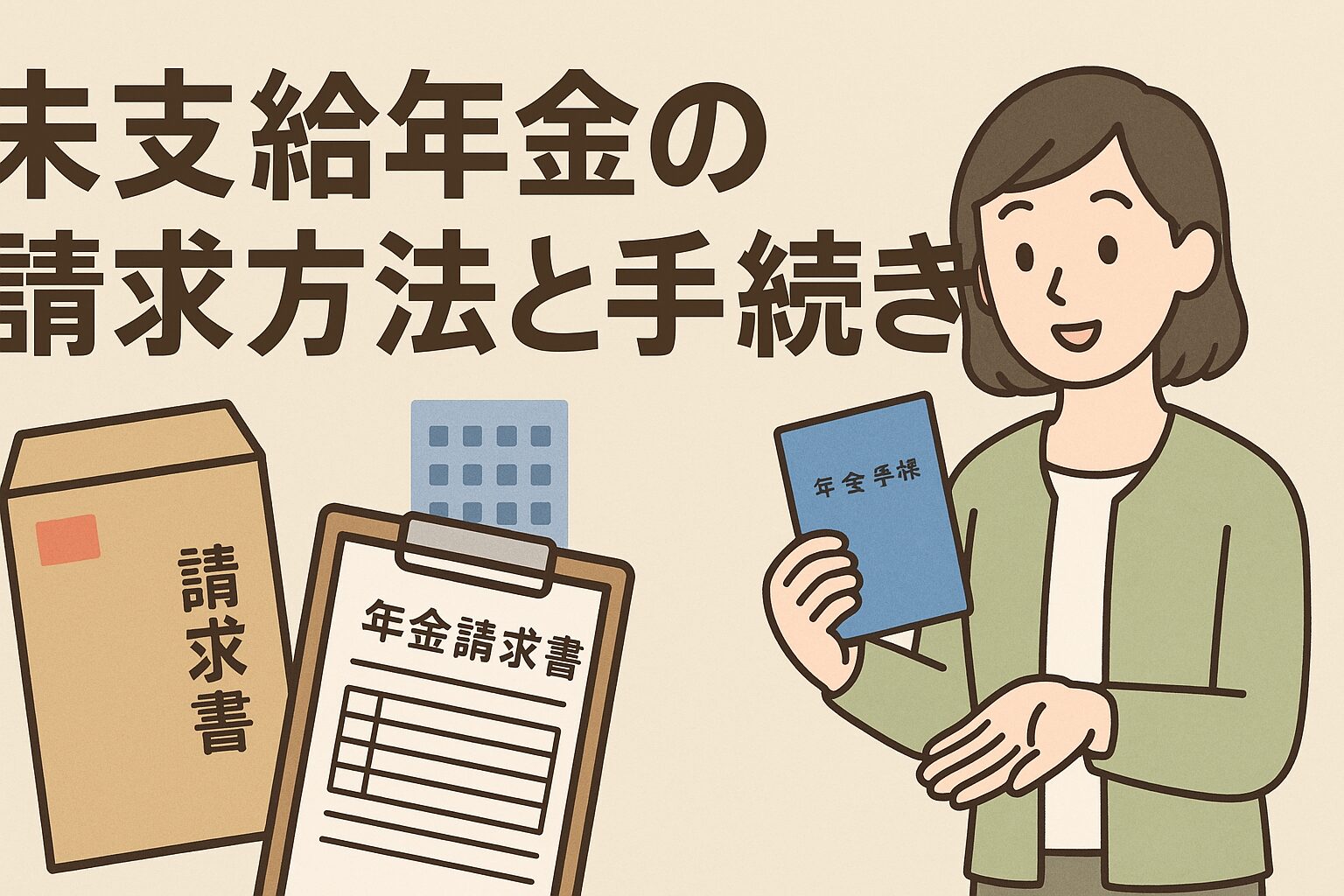
年金受給者が亡くなった際に未支給年金を受け取るには、遺族の側で請求の手続きを行う必要があります。
未支給年金は自動では支払われず、請求しなければ受け取れません。
請求できる遺族の範囲は決まっており、亡くなった方と生計を同一にしていた親族が対象です。
具体的には、亡くなった時に同居して生計を共にしていた順番の近い親族から請求できます。
優先順位の高い順に以下の範囲となっています。
- 配偶者(妻または夫)
- 子(お子さん)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外で亡くなった方と生計同一だった三親等内の親族
上記のような遺族であれば、亡くなった月までに支給対象となっていた年金(未受領分)を請求して受け取ることが可能です。
請求手続きとしては、年金事務所や市区町村役場の窓口に未支給年金請求書を提出します。
厚生年金に関する未支給年金はお近くの年金事務所等で、国民年金に関する未支給分は市区町村の国民年金担当窓口で手続きを行います。
請求書には亡くなった方の年金証書や死亡の事実が分かる書類(死亡診断書や戸籍事項証明等)、請求者の身分証や続柄を証明する書類(戸籍謄本など)、生計同一関係を確認できる書類(住民票など)、受取先金融機関の通帳コピーなど、所定の添付書類を準備して提出します。
必要書類は状況によって異なるため、詳細は年金事務所や市役所窓口に確認すると良いでしょう。
請求の期限にも注意が必要です。
未支給年金の請求権には時効があり、年金受給権者が亡くなった当時の年金支給日翌月初日から5年以内に請求しないと権利が消滅してしまいます(未請求のまま5年が経過すると未支給分は受け取れなくなります)。
例えば本来受け取れるはずだった最後の年金支給日から5年を過ぎてしまうと、未支給年金を請求する権利は時効により消滅します。
したがって、大切なご家族が亡くなられた際には、忘れずに早めに未支給年金の手続きを取ることが重要です。
手続き自体はそれほど難しくありませんので、該当する場合は速やかに請求して本来もらえるはずだった年金を受け取り、故人の残した年金を無駄にしないようにしましょう。
年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度は、公的年金を受給している方のうち所得の低い方に対し、年金に上乗せして支給される制度です。
これは2019年(令和元年)10月の消費税率引き上げに伴い創設されたもので、消費税増収分を財源として低所得の年金受給者の生活を支援する目的で導入されました。
簡単に言えば、年金だけでは生活が厳しい所得水準の高齢者などに対し、毎月の年金にプラスして一定額の給付金を支給する仕組みです。
支給対象となるのは、老齢・障害・遺族いずれかの基礎年金(国民年金)を受給している方で、市町村民税が非課税の世帯に属し、かつ前年の年金収入とその他所得の合計額が一定基準額以下の方です。
例えば65歳以上で老齢基礎年金を受給している方の場合、自身を含め世帯全員が住民税非課税で、その方の年間年金収入額とその他の所得が約90.9万円(令和7年度基準)以下であれば老齢年金生活者支援給付金の対象となります(収入が基準を少し超える場合には補足的給付金の対象となるケースもあります)。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方についても、それぞれ障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の対象条件が設けられています。
要件を満たす方には年金とは別枠で給付金が支給されるため、公的年金だけの場合に比べて毎月受け取る額が増え、生活にゆとりをもたせることができます。
給付金の額は、老齢基礎年金の受給者向けの老齢年金生活者支援給付金の場合、フルで保険料を納めた人を基準に月額5,000円強(令和7年度は月5,450円)となっています。
ただし実際の支給額はその方の保険料納付実績に応じて計算されます。保険料を未納や免除した期間がある場合にはその分減額された額となり、逆に満額納付に近い方ほど基準に近い額を受け取る形です。
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給者向け給付金については定額(令和7年度現在、月額5,032円)となっています。
給付金を受け取るための手続きについては、多くの場合年金請求時に併せて案内されていますが、対象となる方には年金機構から案内が届くこともあります。
まだ受け取っておらず条件を満たす方は、お近くの年金事務所や市町村国民年金係に相談してみると良いでしょう。
なお、年金生活者支援給付金は一度認定されても、その後対象者の所得状況が変わり住民税課税世帯になるなど支給要件に該当しなくなった場合は支給が停止されます。
例えば収入の増加により住民税課税となった場合や、扶養親族との同居状況が変わった場合などは給付金が受けられなくなりますので注意が必要です。
いずれにせよ、公的年金とは別に受け取れる公的支援策として、この給付金制度を活用できる条件にある方は忘れずに手続きを行いましょう。
公的年金と税制優遇措置

公的年金制度には、加入者や受給者に対して税制上の優遇措置がいくつか設けられています。税制面での支援を受けることで、保険料を納める負担や年金を受け取る際の税負担が軽減される仕組みです。ここでは主な優遇措置を紹介します。
まず、公的年金の保険料を支払う段階での優遇として、社会保険料控除があります。国民年金保険料や厚生年金保険料など公的年金の保険料は、所得税および住民税の計算上、全額が社会保険料控除の対象です。1年間に実際に支払った年金保険料の総額だけ所得から差し引くことができるため、その分だけ税金が軽くなります。例えば年に20万円の国民年金保険料を納付した場合、所得税や住民税を計算する際に20万円が控除されます。これは公的年金への加入・保険料納付を奨励するための税制上の措置で、将来の年金受給のために負担した保険料にはしっかり税の面でも配慮がされているということです。会社員の場合、厚生年金保険料は給与天引きされていますが、年末調整や確定申告において自動的に社会保険料控除として反映されるため、個別に申告する必要はありません。
次に、公的年金を受給する段階での税制優遇として、公的年金等控除があります。老齢年金などを受け取ると、その年金額は原則「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。しかし、高齢者の年金生活に配慮し、公的年金等の収入には一定額を他の所得と分離して控除する公的年金等控除が設けられています。控除額は年齢や年金収入額に応じて定められており、年金収入が比較的少ない場合には年金額の大半または全額が控除されるため、結果として課税所得がゼロになり税金がかからないケースも多くあります。具体的には65歳以上の方で年金収入がおおむね年110万円以下であれば所得税・住民税ともに課税されません。仮に年金収入がそれ以上ある場合でも、公的年金等控除によって相当額が差し引かれてから税額計算されるため、現役の給与所得者に比べて税負担は軽減されています。このような仕組みにより、多くの年金受給者は確定申告が不要になるほど税負担が抑えられています(目安として公的年金収入が年400万円以下、かつ他の所得が年20万円以下であれば確定申告は不要とされています)。
さらに、公的年金に関連して知っておきたい税制優遇として、障害年金・遺族年金の非課税扱いがあります。障害基礎年金や障害厚生年金、遺族基礎年金や遺族厚生年金といった障害・遺族給付については、所得税・住民税ともに課税されない非課税所得となっています。これは、障害や死亡による給付金は生活保障の性格が強く、税負担をかけないことで受給者の生活をより手厚く保護する趣旨によるものです。同様に、前述の未支給年金も遺族固有の権利として受け取るものですので所得税や相続税は課されません(公的年金等の未支給分は非課税です)。一方で、老齢年金については前述のとおり公的年金等控除の範囲内までは非課税となりますが、一定以上の高額の年金収入がある場合にはその超えた部分に対して税金がかかります。もっとも、その場合でも高齢者には年金以外の所得が少ないケースが多く、住民税非課税などの優遇措置(例えば高齢者の医療費自己負担軽減など他分野の支援策も含め)につながるラインが考慮されています。
まとめると、公的年金には払うときも受け取るときも税制上のメリットが用意されています。保険料を納める段階では全額が所得控除となり、年金を受給する段階では公的年金等控除によって大幅な控除が受けられるほか、障害・遺族年金は非課税扱いです。これらの優遇措置のおかげで、公的年金制度に参加することで将来の生活保障を準備することは、税の面でも優遇された行為となっています。老後の資金計画を立てる際には、公的年金から得られる収入は手取りベースで考えても想像以上に有利であることを覚えておきましょう。
まとめ
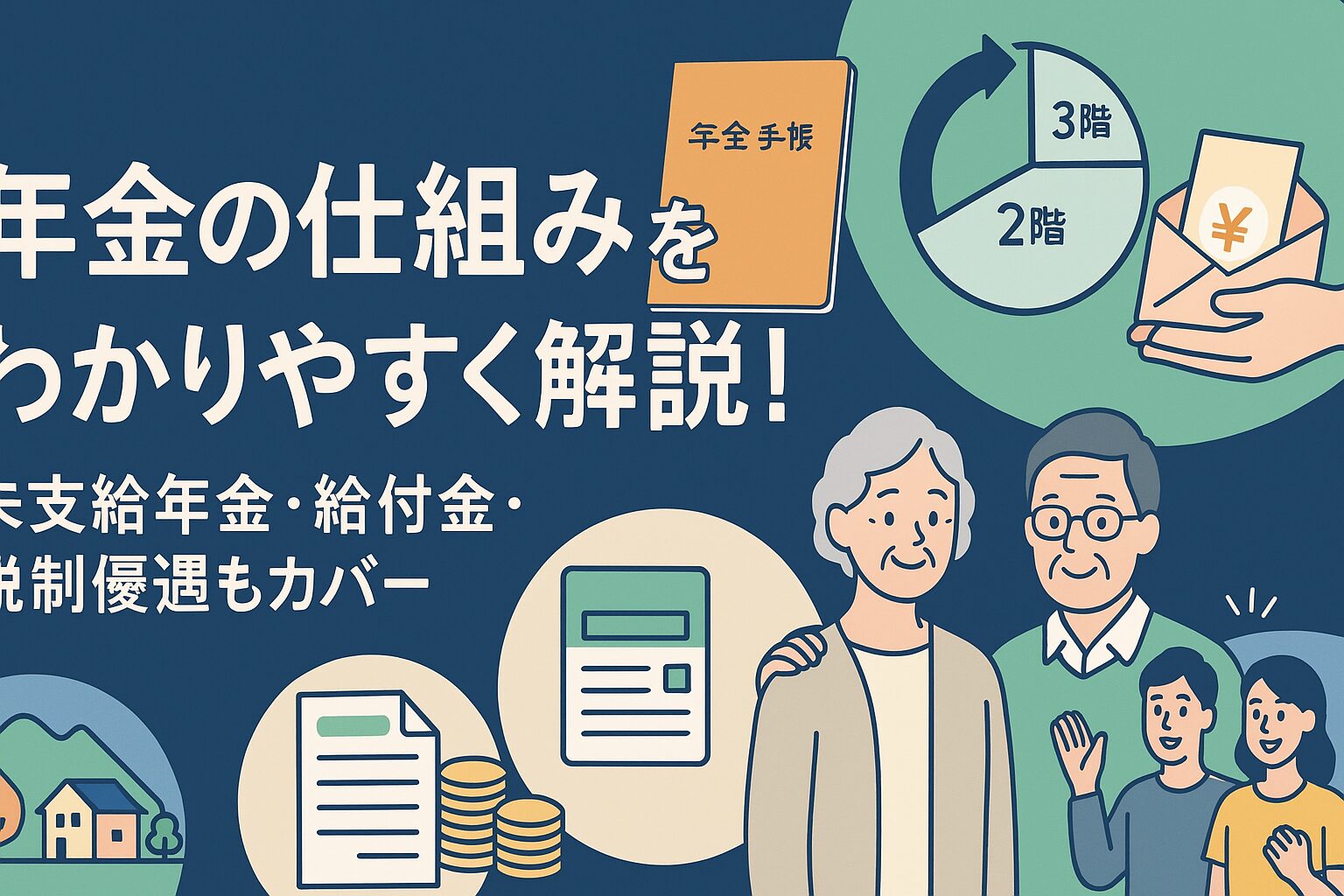
公的年金制度は、日本国民の生活を支える大黒柱として設計された社会保障制度です。
若い現役世代から高齢世代への支え合いという仕組みによって成り立ち、老後だけでなく障害や死亡といった人生のリスクにも対応する包括的な保障を提供しています。
公的年金には国民年金と厚生年金の二層構造があり、誰もがいずれかの形で加入して将来の給付を受け取る権利を築いています。
万一ご家族が年金受給中にお亡くなりになった場合には、未支給年金を速やかに請求することで、本来受け取れるはずだった年金をきちんと受け取ることができます。
また、所得の低い年金受給者には年金生活者支援給付金制度という追加支援策があり、生活面での心強い味方となります。
税制の面でも、公的年金は支払う保険料の控除や受給時の控除・非課税措置など様々な優遇が施されており、加入者・受給者にとって大きなメリットとなっています。
以上、公的年金制度の仕組みから関連する手続き・給付金・税制優遇まで幅広く解説しました。
公的年金は私たちの暮らしに密接に関わる制度です。
正しく理解し活用することで、老後の安心や万一の際の家族の生活保障につなげることができます。
ぜひ本記事の内容を参考に、公的年金制度の恩恵を最大限に活かして将来設計に役立ててください。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。