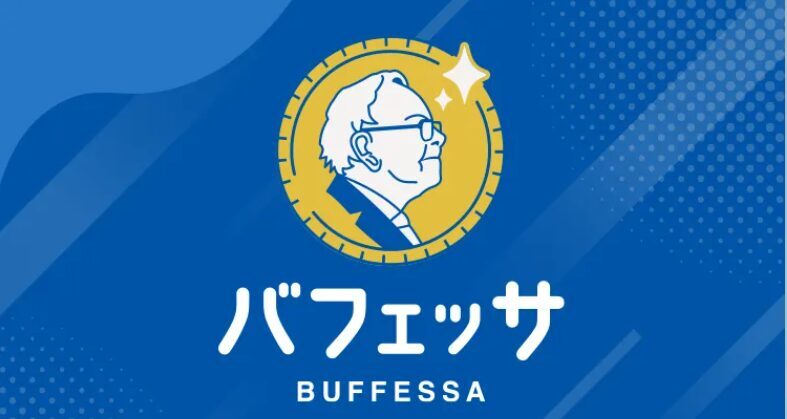※本ページはプロモーションが含まれています。
はじめに|建物には寿命がある?持ち家選びの新基準

「一生住める家が欲しい」と願ってマイホームを検討している方も多いと思います。
しかし、その家に“寿命”があることをご存じでしょうか?
建物にも人間と同じように老化があり、メンテナンスを怠ると寿命はどんどん短くなってしまいます。
特に日本では「戸建ては30年で建て替え」「マンションは50年で老朽化」というようなイメージが一般的に浸透していますが、実はこの認識には誤解が含まれていることもあります。
法定耐用年数と実際に住める年数(実寿命)は大きく異なり、メンテナンスの有無や構造、立地条件などによって寿命は大きく変わります。
本記事では、「住宅の寿命とは何か?」をテーマに、以下のような内容を分かりやすく整理していきます。
- マンションと戸建て住宅の寿命の違い
- 法定耐用年数と実寿命の違い
- 住宅を長く快適に使い続けるためのメンテナンス知識
- 物件選びで寿命に関わるチェックポイント
- 資産価値と寿命の関係
- 中古住宅でも寿命を延ばせる可能性
マイホームは「買って終わり」ではなく、「維持・管理して育てるもの」です。
住宅の寿命を意識して適切に対応すれば、何十年にもわたり安心して暮らせる住まいを手に入れることができます。
これから家を買う人はもちろん、すでに住宅を所有している方にとっても、本記事の内容は将来の備えとして役立つはずです。
まずは、「建物の寿命」という視点から、住まいについて一緒に考えていきましょう。
マンションの寿命は何年?法定耐用年数と実寿命の違い

マンションを購入する際、「この建物はあと何年使えるのか?」という点は非常に重要な判断材料になります。
しかし、多くの方が混同しやすいのが、「法定耐用年数」と「実際に住める年数(実寿命)」の違いです。
まず、法定耐用年数とは、税務上の建物の価値がゼロになるまでの年数を指します。
国税庁が定めているもので、鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションの場合、47年とされています。
これは減価償却という税務上の会計処理に使われる年数であり、決して「47年経ったら住めなくなる」という意味ではありません。
一方で、実寿命とは、適切なメンテナンスが行われた場合に実際に使用可能な年数を指します。
RC造マンションは構造的に強固で、70年〜100年超の使用も可能とされています。
実際に日本各地では築50年を超えるマンションでも、快適に暮らしている住民が多く存在します。
ここで重要なのは、「法定耐用年数=寿命ではない」という事実です。
税法上は価値がゼロになっていても、建物自体はまだまだ健全に使い続けられるケースが多いのです。
また、マンションは共用部の管理や修繕計画が整っている場合が多く、定期的な修繕がきちんと行われれば長寿命化しやすい特徴があります。
特に、以下の点がマンションの寿命に大きく影響します。
- 大規模修繕の実施状況(12〜15年周期が目安)
- 給排水管や電気設備の更新履歴
- 管理組合の運営体制と修繕積立金の状況
これらがしっかりしていれば、築50年を過ぎても快適に住めるマンションは数多くあります。
逆に、いくら新築であっても管理がずさんだったり、修繕計画がない物件では、寿命を縮めてしまう可能性があります。
マンション選びでは「築年数」だけでなく、「どう維持されてきたか」「今後の計画があるか」に注目することが非常に大切です。
住宅の寿命を判断する際には、法的な数字だけに惑わされず、「実際にどのくらい住めるのか」を見極める力を持つことが、後悔しないマイホーム選びにつながります。
戸建て(持ち家)の寿命は?構造によって大きく変わる
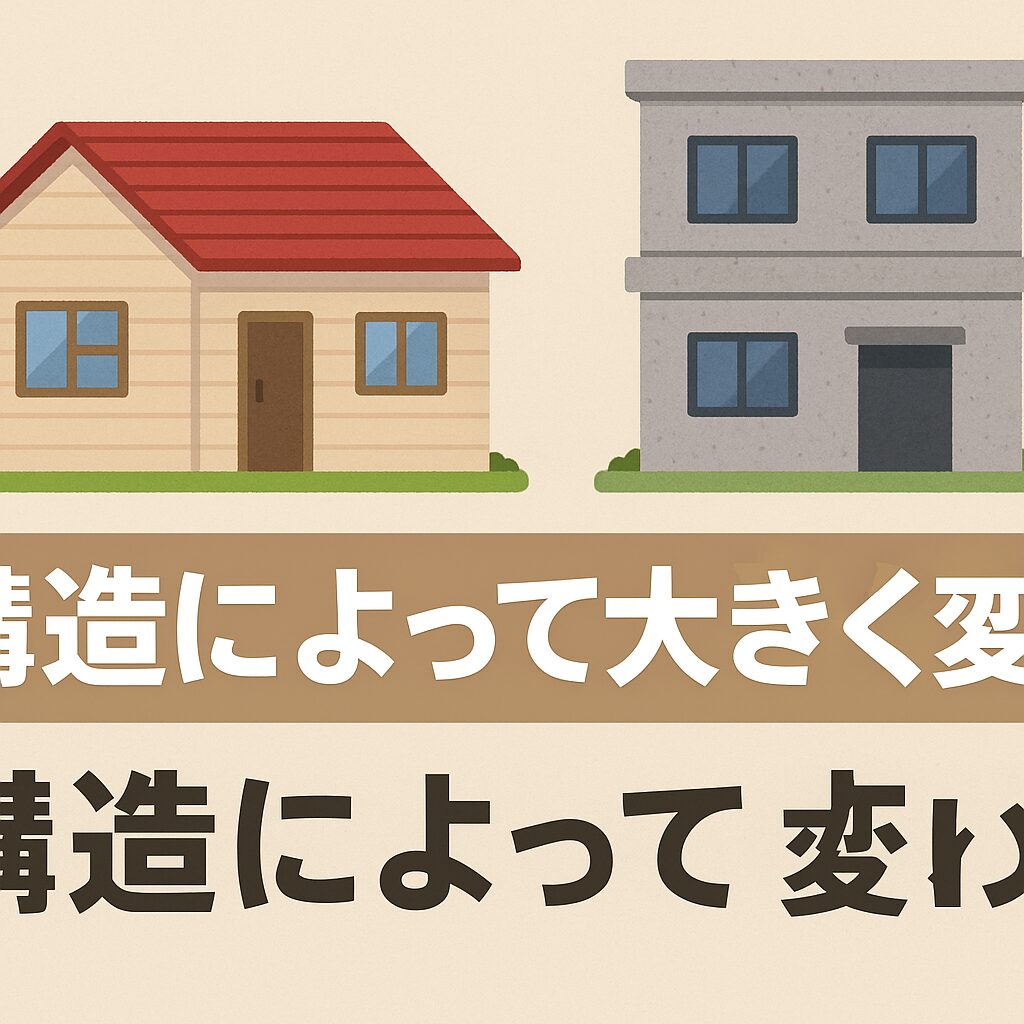
戸建て住宅の寿命は、マンション以上に「構造の違い」によって大きく左右されます。
一口に「持ち家」といっても、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、使われている素材や工法によって耐久性は異なり、寿命の目安も変わってきます。
まず、税務上の指標である法定耐用年数において、代表的な構造ごとの年数は以下の通りです。
- 木造住宅(在来工法):22年
- 木造住宅(2×4工法など):24〜33年
- 軽量鉄骨造:27年
- 鉄筋コンクリート造(RC造):47年
これらは税務上の「価値が減る期間」を示したものですが、実際の寿命(実寿命)とは一致しません。
特に木造住宅は法定耐用年数が短く見えますが、適切なメンテナンスをすれば30年〜80年、場合によっては100年近く持つこともあると言われています。
例えば、古民家として現存している築100年以上の木造住宅が良い例です。
つまり、「どんな構造か」だけでなく、「どう建てられ、どう手入れされてきたか」が寿命を大きく左右するのです。
戸建ての寿命に影響する主な要素は以下の通りです。
1. 使用されている構造材の品質
柱や梁に使われる木材の質が高く、乾燥や防腐処理がしっかり施されている場合、建物の劣化速度は遅くなります。
最近では集成材や耐久性の高い人工素材を使用する住宅も増えており、これらも寿命延長に寄与します。
2. ハウスメーカー・工務店の施工技術
同じ構造でも、施工の丁寧さで寿命は大きく変わります。
断熱処理や防水処理が不十分だと、結露や水漏れから劣化が早まることがあります。
信頼できる業者に建ててもらうことは、長寿命の第一歩です。
3. メンテナンスの有無
戸建て住宅は、屋根・外壁・基礎などの外部から、内装・設備に至るまで、住まい手自身が主体的に管理しなければならない点がマンションと異なります。
定期的な塗装、防水工事、配管の交換などを怠ると、家の寿命は一気に短くなってしまいます。
さらに、近年の戸建て住宅では「長期優良住宅」や「ZEH(ゼッチ)」といった、高耐久・高断熱性能を持つ仕様が増えています。
これらの家は設計段階から長寿命を前提としているため、適切な管理を行えば60年、80年、あるいはそれ以上の寿命も期待できます。
一方で、安価に建てられた建売住宅の中には、20年程度で主要構造が劣化してしまうケースもあるため、物件購入時は構造材や施工状況の確認が重要です。
まとめると、戸建ての寿命は「構造×施工×メンテナンス」の掛け算で決まります。法定耐用年数にとらわれず、「どれだけ丁寧に住み継がれているか」が大切です。
これから持ち家を選ぶ人も、今の自宅に住み続ける人も、寿命を延ばすための意識を持つことが、住宅の価値を守る大きなポイントとなるのです。
法定耐用年数と実際の寿命は違う?誤解されやすい3つのポイント

住宅の寿命を考えるうえで、よく耳にするのが「法定耐用年数」という言葉です。
しかしこの数字、必ずしも「家として住める年数」を示しているわけではありません。
ここでは、法定耐用年数と実寿命の違い、そして多くの人が勘違いしやすいポイントを解説します。
そもそも「法定耐用年数」とは?
法定耐用年数とは、税務上の減価償却計算のために定められた期間です。
例えば、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート(RC造)は47年という具合に、構造によって異なります。
これはあくまで「税務上、資産価値がゼロになるまでの年数」であり、「住めなくなる年数」ではない点が重要です。
では、実際に住める年数はどうなのでしょうか?
多くの住宅は、適切な維持管理さえ行えば、法定耐用年数を大きく超えて使い続けることができます。
木造住宅でも40〜60年、RCマンションなら70〜100年使える事例も珍しくありません。
以下に、よくある誤解ポイントを3つ取り上げ、正しい理解を深めていきましょう。
誤解①「法定耐用年数=家の寿命」
多くの人が「木造住宅は22年経てば価値ゼロ」と思い込んでいますが、それは会計上の話です。
実際には、22年で住めなくなるわけではなく、メンテナンス次第で住み続けられます。
むしろ築30年、40年でも快適に住んでいる人は多くいます。
逆に、20年未満でもメンテナンスが不十分だと雨漏りやシロアリ被害で寿命が短くなることもあるため、年数よりも状態が大事という意識が必要です。
誤解②「築年数が古い家=価値がない」
不動産市場では「築年数=価値の目安」とされがちですが、実はそれだけで評価するのは危険です。
最近はリフォームやリノベーションをしっかり行った住宅であれば、築年数が古くても市場価値を維持している例もあります。
また、特にマンションでは「築30年以上でも修繕計画がしっかりしていて快適に住める」物件が増えてきました。
大切なのは「築年数」ではなく、「劣化状況」や「維持管理履歴」です。
誤解③「古いから買わない、新しいから安心」
新築や築浅の家は当然きれいで魅力的ですが、「安心」とは限りません。
近年は建築の品質にもばらつきがあり、短期間で不具合が出るケースも報告されています。
逆に、築年数が経っていてもメンテナンスが丁寧にされてきた物件は、今後も長く安心して住めることが多いです。
購入時には、「築年数が若い=安全」ではなく、「建物の状態・修繕履歴・施工品質」をしっかり確認しましょう。
状態重視の家選びが主流に
今や住宅の選び方は「築年数」だけで判断する時代ではありません。むしろ「状態を見て判断する」スタイルが主流になりつつあります。
購入・売却・住み続けるいずれの場合でも、「この家はあと何年住めるか?」を考えるなら、法定耐用年数よりも点検履歴・修繕状況・施工品質を重視するべきです。
将来の資産価値にも直結するため、「築○年だから古い」ではなく、「この建物はどんな状態か?」という視点で見直してみましょう。
100年住むために必要なメンテナンスとは?

住宅の寿命を延ばす最大のカギは、日々の「メンテナンス」にあります。
構造材の違いや築年数だけでなく、どれだけ適切なタイミングで点検・修繕を行ってきたかが、家の健康寿命を大きく左右します。
ここでは、100年住める家を目指すために押さえておきたい、部位ごとのメンテナンス内容と周期、そして実施のポイントを時系列で整理してご紹介します。
1. 屋根のメンテナンス(10~20年ごと)
屋根は雨風や日差しから家全体を守る重要な部分です。
種類によって耐久性が異なり、以下のようなメンテナンス周期が目安です。
- スレート屋根:10〜15年ごとに塗装、30年で葺き替え
- 金属屋根:15〜20年ごとに塗装または部分交換
- 瓦屋根:30〜40年で葺き直し、ただし漆喰や防水紙は10〜20年ごとに点検が必要
小さなヒビ割れやコーキングの劣化を放置すると雨漏りの原因になります。定期点検を怠らず、早期補修を心がけましょう。
2. 外壁のメンテナンス(10~15年ごと)
外壁は美観だけでなく、断熱性や防水性にも関わります。
- サイディング:10〜15年ごとに塗装・シーリング打ち直し
- モルタル壁:10年ごとに塗装が必要、ひび割れチェックも重要
コケやカビ、ひび割れは劣化のサイン。塗膜が剥がれてきたら早めに塗装することで、劣化を防げます。
3. 給排水管・配管類(20~30年ごと)
見えない部分ほど危険が潜んでいます。
水漏れや詰まりは深刻なダメージになるため、定期的な点検と交換が不可欠です。
- 鉄管(昔の住宅に多い):20~25年で交換
- 塩ビ管(現代の標準仕様):30年程度を目安に点検・交換
リフォームの際には配管もチェックしておくと安心です。
4. 給湯器・空調設備(10~15年ごと)
生活の快適さを保つうえで欠かせない設備機器も、寿命が来れば入れ替えが必要です。
- 給湯器:10~15年程度が目安
- エアコン:10~12年で寿命、電気代節約のためにも更新がおすすめ
- 換気扇・レンジフード:15年で交換目安
急に壊れて生活に支障が出る前に、計画的に交換しましょう。
5. 電気系統・配線(30年以降に要注意)
漏電や火災のリスクがあるため、築30年を超えたら必ず点検を行いましょう。
古いブレーカーやコンセント、分電盤の劣化もリスクになります。
- 分電盤・配線:30~40年で交換
- 照明配線・コンセント類:必要に応じて更新
リフォーム時に一緒に見直すと効率的です。
6. シロアリ・基礎の点検(5~10年ごと)
特に木造住宅ではシロアリ対策が不可欠です。床下や基礎の点検を定期的に行い、必要に応じて防蟻処理を実施します。
- 床下点検:5~10年ごと
- 防蟻処理:5年ごとが目安
点検サービスを提供しているハウスメーカーや業者も多いため、活用するのも手です。
メンテナンススケジュールの一例(時系列で見る)
| 年数 | 主なメンテナンス内容 |
|---|---|
| 5~10年 | 外壁塗装、シロアリ点検、換気設備清掃 |
| 10~15年 | 屋根塗装、給湯器交換、配管点検 |
| 20~30年 | 外壁張り替え、屋根葺き替え、配管交換 |
| 30~40年 | 電気配線点検・更新、基礎の再チェック |
長寿命住宅は「こまめな管理」から生まれる
住宅は車と同じで、定期的なメンテナンスを怠ると寿命が一気に縮みます。
小さな補修を怠らず、問題が起きる前に対処することで、100年住み続けられる家を実現できます。
メンテナンス費用は一時的には負担ですが、長い目で見れば資産価値を維持する投資とも言えます。
今後の人生設計や家族のライフスタイルに合わせて、計画的に家を育てていきましょう。
買う前に確認したい!寿命に関わる物件チェックポイント

マイホームの購入は人生最大級の買い物です。
だからこそ、「建物の寿命」に関わるポイントを事前にしっかり確認することが重要です。
ここでは、マンション・戸建てそれぞれにおいて、購入時にチェックすべき項目を具体的にご紹介します。
「何十年先まで住めるか」という視点で住まいを選ぶことで、将来の修繕負担や後悔を大幅に減らすことができます。
マンション購入時に見るべきチェック項目
1. 大規模修繕の履歴と予定
マンションは共有部分(外壁・屋上・廊下など)の修繕が定期的に行われます。
購入時には、以下の点を確認しましょう。
- 過去に実施された大規模修繕の時期と内容
- 次回の修繕予定と予算
- 修繕積立金の現在の残高と、将来の値上げ予定
これらは管理組合から「重要事項調査報告書」として入手できます。
修繕計画が適切でなければ、建物の劣化が早まったり、予想外の費用負担が発生したりする可能性があります。
2. 建物の耐震性能と構造
築年数に関わらず、耐震基準を満たしているかどうかは重要な指標です。
1981年(昭和56年)6月以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」となり、それ以前のものより耐震性が高くなっています。
- 新耐震基準に適合しているか
- 耐震補強工事の実施歴があるか
- 構造は鉄筋コンクリート(RC)か?鉄骨か?
耐震性の低いマンションは、長期的に見て資産価値の低下や売却困難に繋がるリスクもあります。
3. 管理状況と管理会社の信頼性
「管理を買え」とも言われるマンション購入。管理体制がしっかりしていれば、建物は長く快適に使えます。
- 清掃や設備の保守点検がきちんと行われているか
- 管理組合が機能しているか(理事会や総会の開催状況)
- 管理会社の実績や対応の良し悪し
ゴミ捨て場や共用部分の清潔さも、管理体制の質を表すサインです。
戸建て購入時に見るべきチェック項目
1. 構造材と工法の種類
木造と一口に言っても、在来工法・ツーバイフォー工法・鉄骨造など多様です。
耐久性や断熱性に差が出るため、以下の情報を確認しましょう。
- 構造材(無垢材、集成材、合板など)の種類
- 土台や柱の防蟻処理の有無と時期
- 工法(例:木造在来軸組み工法 or ツーバイフォー)
特に新築戸建てでは、構造材の説明を営業担当にしっかり確認し、構造計算書や設計図書を保存しておくことをおすすめします。
2. 地盤の強さと地歴
住宅の寿命は建物だけでなく「地盤」にも大きく影響されます。
地盤が弱ければ、いくら建物が丈夫でも沈下やひび割れのリスクがあります。
- 地盤調査報告書(スウェーデン式サウンディング試験など)の有無
- 周辺地域の地歴(土地の履歴)に液状化や埋立の可能性がないか
ハザードマップも併せて確認し、災害リスクも考慮しましょう。
3. 断熱性能と住宅性能表示制度
断熱性が高い家は、結露や湿気による劣化を防ぎ、住宅の寿命延長に貢献します。
- 断熱等性能等級(1~7)の等級は何か?
- 窓サッシは複層ガラスか?
- 換気設備の種類と性能
新築であれば住宅性能評価書、中古であれば断熱リフォーム歴の有無を確認すると良いでしょう。
4. 施工会社の実績とアフターサービス
どんなに立派な家でも、施工会社の質次第で耐久性が変わってしまいます。
- 過去の施工実績や評判
- 長期保証制度(例:構造躯体10年保証)やメンテナンスサービスの内容
- 建築確認・検査済証が発行されているか
特に建売住宅では、安さだけで判断せず、「誰がどのように建てた家か?」に注目してください。
見逃しがちな共通チェックポイント
- 雨漏り歴の有無(壁紙や天井のシミ)
- 周辺環境(騒音・日当たり・通風)
- 住宅履歴情報(リフォーム歴や点検記録)
- 建物インスペクション(専門家による住宅診断)を依頼可能か
これらのチェックは、新築でも中古でも共通して重要です。
「長く住む視点」での選択が後悔を防ぐ
見た目や価格に惑わされず、「どれだけ長く、快適に、安全に住めるか」という視点で物件を選ぶことが、賢い住宅購入の第一歩です。
長寿命の住まいは、安心感だけでなく資産価値の維持にも繋がります。
「買った後の未来を想像しながら選ぶ」ことが、住まい選びの本質です。
資産価値にも影響?寿命とリセールバリューの関係

住宅を購入する際、多くの人が「何年住めるか」に注目しますが、もう一つ忘れてはいけない視点が「将来の売却価値」、つまりリセールバリューです。
建物の寿命は、そのまま資産価値の維持や下落スピードに直結します。
ここでは、マンションと戸建てにおける資産価値と寿命の関係を解説し、売却時にも有利になる住まい選びのヒントを紹介します。
マンションは築30年を超えても価値を維持できる?
一般的に、マンションは築年数が経過するごとに資産価値が下がると言われています。
確かに税務上は47年で耐用年数が終了しますが、それは「減価償却上の数字」であり、実際には70〜100年使用可能な建物もあります。
特に以下の条件を満たすマンションは、築30年を超えても一定の資産価値を維持しています。
- 定期的に大規模修繕が実施されている
- 管理組合が機能しており修繕積立金が安定している
- 立地が良好(駅近・商業施設が多いなど)
- 耐震性や設備が現代基準に近い
たとえば東京都心のヴィンテージマンションなどは、築40年を超えても高値で取引されるケースがあります。
つまり、見た目や築年数だけで価値を判断するのは早計だということです。
戸建ては「土地>建物」が基本構造
一方、戸建て住宅はマンションと比べて、「建物の価値は年々減少し、最終的にはゼロになる」と言われがちです。
これは不動産評価の現実であり、特に木造戸建てでは築20〜30年を超えると建物価値が大幅に減少する傾向があります。
ただし、これは「法定耐用年数に基づいた評価」であり、実際に使用できる年数とは異なります。
建物の実寿命が延びれば、買い手にとっても魅力が増し、売却価格にも影響します。
また、戸建ての資産価値は「建物」よりも「土地」に重きが置かれます。
たとえ建物価値がゼロと見なされても、立地や地形が良ければ土地価格がしっかりと残ります。
そのため、長期的に資産価値を維持したいなら、立地選びが極めて重要です。
メンテナンス履歴が「売却時の武器」になる
マンション・戸建て問わず、建物の価値を維持・向上させる鍵は適切なメンテナンスの履歴です。
以下のような記録が整っていると、売却時の信頼性が高まり、買い手が付きやすくなります。
- 屋根や外壁の塗装履歴
- 給排水設備の交換記録
- 白アリ防除・耐震補強の有無
- インスペクション(住宅診断)の実施記録
これらの情報は、住宅履歴情報として保存しておくことが可能で、住宅性能評価書と並んで評価材料になります。
特に中古住宅を買う人は「手入れされてきた家かどうか」を重視するため、日ごろの管理が将来の売却を左右するのです。
高寿命=資産価値の安定につながる
建物の寿命が長ければ、それだけ住み続けられる年数が伸びるだけでなく、住宅ローン完済後にも資産として機能する可能性が高くなります。
将来子どもに譲る、売却する、賃貸に出す──いずれの選択肢も取りやすくなるのです。
反対に、メンテナンスを怠り、劣化が進んでしまうと、資産価値が急激に下がり、「売れない家」になるリスクもあります。
寿命=資産価値という考え方は、これからの住まい選びにおいてますます重要になってくるでしょう。
【補足】中古住宅でも“長寿命”は狙える?見極めのポイント

「新築でなければ寿命が短いのでは?」という不安を抱く方は少なくありません。
しかし、しっかりと管理・メンテナンスされた中古住宅であれば、新築に劣らない長寿命を実現することも可能です。
この章では、中古住宅の寿命を見極めるためのチェックポイントや、寿命を延ばすためのリフォーム戦略を紹介します。
中古住宅の寿命は「管理履歴」で決まる
建物の寿命は築年数だけでは判断できません。
特に中古住宅の場合、以下のような管理履歴の有無が、寿命に大きく影響します。
- 過去の修繕・リフォーム履歴(屋根、外壁、給湯器、キッチンなど)
- 白アリ対策や防水工事の実施履歴
- 定期的な点検(住宅診断=インスペクション)を受けているか
- 長期修繕計画(マンションの場合)の有無
これらがしっかりと記録されている住宅は、築年数が多少経過していても建物のコンディションが良好である可能性が高いです。
中古でも“狙い目物件”は存在する
中古住宅を購入する際には、以下のような条件が揃った物件を狙うことで、長寿命かつ高コスパな住まいを手に入れやすくなります。
- ハウスメーカー施工や有名工務店による建築
- 耐震基準が現行(2000年以降)の建物
- インスペクション済みの物件
- 長期優良住宅に認定されている、またはその要件を満たす構造
これらの住宅は中古でも人気が高く、リセールバリューも安定している傾向があります。
築年数だけに目を奪われず、こうした「見えない価値」に注目しましょう。
リフォームで寿命を延ばすという選択肢
購入後にリフォームを行うことで、建物の寿命をさらに延ばすことができます。
特に以下のような部位・設備は、20〜30年を超えると交換・改修が必要になるため、リフォームの候補となります。
- 屋根・外壁の再塗装や張り替え(目安:10〜15年ごと)
- キッチン・浴室・トイレなど水まわり設備(20〜30年目安)
- 給排水管の交換(30年程度で劣化)
- 断熱材や窓のリフォームで省エネ性能を向上
これらを計画的に更新することで、住宅としての機能・快適性を保ちつつ、耐久性を向上させることが可能です。
特に断熱性能や耐震性能の向上は、「長く住む」だけでなく、「安心して住む」ためにも大きな意味を持ちます。
見極めのためのチェックリスト
中古住宅の寿命を判断する際には、以下のチェックリストを活用しましょう。
- 築年数だけで判断せず、メンテナンス履歴を確認
- 屋根・外壁・基礎に劣化やひび割れがないか
- 水まわりに水漏れ・カビ・腐食がないか
- 床や柱に傾き・沈み込みがないか
- 白アリ対策がされているか
- 断熱性能や気密性は十分か(結露やカビの原因になる)
- 耐震補強がされているか、もしくは補強可能か
可能であれば、購入前に第三者機関による住宅診断(インスペクション)を依頼すると安心です。
診断結果をもとに、寿命を延ばすための補修やリフォームの計画も立てやすくなります。
中古住宅でも「育てていく意識」がカギ
新築と違い、中古住宅はすでに「過去の手入れ」が寿命を左右します。
しかし、逆に言えば「手入れさえすれば長く使える」余地が残っているともいえるのです。
今後は新築住宅の供給が減少していく中で、中古住宅を再生して使う文化がますます広がっていくと考えられます。
その中で「メンテナンスを怠らない住まい」は、世代を超えて住み継がれる資産となるでしょう。
まとめ|寿命を伸ばす工夫が資産を守ることにつながる

住まいの寿命について考えることは、「どれだけ長く快適に暮らせるか」という視点だけでなく、「どれだけ資産価値を守れるか」という視点にも直結します。
マンションでも戸建てでも、寿命は単に年数の問題ではなく、日々のメンテナンスや暮らし方次第で大きく変わるのです。
本記事では、法定耐用年数と実際の寿命の違いや、構造による差、メンテナンスの重要性、購入時のチェックポイントなど、住まいの寿命を左右するあらゆる要素を詳しく紹介してきました。
改めて、寿命と資産価値の関係を以下にまとめます。
- 法定耐用年数=税務的な目安であり、実際の寿命とは異なる
- 構造や材料、施工品質によって寿命は大きく異なる
- 定期的なメンテナンス・修繕履歴が寿命を伸ばすカギ
- 中古住宅でも、状態が良ければ長寿命・高リセールが可能
- 寿命を意識した住宅選びは、将来の資産価値を守る第一歩
特に最近では「新築でなければ価値がない」という考え方も見直されつつあります。
築年数よりも“建物の状態”が重視される時代です。購入後も「住まいを育てる」という意識を持ち、定期的に点検・補修を行っていけば、長く快適に、そして安心して住み続けられることでしょう。
人生100年時代と言われる今、「住まいの100年寿命」を実現することも、決して夢ではありません。
そしてその過程で得られるのは、単なる建物の維持ではなく、暮らしそのものの安心や、家族の資産を守ることでもあります。
この記事を通して、読者の皆さまが「住まいの寿命」について一歩踏み込んで考え、自宅や購入検討中の物件を見直すきっかけとなれば幸いです。
ちなみに無料でお金の勉強したいって方には、バフェッサがおすすめ!
動画を見るだけでお金の勉強ができて、倍速受講もできるのでこちらも活用するのといいよ👇

イメージキャラクターとして藤本美貴さんを起用しており、特別講師も務められているのも安心感ありますね!
>NISAを始めたい方や投資を始めたい方でバフェッサの詳細が気になる方は、こちらもご覧ください👇
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
新NISA口座をまだ開設していない方は今すぐ開設しましょう!
>おすすめ新NISAの証券口座が知りたい人は、こちらからご覧ください
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。