年末調整とは?知らないと損する“税金の最終チェック”
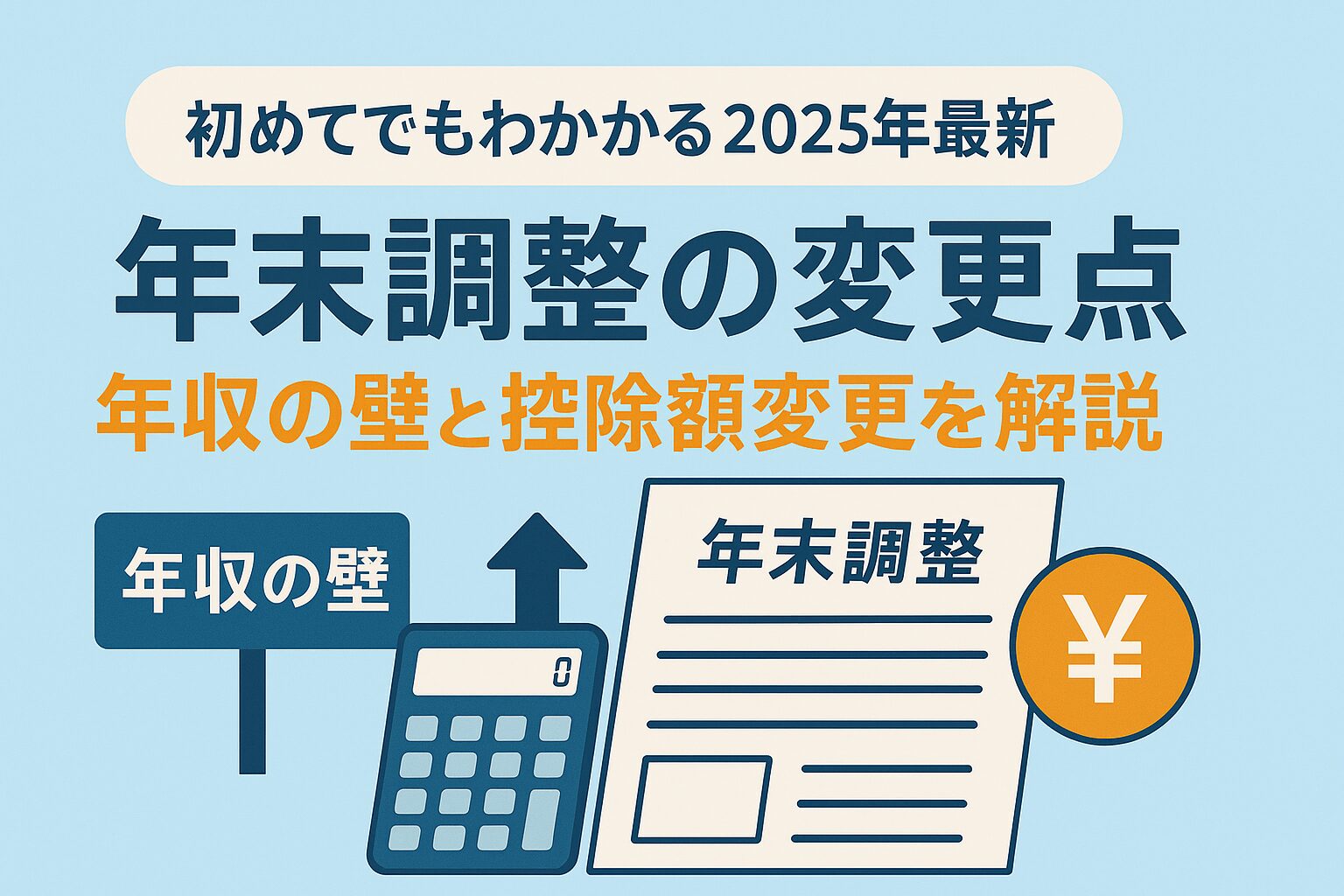
年末調整とは、1年間の給与から天引きされた所得税の過不足を精算する手続きです。
会社が従業員に代わって税金を正しく計算し、払いすぎた税金を返す(還付)、または不足分を追加で納める(徴収)ことを目的としています。
たとえば、毎月の給料から差し引かれる所得税は「仮の金額」です。
年の途中で結婚・出産・住宅ローンなど生活状況が変わると、最終的な税額とズレが生じます。
このズレを12月の給与計算時に修正するのが「年末調整」です。
まずはこちらをご覧ください👇
年末調整と確定申告の違い
「年末調整」と「確定申告」は混同されやすいですが、次のような違いがあります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 会社が代行 | 自分で行う |
| 対象者 | 給与所得者(会社員など) | 個人事業主・副業所得者など |
| 目的 | 給与所得の税金精算 | すべての所得を合算して精算 |
| 実施時期 | 毎年11〜12月頃 | 翌年2月16日〜3月15日頃 |
会社員やパート・アルバイトなどは、基本的に年末調整を受ければ確定申告は不要です。
ただし、副業収入や医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)などがある場合は、別途確定申告が必要です。
なぜ「年末」に行うのか?
所得税は1月から12月の1年間を単位として計算します。
そのため、年末のタイミングで「1年分の所得」が確定することから、年の締めくくりとして調整が行われます。
会社では通常、11月下旬〜12月の給与計算時にまとめて処理され、同時に翌年の扶養控除申告書も提出します。
この時期に手続きを忘れると控除が適用されず、本来より多く税金を払うことになります。
逆に、正しく書類を提出すれば1〜2万円以上の還付金を受け取るケースも珍しくありません。
年末調整の流れをわかりやすく
初心者の方でもイメージしやすいように、手続きの流れを簡単に整理します。
- 会社から申告書が配布される(10月〜11月頃)
- 扶養・配偶者・保険料などを記入して提出
- 会社が1年分の給与と税金を再計算
- 過不足分を12月給与で精算(還付または徴収)
この流れの中で、控除に関する申告内容が正確であることが何より大切です。
2025年は控除項目や所得要件が大幅に変わるため、例年通りに書いたつもりがミスになるケースも増えます。
次章で、その「変更点の全体像」をわかりやすく解説します。
ポイントまとめ
- 年末調整は「税金の最終チェック」
- 会社が税金を再計算し、払いすぎ・不足を調整
- 手続き時期は毎年11〜12月ごろ
- 書類記入ミスや提出漏れは還付金を逃す原因に
- 2025年は“過去最大級の改正年”、内容理解が必須
2025年の年末調整で何が変わる?大改正ポイント総まとめ
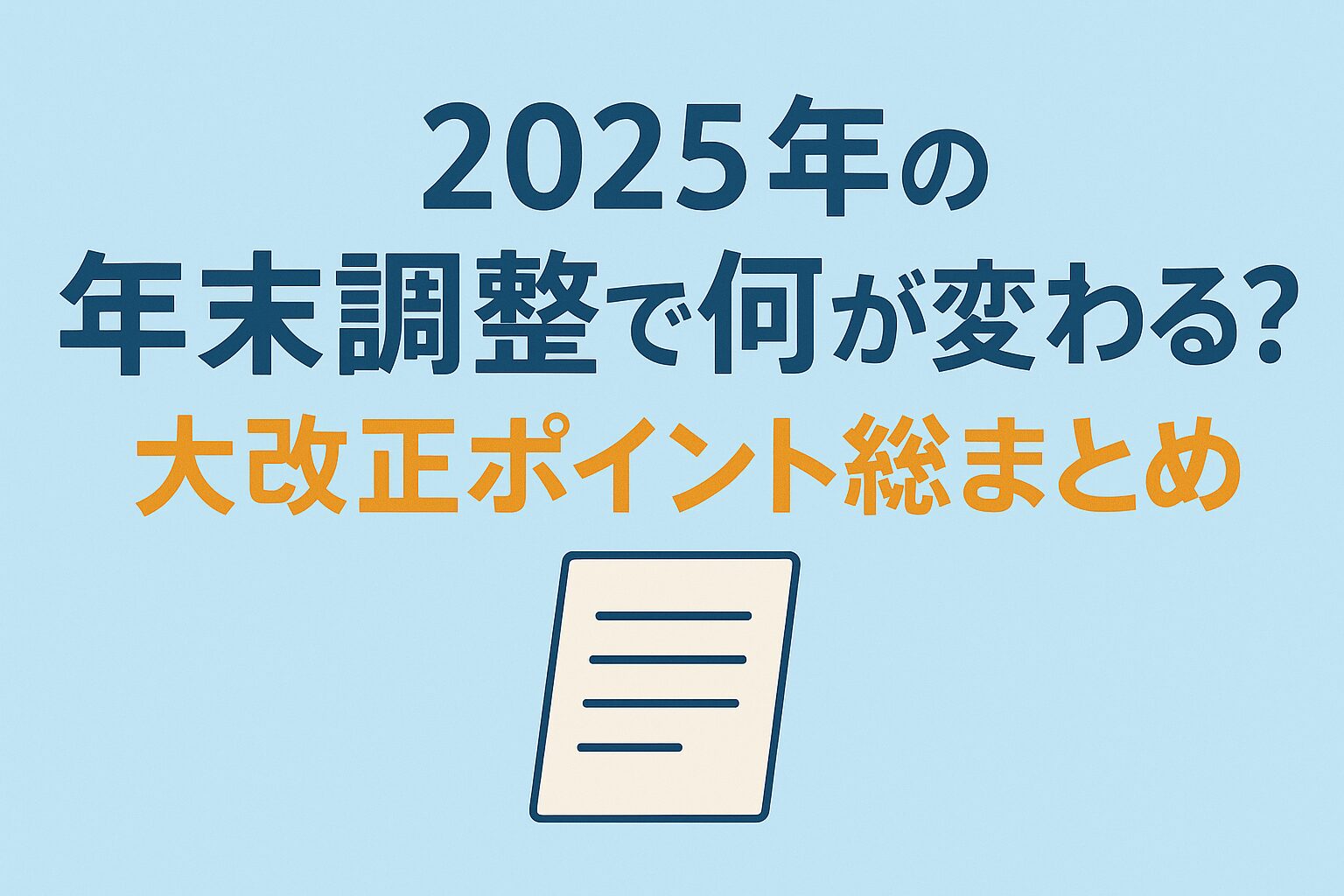
2025年の年末調整は、過去10年で最も大きな制度改正の年です。
特に「年収の壁」「基礎控除・扶養控除の引き上げ」「特定親族特別控除の新設」など、家計に直結する変更が一気に行われます。
「例年通りの記入で大丈夫」と思っていると、控除漏れや追徴課税のリスクもあるため注意が必要です。
改正の背景にある“年収の壁”問題
今回の改正の最大の狙いは、パート・主婦・学生アルバイトなどの就業調整問題を解消することです。
これまで、年収が103万円を超えると扶養から外れ、税負担や社会保険料が急に増える「年収の壁」が課題となっていました。
2025年からは、基礎控除・給与所得控除が大幅に引き上げられ、非課税枠が160万円まで拡大します。
これにより、パートや副業を増やしても「扶養を外れない」ケースが増える見込みです。
主な変更点一覧(総論)
2025年の年末調整では、以下のような改正が行われます。
| 改正項目 | 改正内容 | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 → 最大95万円へ | 全納税者 |
| 給与所得控除 | 最低65万円に引き上げ | 会社員・パート |
| 扶養控除・配偶者控除 | 所得要件が48万円 → 58万円へ緩和 | 家族を扶養している人 |
| 特定親族特別控除 | 新設(19〜23歳・所得58〜123万円) | 学生の子どもがいる家庭 |
| 住宅ローン控除 | 電子データ連携「調書方式」が追加 | 住宅ローン利用者 |
| 提出書類 | 新申告書様式(特定親族特別控除申告書など) | 会社員全体 |
このように、控除額の拡大と手続き方式のデジタル化が今回の大きな特徴です。
改正の目的と狙い
今回の税制改正は、少子高齢化・共働き増加・副業普及などの社会変化に合わせ、
「働く意欲を損なわずに、世帯の実収入を確保できるようにする」ことを目的としています。
とくに「年収の壁問題」は、主婦や学生が「扶養から外れるのが怖いから働きすぎない」という構造を生んでいました。
2025年からは、一定の収入増があっても税制面で急激な負担増にならないよう、段階的な控除方式に見直されています。
誰にどんな影響があるのか
- 共働き世帯の主婦(夫)
→ 扶養控除や配偶者特別控除の緩和で、年収123万円までなら扶養内を維持できる可能性。 - 学生アルバイトがいる家庭
→ 新設の「特定親族特別控除」により、子どもの年収188万円未満までは扶養のまま控除が受けられるケースも。 - 給与所得者(会社員)全般
→ 基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、税負担が軽減される傾向。 - 住宅ローン控除を受けている人
→ 電子化により手続きがスムーズになり、書類提出の手間が減少。
2025年改正のスケジュール
- 2025年1月:新控除制度が適用開始
- 2025年10月頃:会社で新様式の申告書配布開始
- 2025年11月〜12月:新制度に基づいた年末調整を実施
- 2026年1月:還付金(または追徴分)が反映
つまり、2025年末の調整で初めて新制度が反映されるため、今年の提出内容が翌年の税金額を左右します。
今知っておくべきこと
- これまでの「103万円の壁」は実質的に160万円の壁に。
- 控除の種類と提出書類も変わるため、前年のコピー記入は危険。
- 家族の年収や勤務状況を正確に把握し、早めに確認することが重要。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ(変更点1)
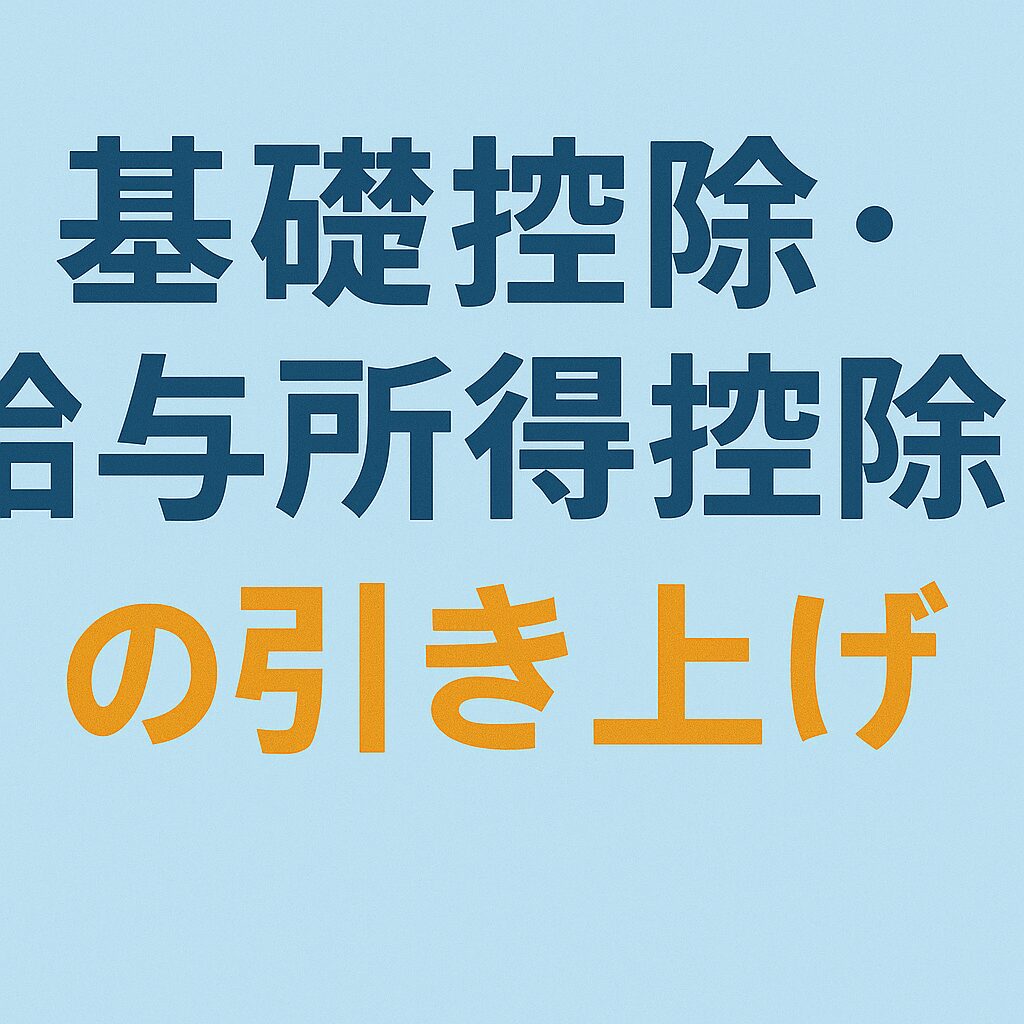
2025年の年末調整では、最も注目すべき改正が「基礎控除」と「給与所得控除」の引き上げです。
この2つの控除は、すべての給与所得者に関係し、実質的に誰でも減税の恩恵を受ける可能性があります。
控除額が増えるということは、課税対象となる所得が減る──つまり、手取り収入が増えることを意味します。
基礎控除の引き上げ内容
従来、すべての人に一律で適用されていた基礎控除は48万円でした。
2025年からは、所得に応じて段階的に58万円〜95万円まで引き上げられます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 95万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 70万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 45万円 |
| 2,500万円超 | 控除なし |
多くの給与所得者やパート勤務者は年収2,400万円未満のため、実質的に全員が95万円の控除を受けられることになります。
給与所得控除の引き上げ内容
給与所得控除とは、会社員やアルバイトなど「給与をもらっている人」に自動的に適用される控除です。
これまでは最低65万円が上限でしたが、2025年からは一律で65万円を保証しつつ、上限額も見直しが行われます。
具体的には、給与収入が増えても控除額が段階的に変わり、より公平な税制に改善されています。
これにより、低所得層だけでなく中堅所得層にも負担軽減の効果があります。
「160万円の壁」に変更された理由
これまで「103万円の壁」と呼ばれていた所得制限は、基礎控除と給与所得控除の合計によって成り立っていました。
従来の構造:
- 基礎控除 48万円
- 給与所得控除 55万円
→ 合計 103万円までは非課税
2025年からは:
- 基礎控除 95万円
- 給与所得控除 65万円
→ 合計 160万円まで非課税
つまり、パートや副業をしても年収160万円までは税金がかからないということになります。
これにより「扶養から外れないように働き方を調整する」必要が減り、家庭の実収入が増えやすくなります。
家計への具体的な影響
たとえば、パート主婦が年収150万円で働く場合、これまでなら課税対象でしたが、
新制度では非課税範囲内となり、年間で約3〜5万円の減税効果が見込まれます。
また、会社員の場合も基礎控除の引き上げによって、実質的な手取りアップが期待できます。
たとえば年収500万円の人なら、所得税と住民税を合わせて年間約1〜2万円の軽減効果があります。
注意点:社会保険の壁は別問題
ただし、今回の改正は「税金」の控除に関するものであり、社会保険の加入要件とは別です。
年収が130万円(または106万円)を超えると社会保険加入義務が発生するケースもあります。
したがって、「税金は非課税でも保険料負担が増える」可能性がある点には注意が必要です。
ポイントまとめ
- 基礎控除が 48万円 → 最大95万円 に引き上げ
- 給与所得控除も 最低65万円を保証
- 非課税範囲は 103万円 → 160万円 に拡大
- 家計の手取りが増加、扶養調整の負担が軽減
- 社会保険の壁とは別ルールのため要確認
扶養控除・配偶者控除の所得要件緩和(変更点2)
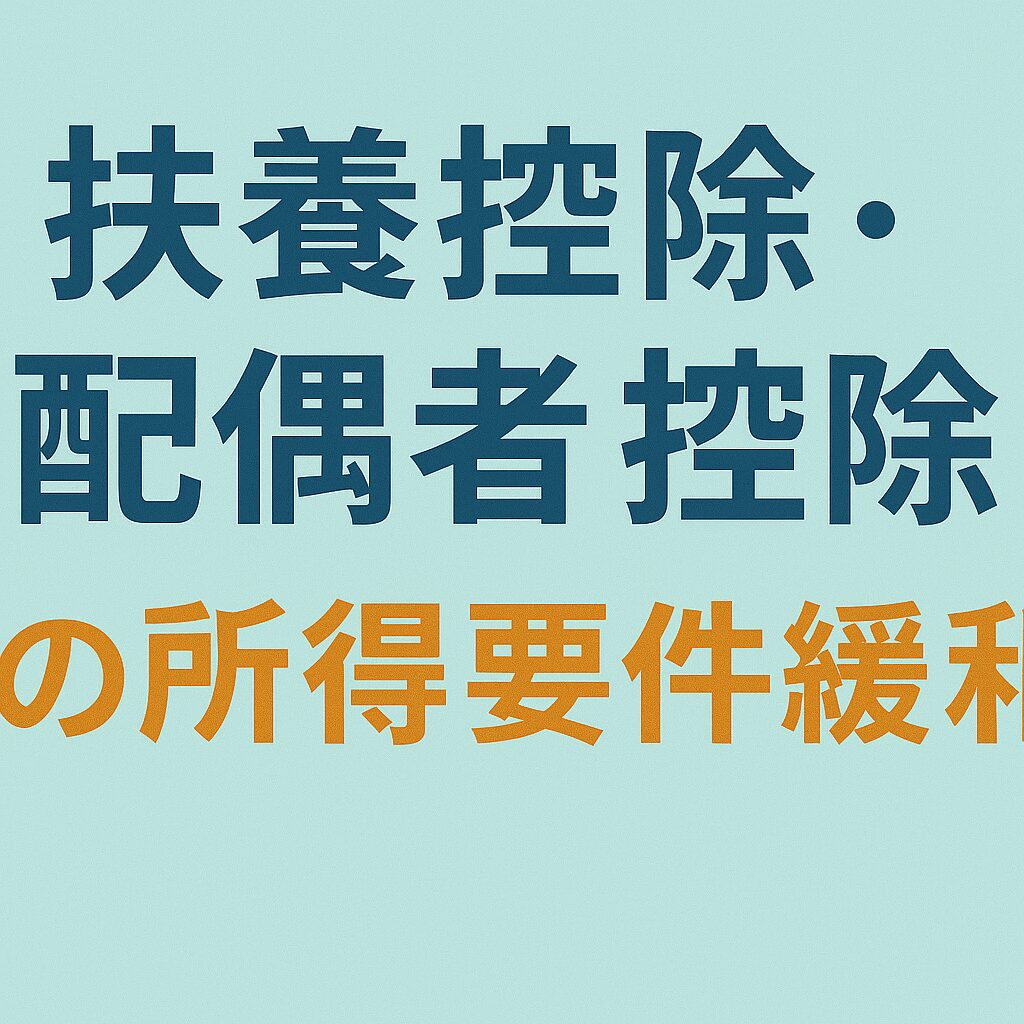
2025年の年末調整では、「扶養控除」や「配偶者控除」にも大きな変更がありました。
特に、扶養親族や配偶者の“所得上限”が引き上げられたことにより、これまで扶養から外れていた人が再び対象になる可能性があります。
共働き家庭やパート勤務の主婦・夫にとって、非常に重要な改正です。
扶養控除の変更点
これまで、扶養親族として認められるのは「合計所得48万円以下(給与収入換算で約103万円以下)」の人でした。
2025年からは、合計所得58万円以下(給与収入換算で約123万円以下)まで緩和されます。
つまり、子どもや配偶者が少し多く働いても、引き続き扶養に入れるようになりました。
| 項目 | 旧制度(〜2024年) | 新制度(2025年〜) |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件 | 合計所得48万円以下 | 合計所得58万円以下 |
| 給与収入換算 | 約103万円以下 | 約123万円以下 |
| 扶養控除額(一般) | 38万円 | 38万円(変更なし) |
この改正によって、「103万円を超えたから扶養から外れる」という従来のラインが緩和され、働き方の自由度が広がります。
配偶者控除・配偶者特別控除の改正ポイント
配偶者控除についても、同様に所得要件が緩和されています。
配偶者控除を受けるための配偶者本人の所得上限が、48万円 → 58万円に引き上げ。
さらに「配偶者特別控除」の対象となる年収範囲も拡大し、150万円超〜201万円までが対象となりました。
| 区分 | 控除対象となる配偶者の年収(目安) | 控除額(最大) |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 123万円以下 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 123万円超〜201万円以下 | 1〜38万円(段階的に減少) |
この結果、共働き世帯でも控除を受けられる範囲が広がり、世帯全体の税負担が軽くなります。
勤労学生控除も拡大
学生アルバイトへの支援として、勤労学生控除の上限も「75万円 → 85万円」へ引き上げられました。
学費を自分でまかなう学生や、仕送りに頼らず生活している大学生にとっては朗報です。
この改正により、年収が130万円前後の学生でも、控除を活用することで税負担を大幅に軽減できます。
家族の年収ラインを再確認することが大切
2025年からは、扶養・配偶者控除・勤労学生控除の基準がすべて変わります。
したがって、「去年と同じ働き方だから大丈夫」という判断は危険です。
次のチェックを必ず行いましょう。
- 配偶者や子どもの年収見込みが123万円以下か確認
- 学生のアルバイト収入が130万円を超えないように調整
- 控除を受けるための申告書に正しい金額を記入
ポイントまとめ
- 扶養控除・配偶者控除の所得要件が 48万円 → 58万円 に緩和
- 配偶者特別控除の対象年収が 150万円超〜201万円まで拡大
- 勤労学生控除の上限も 85万円 にアップ
- これまで扶養外だった人が再び対象になる可能性
- 家族の収入見込みを早めに把握し、申告書記入を正確に
特定親族特別控除の新設(変更点3)
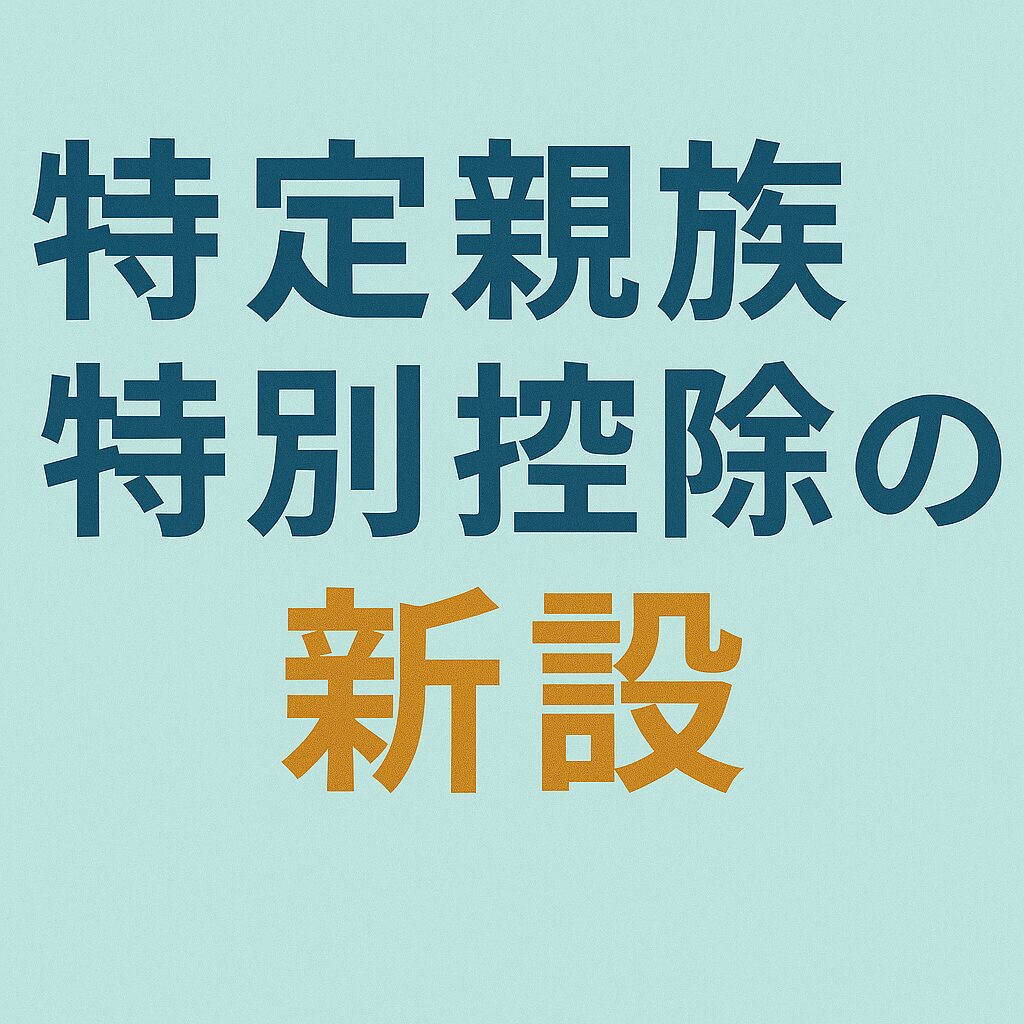
2025年の年末調整で新たに導入されたのが、「特定親族特別控除」です。
この制度は、大学生や専門学生など、19〜23歳の子どもがアルバイト収入を得ている家庭を中心に税負担を軽減する目的で新設されました。
これまで「103万円を超えると扶養から外れる」とされていた学生にも、一定の控除が適用されるようになります。
特定親族特別控除とは?
「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の親族(子どもなど)が一定の所得範囲内で働いている場合に、親が受けられる新しい控除制度です。
従来の仕組みでは、学生アルバイトの所得が103万円を超えると扶養控除の対象外となり、家庭全体で税負担が増加していました。
2025年からは、所得が一定額を超えても段階的に控除が減少する仕組みを採用することで、急激な負担増を防ぐようになっています。
適用対象の条件
| 区分 | 要件内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 19歳以上23歳未満(大学生・専門学生など) |
| 所得要件 | 合計所得58万円超〜123万円以下(給与収入換算:約123万円〜188万円以下) |
| 同居要件 | 原則として生計を一にしている(仕送り等含む) |
| 控除額 | 所得に応じて段階的に減少(最大38万円) |
たとえば、子どものアルバイト収入が年収150万円の場合でも、所得が123万円以下であれば親が一定の控除を受けられます。
このため、大学生の子どもが長期インターンや複数アルバイトをしても、すぐに扶養から外れることはなくなるのです。
控除額のイメージ(段階制)
| 子どもの給与収入 | 親が受けられる控除額 |
|---|---|
| 〜123万円 | 38万円(満額) |
| 130万円 | 約30万円 |
| 150万円 | 約20万円 |
| 180万円 | 約10万円 |
| 188万円以上 | 控除なし |
このように、所得が増えるにつれて控除額が徐々に減っていく「グラデーション型」の制度です。
従来のように「1円でも超えたら一気に扶養外」ではなく、段階的な減額方式になったことが大きな特徴です。
申請に必要な書類と手続き
新制度の控除を受けるには、以下の書類を提出する必要があります。
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書(新様式)
- 扶養控除等(異動)申告書
- 子どもの収入を証明できる書類(給与明細や源泉徴収票など)
これらの書類は、例年通り11月〜12月の年末調整時に会社へ提出します。
記入漏れや誤記があると控除が適用されないため、子どもの収入見込みを早めに確認しておくことが重要です。
家族にとってのメリット
この新控除制度によって、次のようなメリットが期待できます。
- 大学生のアルバイト収入が増えても、親が扶養控除を受けられる
- 家計全体で実質的な可処分所得が増える
- 子どもの就業機会を妨げず、社会経験を積みやすくなる
特に「子どもに働かせすぎると損をする」という構造が緩和されたことで、
親子どちらにもプラスの影響がある制度改正です。
注意点と確認事項
- 子どもが複数の勤務先で働いている場合は合算で所得を計算する必要あり
- 所得の見込みを低く申告してしまうと、後で追徴課税になるリスクあり
- 控除額の詳細は国税庁の最新様式を必ず確認
ポイントまとめ
- 新設「特定親族特別控除」は19〜23歳の子どもが対象
- 所得58〜123万円(給与換算123〜188万円)の範囲で控除適用
- 控除額は最大38万円、段階的に減少
- 扶養外リスクを緩和し、家計負担を軽減
- 申告書の記入と収入確認は年末前に準備を
住宅ローン控除(残高証明書)の手続き変更
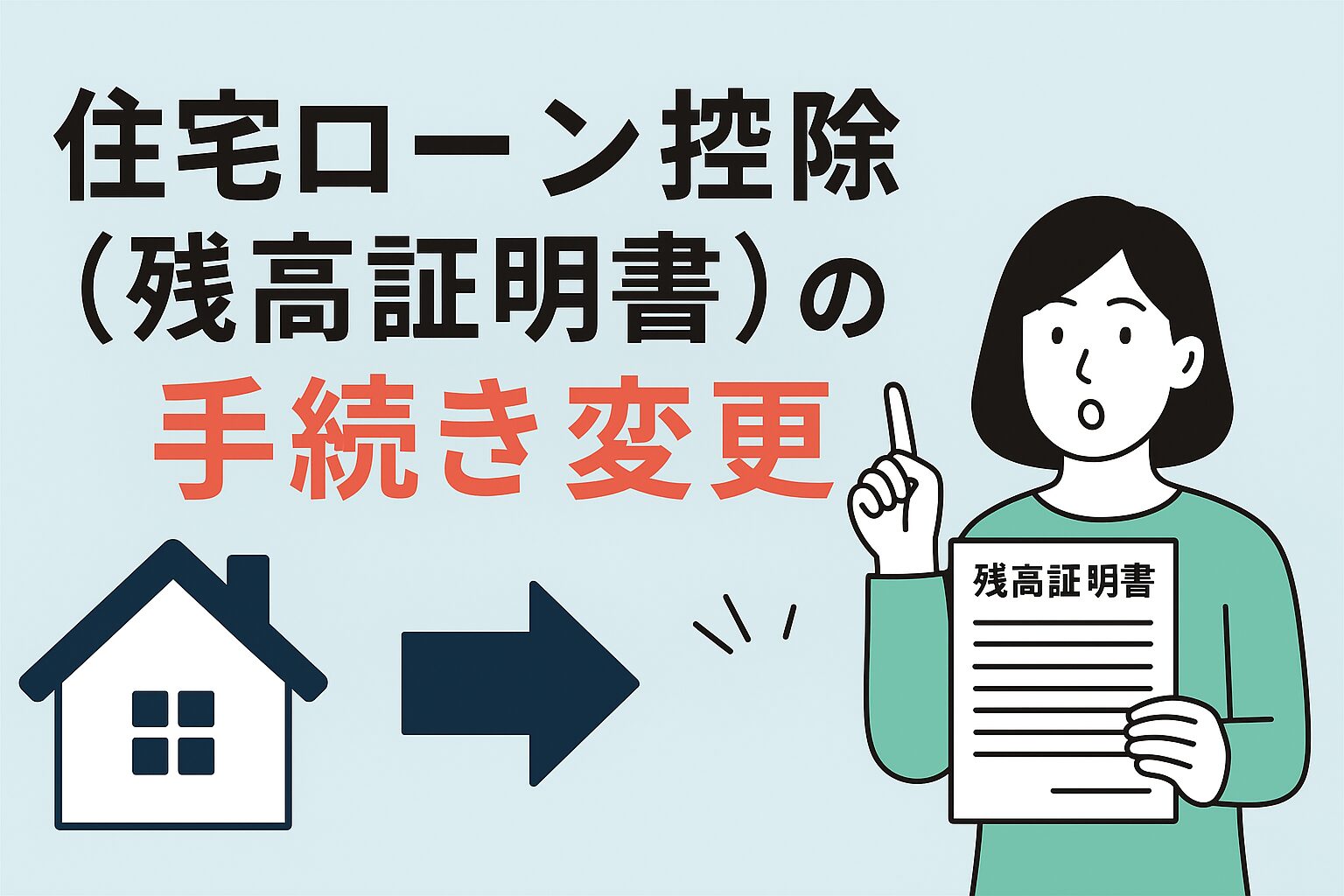
2025年の年末調整では、住宅ローン控除の手続きにも大きな変更が加えられました。
特に注目すべきは、「年末残高等証明書」の提出方法が電子化されたことです。
これにより、従来の紙書類を提出する手間が減り、銀行と税務当局の連携がスムーズになります。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、マイホーム購入時にローンを組んだ人が受けられる所得税の減税制度です。
年末時点での住宅ローン残高の一定割合(通常は1%)を、所得税額から控除できます。
対象となるのは、10年以上の住宅ローンを組み、自ら居住している人です。
電子化の新ルール「調書方式」とは?
これまで、住宅ローン控除を受けるには、金融機関から郵送される紙の「年末残高等証明書」を会社に提出する必要がありました。
しかし、2025年分の年末調整からは、次の2つの方法が選べます。
| 提出方式 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 従来方式 | 紙の「年末残高等証明書」を提出 | これまで通りの運用が可能 |
| 新方式(調書方式) | 銀行等が電子データを税務署へ直接連携 | 書類提出の手間が不要 |
電子方式を選択すると、銀行や住宅金融支援機構などが残高データを国税庁に自動送信し、
そのデータをもとに年末調整が行われます。
つまり、利用者は書類を印刷・提出する必要がなくなるのです。
新制度の利用条件
「調書方式」を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
- 2024年以降に住宅ローンを借り入れた人
- 借入先の金融機関が電子データ連携に対応していること
- 本人が金融機関へ電子交付の同意をしていること
もし、上記条件を満たさない場合は、従来どおり紙の残高証明書を提出すれば控除が適用されます。
手続きの流れ
- 金融機関から電子交付案内が届く(9〜10月頃)
- マイナポータルや金融機関サイトで同意手続き
- 会社へ控除申告書を提出(紙または電子)
- 年末調整で控除額が自動反映
この手続きにより、提出漏れや紛失のリスクが減り、処理スピードも向上します。
注意点:初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるのが初めての人は、初年度のみ確定申告が必要です。
2年目以降から年末調整で自動適用されるため、翌年以降は会社に控除申告書を提出するだけでOKです。
チェックリスト:年末前に確認しておくこと
- ☐ 金融機関が電子連携対応か確認した
- ☐ 電子交付の同意手続きを完了した
- ☐ 控除申告書の最新フォーマットを入手した
- ☐ 初年度の場合、確定申告の準備を済ませた
ポイントまとめ
- 住宅ローン控除の「残高証明書提出」が電子化対応に
- 2025年から「調書方式」と「従来方式」の選択が可能
- 電子連携なら提出不要、ミスや紛失のリスク軽減
- 初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で自動適用
必要な書類と提出時期

2025年の年末調整では、新しい申告書式が導入され、提出が必要な書類の種類も増えています。
これまで「毎年同じ書類で大丈夫」と思っていた方は要注意。
2025年分からは「特定親族特別控除」や「基礎控除」など、新しい控除項目を反映した申告書を必ず使用する必要があります。
提出が必要な主な書類一覧
| 書類名 | 内容 | 提出が必要な人 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養家族の有無・変更を申告 | すべての給与所得者 |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者の所得や控除の有無を記入 | 配偶者がいる人 |
| 基礎控除申告書 | 自身の所得額に応じて控除を適用 | 全員(新様式に対応) |
| 特定親族特別控除申告書 | 19〜23歳の学生などが対象 | 該当家族がいる人 |
| 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 | 生命保険・地震保険料などの控除を申告 | 保険加入者全員 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除を申請する人 | 該当者のみ(2年目以降) |
提出期限の目安
提出時期は企業によって多少前後しますが、以下が一般的なスケジュールです。
| 手続き内容 | 時期 | 担当 |
|---|---|---|
| 会社が申告書を配布 | 10月下旬〜11月初旬 | 経理・人事 |
| 従業員が記入・提出 | 11月中旬まで | 従業員本人 |
| 経理担当が内容を確認・集計 | 11月下旬〜12月初旬 | 会社側 |
| 年末調整の実施 | 12月の給与支給時 | 会社側 |
提出期限を過ぎると控除が反映されない可能性があるため、早めの準備が大切です。
とくに、家族構成や年収が変わった人は、申告内容を見直す必要があります。
記入時の注意点
- 前年のコピーを使い回さない(2025年は様式が変更)
- 扶養親族や配偶者の「合計所得金額」を正確に記入
- 学生やパート家族の所得を「見込み」で書かない
- 生命保険料などは「控除証明書」を必ず添付
チェックリスト:提出前に確認すべき5項目
- ☐ 最新の2025年用申告書を使用している
- ☐ 家族の所得状況を正確に記入している
- ☐ 控除証明書や残高証明書を添付済み
- ☐ 提出期限を確認した
- ☐ コピーを保管しておく
これらを1つでも漏らすと、控除が適用されず税金を余分に払うことになります。
忙しい時期こそ、書類提出は「早め・正確・確認済み」が鉄則です。
よくあるミスと対策
| ミスの例 | よくある原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 扶養人数を前年のまま記入 | 子どもの就職・結婚を反映していない | 最新の家族情報を更新する |
| 控除証明書を紛失 | 郵送物の管理不足 | 生命保険会社の再発行を早めに依頼 |
| 提出期限を過ぎる | スケジュール把握不足 | 会社の提出日をカレンダーに登録 |
| 所得の見積もりミス | パート・副業収入の把握不足 | 源泉徴収票・給与明細を事前確認 |
ポイントまとめ
- 2025年から申告書の様式が刷新され、新しい控除項目に対応
- 提出期限は12月の給与支給前が目安
- 家族構成や所得状況の変化を反映させる
- 書類不備や提出遅延は控除漏れの原因に
- 提出前に「控除証明書」「所得見積」「最新様式」の3点確認
2025年年末調整の具体的アクションプラン
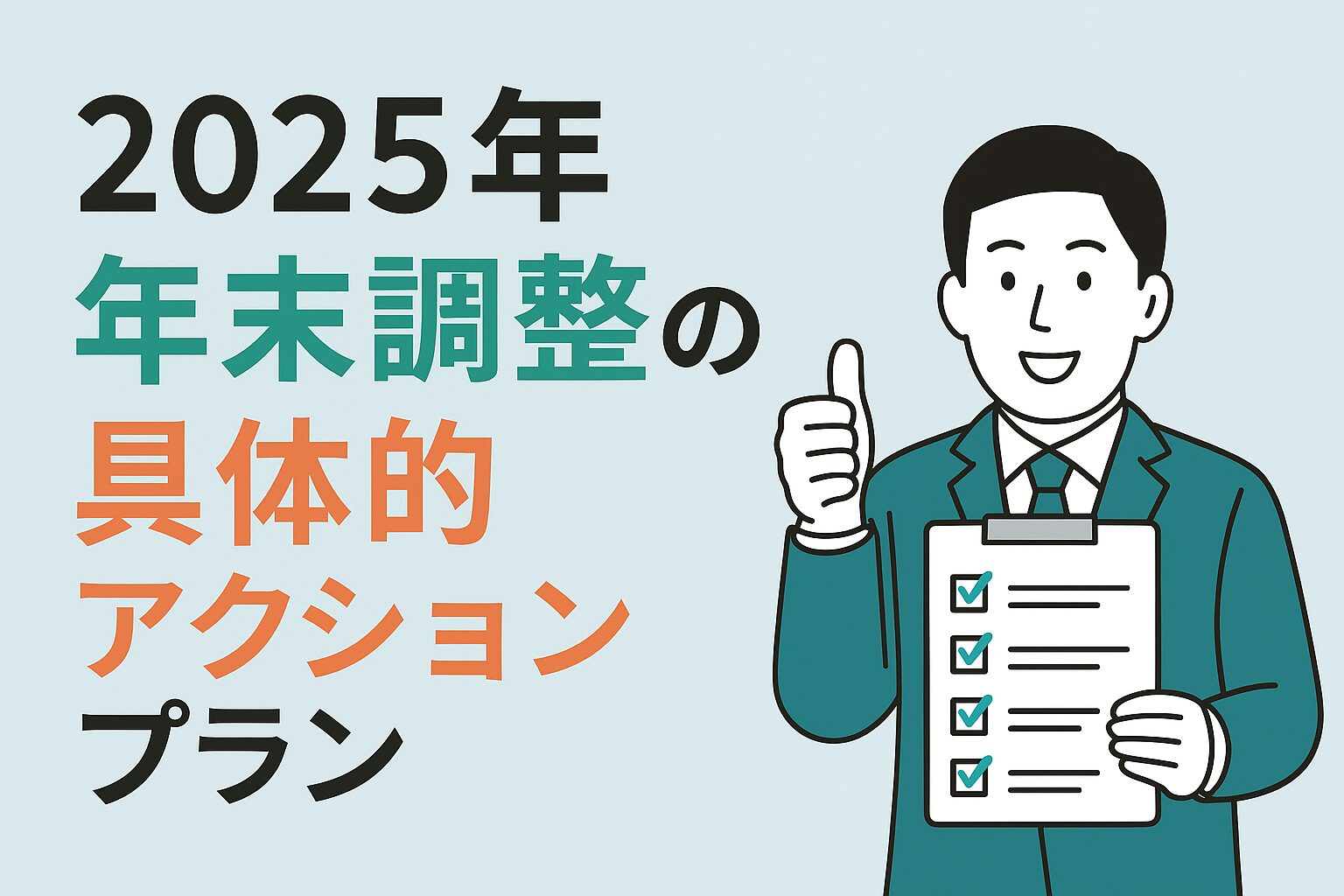
ここまでの内容を踏まえると、2025年の年末調整は「制度が変わったから知っておく」だけでは不十分です。
控除漏れや申告ミスを防ぐためには、今すぐに行動に移すことが何より大切です。
ここでは、会社員・主婦・給与担当者の立場別に、やるべきことを具体的なステップで整理します。
従業員・パート・主婦がやるべきこと
① 家族の所得を確認する
- 配偶者や子どもの収入が「123万円」「188万円」などの新基準に当てはまるか確認。
- アルバイト・副業収入は「源泉徴収票」または「給与明細」でチェック。
② 新しい申告書を正しく記入する
- 扶養控除等申告書・基礎控除申告書などは、2025年用の新様式を使用。
- 特定親族特別控除を使う場合は、専用の申告書に記入が必要。
③ 保険料・住宅ローンの証明書を早めに準備
- 郵送または電子発行される控除証明書を紛失しないよう管理。
- 生命保険会社・金融機関のマイページで電子データをダウンロード可能。
④ 年収の見込みを再確認
- 「去年と同じくらいだろう」で記入しない。
- パート・副業を増やした人は特に注意。所得が上限を超えると控除が減少する。
⑤ 提出期限を守る
- 会社から指定された提出日(多くは11月中旬)を厳守。
- 遅れると還付金が受け取れない可能性もある。
給与・人事担当者がやるべきこと
① 改正内容を全社員に周知
- 「基礎控除95万円」「扶養要件58万円」「特定親族特別控除」などを簡潔に説明。
- 社内メールや掲示板で「変更点まとめ」を共有。
② 最新申告書を配布・回収
- 国税庁公表の2025年様式をダウンロードして配布。
- 提出期限と提出場所を明確に伝える。
③ 記入内容の確認と入力チェック
- 収入・所得の記載漏れ、書類の添付漏れを防ぐためのチェックリストを導入。
- 電子提出の場合はデータ破損・未送信の確認も行う。
④ スケジュール管理
- 社内システム(給与計算ソフト等)で提出・確認・還付の流れをカレンダー化。
- 11月下旬には最終チェックを完了しておくのが理想。
よくあるトラブルと防止策
| トラブル内容 | 防止策 |
|---|---|
| 家族の年収を誤記し、扶養から外れてしまった | 前年実績と今年の見込みを必ず確認 |
| 控除証明書を提出し忘れて減税が適用されなかった | 提出前に「添付書類チェックリスト」で確認 |
| 提出期限を過ぎて還付が翌年になった | 提出日をカレンダーアプリに登録 |
| 電子申告でデータが未送信だった | 送信後に「受付完了メール」を必ず確認 |
行動リストで控除漏れをゼロにする
- ☐ 家族の収入を正確に把握した
- ☐ 2025年用の最新様式を使用した
- ☐ 控除証明書をすべて添付した
- ☐ 提出期限を確認してスケジュール化した
- ☐ 記入内容を第三者(家族や担当者)に確認してもらった
この5項目をチェックしておくだけで、控除漏れや記入ミスのほとんどは防げます。
ポイントまとめ
- 2025年は「提出書類の変更」と「控除要件の緩和」が同時に実施される年
- 早めの準備と情報共有がトラブル防止のカギ
- 家族の所得・控除証明書・提出期限の3点を徹底チェック
- 書類提出は“11月中旬まで”がベストタイミング
まとめ・Q&A形式の要点整理
2025年の年末調整は、基礎控除・扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除など、主要な制度が同時に改正される“大改正の年”です。
ここでは、本記事の重要ポイントを整理し、よくある質問にQ&A形式で答えます。
この記事を読めば、控除漏れを防ぎ、正しい手続きで還付を受けられるようになります。
2025年の主な変更点まとめ
| 項目 | 改正内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 → 最大95万円へ引き上げ | すべての給与所得者が対象 |
| 給与所得控除 | 最低65万円に引き上げ | 非課税範囲が160万円に拡大 |
| 扶養控除 | 所得要件48万円 → 58万円へ | 年収123万円まで扶養可能に |
| 配偶者控除 | 所得要件48万円 → 58万円へ | 共働きでも控除適用しやすく |
| 特定親族特別控除 | 新設(19〜23歳学生など) | 所得58〜123万円に段階的控除 |
| 住宅ローン控除 | 電子データ連携(調書方式)導入 | 書類提出が簡略化 |
| 申告書類 | 新様式に変更 | 特定親族控除など新設項目あり |
Q&Aでよくある疑問を解消
Q1. 2025年の「年収の壁」はどう変わったの?
A. 従来の「103万円の壁」が、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより実質160万円の壁に変わりました。
パートやアルバイトでも年収160万円までは所得税がかからず、扶養内で働きやすくなります。
Q2. 配偶者の年収が150万円を超えたら控除は受けられない?
A. 2025年からは「配偶者特別控除」が拡大され、年収201万円まで段階的に控除を受けられます。
共働きでも扶養控除を活用できるケースが増えました。
Q3. 大学生の子どもがアルバイトしていても扶養に入れる?
A. 新設の「特定親族特別控除」により、子どもの年収が188万円未満なら段階的に扶養扱いが可能です。
収入が増えてもすぐに控除がゼロになることはありません。
Q4. 住宅ローン控除の手続きが変わったと聞いたけど?
A. 2025年から「電子調書方式」が導入され、銀行が国税庁にデータを直接送信できるようになりました。
これにより、紙の「年末残高証明書」を提出しなくても控除が反映されます。
Q5. 年末調整の提出書類はいつまでに出せばいい?
A. 一般的には11月中旬〜12月上旬が目安です。
遅れると還付金が反映されないことがあるため、会社の提出期限を必ず確認してください。
Q6. 年末調整を忘れたらどうなる?
A. 年末調整で控除を受け損ねた場合でも、翌年の確定申告で還付申請が可能です。
ただし、5年以内に申告しないと還付は受けられません。
最後に:2025年は“準備した人”が得をする年
税制改正は複雑ですが、正しく理解して手続きすれば確実に得をします。
特に今年は、提出書類・控除額・扶養要件の3点が同時に変更されるため、例年以上に確認が重要です。
- 新様式の申告書を使用する
- 家族の所得を早めに確認する
- 控除証明書を忘れず添付する
この3つを守るだけで、控除漏れ・還付漏れを防げます。
忙しい年末こそ、今のうちに準備しておきましょう。
✅ まとめポイント
- 2025年の年末調整は「160万円の壁」「特定親族控除」「電子化」がキーワード
- 家計の手取りが増える可能性が高い
- ただし提出漏れや書類ミスは致命的
- 準備と確認を早めに行うことで、確実に控除を受けられる
これで「2025年 年末調整 変更点」完全ガイドは完結です。
もし自分にどの控除が当てはまるか迷った場合は、勤務先の人事担当者または税務署・市区町村窓口に早めに相談しておきましょう。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。