はじめに|今インスタの運用で知っておくべき重要な変化とは?

2025年4月、InstagramのCEOアダム・モセリ氏が発信した公式動画により、2025年に向けたInstagram運用の大方針が明らかになりました。
SNS運用をしている方の多くが一度は感じたことがある「リーチが伸びない」「投稿が埋もれる」「アルゴリズムに嫌われてる気がする」という悩み。
実はこれ、単なる“シャドウバン”疑惑ではなく、Instagramの仕組みや考え方を知らずに使っていることが原因かもしれません。
今回の発表で特に注目すべきは以下の3点です。
- オリジナルコンテンツが強く評価されるようになる
- 小規模クリエイターの発信を優遇する方向にシフト
- バズの再現性を高める仕組みをインスタが後押しする
本記事では、これらの変更点や裏にある意図をわかりやすく整理しながら、これからのインスタ運用で「何を意識すれば伸びるのか」を具体的に解説していきます。
さらに、「シャドウバンって本当にあるの?」「投稿を再開したらリーチは戻るのか?」といったよくある疑問や、TikTokとの違いを踏まえた戦略もお伝えします。
インスタの運用で「成果が出ない」と感じている方にとって、本記事が明確な指針となるよう、最新アルゴリズムの本質を深掘りしていきます。
まずはこちらをご覧ください👇
インスタの2025年運用方針は「オリジナル重視」と「小規模支援」

InstagramのCEOであるアダム・モセリ氏は、2025年に向けた運用方針として、3つの大きな優先事項を発表しました。
これからインスタを活用してフォロワーを増やしたい人、ビジネスに活用したい人にとって、これらの方針を理解することは極めて重要です。
1. 小規模クリエイターの活躍を後押しする
インスタはこれまで、フォロワーが多いアカウントやインフルエンサーが圧倒的に有利な構造でした。
しかし2025年からは、新規や小規模クリエイターにも光が当たりやすい設計に変えていく方針が示されています。
立ち上げ初期のアカウントでも、「必要としている人にコンテンツが届く」アルゴリズムに進化させようという意図があり、これによりフォロワー数が少ない状態でもバズを狙える可能性が広がります。
2. オリジナルコンテンツを明確に評価
これまでのInstagramでは、他人の投稿をリポストする「再投稿アカウント」が増加していましたが、モセリ氏はこれを問題視しています。
今後は、「誰が最初に作ったか」を判定し、そのオリジナル投稿者を優先して表示する仕組みが強化されます。
つまり、引用・転載・切り抜きなどの二次投稿ではなく、自分自身で作成した投稿を重視するという明確な方針転換です。
これにより、一次クリエイターがきちんと評価され、モチベーションを維持しやすい環境になることが期待されます。
3. トレンド・バズの加速を目指す
インスタは、TikTokのように自然発生的なトレンドや「ミーム文化」が広まりにくいとされてきました。
そこで、プラットフォーム自体がバズを加速させるようなアルゴリズム改修を検討しているとのことです。
これは、インスタ発のトレンドが他SNSへ波及することを目指しており、クリエイターにとっては「チャンスが広がる」変化だと言えます。
これら3つの方針は、表面的には「使いやすくなる」だけに見えますが、裏側にはコンテンツの質を重視し、ユーザー体験を向上させる狙いがあります。
今後インスタで伸びていくには、自分の投稿が“オリジナル”であり“価値ある情報”かどうかを見直すことが求められます。
アルゴリズムの変更点を具体的に押さえておこう
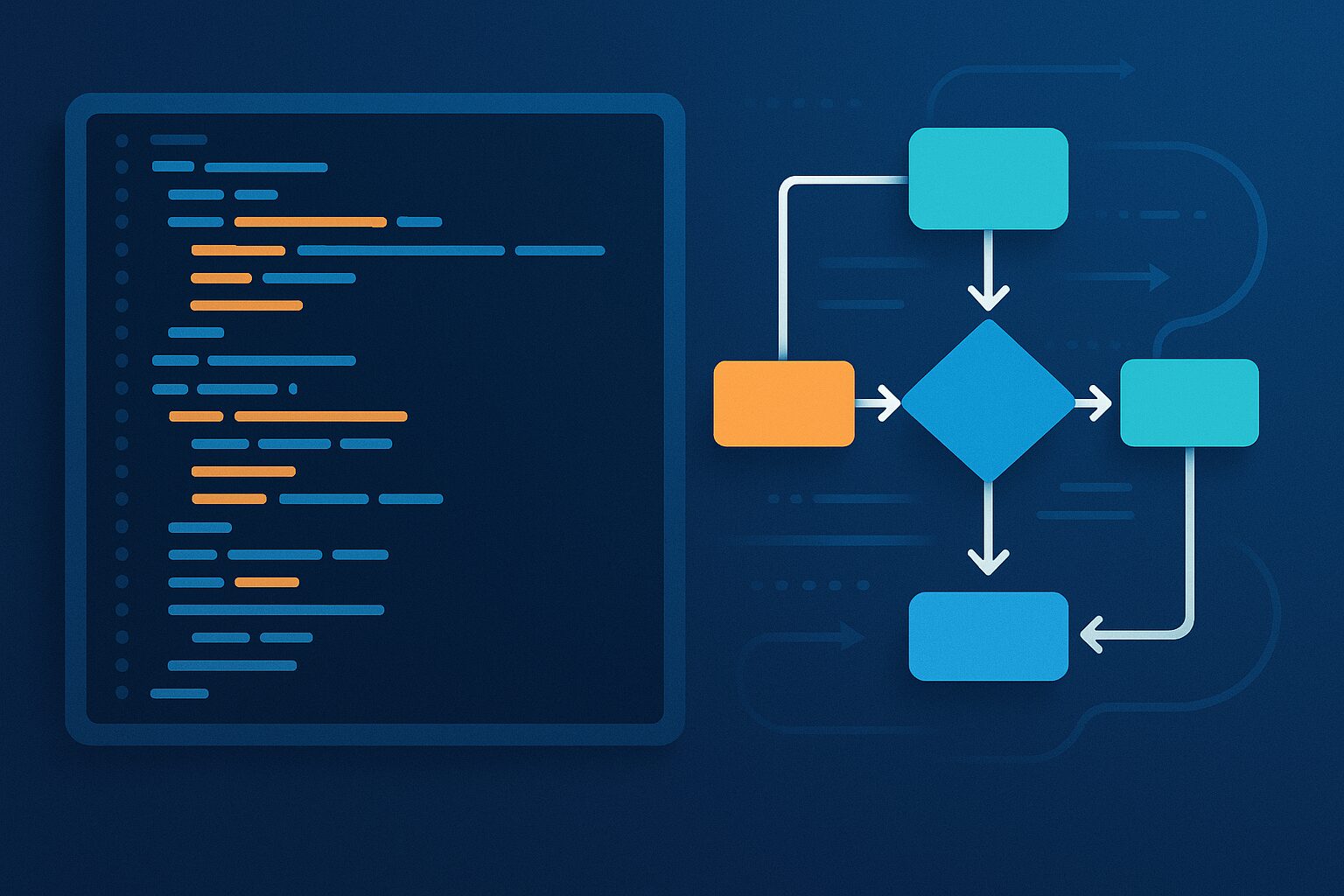
Instagramのアルゴリズムは年々進化していますが、2025年に向けてはより“質重視”かつ“ユーザー体験中心”の設計へと舵を切っています。
ここでは、インスタ運用者が知っておくべき具体的なアルゴリズムの変更点を3つの柱で解説します。
1. 視聴時間と滞在時間が最重要指標に
動画コンテンツ、特にリールにおいては、「どれだけ長く視聴されたか」が強く評価される傾向にあります。
単に再生されるだけではなく、最後まで見られたか、視聴維持率が高いかが鍵です。
また、投稿単体だけでなく、プロフィールページや投稿一覧への滞在時間も重要視されるようになっており、“アカウント全体での魅力”が問われる時代になっています。
2. シェア数が投稿評価に直結
モセリ氏が一貫して強調しているのが「シェアの重要性」です。
ストーリーズやDMで多くシェアされる投稿は、アルゴリズム上でも高評価を得やすく、発見タブやリールタブに載りやすくなる傾向があります。
特にDMでのシェアは、親密度の高いユーザー間で共有されるため、エンゲージメントの質が高いと判断されやすく、これが表示拡大に直結します。
3. リポストやコピー投稿は評価されにくくなる
先述の通り、オリジナル投稿が評価され、リポストは不利になる方向性が強まっています。
特に、他人のコンテンツを再投稿しただけのアカウントは、今後さらにリーチが伸びにくくなる可能性が高いです。
Instagramは「誰が最初に作ったか」という視点でコンテンツを判断するため、他人のアイデアに便乗する運用スタイルでは限界があると認識すべきです。
このように、Instagramは「ただ投稿する」だけでは評価されない時代に突入しています。
“ユーザーが興味を持ち、他人に共有したくなる”投稿を意識して作ることが、これからの伸びる鍵になります。
シャドウバンの真実|インスタのアカウント評価はこうして決まる

「インスタで突然リーチが激減した」「投稿しても全く伸びない」「もしかしてシャドウバンされた?」——こうした声はSNS運用者からよく聞かれます。
しかし、本当に“シャドウバン”は存在するのでしょうか?
実は、Instagramの公式見解としては、「シャドウバン」という明確な機能は存在しないとしています。
代わりに、コンテンツのリーチが制限される“状態”は、いくつかの原因によって発生していると説明されています。
アカウントステータス機能でチェック可能
インスタでは「アカウントステータス」から、自分のアカウントがおすすめ表示制限を受けていないかを確認できます。
そこに問題が表示されていなければ、裏でこっそり制限されているということは基本的にないと考えられます。
✔ アカウントステータスの確認方法:
- プロフィール右上メニュー→「設定とアカウント」→「アカウントステータス」
リーチが落ちる“本当の原因”
リーチが激減する最大の理由は、コンテンツそのものが魅力を失っていることです。
例えば以下のような要因が考えられます。
- 保存・シェア・コメントといったエンゲージメントの減少
- 投稿ジャンルがフォロワーの興味とズレている
- 似たような投稿ばかりで“飽きられている”
アルゴリズムは、ユーザーの反応を基に表示範囲を決定しているため、エンゲージメントの低下=リーチの低下に直結します。
長期間の未投稿はアルゴリズムに影響する
数ヶ月投稿を休んでいたアカウントが、久しぶりに投稿してもなかなかリーチが伸びないという声もよく聞きます。
これは、インスタの仕組み上、新しい投稿が“古いデータ”を元に評価されてしまうため、リーチが不安定になることがあるとされています。
ただし、再開後に継続的に投稿し続ければ、アルゴリズムも新しい行動を学習し、徐々にリーチは回復していきます。
完全に死んだアカウントではないので、焦らず続けることが重要です。
「シャドウバンされたかも」と感じた時こそ、自分のアカウントの状態を客観的に分析するチャンスです。
アルゴリズムの責任にする前に、まずは“ユーザーにとって魅力的な投稿か”を見直してみましょう。
バズるには?Instagramでリーチを伸ばすコンテンツの特徴

Instagramで「バズる」投稿を作るには、単におしゃれな写真や動画を投稿するだけでは足りません。
現在のインスタのアルゴリズムに“好かれる”投稿とは、視聴者の反応を最大化できる構成であることが大前提です。
ここでは、実際にリーチを伸ばしている投稿の共通点をいくつかご紹介します。
シェアされやすい内容が優遇される
インスタの公式見解でも明言されている通り、「シェアされること」が最も重要な評価指標のひとつです。
特にDM(ダイレクトメッセージ)で友人に送られる投稿は、エンゲージメントの質が高いと判断され、発見タブやリールタブに載る可能性が大幅に上がります。
✔ シェアされやすい投稿の例:
- 共感系(あるあるネタ、失敗談、ライフハック)
- 役立ち情報(チェックリスト、How to系)
- おすすめ系(グルメ、美容、旅行スポット)
保存率の高い投稿はロングヒットになりやすい
ユーザーが「あとで見返したい」と思って保存した投稿は、アルゴリズム上でも高評価されやすく、長期間にわたって表示される傾向があります。
✔ 保存を狙うなら:
- 1投稿完結型の情報系投稿(例:◯◯の3ステップ)
- 美容・ファッションの「アイテムまとめ」や「コーデ一覧」
- 実用性の高い「テンプレート」や「チェックリスト」
視聴完了率・離脱率を意識した動画構成を
特にリール動画においては、「動画が最後まで視聴されるかどうか」が大きな評価ポイントです。
長すぎる動画や、最初の数秒でユーザーの興味を惹けないものは、すぐスワイプされてしまい、視聴完了率が下がって評価が落ちます。
✔ バズるリール動画の構成ポイント:
- 冒頭3秒で“引き”を作る(テキスト+音)
- 結論から話し始める
- 適切な長さ(15〜30秒前後)
ハッシュタグは今でも効果があるが、頼りすぎない
かつてはハッシュタグを大量に付けることでリーチを稼げる時代もありましたが、現在はあくまで“補助的”な要素です。
適切なタグを3〜5個選ぶ程度が最適とされています。
✔ ポイント:
- 関連性の高いタグだけを選定する
- 汎用タグよりもジャンル特化タグが◎(例:#カフェ巡り東京)
Instagramでリーチを伸ばすには、「視聴者が反応しやすい仕掛けを意図的に設計する」ことが不可欠です。
コンテンツの質を高め、ユーザーの行動を促すことが“バズ”への近道となります。
TikTokとの違いを理解してインスタを使い分けよう

「インスタとTikTok、どっちがバズるの?」「両方に同じ動画を投稿しても反応が違う」——そんな経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、この2つのSNSには明確な目的の違いとユーザーの心理的特性の差があります。
それを理解しないまま同じ戦略で運用すると、思うような成果が出ない可能性が高くなります。
インスタは“目的型”、TikTokは“偶発型”
Instagramは、「◯◯について知りたい」「お気に入りのアカウントをチェックしたい」といった“目的を持って使うプラットフォーム”です。
一方でTikTokは、アプリを開いた瞬間から興味関心を引く動画が次々と流れる“偶発的な出会い”のSNSです。
✔ 使い分けのイメージ:
- インスタ:興味の深掘り、信頼関係の構築、ファン化
- TikTok:拡散力、爆発的なバズ、初見のインパクト
コミュニティ性はインスタが圧倒的に強い
インスタでは、ストーリーズやDM、親しい友達機能など、“深い繋がり”を築くための仕組みが整っています。
インフルエンサーやビジネスアカウントにとっては、フォロワーとの距離感が近く、濃いコミュニケーションが可能です。
一方、TikTokは基本的に「見る側」「見られる側」が明確に分かれており、コメント以外の双方向コミュニケーションはあまり重視されていません。
アルゴリズムとリーチの設計思想も違う
TikTokでは、「今伸びているコンテンツ」をどんどんレコメンドするトレンド重視型のアルゴリズムですが、インスタでは「その人に合ったコンテンツ」を表示するパーソナライズ型の設計です。
このため、インスタではいきなり爆伸びするよりも、安定した成長とファンの蓄積を重視する方が成功しやすい傾向があります。
どちらかではなく“目的で使い分ける”のが正解
- 新規ユーザーへの露出・拡散を狙うならTikTok
- コミュニティを育ててビジネスに繋げたいならインスタ
というように、自分の発信目的とユーザーの使い方を踏まえて両者を適切に使い分けることで、より効果的なSNS運用が可能になります。
2025年以降の新機能と注目すべきポイント
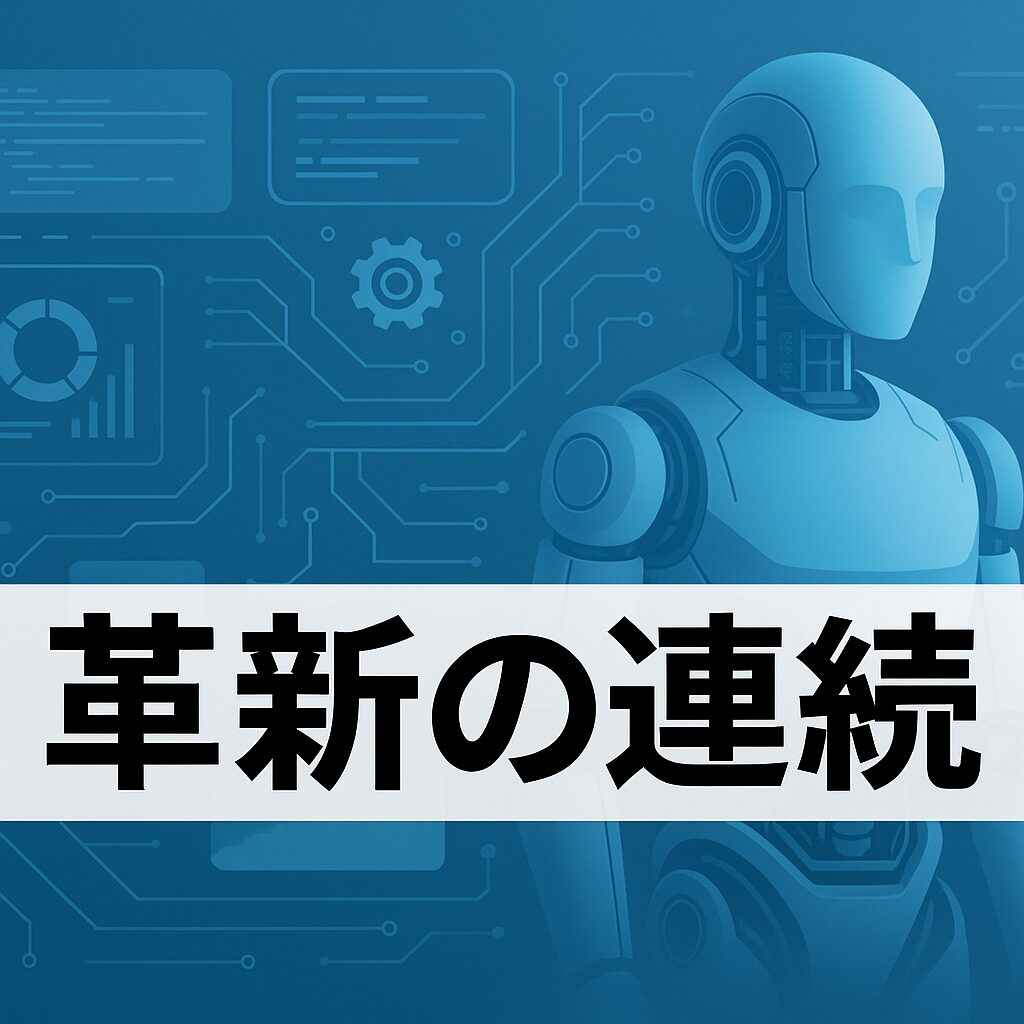
2025年に向けて、Instagramはアルゴリズムの変更だけでなく、新たな機能の実装と既存機能の強化にも力を入れています。
これからインスタを活用するクリエイター・ビジネスユーザーにとって、どの機能がチャンスになるのかを把握しておくことは極めて重要です。
ここでは、特に注目すべき機能をピックアップして紹介します。
パートナー広告機能の実装
最も注目されているのが「パートナー広告」の実装です。
これは、他人のオリジナル投稿を広告として活用できるようにする機能です。
たとえば、インフルエンサーが投稿した商品紹介動画を、その商品を扱う企業が「そのまま広告として出稿できる」という仕組み。
オーガニック投稿で成果が出たクリエイターのコンテンツが広告として“二次利用”されることにより、双方にメリットが生まれるモデルです。
✔ ポイント
- 企業はすでに「成果が出ている」投稿を使える
- クリエイターは自分の投稿が広告として採用され、報酬が得られる
- 質の高いコンテンツを作れば「買われる」時代へ
この機能は、YouTubeのスパンサード投稿やTikTokの広告連携に対抗する重要な武器になる可能性があります。
「ブレンズ」機能によるグループ視聴と共有強化
ブレンズ(Briends)という新機能も実装予定です。
これはDMスレッドの中で、特定の友人グループとリールなどのコンテンツを一緒に見ることができるというもの。
✔ ユーザーへの影響
- コンテンツの「リアルタイム共有」がより自然に行える
- コミュニティ内でのバズを後押しする導線になる
特に若年層ユーザーや友人同士でコンテンツを楽しむユーザーにとっては、新たなエンゲージメントの形となる可能性があります。
Instagram内部検索の強化
過去から構想されていた「ハッシュタグに頼らない検索体験」が、ようやく実装に向けて進展しています。
具体的には以下のような方向性が示されています。
- コンテンツ単体(画像や動画)に対するキーワード検索の対応
- コメント欄やキャプション、音声解析を組み合わせた検索制度の向上
- 外部検索(Googleなど)からの流入強化も視野に
検索機能が強化されれば、“タグを駆使しないと伸びない”という課題をクリアでき、質の高い投稿が自然に見つかる環境が整うと期待されています。
これらの機能はすべて、「オリジナルコンテンツを評価する」「コミュニティとしてのインスタを育てる」というInstagramの新しい戦略に直結しています。
今後は、「いい投稿を作って終わり」ではなく、「どう届け、どう繋がるか」までを設計することが必須となるでしょう。
まとめ|インスタを「伸ばす」には思想と仕組みの理解がカギ

Instagramの2025年運用方針は、表面的には「小規模クリエイター支援」や「オリジナルコンテンツ重視」といった優しい姿勢に見えますが、その背景には明確な思想と戦略があります。
それは、「ユーザー体験を最優先にする」という軸です。
この思想を理解したうえで、アルゴリズムや新機能を正しく活用することが、インスタで伸びるための最大の近道となります。
これまでの記事で解説してきたように、2025年のInstagramでは以下の点が非常に重要になります。
- オリジナルコンテンツの継続的な発信
- シェアされることを意識した設計(特にDMシェア)
- 一貫性あるジャンルとフォロワーとの距離感の近さ
- バズに頼らず、視聴時間・保存数などで着実に評価される投稿
- パートナー広告など、ビジネス化を視野に入れた戦略的活用
「なぜ伸びないのか」をアルゴリズムのせいにするのではなく、“届ける相手に価値を提供できているか”を問い直すことこそが、インスタ運用の本質です。
また、InstagramとTikTokは似て非なるプラットフォームです。
双方の特性を理解し、自分の発信スタイルに合った使い分けをすることで、SNS全体の成果を最大化することも可能です。
最後にもう一度強調したいのは、仕組みを理解し、目的を持った発信を継続することこそが、最大のSEOであり、バズの土台であるということです。
自分自身の「らしさ」と「届けたい相手」を明確にし、Instagramというツールを使いこなすことで、あなたの発信は確実に次のステージへと進化していくはずです。
他にもインスタの変化が気になる方はこちらもご覧ください👇
ただ・・・
まだまだSNSで収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。
じゅんの公式LINEでは、
- インスタアフィで稼ぐロードマップ
- 収益化に向けた詳しいノウハウ
- 各種テンプレート
などを中心に、
今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・
最高じゃありませんか…?
まずは僕の公式LINEを追加していただき、
ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
\無料!登録10秒/
公式LINEに登録するだけで
インスタ初心者でも月6桁目指せる
豪華17大特典配布中🎁
登録解除は、24時間いつでも出来ます