1. 年金はいつ受け取るべき?年齢別受給額とお得な受給開始年齢を徹底解説

年金の受給開始年齢を何歳にするかは、多くの人が悩む重要なポイントです。
一般的に65歳が基準とされていますが、60歳から繰り上げ受給することもできれば、70歳や75歳まで繰り下げ受給することも可能です。
しかし、受給開始年齢によって年金額が変わるため、どの選択が最もお得なのかを慎重に検討する必要があります。
ここでは、年金の繰り上げ・繰り下げ受給の仕組みを解説し、年齢別の受給額の違いについて詳しく説明します。
年金受給開始のタイミングに悩む人が多い理由
年金を受け取るタイミングを決める際に、多くの人が以下の点で迷います。
- 「早く受け取ると損をする?」という不安
- 60歳で受け取ると減額されるが、65歳まで待つと貯蓄を取り崩す必要がある。
- 「繰り下げれば本当に得なのか?」という疑問
- 70歳や75歳まで待つと年金額は増えるが、長生きしなければ損になるかもしれない。
- 「自分のライフプランに合った受給タイミングは?」という悩み
- 健康状態や生活費の状況によって、最適な受給開始年齢が変わる。
繰り上げ受給・繰り下げ受給の仕組みとは?
年金の受給開始年齢を変更することで、毎月もらえる年金額が増減します。
- 繰り上げ受給(60歳~64歳)
- 1ヶ月繰り上げるごとに0.4%減額(最大で24%減)
- 60歳から受給開始すると、本来の年金額の76%しか受け取れない。
- 繰り下げ受給(66歳~75歳)
- 1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額(最大で84%増)
- 75歳まで繰り下げると、本来の年金額の184%を受け取れる。
イメージがつきやすいようにこちらの表をご覧ください👇
このように、受給開始を遅らせるほど1回あたりの年金額は増えますが、総受給額ではどの年齢で得をするのかが重要なポイントになります。
2. 年齢別年金受給額 60歳・65歳・70歳・75歳でどれくらい違う?

年金の受給額は、受け取りを開始する年齢によって大きく変わります。
60歳からの繰り上げ受給では減額され、70歳以降の繰り下げ受給では増額されますが、具体的にどのくらい違いが出るのか気になるところです。
ここでは、年齢ごとの受給額の目安を紹介し、どの選択肢が有利なのかを考えていきます。
イメージがつきやすいようにまずはこちらの表をご覧ください👇
60歳~64歳の受給額とデメリット(繰り上げ受給)
60歳から年金を受け取る場合、基準額より24%減額されます。
例えば、65歳受給開始時の年金額が月10万円の場合、60歳で受け取ると次のようになります。
| 受給開始年齢 | 減額率 | 月額受給額 | 年間受給額 |
|---|---|---|---|
| 65歳(基準) | なし | 10万円 | 120万円 |
| 60歳 | ▲24% | 7万6,000円 | 91万2,000円 |
| 61歳 | ▲19.2% | 8万800円 | 96万9,600円 |
| 62歳 | ▲14.4% | 8万5,600円 | 102万7,200円 |
| 63歳 | ▲9.6% | 9万400円 | 108万4,800円 |
| 64歳 | ▲4.8% | 9万5,200円 | 114万2,400円 |
【メリット】
✅ 60歳から受け取れるため、働かなくても収入が確保できる
✅ 早く受け取ることで「年金がもらえないリスク」が減る
【デメリット】
❌ 毎月の年金額が大幅に減額される
❌ 一生減額されたままの金額しかもらえない
65歳~69歳の標準的な受給額(基準)
65歳で年金を受け取るのが基本であり、減額・増額なしの金額が支給されます。
- 例えば、65歳で月10万円なら、年間120万円を受け取れる。
- 65歳受給開始は、減額リスクがなく、安定した収入を確保しやすい。
【メリット】
✅ 一般的な年金支給開始年齢なので、最も標準的な選択肢
✅ 減額されることなく、安定した年金を受け取れる
【デメリット】
❌ 60歳から繰り上げれば早くもらえたはずの年金を受け取れない
❌ 繰り下げればもっと増額できる可能性がある
70歳~74歳の受給額(繰り下げ受給)
70歳まで繰り下げると、42%増額されるため、より多くの年金を受け取れます。
| 受給開始年齢 | 増額率 | 月額受給額 | 年間受給額 |
|---|---|---|---|
| 65歳(基準) | なし | 10万円 | 120万円 |
| 66歳 | +8.4% | 10万8,400円 | 130万800円 |
| 67歳 | +16.8% | 11万6,800円 | 140万1,600円 |
| 68歳 | +25.2% | 12万5,200円 | 150万2,400円 |
| 69歳 | +33.6% | 13万3,600円 | 160万3,200円 |
| 70歳 | +42% | 14万2,000円 | 170万4,000円 |
【メリット】
✅ 受給額が大幅に増えるため、長生きすれば得になる
✅ 老後資金の心配が減る
【デメリット】
❌ 70歳まで収入なしで生活できるだけの貯蓄が必要
❌ 70歳前に亡くなった場合、未受給分の年金が無駄になる
75歳以降の受給額と損益分岐点(繰り下げ最大84%増額)
75歳まで繰り下げると、年金額が最大で184%に増額されます。
| 受給開始年齢 | 増額率 | 月額受給額 | 年間受給額 |
|---|---|---|---|
| 70歳 | +42% | 14万2,000円 | 170万4,000円 |
| 71歳 | +50.4% | 15万400円 | 180万4,800円 |
| 72歳 | +58.8% | 15万8,800円 | 190万5,600円 |
| 73歳 | +67.2% | 16万7,200円 | 200万6,400円 |
| 74歳 | +75.6% | 17万5,600円 | 210万7,200円 |
| 75歳 | +84% | 18万4,000円 | 220万8,000円 |
【メリット】
✅ 受給額が最大84%増えるため、長生きするほど圧倒的に得
✅ 老後資金の柱として安心感が増す
【デメリット】
❌ 75歳まで無収入で生活できるだけの資産が必要
❌ 75歳前に亡くなった場合、長年払った保険料が無駄になる
年金受給額のシミュレーションまとめ
| 受給開始年齢 | 減額・増額率 | 月額受給額(基準10万円の場合) | 年間受給額 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | ▲24% | 7万6,000円 | 91万2,000円 |
| 65歳 | ±0% | 10万円 | 120万円 |
| 70歳 | +42% | 14万2,000円 | 170万4,000円 |
| 75歳 | +84% | 18万4,000円 | 220万8,000円 |
受給額の面では、繰り下げるほど増えますが、「どこまで生きればお得になるか(損益分岐点)」を計算することが重要です。
3. 繰り上げ受給と繰り下げ受給のメリット・デメリット
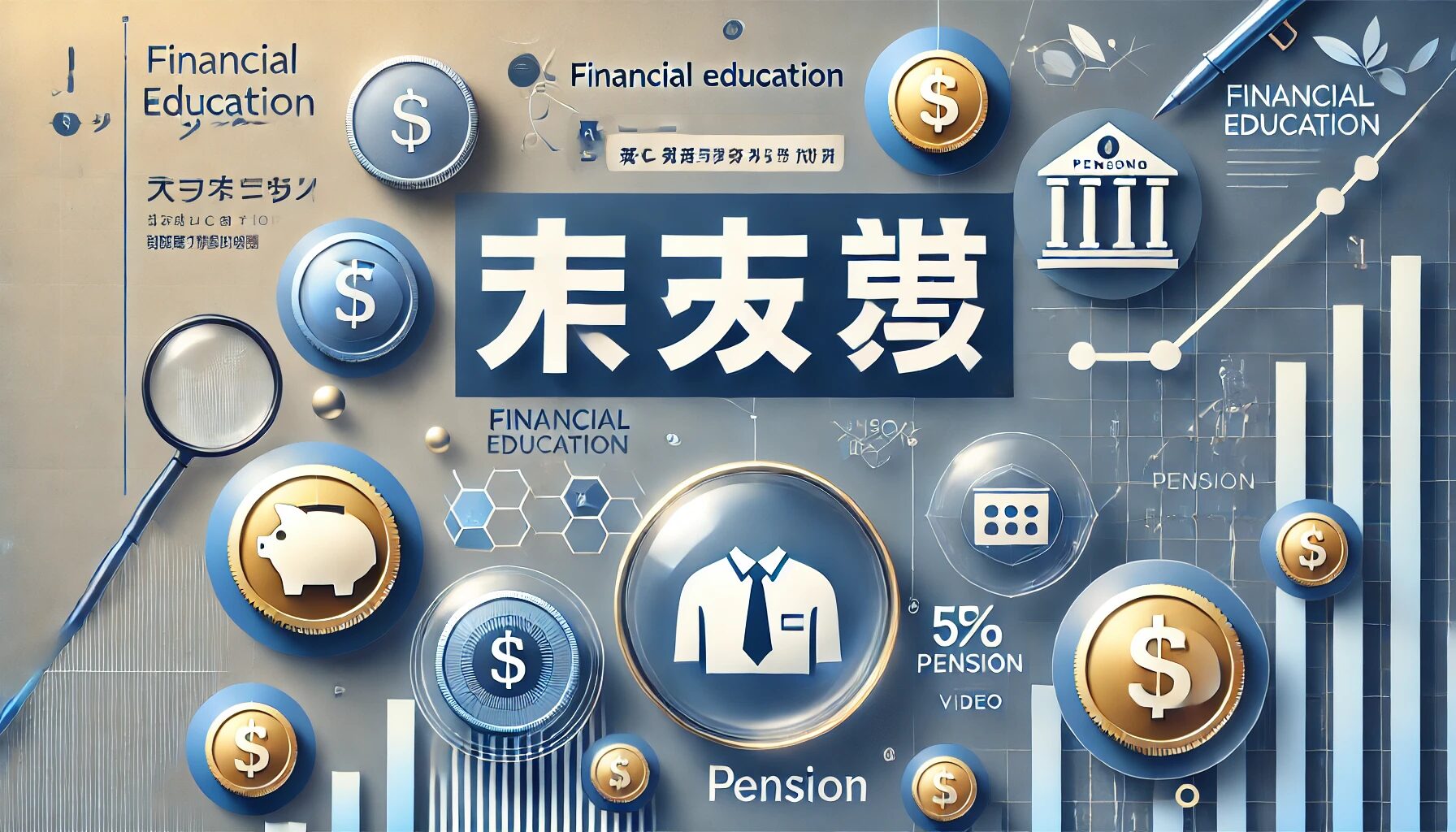
年金の受給開始年齢を変更すると、毎月の年金額が増減します。
60歳からの繰り上げ受給では減額され、70歳以降の繰り下げ受給では増額されますが、どちらが得なのかは個々のライフスタイルや寿命によって異なります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
繰り上げ受給(60歳~64歳)のメリット・デメリット
メリット
✅ 早く受け取れるので、無収入期間を短縮できる
- 60歳で退職した場合でも、すぐに年金収入を得られるため、貯蓄を取り崩す必要が少なくなる。
✅ 「長生きしないリスク」に対応できる
- 万が一、70代で亡くなった場合、繰り下げ受給を選ぶよりも総受給額が多くなる可能性がある。
✅ 働きながら受給することも可能
- 60歳以降も働く場合、年金と給与の両方を得られる。ただし「在職老齢年金制度」による減額に注意が必要。
デメリット
❌ 毎月の年金額が減る(最大24%減額)
- 一度減額されると、一生そのままの金額で固定される。
- 例えば、65歳開始で月10万円もらえるはずの人が、60歳から受け取ると月7万6,000円しかもらえない。
❌ 長生きすると、繰り下げ受給より総受給額が少なくなる
- 80歳以上生きると、繰り上げたことで生涯の受給総額が少なくなる可能性が高い。
❌ 働きながら受給すると減額の可能性がある
- 在職老齢年金制度により、給与が一定額を超えると年金が減額される。
繰り下げ受給(66歳~75歳)のメリット・デメリット
メリット
✅ 受給額が増える(最大84%増額)
- 1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額されるため、70歳なら42%増、75歳なら84%増となる。
- 例えば、65歳開始で月10万円もらえるはずの人が、75歳まで繰り下げると月18万4,000円に増える。
✅ 長生きすればするほどお得
- 80代、90代まで生きると、総受給額で繰り上げ受給者を大きく上回る。
✅ 受給額が多いため、将来的な生活費の不安が減る
- 高齢になり、医療費や介護費が増えても、年金額が多いため対応しやすい。
デメリット
❌ 75歳まで受け取らないと、一切年金がもらえない
- もし75歳前に亡くなった場合、受け取ることなく終わるリスクがある。
❌ 無収入期間を乗り切るだけの貯蓄が必要
- 65歳以降も年金を受け取らないため、それまでの生活資金を貯蓄や他の収入で補う必要がある。
❌ 「いつまで生きるか」という不確定要素がある
- 繰り下げ受給は「長生きすること」が前提となるため、健康状態によってはデメリットになる可能性がある。
繰り上げ・繰り下げ受給の比較表
| 受給方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 繰り上げ受給(60歳~64歳) | ・早く受け取れる(60歳から収入確保)・長生きしない場合、総受給額が多くなる可能性 | ・受給額が最大24%減少・長生きすると損になる・一生減額されたまま |
| 65歳受給(標準) | ・最も一般的な受給方法・減額なしで安定した収入を確保 | ・繰り上げより受給開始が遅い・繰り下げに比べると受給額が少ない |
| 繰り下げ受給(66歳~75歳) | ・最大84%増額(75歳受給時)・長生きするほど得になる | ・75歳まで受給なし・十分な貯蓄が必要・早く亡くなると損 |
どの選択肢がお得?損益分岐点を考える
繰り上げ・繰り下げ受給の損益分岐点を計算すると、81歳~83歳が目安になります。
- 81歳以前に亡くなる場合 → 繰り上げ受給のほうが総受給額が多くなる
- 82歳以上生きる場合 → 繰り下げ受給のほうが総受給額が多くなる
例えば、65歳受給開始のケース(年金月10万円の場合):
- 60歳繰り上げ(▲24%) → 7.6万円 × 21年間(60~80歳)= 約1,910万円
- 65歳受給(基準額) → 10万円 × 16年間(65~80歳)= 約1,920万円
- 70歳繰り下げ(+42%) → 14.2万円 × 11年間(70~80歳)= 約1,860万円
- 75歳繰り下げ(+84%) → 18.4万円 × 6年間(75~80歳)= 約1,324万円
このように、80歳までは繰り上げのほうが総受給額が多く、81歳以降は繰り下げのほうが有利になってきます。
まとめ:どちらを選ぶべき?
✅ 60歳~64歳の繰り上げ受給が向いている人
- 貯蓄が少なく、60歳からの生活費を確保したい
- 長生きする自信がない
- 早めに受け取って資産運用したい
✅ 65歳の標準受給が向いている人
- 減額・増額なしで安定した収入を得たい
- 健康状態や貯蓄のバランスを重視したい
✅ 70歳以降の繰り下げ受給が向いている人
- 長生きの可能性が高く、年金を最大限増やしたい
- 退職後も収入がある、もしくは十分な貯蓄がある
- 老後の生活費をより充実させたい
4. お得な年金の受給タイミングは?判断基準をチェック

年金の受給開始年齢を決める際、単に「早くもらうか、遅くもらうか」ではなく、自分のライフスタイルや経済状況、健康状態を考慮することが大切です。
ここでは、どのような基準で最適な受給タイミングを判断すればよいのか、具体的なポイントを解説します。
① 健康状態や平均寿命を考慮する
年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給の損益分岐点は81歳~83歳とされています。
つまり、長生きするほど繰り下げ受給のほうが得になり、早く亡くなると繰り上げ受給のほうが得になるということです。
判断のポイント
✅ 健康状態が良く、長生きの可能性が高い → 繰り下げ受給が有利
✅ 持病がある、親族が短命の傾向にある → 繰り上げ受給が有利
また、男性の平均寿命は約81歳、女性は約87歳と言われているため、女性は繰り下げ受給のほうが得になるケースが多い傾向にあります。
② 貯蓄や退職後の収入とバランスを取る
受給開始年齢を決める際、手元の資金がどれくらいあるかも重要です。
判断のポイント
✅ 十分な貯蓄があり、退職後も資産運用ができる → 繰り下げ受給を検討
✅ 60歳以降の収入がなく、年金をすぐに必要とする → 繰り上げ受給を検討
例えば、60歳時点で2,000万円以上の貯蓄があり、年金なしでも生活できる人は、繰り下げ受給によって将来的に年金額を増やすのが有効です。
一方で、貯蓄が少なく、60歳以降の生活資金が厳しい場合は、早めに受け取るほうが安心です。
③ 損益分岐点を計算し、最適なタイミングを見極める
年金の受給開始年齢を決めるうえで、「何歳まで生きれば繰り下げ受給が得になるのか?」をシミュレーションすることが大切です。
年齢ごとの総受給額シミュレーション(基準年金額:月10万円)
| 受給開始年齢 | 75歳までの総受給額 | 80歳までの総受給額 | 85歳までの総受給額 | 90歳までの総受給額 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 3,420万円 | 3,960万円 | 4,500万円 | 5,040万円 |
| 65歳 | 2,400万円 | 3,600万円 | 4,800万円 | 6,000万円 |
| 70歳 | 1,700万円 | 3,400万円 | 5,100万円 | 6,800万円 |
| 75歳 | 1,324万円 | 2,646万円 | 3,968万円 | 5,290万円 |
この表を見ると、80歳までは繰り上げ受給のほうが総受給額が多く、81歳を超えると繰り下げ受給のほうが得になることが分かります。
結論:
- 80歳以下で亡くなる可能性が高いなら、早めに受給したほうが得
- 85歳以上生きる可能性が高いなら、繰り下げ受給のほうが得
④ 働き方と在職老齢年金の影響を考慮する
60歳以降も働く予定がある場合、「在職老齢年金制度」に注意が必要です。
在職老齢年金とは?
- 60歳~64歳の場合 → 月収が 28万円以上 あると年金が一部カットされる
- 65歳以上の場合 → 月収と年金額の合計が 47万円以上 で一部カット
判断のポイント
✅ 60歳以降も働く予定で月収が高い → 年金を繰り下げたほうが得
✅ 退職後すぐに年金を生活費に充てたい → 年金を早めに受給
60歳以降も働いて一定以上の収入がある場合、年金を繰り下げて受給額を増やすほうが合理的です。
逆に、早めにリタイアして年金を生活費に充てる場合は、60歳~65歳の間に受給を開始するのも選択肢となります。
⑤ 将来の年金制度の変更リスクを考慮する
政府は年金制度の見直しを続けており、将来的に受給開始年齢が引き上げられる可能性もあります。
現在でも「75歳まで繰り下げ可能」となり、今後さらなる制度変更が行われる可能性は否定できません。
判断のポイント
✅ 今後の年金制度の変更に不安がある → 早めに受給したほうが安心
✅ 現在の制度のままでも十分に生活できる → 繰り下げ受給で増額を狙う
特に、「年金の財源不足」などのニュースが気になる人は、繰り上げ受給を選ぶのも合理的な判断となります。
結論:どのタイミングで年金を受給すべき?
| こんな人におすすめ | 最適な受給開始年齢 |
|---|---|
| 長生きする自信がある(85歳以上まで生きる可能性が高い) | 70歳~75歳(繰り下げ受給) |
| 貯蓄が十分にあり、資産運用もできる | 70歳~75歳(繰り下げ受給) |
| 60歳以降も働き、収入がある | 70歳~75歳(繰り下げ受給) |
| 60歳以降の生活資金が不安 | 60歳~64歳(繰り上げ受給) |
| 親族が短命の傾向がある | 60歳~64歳(繰り上げ受給) |
| 将来の年金制度の変更が不安 | 60歳~65歳(繰り上げ or 標準受給) |
まとめ:あなたにとって最適な受給年齢を選ぼう
- 長生きする可能性が高いなら、繰り下げ受給が有利
- 60歳以降の生活資金が不安なら、繰り上げ受給も選択肢
- 在職老齢年金の影響や将来の年金制度変更も考慮する
自分のライフプランを見直し、最も安心できる受給タイミングを選びましょう。
5. 年金の受給額を増やすための工夫とは?
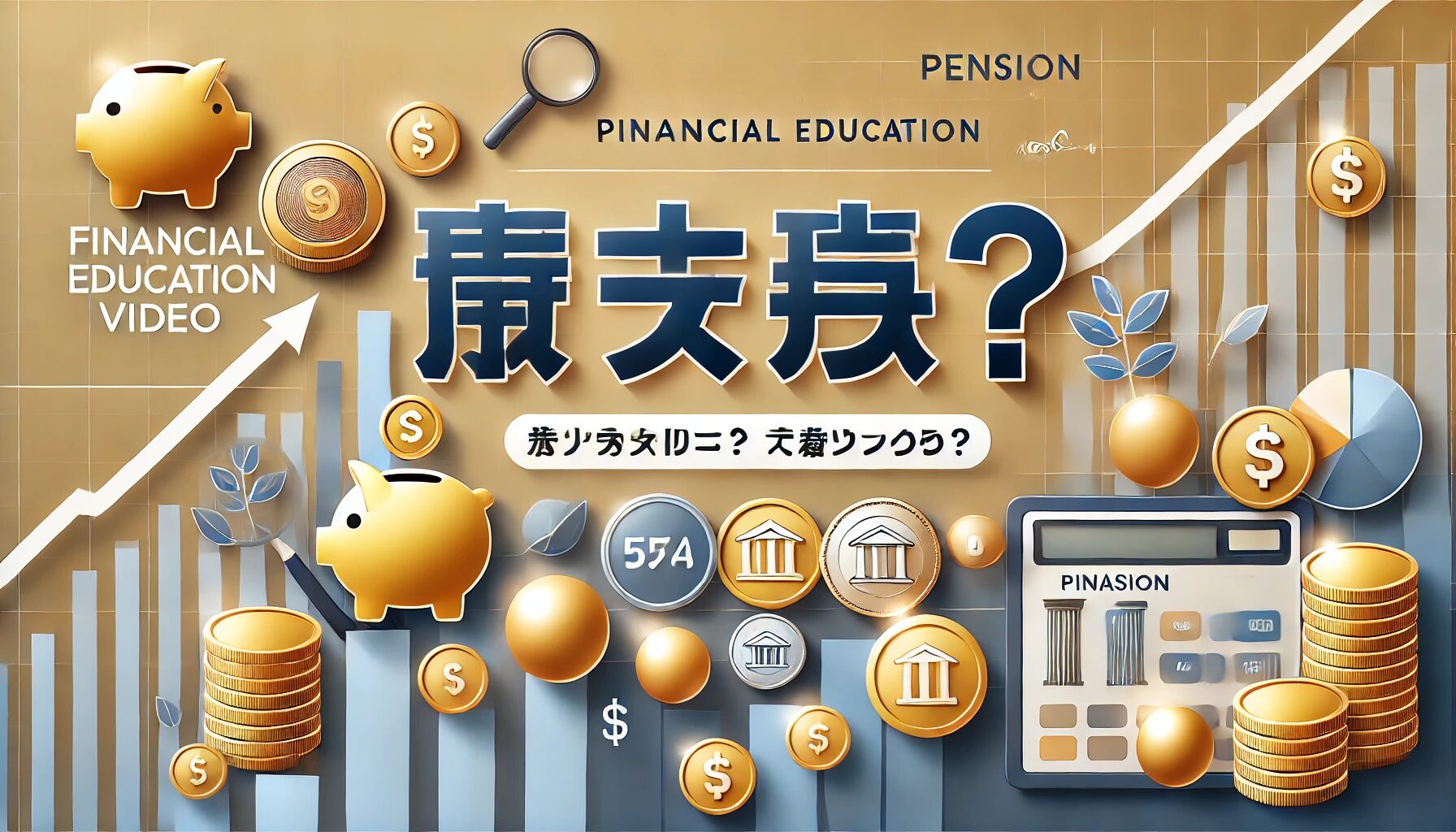
年金の受給開始年齢を決めるだけでなく、受け取る年金額を増やす工夫をすることで、老後の生活にゆとりを持たせることができます。
特に、年金だけで生活するのが難しいと感じる人は、以下の方法を活用して、将来の受給額を増やす対策を考えてみましょう。
① 長く働いて厚生年金の加入期間を延ばす
公的年金には「国民年金」と「厚生年金」がありますが、厚生年金に加入している期間が長いほど、受給額が増える仕組みになっています。
例えば…
✅ 会社員として65歳まで働いた場合 → 年金受給額が増える
✅ 65歳以上も働き続けた場合 → 働いた期間分、さらに受給額が増加
どれくらい増える?
- 会社員として厚生年金に1年間長く加入すると、年間約2万円~3万円の年金額アップが見込める。
- 65歳まで厚生年金に加入すると、基礎年金(国民年金)+ 厚生年金が受け取れるため、国民年金のみの人より多くの年金を受け取れる。
✅ 対策:可能であれば定年後も厚生年金に加入できる形で働くことで、老後の年金額を増やすことができる。
② 繰り下げ受給を活用して年金額を増やす
年金を繰り下げることで、受給額を最大84%増やすことが可能です。
繰り下げ受給の増額率(65歳基準の年金月10万円の場合)
| 受給開始年齢 | 増額率 | 月額受給額 | 年間受給額 |
|---|---|---|---|
| 65歳 | ±0% | 10万円 | 120万円 |
| 70歳 | +42% | 14万2,000円 | 170万4,000円 |
| 75歳 | +84% | 18万4,000円 | 220万8,000円 |
✅ 対策:長生きする可能性が高い場合、繰り下げ受給を検討することで、老後の生活資金を増やせる。
③ iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用する
iDeCo(イデコ)は、自分で積み立てる年金制度で、掛金が全額所得控除になるため、節税しながら年金資産を増やせるのが特徴です。
iDeCoのメリット
✅ 掛金が全額所得控除(所得税・住民税の節税効果)
✅ 運用益が非課税(通常の投資では課税される利益が非課税になる)
✅ 受取時にも税制優遇あり(退職所得控除や公的年金控除の適用)
積み立て例(30歳から月2万円を積み立てた場合)
- 65歳時点で約1,000万円以上の年金資産が形成可能(年利3%運用の場合)。
✅ 対策:将来の年金不足が不安な人は、iDeCoを活用して自分で年金資産を増やすのも効果的。
④ 付加年金を活用して国民年金の受給額を増やす
自営業者やフリーランスなど国民年金のみの人は、「付加年金」を活用することで、少ない負担で年金額を増やせます。
付加年金の仕組み
✅ 月額400円の追加負担で、将来の年金が「200円 × 加入月数」増額される。
例えば…
✅ 20年間(240カ月)付加年金を払った場合 → 年間4万8,000円の年金増額!
✅ 受給から2年で元が取れるので、長生きするほどお得。
✅ 対策:自営業やフリーランスの人は、付加年金を活用して将来の年金額を少しでも増やすのがおすすめ。
⑤ 企業年金・退職金制度を活用する
会社員の人は、公的年金に加えて企業年金や退職金制度がある場合、それを活用することで老後の資金を増やせます。
✅ 企業型確定拠出年金(企業型DC) → 会社が掛金を積み立て、将来の年金資産として受け取れる。
✅ 厚生年金基金 → 一部の企業で導入されている追加の年金制度。
✅ 退職金制度 → 退職時にまとまった資金を受け取れる。
✅ 対策:勤務先の制度を確認し、企業年金や退職金を最大限活用する。
⑥ 資産運用で年金を補完する
年金だけでは生活が厳しい場合、資産運用を活用して老後資金を増やすことも有効です。
✅ NISA(つみたてNISA) → 運用益が非課税のため、老後資金を効率的に増やせる。
✅ 投資信託・ETF → 長期的に資産形成を行い、老後資金を確保。
✅ 不動産投資 → 家賃収入を得ることで、年金とは別の収入源を確保。
✅ 対策:貯蓄だけでなく、NISAや投資信託を活用して、資産を長期的に運用し、老後資金を増やす。
まとめ:年金の受給額を増やすための6つの方法
| 方法 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ① 厚生年金の加入期間を延ばす | 長く働くことで年金額アップ | 年間2~3万円の増額 |
| ② 繰り下げ受給を活用する | 75歳まで繰り下げると最大84%増額 | 年間100万円以上の増額も可能 |
| ③ iDeCoを活用する | 節税しながら老後資産を形成 | 30年で1,000万円以上の資産形成可 |
| ④ 付加年金を活用する | 月400円の負担で年金増額 | 2年で元が取れる |
| ⑤ 企業年金・退職金を活用 | 会社の制度を最大限利用 | 年間数十万円の追加年金が可能 |
| ⑥ 資産運用で補完 | NISAや投資信託で資産形成 | 長期的に老後資金を増やせる |
結論:老後の年金を増やすには?
✅ 長く働いて厚生年金の加入期間を延ばす
✅ 繰り下げ受給を活用して年金額を増やす
✅ iDeCoや付加年金を活用して私的年金を増やす
✅ 企業年金や退職金の制度を最大限活用する
✅ NISAや資産運用を取り入れて、老後資金を確保する
少しの工夫で、将来受け取る年金額を増やすことが可能です。今からできることを実践し、老後の備えをしっかり整えましょう!
6. ねんきんネットを活用して自分の年金を試算する方法

年金の受給開始年齢を決める際に、「自分は何歳から受給するのが最もお得なのか?」をシミュレーションすることが重要です。
そのために便利なのが、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」です。
ねんきんネットを使えば、将来受け取る年金額の試算や、繰り上げ・繰り下げ受給時の受給額の変化を簡単に確認できます。
ここでは、ねんきんネットの基本情報や、具体的な活用方法を詳しく解説します。
① ねんきんネットとは?
✅ ねんきんネットとは
- 日本年金機構が提供する無料のオンラインサービス
- 自分の年金記録や将来の受給額を確認できる
- 繰り上げ・繰り下げ受給のシミュレーションが可能
✅ ねんきんネットでできること
- 現在の年金加入記録を確認(自分が何年厚生年金・国民年金に加入しているか)
- 将来の年金受給額を試算(何歳から受け取るといくらになるか)
- 繰り上げ・繰り下げ受給の試算(受給開始年齢を変えた場合の金額シミュレーション)
- 受給額を増やす方法を試算(例えば、働く期間を延ばしたらどうなるか)
② ねんきんネットの登録方法
ねんきんネットを利用するには、まずアカウント登録が必要です。
📌 登録手順
① 基礎年金番号を用意する
- 基礎年金番号は「ねんきん定期便」や「年金手帳」に記載されています。
② ねんきんネットの公式サイトへアクセス
- ねんきんネット(日本年金機構)
③ 新規登録(ID発行)を行う
- マイナンバーカードを持っている人 → 即時発行可能
- マイナンバーカードがない人 → 郵送でIDを受け取り(約1週間)
④ ログインし、年金記録を確認する
③ ねんきんネットで将来の年金額を試算する方法
📌 試算手順(65歳受給の場合)
① ねんきんネットにログイン
② 「将来の年金額を試算する」をクリック
③ 現在の年齢や年金加入記録を確認
④ 65歳受給の場合の年金額を確認
例)65歳受給の場合の試算結果
- 国民年金のみ:月6.5万円(満額)
- 厚生年金あり:月14万円(会社員時代の給与による)
✅ 65歳受給は「標準の受給額」なので、ここを基準にする。
④ 繰り上げ・繰り下げ受給時のシミュレーション方法
📌 繰り上げ受給の試算(60歳~64歳)
① 「繰り上げ受給」を選択
② 希望する開始年齢(例:60歳)を入力
③ 減額後の年金額を確認
例)60歳受給の試算結果(基準年金額:月10万円)
- 繰り上げ受給(60歳開始)→ 月7万6,000円(▲24%)
- 繰り上げ受給(62歳開始)→ 月8万5,600円(▲14.4%)
✅ 60歳から受給すると、一生減額されたままになるので注意!
📌 繰り下げ受給の試算(66歳~75歳)
① 「繰り下げ受給」を選択
② 希望する開始年齢(例:70歳)を入力
③ 増額後の年金額を確認
例)70歳受給の試算結果(基準年金額:月10万円)
- 繰り下げ受給(70歳開始)→ 月14万2,000円(+42%)
- 繰り下げ受給(75歳開始)→ 月18万4,000円(+84%)
✅ 繰り下げ受給すると年金額は増えるが、無収入期間をどう乗り切るかが課題!
⑤ 受給開始年齢の比較と損益分岐点の計算
ねんきんネットでは、各受給開始年齢ごとの総受給額の試算も可能!
| 受給開始年齢 | 75歳までの総受給額 | 80歳までの総受給額 | 85歳までの総受給額 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | 3,420万円 | 3,960万円 | 4,500万円 |
| 65歳 | 2,400万円 | 3,600万円 | 4,800万円 |
| 70歳 | 1,700万円 | 3,400万円 | 5,100万円 |
| 75歳 | 1,324万円 | 2,646万円 | 3,968万円 |
✅ 80歳まで生きるなら繰り上げ受給が有利、85歳以上なら繰り下げ受給が有利!
⑥ ねんきんネットを活用して最適な受給年齢を決めよう!
📌 ねんきんネットで確認すべきポイント
✅ 65歳受給の金額を確認し、基準とする
✅ 繰り上げ・繰り下げ受給時の金額を試算し、どれくらい変わるか見る
✅ 自分の寿命や貯蓄を考慮し、どの選択が得かをシミュレーション
💡 判断基準
- 60歳から受け取るべきか? → 生活資金が不足している場合
- 65歳の標準受給が最適か? → 無難に安定した受給を望む場合
- 70歳以降に繰り下げるべきか? → 長生きする自信があり、生活資金に余裕がある場合
まとめ:ねんきんネットを使って、最適な年金プランを決めよう!
✅ ねんきんネットを使えば、年金の試算が簡単にできる!
✅ 繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを比較できる!
✅ 損益分岐点を確認し、自分にとってお得な受給年齢を選べる!
「何歳から年金を受け取るべきか?」は、ねんきんネットで試算して、自分に最適な選択をしましょう!
7. まとめ あなたにとって最適な受給年齢を考えよう

年金の受給開始年齢を決めることは、老後の生活設計において非常に重要な判断です。
しかし、「何歳から受け取るのが一番お得か?」は一概には言えません。
なぜなら、個人の寿命、貯蓄額、健康状態、ライフスタイルによって最適な選択肢が異なるからです。
ここでは、これまで解説してきたポイントを整理し、あなたにとって最適な年金の受給開始年齢を考えるためのチェックリストを紹介します。
① 受給開始年齢ごとのメリット・デメリットをおさらい
| 受給開始年齢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 60歳~64歳(繰り上げ受給) | 早く年金を受け取れる長生きしない場合はお得 | 一生減額される(最大▲24%)80歳を超えると総受給額が少なくなる |
| 65歳(標準受給) | 減額・増額なしで安定した受給 | 繰り上げより開始が遅く、繰り下げより年金額が少ない |
| 66歳~75歳(繰り下げ受給) | 受給額が増える(最大+84%)長生きするほどお得 | 75歳まで受給ゼロ長生きしないと損になる |
💡 80歳以下なら繰り上げ受給が有利、85歳以上なら繰り下げ受給が有利!
② 受給開始年齢を決めるためのチェックリスト
以下の項目に当てはまる数が多い方が、あなたに適した受給開始年齢の目安です。
✅ 「繰り上げ受給(60歳~64歳)」が向いている人
- 60歳で退職し、すぐに年金が必要
- 貯蓄が少なく、生活費をカバーする収入源がない
- 親族が短命の傾向があり、長生きする自信がない
- 退職後に働く予定がなく、安定した収入が欲しい
✅ 「標準の65歳受給」が向いている人
- 無難に安定した受給を望む
- 受給額の減額や増額を気にせず、計画的に年金を使いたい
- 長生きするかどうかの判断が難しいので、標準的な選択をしたい
✅ 「繰り下げ受給(66歳~75歳)」が向いている人
- 貯蓄が十分にあり、年金を遅らせても生活に困らない
- 65歳以降も働き続け、収入がある
- 親族が長寿の傾向があり、自分も長生きする可能性が高い
- できるだけ年金額を増やし、老後の安心感を高めたい
③ ねんきんネットを活用して最適なプランを決める
ねんきんネットを使えば、自分の年金受給額を具体的に試算できます!
- 繰り上げ・繰り下げ受給の金額を比較し、どのタイミングが最適か判断できる。
- 損益分岐点(何歳まで生きれば繰り下げのほうが得か)を計算できる。
- 収入や貯蓄と照らし合わせながら、計画的に受給タイミングを決められる。
💡 決め手になるのは「ライフスタイル」! ねんきんネットで試算し、自分に最適な受給年齢を見つけましょう!
④ 老後の生活を豊かにするためにできること
年金の受給開始年齢を決めるだけでなく、老後の生活をより安定させるために、以下の対策を取り入れるのもおすすめです。
- 厚生年金の加入期間を延ばす → 会社員として長く働くほど、年金額が増える!
- iDeCoやNISAで資産形成をする → 将来の年金不足を補うための準備を!
- 付加年金を活用する(自営業・フリーランス向け) → 月400円の負担で将来の年金を増やせる!
- 繰り下げ受給で年金額を増やす → 長生きするなら、最大84%増額も可能!
- 企業年金や退職金制度を活用する → 勤務先の制度をフル活用し、老後資金を増やそう!
⑤ まとめ:あなたに合った受給開始年齢を考えよう!
📌 年金を何歳から受け取るのがベストかは、一人ひとり違う!
📌 「寿命・貯蓄・ライフスタイル・仕事の予定」を考慮して決めることが重要!
📌 ねんきんネットを使って、受給開始年齢ごとの年金額を試算しよう!
💡 最も大切なのは、「自分の老後にとってどの選択が最も安心できるか?」という視点です。
✅ 「早めに受け取りたいなら60歳~64歳」
✅ 「無難に安定した受給なら65歳」
✅ 「長生きの可能性があるなら70歳~75歳で繰り下げ」
🎯 今日からできるアクションプラン
✅ ねんきんネットに登録し、自分の年金額を確認する
✅ 繰り上げ・繰り下げ受給時のシミュレーションを試してみる
✅ 家族と相談し、ライフプランを考えながら受給開始年齢を決める
年金は人生の大切な収入源です。慎重に判断し、最適な受給開始年齢を選びましょう!
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
