はじめに

投資は「長期で続ければ資産が増える」とよく言われますが、実際には多くの人が途中でやめてしまいます。
新NISAのスタート以降、日本では投資を始める人が急増しました。
しかし投資信託の平均保有期間は3年弱と短く、理想と現実のギャップに直面して市場から退場してしまうケースが多いのが実情です。
本記事では、なぜ大半の人が投資をやめてしまうのか、その典型的な6つの理由を整理します。
さらに、それぞれの理由を回避するための具体的な対策も紹介します。
この記事を読むことで、投資を長期的に継続し、資産形成を成功させるための実践的なヒントを得られるはずです。
まずはこちらをご覧ください👇
投資をやめる人が多い背景と現状

投資は本来、長期的に取り組むことで効果を発揮するものです。
しかし実際には、多くの人が数年以内に投資をやめてしまいます。
投資信託の平均保有期間は3年弱であり、せっかく始めても資産形成に至る前に撤退してしまうのが現実です。
特に近年は株価が好調な時期が続き、新NISAの導入によって投資を始める人が急増しました。
ところが、順調に見える相場の裏には多くの落とし穴が潜んでおり、少しの下落や不安感で投資をやめてしまうケースが少なくありません。
こうした背景には、期待と現実のギャップ、相場環境の変化、心理的な不安、そして情報の過多などが複雑に絡み合っています。
次章では、投資をやめる典型的な6つの理由を一つずつ詳しく解説します。
期待とのギャップが生む失望
投資を始めたばかりの人が最初に直面する壁は「期待と現実のギャップ」です。
多くの人は、年利5%や7%といった数字をもとにシミュレーションを行い、長期的には資産がきれいに右肩上がりに増えていくとイメージします。
しかし実際の投資はそのように単調には進みません。
株式市場は常に上下を繰り返し、時には大幅に下落することもあります。
たとえば世界株ETFのVTは、長期的には年平均8%程度の高いリターンを残していますが、リーマンショックやコロナショックの際には一時的に30%以上の下落を経験しています。
こうした現実を知らずに「毎年必ず増える」と誤解していると、下落局面で想定外の資産減少に直面し、パニック売りにつながってしまいます。
実際、2024年8月の世界的な株価下落時には、多くの投資信託が大量に解約されました。
投資を続けるためには、まず「シミュレーションはあくまで平均値にすぎない」という事実を理解し、資産の増減を受け入れる心構えを持つことが不可欠です。
株価の持続的な低迷に耐えられない
次に多くの投資家が市場から退場する大きな理由が「株価の持続的な低迷」です。
近年投資を始めた人の多くは、下落しても短期間で回復する経験しかしていません。
たとえばコロナショックでは1か月で30%以上下落したものの、半年以内に回復し、むしろ最高値を更新しました。
このような経験から「下がってもすぐ戻る」という誤解を持ちやすくなっています。
しかし歴史を振り返ると、株価の低迷が数年間続いた例も多くあります。
2000年のITバブル崩壊では、NASDAQが約80%下落し、回復までに10年以上かかりました。
さらに2008年のリーマンショックではS&P500が50%以上下落し、投資家の多くが市場を去りました。
持続的な低迷は、資産が減る苦痛に加え、世の中全体の悲観ムードが投資家心理を圧迫します。
その結果、本来は「長期保有でこそ回復が期待できる」インデックス投資でさえ、途中で諦めてしまう人が続出するのです。
投資を継続するには、過去の相場の歴史を学び「長期的には必ず上下を繰り返す」という現実を理解し、資産が減っても冷静に対応できるメンタルと準備を整える必要があります。
リスクの取り過ぎが招く強制終了
投資を途中でやめざるを得なくなる大きな原因の一つが「リスクの取り過ぎ」です。
株価が好調な局面では「もっと資金を投じないと損」という雰囲気が広がり、生活資金や将来必要な資金まで投資に回す人が出てきます。
住宅購入でも「頭金を減らして投資に回そう」と考える人も少なくありません。
しかし、こうした行動は景気悪化や暴落の局面で大きなリスクを背負うことになります。
もし株価が長期にわたり低迷すれば、資産は減少するだけでなく、給料の減少や失業など生活面にも打撃が及ぶ可能性があります。
そのような状況で現金を十分に持たず投資に偏った資産構成をしていた場合、含み損を抱えながらも生活費を確保するためにファンドを売却せざるを得なくなります。
結果として、本来なら耐えていれば回復したはずの投資を途中で終えることになり、資産形成のチャンスを失ってしまうのです。
この落とし穴を避けるには、防衛資金の確保が必須です。
最低でも生活費1年分、できれば2年分程度の現金を手元に置き、近い将来に使う予定の資金は投資に回さないことが重要です。
これにより景気が悪化しても冷静に対応でき、投資を継続できる土台が整います。
過剰な不安感が投資を妨げる

投資を続けられなくなる4つ目の大きな理由は「過剰な不安感」です。
投資信託協会の調査では、株式投資信託を保有している人のうち約6割が不安を感じていると報告されています。
値動きに一喜一憂したり、少しの下落でも強いストレスを抱えてしまう人は少なくありません。
こうした心理的負担は、投資を続ける意思があっても「もうやめたい」という気持ちに繋がりやすいのです。
なぜ不安感が強くなるのかといえば、多くは知識不足にあります。
たとえばインデックス投資の中身を理解していれば、そのファンドが世界的な優良企業の株式で構成されていることが分かります。
AppleやAmazon、Googleといった企業は世界中から優秀な人材を集め、成長を続けています。
その事実を知れば「一時的に下落してもいずれ回復するだろう」と考えられるようになり、過剰に不安を抱かずに済むのです。
逆に知識が不足したまま投資を始めると、短期的な下落を「もう終わりだ」と受け取ってしまい、結果的に売却して投資をやめる行動に繋がります。
投資はお金を増やす手段であると同時に、自分の心理との戦いでもあります。
不安を和らげるには、投資の仕組みを理解し、学び続ける姿勢を持つことが欠かせません。
含み益がもたらす誘惑
投資をやめてしまう5つ目の理由は「含み益の誘惑」です。
人は利益よりも損失に強く反応するという心理を持っています。
これはプロスペクト理論として知られ、「1万円の利益の嬉しさ」よりも「1万円の損失の痛み」の方が大きく感じられる、という人間の性質です。
株価が上昇して含み益が出ていると「今売れば確実に利益を確定できる」という誘惑が強くなります。
特に、過去に下落に耐えてようやく資産が戻ったタイミングでは「もう下がる前に売ってしまいたい」という気持ちが生まれやすいのです。
しかし、その心理に流されて売却すると、将来訪れる大きな上昇局面を逃してしまう可能性が高くなります。
インデックス投資は、市場の長期的な成長に乗ることで利益を得る仕組みです。
短期的な売買を繰り返すと、相場の「稲妻が輝く瞬間」と呼ばれる大きな上昇を逃してしまい、結果的にリターンを大きく減らすことにつながります。
投資を継続するためには「含み益に惑わされないルール作り」が欠かせません。
具体的には、明確な目標額や運用方針をあらかじめ設定し、感情ではなくルールに従って判断することが大切です。
メディアの影響
投資をやめてしまう6つ目の理由は「メディアの影響」です。
現代はSNSやニュース、YouTubeなどを通じて日々大量の投資情報に触れる時代です。
その中には「インデックス投資は儲からない」「これからは○○株が来る」といった発信や、より高いリターンを謳う手法の紹介があふれています。
こうした情報は一見説得力がありますが、多くの場合はポジショントークであり、発信者の立場やビジネス上の意図が絡んでいることを理解する必要があります。
例えば証券業界では、多くの人が低コストのインデックスファンドだけを買うと手数料収入が減ってしまいます。
そのため、アクティブ運用や短期売買を推奨する情報発信が出てくるのは自然なことです。
また、メディアに登場する専門家は予想をすることで注目を集め、ビジネスにつなげています。
つまり、彼らの発言に振り回される必要は全くないのです。
実際に市場の大半は機関投資家というプロが占めています。
インデックス投資で得られるリターンは、そうしたプロ集団が日々戦った結果の「平均値」です。
一般の個人投資家が長期的にこの平均を上回るのは極めて難しく、むしろシンプルにインデックス投資を継続することが最も合理的だといえます。
メディアやSNSの情報はあくまで参考程度にとどめ、自分が最初に決めた投資方針をブレずに守ることが重要です。
目先の情報に流されて商品を乗り換えたり、短期的な予想に基づいて売買を繰り返すと、結果的にリターンを大きく損なう可能性があります。
投資をやめてしまう6つの理由まとめ
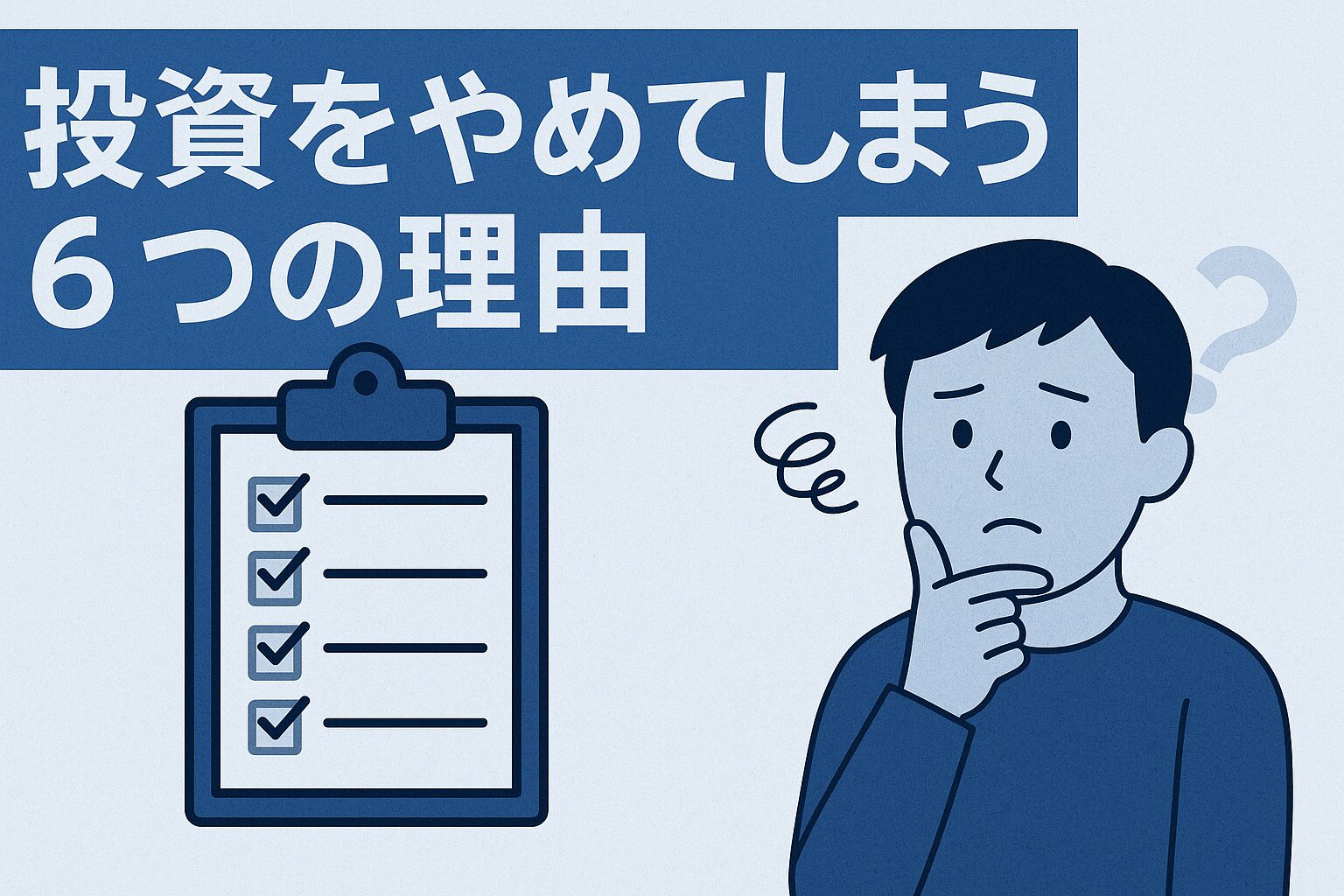
これまで解説してきた通り、多くの人が投資を続けられずにやめてしまうのは、特別な才能や知識がないからではなく、心理的な罠や環境の変化が大きく影響しています。ここで6つの理由を整理します。
投資をやめる主な理由6つ
- 期待とのギャップ
シミュレーション通りに資産が増えないことで失望し、急落時にパニック売りをしてしまう。 - 株価の持続的な低迷
一時的な暴落ではなく、数年にわたりじわじわ下がる局面に耐えられず退場する。 - リスクの取りすぎ
生活防衛資金がなく、ローンや収入減と重なり資産を売らざるを得なくなる。 - 過度な不安感
知識不足から日々の値動きに過剰反応し、精神的に消耗して投資をやめる。 - 含み益の誘惑
少し利益が出ると「確定したい」という心理に負け、本来の長期投資方針を崩してしまう。 - メディアの影響
専門家やインフルエンサーの発信に惑わされ、自分の投資方針を見失ってしまう。
投資を続けるために必要な対策
では、これらを避けて長期投資を継続するにはどうすればよいのでしょうか。
1. シミュレーションは参考程度に
投資は上下を繰り返すもので、常に右肩上がりにはなりません。
短期の値動きに惑わされず、数十年単位の視点を持ちましょう。
2. 生活防衛資金を確保する
最低でも1年分の生活費は現金で持ち、急な収入減にも耐えられる体制を作ることが大切です。
3. 投資の基礎知識を学ぶ
インデックス投資の仕組みやリスクを理解すれば、不安感は大きく軽減されます。
学びながら続ける姿勢が必要です。
4. 感情ではなくルールで動く
利益確定や損切りは感情ではなく、事前に決めたルールや目的に沿って判断しましょう。
5. 情報の取捨選択を徹底する
メディアやSNSの情報は参考にしても、投資方針を変える理由にはしない。
自分の軸を守ることが継続の鍵です。
投資は「知識」「ルール」「心構え」の3つが揃って初めて継続できます。
相場が好調な今だからこそ、将来の厳しい局面を見据えて準備することが大切です。
投資初心者が守るべきルール集
投資を続けるためには、知識だけでなく「自分なりのルール」を決めておくことが重要です。
相場が好調なときも不調なときも、感情ではなくルールに従って行動できる人が最終的に資産を築きやすくなります。
ここでは初心者でもすぐ実践できる基本ルールを整理しました。
1. 生活防衛資金を必ず確保する
投資を始める前に、最低でも1年分の生活費を現金で残しておきましょう。
これがないと、急な収入減や予期せぬ出費で投資資金を取り崩さざるを得なくなります。
2. 毎月の積立額を固定する
投資は「長期・分散・積立」が基本です。
相場が良くても悪くても、毎月同じ額を積み立て続けることが将来のリターンにつながります。
3. 投資目的を明確にする
「老後資金のため」「教育資金のため」「将来の生活防衛のため」など、目的を決めておくことで途中で迷いにくくなります。
目的ごとに投資額や商品を分けるのも有効です。
4. 利益確定や損切りの基準を持つ
「含み益が出たら売る」ではなく、いつ・なぜ売るのかをルール化しておくことが大切です。
例:子どもの大学入学資金として必要になる5年前から少しずつ現金化する。
5. 情報源を絞る
SNSやニュースにはさまざまな意見がありますが、全てに反応すると投資方針がブレてしまいます。
信頼できる情報源を1~2つに絞ることをおすすめします。
6. 相場の下落を想定しておく
「株価は必ず上下する」という前提を忘れないこと。
暴落が来ても慌てず、あらかじめシナリオを想定しておくと冷静に対応できます。
まとめ
投資を継続するためには、感情ではなくルールで動くことが不可欠です。
これらのルールを自分の生活や目的に合わせてカスタマイズし、紙やメモアプリに書き出しておくと効果的です。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。