※本ページはプロモーションが含まれています。
第1章 1株優待とは何か?投資の常識を変える新しい形
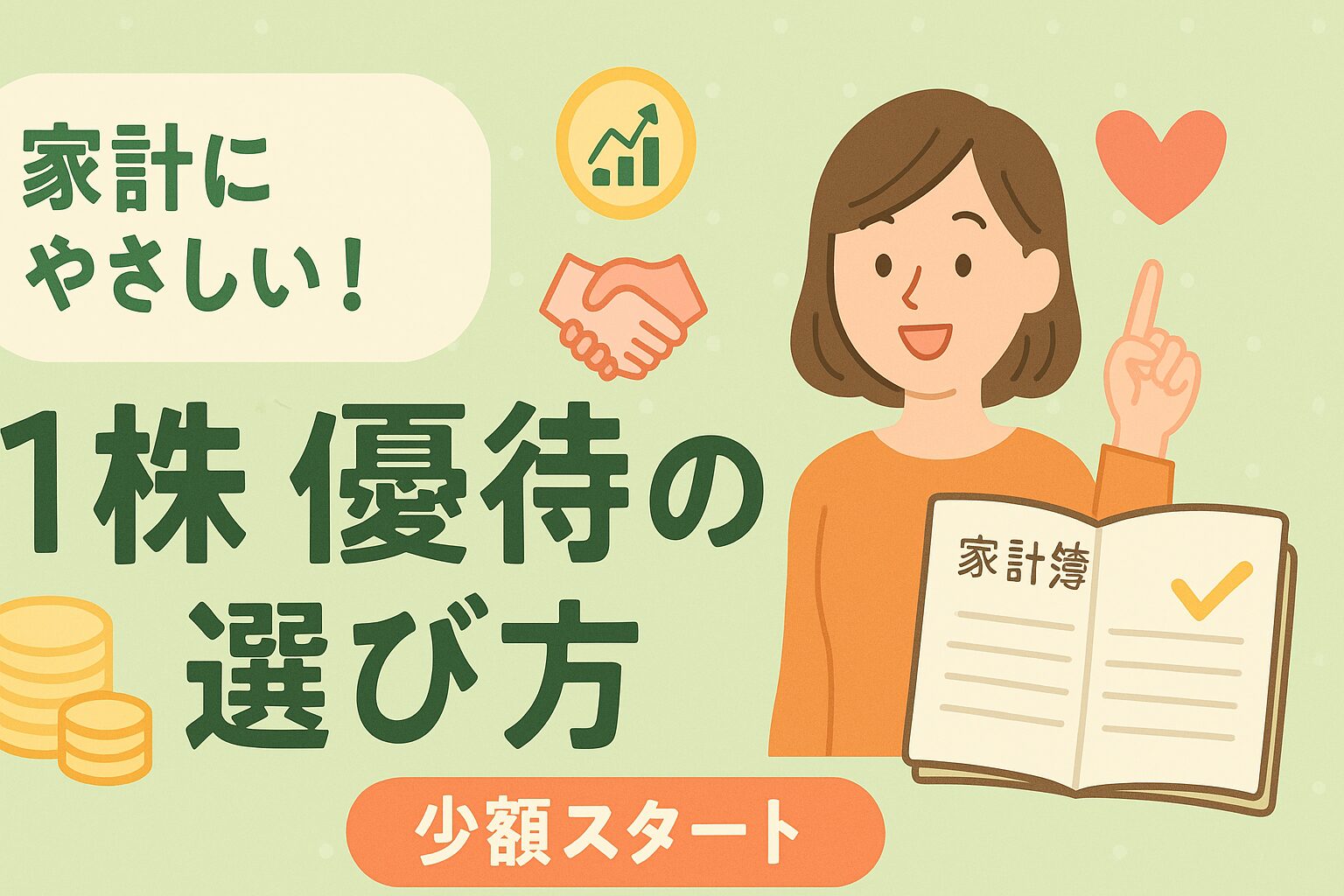
「株主優待」と聞くと、100株以上の保有が必要で、数十万円の資金がないとできない──そう思っていませんか?
実は今、“1株だけでも優待がもらえる”企業が増えています。
それが「1株優待(いちかぶゆうたい)」です。
この仕組みは、投資をもっと身近に、そしてより多くの人に楽しんでもらうために広がっている新しい形です。
わずか数百円から数千円の投資で「株主」として認められ、実際に企業からプレゼントやサービスが届く。
そんな“お得でちょっとワクワクする投資”として注目を集めています。
まずはこちらをご覧ください👇
1株優待とは?基本の仕組みを理解しよう
通常、企業は「単元株(たんげんかぶ)」という単位で優待の条件を決めています。
たとえば「100株以上保有の株主に商品券を贈呈」などが一般的です。
しかし一部の企業は、「端株(たんかぶ)」──つまり100株に満たない少額の株でも優待を提供しています。
この「端株優待」こそが、1株優待の正体です。
1株でも株主名簿に記載されれば、立派に“株主”として認められます。
そのため、優待の対象に含めてくれる企業が存在するのです。
たとえば、
- QUOカードを贈る企業
- 自社製品の試供品を届ける企業
- 自社サービスの割引を提供する企業
など、さまざまな形で「1株でも応援してくれた人」へ感謝を届けています。
少額でも“オーナー体験”ができる時代へ
1株優待の魅力は、単なる「お得」だけではありません。
ほんの1株を持つだけで、あなたは企業のオーナーの一人。
決算書を見たり、株主通信を受け取ったり──企業との“関係”が始まります。
しかも必要な資金は、1株あたり数百円〜数千円程度。
たとえば、信越化学工業は約1,900円前後、Netyearグループなら500円台と、ランチ1回分の金額でも株主になれます。
「ちょっと試してみよう」が叶うのが、1株優待の最大の特徴です。
この手軽さこそが、これまで投資を敬遠していた層──特に主婦や学生──に支持される理由です。
「投資=難しい」「損しそう」というイメージを覆し、日常生活に“お得な投資”を取り入れる文化が広がっています。
企業が1株優待を実施する理由
なぜ企業は、わずか1株の株主にも優待を提供するのでしょうか。
その背景には、「株主との関係を深めたい」という経営戦略があります。
- ファン株主の増加
優待を通じて企業を身近に感じてもらい、自社製品を使ってもらう狙いがあります。 - 株主数の拡大
株主数が増えることで、上場維持基準を満たしやすくなるという側面もあります。 - ブランドロイヤルティの向上
たとえば飲料メーカーが自社製品を贈ることで、商品ファンを増やし、販売促進にもつなげています。
つまり、1株優待は企業にとっても“マーケティング戦略”の一つなのです。
少額の投資家でも企業に関心を持ってもらえるなら、企業側にも大きな価値があります。
投資初心者にとっての「最初の一歩」
1株優待は、株式投資の入門としても理想的です。
リスクが小さく、現物を所有する実感が得られ、実際に優待が届けば成功体験になります。
この“成功体験”が非常に重要です。
多くの人は「投資は怖い」と感じて行動できません。
しかし、実際に優待品が届くことで、
「やってみたら意外と簡単」「もっと学びたい」と前向きな意識に変わります。
こうして、1株優待は投資への第一歩として、多くの初心者を後押ししているのです。
まとめ
1株優待は、少額でも企業とつながり、実際のリターンを感じられる新しい投資の形です。
お金を増やすだけでなく、「企業を応援する」「株主として関わる」という楽しさを知ることができます。
小さく始めて、大きく学ぶ。
これが、これからの時代の“賢い投資スタイル”です。
第2章 1株優待のメリットとデメリットを徹底比較
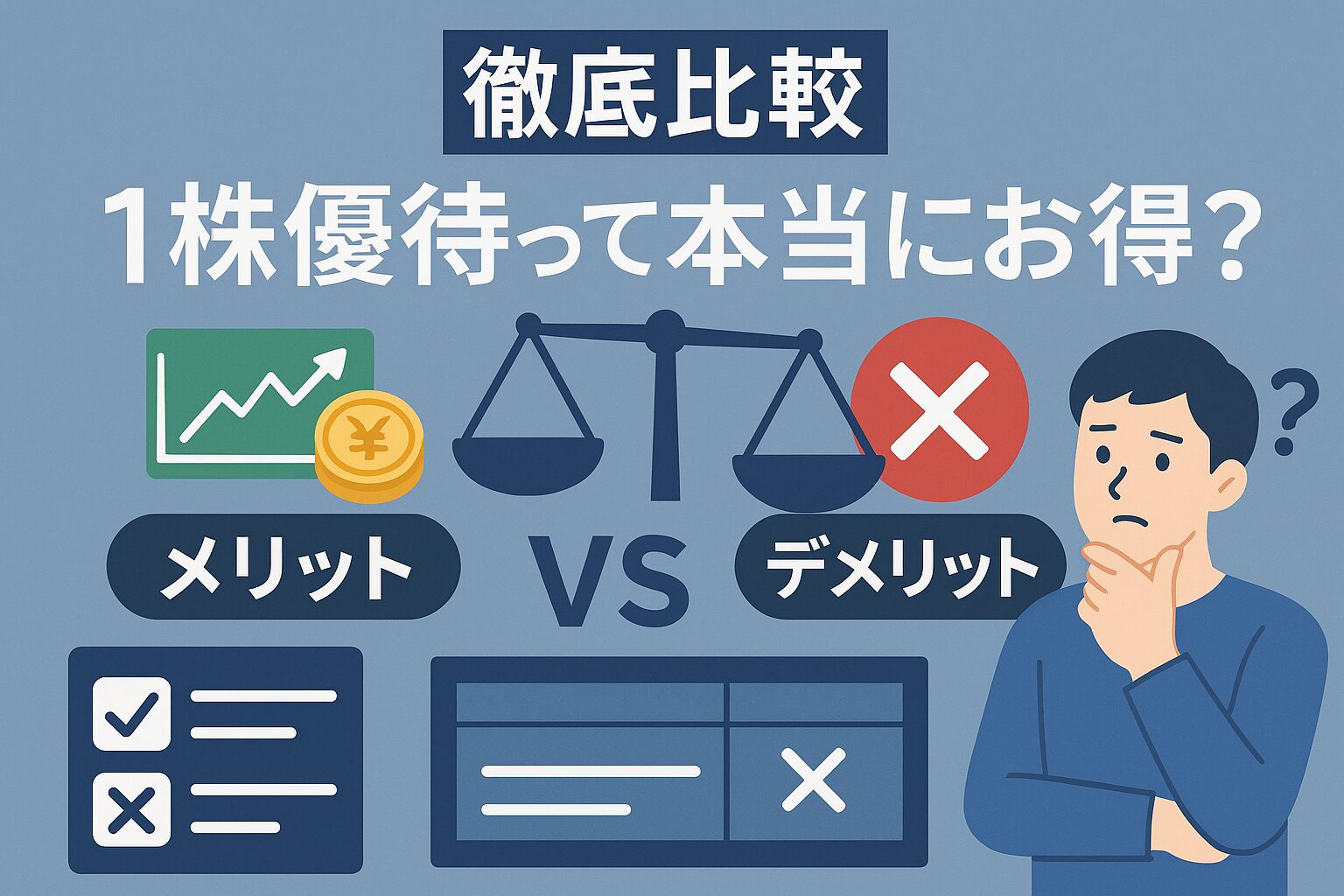
1株優待は、わずか数百円から始められる“最も身近な株式投資”です。
しかし、メリットだけに注目してしまうと、思わぬ落とし穴に気づけないこともあります。
ここでは、初心者が誤解しやすいポイントを整理しながら、メリットとデメリットを冷静に比較していきましょう。
1株優待の主なメリット
① 少額で株主体験ができる
1株優待の最大の魅力は、わずかな資金で“株主”になれることです。
たとえば、株価が500円の企業であれば、たった500円の投資で株主として登録され、
優待や配当を受け取れる可能性があります。
「投資に興味はあるけど、いきなり10万円は怖い」
そんな人でも、リスクを抑えながら実際に株主体験を得られるのが魅力です。
② 優待を通じて企業を“応援”できる
1株優待を実施する企業は、株主との関係を大切にする傾向があります。
自社製品を贈ることで、ファンづくりや企業ブランドの浸透を狙っているのです。
たとえば、食品メーカーが「自社お菓子詰め合わせ」を送るケース。
実際に手に取ることで「この企業、応援したいな」と思える瞬間が生まれます。
投資=お金を増やすだけでなく、“企業とのつながりを楽しむ”という体験価値を得られるのです。
③ 株主通信やIR資料で金融リテラシーが上がる
1株でも株主になると、企業から「株主通信」や「事業報告書」が届きます。
これは、普段ニュースでは触れない“企業のリアル”を学べる教材そのものです。
どんな事業で利益を出しているのか、配当方針はどうか。
数字を通して経営を学べるため、投資初心者の金融リテラシー向上にもつながります。
④ 長期保有で優待内容がアップするケースも
一部の企業では、「継続保有」を条件に優待内容を充実させています。
つまり、1株だけでも“持ち続けるほどお得になる”設計です。
例:
- 1年以上保有 → QUOカード1,000円分
- 3年以上保有 → QUOカード2,000円分
短期売買では得られない「長期応援型優待」は、家計にもやさしい継続インセンティブになります。
1株優待の注意点・デメリット
① すべての企業が対象ではない
最も大きな注意点は、1株で優待をもらえる企業は限られているという点です。
多くの企業は「100株以上」を条件としており、1株では優待が発生しません。
また、「過去は1株でOKだったが、現在は廃止」というケースも少なくありません。
必ず最新のIR情報を確認する習慣が必要です。
② 優待廃止・改悪のリスク
1株優待は、コスト負担が企業側にあります。
経営環境の変化で「優待の廃止」や「内容の縮小」が発表されることもあります。
過去には、1株優待で人気だった企業が制度を見直し、
100株以上の保有者限定に変更する例もありました。
「永遠に続く優待は存在しない」という前提を理解しておきましょう。
③ 名義の扱いに注意が必要
証券会社によっては、1株購入でも名義が本人ではなく“信託口”扱いになることがあります。
この場合、株主名簿にあなたの名前が載らず、優待対象外になるケースがあります。
回避策としては、
- 名義が本人で登録される証券会社を選ぶ
- 優待対象企業をIRページで確認する
ことが必須です。
④ 配当金はごくわずか
1株分の配当は、数円〜数十円程度です。
「優待+配当で高利回り!」と考えるのは誤りです。
1株優待は経済的リターンよりも体験価値重視と考えたほうが現実的です。
メリット・デメリットのまとめ表
| 視点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 資金面 | 少額で始められる | 優待対象が限られる |
| 体験面 | 株主として企業と関われる | 制度変更リスクあり |
| 学習面 | 株主通信で金融リテラシーUP | 名義や制度の理解が必要 |
| 継続面 | 長期保有でお得になる企業も | 廃止時の対応が必要 |
結論:小さく始めて「リスクを知る」ことが最大の学び
1株優待は、“最小リスクで最大の経験を得られる投資法”です。
一方で、制度が変化するリスクも存在します。
しかし、株主通信を読み、企業の経営姿勢を知り、
「投資ってこういうことなんだ」と体感できる──
この学びは、100株投資では得られない貴重な財産です。
第3章 1株優待がもらえる神企業10選+注目銘柄ランキング

「1株優待」は、企業によって内容も条件もさまざまです。
ここでは、2025年時点で1株から優待がもらえる“神企業”10選を紹介します。
さらに、今後注目したい「優待拡充の兆しがある企業」もあわせてピックアップしました。
第1位 信越化学工業(4063)
優待内容:自社製品カタログ(生活用品セット)
株価目安:約1,900円/1株
化学メーカーのトップ企業。
自社グループの家庭用製品や生活雑貨など、品質の高いアイテムがもらえることで人気です。
1株でも株主通信や製品案内が届くため、「優待を実感できる端株企業」として代表格です。
ポイント
- 長期保有で企業通信が定期的に届く
- 株価が安定しており長期投資にも向く
第2位 伊藤忠食品(2692)
優待内容:グルメギフト券/食品カタログ
株価目安:約9,900円/1株
食品卸の大手。
1株でも優待案内が届くことがあり、「食」に関連する主婦人気の高い銘柄。
特に年末の優待では、選べるグルメ商品が届くケースもあります。
ポイント
- 食品系優待で満足度が高い
- 配当利回りも安定(年2%前後)
第3位 佳能電子(7739)
優待内容:QUOカード(500円相当)
株価目安:約2,700円/1株
1株保有で優待対象になりやすく、実際にQUOカードが届いた報告も多い人気企業。
生活に役立つ全国共通カードなので「優待の使い勝手」が高評価。
ポイント
- 毎年の優待実績が安定
- 株主番号が継続カウントされやすい
第4位 三菱商事(8058)
優待内容:自社グループ製品/食品ギフト
株価目安:約1,500円/1株
総合商社の代表格。
100株優待が基本ですが、1株でも株主通信や企業パンフが届く“準優待”的体験ができます。
株主として企業経営に触れる教材的価値も高いです。
ポイント
- 「株主通信」で投資学習に最適
- 世界経済のニュース理解が深まる
第5位 日本製粉(2001)
優待内容:自社製品(パスタ・小麦粉など)
株価目安:約6,900円/1株
家庭向け食品の優待が主婦層に大人気。
1株でも株主番号を維持しやすく、将来的に単元株化を目指すステップにも最適です。
ポイント
- 実用性の高い食品優待
- 自社商品ファンが多くSNSでも人気
第6位 Netyearグループ(3622)
優待内容:ECポイント(公式サイト割引)
株価目安:約500円/1株
デジタルマーケティング企業。
株価が非常に低いため、ワンコインで優待体験ができる“初心者の登竜門”。
ポイント
- 低資金でスタート可能
- 1株優待初心者におすすめ
第7位 永旺フィナンシャルサービス(8570)
優待内容:イオン商品券・割引特典
株価目安:約1,400円/1株
イオングループの金融子会社。
1株でも企業案内や優待関連資料が届き、系列店舗での特典を受けられる可能性があります。
ポイント
- イオン系列利用者にメリット大
- 株主カードで日常的に恩恵あり
第8位 PSコンストラクション(1871)
優待内容:QUOカード(500円)
株価目安:約1,800円/1株
建設業界ながら、株主との信頼関係を重視。
1株優待報告が多く、安定した実績でコスパが高い人気企業。
ポイント
- 端株でも優待対象になりやすい
- 長期保有で企業認知UP
第9位 トラスコ中山(9830)
優待内容:自社カタログ商品・工具セット
株価目安:約3,700円/1株
「モノづくり企業」の代表格。
優待で工具やDIY商品がもらえる点が特徴。
1株保有でも長期認定対象になりやすく、男性ファンも多い銘柄です。
ポイント
- 実用性が高くリピーター多数
- 家族で使える優待が人気
第10位 オリックス(8591)
優待内容:カタログギフト・レンタカー割引など
株価目安:約3,200円/1株
優待満足度ランキング常連。
1株優待は終了しましたが、「端株保有で長期保有認定」されるケースがあるため、将来の100株投資を見据えた“入口”として注目。
ポイント
- 長期認定狙いの“仕込み銘柄”
- 配当も高く総合利回りが優秀
【番外編】今後注目の1株優待候補
| 銘柄名 | 優待傾向 | 備考 |
|---|---|---|
| KDDI | カタログギフト | 長期保有で認定される傾向 |
| ANAホールディングス | 航空券割引券 | 端株長期で優待継続対象に含まれる場合あり |
| 三越伊勢丹HD | 買物割引カード | 継続保有重視の設計 |
| 花王 | 自社製品セット | 社員向け配布品から優待転用例あり |
主婦・初心者が選ぶなら「実用系」から始めよう
投資の目的が「お得」なら、最初の一歩は生活に直結する優待がベストです。
QUOカード・食品・商品券などは家計の節約にもつながり、心理的ハードルも低いです。
一方で、「体験型優待」や「株主カード系」は、投資を“生活の一部”として楽しみたい人に向いています。
💡ポイント
まずは3〜5社を1株ずつ試してみましょう。
優待が届いた体験が「次の1株」を買うモチベーションになります。
第4章 1株優待を確実にもらうための実践ステップと注意点

「1株買ってみたのに、優待が届かなかった…」
そんな声をよく耳にします。
実は、1株優待をもらうには“ちょっとしたコツ”があるのです。
この章では、初心者でも失敗せず確実に優待を受け取れるよう、実践ステップ+注意点を時系列で解説します。
ステップ1:証券会社を選ぶ
まずは「どの証券会社で買うか」が最重要ポイントです。
1株優待の成功率は、証券会社の名義管理方法によって決まります。
おすすめの証券会社
| 証券会社名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 名義が本人になる端株取引に対応 | 優待を確実に受け取りたい人 |
| マネックス証券 | 株主番号を継続しやすい設計 | 長期保有を狙う人 |
| auカブコム証券 | ミニ株サービス(プチ株)対応 | スマホ完結で始めたい人 |
| SMBC日興証券 | ネットと店頭の両対応 | 安定志向の初心者 |
💡ワンポイント
PayPay証券やLINE証券などは、名義が本人にならない「信託口」形式が多く、優待対象外になる場合があります。
「株主名簿に自分の名前が載る取引」であることを必ず確認しましょう。
ステップ2:企業の優待条件を確認する
次に、購入したい企業の最新のIR情報をチェックします。
公式サイトの「株主・投資家情報(IR)」ページに、以下のような記載があるかを確認しましょう。
- 優待制度の有無
- 対象株数(1株でも可か)
- 権利確定日
- 継続保有の有無
- 優待内容の詳細
もし「1株で優待対象」と明記されていない場合でも、“株主通信が届く企業”はチャンスです。
優待の前兆として、企業が株主への接点を重視している証拠です。
ステップ3:権利確定日に間に合わせて購入する
優待をもらうには、権利確定日の2営業日前までに株を保有していることが条件です。
これを「権利付最終日」と呼びます。
権利確定までの流れ(例)
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 3月26日 | 権利付最終日(この日までに購入) |
| 3月27日 | 権利落ち日(この日以降の購入は対象外) |
| 3月31日 | 権利確定日(名簿に記載) |
💡注意
1株購入後、株主名簿に反映されるまで数日かかる場合があります。
遅くとも権利確定日の10日前には購入しておくと安全です。
ステップ4:長期保有で「優待認定」を維持する
企業によっては、「継続保有○年以上」が条件になるケースがあります。
この場合、途中で売却すると優待資格がリセットされてしまいます。
そのため、
- 長期で保有し続ける
- 同じ証券口座で管理する
の2点を意識しましょう。
とくに「株主番号の維持」が重要です。
証券会社を変更すると番号が変わり、長期認定がリセットされることがあるため、長期狙いは口座を固定するのがおすすめです。
ステップ5:優待到着を確認しよう
優待が届くのは、権利確定から約2〜3カ月後が一般的です。
(例:3月末確定 → 6〜7月頃に到着)
届くものは、封筒・ハガキ・ゆうパックなど企業によって異なります。
内容が「株主通信+優待券」になっている場合も多く、最初は見逃さないように注意しましょう。
💡届かないときは?
- 権利確定日に名義が本人でなかった
- 住所変更が反映されていない
- 優待制度が変更・廃止された
このいずれかが原因であることが多いです。
企業のIR担当に連絡すれば確認できます。
よくある失敗パターンと回避法
| 失敗例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 優待が届かない | 名義が信託口扱い | SBI証券・マネックス証券など本人名義対応口座を使う |
| 権利日に間に合わなかった | 名簿反映遅れ | 10日前購入ルールを徹底 |
| 優待が突然終了 | 企業側の制度変更 | IRニュースを月1回チェック |
| 長期認定が消えた | 証券会社を変えた | 口座を固定・同一名義で保有 |
まとめ:準備8割、受け取り2割
1株優待を確実にもらうための最大のコツは、
「準備を怠らないこと」です。
- 名義を確認
- 企業IRを定期チェック
- 余裕をもって購入
この3つを守れば、ほぼ確実に優待が届きます。
優待が届く瞬間は、投資の喜びを実感できる特別な体験です。
最初の1株から、自分のお金が“企業を応援する力”に変わる──
それが1株優待の本質です。
第5章 主婦・初心者が1株優待で月1,000円得する実践ポートフォリオ

1株優待は、少額からでも生活を豊かにする“お得な資産づくり”の第一歩です。
この章では、主婦や投資初心者でも無理なく始められる実践的ポートフォリオを紹介します。
テーマは「家計の節約+楽しみながら投資体験」。
目標は、1株優待を活用して月1,000円分の価値を得ることです。
1. まずは目的を決めよう
1株優待を活用する上で重要なのは、「何を得たいか」を明確にすることです。
| 目的タイプ | こんな人におすすめ | 狙う優待ジャンル |
|---|---|---|
| 節約型 | 家計の出費を減らしたい | QUOカード・商品券 |
| 生活充実型 | 日用品や食品を楽しみたい | 食品・日用品優待 |
| 体験型 | 旅行・外食をお得にしたい | 施設券・飲食優待 |
| 教育型 | 投資を学びたい | IR通信・長期優待 |
自分のライフスタイルに合わせて目的を決めることで、
優待の“満足度”が一気に上がります。
2. 月1,000円を得る1株優待ポートフォリオ例
ここでは、実際に主婦が組みやすい構成を紹介します。
予算は1万円以内。リスクを抑えながら複数企業の優待を楽しめる内容です。
| 銘柄 | 優待内容 | 目安株価 | 想定価値 |
|---|---|---|---|
| 佳能電子(7739) | QUOカード500円 | 約2,700円 | 500円 |
| Netyearグループ(3622) | ECポイント | 約500円 | 300円 |
| 日本製粉(2001) | 食品詰め合わせ | 約6,900円 | 1,000円相当 |
| 永旺フィナンシャルサービス(8570) | イオン特典 | 約1,400円 | 200円 |
| 合計 | - | 約11,500円 | 月平均換算で約1,000円価値 |
わずか1万円程度の投資で、毎月1,000円相当の“価値還元”が得られるポートフォリオです。
食品・金券・ポイントがバランス良く組み合わされているため、
生活面でも実感を得やすい構成になっています。
3. 優待スケジュール管理のコツ
1株優待は、権利確定日がバラバラです。
スケジュールをうまく分散させることで、毎月なにかが届く喜びを作れます。
| 月 | 優待確定企業 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 3月 | 信越化学工業/日本製粉 | 製品カタログ・食品セット |
| 6月 | 佳能電子/PSコンストラクション | QUOカード |
| 9月 | 伊藤忠食品 | グルメギフト |
| 12月 | 永旺フィナンシャルサービス | 商品券・特典 |
💡ポイント
優待が届くタイミングをカレンダーに登録しておくと、モチベーションが続きます。
また、SNSや家計ノートに届いた優待を記録すると“自分の成長記録”にもなります。
4. 家計に活かす優待の使い方
優待を「おまけ」ではなく、「家計の一部」として活かすのが賢い使い方です。
- QUOカード系 → コンビニ・ドラッグストアで生活費節約
- 食品系優待 → 外食を減らして自炊の楽しみアップ
- 商品券系 → スーパー・ショッピングモールで実用的に消化
例えば、QUOカード500円分を毎月1枚でももらえれば、年間6,000円。
お米や日用品の優待と合わせると、年間1万円以上の節約効果になります。
5. 優待を「もらって終わり」にしない工夫
優待は「届いた瞬間がスタート」です。
届いたら以下の3ステップで活用しましょう。
- SNSでシェア
→ #株主優待 などのタグで投稿すると、情報交換ができる - 企業の株主通信を読む
→ 経営方針や新製品情報を理解して“応援力”を高める - 次に欲しい優待をリスト化
→ 優待を通して“自分に合った投資スタイル”が見えてくる
「楽しみながら学べる投資」が、1株優待の醍醐味です。
まとめ:少額から“家計に喜びを生む投資”を始めよう
1株優待は、お金を増やす投資というより、
お金を「楽しみに変える」投資です。
・1万円で始められる
・毎月なにか届くワクワク感
・家計を少しラクにする効果
この3つを体感できれば、投資へのハードルは一気に下がります。
大切なのは、小さく始めて続けること。
今日の1株が、あなたの家計を、未来を、少し豊かにします。
第6章 1株優待を長期で活かす“お金の育て方”戦略
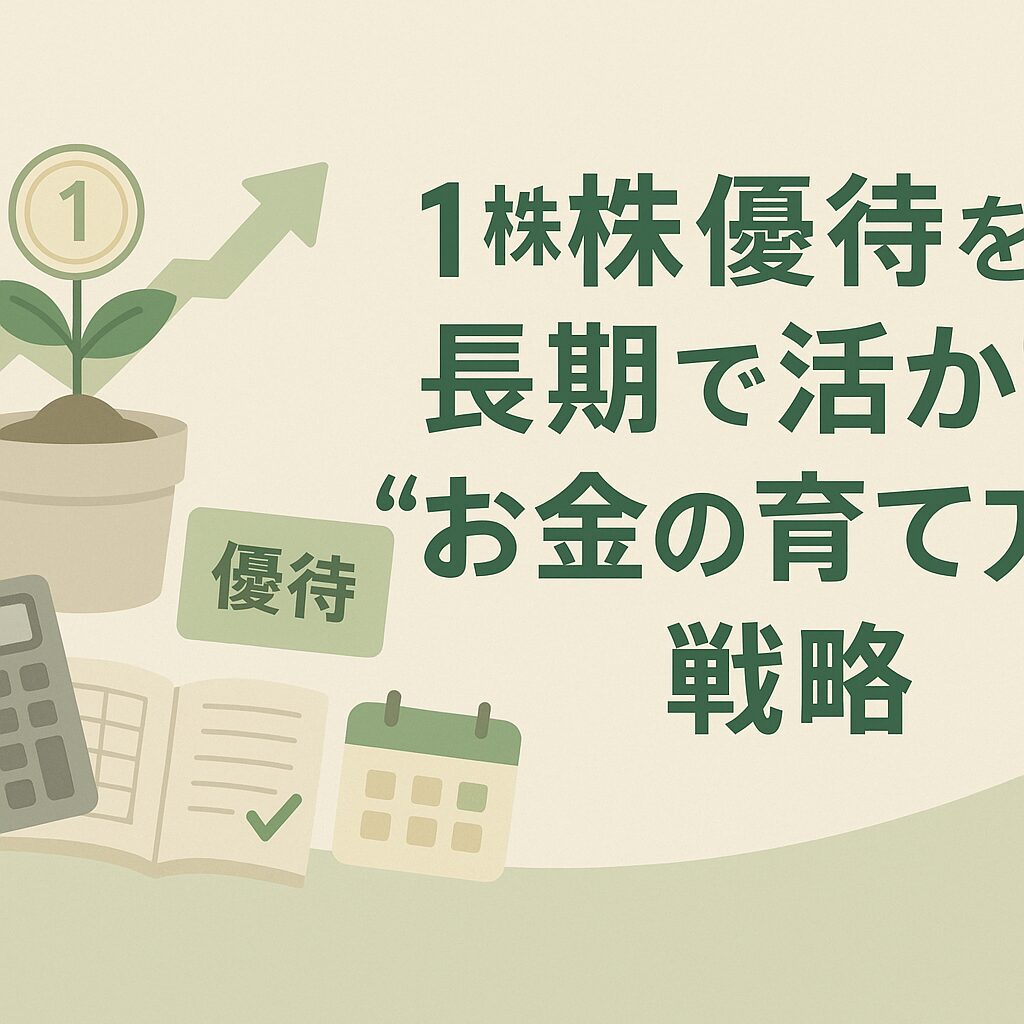
1株優待は、「少額で楽しむ投資」という入り口として最高の仕組みです。
しかし本当の価値は、“長期で続けることでお金を育てる基盤になる”ことにあります。
この章では、1株優待を軸に、家計・投資・学びをつなぐ“お金の育て方”を解説します。
1. 1株優待は「学びのための投資」と考える
1株投資の魅力は、利益ではなく「知ること・慣れること」にあります。
- 優待をもらう
- 株主通信を読む
- 株価の動きを観察する
このサイクルを繰り返すだけで、「投資がどう動くか」が自然に身につきます。
つまり、1株優待は金融リテラシーを“お金を使わずに学ぶ”実践教材なのです。
たとえば食品メーカー株を持てば、原材料価格の変動が株価に影響する理由が体感できます。
この経験こそ、将来の資産形成に最も役立つ“生きた勉強”です。
2. 長期保有は「ゆっくり効く複利」
1株でも長期で持てば、「株主番号の継続カウント」という形で実質的なリターンが増えていきます。
企業によっては、
- 1年以上保有 → 優待金額アップ
- 3年以上保有 → グレードアップ優待
といった制度があります。
これは“複利”の考え方と似ています。
お金を増やすスピードは遅くても、時間を味方につけることでリターンが育つのです。
💡POINT
長期保有は「増える投資」ではなく「積み重なる信頼」。
株主番号を継続するだけで、企業からの“ご褒美”が増えていくのが1株優待の魅力です。
3. 優待を「資産の一部」として捉える
優待は現金ではないものの、実質的な価値を持つ“現物資産”です。
例:
- QUOカード → 生活費の現金代替
- 商品券 → 家計の支出軽減
- 食品優待 → 物価上昇の防波堤
つまり、1株優待を受け取ることは、支出を抑える=資産を増やすことと同義です。
年間で数千円分の優待を得られれば、それだけで“貯金が減らない家計”になります。
💬 投資初心者のゴールは、「お金を増やす」ではなく「減らさない」こと。
優待はまさにその第一歩です。
4. 優待から“次の投資”へステップアップ
1株優待で経験を積んだら、次のステップは「複数株への分散投資」です。
成長ステップ例
| 段階 | 内容 | 目標 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 1株優待を5社保有 | 投資の流れを理解 |
| ステップ2 | お気に入り企業を10株保有 | 優待+配当を実感 |
| ステップ3 | 100株保有にチャレンジ | 本格的な資産形成へ |
このように、1株優待は“投資練習場”として最適。
損を恐れず試せる環境だからこそ、投資体質が自然に育つのです。
5. 優待廃止・改悪時の正しい判断法
優待投資のリスクのひとつが、「制度変更」です。
しかし、焦って売るのはおすすめしません。
判断の3ステップ
- IRで企業の意図を確認
→ 経営再編やコスト削減が理由かを判断。 - 配当・業績の推移をチェック
→ 優待廃止でも増配なら、保有価値あり。 - 株主通信で企業姿勢を読む
→ 長期的な株主還元意識があれば継続もあり。
感情的に手放すより、「数字と姿勢」で見極めるのが上級者の判断です。
6. 1株優待を「家族投資」に変える
1株投資は、家族で楽しめる投資教育にも最適です。
- 子どもに1株買って「株主とは何か」を教える
- 夫婦で優待を共有して“家計のご褒美化”
- 親世代と一緒に長期保有を楽しむ
特に家族で優待をシェアすると、
「投資=難しい」から「投資=うれしい」に変わります。
これが、未来の資産形成リテラシーを育てる最強の方法です。
まとめ:1株優待は“お金の基礎体力”を育てる投資
1株優待は、少額で始められるだけでなく、
長期的に見れば“お金の筋トレ”のような存在です。
- 続けることでリテラシーが上がる
- 家計の支出が減る
- 投資を“習慣”にできる
これが、優待投資の本質です。
🌱 今日の1株が、10年後の安心を育てる。
「楽しみながら増やす」ことこそ、これからの時代のお金の教養です。
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
>おすすめ新NISAの証券口座が知りたい人は、こちらからご覧ください
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。


