※本ページはプロモーションが含まれています。
株価急落の概要|味の素がストップ安に至った背景

2025年11月7日、味の素(証券コード2802)の株価が東京証券取引所でストップ安(前日比‐700円、‐16.19%)となり、終値3,623円で取引を終えました。
出来高は通常の約3倍にあたる1,117万株超と急増し、個人投資家・機関投資家ともに大幅な売り注文が殺到しました。
この日、味の素は値幅制限の下限いっぱいまで売られ、「売り気配のまま取引終了」という異例の展開を見せました。
市場全体が落ち着きを見せるなか、同社株だけが突出して下落した背景には、決算内容への深い失望感がありました。
6日発表の決算が市場予想を下回る
株価急落の直接的な引き金となったのは、前日の2026年3月期第2四半期決算(2025年4〜9月期)の発表です。
味の素はこの期間で事業利益868億円(前年同期比‐0.2%)と、ほぼ横ばいながらも市場予想を下回る結果を示しました。
特に注目されたのは、第2四半期(7〜9月)単体で最終利益が28%減少した点です。
第1四半期では9.7%増益と好調を維持していたため、わずか3か月での急減速は投資家に強い衝撃を与えました。
主力事業の減速が顕著に
決算資料によると、減速の主因は調味料・冷凍食品事業の伸び悩みにあります。
価格改定による一時的な売上上昇の後、国内外での消費鈍化と競争激化が影響。
家庭用調味料や冷凍食品が想定以上に伸びず、海外市場では為替の影響も加わりました。
一方で、半導体関連素材を扱う電子材料事業は堅調だったものの、主力の食品セグメントの不振を補い切れず、全体業績を押し下げる結果となりました。
投資家心理を冷やした「通期進捗率48%」
同社は通期見通しとして事業利益1,800億円(前期比+13%)を据え置いています。
しかし、上半期終了時点での進捗率はわずか48%にとどまり、
「このペースでは目標未達の可能性が高い」との見方が市場で広がりました。
特に、第3〜4四半期での大幅な回復を前提とした通期計画に対し、投資家は現実性を疑問視。
結果として、決算発表直後の時間外取引から売りが先行し、翌日の取引開始と同時にストップ安水準まで一気に売られる展開となりました。
市場の反応とアナリストの見方
市場関係者の間では、
「食品大手の中でも味の素は業績安定株と見られていただけに、今回の下落は心理的ショックが大きい」
との声が多く聞かれます。
また、アナリストの間でも「第2四半期での減益転換は一時的か、構造的かを見極める必要がある」との慎重な意見が目立ちました。
つまり、投資家は単なる短期業績のブレではなく、味の素の成長モデルそのものに疑問を抱き始めたということです。
今回のストップ安が意味するもの
今回の株価急落は、単なる一企業の決算ショックにとどまりません。
「食品業界全体における価格転嫁の限界」と「消費者の節約志向の強まり」を象徴する出来事でもあります。
特に味の素は長年にわたり「安定・堅実」な銘柄として評価されてきたため、
今回のストップ安は“安全株”への信頼を揺るがす警鐘となりました。
次章:決算内容を詳細チェック|上半期実績と通期予想のギャップ
──ここからは、味の素の決算内容を具体的な数字とともに分解し、どこで誤算が生じたのかを明らかにします。
決算内容を詳細チェック|上半期実績と通期予想のギャップ
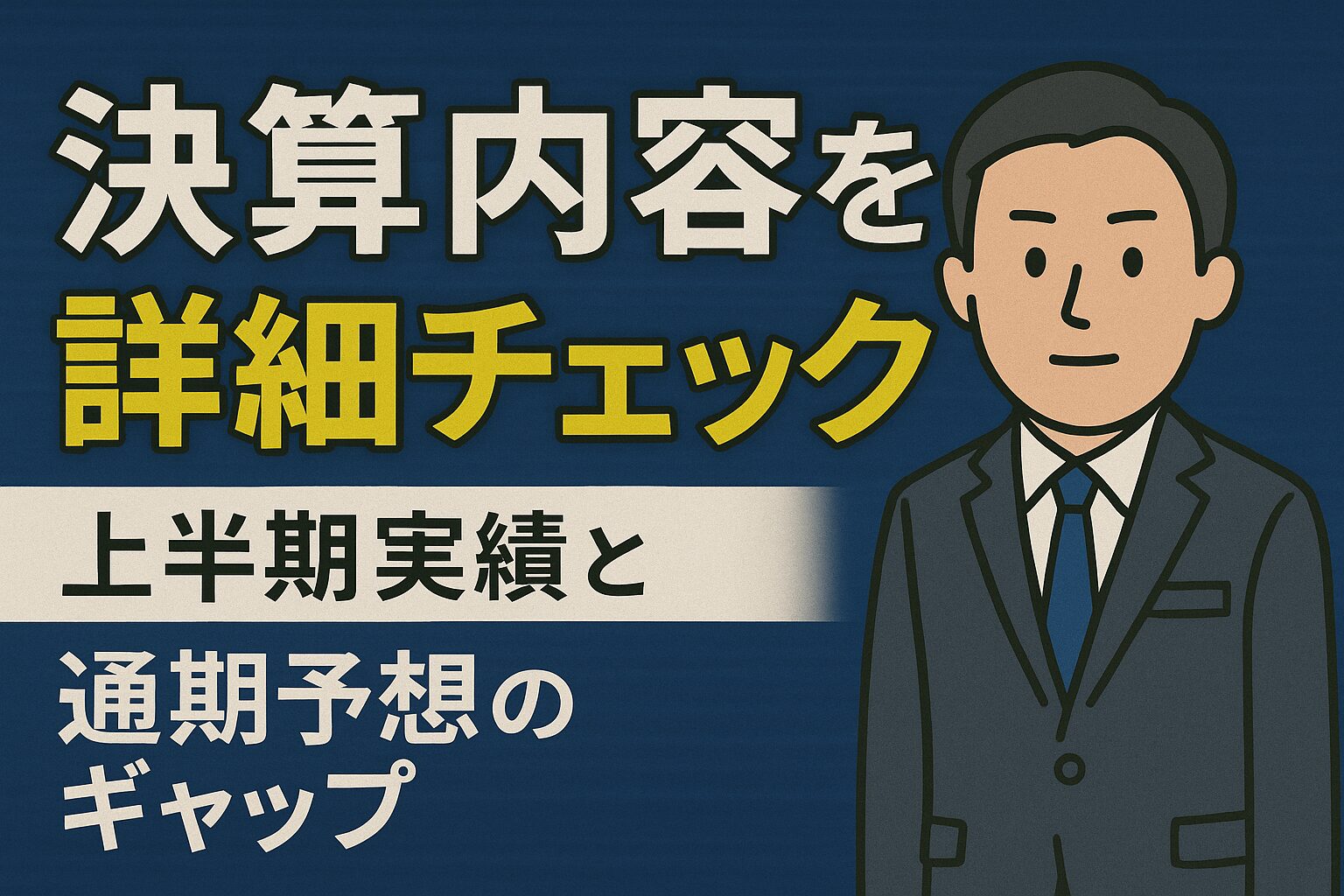
味の素の株価急落を正確に理解するには、2026年3月期第2四半期(2025年4〜9月)の決算内容を冷静に分析する必要があります。
一見、売上・利益ともに大幅な悪化ではないように見えますが、実際には市場の期待との乖離が極めて大きいものでした。
上半期業績の概要
味の素の上半期業績は次の通りです。
- 売上高:6,084億円(前年同期比 +1.1%)
- 事業利益:868億円(前年同期比 -0.2%)
- 営業利益率:14.3%(前年同期比 -0.2pt)
数値だけを見ると「横ばい」に見えますが、これは第1四半期の貯金で成り立っているものです。
実際、第2四半期単体では営業利益が前年同期比28%減と、業績が明確に失速しています。
売上横ばいでも収益率が悪化
今回の決算で特に注目すべき点は、売上がほぼ維持されているにもかかわらず、利益率が低下していることです。
その背景には、次の2つの要因が挙げられます。
- 値上げ後の販売鈍化
- 2024年度に実施した価格改定で一時的に利益率が改善したものの、消費者の節約志向が強まり、家庭用商品で販売数量が減少。
- 「味の素®」「Cook Do®」などの主力ブランドが想定よりも伸び悩みました。
- 広告宣伝・人件費の増加
- 海外ブランドの認知拡大やマーケティング投資を強化した結果、販管費が上昇。
- その費用が営業利益を圧迫しました。
特に、国内市場の冷凍食品カテゴリーは競争が激化しており、値下げキャンペーンや販促コストの増大が収益を削る結果となっています。
セグメント別の明暗
味の素の事業構成は大きく「食品事業」と「アミノサイエンス事業」に分かれます。
今回の決算では、この2部門で明確なコントラストが生まれました。
| 事業区分 | 売上高(前年比) | 主な要因 |
|---|---|---|
| 食品事業 | -1.8% | 調味料・冷凍食品の販売鈍化、国内市場の競争激化 |
| アミノサイエンス事業 | +9.5% | 電子材料・バイオ医薬品関連の堅調な需要 |
| その他 | +2.0% | ヘルスケア製品やペットフードの安定推移 |
電子材料や医薬品素材などを扱う「アミノサイエンス事業」は、世界的な半導体・医薬品需要の回復を受けて好調でした。
しかし、全社の7割を占める食品事業が足を引っ張ったことで、全体の利益成長は止まりました。
通期予想との乖離
会社側は、通期の事業利益見通しを1,800億円(前期比+13.0%)と据え置いています。
しかし、上半期終了時点での進捗率は48.2%にとどまり、計画達成には残り半年で約930億円の事業利益を積み上げる必要があります。
この数字を実現するには、下期で前年同期比30%超の増益が必要となり、極めて高いハードルです。
そのため、市場では「目標を据え置いたのは強気すぎる」との見方が広がりました。
投資家が注目した「第2四半期の落差」
第1四半期は増益基調、第2四半期は大幅減益。
この「落差」が、今回の株価急落の核心です。
企業の成長トレンドを見るうえで、投資家は勢いの継続性を重視します。
したがって、「勢いが止まった」と判断された瞬間、失望売りが広がったのです。
ポイントまとめ
- 上半期の事業利益は前年並みだが、第2四半期で急失速
- 主力の食品事業が低迷し、アミノサイエンスの好調を打ち消した
- 通期進捗率48%で、計画達成には高いハードル
- 市場が注目したのは「勢いの鈍化」
- 「据え置き予想」がむしろ失望要因に
次章:セグメント別に見る弱点と強み|調味料・冷凍食品、電子材料など
──ここでは、味の素の事業ごとの収益構造を掘り下げ、どの分野がブレーキとなり、どこに成長余地があるのかを明確にします。
セグメント別に見る弱点と強み|調味料・冷凍食品、電子材料など
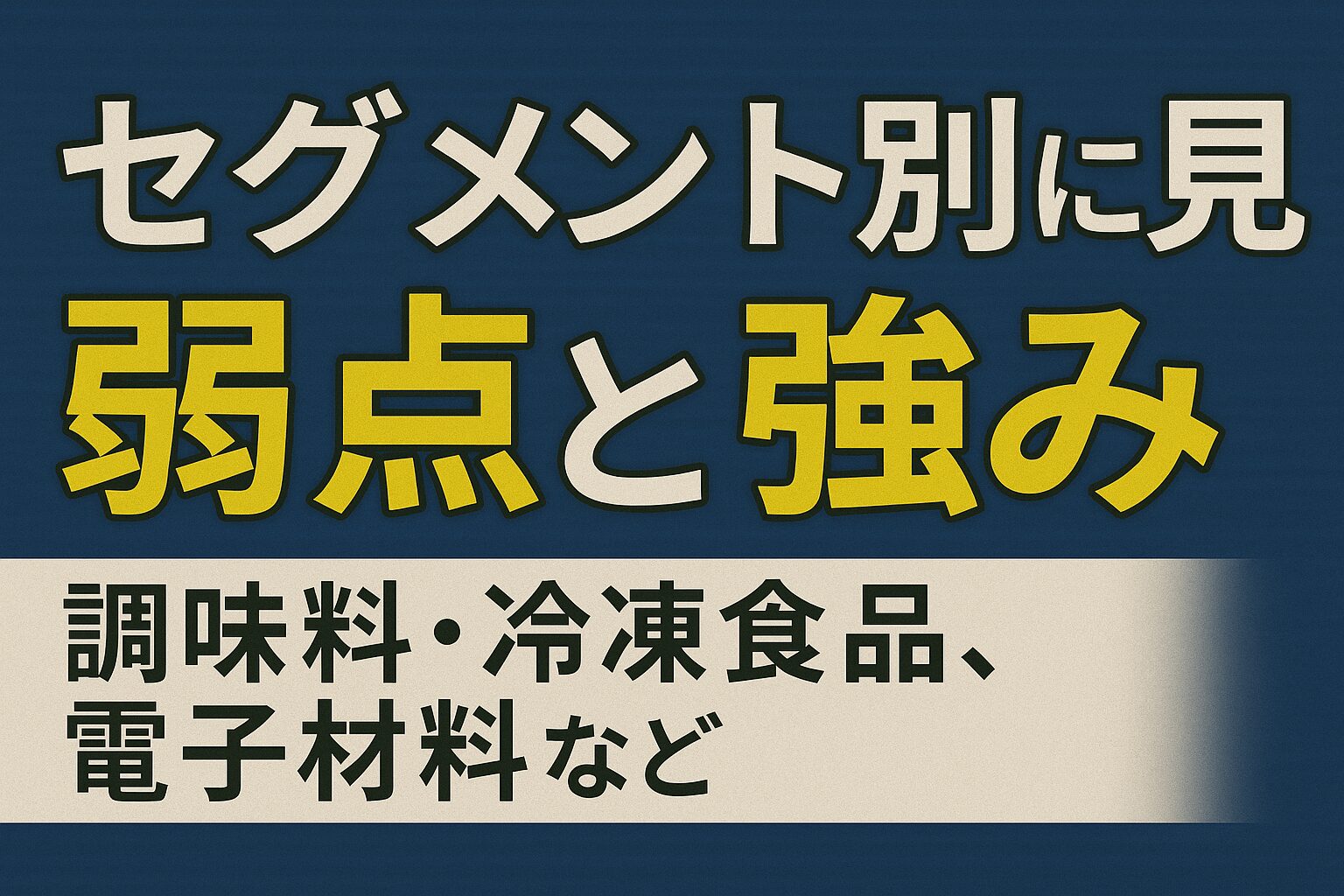
味の素の事業構成は、大きく「食品事業」と「アミノサイエンス事業」の2本柱で成り立っています。
今回のストップ安の背景には、この2つの柱のバランスが大きく崩れたという構造的問題がありました。
以下では、それぞれのセグメントを詳しく見ていきます。
調味料・食品事業の現状|“ブランド頼み”の限界が露呈
味の素の中核である調味料・食品部門は、売上全体の約7割を占めます。
しかし、今回の決算ではこの主力分野が最も業績を押し下げました。
原因は、値上げ後の反動減と需要停滞です。
2024年に原材料高を受けて複数商品を値上げしましたが、消費者の節約志向が強まり、売上数量が伸び悩みました。
特に「味の素®」「Cook Do®」「冷凍ギョーザ」などの主力商品が、国内市場での販売数量を減らしています。
さらに、アジア新興国市場でも競合ブランドが急成長しており、これまで優位だった東南アジアでのシェアがじわじわと低下。
結果として、食品セグメントの利益率は前年同期から約1ポイント低下し、ブランドパワー頼みのビジネスモデルに陰りが見えた形です。
冷凍食品事業|コスト構造の歪みが浮き彫りに
冷凍食品分野も業績悪化の一因となりました。
生産コスト上昇に加え、物流費や人件費が重くのしかかり、販促活動の強化で利益率がさらに低下しています。
とくに国内では、競合他社が値下げキャンペーンや新商品攻勢を強めており、
「数量を維持するために利益を削る」構造が続いています。
一方で、北米・欧州市場では新商品投入が進んでいるものの、現時点ではまだ業績貢献は限定的です。
中期的には海外比率を高めることが課題となっています。
アミノサイエンス事業|唯一の“光明”
業績全体が苦戦する中で、唯一明るい兆しを見せたのがアミノサイエンス事業です。
電子材料、医薬品素材、バイオ関連などを扱うこの分野は、前年同期比で約9%の増収。
特に半導体製造用薬品やアミノ酸誘導体など、高付加価値素材の需要増が業績を支えました。
この分野は利益率も高く、企業としての成長ドライバーになりつつあります。
味の素は今後、食品分野から得たキャッシュをこのアミノサイエンス事業に再投資する方針を示しており、
中長期的には「素材・サイエンス企業」への転換が進む可能性があります。
地域別の収益動向
| 地域 | 売上傾向 | コメント |
|---|---|---|
| 日本 | 微減 | 家庭用調味料・冷凍食品の販売数量が減少 |
| アジア(タイ・インドネシアなど) | 横ばい | ローカルブランドの台頭、価格競争が激化 |
| 北米 | 増加 | 冷凍食品や電子材料が好調、収益性改善傾向 |
| 欧州 | 横ばい | 為替の影響と景気後退懸念が重石 |
日本市場の成熟化に対し、海外市場は成長ポテンシャルを持ちながらも、為替・景気・競合の壁が厚い状況です。
セグメント別課題まとめ
- 食品・調味料事業:価格改定後の販売失速。ブランド競争が激化。
- 冷凍食品事業:物流・人件費の上昇で採算が悪化。
- アミノサイエンス事業:電子材料や医薬素材が堅調。利益率を支える主力へ。
- 地域別では日本・アジアが停滞、欧米が伸び代。
今後の焦点
投資家の関心は、味の素がどのように食品事業の収益性を立て直すかに集まっています。
一方で、アミノサイエンス事業が中期的に企業の柱に成長すれば、
「調味料メーカーからバイオ・素材企業への変革」が現実味を帯びるでしょう。
次章:投資家視点のリスク要因|進捗率・市場期待・外部環境
──ここでは、味の素株が今後直面する可能性のある3つのリスク(業績進捗・期待剥落・外部要因)を専門家の視点で分析します。
投資家視点のリスク要因|進捗率・市場期待・外部環境
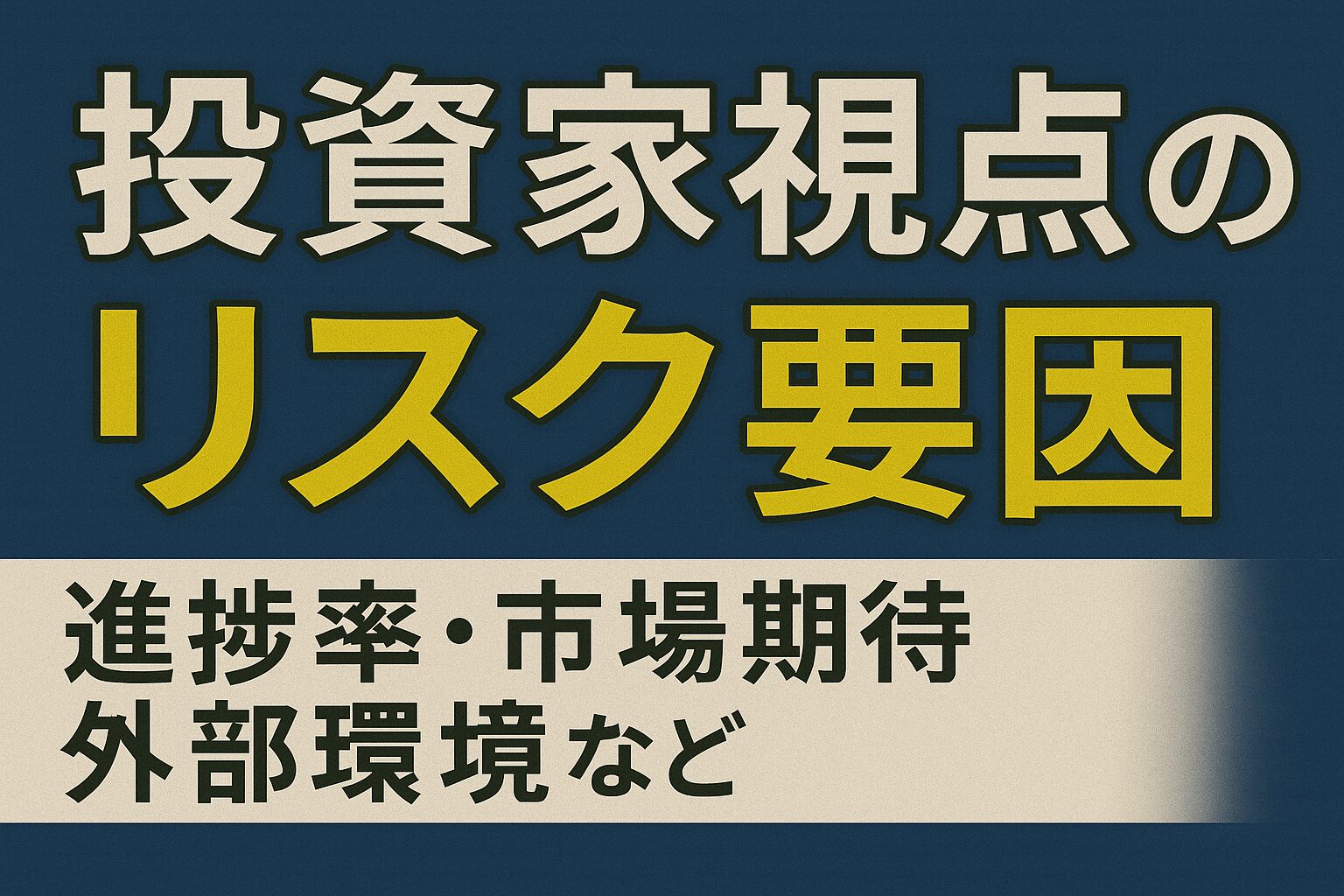
味の素の株価がストップ安まで売り込まれた背景には、単なる決算の悪化だけでなく、投資家心理を冷やす3つの構造的リスクが存在します。
ここでは、プロ投資家や機関投資家が注視する「業績進捗リスク」「市場期待の剥落」「外部環境リスク」の3つを整理して解説します。
① 業績進捗リスク|通期目標との乖離が拡大
味の素の通期事業利益目標は1,800億円(前期比+13.0%)ですが、上半期終了時点での進捗率は48.2%にとどまっています。
これは、通常なら“順調ペース”とされる50%を下回る水準であり、下期での挽回が必須です。
しかし、下期に計画どおりの利益を積み上げるには、
前年同期比で30%以上の増益を達成しなければならず、現実的にはハードルが高い状況です。
とくに食品事業の回復が見通せない現状では、「通期未達 → 下方修正 → 信用低下」という連鎖懸念が市場に広がっています。
決算後も目標を据え置いたことが、むしろ“強気すぎる姿勢”と受け止められた点が株価急落の一因です。
② 市場期待の剥落|“安定成長株”から“警戒銘柄”へ
味の素はこれまで「安定的な収益を生み出すディフェンシブ株」として個人投資家・機関投資家から支持を集めてきました。
しかし今回のストップ安によって、その信頼が揺らぎ始めています。
投資家が抱いていた期待と実際の数字とのギャップは以下の通りです。
| 項目 | 市場の期待 | 実際の結果 |
|---|---|---|
| 収益の安定性 | 増収増益基調の維持 | 下期に向けて減速懸念 |
| 価格転嫁効果 | 継続的に利益率改善 | 値上げ後に販売鈍化 |
| 通期見通し | 計画超過の上方修正期待 | 据え置きで失望売り |
市場は「堅実に利益を積み上げる企業」というイメージを持っていたため、今回の結果はブランドの信頼低下につながりました。
特に長期投資家にとって、「味の素=安全資産」という構図が崩れたことが心理的に大きな打撃となりました。
③ 外部環境リスク|コスト高・為替・消費動向の三重苦
業績に直接影響を与える外部要因も無視できません。
2025年下期以降、味の素が直面する主な外部リスクは以下の3つです。
- 原材料・エネルギー価格の再上昇
原油価格の上昇や物流費の高止まりが続いており、食品製造コストを押し上げています。 - 為替変動の影響
円安は海外利益の押し上げ要因となる一方、原材料輸入コストを増やす二面性があります。
現状では「輸入コスト増>為替差益」となっており、マージンを圧迫しています。 - 消費マインドの冷え込み
物価上昇により国内消費者の節約志向が強まり、プレミアム商品や高価格帯商品の販売が鈍化しています。
これが、味の素の主力カテゴリである家庭用調味料・冷凍食品の売上を直撃しています。
アナリストが警戒する“業績モメンタムの鈍化”
証券各社の分析では、味の素の株価下落を「一時的」ではなく「業績モメンタムの減速」と位置づける声が多くなっています。
つまり、単なる四半期のブレではなく、中期的な成長トレンドの変化と捉えられているのです。
一部では、「アミノサイエンス事業の好調をもってしても、食品事業の減速を補いきれない」との評価もあり、
今後、経営陣がどのような再成長戦略を打ち出すかが試される局面に入っています。
リスクまとめ
- 通期進捗率48%で、下期は30%超の増益が必要
- 据え置き予想が市場の“強気期待”を裏切る結果に
- 原材料高・為替変動・消費冷え込みの三重苦
- 安定成長株としての信頼が揺らぐ
- 中期的な“成長モメンタムの鈍化”が最大の懸念
次章:今後の見通しと注目ポイント|反発余地・配当・自社株買い
──ここでは、味の素の株価が今後どう動くのか、専門家の視点から「反発要因」と「注意点」を整理します。
今後の見通しと注目ポイント|味の素株式会社ストップ安後の戦略と株価の行方
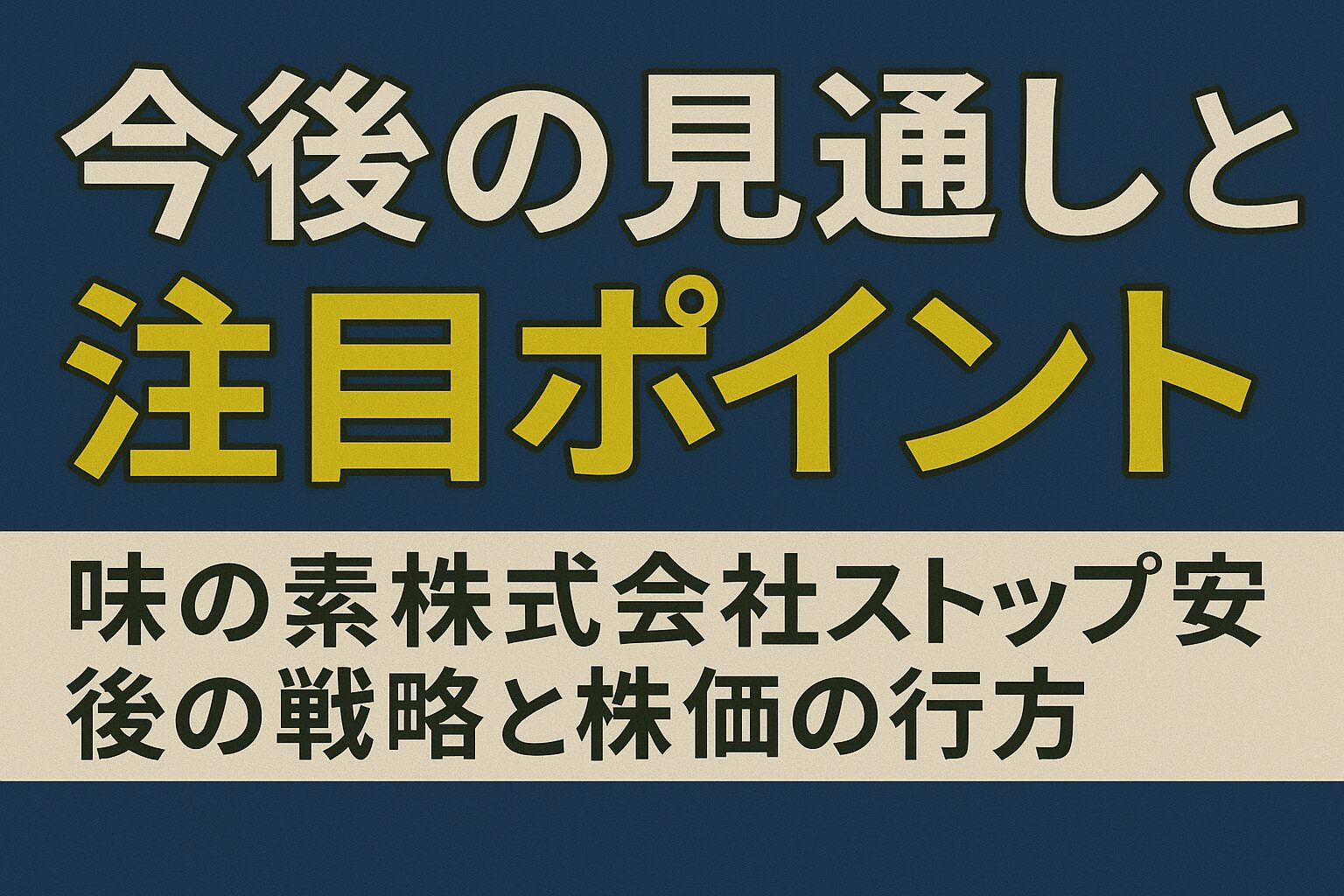
株価がストップ安に至った味の素株式会社(証券コード:2802)ですが、今後の展開には明確な注目ポイントがあります。
まずは反発余地・株主還元・中期戦略という観点から可能性を整理し、その上で投資家が注意すべき点を挙げます。
反発の余地となる3つの要因
- 中期経営計画と成長戦略の存在
味の素は「2030年に向けた成長モデル変革(BMX)」を掲げ、提供価値起点に事業モデルをシフトする方向性を示しています。
これは「食品+素材」から「高収益・高成長の4成長領域」へ移行する大きな戦略転換です。戦略が浸透すれば、株価回復の根拠となりえます。 - 株主還元と期待される増配・自社株買い
最新の資料では、売上・事業利益の回復を前提に、株主への還元を拡充する方針が明示されています。
例えば純利益見通しの改善が確認できれば、「安定配当+成長期待」の組み合わせが株価を下支えする可能性があります。 - 成長分野の実績が出始めている
食品・冷凍・調味料事業が苦戦する中でも、アミノサイエンスなど素材・電子材料領域において実績が出てきており、これが「次の成長エンジン」として期待されます。
この側面が市場に理解されれば、評価改善→株価上昇という流れも想定できます。
投資家が今後注視すべき具体的指標
- 通期業績の進捗率:上半期で48%にとどまったことが株価急落を招いた背景です。挽回のペースを確認する必要があります。
- 予想の上方修正の有無:据え置き発表が失望売りの要因となったため、次の決算での予想変化が鍵です。
- 増配・自社株買いの発表:株主還元の強化が明確に打ち出されれば、マインド改善に繋がります。
- 新規成長領域(海外調味料・冷凍食品・医薬・電子材料等)の規模拡大:特に、海外市場での数量拡大や利益率改善が出てくると「再成長転機」の合図となります。
- 為替・原材料コスト・消費者マインドなど外部環境の変化:これらは収益を左右する要因となるため、業績発表以外のモニタリングも重要です。
注意すべきリスクと逆シナリオ
- 食品・調味料分野の回復が遅延すると、株価が低迷したまま長期化する可能性があります。
- 下期で過度な利益改善を前提にしているため、想定未達の場合には再び下方修正リスクがあります。
- 外部環境(原材料高・物流費・円安・消費低迷等)が悪化すると、プラスの成長トレンドを打ち消すおそれがあります。
- 成長戦略の実行(特に海外展開・素材分野拡大)が時間を要するケースでは、期待先行型の株価上昇も反落リスクに晒されます。
総括:今が買いのタイミングか?
ストップ安に至ったこと自体はネガティブですが、株価低迷が一定のリスク織込みを進めた今、「反発のきっかけ」が出れば評価回復の余地が十分にあります。
戦略が明確で株主還元が意識されている点を踏まえると、中期保有を想定した投資機会として検討可能です。
ただし、「回復までの期間・収益の裏付け」を慎重に確認する姿勢が必要です。
投資家が取るべきアクション|初心者・中級者向けの対応策
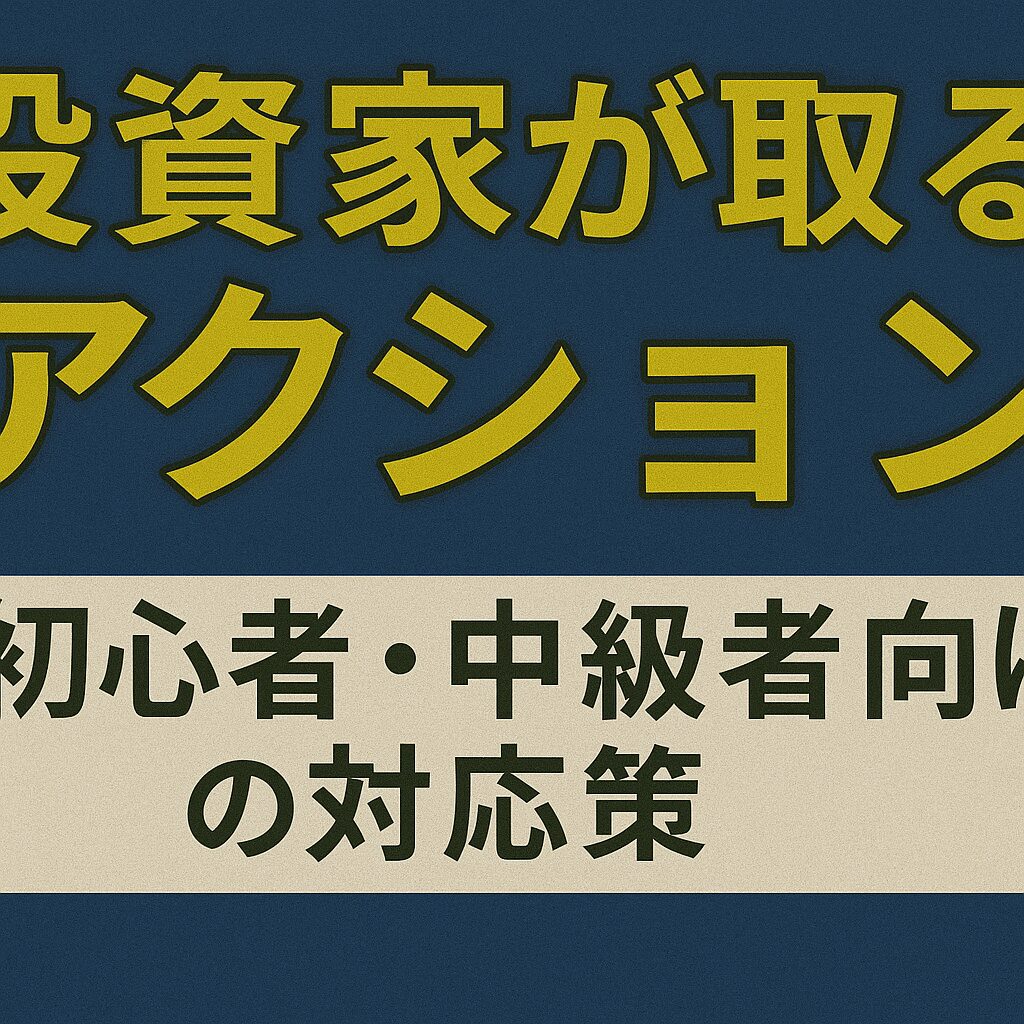
味の素の株価がストップ安にまで下落したことで、多くの投資家が「今後どうすべきか」と迷っています。
しかし、短期的な混乱の中でも冷静に戦略を立てることが重要です。
ここでは、投資スタイル別に「取るべき行動」を整理し、損失を抑えつつ次のチャンスを掴むための実践的アドバイスを紹介します。
初心者投資家のアクションプラン
① 慌てて売らない
ストップ安直後は出来高が急増し、投げ売りが相次ぐため、株価が一時的に「実力以下」に落ち込むことがあります。
焦って売却するよりも、数営業日〜1週間ほど様子を見て、需給が落ち着くのを待つことが鉄則です。
② 企業の根本的価値を再確認
味の素は依然として世界的な食品・素材メーカーです。
短期的に業績が失速しても、長期的に見ればブランド力・研究開発力・海外基盤は強固です。
「短期ショックか構造的問題か」を区別し、長期保有の視点を取り戻すことが重要です。
③ 平均取得単価を下げるチャンスを探る
業績が底打ちしたサイン(下方修正発表や第3四半期での改善傾向など)が見えた時点で、
少額でナンピン買いを行う戦略も有効です。
ただし、資金管理を徹底し「分散購入」「中長期目線」を前提に行いましょう。
中級〜上級投資家のアクションプラン
① 業績モニタリングを強化する
今後の焦点は、下期(10〜3月)でどこまで利益を積み上げられるかです。
- 通期利益進捗率
- 食品事業の回復傾向
- アミノサイエンス事業の成長率
これら3点の指標を定点観測し、計画比の進捗率が50%を超えた時点で再評価するのが有効です。
② 配当利回り・自社株買いに注目
味の素は株主還元を重視する企業であり、過去にも株価下落局面で自社株買い・増配を実施しています。
株価が下がったタイミングでこれらの施策が発表されれば、反発トリガーになる可能性が高いです。
③ テクニカル的視点でのリバウンド狙い
ストップ安後の反発局面では、短期的な買い戻しが入りやすく、数日〜1週間で5〜10%戻すことがあります。
ただしこれは「短期リバウンド」であり、根本的な業績回復を確認するまではあくまで短期トレードに限定するべきです。
注意すべきポイント
- 通期未達・下方修正リスクが依然残る
- 消費環境・為替・原材料など外部要因が不透明
- 決算説明会やIR発表内容を必ず確認してから判断
短期的な反発を狙うよりも、「業績回復シグナルが出てから本格参入」する方が安全です。
一度ストップ安を経験した銘柄は、信用残や需給が崩れている可能性があるため、
慎重なポジション管理を徹底しましょう。
長期的な投資判断の軸
| 投資判断の観点 | 着目ポイント | 判断基準 |
|---|---|---|
| ファンダメンタル | アミノサイエンス事業の成長率 | 2桁成長を維持できるか |
| 収益体質 | 食品事業の利益率回復 | 原材料高・販管費圧力に対応できるか |
| 経営戦略 | 「BMX」中期計画の進展度 | 構造改革が実行フェーズに入るか |
| 株主還元 | 自社株買い・増配の有無 | 下落時に還元姿勢を示すか |
これらの条件がそろえば、株価は自然と中長期的に回復します。
焦らず、「数字で確認してから投資」が王道です。
まとめ
- 初心者は「売り焦らず・再評価のタイミングを待つ」
- 中級者は「業績進捗・還元策・テクニカル反発」を観察
- 下落局面はリスクであると同時に割安で拾える好機にもなり得る
味の素は依然としてグローバル競争力を持つ優良企業です。
一時的なストップ安に動揺せず、長期的な視点で企業価値を見極める姿勢が、結果的に最も大きなリターンを生み出す可能性があります。
次章:要点まとめ|味の素ストップ安の教訓と次のステップ
──最後に、今回の急落から得られる投資上の学びと、次に向けての戦略を総括します。
要点まとめ|味の素ストップ安の教訓と次のステップ

2025年11月7日のストップ安は、味の素にとって単なる一日の値動きではなく、投資家・企業双方にとっての重要な転換点でした。
ここでは、今回の出来事から得られる教訓と、今後の行動指針を整理していきます。
今回のストップ安が示した3つの教訓
①「安定株」でも油断は禁物
味の素は長年、食品セクターの中で「守りの銘柄」として評価されてきました。
しかし今回のように、一見堅実な企業でも業績進捗の遅れや市場の期待外れで急落することが証明されました。
投資家は「ディフェンシブ株=安全」という思い込みを改める必要があります。
② 市場は“数字の勢い”を重視する
今回、売上が横ばいでも「第2四半期の減益」「通期進捗率48%」という数字が投資家心理を冷やしました。
市場は過去の実績よりも「今と未来の成長トレンド」を評価します。
つまり、数字の“勢い”が止まった瞬間、株価も止まるということです。
③ 中期戦略とIR発信の重要性
企業側にとっての教訓は、投資家に「なぜ失速したのか」「次にどう回復するのか」を明確に伝えること。
とくに味の素のように多角的事業を持つ企業では、成長ドライバーの説明責任が株価維持の鍵となります。
投資家にとっての行動指針
- 短期的なパニックに巻き込まれないこと
→ ストップ安直後の過剰反応は一時的な需給崩れにすぎないケースが多いです。 - 業績と中期戦略の「整合性」を確認すること
→ 通期目標が据え置かれた理由や、下期での挽回策をIR資料で確認しましょう。 - 数字で“底打ち”を確認してから再参入すること
→ 決算や四半期報告で営業利益・事業利益が反転したタイミングを狙うのが理想です。 - 株主還元に注目すること
→ 自社株買いや増配の発表は、信頼回復の合図となり得ます。
味の素に期待できる中期的展望
今後の焦点は、食品事業の再成長とアミノサイエンス事業の拡大です。
調味料や冷凍食品の収益性を改善しながら、バイオ・素材領域での競争優位を確立できれば、
味の素は「食品メーカーから総合ライフサイエンス企業」へ進化する可能性を秘めています。
この変革が進めば、2025年のストップ安は“再成長の序章”として語られることになるでしょう。
最後に:投資家が持つべき視点
株式投資で最も重要なのは、短期の値動きよりも企業の本質的価値を見抜く力です。
味の素のような老舗企業でも、事業ポートフォリオの再構築や市場環境の変化に対応できるかが問われています。
今回の急落は、投資家にとって「リスク管理とチャンス発見の両面を磨く」貴重な機会です。
✅ まとめポイント
- 味の素ストップ安は「安定株への過信」を見直すきっかけ
- 業績進捗率・成長モメンタムの停滞が市場を失望させた
- 反発の鍵は「下期業績の回復」と「成長事業の可視化」
- 株主還元強化とIR発信で信頼回復の余地あり
- 長期的にはアミノサイエンス事業が株価再評価の軸になる
この出来事を一時的なショックとして終わらせるのか、それとも将来の成長転換点とするのか──。
答えは、企業の実行力と投資家の冷静な判断力にかかっています。
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

