はじめに

AI画像生成技術が一般にも普及した現在、誰でも簡単に「プロのようなイラスト」を作成できる時代になりました。
中でも人気なのが、スタジオジブリ作品を彷彿とさせる“ジブリ風”のイラストです。
ノスタルジックで温かみのある作風は、多くの人の心をつかみ、SNSでも話題となっています。
しかし、その一方で著作権の問題が浮上しています。
特に、AIで生成されたジブリ風イラストが「ジブリ作品に似すぎているのでは?」「法的に問題ないのか?」という声もあり、利用には注意が必要です。
この記事では、AIでジブリ風画像を生成する際のリスクや著作権との関係、トラブルを避けるための実践的なアドバイスをわかりやすく解説していきます。
第1章 AIでジブリ風画像を生成するとは
AI画像生成ツールの進化により、「ジブリ風」のイラストを自動的に描かせることが可能になっています。
代表的なツールには以下のようなものがあります。
- Stable Diffusion
- Midjourney
- DALL·E
- Leonardo AI
これらのツールでは、プロンプトと呼ばれる「指示文」を入力することで、任意のスタイルで画像を出力できます。
たとえば、「Studio Ghibli style」「Ghibli-style scenery」「ジブリ風の田舎の風景」と入力すると、それっぽい画像が生成されます。
生成される画像の中には、ジブリ作品のキャラクターは登場しないものの、「トトロ」や「千と千尋の神隠し」に似た雰囲気を持つ風景や人物が登場する場合もあります。こうした作風は、SNSでも「ジブリっぽくてかわいい」と話題になっています。
ただし、この「ジブリ風」というスタイルが、著作権的に問題がないのかどうかについては、しっかりと理解しておく必要があります。
第2章 著作権法における「スタイル」の扱い

AIでジブリ風イラストを生成する際に最も気になるのが「著作権侵害ではないか?」という点です。
この問題を理解するためには、まず著作権法における「保護される対象」と「保護されない対象」を明確に区別する必要があります。
著作権が保護するのは“具体的な表現”
著作権法では、保護されるのは具体的な創作物、つまり「特定のキャラクターのデザイン」や「物語の展開」「作画の構成」といった、“一意に識別できる表現”です。たとえば、
- トトロの形状や表情
- ハクや千尋のキャラクターデザイン
- 油屋の外観や内部構造
といったものはすべて著作権の対象となります。
これらをAIで生成し、それと容易に認識できる形で公開・使用した場合、著作権侵害と判断されるリスクが非常に高いです。
スタイルや世界観は原則として保護対象外
一方で、著作権法では「作風」や「アイデア」は保護の対象ではありません。
つまり、「ジブリのようなやわらかいタッチ」や「草花が生い茂る田舎風景」「懐かしさを感じさせる空気感」などは、法的には直接的な著作権侵害には該当しないと考えられています。
ただし、以下のような場合はグレーゾーンに入る可能性があります。
- 特定の背景や構図があまりにも酷似している
- キャラクターの雰囲気や配置が一致している
- スタイルに加え、名前やセリフなどもジブリ風に設計している
こうしたケースでは、単なる「スタイル模倣」を超えた“依拠性”の問題が問われる可能性があります。次章で詳しく解説します。
第3章 AIによる画像生成と依拠性の問題
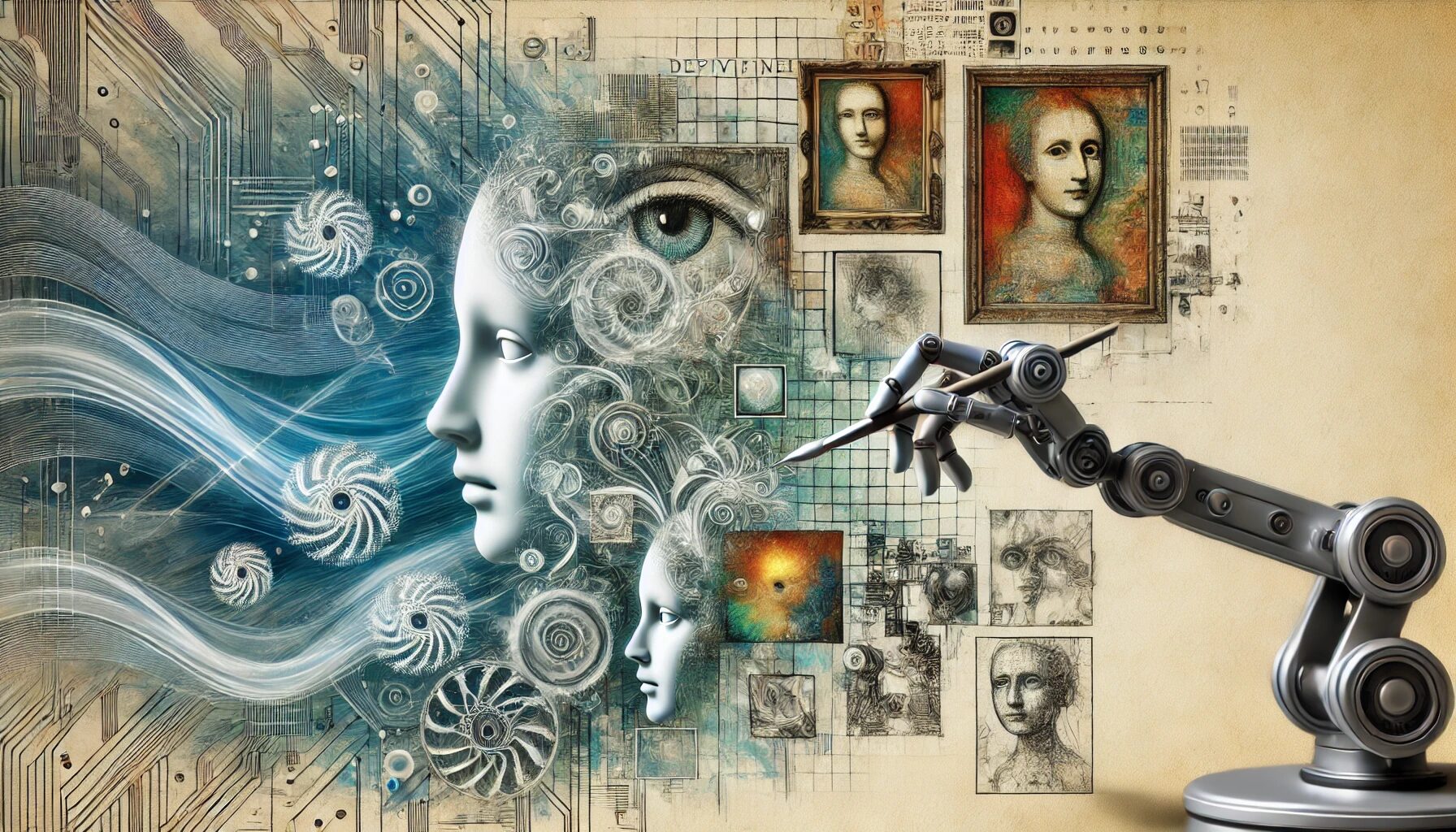
AIでジブリ風の画像を生成する際、著作権の観点から重要になるのが「依拠性(いきょせい)」という概念です。
これは、AIが既存作品をどれだけ意識して、あるいは参考にして生成されたかを判断する重要な要素となります。
依拠性とは何か?
著作権法において「依拠性」とは、既存の著作物に基づいて新たな作品を創作したかどうかという点を指します。
つまり、その作品が「過去の作品に依拠して作られた」と判断されると、たとえ見た目が少し異なっていたとしても著作権侵害とされる可能性があります。
たとえば、「トトロに似たキャラクターを描こう」と意図してAIにプロンプトを入力し、その結果として似たような見た目のキャラクターが生成された場合、それは依拠している=意図的に真似していると見なされる余地があるのです。
「ジブリ風」というプロンプトがリスクを高める
画像生成AIに「ジブリ風」「宮崎駿スタイル」などといった指示を与えることは、明確に“依拠している”と受け取られる可能性が高くなります。
とくに以下のようなプロンプトは注意が必要です:
- 「Ghibli style illustration」
- 「anime background in Studio Ghibli aesthetic」
- 「character that looks like Totoro」
これらは、特定の作風やキャラクターに寄せた結果を期待していると判断されやすく、法的にはグレー、もしくはブラックに踏み込むおそれがあります。
AI自身は責任を持たない
AIツールそのものには著作権上の責任が問われません。
責任を負うのはあくまでも「生成を行った人間」、つまりユーザー本人です。
そのため、AIが勝手に似た画像を作ったとしても、その使用者が著作権侵害の当事者と見なされることになります。
これは、生成画像をSNSやブログなどにアップしたり、商品化したりした際に特に問題となります。
回避するためのコツ
著作権侵害リスクを減らすには、プロンプトの工夫が不可欠です。
以下のような対策をとることで、依拠性を疑われる可能性を減らせます:
- 特定の作風・作品名はプロンプトに入れない
- オリジナルのキャラクターや世界観を意識して作る
- 生成画像をそのまま使用せず、編集・加筆を加えて差異を強調する
第4章 実際の事例と専門家の意見

AIでジブリ風のイラストを生成し、SNSなどでシェアする人が増える中、実際にトラブルに発展したケースや、法律・知的財産の専門家が指摘するリスクについても注目されています。
この章では、そうした実例や見解をもとに、ユーザーが注意すべき点を掘り下げていきます。
SNSでの「ジブリ風AI画像」投稿が炎上した事例
2023年以降、画像生成AIが一般にも普及したことで、「ジブリ風AI画像」もSNSで頻繁にシェアされるようになりました。
中には、まるで公式作品の一場面かと錯覚するようなクオリティの高い画像もあり、大きな話題になりました。
しかし、ある投稿では「これはAIで作ったジブリ風イラストです」と記載していたにもかかわらず、コメント欄には「ジブリを勝手に使うのはダメ」「公式と誤解される」などの批判が殺到。投稿者はアカウントを一時削除する騒動に発展しました。
このようなケースは、たとえ営利目的でなくても、「ファンアートの域を超えて公式に混同されるリスク」があることを示しています。
弁護士・専門家の見解
著作権問題に詳しい弁護士の多くは、次のような見解を示しています:
- 「ジブリ風」などと名指しして画像を生成し、公開する行為は、著作権侵害や不正競争防止法のリスクをはらむ
- 営利・非営利を問わず、作品が「公式」と誤認される可能性がある場合、法的トラブルになる可能性がある
- 特に「キャラクターや舞台設定」などが明確に既存作品と似ている場合は、著作権侵害の立証がしやすくなる
一方で、「AIが学習したデータにジブリ作品が含まれていなければ問題ないのでは」という意見もありますが、プロンプトで明確に“似せよう”とする意図がある時点で、依拠性が認定される可能性は否定できないというのが大勢の見解です。
ジブリスタジオ自身の立場
スタジオジブリは、かねてより「ファンアート」や「二次創作」に対しては厳しい姿勢で知られています。
宮崎駿監督はインタビューの中で、「キャラクターは自分の“子ども”のような存在」と語っており、無断使用や模倣について強い拒否感を持っていることが伝えられています。
したがって、AIを使ってジブリ風のイラストを生成し公開することも、公式の理念に反する行為として見なされる可能性が高いといえるでしょう。
第5章 ユーザーが取るべき具体的なアクションプラン
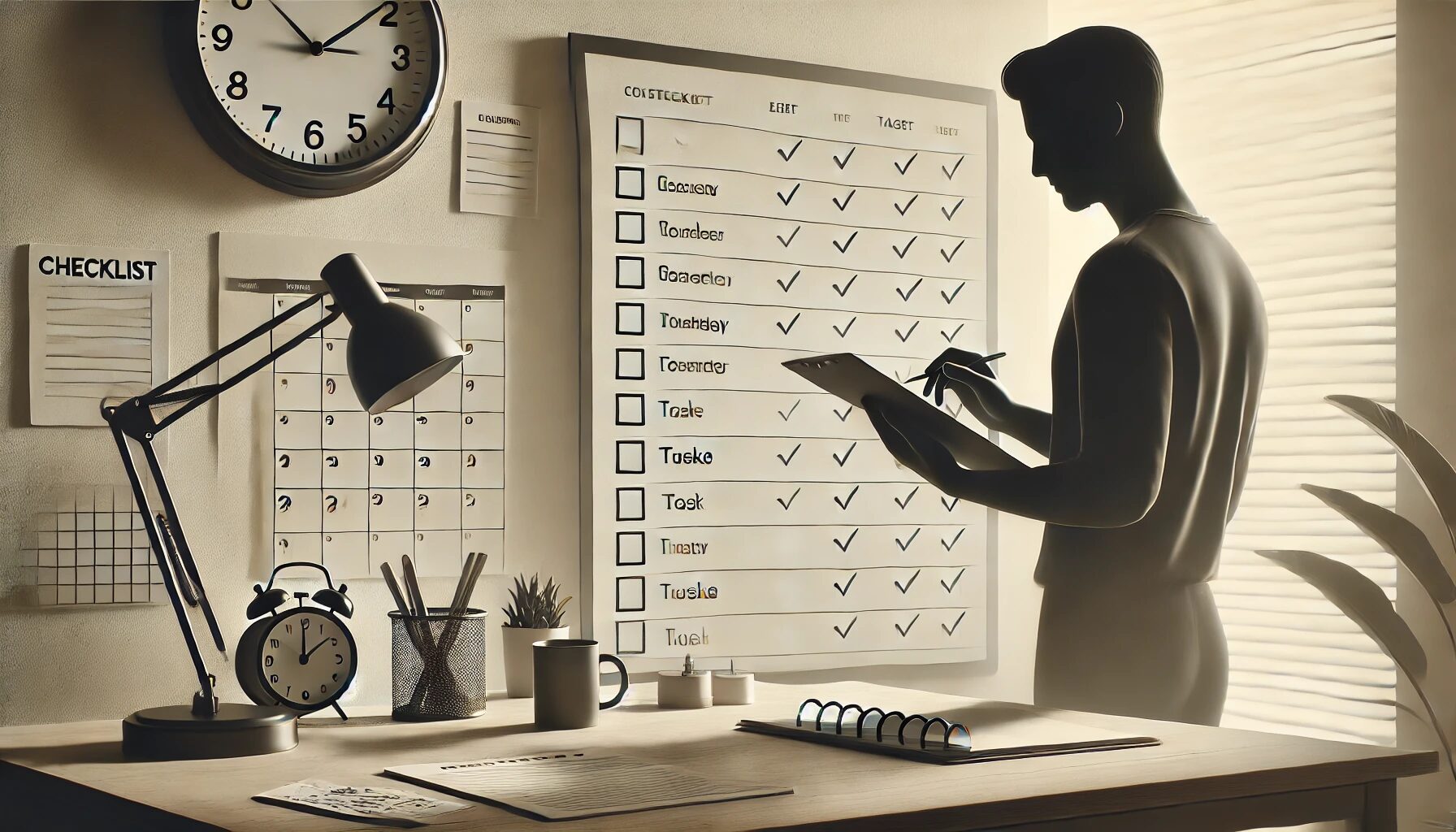
AIを使ってジブリ風の画像を生成する際には、著作権侵害などのリスクを避けるために、ユーザー自身がしっかりと意識して行動する必要があります。
ここでは、法律的トラブルを未然に防ぐための実践的な対策と注意点を解説します。
プロンプトの表現に「ジブリ」と明記しない
AIに画像を生成させる際のプロンプト(指示文)に「ジブリ風」「Ghibli style」などと明記してしまうと、意図的に似せている=依拠性があるとみなされる可能性が高くなります。
これを避けるためには、以下のように抽象的かつ一般的な表現に言い換える工夫が有効です。
例:
- 「ジブリ風」→「手描き風のファンタジーイラスト」
- 「トトロっぽい」→「大きな森の生き物のキャラクター」
このようにプロンプトを調整することで、作品が特定の著作物に依存していると判断されるリスクを軽減できます。
作成した画像の用途を限定する
生成したジブリ風画像を、次のような目的で使用することは避けた方が安全です。
- 商用利用(販売、広告バナー、サムネイルなど)
- コンテストへの応募
- NFTなどのデジタル資産化
- 「ジブリ風」として明示的に紹介・投稿すること
反対に、完全な私的利用(非公開で楽しむ、学習目的で参考にするなど)であれば、法的なリスクは比較的低く抑えられると考えられます。
ただし、SNSへの投稿は不特定多数が閲覧するため「公開行為」とみなされる点に注意しましょう。
SNSで発信する際は注意書きを添える
どうしてもAIで作成したジブリ風画像をSNSでシェアしたい場合は、以下のような注意書きを添えておくと、誤認を防ぎやすくなります。
- 「本作品はスタジオジブリとは一切関係ありません」
- 「AIによって生成されたイラストであり、非営利目的の個人投稿です」
これにより、閲覧者が「公式作品」と誤解することをある程度防ぐことができますが、完全なリスク回避にはならないことも理解しておきましょう。
二次創作・ファンアートとの違いを認識する
AI生成画像は、手描きのファンアートとは異なり、「人間の創作性」が極めて低いと見なされる傾向があります。
日本の著作権法では、AIが生成した画像自体に著作権が発生しないという議論もありますが、生成された画像が既存の著作物に酷似していれば、著作権侵害になる可能性は十分あります。
この点を踏まえ、「自分で描くのではなく、AIで作る」ことのリスクを十分に認識したうえで利用することが大切です。
商用利用したいなら、ライセンスフリー素材を活用する
ビジネスや広告、販売商品に使う画像が必要な場合は、AIではなくライセンスフリー(著作権フリー)のイラスト素材を利用するのが安全です。
例えば、商用利用可の素材サイトや、有償でライセンス提供しているアーティストからの購入など、合法的な方法を選びましょう。
おわりに

AIの進化により、誰でも高品質な画像を手軽に生成できる時代が到来しました。
中でも「ジブリ風」のイラストは人気が高く、SNSを中心に多くのユーザーが楽しんでいるのが現状です。
しかしその一方で、著作権という法的なリスクが常につきまとうことも忘れてはなりません。
ジブリ作品は、スタジオジブリが長年かけて築き上げてきた独自の世界観やキャラクターで構成されています。
そのため、たとえAIが自動的に生成したとしても、明確に「ジブリ」と関連づけてしまえば、著作権侵害と見なされる可能性が出てくるのです。
本記事で解説してきた通り、「スタイルの模倣」は法律的にグレーな領域であり、使用方法や発信方法によってはトラブルに発展するケースもあります。
特に商用利用や公共の場での発信は慎重に判断することが求められます。
これからAI技術はさらに進化し、創作活動の在り方も大きく変わっていくでしょう。
その中で私たちが大切にすべきことは、「誰かの作品や権利を尊重する姿勢」と「情報を正しく理解した上での活用」です。
もしあなたがAIでジブリ風の画像を楽しみたいなら、「あくまで個人の範囲で」「誤解を生まない形で」「著作権を尊重して」利用することが、安全でトラブルのないクリエイティブライフを送る第一歩となります。
今後もAIと著作権の関係は常に変化していくため、最新の動向をチェックしつつ、創作活動を楽しんでいきましょう。
ただ・・・
まだまだAIで収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。
じゅんの公式LINEでは、
- インスタアフィで稼ぐロードマップ
- 収益化に向けた詳しいノウハウ
- 各種テンプレート
などを中心に、
今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・
最高じゃありませんか…?
まずは僕の公式LINEを追加していただき、
ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
\無料!登録10秒/
公式LINEに登録するだけで
インスタ初心者でも月6桁目指せる
豪華17大特典配布中🎁
登録解除は、24時間いつでも出来ます🙆♂️