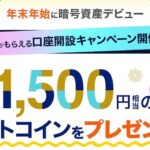コインチェックの不正アクセス事件とは?被害の概要と経緯を振り返る

2018年1月、日本国内の仮想通貨取引所「コインチェック(Coincheck)」が受けた不正アクセス事件は、当時としては世界最大規模の暗号資産流出事件として大きな注目を集めました。
この事件により、約580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム/XEM)」がハッカーによって盗まれ、日本のみならず世界の暗号資産市場に深刻な影響を与えました。
事件の発端は、コインチェックが保有する大量のNEMを、セキュリティの甘い「ホットウォレット」で管理していたことにあります。
ホットウォレットとは、インターネットに接続された状態で資産を保管する方法で、利便性が高い反面、外部からの不正アクセスに対して脆弱です。
当時、コインチェックはNEMに対してマルチシグ(複数の署名による承認)やコールドウォレット(インターネット非接続の資産保管方法)を導入しておらず、単一の秘密鍵で大規模な資産を一元管理していました。
このセキュリティ体制の甘さが、外部からの侵入を許す結果となったのです。
不正アクセスは深夜帯に行われたとされており、長時間にわたって異常が検知されなかったことからも、監視体制の不備が露呈しました。
また、事件発覚後の記者会見では、コインチェックの経営陣がセキュリティ強化に消極的だったことも判明し、利用者の信頼を大きく損なう要因となりました。
この事件は、日本の金融庁による仮想通貨交換業者への規制強化の引き金にもなりました。
事件後、コインチェックは金融庁から業務改善命令を受け、内部管理体制や資産保護措置の見直しを迫られることになります。
仮想通貨投資が急速に普及しはじめたタイミングで起きたこの事件は、「自己責任」が原則の暗号資産運用においても、取引所側のリスク管理体制の整備が不可欠であるという教訓を多くの人に与えました。
このように、コインチェックの不正アクセス事件は、単なるハッキング被害にとどまらず、仮想通貨業界全体のルール形成や投資家保護のあり方を考え直すきっかけとなった重要な出来事でした。
不正アクセスの手口とハッカーの狙いとは
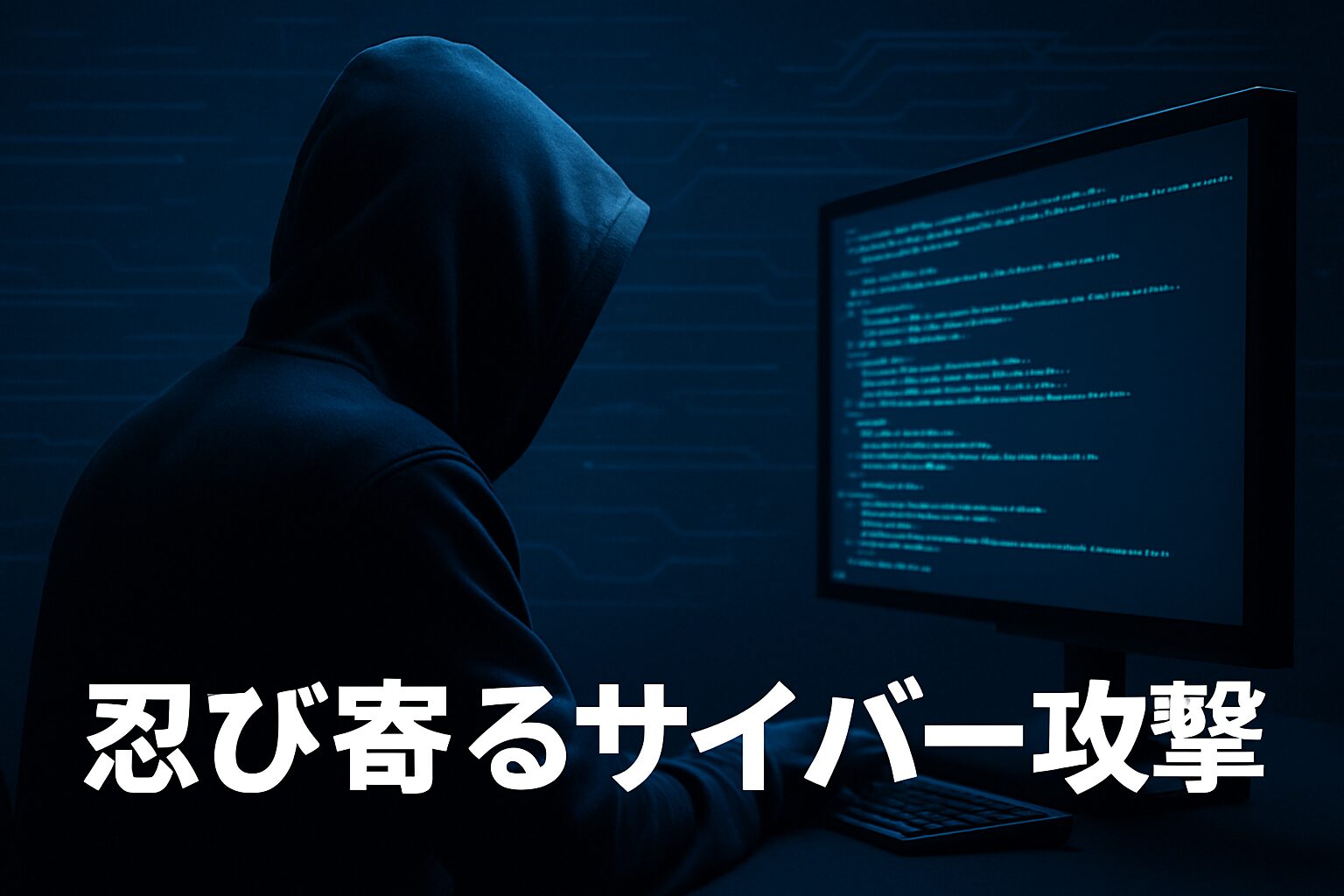
コインチェックをはじめとする暗号資産取引所の不正アクセス事件では、ハッカーたちは非常に高度で計画的な手口を用いて侵入を成功させています。
その背景には、巨額の資産が短時間で移動できるという仮想通貨特有の性質があり、世界中の攻撃者にとって大きなターゲットとなっているのです。
まず、一般的な不正アクセスの第一歩は、フィッシング攻撃です。
これは、ユーザーや取引所関係者を偽のログインページやメールに誘導し、IDやパスワードを盗み出す手法です。
特に仮想通貨業界では、Google広告を悪用した偽サイトの誘導も多く報告されています。
次に挙げられるのが、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)による感染です。
ターゲットとなるパソコンにウイルスを仕込み、ログイン情報や秘密鍵を盗み出します。
この手口は、取引所の社員や関係者の端末を狙う「標的型攻撃」として使われることが多く、特定の企業を長期間監視しながら侵入のタイミングをうかがう高度な戦術が使われることもあります。
また、ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)と呼ばれる手法もあります。
これは、膨大な数のパスワードを自動的に試して突破を試みるものです。
短く単純なパスワードを使用していた場合、この攻撃に数分で破られてしまうことがあります。
さらに、最近ではSIMスワップ詐欺の事例も増えています。
これは、通信キャリアに対してなりすましを行い、ターゲットの電話番号をハッカーの手元のSIMカードに移すことで、SMS認証などを突破する手口です。
SNSや仮想通貨取引所で利用されている二段階認証(2FA)を突破される可能性があるため、特に注意が必要です。
こうした多様な攻撃手法の背景にあるハッカーの狙いは、当然ながら「暗号資産の奪取」です。
仮想通貨は銀行を経由せずに匿名で即座に送金が可能なため、一度盗まれた資産を追跡・回収することは非常に困難です。
さらに、多くの場合、盗まれた資産は海外の複数のウォレットに細かく分散され、ミキシングサービスなどを使ってトレース不可能な状態にされてしまいます。
また、近年では国家支援を受けたとされる高度なハッカー集団による攻撃も顕在化しています。
北朝鮮系グループ「ラザルス(Lazarus)」はその代表例で、日本のDMMビットコインの事件や他国の取引所でも関与が疑われています。
このように、仮想通貨取引所に対する不正アクセスは、単なる個人の犯行ではなく、組織的かつ長期的に計画された犯罪である場合が多くなっています。
私たち投資家や事業者は、そのリスクを正しく理解し、常に警戒を怠らないことが求められます。
個人投資家が直面するリスクと今すぐできる対策

コインチェックの不正アクセス事件やその他のハッキング被害は、取引所だけでなく個人投資家にとっても他人事ではありません。
実際に、個人レベルでのセキュリティ対策が甘いことが原因で、大切なビットコインやイーサリアムが一瞬で奪われてしまうケースは後を絶ちません。
被害例1:フィッシングメールに騙され資産を全額喪失
ある投資家は、取引所からの通知を装ったメールに記載されたURLをクリックし、偽のログインページにIDとパスワードを入力してしまいました。
数時間後にはすでに全資産が不正に送金されており、取り戻すことはできませんでした。
このようなフィッシング攻撃は、実在するメールデザインを巧みにコピーしているため、誰もが引っかかる危険性があります。
被害例2:スマートフォンに仕込まれたマルウェア
別のケースでは、仮想通貨ウォレットアプリと称する偽アプリをインストールしたことにより、スマートフォンが乗っ取られ、保存していたシードフレーズ(秘密鍵の復元情報)が盗まれました。
この情報を使って資産が抜き取られる被害が発生しています。
個人でできる基本的なセキュリティ対策
被害を防ぐためには、以下のような基本対策を実践することが重要です。
- 強力なパスワードを設定する
英数字・記号を組み合わせた12文字以上のパスワードを使用し、定期的に変更します。 - 二段階認証(2FA)を必ず設定する
Google Authenticatorなどの認証アプリを利用して、ログインのたびにワンタイムコードを要求するようにします。
SMS認証よりも安全です。 - 公式サイト以外からウォレットアプリをダウンロードしない
Google PlayやApp Storeでも偽アプリが存在するため、必ず公式リンクからダウンロードします。 - 不審なメールやリンクを開かない
「ログインを再確認してください」や「特別キャンペーン」などのメールには注意し、リンクをクリックせず、公式サイトから直接ログインします。 - SNSやインフルエンサーの「無料配布」詐欺に警戒する
X(旧Twitter)やTelegramなどでの「無料ビットコイン配布」は高確率で詐欺です。
URLを踏むだけでもマルウェアに感染するリスクがあります。 - パスワード管理アプリを活用する
1PasswordやBitwardenなどの安全なパスワードマネージャーを使い、複雑なパスワードを安全に管理しましょう。
これらの対策を実践することで、個人が直面する大半のハッキングリスクを軽減できます。
とくに、仮想通貨の世界では「自己責任」という原則が強く、盗難に遭っても取引所や第三者が補償してくれるとは限りません。
そのため、自分の資産は自分で守るという意識を常に持つことが大切です。
不正アクセス事件の背景とハッカーの動機

ビットコインを狙った不正アクセス事件は、単なる個人の犯行ではなく、国家レベルの関与が指摘されるほどの組織的な攻撃にまで発展しています。
とくに2024年から2025年にかけてのハッキング事案は、北朝鮮系のサイバー攻撃グループ「ラザルス」などが関与しているとされ、被害の規模も数百億円から数千億円に達しています。
国家関与のハッカー集団「ラザルス」
警察庁によれば、2024年5月に発生したDMMビットコインの不正アクセス事件では、約482億円相当のビットコインが外部に流出しました。
調査の結果、北朝鮮政府とつながりのある「ラザルス」というハッカー集団が関与していたことが明らかになっています。
彼らの目的は、経済制裁を回避するための外貨獲得であり、仮想通貨を現金化して兵器開発や軍事資金に充てるといった実態も指摘されています。
金銭目的だけではない戦略的な攻撃
ハッカーたちの動機は金銭目的にとどまりません。
大規模な仮想通貨取引所を標的にすることで、市場の混乱を引き起こし、国際社会の信用不安を煽るような戦略も含まれています。
また、ビットコインなどの匿名性を利用して、攻撃資金や不正資金のロンダリングを行う事例も確認されています。
なぜ仮想通貨が狙われるのか?
仮想通貨がサイバー攻撃の標的になりやすい理由は以下のとおりです。
- 匿名性が高い
ブロックチェーン上では取引履歴が公開されていますが、ウォレットアドレスに個人情報が紐づいていないため、資金の追跡が困難です。 - 瞬時に資産移動が可能
攻撃成功後、数分以内に資金を複数のアドレスへ分散送金する「チェーンホッピング」や「ミキシング」によって足取りを消されます。 - グローバルかつ監視が緩い
法整備の進んでいない国や規制の甘い国の取引所を経由することで、追跡や凍結が難しくなっています。
一般人も巻き込まれる時代へ
以前は国家や大企業が主なターゲットでしたが、現在では個人投資家や中小規模のプロジェクトまでが標的になっています。
これはセキュリティ意識の低さにつけ込んだものであり、「誰もが被害者になり得る時代」に突入していると言えるでしょう。
資産を守るためのセキュリティ対策とツールの選び方

仮想通貨投資において、不正アクセスから資産を守るためには「自分自身が最終的な防波堤である」という意識が必要です。
ここでは、個人でも実践できる代表的なセキュリティ対策と、信頼できるツールの選び方を具体的にご紹介します。
コールドウォレットの活用
もっとも確実な防衛策のひとつが、コールドウォレット(ハードウェアウォレット)を活用することです。
これはインターネットに接続されていない環境で秘密鍵(資産を引き出すための鍵)を保管する方法で、オンラインからの攻撃をほぼ完全に遮断できます。
- 代表的な製品:Trezor(トレザー)、Ledger Nano(レジャーナノ)など
- 利用方法:パソコンにUSB接続して初期設定を行い、暗号資産の送金時にのみ一時的に接続する
- 注意点:シードフレーズ(復元用の秘密の単語リスト)を紙にメモして保管し、絶対にネット上には保存しないようにしましょう
二段階認証(2FA)の導入
取引所アカウントには必ず二段階認証(2FA)を設定しましょう。
パスワードの入力に加え、スマートフォンの認証アプリで生成される「ワンタイムパスコード」を入力することで、他人による不正ログインを大幅に防ぐことができます。
- 推奨アプリ:Google Authenticator、Authy
- 推奨設定:主要取引所やウォレット、メールアカウントすべてに2FAを導入
- 補足:2FA用のアプリが使えない場合に備えて、バックアップコードの保存も重要です
強固なパスワード管理と変更
使い回しのパスワードは危険です。以下の点を守りましょう。
- 英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた長いパスワードを使用する
- 最低でも3ヶ月ごとに変更する
- パスワードマネージャーを活用する(例:1Password、Bitwarden)
マルチシグ対応ウォレットの検討
資産が多い場合は、マルチシグ(複数署名)対応のウォレットを使うのも有効です。
たとえば「3人中2人の署名が揃わないと送金できない」ような設定が可能です。
- 利用例:法人での資産管理、家族や仲間での共同運用など
- メリット:1人が鍵を紛失しても資産を守れる
- デメリット:設定や運用がやや複雑なので初心者向けではない
SNS・メールのセキュリティ対策
ハッキングの入り口は意外とSNSやメール経由のことが多いです。以下に注意しましょう。
- 不審なリンクは絶対にクリックしない
- 「エアドロップ詐欺」や「無料ビットコイン配布」などの誘いは無視する
- 公式アカウントを装った偽アカウントに注意(ユーザー名の1文字違いなど)
安全な取引所の選び方と信頼できるサービスの見分け方

暗号資産を保管・売買する上で、どの取引所を使うかは非常に重要です。
不正アクセスの多くは、セキュリティ管理の甘いサービスを利用していたことが一因となっています。
この章では、個人でも実践できる「安全な取引所を見分けるポイント」をわかりやすく解説します。
金融庁の登録業者かを必ず確認する
まず、日本国内で暗号資産交換業を行うには、金融庁に登録された業者であることが法律で義務付けられています。
登録業者であれば、最低限のセキュリティ基準・内部管理体制が整っており、万が一トラブルが起きた際にも一定の対応が期待できます。
- 金融庁の「登録業者一覧」は公式ウェブサイトから確認可能
- 登録番号や運営会社名を必ずチェックしましょう
セキュリティ対策を公開しているか確認する
信頼できる取引所は、セキュリティ対策に自信を持ち、その内容を公式サイトで公開しています。
以下のような情報があるかを確認してください。
- コールドウォレット保管率(例:顧客資産の95%以上をコールドウォレットで管理)
- 外部監査を受けているか(第三者セキュリティ会社のチェック)
- 保険に加入しているか(ハッキング被害時の補償)
- マルチシグ署名の利用有無
- 社員の権限管理体制や内部不正の防止策
これらの情報が公式に明記されていない取引所は避けるべきです。
実績と評判を確認する
新興取引所や海外の無登録サービスにはリスクが伴います。以下の点を確認しましょう。
- 創業年数が3年以上か(短命の業者は倒産リスクあり)
- 過去にハッキング被害を受けていないか
- SNSやレビューサイトでの利用者の評判
評判を見る際は、「出金が遅れる」「サポートが返ってこない」などの声が多い場合は注意が必要です。
取引所の運営体制と対応力をチェック
セキュリティ以外にも、信頼性の高い取引所には以下の特徴があります。
- カスタマーサポートが日本語で対応しているか
- 本人確認(KYC)が厳格に行われているか
- 取引データや履歴が見やすく、UIが直感的に使える設計か
特に、KYCが緩い=マネロンや不正送金がしやすい環境という意味でもあるため、厳格な本人確認制度は逆に安心材料と考えてよいでしょう。
こんな取引所は避けるべき
以下のような特徴を持つサービスには、要注意です。
- 金融庁の登録がなく、「海外取引所なので問題ありません」と主張している
- 高利回りを謳って資産を預けさせる「貸付」機能を推している
- 運営会社の住所や責任者が明記されていない
- 出金に数日~1週間以上かかる
信頼できる取引所選びは、資産保全の第一歩です。多少手間がかかっても、透明性が高く実績のある国内登録業者を選ぶようにしましょう。
もし不正アクセスの被害に遭ったら?初動対応と相談先の手順

どれだけ気をつけていても、不正アクセスの被害は突然起こり得ます。
ウォレットの中身が空になっていた、取引所のアカウントに見知らぬログイン履歴があるなど、異変に気付いたときの初動対応が被害拡大を防ぐ鍵となります。
第一にやるべきこと:パスワードの即時変更とログイン停止
不正アクセスが疑われる場合は、まず以下の対応を迅速に行ってください。
- すべての関連アカウントのパスワードを即時変更(メール、取引所、ウォレットアプリなど)
- 2段階認証(2FA)を有効にする。すでに設定済みの場合は、認証アプリや登録端末の再設定も検討します。
- 取引所の管理画面からアカウントの一時凍結や出金停止依頼を出せるか確認
特にメールアドレスは他のサービスと紐づいているため、最優先で変更しましょう。
第二にやるべきこと:取引所・ウォレット提供元への報告
取引所やウォレットアプリのカスタマーサポートへ、次の情報を添えて連絡します。
- アカウントIDや登録メールアドレス
- 被害に気付いた日時と状況(例:「○月○日AM3時ごろ不審な出金を確認」)
- 被害額や、流出した通貨の種類
- 自身のIPアドレスとログイン履歴に関する情報(可能であれば)
多くの取引所では、調査用の専用フォームや問い合わせ窓口が用意されています。
早期通報によって出金ブロックや犯人特定につながることもあります。
第三にやるべきこと:警察・関係機関への通報
不正アクセスは刑法上の犯罪です。以下のような機関に通報しましょう。
- 警察庁「サイバー犯罪相談窓口(#9110)」または最寄りの警察署のサイバー犯罪課
- 暗号資産業界の自主規制団体「JVCEA(日本暗号資産取引業協会)」
- 「消費者庁(電子マネー・仮想通貨詐欺の相談窓口)」
- 金融庁「暗号資産に関する相談受付フォーム」
警察に届け出る際は、被害金額の証明(取引履歴や出金記録のスクリーンショットなど)を持参すると、事情説明がスムーズです。
被害を最小限に抑えるためのヒント
- 取引所やウォレットから「不審なログイン通知」が来た時点で、即時対処する習慣をつけましょう。
- 常に資産の一部だけを取引所に置き、大半をオフライン保管(コールドウォレット)しておくのが理想です。
- SNSや掲示板で被害を報告するのも、他の被害者と情報共有できる可能性があります(ただし個人情報は絶対に公開しないでください)。
不正アクセスの被害に遭った場合、「動揺しすぎて何もしなかった」「どこに相談すればよいか分からなかった」という声が多く聞かれます。
あらかじめ手順を把握し、冷静な対応が取れるよう準備しておくことが、資産と信用を守るために欠かせません。
よくある誤解と正しい認識 仮想通貨セキュリティの勘違いに注意

仮想通貨のセキュリティに関する誤解は、初心者だけでなく経験者の間でも多く見られます。
誤った理解のまま資産を管理していると、思わぬリスクにさらされてしまうことがあります。
ここでは特に頻度の高い誤解と、それに対する正しい知識を整理してお伝えします。
誤解1:「コールドウォレットに入れれば絶対安全」
誤解内容:
「インターネットに接続されていないハードウェアウォレットなら、どんな攻撃にも耐えられる」と思っていませんか?
実際には:
コールドウォレットは確かにオンライン攻撃に強く、ハッキングリスクを大きく減らせます。
しかし、シードフレーズ(復元用パスワード)を紙にメモして保管していた場合、その紛失・盗難・火災による焼失など、物理的なリスクは依然として残っています。
また、シードフレーズを入力する際に、悪質なソフトウェアを通じて盗まれるケースもあります。絶対安全という考えは禁物です。
誤解2:「ウォレットは1人の秘密鍵で十分に守れる」
誤解内容:
「ウォレットの秘密鍵は自分だけが持っていればOK」と考えがちですが、万が一のことを想定していない方が多くいます。
実際には:
秘密鍵が一つだけの場合、それを失くしたり盗まれたりすると資産の回復が不可能になります。
最近では、マルチシグ(複数署名)という技術を使って、2人以上の署名で資産を動かすようにすることができます。
たとえば「3人中2人の署名があれば出金できる」よう設定しておけば、一人が鍵を紛失しても資産を守ることが可能です。
これは法人やファミリーオフィスでも一般的な運用法になっています。
誤解3:「大手取引所だから安心、安全対策も万全」
誤解内容:
「有名な仮想通貨取引所を使っているから安心」「CMで見たから信頼できる」といった安心感から、つい警戒を怠ってしまう方がいます。
実際には:
2024年のDMMビットコイン事件や2025年のBybit事件のように、大手でも被害に遭う可能性はあります。
たとえセキュリティが堅牢でも、内部不正や外部からの高度な攻撃には完全な防御は存在しません。
そのため、自分自身で2段階認証や資産の分散管理を行うなど、「自己防衛」が前提であるという認識を持ちましょう。
誤解4:「メールが届いたなら正規の通知だろう」
誤解内容:
取引所やウォレットを装った偽メール(フィッシングメール)に気付かず、リンクを開いてしまうケースが後を絶ちません。
実際には:
公式の連絡メールのように見せかけて、ログイン情報を盗もうとするフィッシングは年々巧妙化しています。
メール内のリンクではなく、ブラウザのお気に入りからアクセスする習慣を徹底することが重要です。
また、メールアドレスや文面に不自然な点がないか、URLが正規のものかを慎重に確認しましょう。
このような誤解を避け、常に最新のセキュリティ知識をアップデートしていくことが、仮想通貨資産を守るうえで不可欠です。
情報の信頼性を確認し、自らの判断で安全対策を講じる意識を持ち続けましょう。
この機会にぜひ仮想通貨を始めてみてください!
初心者の方であれば、自己資本0でも1,500円もらえる取引所もあるので、
リスクを最小限に抑えてビットコインを始めたい方は、ビットポイントもおすすめです!
>ビットポイントについては、こちらをご覧ください。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。