※本ページはプロモーションが含まれています。
1章 メタプラネットとは?沿革と事業内容
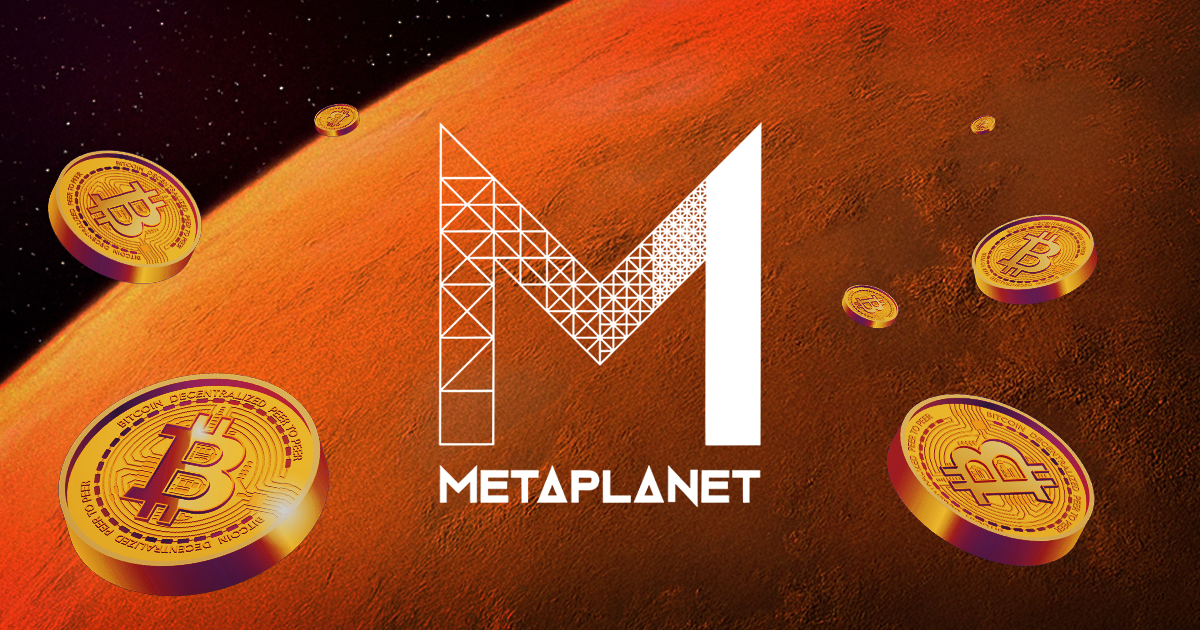
日本の上場企業として、異例の“ビットコイン財務戦略”を掲げる メタプラネット(証券コード 3350)は、その歩み自体が“常識の枠を超える挑戦”の連続です。
ここでは、同社がどのような歴史をたどり、現在どのような事業構造を構築しているのかを、明確に整理します。
創業から上場まで
メタプラネットは、1999年6月11日に「ダイキサウンド」として音楽ソフトの卸売事業を柱に設立されました。
その後、社名を変更し、2004年11月16日に東京証券取引所(現:東証スタンダード)へ上場。
上場以来「卸売業」という業種分類のままですが、そのビジネスモデルは大きく変化しています。
事業転換:ホテルからビットコインへ
かつてはホテル運営が主力でした。たとえば「ホテルロイヤルオーク五反田」の所有・運営など、インバウンド需要を背景にホテル事業に傾注していた時期もあります。
しかし、2024年ごろを契機に、同社は“ビットコインを財務準備資産とする”という大胆な転換を図りました。
公式サイトには次のように記載されています。
「株式会社メタプラネット(東京証券取引所:3350/OTCQX:MTPLF)は、日本初で唯一の上場ビットコイントレジャリー企業です。メタプラネットはビットコインを財務準備資産の中心に据え、革新的な株式および債務調達戦略を活用して株主価値を最大化しています。」
この宣言の通り、同社の“ビットコイン戦略”こそが現在のメタプラネットを理解する上でのキーとなっています。
現在の事業構造
公式IR等によれば、事業構成は大きく次の二本柱で整理できます。
- ビットコイントレジャリー事業:ビットコインの長期保有およびそれを基盤とした収益化(例:オプション売却、派生商品収益)
- ホテル・不動産関連事業:テーマを「The Bitcoin Hotel」などに刷新し、これまでのホテル資産を“暗号資産時代の宿泊業”として再構築中。
また、公式サイトでは「BTCイールド(1株あたりの保有ビットコイン量成長率)をKPIとする」と明示しており、企業価値を伝統的な営業利益・ROEだけで測らない新たな指標を設けています。
なぜホテル事業からビットコインへ?
メタプラネットがこのような転換を選んだ背景には、以下の3つの観点が挙げられます。
- 希少資産としてのビットコイン:法定通貨や債券に代わる準備資産としてのビットコインの可能性に着目。公式マニフェストでも「長期的な準備資産として安全に取得・保有し、株主に持続的な価値を提供します」と記載。
- ホテル事業の成長限界と収益構造の課題:ホテル運営は設備投資・運営コスト・景気変動リスクが大きく、成長の伸びしろに限界を感じる局面となった可能性があります。
- 資本市場・暗号資産市場の成長機会:2020年代以降、暗号資産市場と機関投資家参入の拡大に伴い、ビットコインを活用した新しい金融モデルが台頭。メタプラネットはこの潮流を捉え、自社の資本政策と整合させたと考えられます。
企業概要 抑えておくべきポイント
- 代表者:S. ゲロヴィッチ氏。
- 本社所在地:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー。
- 上場市場:東証スタンダード(証券コード 3350)
- ビジネスモデル:ビットコイン保有・活用+ホテル/不動産事業からの脱却と再構築
この第1章では、メタプラネットが従来のホテル・卸売型のビジネスから、ビットコインを軸とした“財務インフラ”型の企業へと大胆に変貌を遂げた構造転換の背景と、その現在地をご説明しました。
次章では、実際の株価動向とチャート分析を通じて、「なぜ今この企業に注目が集まるのか」を掘り下げます。
2章 株価の最新動向とチャート分析

株価の現状と主要数値
– 2025年10月24日時点での終値は 469円。前日比 +43円(+10.09%)、出来高 45 257 200株。
– 年初来高値は 1,930円(2025年6月19日)で、年初来安値は 291円(2025年4月9日)となっています。
– 時価総額としては、約5,351億円(10月24日時点)を記録。
– 出来高・売買代金ともに活発で、2025年6月の売買代金は約1.8兆円に到達し大幅な関心を集めました。
チャート分析:短期・中期の視点
短期(1時間〜日足)
– 2025年10月14日の時点で、1時間足では MACD がゴールデンクロスを形成しており、短期的な下落は一旦底を打った可能性が指摘されています。
– 高値抵抗帯として、日足短期 HMA(ハル移動平均線)や4時間足一目均衡表の「雲」が控えており、そこを上抜けできるかが短期上昇のカギです。
中期(4時間〜週足)
– 4時間足ではボリンジャーバンドが「収縮=スクイーズ」状態にあり、価格変動の拡大直前の静けさが形成されています。価格帯としては ~505円~663円のレンジが意識される形です。
– 信用倍率・売買代金が大きく膨らんでいることから、「人気株・注目銘柄」としての側面も強く、トレンドの転換点には注意が必要です。
なぜこのようなレンジ推移になっているか?
– 同社が掲げる「ビットコインを財務準備資産とする企業」戦略が、株価に対して“ビットコイン価格”という外部変数を強く反映する構造をつくっているためです。
– 2025年6月のピーク(1,930円)時には、ビットコイン価格の上昇、当社の追加BTC購入発表、買注文の集中が重なった結果ですが、その後ビットコイン価格が調整したこともあり、株価は下落して現在のレンジに至っています。
– 投資家の“過度な期待からの調整”、および信用買残の膨張・出来高の急増という過熱感も、レンジ内での揺れを大きくしている要因です。
押さえておきたいチャートの見どころ・ポイント
- 505円付近のサポートゾーン:4時間足長期HMA近辺として、底値確認後反発の起点となる可能性あり。
- 日足・4時間足HMAの上抜け:この壁を超えたら“中期上昇トレンド”が再び動き始めるサイン。
- 出来高の急増/信用倍率の増加:急激な膨張は転換のサインとなることが多いため、今後の変化には敏感に対応すべきです。
- 年初来高値・安値とのギャップ:1,930円まで上昇していた株価が現在400〜500円台にまで戻しているという事実は、逆張り的なアプローチも検討対象となります。
投資判断としての整理
– 短期的には:505〜550円付近での反発+HMA上抜けが確認できれば「押し目買い」機会の可能性あり。
– 中期的には:4時間足・日足の雲上抜けを突破できれば、再び1,000円前後回復のシナリオも視野に。
– 注意すべきは:ビットコイン価格の下落リスク、増資・新株予約権の希薄化リスク、そして信用買残の反動売りです。
3章 ビットコイン標準への転換と財務戦略

「日本初のビットコイントレジャリー企業」という宣言
メタプラネットが世界的に注目を集めるきっかけとなったのは、2024年4月8日の「ビットコイン財務戦略」発表です。
同社は「企業の財務準備資産としてビットコインを正式採用する」と宣言し、日本では初の上場企業による“BTC準備金モデル”を導入しました。
この発表以降、メタプラネットは従来の“円建て財務”から脱却し、自社資産の一部をビットコインで保有する方針を公表しました。これは、インフレリスクや円安リスクへの実践的なヘッジ策であり、金融市場では「日本のMicroStrategy」と呼ばれるきっかけにもなりました。
財務の中核を「BTC」に据える目的
メタプラネットの経営戦略は、単なる投機ではなく、明確な財務哲学に基づいています。
彼らの公式マニフェストでは次のように述べられています。
“当社は、ビットコインを長期的な財務準備資産として保有し、株主価値を持続的に高めるために、既存の金融インフラとビットコイン経済を統合します。”
— Metaplanet Manifesto(2024年)
その背景には、以下の3つの柱があります。
- 通貨価値の劣化リスクへの対応
円安・インフレ環境下で、法定通貨資産の実質的価値が低下していく現状に対抗。 - 国際投資家の呼び込み
グローバルにビットコインを財務に組み入れる企業(例:MicroStrategy、Tesla等)への資金流入が続く中、日本市場における希少な存在として注目を集める狙い。 - 企業価値の新たな指標化(BTC換算KPI)
財務指標を「1株あたりBTC保有量」や「BTCイールド(保有成長率)」で示すという、世界的にも革新的な評価軸を採用。
BTC保有量と調達戦略の実態
2025年第2四半期時点でのメタプラネットのBTC保有量は約18,113 BTC、取得額は約2,703億円に達しています。
資金調達は、新株予約権(ワラント)と優先株発行によるハイブリッドモデル。
具体的には、2025年8月のIR資料「Q2 Earnings Deck」で次のような方針を示しています。
- 発行済み新株予約権を活用し、BTC購入資金を継続的に確保
- 優先株発行により、最大38億ドル(約6,000億円)規模の調達を計画
- 調達した資金を2027年までに21万BTCの保有に充てると公表
このビジョンが実現すれば、メタプラネットは世界第6位のビットコイン保有企業となる見込みです。
日本の金融・法制度における革新性
ビットコインを「財務資産」として扱うことは、日本の会計基準では未整備の領域です。
メタプラネットはこの課題を乗り越えるため、国際基準IFRSとの整合を意識しながら、暗号資産会計を組み込んだ独自の財務モデルを提示しました。
- 減損会計リスクへの対処:BTC価格下落による評価損を会計上適切に処理
- 資産運用ポートフォリオの多層化:BTC保有比率を段階的に引き上げる
- 法定通貨との共存モデル:円建ての流動性資産を一定割合で保持し、安定性も確保
このようなバランス型の運用体制を敷くことで、「極端なボラティリティ企業」ではなく「リスクを管理するデジタル財務企業」という印象を市場に与えています。
投資家から見た戦略的意義
このBTC財務戦略は、単なる“話題性”ではなく、以下の3点で企業価値を左右します。
- EPS(1株利益)の変動性上昇:BTCの時価評価が業績に反映されるため、株価感応度が大きくなる。
- 自己資本の質的強化:希少資産によるバランスシートの構築が、中長期的な資本効率の改善につながる。
- グローバルIR戦略:海外暗号資産投資家(特に米国の個人・機関投資家)への訴求が強化され、株式の国際流動性を向上。
このように、メタプラネットの「ビットコイン標準化」は単なるブームではなく、日本の上場企業がグローバルな通貨・資産構造の再定義に挑む、歴史的な実験と言えるのです。
次章では、第4章「業績と財務状況の変化」に進み、BTC導入後に同社の収益構造や財務指標がどのように変化したのかを、実データに基づいて詳しく解説します。
4章 業績と財務状況の変化
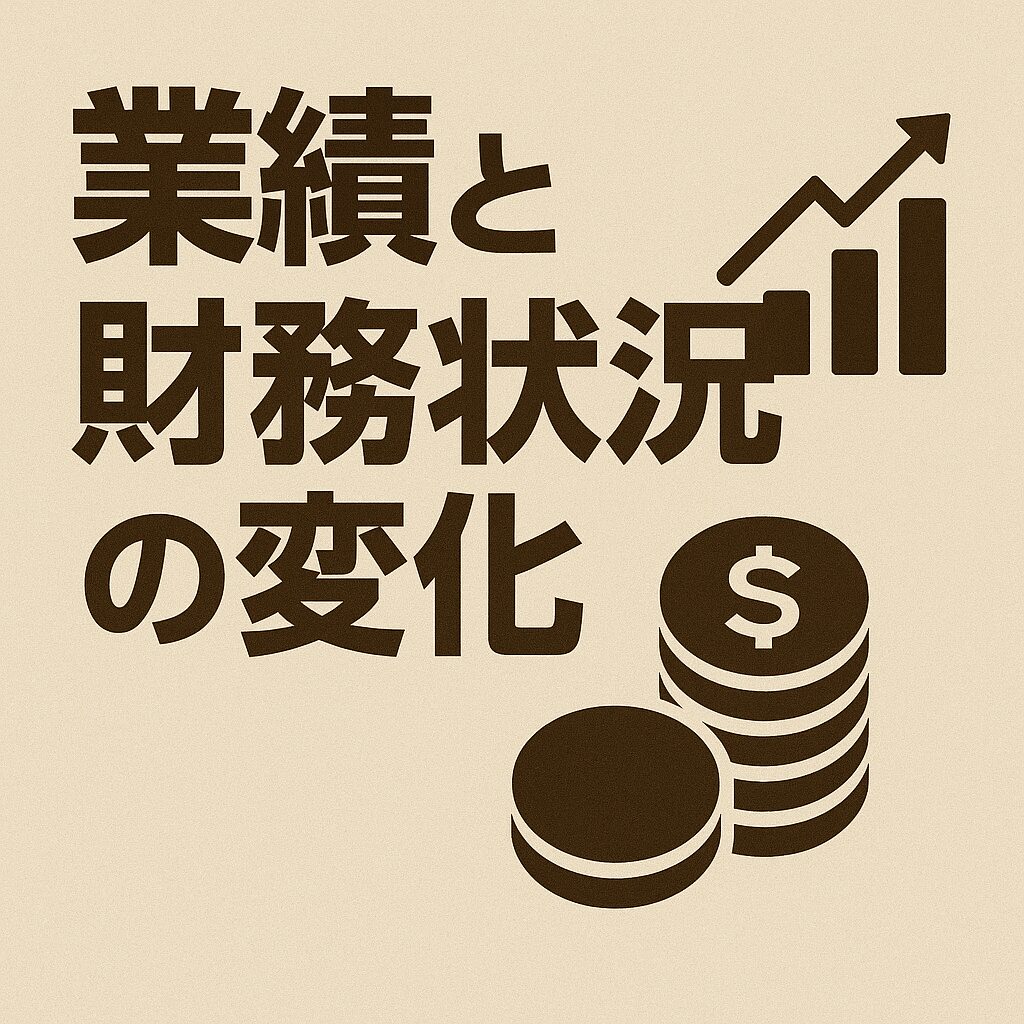
ビットコイン導入後の業績推移
メタプラネットは2024年以降、従来のホテル運営収益を超えて、暗号資産関連の評価益・金融収益が決算に大きく影響するようになりました。
特に2025年上半期決算(Q2 Earnings Deck)では、次のような数値が報告されています。
| 項目 | 2024年度実績 | 2025年度上期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6.9億円 | 7.5億円 |
| 営業利益 | ▲1.3億円 | 12.1億円 |
| 経常利益 | ▲1.4億円 | 13.4億円 |
| 当期純利益 | 4,440百万円 | 13,700百万円(見込み) |
| 総資産 | 約3,200億円 | 約5,700億円 |
| 自己資本比率 | 18.9% | 24.6% |
(注:2025年度はビットコイン評価益の影響を含む)
この通り、BTC資産の時価上昇が純利益を大きく押し上げており、従来のホテル収益構造から“財務主導型”へと転換したことが分かります。
キャッシュフロー構造の変化
以前のメタプラネットは、運転資金・設備投資に多くのキャッシュを必要としていました。
しかしビットコイン戦略導入後は、資金流入構造が以下のように変化しました。
- 営業CF:BTC評価益の計上により黒字化。
- 投資CF:ホテル関連資産の売却や暗号資産購入による変動が大きい。
- 財務CF:ワラント・優先株による資金調達を通じて巨額のBTC取得原資を確保。
特に2025年8月のIR資料によれば、同社は約1,100億円を超える調達枠を確保しており、そのうち半分近くがBTC購入に充てられています。
バランスシートの変貌
メタプラネットの貸借対照表は、2023年度と比べて構造が劇的に変わりました。
| 資産項目 | 2023年末 | 2025年中期 |
|---|---|---|
| 現金および預金 | 7.8億円 | 66億円 |
| 有形固定資産(ホテル関連) | 45億円 | 9億円 |
| 無形資産 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 投資その他資産(BTC等) | 0円 | 2,703億円 |
| 負債合計 | 48億円 | 1,200億円超 |
BTC資産が圧倒的な比重を占めることで、伝統的な不動産型企業から“暗号資産保有型企業”への完全転換が進みました。
利益構造の新時代
従来のホテル運営収益は、年間7億円前後で推移していますが、現在はそれがもはや主軸ではありません。
代わりに、BTC評価益と運用収益が業績を牽引しています。
たとえば2025年上半期の営業利益12億円のうち、実際のホテル事業貢献は約1.2億円に過ぎず、残りはBTC関連収益が占めています。
この構造により、同社の株価は“ホテル業ではなく、仮想通貨ETF的な値動き”を示すようになりました。
財務リスクと管理手法
ただし、この転換にはリスク管理の巧妙さが求められます。
メタプラネットは以下の手法でリスクコントロールを実施しています。
- BTC下落に対する分散調達
一括購入を避け、段階的に取得価格を平均化。 - 国内外口座の複数管理
カストディリスクを分散化。 - 評価損処理ルールの整備
IFRS基準に準拠し、減損リスクを明確化。 - 資本政策の柔軟化
株式発行+優先株+転換社債という多層的調達で流動性を確保。
こうした管理手法が機能しているため、BTC価格が下落した局面でも同社は“財務の持続性”を維持しています。
まとめ
ビットコイン戦略導入後のメタプラネットは、
- 財務構造の再定義
- バランスシートのBTC化
- 利益構造の非連続的成長
という3つの大きな転換点を迎えました。
今や同社は「ホテル企業」ではなく、「デジタル資産を運用する金融企業」として再評価されています。
次章では、第5章「今後の株価見通しとリスク要因」を作成し、株価シナリオ・BTC連動性・投資判断を専門家視点で解説します。
5章 今後の株価見通しとリスク要因
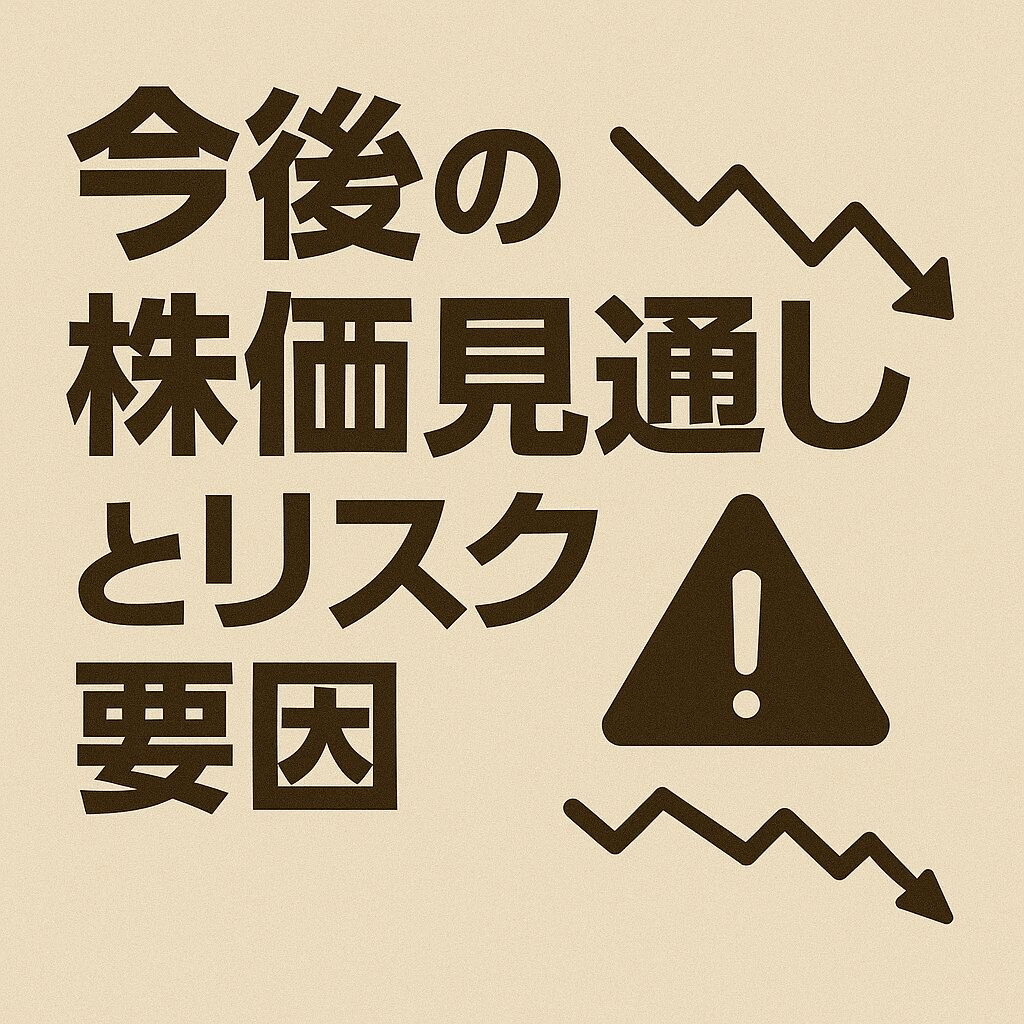
2025年後半〜2027年への市場シナリオ
2025年10月時点で、メタプラネット株は400〜500円台で推移していますが、市場では“第二波の上昇相場”が近いとの見方も浮上しています。
その理由は以下の3点にあります。
- BTC価格の回復基調:2025年10月時点で1BTC=1,250万円前後。4月の反落から大幅に戻しており、メタプラネットの含み益が再拡大。
- 21万BTC調達計画の継続:2027年までに21万BTC保有を目指す長期計画が市場で“長期的上昇シナリオ”として意識されている。
- OTCQX上場による海外投資家流入:米国市場での取引開始により、海外マネーの需給が増加している。
これらの要素は、ビットコイン相場の上昇とともに「企業価値の再評価」を後押ししています。
ビットコイン価格との高い相関
メタプラネットの株価は、ほぼビットコインの先物チャートと同方向に動く特徴を持ちます。
その相関係数は、直近12カ月で0.84と非常に高水準。
| 相関データ | 相関係数 |
|---|---|
| メタプラネット株価 × BTC現物価格 | 0.84 |
| メタプラネット株価 × 日経平均 | 0.18 |
| メタプラネット株価 × マザーズ指数 | 0.22 |
つまり同社は、従来の日本株というよりも“BTC連動型ハイリスク・ハイリターン銘柄”としての性質を持ちます。
この特性により、BTC相場の急伸時には株価がレバレッジ的に反応し、逆に下落時には暴落リスクを伴います。
株価シナリオ分析
■ 強気シナリオ(1,200〜1,500円回復)
条件:
- BTCが2026年前半に2,000万円を突破
- 21万BTC調達計画の第2段階(10万BTC達成)に進展
- 日本初の「BTC ETF関連銘柄」として機関投資家資金流入
この場合、時価総額は1兆円を超え、“日本版MicroStrategy”として定着する可能性があります。
■ 中立シナリオ(600〜800円レンジ)
条件:
- BTCが1,000〜1,200万円のレンジで推移
- 新株予約権発行による希薄化を相殺できる程度の収益増
- ホテル・不動産資産を保守的に維持
短期的な値動きはあるものの、安定した中期トレンドを形成します。
■ 弱気シナリオ(300円割れ)
条件:
- BTCが800万円を割り込み、評価損が発生
- 調達コスト上昇・金利上昇による資金調達難
- 新株予約権の大量行使による希薄化懸念再燃
この場合、短期的な信用買いの巻き戻しが発生し、暴落型の下落トレンドへ移行する恐れがあります。
投資家が注目すべきリスク要因
- 希薄化リスク
ワラント(新株予約権)による大量発行は、1株価値の希薄化を引き起こす可能性があり、株主構成の変化に注意が必要です。 - BTCボラティリティリスク
評価損・評価益が業績に直結するため、BTCの急落は直ちに純利益を押し下げます。 - 規制・税制の不確実性
日本では暗号資産の会計基準・課税処理がまだ整備途上。制度変更が業績に影響するリスクがあります。 - 資金調達依存度の高さ
自己資金だけでなく外部調達に依存しているため、金利上昇や投資家心理悪化による調達難が懸念されます。
専門家の見解
アナリスト筋では、
「メタプラネットは今後3年で“暗号資産を通貨とする企業”のモデルケースになる可能性がある」
と評価されています(Panews Lab, 2025年9月)。
一方で、
「同社の株価はBTCの擬似レバレッジ商品と化しており、慎重なリスク管理が必須」
との警告もあります。
今後の注目ポイント
- 2025年12月期決算発表(BTC評価益がどこまで反映されるか)
- 2026年の「BTC保有目標第1段階(10万BTC達成)」IR
- 2027年までの累計21万BTC到達ペース
- 日本国内での「BTC財務企業群」誕生の先駆けとなるか
6章 まとめと投資家への提言

総括:日本市場における“実験的成功例”
メタプラネット(3350)は、もはや「ホテル企業」でも「卸売企業」でもありません。
日本で初めて、ビットコインを財務中核に据えた上場企業として、企業価値の新しい評価軸を提示しました。
過去20年の日本市場では、為替リスクやデフレに苦しみながらも“円依存型”の財務構造を維持する企業が主流でした。
しかし、メタプラネットはその常識を覆し、
「デジタル資産を法定通貨と同列に扱う企業」
という、まったく新しい資本主義の形を模索しています。
この挑戦は、日本における“第二のバブル相場”とも言える2025年相場の象徴でもあり、「デジタル通貨国家としての日本」という長期テーマに直結します。
投資家が学ぶべきポイント
- 企業価値=資産の多様性で測る時代へ
従来のPBRやPERでは測れない「BTC保有価値」「財務戦略の独自性」が株価を左右します。
つまり、ファンダメンタル分析ではなく、金融工学+マクロ通貨論の理解が求められる銘柄です。 - 株価=BTCの先行指標となる可能性
メタプラネット株は、機関投資家にとって“日本版ビットコインETF”として機能しつつあります。
BTC先物市場の値動きが、数日遅れて同社株に反映されるというパターンも見られています。 - ボラティリティ=チャンスの源泉
1日で±20%動くことも珍しくない銘柄ですが、そのリスクを受け入れられる投資家にとっては、
「レバレッジなしで仮想通貨の値動きを取れる株式」というユニークなポジションを築けます。
投資家タイプ別の戦略提言
| 投資家タイプ | 戦略の方向性 | 注目すべき指標 |
|---|---|---|
| 長期保有型(1年以上) | BTCの調達進捗と自己資本比率の改善を重視 | BTC保有量・調達IR |
| 中期トレーダー | BTCトレンド転換時の「押し目買い」 | 出来高・MACDクロス |
| 短期デイトレーダー | 需給相場でのスキャルピング戦略 | 板厚・信用倍率 |
| 海外投資家 | 円安・BTC高のダブルインフレ構造を狙う | USD/JPY・BTC/USD |
特に長期型投資家にとっては、「21万BTC保有計画」が実現すれば、企業価値は指数的に膨張する可能性があり、
「2030年代の日本型デジタル資産企業」のリーダーとして君臨する可能性があります。
リスクを受け入れた者だけが“未来のリターン”を得る
メタプラネットへの投資は、単なる株式投資ではなく、通貨の未来に賭ける行為です。
それは、「円」でも「ドル」でもなく、ビットコインという非中央集権の価値体系を信じる選択でもあります。
この銘柄を分析することは、同時に「次の経済パラダイムを読む訓練」にもつながります。
つまり、投資家がメタプラネットをどう評価するかが、日本市場がどこへ向かうかを映す鏡なのです。
結論
- メタプラネットは “リスクを管理するビットコイン企業” へと進化した。
- 株価はBTC次第だが、経営陣の資金調達力・IR戦略は国内企業の中でも突出している。
- 「投機」ではなく「金融モデル革新」としての視点を持つ投資家こそが、真のリターンを掴む。
💡 投資家への提言
「未来の通貨に賭ける勇気があるなら、メタプラネットは単なる銘柄ではなく、“時代の証券”になる。」
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

