※本ページはプロモーションが含まれています。
第1章 楽天証券のAI分析が投資家に支持される理由

楽天証券は2023年10月に米国株向けのAI分析サービスを公開し、2025年7月には国内株を加えた総合版へと拡張しました。
現在カバーする銘柄は日米合わせて約8,500社にのぼり、目標株価や財務健全性、トレンド強度などをスコア化して提供しています。
このアップデートにより、従来は専門家に依存していた高度な定量分析が、パソコンの「MARKETSPEED II」やスマホアプリ「iSPEED」からワンクリックで利用できるようになりました。
投資家が同機能を高く評価する背景には、次の三つの要因があります。
第一に、情報収集の高速化です。
決算発表や業界ニュースが反映されるまで最短24時間というスピードでアルゴリズムが再計算されるため、時間的優位性が得られます。
第二に、判断の客観性です。
感情に左右されがちな個人投資家でも、機械学習モデルが算出したリスク・リターンスコアを基準にすることで、バイアスを排除した意思決定が可能になります。
第三に、視覚的な分かりやすさです。
ヒートマップやレーダーチャートが標準搭載され、カラーグラデーションでリスク水準を即座に把握できるため、初心者でも迷わず次のアクションに移れます。
また、楽天グループが蓄積するビッグデータとの連携も見逃せません。
ポイント経済圏やカード決済データを横断的に解析することで、消費動向と株価トレンドを関連付けた先読みシグナルの開発が進行中です。
今後はNISA口座の積立最適化やテーマ投資の自動提案など、さらにパーソナライズされた金融サービスへと進化する見通しです。
つまり、楽天証券のAI分析は「速い・正確・分かりやすい」を同時に満たす次世代型の情報インフラとして、投資経験の浅いユーザーから高度な戦略を求めるトレーダーまで幅広い層にメリットを提供しています。
本章ではその全体像を概観しましたが、次章以降では具体的な機能や操作方法を掘り下げ、実践的な活用ノウハウを詳しく解説していきます。
第2章 楽天証券のAI分析機能とは―概要と開発の背景

楽天証券のAI分析は、イスラエルのフィンテック企業Bridgewiseが開発したエンジンを中核に据え、企業開示情報・株価時系列・市場ニュースなど数百種のデータを学習させた機械学習モデルを用いています。
モデルはファンダメンタルズとテクニカルを融合したスコアリングを行い、3~6か月先を想定したパフォーマンスを予測します。
ユーザーが目にするのは総合評価を示すレターグレードと、目標株価、財務健全性、業界比較のレーダーチャートで、複雑な計算過程を意識せずとも要点を把握できる設計です。
開発のマイルストーン
- 2023年10月 米国株向けに「アナリスト注目度ランキング」とAI目標株価を無料公開し、個人投資家の情報格差を圧縮
- 2024年4月 決算速報の自然言語処理を組み込み、財務データの反映時間を従来比70%短縮
- 2025年7月 国内株を含む総合版をリリースし、対象銘柄を約8,500社へ拡大。総合評価・財務評価・目標株価・短期パフォーマンスの四本柱を全口座保有者に提供
なぜ今AI分析が必要とされるのか
株式市場の情報量は指数関数的に増加しており、人手だけで精査するには限界があります。
楽天証券は「情報処理の民主化」を掲げ、AIの推論速度と網羅性を活用することで、個人でも機関投資家に匹敵する分析環境を獲得できる仕組みを構築しました。
AI分析は単なるシグナル提示に留まらず、①情報の収集、②評価、③視覚化の三段階すべてを自動化している点が特徴です。
モデルの信頼性を担保する仕組み
- 継続的学習 四半期ごとに訓練データを更新し、市場構造の変化を捕捉
- 異常値フィルター 急騰暴落や決算外れ値は統計的テストで除外し、極端値による歪みを抑制
- 説明変数の開示 スコア計算に寄与した主要ファクターをバーグラフで開示し、ブラックボックス化を回避
利用インターフェースの一体化
PCウェブ、MARKETSPEED II、スマホアプリiSPEEDは同一レイアウトでAI分析ウィジェットを表示します。
例えば銘柄ページを開くと、左側に目標株価と乖離率、右側にスコアリング要因の詳細が並び、ワンクリックでテクニカルチャートへ遷移できます。
UIの統一により、デバイスを跨いだ学習コストが最小化されています。
今章のまとめ
楽天証券のAI分析は、Bridgewiseの高度なアルゴリズムと楽天グループのインフラを融合させることで、「網羅的データ×高速処理×直感的可視化」を実現しました。
2025年の国内株対応で対象ユニバースが大幅に広がり、個人投資家がプロ水準の多角的分析を手軽に享受できる土台が整っています。
次章では、銘柄レコメンド・チャート分析・ランキング生成といった主要機能をさらに深掘りし、実際の画面イメージに即して解説します。
第3章 主要機能を徹底解説—銘柄レコメンド・AIチャート分析・株式ランキング生成

銘柄レコメンド機能—個別化されたスコアリングで厳選提案
銘柄レコメンドは、ユーザーの保有銘柄・過去の取引履歴・ウォッチリストをベースに、AIが投資嗜好をクラスタリングしながら上昇期待度とリスク耐性を数値化します。
スコアは A+〜D までのレターグレードに加え、0〜100 のパーセンタイルでも表示されるため、「業界内で上位○%」という相対評価が一目で把握できます。
さらに目標株価との乖離率が自動計算され、割安度を判断しやすい設計です。
フィルターでは「PER20倍以下」「ボラティリティ低」「時価総額1,000億円超」などを組み合わせて多面的に絞り込めるので、長期保有向けの堅実株から短期狙いの成長株までニーズに合わせて候補を抽出できます。
活用ヒント
- スコアが急上昇した銘柄は、決算サプライズやアナリストの格上げが反映された可能性が高いです。
- 乖離率がマイナスで総合評価が高い銘柄は“押し目”狙いの有力候補になります。
AIチャート分析—パターン認識と確率的トレンド予測
AIチャート分析では、過去20年超の時系列データを教師データとして自己相関・異常値を学習し、類似パターン出現後の値動きを確率分布で提示します。
画面左には「上昇継続 68%」「保ち合い 22%」「下落転換 10%」といったシナリオ別確率が円グラフで表示され、右側チャートには期待レンジが色帯でオーバーレイされます。
移動平均線やRSIはAIが自動最適化した期間で描画されるため、テクニカル設定に迷う必要がありません。
ボラティリティが高まる局面ではレンジ幅が拡大し、リスクの可視化にも役立ちます。
活用ヒント
- トレンド継続確率が60%以上、かつレンジ上限が目標株価に近い場合は“順張り”戦略が機能しやすい傾向があります。
- レンジ幅が急拡大したときは“イベントリスク”を警戒し、ストップ価格を必ず設定してください。
株式ランキング生成—リアルタイムで市場全体を俯瞰
株式ランキング生成は、国内外8,500銘柄を対象にリアルタイム演算を行い、トレンド・業績・バリュエーション・ESGスコアなど多軸でランキングを提示します。
一覧表は上位200銘柄までスクロール表示でき、各列ヘッダーをクリックするだけで並び替えが可能です。
特筆すべきはキーワードサーチで、たとえば「半導体」「GX」「メタバース」などテーマを入力すると、該当キーワードを多用する決算書・IR資料をAIが抽出し、トレンド感度の高い銘柄を即時リスト化します。
| ランキング例 | 指標 | 特徴的な使い方 |
|---|---|---|
| 上昇モメンタムTOP50 | 5日騰落率 & AI短期パフォーマンススコア | デイトレ・スイング向け候補の発掘 |
| 財務健全度TOP50 | 自己資本比率 & 利益率 & 業界平均差分 | 低リスクの長期保有銘柄を抽出 |
| ESGスコアTOP50 | 環境・社会・ガバナンス項目のAI評価 | SDGs投資や機関投資家の関心領域を先取り |
活用ヒント
- ランキングとレコメンドを組み合わせ、上位10銘柄をウォッチリストに登録すると情報更新時にプッシュ通知が届き、売買タイミングを逃しにくくなります。
- 「テーマ検索 → レコメンドスコア確認 → AIチャート分析」の三段階フローを習慣化すると、調査効率が大幅に向上します。
今章では、楽天証券のAI分析が提供する三大コア機能を深掘りしました。
個別化スコアリング、確率論に基づくチャート予測、膨大な銘柄を瞬時に順位付けするランキングの三位一体により、投資判断のスピードと精度が飛躍的に向上します。
次章では、これらの機能をどのように組み合わせれば初心者でも短時間で最適ポートフォリオを構築できるのか、活用メリットを具体的な事例とともに解説します。
第4章 活用メリット—初心者でも効率よく銘柄選定できる理由

楽天証券のAI分析は、投資経験の浅いユーザーが抱えやすい「銘柄が多すぎて選べない」「データの読み方が難しい」「時間がない」といった課題を一気に解決します。
本章では 六つの具体的メリット を整理し、なぜ初心者でも短時間で質の高いポートフォリオを構築できるのかを解説します。
1. 情報収集の高速化—数クリックで市場を俯瞰
従来はスクリーナー設定やIR資料の確認に数時間を要しましたが、AIランキングはリアルタイムの統計処理を経て最大200銘柄を即時表示します。
テーマ検索や財務健全度フィルタを組み合わせれば、最短3分で「今見るべき候補リスト」が完成します。
2. 客観性の担保—エモーショナルバイアスを排除
機械学習モデルは統計的優位性のあるシグナルのみに基づいてスコアリングを行うため、相場ニュースに流されがちな感情的判断を抑制できます。
特に短期売買で陥りやすい「追い買い」や「狼狽売り」を回避しやすくなり、一貫したトレードルールの維持につながります。
3. 視覚的理解の容易さ—ヒートマップとレーダーチャート
総合スコアは色分けヒートマップ、財務要因はレーダーチャートで提示されるため、数字を並べるだけの従来型リストより判断が速く正確です。
たとえば赤系ほどリスクが高く、緑系ほどリスクが低いと直感的に認識できるため、初心者でも迷わず次のアクションに移れる利点があります。
4. 時間対効果の最大化—調査→売買をワンストップ
iSPEED アプリ内では「レコメンド → チャート分析 → 注文」まで同一画面で完結し、PC の MARKETSPEED II でもタブ一つで遷移できます。
これにより情報閲覧から発注までのリードタイムを半減でき、マーケットの急変に俊敏に対応可能です。
5. リスク管理の自動補助—確率レンジ表示とアラート
AIチャート分析が提示する期待レンジはボラティリティを反映して広狭が変動します。
乖離率やリスクスコアの急変はプッシュ通知でも届くため、リスク限度を視覚と数値で二重に管理できます。
ストップロス設定を事前に行えば、予想外の値動きにもシステマティックに対応できます。
6. 学習コストの低減—モデル因子の可視化で理解が深まる
スコア計算に寄与した主要因子(売上成長率・EPS 変化率・トレンド強度など)がバーグラフで開示されるため、「なぜこの評価なのか」を確認できます。
ブラックボックス感を排除しつつ “AI の思考過程” を学習教材として活用できる点は、今後の自己成長にも直結します。
今章のまとめ
楽天証券のAI分析は、高速・客観・視覚化の三拍子で情報処理を効率化し、初心者が抱えるハードルを大幅に引き下げます。
さらに自動アラートや因子開示といった補助機能によってリスクコントロールと学習効果も高められ、投資行動の一貫性と再現性が向上します。
次章では、このメリットを最大化するための具体的な操作手順とワークフローを、アプリとWebそれぞれの画面イメージを想定しながら解説します。
第5章 使い方ガイド—アプリとWebでの具体的な操作手順
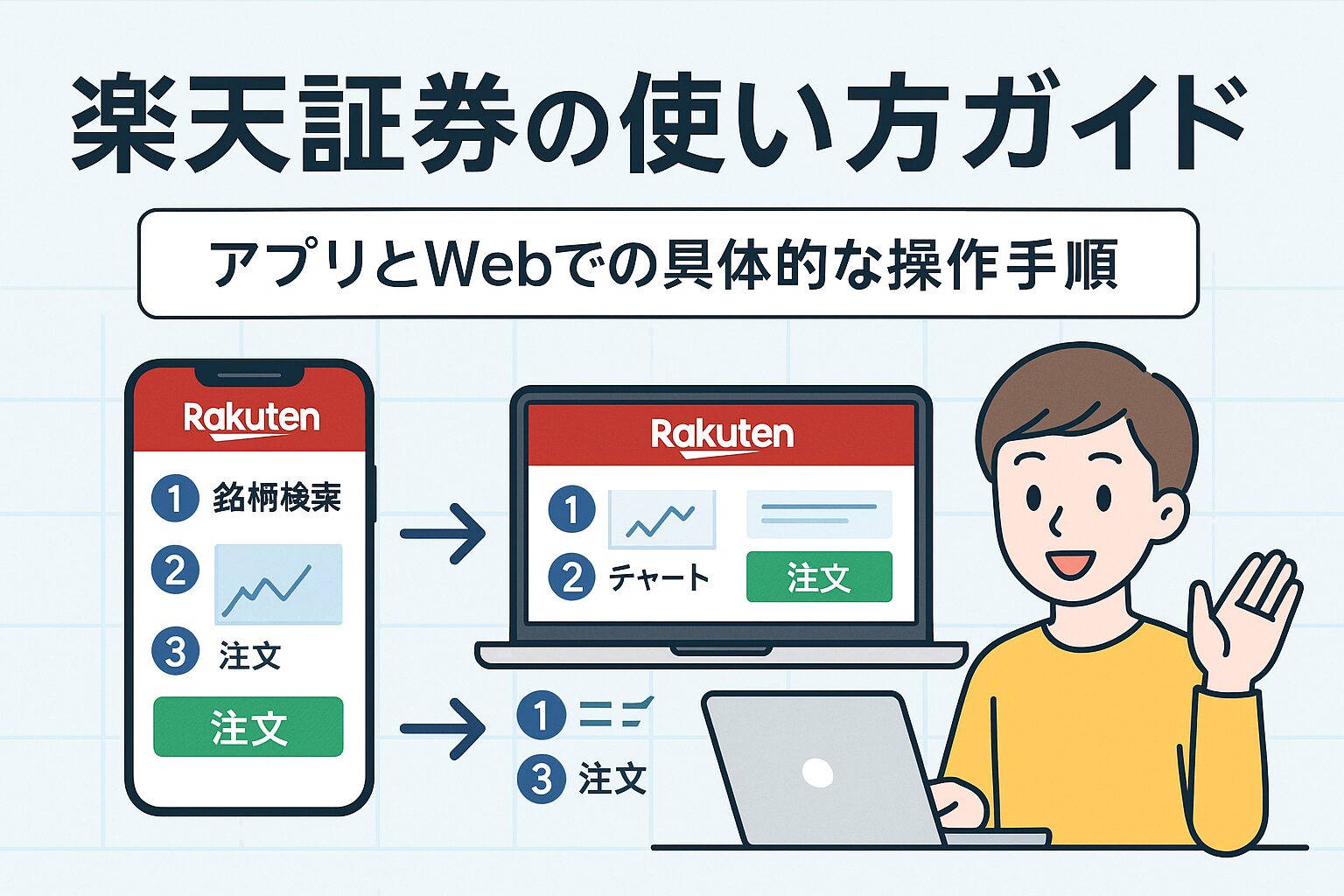
楽天証券のAI分析は、スマホアプリ「iSPEED」とPC向け取引ツール「MARKETSPEED II」、およびブラウザ版ウェブサイトの三つのインターフェースで同一機能を提供しています。
本章では、それぞれの画面遷移と設定ポイントを詳しく解説し、初回利用から日常運用までをスムーズに行うためのワークフローを紹介します。
5-1 アプリ「iSPEED」での操作フロー (所要時間 約3分)
- ログイン後ホーム画面
画面下部メニューの[マーケット]をタップし、上部タブからAI分析を選択します。
初回のみ簡易チュートリアルが表示されるので、ガイドに沿って進めてください。 - 銘柄レコメンドの確認
- 「あなたへのおすすめ」セクションに、AIが自動算出したスコア付き銘柄が一覧表示されます。
- 右上のフィルターアイコンをタップし、業種・時価総額・ボラティリティなどの条件を設定して絞り込みます。
- 気になる銘柄をタップすると詳細画面へ遷移し、スコア要因と目標株価、乖離率が確認できます。
- AIチャート分析でトレンドを把握
詳細画面の[AIチャート]タブを開くと、予測レンジとシナリオ別確率がチャート上に重ねて表示されます。- [期間]プルダウンで 1か月/3か月/6か月 を切替え、短期と中期の両面からリスクとリターンを比較しましょう。
- 画面右上の🔔アイコンでレンジ上限・下限アラートを設定できます。
- 株式ランキング生成を活用
[ランキング]タブでは、モメンタム・財務健全度・ESG など多軸のランキングをリアルタイムで閲覧可能です。- [テーマ検索]ボタンにキーワードを入力すると、関連キーワードを多用する銘柄の一覧が表示されます。
- 「+」ボタンでウォッチリストに登録すると、ランキング更新時にプッシュ通知を受け取れます。
- 注文までワンストップ
画面下部の[取引]ボタンをタップすると注文入力画面が開きます。
成行/指値/逆指値のほか、リスク通知連動ストップロスも事前設定でき、想定外の値動きに備えられます。
ポイント
- 通勤時間や休憩中など隙間時間で銘柄選定から発注まで完了できるため、仕事と投資を両立しやすいワークフローが構築できます。
5-2 PCツール「MARKETSPEED II」での操作フロー (所要時間 約5分)
- ログイン後ダッシュボード
画面左側ツリーの[マーケット情報]→[AI分析]をクリックします。
AIウィジェットがメインパネルに展開されます。 - 銘柄レコメンドの詳細検証
- 表示列のカスタマイズで 総合スコア・財務スコア・目標株価乖離率・短期トレンド を追加しておくと一覧比較がはかどります。
- 行をダブルクリックすると個別銘柄の「AIチャート+四半期業績推移」が分割表示され、ファンダメンタルズを併読しながら検討できます。
- AIチャート分析の拡張表示
チャート上で右クリック→[AIレンジ表示]をONにすると、直近パターンだけでなく過去100類似パターンの平均シナリオがヒートマップで重ね表示されます。- ボラティリティ指標(ATR・標準偏差)もワンクリックで追加でき、リスク幅を数値と視覚で同時に確認できます。
- ランキング生成とCSVエクスポート
AIランキングの右上メニューからCSV出力が可能です。
ExcelやPythonで独自バックテストを行いたい上級者は、ランキング→CSV→自前分析→再インポートのサイクルでカスタムスコアを作成できます。 - マルチモニター活用
MARKETSPEED IIはウィンドウを独立ポップアウトできるため、レコメンド一覧/チャート/ニュース/発注画面を4面配置すれば、イベント発生時も視線移動だけで即時トレードが可能です。
ポイント
- PCでは大量情報を同時表示できるため、スクリーニングとファンダメンタル分析を行い、最終確認と発注はスマホで行う“デュアルデバイス戦略”が効率的です。
5-3 ブラウザ版ウェブサイトでのクイックチェック (所要時間 約2分)
- ログイン後ヘッダーの[マーケット情報]をクリックし、サブメニューからAI分析を選択します。
- デフォルトで表示される「今日の注目銘柄」は、総合スコア上位20社を日次で自動更新しています。
- スマホと同じアルゴリズムながらレイアウトが1カラムに最適化されており、会社PCやタブレットからでも短時間でマーケット状況を把握できます。
5-4 ワークフロー例—朝5分・夜10分で完結する日次ルーチン
| 時間帯 | デバイス | 操作 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 7:30 出勤前 | スマホ | レコメンド上位10銘柄を確認→ウォッチリスト更新 | その日の注目銘柄を把握 |
| 12:15 昼休み | スマホ | AIチャートのレンジ拡大銘柄にストップロス設定 | リスク増大銘柄を監視 |
| 19:00 帰宅後 | PC | ランキング生成→スクリーニング条件を微調整→CSV出力 | 中長期候補を追加選定 |
| 22:00 夜間 | スマホ | 新規候補の目標株価乖離率を確認→発注 | 翌営業日の指値注文準備 |
今章のまとめ
スマホアプリ、PCツール、ウェブブラウザの三つのインターフェースは共通アルゴリズムながら操作性に特色があり、場面に応じて最適デバイスを使い分けることで調査効率とトレード速度を最大化できます。
朝の短時間で市場全体を俯瞰し、昼にリスクを微調整、夜に深掘り分析と発注準備というルーチンを確立すれば、忙しい社会人でもデータドリブンな資産運用が実現します。
次章では、実際のユーザーがどのようにAI分析を活用して成果を上げたのか、成功体験と失敗例を交えて紹介します。
第6章 ユーザーの声と活用事例—成功体験から学ぶベストプラクティス

楽天証券のAI分析は、投資歴や運用スタイルの異なる利用者から多彩なフィードバックが寄せられています。
本章では、実際に成果を上げた代表的な三つのケーススタディと、そこから導かれるベストプラクティスを紹介します。
数値データや運用フローを具体的に示しながら、読者が明日から実践できる活用法を整理します。
ケース1 兼業投資家Aさん—朝の隙間時間で月次+7%を達成
プロフィール
- 年齢:35歳
- 投資経験:2年
- 運用資金:300万円
- 売買スタイル:スイング(保有期間 1〜2週間)
活用方法
- 出勤前にiSPEEDでAIランキング「上昇モメンタムTOP50」をチェック
- 総合スコアA以上かつ5日騰落率+10%未満の銘柄を3つ選定
- AIチャートで上昇継続確率60%以上を確認し、逆指値付き成行でエントリー
- 目標株価乖離率+15%に到達したら半分利確、残りはトレailingストップで追従
結果
平均保有6営業日で月次リターン+7%を継続。
損切りラインをAIレンジ下限に連動させることで、最大ドローダウンを−3%以内に抑制。
学び
- AIランキング→チャート確認→即発注の三段階をテンプレ化すると朝15分で完結
- 逆指値とトレーリングを併用すれば、仕事中の値動きも自動で管理できる
ケース2 主婦投資家Bさん—配当重視ポートフォリオで年次+12%を実現
プロフィール
- 年齢:46歳
- 投資経験:1年
- 運用資金:500万円(NISA枠含む)
- 売買スタイル:中長期保有・高配当重視
活用方法
- MARKETSPEED IIでAIランキング「財務健全度TOP50」をCSV出力
- 自己資本比率60%以上・配当利回り3%以上でフィルタリングし20銘柄に絞り込み
- 各銘柄のレーダーチャートでキャッシュフロー安定性スコアを確認
- ポートフォリオに均等配分し、四半期ごとにスコアを再チェックしてメンテナンス
結果
配当込み年次リターン+12%(TOPIX配当込み+9%をアウトパフォーム)。
銘柄入替は年間2回のみで、家事と育児の合間でも無理なく運用を継続。
学び
- 財務スコアと配当利回りを同時に満たす銘柄を選ぶことで、下落局面でも心理的負担が軽減
- CSV活用により、エクセルで独自スコアを足しても作業時間は週30分以内
ケース3 大学生Cさん—テーマ投資で資金30万円を半年で+40%
プロフィール
- 年齢:20歳
- 投資経験:半年
- 運用資金:30万円
- 売買スタイル:テーマ株短期集中
活用方法
- ウェブ版のテーマ検索にキーワード「生成AI」「EV充電」を入力
- 出力された銘柄を乖離率順に並べ替え、−5%以上で総合スコアA−以上を3銘柄選択
- AIチャートでレンジ幅とボラティリティを確認し、短期資金を分散投資
- 乖離率が±0%に戻った時点で全株売却し利益確定
結果
6か月間でトータルリターン+40%。
小型成長株に絞る代わりにエントリー回数を月4回に抑え、手数料とリスクをコントロール。
学び
- テーマ検索はトレンドの初動検知に有効だが、乖離率管理で過熱感を必ずチェック
- 小資金でも分散と出口ルールの徹底でリスクを限定できる
ベストプラクティス—成功者に共通する5つの行動原則
- テンプレート化:レコメンド→チャート→発注の固定フローを確立し、意思決定を時短
- リスク連動型注文:AIレンジ下限や乖離率を基準に逆指値やトレailingストップを設定
- 定期メンテナンス:四半期決算やランキング更新のタイミングでポートフォリオを点検
- データエクスポート活用:CSVやエクセル連係で独自分析を加え、AIスコアを自分流に拡張
- テーマと財務の両輪:旬のテーマ株でも財務健全度スコアを確認し、過度なリスクを回避
今章のまとめ
ユーザー事例から浮かび上がる共通項は、AI分析を「盲目的に頼る」のではなく「自分のルールに組み込む」ことです。
スコアリングとレンジ表示で市場の大枠を把握しつつ、逆指値・トレーリング・定期点検など人間の裁量を組み合わせることで、リスクを抑えつつ安定的なリターンを実現しています。
次章では、AIでは補いきれないリスクと限界を整理し、ヒューマンジャッジと併用するための実践的ガイドラインを解説します。
第7章 AI分析の限界とリスク管理—人間の判断が必要な場面とは

楽天証券のAI分析は高度な機械学習アルゴリズムを駆使していますが、万能ではありません。
AIが苦手とする領域や想定外の事象に備えるためには、投資家自身の判断とルール設定が欠かせません。
本章では、AI分析が直面する主な限界と、それを補完するためのリスク管理の実践ポイントを整理します。
7-1 モデルの前提条件とデータ依存性
- 過去データへの依存
AIモデルは過去の株価・財務・ニュースデータを学習して将来を推定します。
したがって、想定外の出来事(自然災害、地政学リスク、規制変更など)が起きた場合、モデルは即応できません。 - 統計的平均化の落とし穴
機械学習は大量サンプルを前提とした平均的シナリオを提示するため、個別銘柄の極端な動き(合併、上場廃止、新薬承認など)を精緻に予測するのは困難です。 - データ品質の影響
開示ミスや遅延が発生すると、一時的にスコアが歪む可能性があります。
特に中小型株は開示情報が限定的で、AIの精度が低下しやすい点に注意が必要です。
7-2 AIが不得手な三つの局面
| 局面 | 説明 | 投資家の対策 |
|---|---|---|
| ブラックスワン | 想定外かつ影響が大きい出来事(大規模テロ、パンデミック) | ポートフォリオの分散と現金比率の確保 |
| 政策ショック | 政府・中央銀行の突発的な政策変更(為替介入、規制強化) | 経済指標カレンダーや要人発言スケジュールを事前確認 |
| 低流動性相場 | 売買高が極端に減少しスプレッドが拡大 | 板厚と出来高を監視し、逆指値幅を広めに設定 |
7-3 人間の判断が活きる五つのチェックポイント
- ファンダメンタルの深読み
AIが提示するレーダーチャートに加え、事業ポートフォリオや競合優位性を企業IR資料で確認します。 - イベントカレンダーの併用
決算発表や経済指標の発表日は、AIレンジよりボラティリティが拡大する可能性があるため、ポジション縮小やヘッジを検討します。 - 市場センチメントの把握
SNSや掲示板での言及件数が急増する場合、短期的な過熱感を示唆することがあり、AIスコアだけで安心せず警戒が必要です。 - リスク許容度の再評価
年齢・収入・投資経験の変化に合わせて、逆指値幅や資金配分を更新し、AI推奨銘柄が自分のリスクプロファイルに適合するかを点検します。 - 代替シナリオの策定
AIが想定するメインシナリオが外れた場合のプランB・プランCをあらかじめ用意し、状況に応じて迅速に切り替えられるようにします。
7-4 実践的リスク管理ツールの活用
- 逆指値・OCO・IFD注文
AIチャートのレンジ下限やATR(平均真の値幅)を目安に逆指値を設定し、損失を限定します。
OCO注文で利益確定と損切りを同時に発注すれば、相場急変時も自動でポジションが管理できます。 - ボラティリティ連動ストップロス
ATRが急拡大した際に自動でストップ幅を広げる設定を利用し、ノイズに引っ掛かりにくい損切りルールを構築します。 - ポートフォリオ分散シミュレーション
MARKETSPEED IIのポートフォリオ分析機能で業種・地域・時価総額の分散状況を可視化し、同一リスク因子への集中を回避します。
7-5 メンタルマネジメントとAIの役割分担
AI分析は合理的な数値判断を提供しますが、実際の売買時には恐怖・欲望・後悔といった感情が介入します。
- ルールの自動化:AIのレンジ下限と逆指値を連動させ、感情的な判断を事前に排除
- 取引日誌の記録:売買の理由と感情状態をログに残し、AI推奨と実際の行動差分を検証
- 休息の取り方:連敗時は一時的にトレードを停止し、AIチャートのボラティリティ縮小を待つなど、メンタルをリセットするルーチンを設けます。
今章のまとめ
楽天証券のAI分析は、多角的なデータ解析と視覚化によって投資判断を大幅に効率化しますが、ブラックスワンや政策ショック、低流動性相場などの不確実性には限界があります。
AIの数値を鵜呑みにせず、ファンダメンタル確認やイベントリスク管理、ポジション調整といったヒューマンジャッジを重ねることで、想定外の局面でも冷静に対処できます。
次章では、楽天グループのAI戦略や今後予定されている機能拡充を踏まえ、投資環境がどのように進化していくのかを展望します。
第8章 今後の展望—楽天グループのAI戦略と証券サービスの進化

8-1 2025年7月「完全無料化」がもたらすゲームチェンジ
2025年7月27日、楽天証券は国内・米国株のAI分析データを口座保有者全員に無償提供しました。
従来は米国株のみ対象だったサービスを国内株へ拡張し、機能制限も撤廃したことで、投資家の情報格差はほぼゼロへ近づきました。
無料化によりユーザー母数が急増すると同時に、モデルへのフィードバックデータも指数関数的に増え、アルゴリズムの改善サイクルがさらに高速化することが期待されています。
8-2 NISA・投資信託領域へのAI拡張
楽天証券は2025年後半から、新NISA積立枠や投資信託向けにもAIスコアリングの適用範囲を広げる方針を公表しています。
ファンド選定では運用コストやトラッキングエラーのほか、銘柄組み入れの重複度合いまで自動診断し、最適な組み合わせを提案する「AIファンドセレクター(仮称)」を開発中です。
これにより個人投資家は、分散効果と手数料効率を同時に満たすポートフォリオを数クリックで構築できるようになります。
8-3 楽天経済圏データ連携と“Hyper Personalization”
楽天カード・楽天市場・楽天ペイに蓄積された購買データを解析し、消費行動と株価トレンドをリアルタイムに結び付けるシグナルを生成する実証プロジェクトが進行中です。
たとえば家電の買い替え需要が急増した際に、関連銘柄のモメンタムを早期検知してレコメンドに反映するなど、経済圏横断の“Hyper Personalization”が実現すれば、AI分析は単なる株価予測ツールから総合的な資産ライフスタイル提案エンジンへ進化します。
8-4 「かぶピタッ™」×AIで少額投資を民主化
2025年7月に開始した100円単位の国内株金額指定取引サービス「かぶピタッ™」とAI分析を組み合わせることで、評価スコアAの銘柄をワンタップ100円から購入する導線がアプリに実装されました。
これにより、投資初心者や学生でもAI推奨ポートフォリオを少額でテストでき、PDCAサイクルを早期に回すことが可能になります。
少額ゆえに心理的ハードルが低く、投資人口拡大の起爆剤として期待されています。
8-5 外部連携とオープンAPI戦略
2025年7月には、みずほ銀行の「みずほダイレクトアプリ」に楽天証券残高を表示するAPI連携が始まりました。
今後は他行・フィンテック企業とのオープンAPIを拡充し、外部プラットフォームでもAIスコアを参照できる環境を整備する計画です。
複数の金融口座をまたいだ一元的リスク管理や、家計簿アプリとの自動連係によるキャッシュフロー最適化など、証券サービスを越えた顧客体験の統合が実現します。
8-6 次世代AI機能ロードマップ
| 時期 | 予定機能 | 主な内容 | ユーザー便益 |
|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | AIファンドセレクターβ | 投資信託をコスト・運用実績・資産重複率でスコア化 | 新NISA積立の銘柄選びを自動化 |
| 2026年上期 | リアルタイムAIスコア更新 | チャート、決算速報、ニュースをストリーム処理 | スコア反映を日次→分単位へ高速化 |
| 2026年下期 | 生成AIチャットアシスタント | スコアの根拠や投資テーマを自然言語で質疑応答 | 専門知識がなくても深い洞察を得られる |
| 2027年 | ESG&サステナビリティAI評価 | 企業の非財務データを統合しESGリスクを数値化 | 長期投資家のリスク管理を高度化 |
8-7 まとめ
楽天証券は“無料化→多資産対応→経済圏連携→外部API開放”という四段階のロードマップを明確に示し、AI分析をコアとしたフィンテックエコシステムを構築しつつあります。
これにより、ユーザーは少額投資から高度な分散ポートフォリオまでをワンストップで最適化でき、さらには生活データを活用したパーソナライズ戦略によって、資産運用と日常消費がシームレスにつながる世界が現実味を帯びてきました。
次章では、本稿で取り上げた全機能を総括し、AI分析を最大限活用するための実践的アクションプランを提案します。
第9章 まとめ—楽天証券AI分析を味方に資産運用を加速する五つのアクションプラン

本記事では、楽天証券のAI分析機能を中心に、その概要から具体的な操作方法、ユーザー事例、限界と今後の展望までを体系的に解説しました。
最後に、これらの知見を実践へ落とし込むための 五つのアクションプラン を提示し、読者が明日から取れる具体的ステップを整理します。
1. レコメンド→チャート→注文の“三段階フロー”をテンプレ化する
- 毎朝 iSPEEDでレコメンド上位10銘柄を確認し、気になる銘柄をウォッチリストへ追加します。
- 出勤時間など隙間時間でAIチャートをチェックし、上昇継続確率60%以上の銘柄をピックアップします。
- マーケット開始前に逆指値付き成行を設定し、仕事中は自動執行に委ねます。
効果 情報収集から発注までを15分以内に短縮し、相場急変時の機会損失を防ぎます。
2. AIレンジ下限とATRを基準に逆指値を自動連動させる
- MARKETSPEED IIでボラティリティ連動ストップロス機能をONにし、ATR×2倍を初期設定にします。
- AIチャートでレンジ幅が拡大した場合はストップ幅も自動的に広がり、ノイズ損切りを抑制します。
効果 損切りを“数値ルール”に落とし込み、メンタルブレを最小化できます。
3. テーマ検索+財務健全度スコアで分散ポートフォリオを構築する
- キーワード検索で旬のテーマ株を抽出し、財務スコアA以上に限定してリスクを低減します。
- NISA枠では配当利回り3%以上の財務健全銘柄を積立し、短期テーマ株とのハイブリッド運用を行います。
効果 成長ポテンシャルと堅実配当を両立し、マーケットサイクルに左右されにくい資産構成を実現します。
4. 四半期ごとにCSVをエクスポートして自前分析を加える
- ランキング生成画面からCSVを出力し、ExcelやPythonでオリジナル指標(例:配当×成長率)を算出します。
- AIスコアと自作スコアを比較し、乖離が大きい銘柄を深掘り調査の優先リストに設定します。
効果 AI分析を“ブラックボックス”にせず、独自視点を掛け合わせて投資精度を向上させます。
5. ライフスタイル連携で“Hyper Personalization”を先取りする
- 楽天カードや楽天ペイで主要支出を集約し、購買データとポートフォリオの相関を確認します。
- 家計簿アプリ連携APIが公開されたら即接続し、収支・投資・ポイントを一元管理します。
効果 生活データと投資情報がシームレスに結び付き、資産形成に最適化された消費行動が可能になります。
総括
楽天証券のAI分析は、高速性・客観性・視覚的分かりやすさを兼ね備え、初心者から上級者まで幅広い投資家にとって強力な武器となります。
無料化と多資産対応により情報格差はさらに縮小し、今後はNISAや投資信託、経済圏データ連携を通じて“Hyper Personalization”が現実のものとなるでしょう。
- 初心者 はワンタップ100円投資とAIレコメンドで市場参加のハードルを下げ、
- 中級者 は逆指値自動連動とテーマ検索でリスクとリターンのバランスを最適化し、
- 上級者 はCSVエクスポートと自作指標でAIを拡張し、競合優位を保てます。
本稿で提案した五つのアクションプランを実践し、AI分析を“使い倒す”習慣を構築することで、あなたの資産運用は次のステージへと進化します。
いまこそ、楽天証券AI分析を味方にデータドリブンな投資戦略を加速させましょう。
【たったの5分で申込完了】
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
