※本ページはプロモーションが含まれています。
はじめに「ドラゴンボール風動画」で収益化できるって本当?

近年、AI技術の進化により、個人でも手軽にアニメ風動画を制作できるようになりました。
特に人気アニメ「ドラゴンボール」のような世界観やキャラクタースタイルを模した“ドラゴンボール風AI動画”が、SNSやYouTubeなどで大きな注目を集めています。
こうした背景の中で、「AIでドラゴンボール風の動画を作ってお金を稼げるのでは?」と考える方が増えてきました。
結論から言うと、条件を守れば収益化は可能です。
ただし、そこには著作権や商標権に関する重大なリスクが潜んでおり、単純に“似せて作るだけ”ではすぐに警告や削除の対象となる可能性もあります。
この記事では、そんな疑問を抱える読者の方に向けて、以下の内容を詳しく解説していきます。
- AIで「ドラゴンボール風動画」はどこまで作れるのか?
- 収益化における著作権・商標の注意点とは?
- 実際に収益化できるケースとNGなパターン
- オリジナルキャラで合法的にマネタイズする方法
- YouTubeやTikTokでの審査基準と対策
- 今後の展望と“攻め方”の戦略
ドラゴンボールが好きで、インスパイアされた作品を作ってみたい。
そんな想いを“合法的かつ創造的”に形にするための、完全ガイドとして、ぜひ最後までお読みください。
AIで作れる「ドラゴンボール風動画」とは?人気ツールと事例

「ドラゴンボール風のAI動画って本当に作れるの?」という疑問に対し、答えはイエスです。
現在、AIによるアニメ風表現は驚くほどリアルかつ多様化しており、簡単なプロンプト(指示文)を入力するだけで、まるで鳥山明先生のタッチを彷彿とさせるキャラクターや背景を自動で生成することが可能になっています。
ここでは、実際に使われている人気ツールや、SNS上で話題となっている事例を紹介しながら、その可能性を具体的に解説します。
AnimeGenius|アニメ特化の画像生成AI
AnimeGeniusは、アニメスタイルに特化した画像生成AIで、「超サイヤ人風の髪型」「筋肉質なシルエット」「エネルギー波を放つ演出」など、ドラゴンボールらしさを感じるビジュアルを驚くほど高精度で生成できます。
日本語対応のプロンプトにも対応しており、初心者でも扱いやすい点が魅力です。
たとえば、
- 「超戦士 金髪 オーラ 空中戦」
- 「宇宙で戦う エネルギー球 筋肉のある少年」
といったキーワード入力だけで、ドラゴンボール風のワンシーンを演出できます。
Promptchan|シーン別に構図を指定できる万能ツール
Promptchanは、プロンプトをカスタマイズして背景・ポーズ・構図などを詳細に指定できる画像生成サービスです。
キャラ1体だけでなく、複数のバトルシーンやパースの効いた構図も得意で、アニメの1カットのような絵作りが可能になります。
バトル中の静止画やコマ風のカット作りに最適で、漫画動画の素材制作にも活用されています。
Runway ML × Filmoraで動画化
画像生成だけでなく、Runway MLの「Text to Video」機能や、CapCutでの編集機能を組み合わせることで、静止画を動画化し、モーションや効果音を加えた「動くドラゴンボール風動画」を作成することができます。
爆発エフェクト、カメラの揺れ、ズーム効果を取り入れることで、まるで本物のアニメのような仕上がりにすることも可能です。
SNSで話題のバズ事例
実際に「ドラゴンボール風AI動画」でバズった例もいくつかあります。
- TikTokにて「超サイヤ人になってみた風AIアニメーション」で10万再生突破
- YouTube Shortsで「オリジナル超戦士の覚醒」を描いたAI漫画動画がコメント殺到
- Instagramリールで「悟空風キャラ vs フリーザ風キャラ」のファンアート動画が拡散
ただし、これらの動画は「完全にオリジナルで似せすぎていない」ことが前提です。似すぎていたり、名称やBGMを無断使用していた場合、削除対象となった事例もあります。
注意点:便利でも法的責任は自分にある
どれほど優れたAIツールを使っても、生成された作品を公開・収益化するのは人間です。
著作権侵害や商標リスクを回避する知識がなければ、AIは“凶器”にもなり得るということを忘れてはいけません。
次章では、この「そっくり作品」がなぜ法的に危険なのか、著作権と商標の視点から詳しく解説します。
なぜ「ドラゴンボール風」は危険?著作権と商標の基本知識
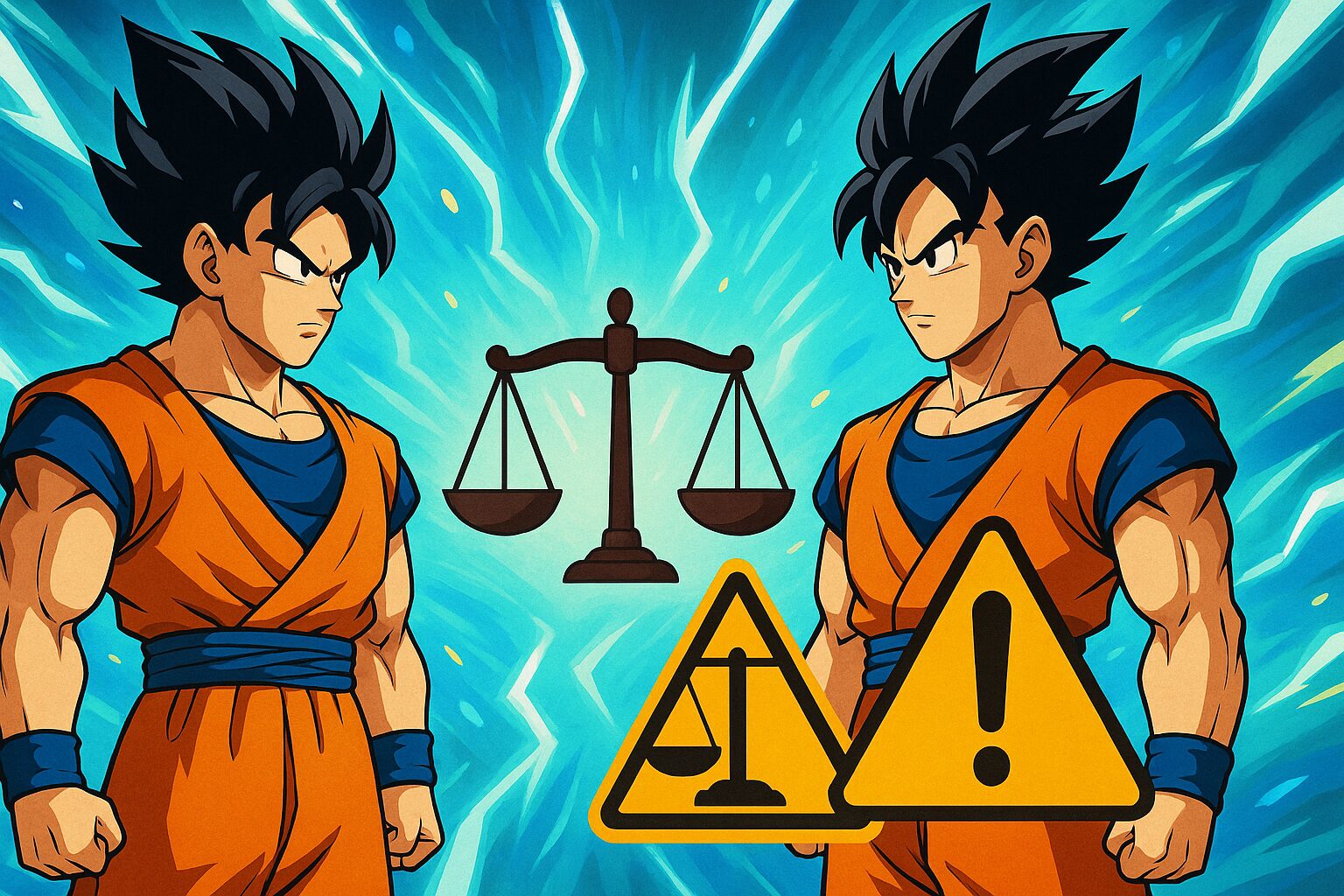
AIで「ドラゴンボール風」の動画やキャラクターを制作すること自体は、技術的に可能です。
しかし、それをネット上に公開したり、収益化を図ったりする行為には、重大な法的リスクが潜んでいます。
この章では、なぜ“そっくり作品”や“パロディ風コンテンツ”が危険なのか、著作権と商標の基本的な考え方を中心に解説します。
著作権とは何か?創作物を守る法律
著作権とは、創作された作品(絵、音楽、映像、文章など)に対して自動的に与えられる保護権のことです。
つまり、誰かが描いたキャラクターや作ったストーリーには、その人(または企業)に使用・複製・配布などを許可する独占的な権利があるということです。
「ドラゴンボール」の場合、原作のキャラクターデザイン、ストーリー、名称などは鳥山明氏および集英社・東映アニメーションの著作物として保護されています。
商標権とは?名前やロゴも守られている
一方で商標権とは、ブランドや商品名、ロゴなどを守るための法律です。
たとえば「悟空」や「ドラゴンボール」といった名称、「カメハウスのマーク」「Zのロゴ」「界王拳」なども登録商標である可能性があり、無断使用すると商標侵害となります。
重要なのは、「名前を変えても見た目や印象が似ていれば商標としてアウトになる」ケースがある点です。
パロディやオマージュはOKなのか?
「これはファンアートだから大丈夫」「オマージュ作品だし収益化してないからセーフ」という考えは、多くの場合通用しません。
著作権侵害は営利・非営利に関わらず成立するものであり、パロディであっても原作に似すぎていたり、商用目的であれば、訴えられる可能性が十分にあります。
特にドラゴンボールのような大手IP(知的財産)に対しては、企業側の法的対応が非常に厳しいことが知られています。
よくある勘違い「AIが作ったからセーフ」
AIが自動で生成したキャラやシーンであっても、その作品を投稿・販売・収益化するのは“人間”の責任です。
「AIが作ったので自分は関係ない」という主張は法的には通らず、その使用者が責任を負うことになります。
まとめ:リスペクトと無断使用は違う
クリエイターとして好きな作品にインスパイアされることは自然なことです。
しかし、その“想い”が強すぎて「限りなく似せた」作品を発表すると、それは単なる盗用と受け取られる危険性があります。
合法的に活動を続けるためには、「どこまでがリスペクトで、どこからが侵害になるのか」を正しく理解し、線引きを守る姿勢が欠かせません。
AIで作った“ドラゴンボール風キャラ”に著作権はあるのか?

AIを活用すれば、驚くほどリアルで“それっぽい”キャラクターを簡単に作り出せる時代になりました。
特に、ドラゴンボール風の筋肉質な戦士や、エネルギーをまとったキャラなどはSNS映えし、バズを狙いやすいコンテンツです。
しかし、こうしたAI生成キャラクターには、著作権があるのでしょうか?そして、そのキャラクターを使って収益化しても問題ないのでしょうか?
この章では、AI生成キャラに関する著作権の有無と“似ているだけ”でも違法になる可能性について詳しく解説します。
AI生成物に著作権は発生するのか?
日本の著作権法においては、著作物と認められるためには「人の創作的関与」が必要とされています。
つまり、AIが完全自動で生成したイラストや動画は、原則として著作権が発生しないと解釈される可能性が高いです。
ただし、人がプロンプトを工夫し、複数の素材を組み合わせて編集を加えるなどの「創作的行為」を行っていれば、その成果物には著作権に準じた扱いが与えられる場合があります。
とはいえ、それはあくまで「自分がオリジナルとして作った場合」に限られます。
似ているだけでもNG?ドラゴンボール風の危険性
仮にあなたがAIで作成したキャラクターに著作権があるとしても、そのキャラが「既存の著作物に酷似している」場合は話が別です。
たとえば、
- 髪型や筋肉のつき方が悟空にそっくり
- 背景にナメック星や天下一武道会風の建物がある
- 必殺技のエフェクトがかめはめ波そっくり
このような場合、「二次的著作物」や「著作権侵害」として扱われる可能性が高くなります。
特に商用利用や収益化をする際には、企業側が黙っていないことが多く、YouTubeでの削除申立、SNSでのアカウント凍結、さらには法的措置まで発展するケースも報告されています。
「オリジナルです」と言い張っても通用しない
SNSや動画のコメント欄で、「これはAIが自動生成したもので、既存作品とは無関係です」と説明していても、それだけで著作権リスクが回避されるわけではありません。
判断基準はあくまで第三者(一般視聴者や著作権者)が見てどう感じるかです。
似ていると認識されれば、それだけでトラブルの火種になりかねません。
過去に起きた問題事例
- AIで生成された“超サイヤ人風キャラ”をNFT化して販売 → 削除&購入者から返金要求
- TikTokでドラゴンボール風漫画動画を投稿 → 再生数は伸びたが、通報されてBAN
- YouTubeで「悟空そっくりなオリキャラ」のアニメを投稿 → 著作権侵害でチャンネル停止
これらはすべて、「似てるだけ」「名前を変えただけ」では通用しないことを証明する実例です。
安全に創作するためには
- 完全に異なる見た目、名前、背景、設定にする
- キャラのポーズや構図も意識的にオリジナルにする
- 「連想させるが一致しない」絶妙なバランスを追求する
次章では、こうした法的リスクを現実に引き起こす「収益化NGの具体例」について、実際のトラブルパターンとともにご紹介します。
収益化NGの具体例|炎上・削除・警告になりやすいパターン

ドラゴンボール風のAI動画を作り、YouTubeやTikTokで投稿して収益化を狙う。
このアプローチは一見魅力的ですが、実際には「収益化NG」とされるパターンが数多く存在します。
ここでは、AIコンテンツでやりがちな違反行為や、実際に起こった削除・炎上・警告の事例を紹介し、何がNGだったのかを明確にしていきます。
NG例1:名前だけ変えた“ほぼ悟空”キャラで収益化
あるYouTuberが、AIで作成した「スーパーバースト」というキャラクターを使って漫画風アニメを投稿。
キャラは金髪、オレンジの道着、エネルギーをまとった姿で、誰が見ても“悟空にしか見えない”内容でした。
結果、1週間で5万再生を記録するも、東映アニメーションから著作権侵害の申し立てが入り、動画削除+チャンネル収益化停止という処分に。
このように、「名前が違っても見た目が酷似している」場合は、二次創作の範囲を超えた侵害と判断されます。
NG例2:ドラゴンボール風キャラをNFT販売
AIで生成した“悟空風キャラ”を使ったNFTアートがOpenSeaなどで出品されるケースもありました。
デザインはオリジナル要素も含まれていましたが、髪型や道着が明らかにドラゴンボール風。
結果、削除要求が出され、出品者アカウントは停止処分。購入者には返金が行われる事態となりました。
NFTのように販売・所有権の移転が関わるコンテンツでは、企業側のチェックも厳しく、商標・著作権違反が即問題視されます。
NG例3:音楽や効果音の無断使用
TikTokで「悟空風キャラがかめはめ波を放つ」短編動画を投稿したクリエイターが、原作アニメの効果音やBGMをそのまま使用。
動画は瞬く間に10万再生を突破しましたが、数日後に音源の著作権侵害で削除されました。
効果音やBGMも立派な著作物であり、音だけでも著作権侵害は成立します。
動画のクオリティが高くても、音声素材でアウトになることがある点に注意が必要です。
NG例4:原作キャラの名前や用語の乱用
「カメハメ波」「フリーザ」「サイヤ人」など、原作特有の用語を動画内やタイトル・タグに使用するのもリスクが高い行為です。
Google検索経由で流入を増やす目的でも、商標権を侵害する表現を含めてしまうと、プラットフォームから削除・警告対象になる可能性があります。
一見セーフでも通報でアウトになることも
YouTubeやTikTokは、著作権者からの申し立てだけでなく、一般ユーザーからの通報でも対応が行われることがあります。
特にフォロワーが増えてバズった後ほど、「パクリでは?」といった声が上がりやすく、結果的に炎上・削除へと発展するケースも多いのです。
収益化が目的なら、限界ラインを知るべき
SNS上には“ギリギリセーフ”に見える動画が溢れていますが、それを真似してもあなたが同じ結果になる保証はありません。
企業の対応はタイミングや内容により変動します。
収益化を目指すなら、「これは100%自分のオリジナルである」と言えるレベルの作品だけに絞るべきです。
合法的に収益化する方法|3つのマネタイズ戦略

これまでの章で、「ドラゴンボール風AI動画」を無断で収益化しようとすることが、著作権・商標の観点から大きなリスクを伴うことを説明してきました。
では、どうすればそのリスクを避けながら、合法的かつクリエイティブに収益化できるのでしょうか?
ここでは、現実的かつ実践可能な3つの収益化戦略をご紹介します。
戦略1:完全オリジナルキャラでブランドを構築する
もっとも確実な方法は、完全に自分で設計したキャラクターと世界観を用いてコンテンツを制作することです。
AIツールは便利ですが、その生成結果をそのまま使うのではなく、以下のような工夫を加えることが重要です。
- キャラクター名や設定を自分で考案
- 見た目のデザインや服装、色彩もオリジナル
- ストーリーやセリフも独自の構成で展開
これにより、知的財産権を自分で保持できるため、収益化だけでなくグッズ化・書籍化・NFT展開などの幅広い展開も可能になります。
戦略2:商用フリー素材とライセンス確認済みのAIを活用
「ゼロから作るのは難しい」「デザイン力がない」と感じる方は、商用利用が許可された素材やAIツールを組み合わせる方法がおすすめです。
以下の点をチェックしましょう。
- 利用するAIツールの利用規約に「商用利用可」とあるか
- 画像・音楽・効果音などの素材が商用フリー(またはライセンス購入済)か
- 有料プランに切り替えることで、商用許可が得られるケースも多い
たとえば、Runway ML(商用OKプラン)、Leonardo AI(生成画像の商用許可)などは収益化前提の動画制作に適しています。
戦略3:知的財産に触れない“構成と演出”で勝負する
キャラクターやデザインはオリジナルにしても、演出や構成は「ドラゴンボール風」に近づけることが可能です。
以下のような工夫で、オマージュの雰囲気を出しながらも、法律的には安全圏で勝負できます。
- 「修行」「覚醒」「対決」などの王道展開を使う
- 背景や戦闘シーンを似ていないがインスパイアされた構図で再現
- 効果音やエフェクトもオリジナル音源や自作素材を使用
このように、「雰囲気は近いけど中身はまったく別物」となることで、視聴者の興味を引きつけながら、収益化の安全圏に留まることが可能です。
補足:オリジナリティは審査でも重要
YouTubeやTikTokの収益化審査においても、“そのコンテンツが誰のものか”を判断するポイントとして、「オリジナリティの有無」は非常に重要です。
AI作品であっても、以下のような工夫をしていれば、自分の創作物として認められる可能性が高くなります。
- ナレーションや解説の追加
- シナリオやセリフに創作性を持たせる
- 複数の素材を組み合わせて独自性を高める
「似てるけど違う」デザインとは?安全な“風”キャラの作り方

ドラゴンボールのような世界観に影響を受けた作品を作りたい。でも著作権や商標リスクは避けたい。
そのようなクリエイターにとってカギとなるのが、「似てるけど違う」キャラクターデザインの発想です。
この章では、ファンにとって魅力的でありながら、法律的にはオリジナルと認められる“風キャラ”の作り方について解説します。
視覚的に似せすぎないバランスがポイント
オマージュ作品やインスパイアされたコンテンツでは、「どこまでならセーフか」が曖昧になりがちです。
重要なのは、要素のコピーではなく“雰囲気の再構成”を意識することです。
たとえば、ドラゴンボールの特徴的なデザインである以下の要素には特に注意が必要です。
- トゲトゲの金髪+オーラ → 形状や色合いを変えて独自性を出す
- 道着(胴着)のデザイン → 色やマークを変更し、異なる文化の衣装にする
- 顔のパーツ配置 → 目の形や輪郭を変えて別の印象に
つまり、「なんとなく似てるけど、違う」と感じさせることが鍵になります。
髪型・色・服装の工夫で差別化を図る
髪型や色使いは視覚印象を大きく左右するため、次のようなテクニックを活用して差別化を図りましょう。
- 髪の毛のボリュームや流れ方を逆にする(例:上ではなく横方向へ跳ねる)
- カラーリングを反転させる(例:金→青、赤→緑など)
- 服装を民族衣装風・近未来風など異ジャンルに寄せる
また、アクセサリー(腕輪、イヤリング、マントなど)を加えることで、“自分だけのキャラ”感を強調することも有効です。
名前のネーミングルールで完全オリジナルへ
キャラ名が「カカロット」や「悟空」に似ているだけでも、商標リスクが高くなります。
以下のようなネーミング法でオリジナル性を演出しましょう。
- 完全な造語(例:ザルフェス、ブリオンなど語感重視)
- 意味を持たせた異国風の名前(例:ファラント=「戦う者」)
- 植物・鉱石・天体などの単語を組み合わせる
ネーミングが独創的であればあるほど、“ブランド化”もしやすくなり、商業展開の可能性が広がります。
背景設定や性格でキャラクターを深くする
キャラの外見だけでなく、物語や内面を明確に設定することで、唯一無二のキャラとして成長させることができます。
- 出身地、育った環境、信念、苦手なことなどの設定を考える
- “強さ”以外の個性(臆病、優柔不断、ナルシストなど)を加える
- 対立キャラや師匠など、周囲との関係性を描く
これらの要素が加わることで、視聴者にとっても“本物らしい”キャラに映り、作品としての魅力が大幅に向上します。
まとめ:「違うけど魅力的」が最大の強み
ドラゴンボール風の要素を取り入れつつ、法的に安全な“風”キャラを生み出すためには、
「見た目」「名前」「性格」の3点セットで差別化する意識が不可欠です。
- 似ているだけのコピーでは、ファンにも企業にも受け入れられません
- 「新しいけど、どこか懐かしい」印象を持たせることが成功のコツです
AI漫画動画はYouTubeで収益化できる?稼げる仕組みと注意点

「AIで作ったオリジナルのアニメや漫画風動画で、YouTubeから収益を得たい」
こう考えるクリエイターは年々増えています。
特に“ドラゴンボール風”の演出や作風を取り入れたAI漫画動画は、再生数を集めやすいフォーマットとして注目されています。
しかし、YouTubeで収益化を狙うには、単に動画を投稿するだけでは不十分です。
この章では、収益化の仕組み・審査基準・AI動画の注意点について詳しく解説します。
YouTube収益化の基本条件とは?
YouTubeパートナープログラム(YPP)に参加するには、以下の要件を満たす必要があります。
- チャンネル登録者数:1,000人以上
- 過去12か月間の総再生時間:4,000時間以上
または - YouTube Shortsでの再生回数:過去90日間で1,000万回以上
さらに、AdSenseアカウントの紐付けや、ガイドラインの遵守も必須です。
AI漫画動画で稼ぐために重要な審査ポイント
AIを使った動画でも収益化は可能ですが、YouTube側は「誰が制作したのか」「コンテンツに創造性があるか」を重視しています。以下の点が特に重要です。
① オリジナリティの有無
YouTubeは「再利用されたコンテンツ(Reused Content)」を収益化対象から除外しています。
以下のような動画は審査で落とされやすくなります。
- 他者が作成したAI画像を無断で組み合わせたもの
- キャラクターや演出が既存作品と酷似しているもの
- 編集やナレーションのないスライドショー型動画
一方で、次のような要素が加わると「自分の作品」と判断されやすくなります。
- 自作のプロンプトで生成したキャラや背景
- 独自ストーリーによる構成
- 字幕、BGM、ナレーションの挿入
② 教育的・娯楽的な価値
最近のアルゴリズムでは、「視聴者が学びを得る」「感情的に楽しめる」動画が評価されやすい傾向があります。
- キャラが成長するドラマ性
- 読者に問いかける展開
- 視聴者のコメントを誘導する設計
これらを取り入れることで、再生数と収益の両方を狙いやすくなります。
③ 編集と構成の工夫
ナレーションを加える、カットごとに視点を切り替える、BGMや効果音でテンポを作るといった編集作業は、収益化審査の通過率を大きく高めます。
CapCutやPremiere Proなどのツールを活用し、単調な動画ではなく“ストーリー性ある映像”にすることが求められます。
AI漫画動画が通報・削除される原因とは?
AI動画が著作権的に問題になるケースも増えています。以下のような行為は特に注意が必要です。
- ドラゴンボール風キャラを使用して「悟空」「かめはめ波」と明記
- アニメの音声や効果音をそのまま使用
- 動画説明欄に「ドラゴンボール」など公式名を記載
これらが原因で動画が削除・非公開・収益化取り消しになる例も多くあります。
収益化を目指すなら“AI”だけに頼らない
AIはあくまで補助ツールであり、本当の収益化には“人の創造力”が欠かせません。
AI画像に物語と感情を吹き込む作業こそが、収益化コンテンツを生む鍵です。
商用利用してもOK?AI動画の収益化と利用規約の確認ポイント

AIツールを使って動画やイラストを制作し、それをYouTubeやTikTokで公開・収益化する場合、必ず確認すべきなのが各AIサービスの利用規約と商用利用可否です。
どれだけクオリティの高い作品ができても、使用しているAIツールが商用利用を禁止していれば、動画の公開や収益化そのものが利用規約違反となる可能性があります。
この章では、主要AIツールの商用利用ルールと、収益化前に確認しておくべき重要ポイントを解説します。
商用利用可能な代表的AIサービスと特徴
Midjourney(ミッドジャーニー)
- 有料プラン加入で商用利用が可能
- 無料プランでは生成画像の商用利用は不可
- 利用時には「商用OK」プランであるかの確認が必須
Midjourneyで制作した画像を動画に使用して収益化するには、有料プランに加入している証拠(契約情報)が必要です。
Runway ML(ランウェイ エムエル)
- 有料プランで商用利用可能
- 動画やアニメーション生成機能あり
- 素材の著作権は基本的にユーザーに帰属(ただし規約に従うこと)
RunwayはAI動画制作に強く、商用利用前提で設計されていますが、AIが生成したコンテンツに他人の著作物が含まれないよう注意が必要です。
Leonardo AI(レオナルドAI)
- 一部プランで商用利用可(使用時は明示あり)
- フリー素材風キャラクターの生成が得意
- 配布・販売には追加ライセンスの取得が必要な場合も
レオナルドAIは“オリジナル風”キャラの生成に向いていますが、プランによっては商用NGのケースもあるため契約時の条件確認が必要です。
素材サイトや編集ツールのライセンスも確認
動画に使用する画像、音楽、効果音、フォントなども、すべてにおいてライセンスの確認が必要です。
- Pixabay、Pexels、DOVA-SYNDROMEなどの無料素材サイトは「商用利用可」「クレジット表記不要」の条件を確認する
- 有料BGM・効果音は、購入後の利用範囲(YouTube、広告、販売作品など)を明確に理解しておく
また、動画編集ツール(例:Canva、CapCutなど)でも、無料テンプレートや素材の中には「非商用限定」のものがあります。
使用時には商用利用マークのある素材だけを選ぶことが基本です。
利用規約の“落とし穴”に注意すべき理由
AIサービスの利用規約には、一般的に次のような注意点が含まれています:
- 自動生成された画像でも、著作権や肖像権を侵害する表現は禁止
- 商用利用にはライセンス証明の提示が必要な場合あり
- AI生成物に関する責任は利用者が負う
つまり、AIを使って制作したコンテンツで問題が起きた場合、その責任は使用者本人が負うのが原則です。
「規約を読まずに使った」「フリー素材だと思った」という言い訳は通用しません。
特に収益が発生する場合は、企業や著作権者が対応を厳しくする傾向があるため、あらかじめ規約を読み込んでから制作を始めることが鉄則です。
トラブル回避のためにできること
- 使用したAIツールと素材の利用規約を保存・スクショしておく
- 商用利用の可否が不明な場合は、直接運営に問い合わせる
- 収益化前に、第三者チェック(法務・ライセンス専門家)を入れるのも有効
AIで作った“ドラゴンボール風NFT”を売るのは違法?

NFT(Non-Fungible Token)市場の拡大により、個人クリエイターでもAI生成コンテンツをトークン化して販売する機会が増えてきました。
その中で「ドラゴンボール風キャラをAIで作ってNFTとして売れば稼げるのでは?」と考える人も少なくありません。
しかし結論から言うと、“ドラゴンボール風”NFTを無許可で販売する行為は、極めて違法性が高い行為です。
ここでは、その理由と過去の事例、NFT特有のリスクについて詳しく解説します。
所有権と著作権はまったく別物
NFTを販売する際、多くの人が誤解しがちなのが「NFTにすれば作品の権利も売れる」という認識です。
実際には、NFTはデジタル上の“所有証明”を記録するものであり、著作権や商標権が購入者に移るわけではありません。
つまり、あなたが作った“悟空風”キャラをNFTにして売ったとしても、そこに著作権的な問題があれば、NFTという形にしても侵害行為は成立します。
“ドラゴンボール風”の見た目が違法の原因になる
NFTとして販売する場合、通常のYouTubeやTikTok投稿以上にビジュアルの独自性が問われます。
なぜなら、NFTは基本的に商品・資産としての価値を持ち、購入者が「所有するもの」として見なされるからです。
以下のようなデザインは、ドラゴンボールの著作権や商標権を侵害していると判断される可能性があります。
- 超サイヤ人風の髪型、筋肉、顔立ち
- 悟空の道着とそっくりな衣装や色合い
- キャラ名に「カカ○ット」「孫○空」といった類似性のある名称
たとえ「これはAIが作ったオリジナルです」と主張しても、視覚的に似ていると判断されれば即アウトです。
実際に削除されたNFT事例
過去には、次のようなトラブル事例が報告されています。
- OpenSeaで販売された“悟空風NFTアート”が即日削除
→ 東映アニメーションが申し立てを行い、出品者のアカウントは停止処分に。 - AI生成キャラを「ドラゴン〇ール風」とタグ付けして販売
→ 購入者から通報が入り、NFTマーケット運営が強制削除。 - NFT販売後にSNSで炎上→購入者から返金要求が殺到
→ クリエイター側は「知らなかった」と主張するも、対応が遅れ信用を喪失。
これらの事例に共通しているのは、「オリジナルと主張しているが、誰が見ても似ていた」という点です。
NFT販売は通常の収益化以上に“リスクが重い”
NFTはデジタル資産として明確な金銭的価値を持つため、問題が発生した場合の影響は非常に大きくなります。
- 著作権者からの正式な法的措置が取られやすい
- 購入者とのトラブルや返金交渉が発生する
- 販売プラットフォームからのアカウント永久停止
「売って終わり」ではなく、購入後の責任まで発生することを認識しておく必要があります。
安全にNFTを展開するためには?
NFTで合法的に展開していくためには、以下の点を徹底する必要があります。
- キャラや世界観を完全にオリジナルにする
- ライセンス確認済みの素材やAIツールのみを使用する
- マーケット規約と著作権法を事前に確認する
- AI生成物であることを明記し、誤認を避ける
NFTは確かにチャンスのある市場ですが、それ以上にクリエイターとしての信用と責任が問われるフィールドです。
収益化を目指すための動画制作フローとおすすめツール

AIを活用したオリジナル動画で収益化を狙うなら、しっかりとした制作フローと適切なツールの選定が不可欠です。
特に“ドラゴンボール風”の雰囲気を持ちながらも、著作権・商標リスクを回避し、オリジナリティを担保した動画制作が求められます。
この章では、収益化までの具体的なステップと、その過程で使えるおすすめツールをご紹介します。
ステップ1:キャラクターと世界観の構築(AI画像生成)
まずは動画の主役となるキャラクターや背景を作成します。
ここで大切なのは、“似ている”ではなく“自分だけの”キャラを生み出すことです。
おすすめツール:
- Leonardo AI:ファンタジーやアニメ風の高精度キャラクター生成が可能。構図やスタイルを細かく指定できる。
- AnimeGenius:アニメテイストのキャラ生成に特化。AIによる多様なスタイル生成に対応。
キャラだけでなく、背景や小物などもあわせてデザインすることで、世界観に一貫性を持たせましょう。
ステップ2:物語・セリフの構成(プロンプト+シナリオ作成)
オリジナル動画には、ストーリー性が必要不可欠です。
単なる画像の羅列では収益化審査を通過しにくいため、ナレーションやセリフを含んだシナリオ設計を行います。
おすすめツール:
- ChatGPT:ストーリー構成、セリフ、ナレーション文の生成に最適。バトルの展開やキャラ同士の掛け合いも自然に作成可能。
- Notion / Google Docs:構成メモの整理やスクリプトの編集に便利。
ステップ3:画像から動画への変換・アニメ化
生成したキャラクター画像をアニメーションや動画に落とし込むフェーズです。
視覚的に動きがあることで、視聴者の滞在時間が伸びやすくなります。
おすすめツール:
- Runway ML:画像から短い動画を自動生成。Text to Video機能でバトル演出やカメラワークを再現可能。
- Kaiber:静止画をアニメ風動画に変換。Zoom・Shakeなどの動きのある演出に強み。
- Pika Labs:SNS向けのショートアニメを生成可能。動きのあるエフェクトに優れる。
ステップ4:編集・演出(動画編集)
編集作業では、視覚演出・効果音・字幕・BGMなどを加えて、動画の完成度とオリジナリティを強化します。
おすすめツール:
- CapCut:スマホで完結する高性能無料編集アプリ。字幕挿入、効果音、エフェクトが豊富。
- Adobe Premiere Pro:本格的な編集作業に最適。カット編集、音声調整、色補正など対応。
- Canva Pro:テンプレートを使った動画タイトルやサムネイル制作に便利。
編集で特に重視すべきなのは、「単なるスライドショー」にしないこと。
動画らしい“流れ”と“テンポ”を演出しましょう。
ステップ5:投稿と収益化導線の設計
完成した動画をYouTubeやTikTokに投稿し、視聴数・登録者数を伸ばして収益化を目指します。
投稿のポイント:
- タイトルとサムネイルは明確&魅力的に
- 説明欄に「完全オリジナル作品であること」を明記
- #AIアニメ #オリジナルキャラ などのタグでターゲットを狙う
- 関連動画リンクやLINE登録への誘導など、外部導線も設計
忘れてはいけないチェックリスト
| チェック項目 | 対応済み? |
|---|---|
| 商用利用可のAIツールを使用しているか? | ✅ |
| 似ていないオリジナルキャラを使っているか? | ✅ |
| シナリオやナレーションは自作か? | ✅ |
| 音源・効果音・フォントはライセンス確認済? | ✅ |
| 動画に動きと演出が含まれているか? | ✅ |
プラットフォームの収益化ルールとAI動画の扱い

AIで制作したオリジナル動画を収益化するにあたり、どのプラットフォームで展開するかは極めて重要です。
特にYouTubeとTikTokは、収益化ポリシーやAIコンテンツに対する取り扱い方が異なるため、それぞれの特徴とルールを理解した上で投稿戦略を立てる必要があります。
この章では、YouTubeとTikTokの収益化条件の違いと、AI動画の扱いにおける注意点を比較しながら解説します。
YouTubeの収益化ルールとAI動画への対応
YouTubeでは、収益化のためにYouTubeパートナープログラム(YPP)への参加が必要です。
条件は以下のとおりです。
基本条件:
- チャンネル登録者数:1,000人以上
- 過去12か月の総再生時間:4,000時間以上
または - Shortsの再生数:過去90日で1,000万回以上
AI動画に関する注意点:
YouTubeでは、AIによって自動生成されたコンテンツであっても、収益化可能ですが、以下のポイントが求められます。
- オリジナリティがあること(AIだけで生成されたスライドショーは不可)
- ナレーション、編集、シナリオなど、創作性の高い付加価値があること
- 著作権侵害素材(音楽、画像、映像など)を使っていないこと
- ガイドラインや広告主ポリシーに違反しないこと
特に「再利用コンテンツ(Reused Content)」と判断されると、収益化審査に通らない、または収益が停止されるリスクがあります。
TikTokの収益化ルールとAI動画の扱い
TikTokは、YouTubeとは異なり動画単体からの広告収益ではなく、主に以下の方法でマネタイズされます。
主な収益化手段:
- TikTok Creator Fund(クリエイターファンド)
→ 対象国、条件(フォロワー1万人以上など)あり - LIVE配信中のギフト(投げ銭)
- 企業案件・タイアップ投稿
- 外部リンクによる販売導線(EC、LINE登録など)
AI動画に関する注意点:
TikTokでは、AIで作成されたコンテンツも投稿可能ですが、以下のような対応が求められます。
- 視聴者を誤認させない表現にする(例:公式作品に見せかけない)
- BGM・効果音の著作権を守る(使用楽曲はTikTok内のライブラリから選ぶ)
- 「これはAIで作られた創作作品」と明示する
TikTokは拡散力が非常に高いため、少しの炎上でアカウント停止・削除のリスクが高まるという特徴もあります。
両プラットフォームの比較表
| 項目 | YouTube | TikTok |
|---|---|---|
| 収益化条件 | 登録者数と再生時間で審査制 | フォロワー数と再生数で段階的収益 |
| 主な収益源 | 広告収益、Super Thanksなど | クリエイターファンド、投げ銭など |
| AI動画への対応 | 編集・ナレーションが必須 | 簡易編集でも拡散されやすい |
| 著作権監視の厳しさ | 高い(Content IDなど) | 高い(通報と自動検出の組み合わせ) |
| 投稿後の炎上リスク | 中程度(再審査の余地あり) | 高め(アカウント凍結のリスク) |
どちらを選ぶべきか?
- 継続的な広告収入とブランド構築を重視するならYouTube
- バズを狙った短期的な拡散と成長ならTikTok
どちらも活用するハイブリッド戦略も有効ですが、どのプラットフォームでも、“オリジナルで合法的な動画”という土台がなければ、安定した収益化は不可能です。
東映アニメーションや集英社が訴える可能性は?実際の事例紹介

AIで作った“ドラゴンボール風動画”やキャラクターを公開・収益化するうえで、最も注意しなければならないのが、著作権の管理元である企業の対応姿勢です。
ドラゴンボールの場合、アニメは東映アニメーション、原作は集英社が著作権を管理しており、この2社は過去に著作権侵害に対して非常に厳しい対応を行ってきた実績があります。
この章では、実際に行われた削除・警告・訴訟などの事例を紹介しながら、AIコンテンツにも十分にリスクが及ぶ可能性があることを解説します。
東映アニメーションの“徹底した削除対応”
東映アニメーションは、YouTube上での著作権侵害動画の取り締まりにおいて、日本でも最も厳しい対応を行う企業の一つとして知られています。
実際の対応例:
- 2021年、YouTubeで「ワンピース」や「ドラゴンボールZ」などのアニメクリップを投稿した複数のチャンネルが一斉に削除
- 一部のクリエイターは警告を受けた後も投稿を続けた結果、チャンネルが永久停止処分
- 動画が「二次創作」「解説付き」であっても、映像や音声が使われていれば容赦なく削除対象
このことから、仮にAIで描いた動画であっても、見た目が類似していたり、効果音・BGMを無断使用していた場合、同様に削除される可能性が極めて高いといえます。
集英社の法的対応は“静かに、しかし確実に”
集英社は東映ほど表立った大量削除を行うことは少ないものの、個別対応での警告・法的措置に強い姿勢を見せています。
過去の主な事例:
- 漫画を無断転載していた個人ブログ運営者に対し、民事訴訟を提起
- 同人誌での「商用的利用」が確認された場合に、警告文書を送付
- 「ジャンプ系キャラのAIイラストをNFT販売」したクリエイターに対し、マーケットプレイスを通じて削除申請
集英社はSNSや二次創作に対しては比較的寛容な面もありますが、それはあくまで非営利かつファン活動としての範囲に留まっている場合に限ります。
AIコンテンツでも例外ではない理由
一部のクリエイターは、「AIで自動生成したから著作権侵害に当たらない」と主張するケースもありますが、
企業側が見るのは“視覚的な類似性”と“収益化の有無”です。
たとえば、
- キャラの髪型や服装が悟空に酷似している
- 世界観がナメック星を連想させるような背景
- 動画タイトルやタグに「ドラゴンボール風」と明記
このような要素が揃っていれば、AIであっても十分に“模倣コンテンツ”と認定され、対応される可能性が高いのです。
SNSでも通報から削除される例が増加中
- TikTokで「超サイヤ人風キャラでバトル」動画を投稿 → 3日後に通報殺到で削除
- Instagramで「AI版悟空」の投稿に対し、ユーザーから「公式に通報しました」とのコメントが相次ぐ
- NFT販売後にX(旧Twitter)で炎上 → 購入者から返金要求が殺到
これらの事例からも、視聴者の目や反応が“法的トリガー”になる時代になっていることが分かります。
法的トラブルを避けるには?
- 完全オリジナルキャラクターの開発
- デザインの差別化(服装、顔、髪型、名前)
- 「〇〇風」「悟空風」などの表現を避ける
- 商用利用前に専門家に相談する
AIというテクノロジーは創作の幅を大きく広げてくれますが、それに伴ってクリエイター自身が法律リテラシーを持つ必要性も増しています。
まとめ|好きを活かしつつオリジナルで攻める時代へ

AIの進化により、かつてはプロだけが制作できたようなアニメ風の動画やキャラクターを、個人でも簡単に生み出せる時代がやってきました。
中でも「ドラゴンボール風」の世界観やキャラを模したコンテンツは人気が高く、多くのクリエイターが挑戦しています。
しかし、本記事で繰り返し強調してきたように、「似ているだけ」でも著作権や商標権の侵害リスクがあるという現実は、決して軽視できません。
AIは創作の味方、だが責任は制作者にある
AIが生成する画像・動画は魅力的で創造的です。しかし、その結果物をどう使うかは人間の判断と責任に委ねられます。
たとえAIが自動で作ったとしても、それが著作物や商標を侵害していれば、動画の削除、アカウント停止、訴訟リスクなどの重大な問題に発展する可能性があります。
「好き」という情熱を“安全に”表現する工夫が必要
ドラゴンボールのような作品に憧れ、インスパイアされた世界観を表現したい気持ちは、多くのクリエイターに共通するものです。
だからこそ、オリジナルキャラや独自の物語を創ることが、長く活動するための正解だといえます。
- 髪型や服装を工夫して独自デザインにする
- キャラ名やセリフにオリジナリティを持たせる
- 世界観はファンタジー風でも、設定は完全オリジナルにする
このように「攻めるけど守る」姿勢が、ファンからの信頼やプラットフォームからの評価にもつながります。
オリジナル作品こそ、収益化の“本当の武器”になる
YouTubeやTikTokで収益化を目指す場合、ただ再生数を狙うだけでは継続的な成果は得られません。
重要なのは、あなたの作品に“唯一無二の価値”があること。
オリジナルのキャラクター、世界観、物語は、それだけでブランドになり、将来的に以下のような展開も視野に入ります。
- グッズ化やLINEスタンプの販売
- ファンコミュニティの形成
- 書籍化や電子出版
- NFTやメタバース展開
AIはその起爆剤になり得ますが、成功するための火種は“あなた自身の想像力”です。
今こそ、「好き×合法×オリジナル」で勝負しよう
・AIで創る「ドラゴンボール風」の世界観を、安全に、かつ創造的に活用するには
・著作権と商標の理解が欠かせません
・そして、収益化を継続するには、オリジナルのブランド化が最も重要です
本記事を通じて、あなたが“好き”を活かしながら、安心して創作活動を続け、夢を形にする方法を見つけていただけたなら幸いです。
ただ・・・
まだまだ収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。
じゅんの公式LINEでは、
- インスタアフィで稼ぐロードマップ
- 収益化に向けた詳しいノウハウ
- 各種テンプレート
などを中心に、
今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・
最高じゃありませんか…?
まずは僕の公式LINEを追加していただき、
ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
\無料!登録10秒/
公式LINEに登録するだけで
インスタ初心者でも月6桁目指せる
豪華17大特典配布中🎁
登録解除は、24時間いつでも出来ます🙆