※本ページはプロモーションが含まれています。
第一章 はじめに – ついにWindows10サポートが終了

2025年10月14日──
ついにWindows 10のサポートが正式に終了しました。
この日を境に、MicrosoftはWindows10へのセキュリティ更新や技術サポートの提供をすべて停止。
つまり、今後はあなたのPCが新たなウイルスやサイバー攻撃にさらされても、守ってくれる“公式の盾”はなくなるということです。
「動くから大丈夫」では済まされない現実
「電源を入れたら普通に動くし、問題ないでしょ」──
多くの人がそう考えています。
たしかに、サポート終了後もWindows10は起動します。
WordやExcelも使えるし、ネットも見られるかもしれません。
しかし、それは“安全に動いている”のではなく、
“見えない危険にさらされながら動いている”状態です。
サポート終了後は、
- 新しいウイルスへの防御ができない
- 不正アクセスやデータ漏えいのリスクが高まる
- オンラインバンキングやECサイトでの利用が危険になる
という、日常生活やビジネスに直結するリスクが発生します。
今、あなたのPCが「時限爆弾」になる可能性
セキュリティ更新が止まったWindows10は、
言い換えれば“新しい脆弱性を無防備に抱えた状態”です。
サイバー犯罪者は、サポート終了後に見つかった脆弱性を狙って攻撃を仕掛けてきます。
彼らは、アップデートが止まった古いOSを“格好の標的”として監視しているのです。
つまり、今後Windows10を使い続けることは、
家の鍵を壊れたまま放置して外出するようなもの。
何も起きない日が続くかもしれませんが、
一度でも狙われれば、被害は取り返しがつかなくなります。
なぜ2025年10月14日が重要なのか
この日は、Microsoftが「最後のWindows10更新プログラム」を配信する最終日。
以降は、いかなるセキュリティ修正もリリースされません。
さらに、
- Microsoft 365(Word・Excel・Outlookなど)もWindows10上でのサポートを終了
- 新しいブラウザやドライバもWindows10では非対応になる見込み
つまり、OSだけでなく、アプリや周辺機器の利用にも影響が出始めるのです。
まだWindows10を使っている人は多い
最新のデータによると、2025年10月時点でもWindows10のシェアは約40%。
多くの個人・企業ユーザーがまだ移行を完了していません。
しかし、「まだ大丈夫」と思っているうちに、
あなたのPCはじわじわと“取り残されていく”のです。
- 新しいアプリがインストールできない
- クラウドサービスが非対応になる
- ZoomやTeamsがアップデートできない
そんな“小さな不便”が、やがて“重大な障害”に変わります。
この記事でわかること
この記事では、
- Windows10サポート終了後に何が起こるのか
- 今すぐ取るべき3つの対策
- Windows11への安全な移行手順
- どうしても移行できない場合の延命方法
を、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「まだ動くから大丈夫」と思っている人ほど、今すぐ読むべき内容です。
次章では、
そもそも“サポート終了”とは何を意味するのか──
その本当の意味と影響をわかりやすく説明します
第二章 Windows10サポート終了とは?何が終わるのか
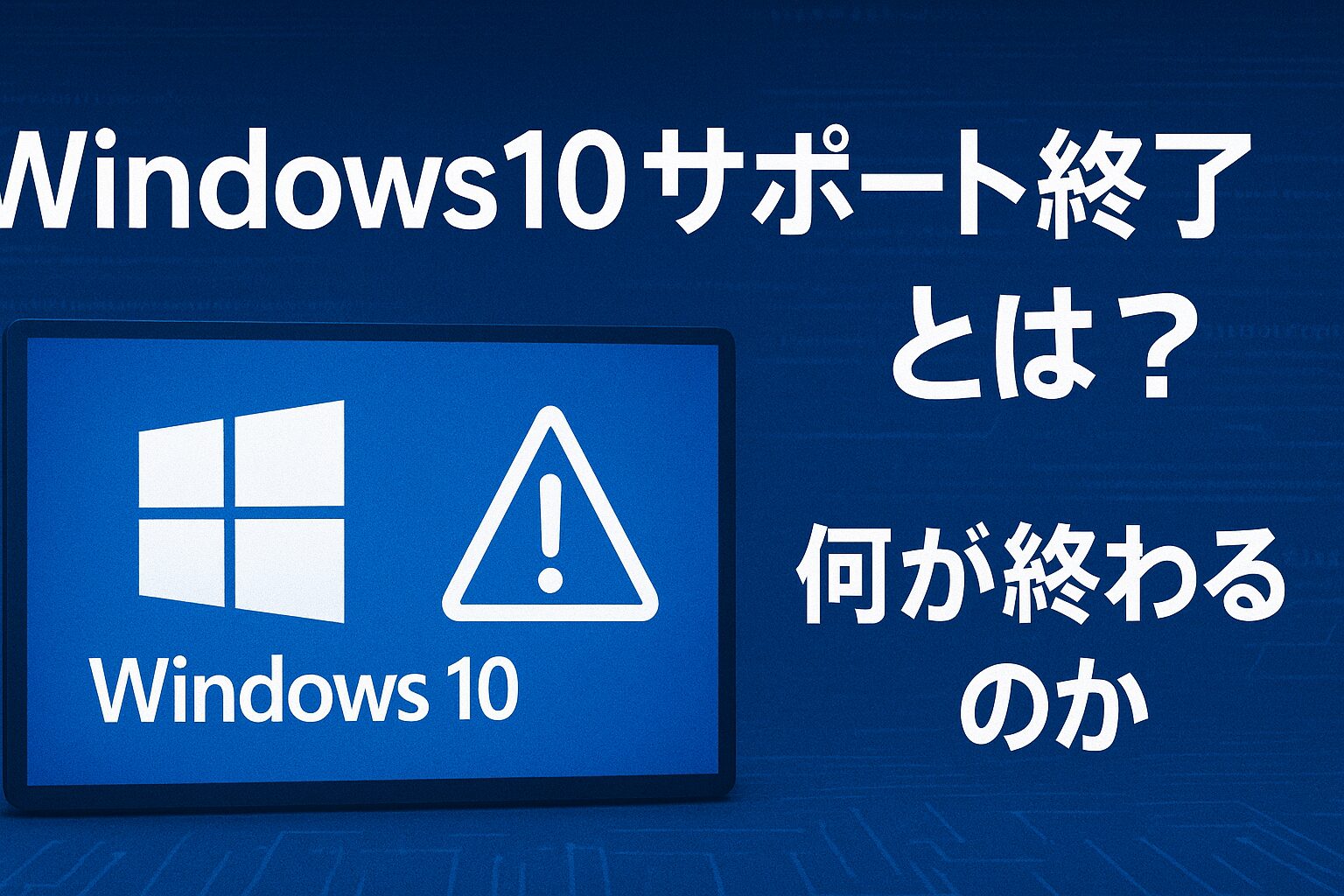
Windows10の「サポート終了」とは、単に古いOSになるという意味ではありません。
それは、Microsoftが今後一切の更新・保護・サポートを提供しなくなるという、非常に重要な節目を指します。
サポートとは「安全に使うための命綱」
普段意識されにくいですが、Windowsには常に“裏で動く守りの仕組み”があります。
それが、セキュリティ更新プログラムです。
この更新により、ハッカーが発見した脆弱性や新しいウイルスの侵入経路が塞がれ、PCが守られてきました。
サポートが終了するということは、その防御ネットが完全に消えることを意味します。
つまり、今後はどんな新しい脆弱性が発見されても、
「Microsoftは一切の修正を行わない」という状態になるのです。
サポート終了後に止まるもの
Windows10のサポートが終了した今、止まるのは次の4つです。
- セキュリティ更新プログラム
→ 新しいウイルスやハッキング手口への修正が配信されません。
例:脆弱性を狙った攻撃で情報漏えいする可能性が高まります。 - ソフトウェア更新(バグ修正・機能改善)
→ 不具合が発生しても修正されず、徐々に動作が不安定になります。 - テクニカルサポート
→ Microsoftに問い合わせても、対応対象外になります。 - Microsoft 365 Appsのサポート
→ Word、Excel、OutlookなどのMicrosoft 365製品も、Windows10上では非対応になります。
表面上は動く。しかし中身は「無防備」
サポート終了後も、Windows10は起動します。
しかしそれは“サポートが切れた車で高速道路を走るようなもの”です。
- セキュリティが更新されない
- ウイルス対策ソフトが対応をやめる
- ChromeやEdgeなどのブラウザも、順次サポート対象外になる
結果として、インターネットに接続するだけでリスクが生じる環境になります。
サポート終了後、特に危険なのは“個人情報の流出”
サイバー攻撃者は、サポート終了直後を狙って活動を活発化させます。
なぜなら、新たな脆弱性が見つかっても修正されないことを知っているからです。
- ネットバンキング
- ネットショッピング
- クラウドサービス(OneDrive・Google Driveなど)
これらの利用は非常に危険です。
特にパスワードやカード情報を扱うサイトへのアクセスは、“見えない危険地帯”になると考えておきましょう。
「企業利用」では法的リスクも
法人や団体でWindows10を使い続ける場合、コンプライアンス違反になる可能性があります。
- 個人情報保護法やセキュリティ基準に抵触
- 顧客データ流出の際、企業責任を問われる
- 業務委託先から取引停止を受けるケースも
多くの企業は、法令遵守の観点から「サポート切れOSの利用禁止」を明記しています。
もし社内でWindows10が残っているなら、今すぐ対策が必要です。
Microsoftの公式声明
Microsoftは公式に次のように発表しています。
“Windows10のサポートは2025年10月14日をもって終了します。”
これは延長されることはありません。
唯一の例外は、有料の「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」を購入した場合のみ。
つまり、ほとんどのユーザーにとっては、「本当に終わった」のです。
ここまでのまとめ
- サポート終了=セキュリティ・更新・サポートすべて停止
- 動いても安全ではない
- 個人情報・企業データの流出リスクが高まる
- 対策は「アップグレード」か「ESU」か「買い替え」
次章では、
「サポート終了後に起こる3つの重大リスク」を具体的に解説します。
あなたのPCやデータにどんな危険が迫るのか、わかりやすく整理していきます。
第三章 サポート終了後に起こる3つのリスク

Windows10のサポートが終了した今、見た目には何も変わらなくても、
あなたのPCは確実に“危険な状態”に近づいています。
ここでは、サポート終了後に実際に起こる3つの重大リスクを、わかりやすく解説します。
リスク① セキュリティリスク – ウイルス感染と情報漏えい
最も深刻なのが、セキュリティ更新プログラムが提供されなくなることです。
新しいウイルスやハッキング手法は毎日のように発見されています。
これまではMicrosoftが迅速に修正プログラム(パッチ)を配信し、
その都度ユーザーのPCを守ってきました。
しかし、サポートが切れた今、
新しい脆弱性が見つかっても修正されることはありません。
- 悪意あるサイトにアクセスしただけで感染
- メール添付のファイルから不正アクセス
- Wi-Fi経由でデータが抜き取られる
このような被害は、Windows10を使い続けるほど現実味を帯びます。
とくにオンラインバンキングやショッピングに利用している人は要注意です。
「動いているから大丈夫」ではなく、「守られていないから危険」と認識してください。
リスク② ソフト・サービスが動かなくなる互換性問題
次に大きいのが、ソフトウェアやアプリが使えなくなるリスクです。
サポート終了に合わせて、各社のアプリやクラウドサービスもWindows10を切り捨て始めています。
- Microsoft 365(Word・Excel・Outlook)がサポート終了
- Google ChromeやEdgeも順次アップデート対象外へ
- ZoomやTeamsなどビジネスツールが動作保証外になる
- プリンターやスキャナーのドライバが提供終了
つまり、「起動はできるけど使えない」という状態が次第に増えていきます。
さらに、オンラインでの本人確認・電子署名なども、セキュリティ要件を満たさず使えなくなる可能性があります。
リスク③ 企業・団体での利用はコンプライアンス違反に
個人利用以上に深刻なのが、企業・学校・自治体での利用リスクです。
サポート切れOSを業務に使うことは、情報セキュリティ基本方針の違反につながります。
もしサイバー攻撃によって顧客情報が漏えいした場合、
「なぜサポートが切れたOSを使っていたのか」と責任を問われる可能性があります。
特に以下のようなリスクが現実的です:
- 個人情報保護法に抵触するおそれ
- 顧客・取引先からの信頼喪失
- 監査や契約更新で“非適格”と判断される
このように、企業や団体がWindows10を使い続けるのは、事業継続上の大きなリスクとなります。
放置の代償は“データ喪失”と“金銭的損失”
一度ウイルス感染すると、復旧には想像以上の費用と時間がかかります。
実際、ランサムウェア感染による被害額は、1台あたり数十万円〜数百万円に達するケースもあります。
また、重要データが暗号化・削除されると、バックアップがなければ取り戻すことはできません。
「まだ使える」ではなく「いつ壊れてもおかしくない」──
それが今のWindows10の現実です。
今すぐ確認したいチェックリスト
✅ 自分のPCがWindows10のままになっていないか
✅ セキュリティソフトが「サポート外」と警告を出していないか
✅ Microsoft 365やブラウザが古いままになっていないか
ひとつでも当てはまるなら、すでに“リスクゾーン”に入っています。
次章では、これらのリスクを回避するために今取れる3つの行動──
「Windows11へのアップグレード」「ESU延長」「PC買い替え」について、
それぞれのメリット・デメリットを徹底比較して解説します。
第四章 今後の選択肢と最適な移行パターン
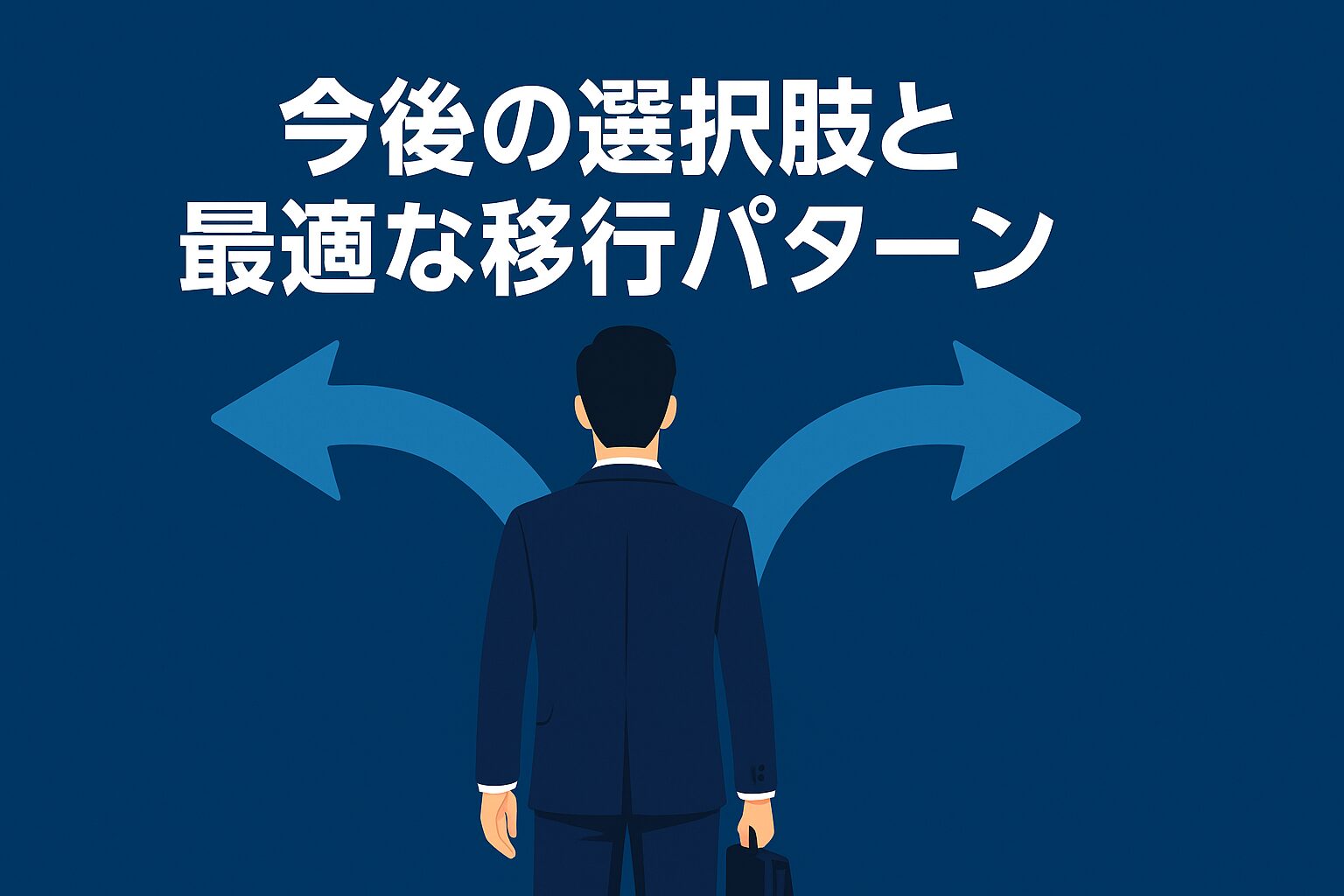
Windows10のサポートが終了した今、取るべき行動は大きく分けて3つです。
- Windows11へアップグレード(推奨)
- 拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)で延命する
- 新しいPCへの買い替え
それぞれの特徴と、どんな人に向いているかを整理していきます。
選択肢① Windows11へアップグレード(最もおすすめ)
もっとも安全でコスパの良い方法が、Windows11へのアップグレードです。
メリット
- 無料でアップグレード可能(対応PCの場合)
- セキュリティ更新と新機能を継続的に受け取れる
- 操作感がWindows10に近く、違和感が少ない
注意点
- TPM 2.0とSecure Bootが必須(古いPCは非対応)
- 古い周辺機器が使えなくなる可能性あり
対応確認の手順
- Microsoft公式の「PC 正常性チェック アプリ」をダウンロード
- 「このPCはWindows11に対応しています」と表示されればOK
- 対応していれば、「設定 → Windows Update → アップグレードを確認」で開始できます
ポイント:データはそのまま移行できるため、再設定の手間も最小限です。
PCが対応しているなら、最優先で選ぶべき方法です。
選択肢② 拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)を利用
もし今すぐWindows11に移行できない場合、有料でセキュリティ更新を延長する「ESU」という選択肢があります。
ESUとは
Extended Security Updates(拡張セキュリティ更新プログラム)の略で、
サポート終了後も一定期間、重要なセキュリティ更新を受け取れる仕組みです。
概要
- 提供期間:2026年10月13日まで登録可能
- 対象:Windows10 Pro / Enterprise / Home
- 費用:年単位の課金制(個人ユーザーも対象)
- 提供内容:セキュリティ更新のみ(機能追加はなし)
メリット
- 新しいPCをすぐに買わずに済む
- 既存環境を維持したまま安全性を確保できる
デメリット
- 無料ではなく有料(年間数千円〜)
- あくまで“延命措置”であり、根本解決ではない
ポイント:ESUは“時間稼ぎ”には最適ですが、いずれはWindows11への移行が必要になります。
選択肢③ 新しいPCへの買い替え
もしあなたのPCがWindows11に対応していない場合、
買い替えが最も現実的で安全な選択肢です。
メリット
- 最新CPU・SSD・Wi-Fi 6などで動作が圧倒的に速い
- 省電力・静音性も向上し、長く使える
- 既にWindows11がプリインストール済み
買い替え時の目安
- 購入から5年以上経過している
- スペックが「メモリ8GB未満・HDD搭載」
- 起動や動作が遅く感じる
この条件に当てはまるなら、今の買い替えが最も賢いタイミングです。
おすすめの判断基準
| 用途 | 推奨スペック | 価格帯(目安) |
|---|---|---|
| 仕事・ビジネス用 | Core i5以上 / メモリ16GB | 10〜15万円前後 |
| 学習・一般利用 | Core i3 / メモリ8GB | 7〜10万円前後 |
| 動画編集・クリエイティブ | Ryzen 7 / メモリ32GB | 15〜25万円前後 |
3つの選択肢の比較表
| 項目 | Windows11へアップグレード | ESU延長 | 新しいPC購入 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料(対応PCのみ) | 有料(年額制) | 新規購入費用あり |
| 安全性 | ◎(最新サポート) | ○(一時延命) | ◎(最新環境) |
| 手間 | 少ない | ほぼなし | 多いが長期的に安定 |
| 推奨度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
結論:対応しているなら「アップグレード」、非対応なら「買い替え」
- 対応PC → すぐにWindows11へアップグレード
- 非対応PC → ESUで延命 or 新機種購入
どちらにしても、“Windows10を使い続ける”という選択肢だけは避けるべきです。
今後の安全性・快適性・コストを考えると、動くうちに移行するのが最善策です。
次章では、Windows11へ移行する際の注意点とトラブルを防ぐコツを、
わかりやすく手順付きで解説します。
第五章 Windows11へ移行する際の注意点
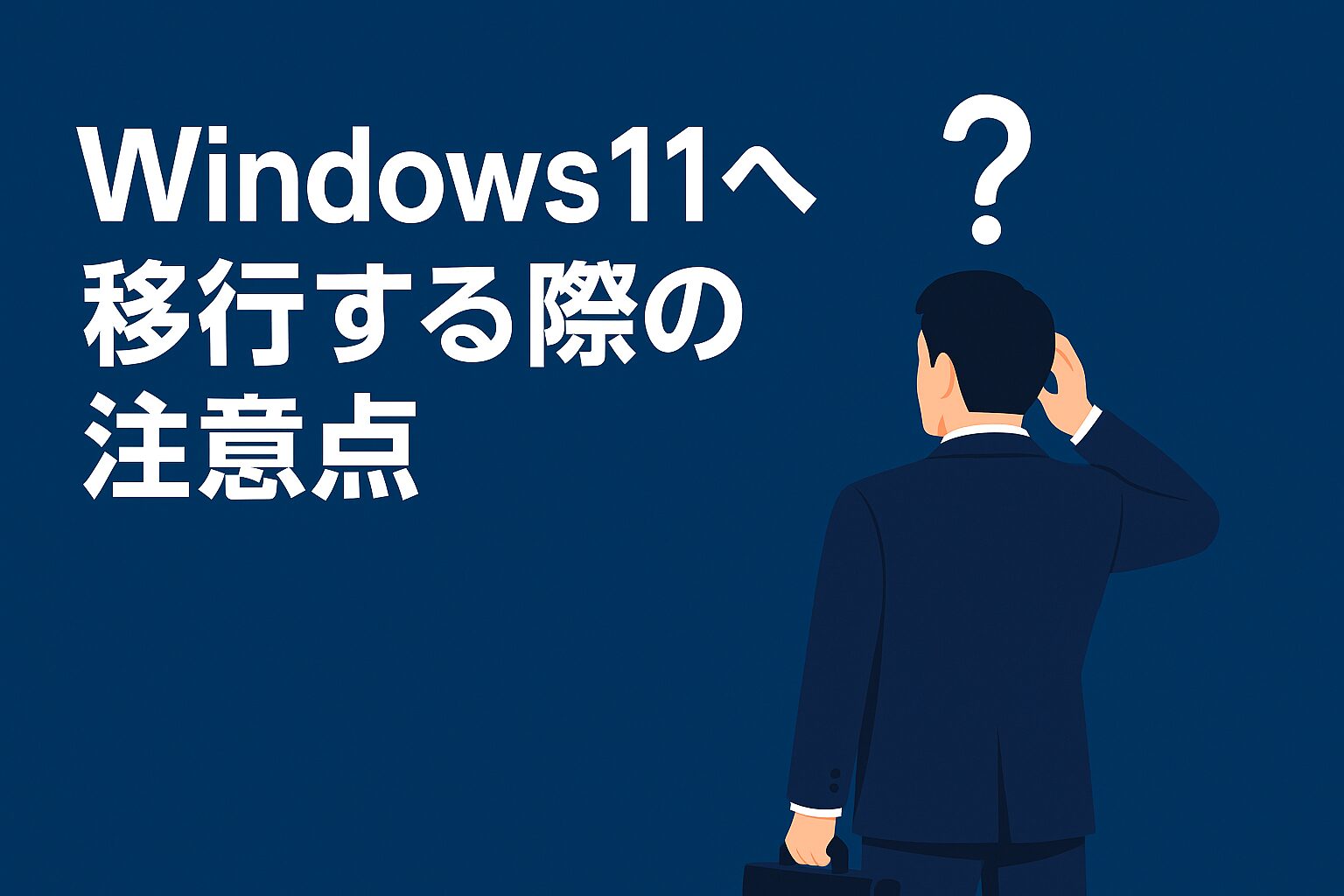
Windows10からWindows11への移行は、多くのユーザーにとって“最後の大きなステップ”です。
無料でアップグレードできるとはいえ、準備不足のまま移行するとデータ消失や動作不良が起こるリスクがあります。
ここでは、トラブルを防ぎながらスムーズに移行するための注意点を整理します。
注意点① まず「対応しているPCかどうか」を確認する
Windows11は、セキュリティ強化のためにシステム要件が大きく変わりました。
そのため、すべてのPCがアップグレードできるわけではありません。
主なシステム要件
- TPM 2.0 が有効化されている
- Secure Boot(セキュアブート) に対応
- CPU:Intel 第8世代以降 または AMD Ryzen 2000シリーズ以降
- メモリ:4GB以上、ストレージ:64GB以上
確認方法
- Microsoft公式の「PC 正常性チェック アプリ」をインストール
- アプリを起動し、「今すぐチェック」をクリック
- 結果に「このPCはWindows11に対応しています」と表示されればアップグレード可能です
対応していない場合は、ESU(延長更新)または新しいPCへの移行を検討しましょう。
注意点② データのバックアップは必須
移行作業の前に、すべてのデータをバックアップしておくことが絶対条件です。
バックアップ方法は3つあります:
- 外付けHDDやUSBメモリにコピー
- クラウド(OneDriveやGoogle Drive)に保存
- バックアップソフトを使って丸ごと保存
特に、写真・書類・メール・ブラウザのお気に入り・年賀状ソフトの住所録などは忘れがちです。
アップグレードに失敗しても、バックアップさえあれば復元できます。
注意点③ 不要なソフトを削除してから実行
古いアプリや常駐ソフトが多いと、アップグレード中にエラーが発生する場合があります。
以下の作業をしてから移行を始めましょう。
- 使っていないアプリをアンインストール
- 一時ファイルを削除(ディスククリーンアップ)
- 外部デバイス(USB、プリンターなど)を一時的に外す
こうすることで、アップデート中の競合やフリーズを防げます。
注意点④ Microsoftアカウントを用意しておく
Windows11では、Microsoftアカウントによるログインが基本になります。
Windows10でローカルアカウントを使っていた人は、事前にアカウント作成を済ませておくのがおすすめです。
- Outlookメールを持っていればそのまま利用可能
- 持っていない場合は https://account.microsoft.com で無料作成
アカウントを使えば、OneDriveへの自動バックアップやPC間の設定同期も簡単になります。
注意点⑤ アップグレード後のドライバ更新を忘れずに
Windows11にアップグレードすると、グラフィックやサウンド、ネットワークなどのドライバが古いまま残る場合があります。
アップグレード後は必ず以下をチェックしましょう。
- 「設定 → Windows Update → 更新プログラムの確認」
- すべての最新ドライバをインストール
- 周辺機器(プリンター・スキャナー・マウスなど)の動作確認
最新のドライバを適用することで、動作安定性が大幅に向上します。
注意点⑥ 時間に余裕をもって行う
アップグレード作業には、平均で1〜2時間かかります。
インターネット環境やPC性能によってはさらに時間がかかるため、
夜間や休日など、作業中に中断しないタイミングで行うのがおすすめです。
途中で電源を切ったり、Wi-Fiを切断したりすると失敗することがあるため注意が必要です。
注意点⑦ アップグレード後に設定を見直す
移行が完了したら、次の設定を確認しておきましょう。
- OneDriveの同期が有効になっているか
- 既定のブラウザやメールアプリが変わっていないか
- セキュリティ設定(Windows Defender)がオンになっているか
特に企業ユーザーは、共有フォルダやVPNの再設定が必要なケースがあります。
補足:どうしてもアップグレードできない場合
古いCPUやTPM非搭載PCなど、物理的にWindows11に対応できない機種もあります。
その場合は、
- 一時的にESU(拡張セキュリティ更新)を利用
- 1〜2年以内に新しいPCへ買い替え
という計画を立てるのが現実的です。
次章では、Windows11非対応のユーザーに向けて、
「買い替え時に失敗しないPC選びの基準」を紹介します。
スペックや価格の目安をわかりやすくまとめます。
第六章 買い替え時におすすめのPC選びの基準
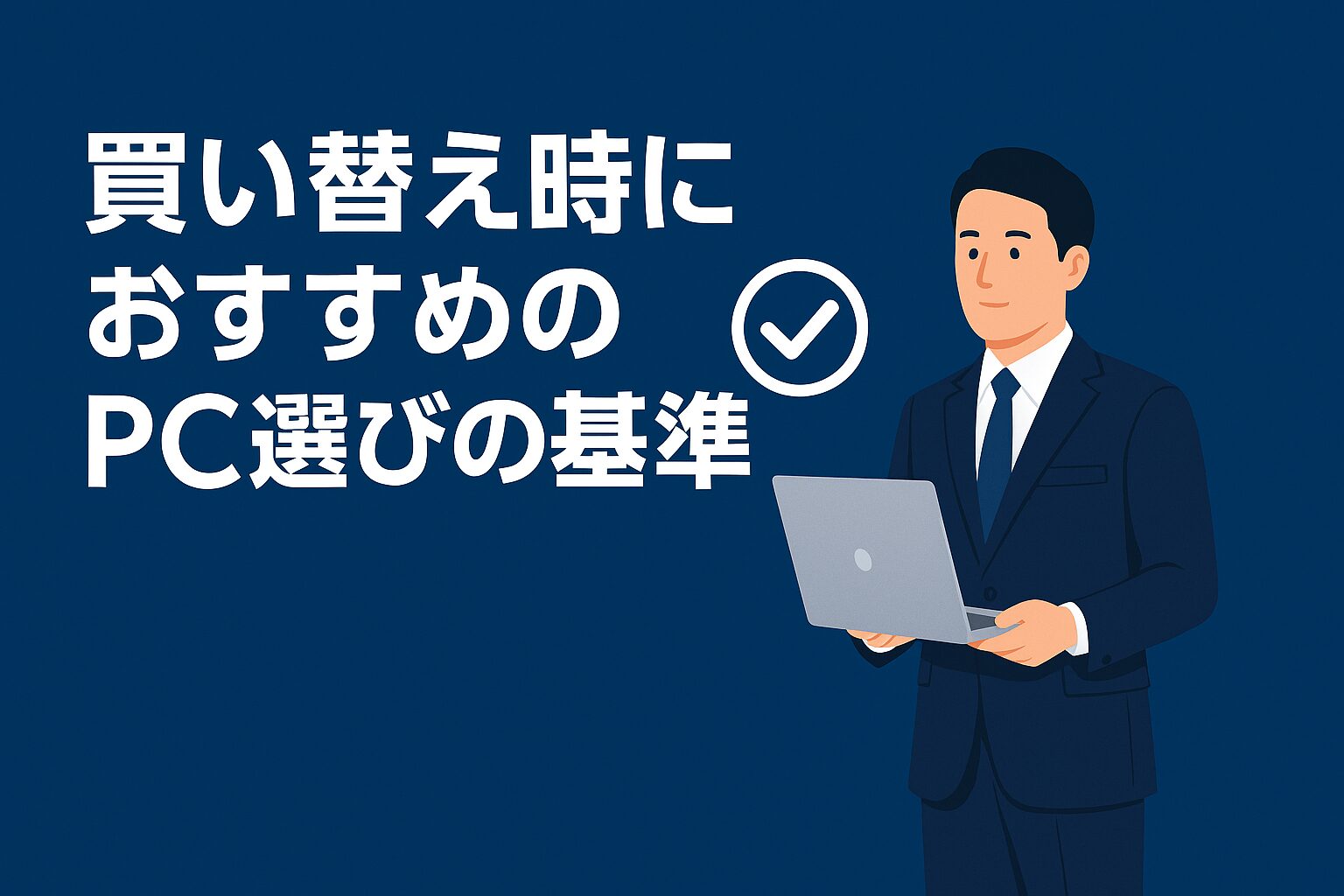
Windows11に対応していないPCを使っている人にとって、買い替えは最も確実で安心な選択肢です。
ただし、「どんなPCを選べばいいのかわからない」という声も多いですよね。
ここでは、買い替えのタイミング・選び方・用途別おすすめスペックをわかりやすく紹介します。
買い替えを検討すべきサイン
以下の項目にひとつでも当てはまる場合は、買い替えのタイミングです。
✅ 起動やアプリの立ち上がりが遅い
✅ HDD(ハードディスク)搭載モデルを使っている
✅ メモリが8GB未満
✅ CPUが「第7世代以前(Intel Core i7-7700以前)」
✅ Windows11非対応と診断された
これらの条件では、今後のOSアップデートやソフト利用で支障が出る可能性が高くなります。
新しいPCを選ぶときの3つのポイント
1. CPU(頭脳)
- Intel Core i5 / Ryzen 5以上を推奨。
- 動画編集や3D作業をするならCore i7 / Ryzen 7以上が安心です。
- 「Celeron」や「Pentium」搭載モデルは動作が遅く、長期利用には不向きです。
2. メモリ(作業スペース)
- 一般用途なら8GB
- ビジネスや複数作業を同時に行うなら16GB以上
- クリエイティブ用途(動画・画像編集)なら32GB以上が快適です。
3. ストレージ(保存領域)
- SSD(ソリッドステートドライブ)必須。HDDモデルは起動が非常に遅くなります。
- 容量は最低256GB以上、写真や動画を多く扱うなら512GB〜1TBを目安に。
用途別おすすめスペック早見表
💻 一般利用(ネット・動画・メール中心)
| 項目 | 推奨スペック | おすすめ機種例 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3 / Ryzen 3 以上 | Lenovo IdeaPad Slim 3(楽天市場で見る) |
| メモリ | 8GB | ASUS Vivobook 15(楽天市場で見る) |
| ストレージ | SSD 256GB以上 | HP 240 G9(楽天市場で見る) |
| 価格帯 | 約7〜9万円 | 初心者や学生におすすめのコスパモデル |
💡ポイント:オンライン授業・動画視聴・SNSなど、日常使いに最適。
ブラウジングがサクサク動くSSD搭載モデルを選びましょう。
🧑💼 ビジネス・事務作業用(テレワーク・Excel中心)
| 項目 | 推奨スペック | おすすめ機種例 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 / Ryzen 5 | Dell Inspiron 14 ノートパソコン(楽天市場で見る) |
| メモリ | 16GB | HP Pavilion Aero 13(楽天市場で見る) |
| ストレージ | SSD 512GB | Lenovo ThinkBook 14 Gen5(楽天市場で見る) |
| 価格帯 | 約10〜14万円 | 仕事・副業どちらにも使いやすい軽量ノートPC |
💡ポイント:Office系作業・Zoom・副業ブログ運営などに最適。
静音・軽量タイプを選ぶとテレワーク効率が格段に上がります。
🎬 クリエイティブ作業(動画編集・デザイン・AI用途)
| 項目 | 推奨スペック | おすすめ機種例 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 / Ryzen 7 以上 | Apple MacBook Air M3(楽天市場で見る) |
| メモリ | 32GB | ASUS Vivobook Pro 16X(楽天市場で見る) |
| ストレージ | SSD 1TB | MSI Creator Z16(楽天市場で見る) |
| 価格帯 | 約18〜25万円 | 高負荷作業に強い高性能モデル |
💡ポイント:YouTube編集やCanvaデザイン、副業動画制作などに最適。
GPU搭載モデルを選ぶとレンダリング速度が大幅に向上します。
🕹 ゲーム・高性能PC派
| 項目 | 推奨スペック | おすすめ機種例 |
|---|---|---|
| CPU | Core i9 / Ryzen 9 | ASUS ROG Zephyrus G14(楽天市場で見る) |
| メモリ | 32GB以上 | MSI Raider GE78 HX(楽天市場で見る) |
| GPU | RTX 4070〜4090 | Dell Alienware M16(楽天市場で見る) |
| 価格帯 | 約25〜40万円 | ゲーム配信・3D制作にも対応するプロ仕様モデル |
💡ポイント:4K編集やゲーミング配信をしたい人向け。
冷却性能やディスプレイ品質も重視すると後悔しません。
💡 迷ったらこれ!筆者おすすめNo.1モデル
👉 HP Pavilion Aero 13(在庫を確認する)
軽量・高性能・価格バランスが最強の1台。テレワークにも副業にも最適です。
ノートPC vs デスクトップ どっちを選ぶべき?
| タイプ | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ノートPC | 軽量・省スペース・持ち運びやすい | 自宅でも外出先でも使いたい人、在宅勤務者 |
| デスクトップPC | 拡張性が高くコスパ良し | 長時間作業やクリエイティブ業務向け、パフォーマンス重視派 |
近年ではノートPCでも十分な性能が得られるため、一般ユーザーにはノート型が人気です。
Windows11搭載PCを選ぶときの注意点
- プリインストールOSがWindows11 HomeまたはProか確認
- Office搭載モデルはライセンスが永続型かサブスク型かをチェック
- メーカー保証期間(1年以上)と修理対応の有無
- クレカ決済や延長保証オプションの利用も検討
これらを確認しておけば、長期的に安心して使えます。
おすすめメーカーの一例
- 国内メーカー:NEC、富士通、Dynabook
→ 安心のサポート体制、初心者におすすめ - コスパ重視:Lenovo、HP、ASUS、Acer
→ 性能の割に価格が安く、種類が豊富 - ビジネス用途:Dell、Microsoft Surface
→ 堅牢性が高く、デザイン性も優秀
タイミングは「今がベスト」
サポート終了直後の今は、各メーカーがWindows11対応モデルのセールを強化しています。
年末にかけて在庫が減る傾向があるため、迷っているなら早めの決断が得策です。
まとめ
- Windows11非対応なら、早めに買い替えを検討
- CPUはCore i5以上、メモリ16GB以上、SSD搭載が基本
- 使い方と予算に合ったモデルを選べば、5年以上快適に使える
新しいPCは、ただの機械ではありません。
「安心して仕事・生活を続けるための投資」です。
次章では、この記事の最終まとめとして
「今すぐ行動すべき理由と、Windows10からの安全な卒業ステップ」を解説します。
第七章 まとめ – 今すぐ行動すべき理由
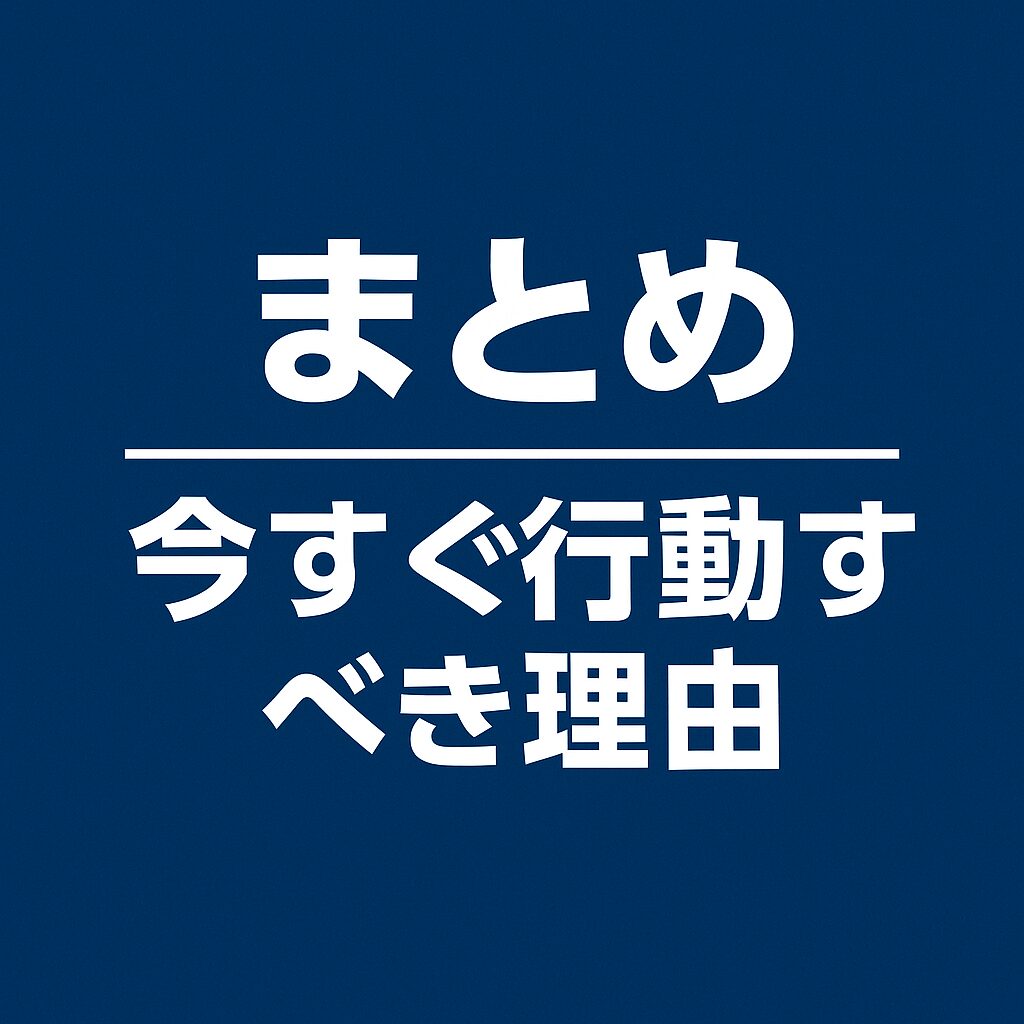
2025年10月14日、Windows10のサポートは正式に終了しました。
この日を境に、あなたのPCはもうMicrosoftの保護の外に置かれています。
動くからといって安全とは限りません。
それは、セキュリティのないネットに接続されたPCを使うということ。
見えないリスクは、気づかないうちにあなたのデータ・お金・時間を奪っていきます。¥
先延ばしが“最大のリスク”
サポート終了後のWindows10は、使えば使うほどリスクが積み重なります。
- 新しいウイルスへの防御ができない
- 銀行やECサイトでの利用が危険
- ソフトや周辺機器が徐々に非対応
これらの問題は、“ある日突然”やってきます。
多くの人が「昨日まで動いていたのに…」と後悔するのです。
行動すれば、安全も快適さも取り戻せる
逆に、今日行動すれば、あなたのPC環境は一気に安全で快適になります。
- 対応PCならWindows11に無料アップグレード
- 非対応PCならESUで安全を延長
- 古いPCなら最新モデルに買い替えて5年安心
どの方法を選んでも、共通して言えることはひとつ。
「行動した人から安心を得られる」ということです。
Windows11への移行で得られる3つの未来
- セキュリティの安心
→ Microsoftが継続的に守ってくれる環境へ。 - 快適な動作と新機能
→ 起動も速く、AI機能や最新UIも使える。 - 長期的なコスパの良さ
→ OS更新が不要になり、5〜10年安心して使える。
つまり、Windows11は“次の時代の標準OS”です。
あなたの作業効率も安全性も、すべてここから変わります。
今やるべき3つのステップ
✅ 1. 自分のPCがWindows11対応かチェックする
→ Microsoft公式「PC 正常性チェック」ツールで確認。
✅ 2. データをバックアップして準備
→ OneDriveや外付けHDDで大切なファイルを保存。
✅ 3. アップグレードまたは買い替えを実行
→ 対応PCなら即アップグレード。
→ 非対応PCならESU登録、もしくは新しいPCへ移行。
この3つを済ませれば、あなたのPC環境は再び“安全圏”に戻ります。
最後に伝えたいこと
テクノロジーの進化は止まりません。
そして、セキュリティの脅威もまた日々進化しています。
「そのうちやろう」ではなく、
「今やる」ことがあなたの情報と資産を守る最善の方法です。
💡 結論:今日の決断が、5年後の安心をつくる
Windows10の時代にありがとうを。
そして、これからの安心をWindows11で。
✅ 今すぐやるべきアクションリスト
- PCが対応している → [Windows11へ無料アップグレード]
- 対応していない → [ESU延長プログラムに登録]
- 古いPC → [Windows11搭載モデルに買い替え]