※本ページはプロモーションが含まれています。
高市政権で中国関連株が売られる背景とは?

高市早苗政権が発足した直後から、市場では中国関連株に強い売り圧力がかかる状況が続いています。
特に、訪日観光に依存するインバウンド関連企業、中国市場での売上比率が高い企業、そして中国と深いサプライチェーンを持つ製造業まで幅広く株価が下落しました。まずは、その背景を事実ベースで整理します。
高市首相の発言が市場心理に影響を与えた
高市首相はこれまでも台湾情勢に対して明確な危機認識を示しており、台湾海峡の安定を強く重視する姿勢をとってきました。
このスタンスに対し、中国政府は即座に反発を強め、自国民に「日本への渡航自粛」を促す対応を取りました。
これが市場の不信感を一気に高め、中国関連株の売りを誘発しました。
訪日客の流れを左右する政策・外交的声明は、即座に百貨店、空港運営、鉄道、化粧品、小売といった業界に影響します。
投資家は需要減を織り込む形で株価を調整し始め、関連企業の株価は連日大きく売られる展開となりました。
インバウンド関連銘柄の急落が象徴的
中国政府が渡航自粛を発表した直後、最も大きく売られたのがインバウンド関連の銘柄です。
航空・鉄道・百貨店など訪日需要に業績が直結する企業にとって、中国人観光客の減少は売上へのインパクトが大きく、市場は早期にリスクを織り込みに動きました。
こうした値動きは「高市政権 × 中国関連」というテーマが、瞬時に市場参加者の意識に入り込んだことを示しています。
中国市場依存企業にも波及した売り
売り圧力はインバウンド銘柄だけにとどまりませんでした。
日本企業の中には、中国での売上が全体の30〜50%を占める企業も珍しくありません。
今回の緊張感の高まりを受け、投資家は「中国ビジネス全体の縮小リスク」を意識し、これらの企業も売却対象となりました。
たとえば、
- 日用品・化粧品メーカー
- アパレル企業
- 小売チェーン
- 製造業の一部
などが一斉に下落し、「中国関連度の高い企業」がマーケットで可視化される展開となりました。
市場が恐れているのは「業績悪化」ではなく“関係悪化の長期化”
株価の下落は単なる短期業績への懸念ではありません。
市場が最も恐れているのは、外交関係の悪化が長期にわたって続き、中国からの規制・報復措置が常態化するシナリオです。
投資家は、もしこの流れが長期化すれば、
- 中国人観光客の戻りが遅れる
- 中国市場での販売が鈍化する
- サプライチェーン再構築コストが重くのしかかる
といった複合的な悪影響が広がると判断しています。
高市政権のスタートと同時に売りが加速したのは、まさにこの「長期リスク」を市場が織り込み始めたからです。
高市政権で何が変わるのか?政策リスクと日中関係の行方
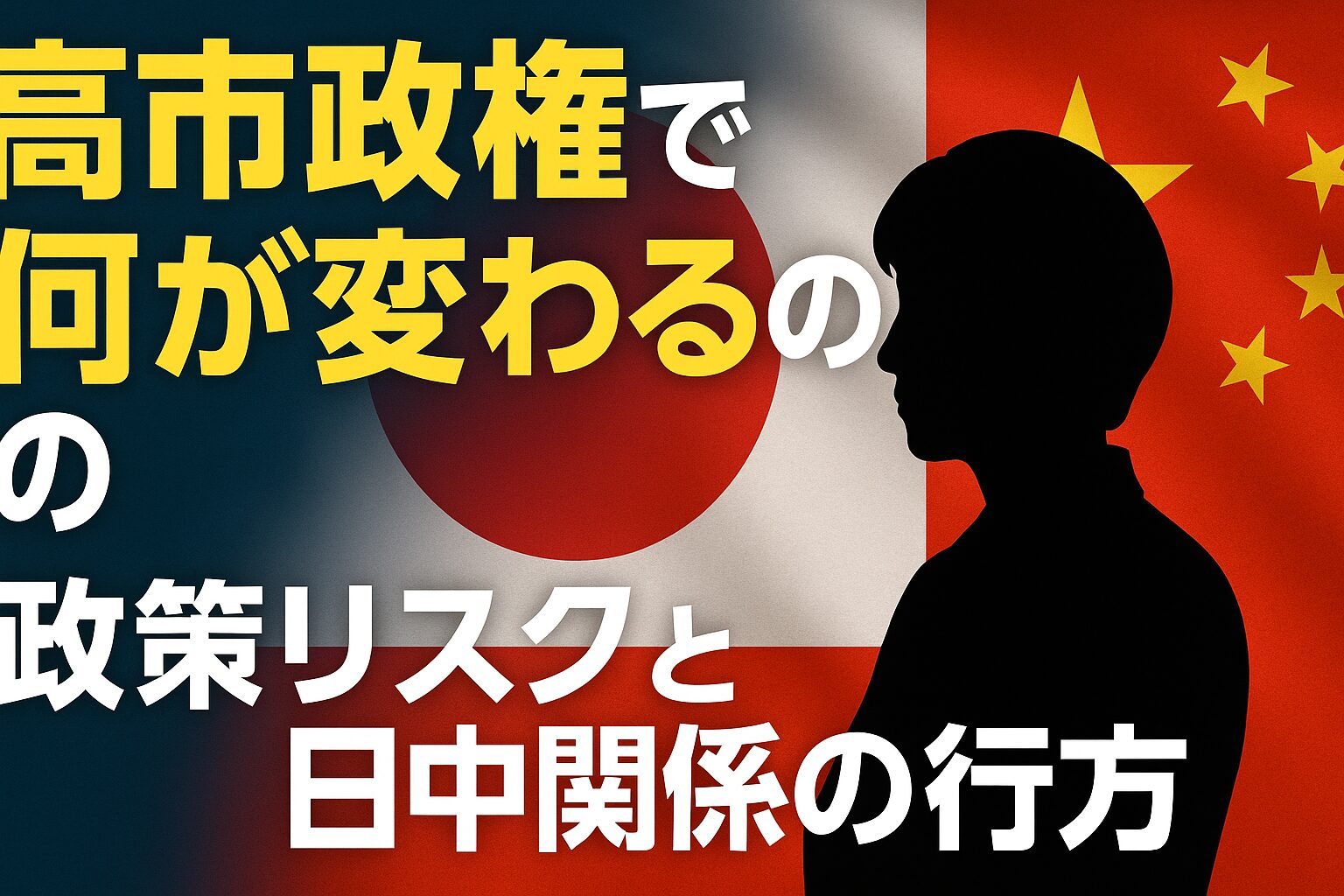
高市政権の発足により、これまでの日本の外交・経済政策は新たな方向性を示し始めています。
特に中国との関係においては、市場が敏感に反応する要素が多く、高市首相の政策スタンスは投資家にとって重要な判断材料となっています。
この章では、事実ベースで「何が変わり、何がリスクになるのか」を整理します。
高市首相は“対中強硬路線”が明確な政治家
高市首相は、これまでの発言や政策提言を見る限り、明確に中国依存を減らす方向性を示してきました。
その特徴は次のとおりです。
- 経済安全保障を最優先課題に掲げる
- 台湾有事に対する危機認識が強い
- サプライチェーンの中国依存度を下げる方針を持つ
- デジタル・防衛・半導体などの国策分野強化を重視
これらの方針に対し、中国政府は敏感に反応しており、今回の「渡航自粛要請」のように、関係悪化の火種が表面化しやすい構造になっています。
市場が警戒する“政策リスク”とは何か?
高市政権の政策は、その多くが長期的には日本の競争力向上につながる内容ですが、短期的には以下のようなリスクを引き起こす可能性があります。
1. 中国依存サプライチェーンの見直しによるコスト増
製造業を中心に、中国からの調達や現地生産は長年続いてきたコスト優位性の象徴です。
しかし、高市政権では「中国依存脱却」を柱のひとつとして掲げているため、企業は以下の負担を背負う可能性があります。
- 調達先の変更に伴うコストアップ
- 生産拠点移転にかかる投資
- 生産効率の一時低下
この影響は短期的な業績悪化につながり、中国関連株には売り材料になります。
2. 外交的対立が企業の業績に波及する可能性
今回の「渡航自粛」発表のように、中国政府は外交カードとして民間の往来や経済活動を制限することがあります。
その結果、
- インバウンド需要の低下
- 中国国内での日本企業の販売が伸び悩む
- 新規出店や投資が遅れる
- 輸出入手続きの厳格化
など、企業活動の幅広い領域で悪影響が出る可能性があります。
特に、
- 百貨店
- 小売
- 化粧品
- 空運(航空会社)
- 不動産・ホテル
といった「中国人の購買行動」に依存する企業は、継続的な売り圧力を受けやすい状況です。
3. 国防・安全保障政策の強化により地政学リスクが高まる可能性
高市首相の政策では、防衛分野を含む「安全保障の強化」が最優先課題です。
しかしこれは、中国からの警戒感を強める要因でもあります。
地政学リスクが高まると、市場は次のような反応を示します。
- リスク資産からの資金逃避
- 中国関連企業への売り加速
- 円高圧力が発生し輸出企業の業績懸念が台頭
つまり政治の変化が、投資家心理を揺さぶり、株価に波及する環境が続いているのです。
では、日中関係は今後どう動くのか?(事実ベースで整理)
現時点で確認されている事実は以下の通りです。
- 高市政権は中国依存を減らす明確な方針を持っている
- 中国政府はこれに強く反発している
- 市場は外交面の緊張感を敏感に株価へ織り込み始めている
しかし、ここで重要なのは「悪化が確定しているわけではない」という点です。
中国側もビジネス面では日本との協調が不可欠な分野が多く、
日本企業に対して全面的に規制をかける状況ではありません。
つまり、
“緊張は高いが断絶には至っていない”
というバランスが現状の正しい理解になります。
中国関連株にとって「いちばん警戒すべき」は関係悪化の長期化
短期的な問題であれば株価は調整後に戻ることが多いですが、
投資家が今もっとも懸念しているのは次の部分です。
- 外交的な緊張が長期化する
- 中国市場の需要が戻らない
- 日本企業の現地投資が停滞する
- サプライチェーン再構築の負担が長期的な収益圧迫につながる
これらが現実化すると、中国関連株にとって中期〜長期の逆風が続くシナリオとなります。
市場が敏感に反応しているのは、この「長期リスク」への警戒が強いからです。
投資家が描く望ましい未来とは?チャンスと期待
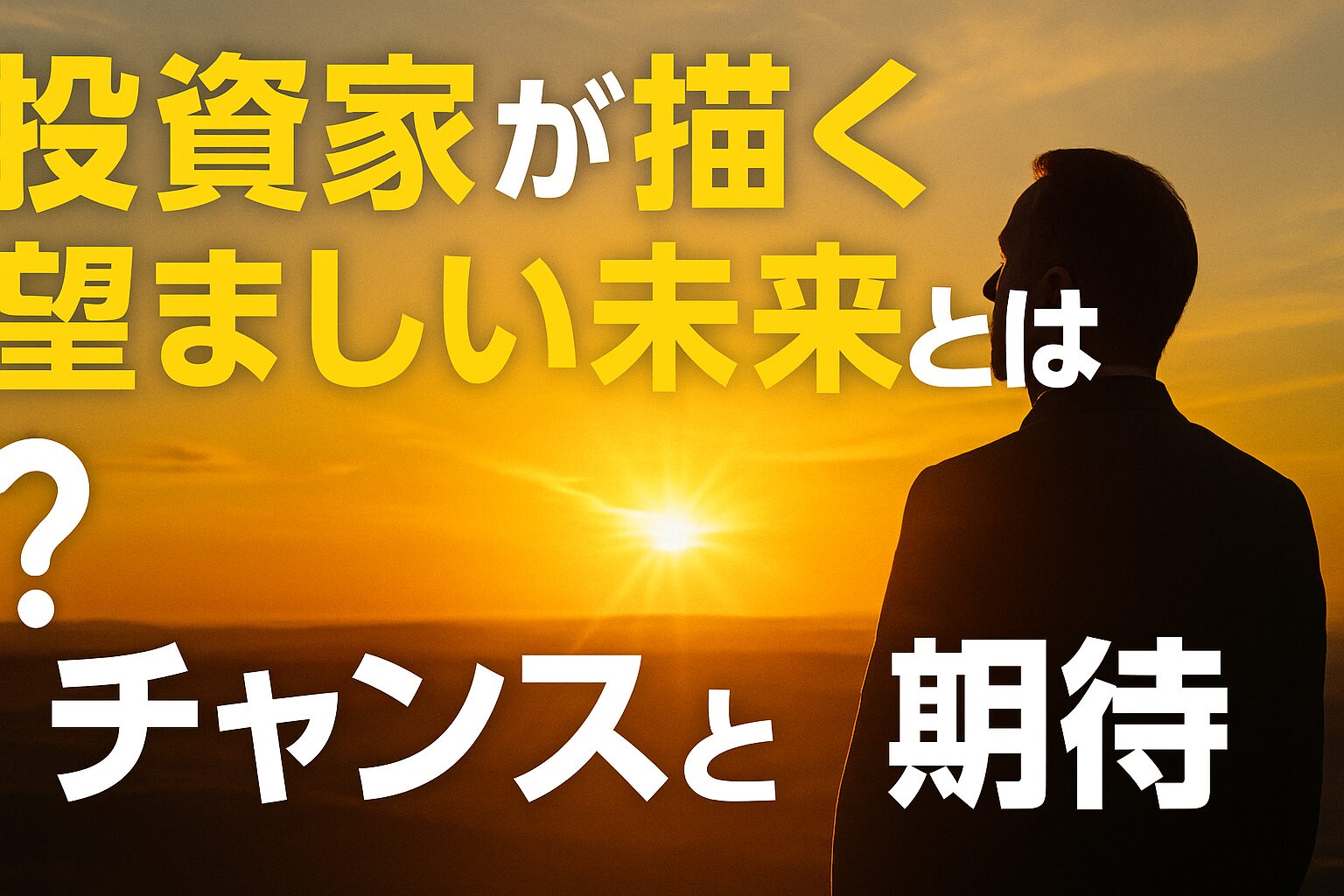
高市政権の誕生は、市場にとって一見ネガティブな側面ばかりが注目されがちですが、実はその裏側に 大きなチャンス が存在しています。
投資家が本当に知りたいのは、
- 「どんな銘柄が危ないのか?」
- 「どこに資金が流れ始めているのか?」
- 「この政策変化をどう“味方”にするか?」
という未来志向の視点です。
この章では、事実ベースで“高市相場”の追い風となる要素を整理し、投資家が描きうる望ましい未来を明確にします。
中国関連株が売られても市場全体は悪くないという事実
まず押さえておくべきポイントは、
「中国関連株≠日本株全体」 だということです。
実際、市場では次のような動きが確認されています。
- 中国依存度の高い銘柄は売られやすい
- 一方で、高市政権の政策に沿った“国策テーマ株”には資金流入が発生
- インバウンドや小売の下げを、半導体や防衛関連が吸収する動き
つまり、
「痛む場所と伸びる場所」がハッキリ分かれてきている
というのが現在の相場の特徴です。
ここにこそ、投資家にとっての大きなチャンスがあります。
高市政権が掲げる17の戦略分野は市場の資金の“受け皿”になる
高市政権では、
「経済安全保障」と「積極財政」の2本柱が打ち出されています。
そして、政府が重点的に投資を進める17の戦略分野には、
すでに投資家の目線が集まり始めています。
代表的な分野は以下の通りです。
- 防衛・宇宙
- 半導体・先端素材
- AI・量子技術
- サイバーセキュリティ
- エネルギー(原発・核融合)
- インフラ・国土強靭化
- 国産化関連
- デジタル産業
高市政権の支持率が8割を超えて高いことからも、
市場は「政策の実行力=テーマ株の継続的な追い風」を期待する構造になっています。
投資家が描く“理想の未来”は次の2点に集約される
投資家は、高市政権のリスクとチャンスを踏まえ、次のような未来を望んでいます。
1. 中国関連の下落リスクから資産を守ること
- インバウンド依存が強い銘柄を減らす
- 中国市場への売上比率の高い企業の比率を調整する
- サプライチェーン依存が強すぎる企業を避ける
つまり 「リスク源をしっかり見極める」 ことが理想の第一歩です。
2. 高市政権が推進する“国策テーマ”の成長を取り込むこと
これはまさに、
“国策に売りなし” の現代版 です。
具体的には、次のような利益が期待できます。
- 防衛予算増で、防衛産業が長期的に成長
- 半導体国産化支援により製造装置・素材の需要拡大
- サイバー攻撃増でセキュリティ需要が拡大
- AI・量子技術への研究開発投資が増加
- インフラ強化で建設・メーカーが潤う
高市政権が掲げる「積極財政」は、
“予算が動く → 関連企業が伸びる → 株価に反映される”
という非常にシンプルな仕組みを市場にもたらします。
これは株式市場にとって明確な追い風です。
なぜ“中国関連売り × 国策買い”が最強の流れなのか?
理由は非常にシンプルです。
市場は「避けたいもの」から逃げ、「伸びるもの」に集中する
- リスク要因(中国関連)が明確 → 売られる
- 成長テーマ(国策)が明確 → 買われる
これはすでに市場で起きている事実であり、
投資家はそこに沿って動くことで利益チャンスを最大化できます。
具体的にどのテーマにチャンスがあるのか?
次章で詳細に解説しますが、“予兆”としては下記が特に強いです。
- 防衛
→ 三菱重工、川崎重工、IHI などは政策と需給が直結しやすい分野 - 半導体
→ 日本製素材・装置企業は国産化支援の恩恵が大きい - サイバーセキュリティ
→ 国家レベルで予算が増えるため構造的に伸びやすい - インフラ・国土強靭化
→ 震災対策や老朽化対策で長期テーマになる - AI・量子技術
→ 新産業の枠として最も政策恩恵の大きい分野
つまり、
中国関連の下げを“避難所”とし、高市政策の追い風を“上昇エンジン”に変える
というのが投資家の理想のストーリーなのです。
高市関連銘柄とは?注目テーマと具体的企業例

高市政権の発足によって、市場では早くも「高市銘柄」という言葉が浸透し始めています。
これは単なる流行語ではなく、政府の方針と予算配分が株価トレンドを動かす現実的な投資テーマです。
中国関連株が売られる一方で、資金が向かっているのは次のようなテーマ。
この章では、その中心となるセクターと具体的な企業を、事実ベースでわかりやすく整理します。
防衛関連は最重要テーマ。継続的に予算が流れ込む
高市政権が特に重視しているのが、防衛力強化と経済安全保障の徹底です。
現在の日本は、防衛費を
「GDP比2%」に段階的に引き上げる方針
を明確にしています。
これにより、防衛関連は長期に渡る追い風が期待できる数少ない国策分野です。
代表的な銘柄
- 三菱重工業
→ ミサイル防衛、護衛艦、航空エンジンなど国家基盤を支える主力企業 - IHI
→ エンジン、宇宙・防衛領域で需要拡大 - 川崎重工業
→ 潜水艦、航空機関連で恩恵 - NEC・富士通(日米連携の防衛通信)
→ 安全保障通信網の強化で需要増が見込まれる
防衛は「予算が削られにくい分野」であり、
地政学リスクが高まるほど資金が流れやすい
という特性があります。
サイバーセキュリティは“新時代の防衛”として資金流入が加速中
高市政権は、日本のサイバー防衛力を強化する方針を強く示しています。
政府・企業へのサイバー攻撃は年間数万件規模で発生しており、国策として避けられないテーマです。
代表的な銘柄
- NTT(NTTセキュリティ)
→ 国家レベルの防御網を担う中心的企業 - 富士通
→ 公共・企業向けセキュリティソリューションに強み - 日立製作所
→ 重要インフラ防衛で存在感
サイバー領域は、アメリカやEUでも成長産業の中心となっており、
高市政権の政策を受けて日本でも加速する見通しです。
半導体・先端素材は国産化シフトで利益拡大の可能性
サプライチェーン強化と経済安全保障の観点から、
日本は半導体製造を「国家戦略」に位置づけています。
これは中国依存度を下げる政策とも整合しており、
株式市場では“長期テーマ”として注目が高まっています。
代表的な銘柄
- 東京エレクトロン(装置)
- SCREENホールディングス(洗浄装置)
- アドバンテスト(検査装置)
- 信越化学工業(半導体向け素材)
- SUMCO(シリコンウェーハ)
これらは世界トップシェアを持つ企業も多く、
国策×世界需要 のダブル追い風が期待できます。
インフラ・国土強靭化は継続予算で安定した成長が期待される
高市政権は積極財政を掲げており、
老朽化インフラの刷新、防災・減災対策にも大規模予算を投じる方針を示しています。
代表的な銘柄
- 大成建設・清水建設・大林組(ゼネコン)
- 日立製作所・東芝(社会インフラ)
- 前田道路・NIPPO(道路インフラ)
国土強靭化は毎年安定した予算がつきやすいため、
**値動きが重くても中長期で堅実に成長する“ディフェンシブな国策テーマ”**です。
AI・量子技術は“未来の成長産業”として高市政権が重点投資
AI、量子コンピュータ、ロボティクスなどは、
日本が国際競争力を維持する上で不可欠な分野です。
代表的な銘柄
- 日立製作所(AI・量子)
- 富士通(量子コンピュータ)
- ソニーグループ(AI・半導体)
- ソフトバンクG(AI投資)
これらは短期で上下しやすいですが、
国策テーマは長期で伸びる傾向が明確です。
エネルギー(原発・核融合)は再注目テーマ
高市政権はエネルギー安全保障を強化する方針を掲げています。
日本はエネルギーの多くを輸入に頼っているため、
原発再稼働や核融合研究が政策の中心に置かれています。
代表的な銘柄
- 三菱重工(原発設備)
- 東芝(原子力関連)
- 東洋炭素(核融合素材)
特に核融合は世界的に“次世代エネルギー”として注目されており、
政府支援の規模が拡大すれば長期テーマになりやすい分野です。
国策テーマ全体が中国関連株の“逆相関”で資金の受け皿に
中国関連株が売られるタイミングでは、
その資金がどこに向かうのかが非常に重要です。
現状、市場は次のように反応しています。
- 中国関連 → 売られる(インバウンド、化粧品、小売など)
- 国策テーマ → 買われる(防衛、半導体、サイバーなど)
そのため、
“高市政権×国策テーマ”は相場の中心軸になる可能性が高い
と言えるでしょう。
ポートフォリオを守りつつ成長を取り込むには?理想の資産構成と実践ステップ
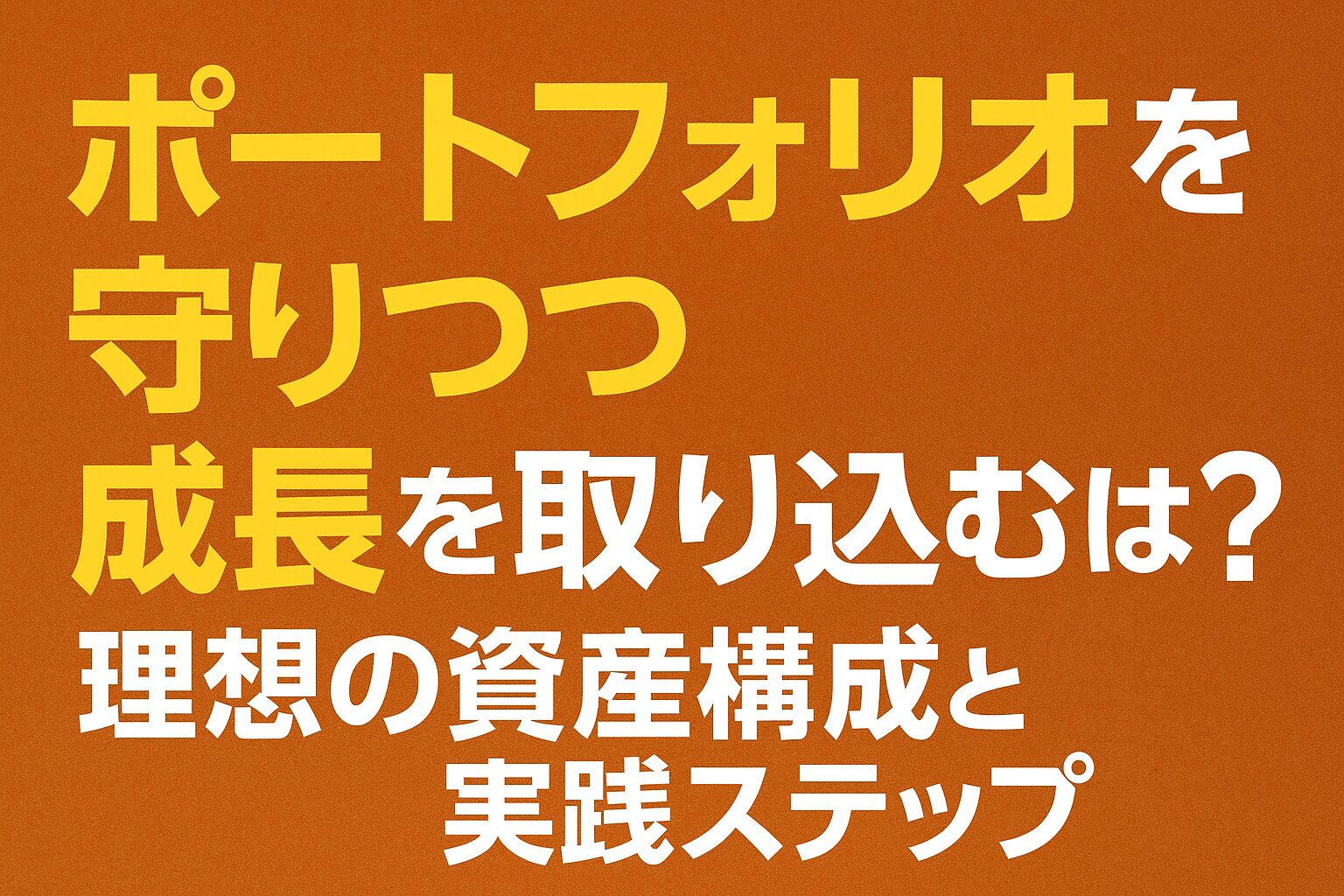
高市政権の発足で市場構造が変わりつつある今、最も重要なのは
「リスクを減らしながら、国策テーマで成長を取り込むバランス」 を実現することです。
市場は常に変動しますが、
・地政学リスク(中国関連の下落)
・国策テーマ(防衛・半導体・サイバーなど)の上昇
という“二極化”が進んでいる状況では、ポートフォリオにも柔軟な調整が求められます。
この章では、初心者でもすぐに実践できる「理想のポートフォリオ像」と「行動ステップ」を、専門家の視点で整理します。
今の相場に合ったポートフォリオ構成の基本方針
結論から言うと、今の相場で個人投資家が目指すべきなのは次の構成です。
1 中国関連資産の比率は“必要以上に高くしない”
中国依存度が高い企業は、市場のニュースや政策発言に反応しやすく、
株価が大きく揺れやすい性質があります。
代表的なリスク例
- 中国人観光客の減少
- 中国政府による対抗措置(渡航自粛・不買運動など)
- 日中外交摩擦による売上圧迫
- 中国景気の減速
- 現地ロックダウンや規制強化での供給停止
これらは**企業努力ではコントロールできない“外部要因リスク”**です。
そのため、
中国関連比率はポートフォリオ全体の30%以下を推奨
とする投資家も多く、特に現在の情勢では妥当な目安と言えます。
2 国策テーマ(高市関連株)は“成長枠”として組み入れる
防衛・半導体・サイバー・インフラ・AIなどは、
政府の予算がつく=中長期の成長が期待できる「国策テーマ」です。
国策テーマは以下の特徴があります。
- 業績への追い風が長期で続きやすい
- 市場全体が下がる時でも資金が集まりやすい
- テーマが継続する限り投資家の関心が途切れない
そのため、成長枠として
20〜40%程度を国策分野に割り当てる
のが現実的な戦略となります。
例:
- 防衛
- 半導体
- AI
- サイバーセキュリティ
- 国土強靭化
- インフラ更新
- エネルギー(原発・核融合)
これらはいずれも高市政権の政策と整合しており、
市場もすでに資金を振り向けています。
3 安定運用枠(ディフェンシブ株・現金)でポートフォリオを支える
市場が荒れたときに強いのが「ディフェンシブ銘柄」です。
具体例
- 食品
- 通信(NTTなど)
- 医薬品
- 電力・ガス
また、現金比率を10〜20%程度確保しておくと、
大きく下落したときの買い場にすぐ動けます。
100万円ポートフォリオの“理想モデル例”
実際に100万円を運用する場合、次のような構成がバランスが良い例です。
モデル例①(バランス型)
| 分野 | 割合 | 金額 |
|---|---|---|
| 中国関連株 | 20% | 20万円 |
| 国策テーマ(防衛・半導体・AIなど) | 40% | 40万円 |
| ディフェンシブ株 | 20% | 20万円 |
| 現金 | 20% | 20万円 |
→ リスクと成長を両立した、誰でも取り組みやすい構成。
モデル例②(成長重視)
| 分野 | 割合 | 金額 |
|---|---|---|
| 中国関連株 | 10% | 10万円 |
| 国策テーマ | 50% | 50万円 |
| ディフェンシブ株 | 20% | 20万円 |
| 現金 | 20% | 20万円 |
→ 国策テーマの上昇トレンドをしっかり取り込む構成。
モデル例③(守り重視)
| 分野 | 割合 | 金額 |
|---|---|---|
| 中国関連株 | 20% | 20万円 |
| 国策テーマ | 30% | 30万円 |
| ディフェンシブ株 | 30% | 30万円 |
| 現金 | 20% | 20万円 |
→ 下落局面でも大きく崩れにくいリスク低減型。
高市政権相場で失敗しないための3つのルール
ルール1:ニュースで慌てて売らない
短期的な発言や外交ニュースで売買すると、
ほぼ間違いなくタイミングを誤ります。
必要なのは
「長期トレンド:国策」
「短期リスク:中国関連」
の違いを理解することです。
ルール2:テーマ集中しすぎない
防衛・半導体・AIなどは人気ですが、
どれか一つに全振りするのは危険です。
テーマは循環し、
資金が移動するタイミングがあります。
ルール3:年に2〜4回のリバランスでポートフォリオを最適化する
評価額の動きに合わせて比率が偏ったら、
年に数回、元のバランスに戻すだけで
リスクを抑えながら収益を高められます。
高市政権の変化を味方につけ、賢い投資判断を
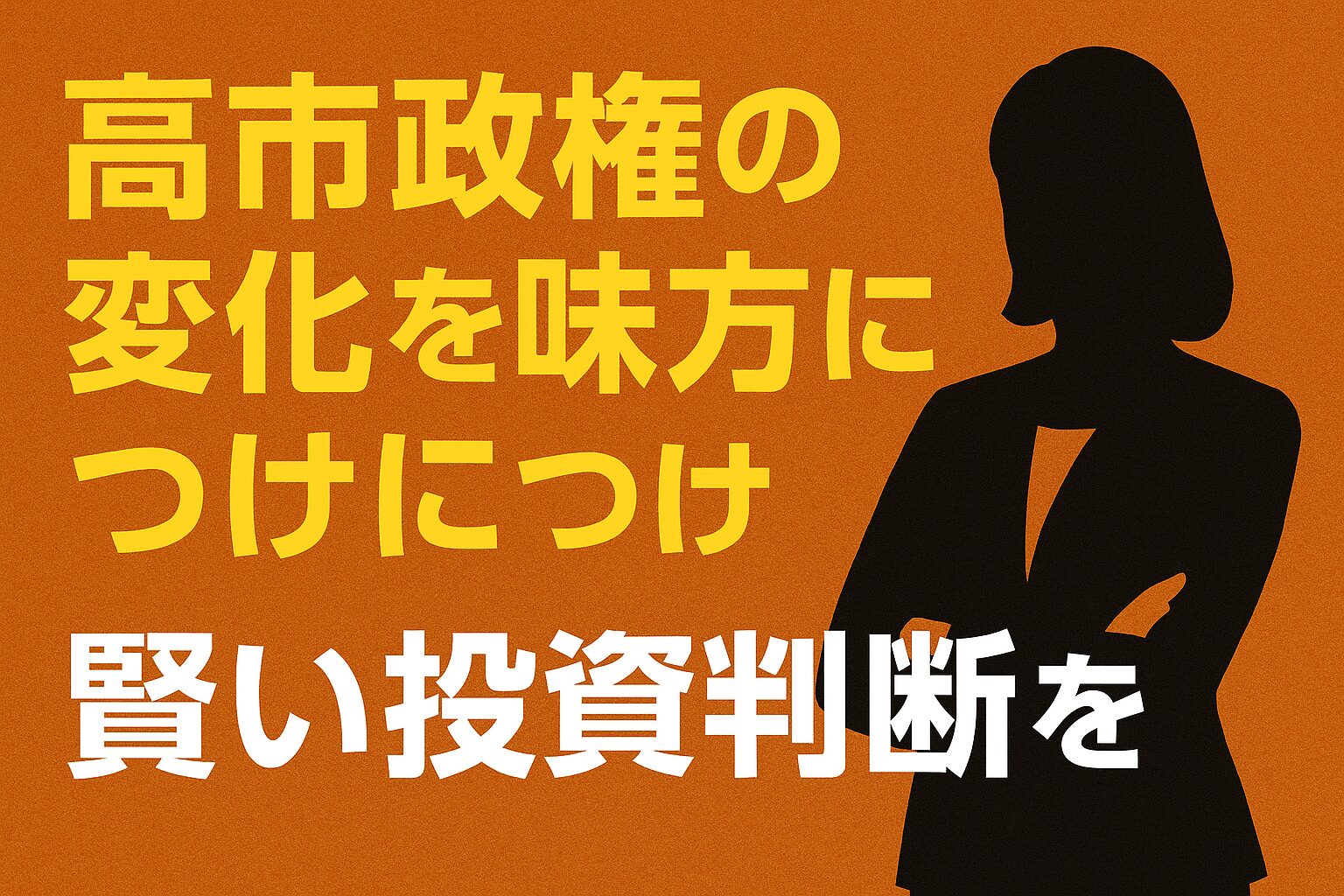
高市政権の発足によって、市場には大きな変化が訪れています。
中国関連株が売られる局面が続く一方で、防衛・半導体・先端技術など国策分野には強い資金流入が起きています。
本章では、本記事で解説したポイントを整理しつつ、今後の投資判断で何を意識すべきかをまとめます。
中国関連株が売られる動きは「地政学リスク」の表れ
今回の売りは、高市首相の安全保障姿勢に対する中国側の反発が引き金となり、訪日観光需要の後退懸念や、中国販売比率の高い企業への不安が一気に広がったことにあります。
市場では、
- インバウンド関連
- 中国向け売上比率が高い企業
- 中国からの調達依存度が高い企業
がまとめて売りの対象となりました。
これは「企業業績が悪化したから下がっている」のではなく、地政学リスクが一時的に株価に強く織り込まれている状態です。
リスクだけでなく「チャンス」も同時に生まれている
高市政権は国内産業の強化と経済安全保障を最重要テーマに掲げています。これにより、
- 防衛関連
- サイバーセキュリティ
- 半導体・AI
- エネルギー(核融合・次世代電力)
- インフラ・国土強靱化
などの国策セクターに資金が集中しています。
市場には「高市トレード」と呼ばれる投資テーマも生まれ、国策銘柄への関心が急速に高まっています。
つまり、今回の揺れは、
中国関連のリスクを減らし、国策テーマにシフトする好機
という側面も持っています。
投資家が今すぐできるアクション
本記事で解説した内容をもとに、個人投資家が実行できる行動をあらためて整理します。
1. 保有銘柄の中国依存度を確認する
売上比率、調達、観光依存など、企業のどこが中国と結びついているのかを可視化しましょう。
2. 過度に依存している銘柄は比率調整する
全面売却ではなく、リスク許容度に合わせて段階的に比率を下げることが重要です。
3. 国策テーマをポートフォリオに組み込む
防衛・サイバー・半導体など、高市政権が支援する分野に一部資金を振り向けることで、成長性を取り込めます。
4. 価格変動に備えて分散を徹底する
テーマ集中はリターンも大きいですが、リスクの波も大きくなります。
地域・セクター・通貨を分散して守りを固めましょう。
5. 情勢の変化に柔軟に対応する
日中関係はニュース一つで大きく動きます。
最新情報を絶えずチェックし、「状況に合わせて方針を変えられる」姿勢が不可欠です。
投資で最も重要なのは「情報を正しく読み解く力」
高市政権の政策は、リスクとチャンスが同時に進行する非常にダイナミックな環境を生み出しています。
だからこそ、感情的にならず、事実ベースで状況を読み解く姿勢が投資成果に直結します。
- 日中関係の緊張
- 国策による産業振興
- 消費者需要の変化
- 地政学的リスク
これらの動きを冷静に見極めれば、今回のような局面でも資産を守りながら成長機会をつかめます。
最後に(読者へのメッセージ)
高市政権下の市場は変化が大きく、不安を感じる投資家も多いはずです。
しかし、変化は必ずしも悪いことではありません。むしろ、環境が大きく動くときこそ、投資チャンスも増えていきます。
本記事の内容を参考にしながら、
- リスクを恐れすぎず
- 極端に楽観もせず
- 正しい情報をもとに冷静に判断する
という姿勢を大切にしてください。
変化の波を味方につければ、投資は必ずあなたの力になります。
今後の市場動向をしっかりと追いながら、賢い投資判断を行っていきましょう。
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

