はじめに|賃貸と持ち家の違いとは?
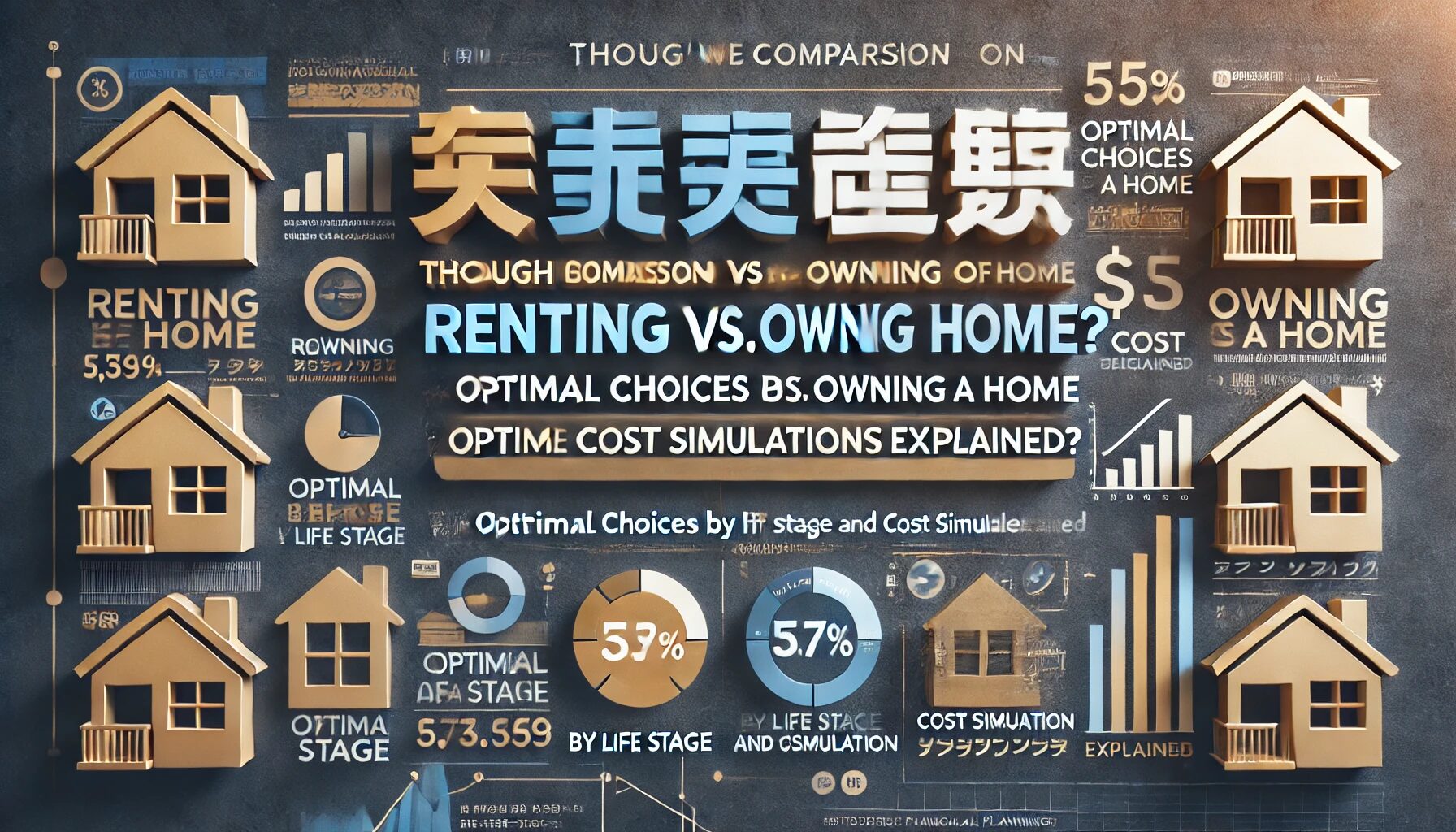
住まいを選ぶ際に、多くの人が悩むのが「賃貸に住み続けるか? それとも持ち家を購入するか?」という問題です。
どちらにもメリット・デメリットがあり、ライフスタイルや価値観、経済状況によって最適な選択肢は異なります。
賃貸は、住み替えの自由度が高く、初期費用を抑えられるのが魅力ですが、家賃を払い続けても資産にはならないという欠点もあります。
一方、持ち家は、長期的な資産形成や住宅の自由度が強みですが、住宅ローンや維持費などのコスト負担が大きいのがデメリットです。
まずはこちらをご覧ください👇
本記事では、賃貸と持ち家の違いを詳しく比較し、それぞれのメリット・デメリット、ライフステージ別の住まい選びのポイントなどを解説します。
最適な住まいの選択に役立ててください。
時間がない方向けに賃貸と持ち家の違いを表にまとめたよ👇
賃貸のメリットとデメリット
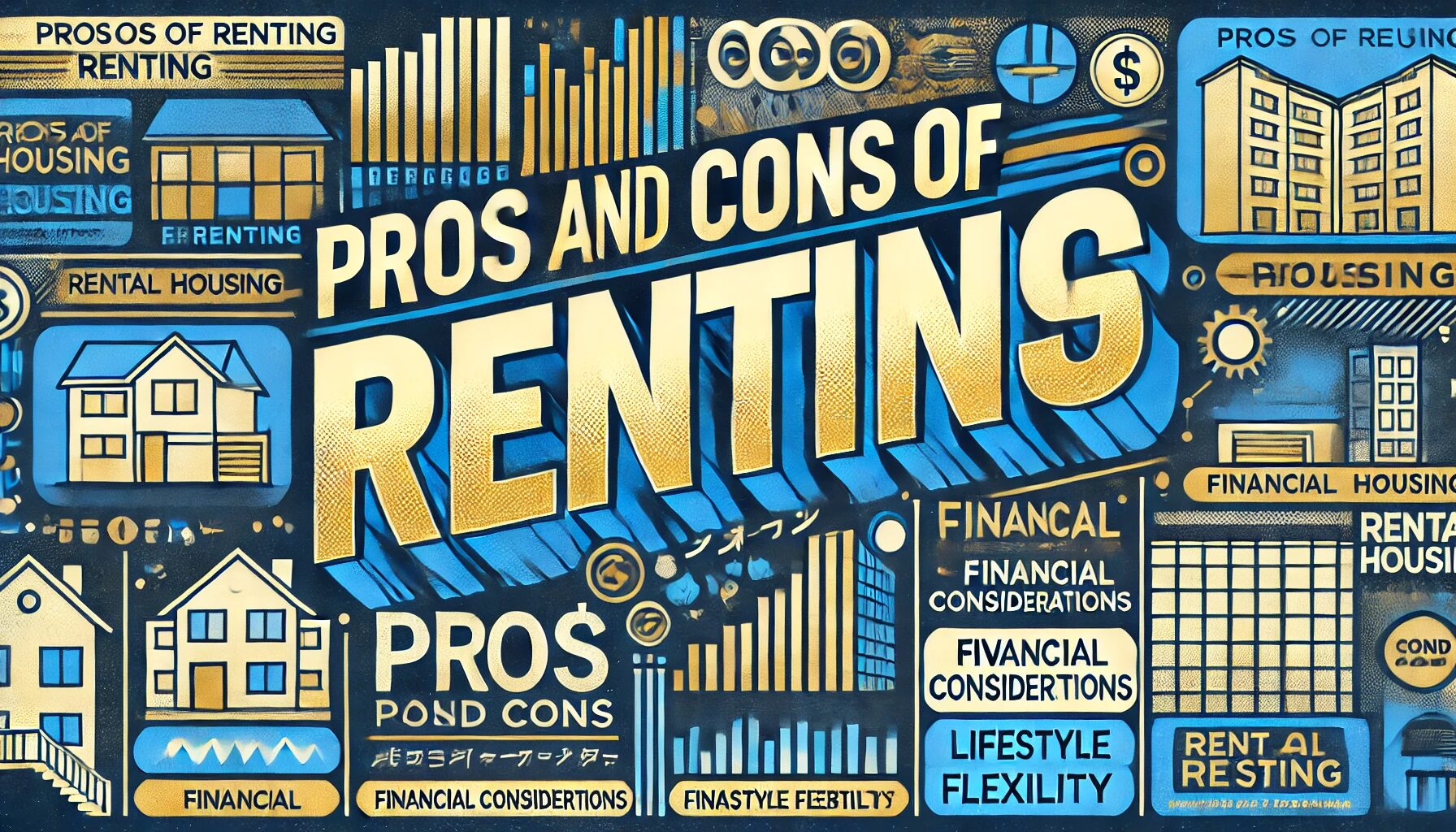
賃貸物件は、住み替えの柔軟性が高く、初期費用を抑えやすいため、多くの人にとって手軽な選択肢となります。
しかし、一方で資産にならない、家賃を払い続ける必要があるといったデメリットも存在します。
ここでは、賃貸のメリットとデメリットを詳しく解説します。
賃貸のメリット
✅ 住み替えが自由でライフスタイルに合わせやすい
賃貸の最大の魅力は、ライフスタイルや仕事の変化に応じて、気軽に住み替えができることです。
転勤や結婚、家族の増減などに柔軟に対応できるため、将来の予定が不確定な人にとっては大きなメリットとなります。
✅ 初期費用が安く、住宅ローンの負担がない
賃貸では、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は必要ですが、持ち家のように数千万円の住宅ローンを組む必要がないため、経済的な負担を抑えられます。また、ローン審査や頭金の準備が不要なため、すぐに住むことができます。
✅ 修繕・メンテナンスの負担が少ない
持ち家の場合、屋根や外壁の修繕、設備の交換などの維持費がかかりますが、賃貸では基本的に大家や管理会社が修繕費を負担してくれるため、自分で大きな出費をする必要がありません。
✅ 固定資産税や管理費が不要
持ち家を購入すると、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金などの負担が発生します。
しかし、賃貸の場合はそうした費用が不要で、毎月の家賃だけで済むため、家計管理がしやすいです。
✅ 物件の選択肢が広い
賃貸は、都市部や駅近など好立地の物件にも住みやすいのがメリットです。
持ち家では、予算の関係で郊外を選ばざるを得ない場合もありますが、賃貸なら予算内で立地や条件の良い物件に住める可能性が高くなります。
賃貸のデメリット
⚠ 家賃を払い続けても資産にならない
賃貸の最大のデメリットは、毎月の家賃が単なる支出となり、将来的に資産として残らないことです。
持ち家の場合はローンを完済すれば住居を資産として残せますが、賃貸は一生家賃を払い続ける必要があります。
⚠ 高齢になると借りにくくなる可能性がある
若いうちは問題なく賃貸契約ができますが、高齢になると賃貸物件を借りづらくなる可能性があります。
特に、年金暮らしになると保証人や家賃保証会社の審査が厳しくなるため、老後の住まいをどうするか考える必要があります。
⚠ リフォームや改装ができない
賃貸では、壁に穴を開けたり、床やキッチンを自由にリフォームすることが禁止されているケースがほとんどです。
自分好みの住空間を作りたい人にとっては、持ち家のほうが向いているでしょう。
⚠ 更新料や家賃の値上げリスクがある
地域によっては、2年ごとの契約更新時に更新料(家賃1ヶ月分程度)を支払う必要がある場合があります。
また、賃貸物件は大家の判断で家賃が値上げされる可能性があるため、長期間住み続けると負担が増えることもあります。
⚠ ペット飼育や楽器演奏に制限がある
賃貸物件では、ペットの飼育や楽器の演奏が禁止されていることが多いため、ペットと暮らしたい人や音楽活動をしたい人には不向きです。
賃貸のメリット・デメリットまとめ
| 項目 | 賃貸のメリット | 賃貸のデメリット |
|---|---|---|
| 柔軟性 | 住み替えが簡単 | 高齢になると借りにくい |
| 費用負担 | 初期費用が安い・ローン不要 | 家賃を払い続けても資産にならない |
| 維持管理 | 修繕費や固定資産税が不要 | リフォームが自由にできない |
| 追加コスト | 不要な支出が少ない | 更新料や家賃の値上げリスク |
| ライフスタイル | 立地の選択肢が広い | ペットや楽器演奏に制限がある |
賃貸は、住み替えの自由度やコスト負担の軽さを重視する人に向いている選択肢です。
一方で、長期的に見ると家賃を払い続けても資産が残らないことが大きなデメリットとなるため、将来のライフプランを考えたうえで判断することが重要です。
持ち家のメリットとデメリット
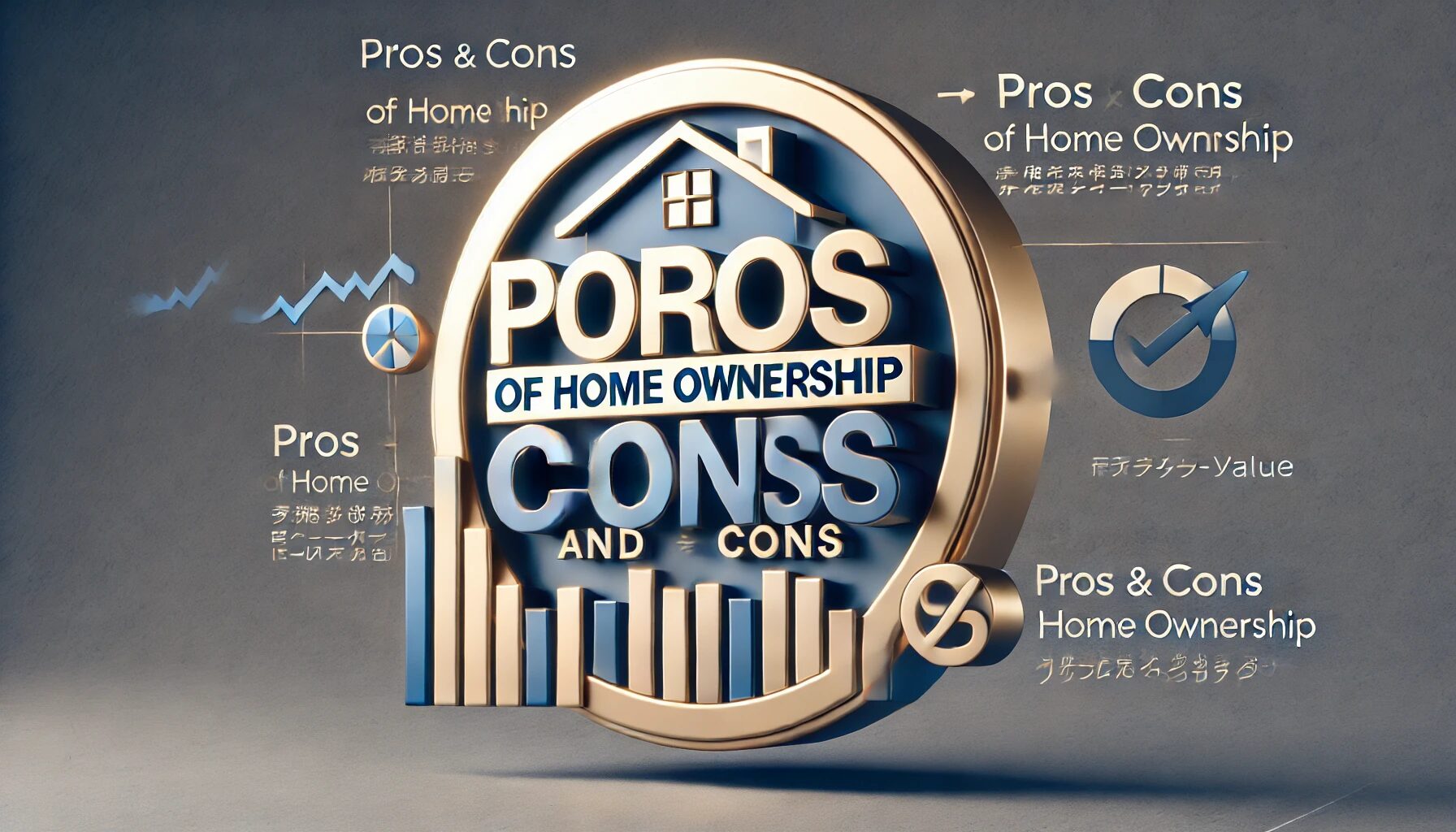
持ち家は、住宅ローンを完済すれば自分の資産になるため、将来的な安心感があります。
しかし、購入時の初期費用や維持費が高く、住み替えの自由度が低いというデメリットもあります。
ここでは、持ち家のメリットとデメリットを詳しく解説します。
持ち家のメリット
✅ 資産として残る
持ち家の最大のメリットは、住宅ローンを完済すれば資産として自分のものになることです。
賃貸では家賃を払い続けても何も残りませんが、持ち家なら売却や賃貸に出して収益化することも可能です。
✅ 老後の住居費負担を軽減できる
持ち家は、ローン完済後は住居費がほぼゼロになるため、年金生活になった際の負担が大きく軽減されます。
一方、賃貸では一生家賃を支払い続ける必要があるため、老後の経済的安定を考えると持ち家のほうが有利です。
✅ リフォームやカスタマイズが自由
賃貸とは異なり、持ち家なら好きなようにリフォームやリノベーションが可能です。
キッチンや浴室の設備を最新のものにしたり、間取りを変更したりと、ライフスタイルに合わせたカスタマイズができます。
✅ 住宅ローンの金利が低い
近年は住宅ローンの金利が非常に低く、固定金利タイプの住宅ローンを利用すれば、家賃と同程度の支払いでマイホームを持つことも可能です。
また、住宅ローン控除などの税制優遇を受けられるため、経済的なメリットもあります。
✅ 固定の住まいがある安心感
持ち家は、契約更新や家賃の値上げを心配する必要がなく、一生安心して住めるのが大きなメリットです。
特に、子どもがいる家庭では、教育環境を変えずに済むため、子育ての安定にもつながります。
持ち家のデメリット
⚠ 初期費用が高い
持ち家を購入する際には、頭金・登記費用・住宅ローン手数料・火災保険料など、数百万円の初期費用が必要です。
賃貸と比較すると、購入時の金銭的な負担が大きい点がデメリットです。
⚠ 維持費や固定資産税がかかる
持ち家は、住宅ローン以外にも、固定資産税・修繕費・管理費などの費用が発生します。
特に戸建ての場合、外壁や屋根の修繕、給湯器の交換などで大きな出費が必要になることがあります。
⚠ 住み替えが難しい
賃貸とは異なり、持ち家は簡単に住み替えができない点がデメリットです。
転勤や家族構成の変化に対応しづらく、売却や賃貸に出す場合も、買い手や借り手を見つける手間がかかります。
⚠ 災害リスクがある
地震・台風・火災などの自然災害による被害を受けるリスクがあるため、万が一に備えて火災保険や地震保険に加入する必要があります。
特に、ハザードマップを確認せずに購入すると、後々大きなリスクを抱えることになるかもしれません。
⚠ 住宅ローンの負担が続く
住宅ローンを組むと、数十年間の支払い義務が生じるため、収入が不安定な人にとっては大きなリスクとなります。
途中で返済が厳しくなった場合、最悪の場合はローン破綻して家を手放すことになりかねません。
持ち家のメリット・デメリットまとめ
| 項目 | 持ち家のメリット | 持ち家のデメリット |
|---|---|---|
| 資産価値 | 資産として残る | 売却・住み替えが難しい |
| 老後の安心感 | 住居費を抑えられる | 固定資産税や維持費がかかる |
| カスタマイズ | リフォームが自由にできる | 修繕費が高額になることがある |
| 経済的負担 | 住宅ローン控除などの税制優遇 | 初期費用・ローン負担が大きい |
| 安心感 | 長期的に安定した住まいが得られる | 災害リスクに備える必要がある |
持ち家は、長期的に住む予定がある人や、将来の資産形成を重視する人に向いている選択肢です。
ただし、住宅ローンの返済や維持費、住み替えの難しさを考慮する必要があるため、慎重に判断することが重要です。
ライフステージ別に考える最適な住まいの選び方
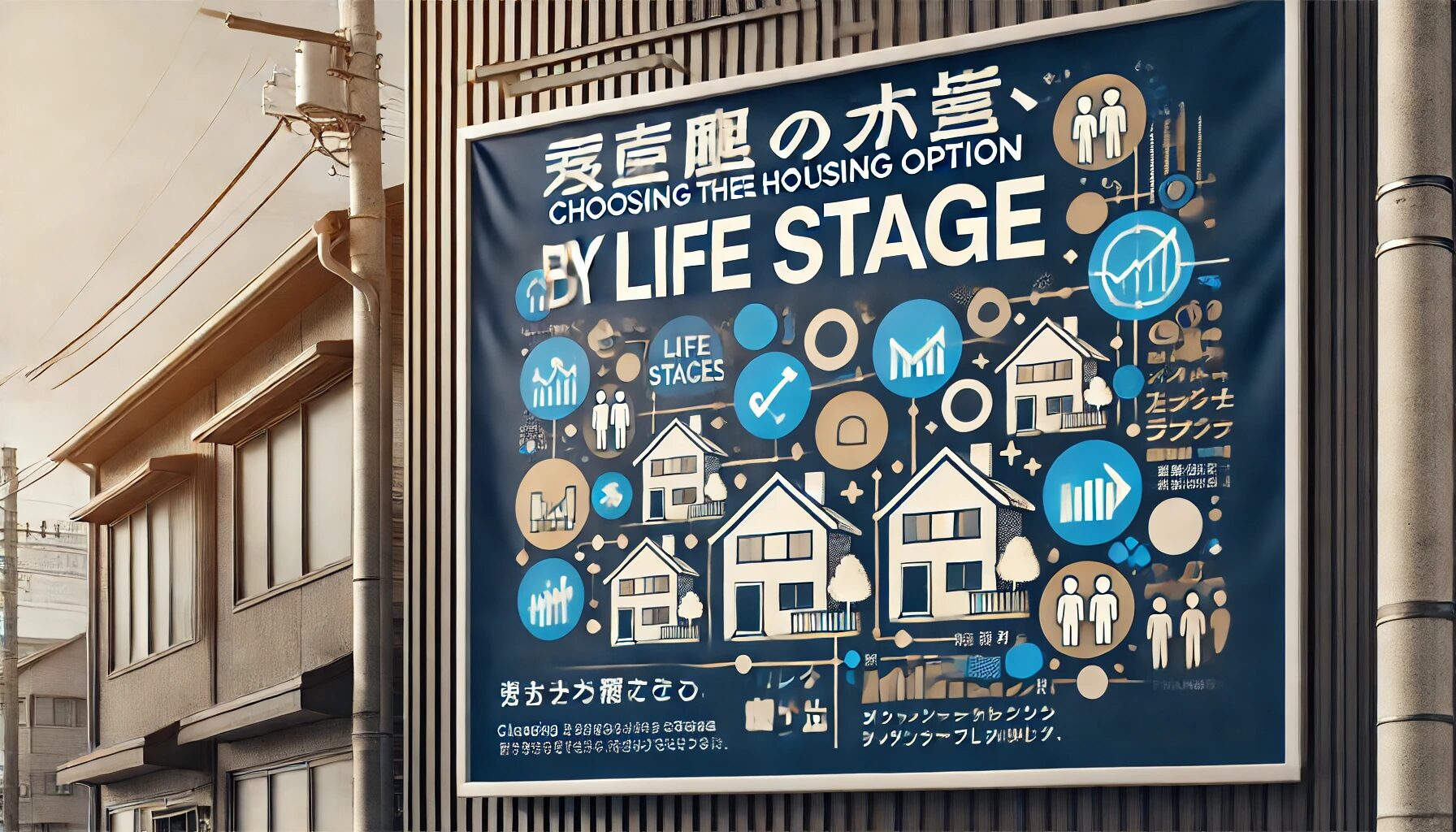
住まい選びは、人生のライフステージによって最適な選択肢が変わるものです。
独身時代と結婚・子育て期、老後では、それぞれ住まいに求める条件が異なります。
ここでは、各ライフステージにおける賃貸と持ち家の選び方のポイントを解説します。
独身時代に向いている住まい
✅ 賃貸が向いている理由
- ライフスタイルの変化に対応しやすい(転職・転勤・結婚など)
- 初期費用を抑えて自由に貯蓄・投資ができる
- 身軽な生活がしやすく、気軽に引っ越しできる
独身時代は、仕事やライフスタイルの変化が大きいため、柔軟な住み替えができる賃貸が向いているケースが多いです。
特に、転勤が多い職種の場合は、持ち家を購入してしまうと将来的な住み替えの負担が大きくなるため、慎重に検討する必要があります。
✅ 持ち家を選ぶ場合のメリット
- 若いうちに購入すると、住宅ローンの返済期間を長くできる
- 将来的な資産形成につながる(ローン完済後の住居費削減)
- 家賃を払い続けるより、購入したほうが得になるケースもある
収入が安定しており、長く住みたいエリアが決まっている場合は、独身時代に持ち家を購入するメリットもあります。
特に、早いうちに住宅ローンを組めば、定年前に完済できるため、老後の住居費負担を減らすことが可能です。
結婚・子育て世代に向いている住まい
✅ 持ち家が向いている理由
- 子どもの教育環境を安定させやすい(学区変更の心配がない)
- 家族の人数に合わせた広い間取りを確保しやすい
- リフォームや間取り変更が自由にできる
結婚・子育て世代では、長期的な安定を求めるため、持ち家を選ぶ人が多いです。
特に、子どもがいる家庭では、学区を固定できる点や、家族の成長に合わせたリフォームが可能な点がメリットとなります。
✅ 賃貸を選ぶ場合のメリット
- ライフスタイルの変化に対応しやすい(転勤・家族の増減など)
- 住宅ローンのリスクを負わずに済む
- 初期費用が少なく、家計への負担が軽い
転勤が多い仕事や、将来的に住む場所を決めかねている場合は、あえて賃貸を選ぶことで、経済的なリスクを抑えつつ住環境を整えることができます。
また、子どもの成長に応じて広い家に引っ越すことができる点もメリットです。
老後に向いている住まい
✅ 持ち家が向いている理由
- ローン完済後は住居費がほぼゼロになる
- リフォームしてバリアフリー対応が可能
- 売却やリバースモーゲージで資金調達ができる
老後を迎えると、持ち家のメリットがより大きくなります。
住宅ローンを完済すれば、住居費の負担がほぼなくなるため、年金生活でも安心して暮らせるのが強みです。
また、高齢になってから賃貸を借りるのは難しくなることが多いため、持ち家を所有していることは大きな安心材料となります。
✅ 賃貸を選ぶ場合のメリット
- 維持費や修繕の負担がなく、管理が楽
- 体調やライフスタイルに応じて住み替えが可能
- バリアフリー対応の物件に引っ越しやすい
一方、持ち家を維持するのが大変になった場合は、賃貸に住み替えるのも選択肢です。
特に、高齢者向けのバリアフリー対応マンションや、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への移行を考える人も増えています。
ライフステージ別の住まい選びまとめ
| ライフステージ | 賃貸が向いている人 | 持ち家が向いている人 |
|---|---|---|
| 独身時代 | 転勤が多く、自由な生活をしたい | 早めに資産形成をしたい |
| 結婚・子育て | 住み替えの可能性がある | 家族の安定した住環境を求める |
| 老後 | 維持費の負担を減らし、身軽に暮らしたい | 住居費を抑え、老後の安心を確保したい |
賃貸と持ち家のどちらを選ぶべきかは、ライフステージごとに異なります。
独身時代は賃貸の自由度が魅力的ですが、家族が増えると持ち家の安定感がメリットになり、老後は持ち家を活用することで生活の負担を軽減できることが分かります。
賃貸と持ち家の費用シミュレーション比較

賃貸と持ち家のどちらが経済的にお得なのかを判断するためには、長期間のトータルコストを比較することが重要です。
ここでは、30年間住み続けた場合の費用シミュレーションを行い、それぞれの違いを詳しく解説します。
ケース1:賃貸に30年間住み続けた場合
試算条件
- 家賃:月10万円(更新時に家賃が若干上昇)
- 更新料:2年ごとに家賃1ヶ月分(10万円)
- 引っ越し:10年ごとに1回(引っ越し費用50万円)
30年間の合計コスト
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 家賃(10万円 × 12ヶ月 × 30年) | 3,600万円 |
| 更新料(10万円 × 15回) | 150万円 |
| 引っ越し費用(50万円 × 2回) | 100万円 |
| 総額 | 3,850万円 |
賃貸のポイント
✔ まとまった初期費用が不要で、生活環境の変化に応じて住み替えが可能
✔ 住宅ローンの負担がないが、払い続けても資産にはならない
✔ 家賃が値上がりするリスクがあるため、老後の生活費を確保する必要がある
ケース2:持ち家を購入して30年間住み続けた場合
試算条件
- 購入価格:4,000万円(新築マンション)
- 頭金:500万円
- 住宅ローン:3,500万円(35年返済、金利1.0%)
- 月々の返済額:10万円(ボーナス払いなし)
- 固定資産税:年間15万円
- 修繕・リフォーム費用:10年ごとに200万円(合計600万円)
30年間の合計コスト
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 住宅ローン支払い(10万円 × 12ヶ月 × 30年) | 3,600万円 |
| 固定資産税(15万円 × 30年) | 450万円 |
| 修繕・リフォーム費用(200万円 × 3回) | 600万円 |
| 総額 | 4,650万円 |
持ち家のポイント
✔ 住宅ローン完済後は住居費の負担がほぼゼロになる
✔ 固定資産として残るため、将来的に売却や賃貸に出すことも可能
✔ 維持費・修繕費がかかるため、長期的な資金計画が必要
賃貸 vs 持ち家 費用比較まとめ(30年間の場合)
| 項目 | 賃貸 | 持ち家 |
|---|---|---|
| 総支払額 | 約3,850万円 | 約4,650万円 |
| 住居費の将来負担 | ずっと家賃を支払い続ける | ローン完済後の負担がほぼゼロ |
| 資産価値 | 残らない | 残る(売却・賃貸が可能) |
| 住み替えの自由度 | 高い(ライフスタイルに応じて引っ越せる) | 低い(簡単に移動できない) |
| メンテナンス | 不要(大家が負担) | 必要(修繕費・リフォーム費) |
どちらが得か?判断ポイント
🏠 持ち家が向いている人
- 長期間同じ場所に住む予定がある
- 住宅ローンを完済すれば、老後の住居費を抑えられる
- リフォームやDIYを楽しみたい
🏢 賃貸が向いている人
- 転勤や住み替えの可能性がある
- 家賃を払い続けても気にならない(資産価値にこだわらない)
- 初期費用を抑えて生活の自由度を優先したい
賃貸と持ち家では、単純な支払い額の比較だけでなく、「資産価値」「住み替えの自由度」「老後の安心感」なども考慮する必要があります。
賃貸と持ち家の選び方のポイント

賃貸と持ち家は、それぞれ異なるメリット・デメリットがありますが、最終的には「自分のライフスタイルや価値観に合っているか」が重要になります。
ここでは、賃貸と持ち家を選ぶ際に考慮すべきポイントを解説します。
1. ライフプランを考慮する
✅ 賃貸が向いている人
- 仕事の都合で転勤が多い
- ライフステージの変化に応じて住まいを変えたい
- 将来の計画がまだ不確定
✅ 持ち家が向いている人
- 家族のために安定した住環境を確保したい
- 住宅ローンを完済し、老後の住居費を抑えたい
- 将来的に資産として家を残したい
「今後どこに住むのか?」「家族構成はどうなるのか?」を考えながら、自分に合った住まいの選択をすることが大切です。
2. 経済的リスクとリターンのバランスを考える
✅ 賃貸のリスクとリターン
- 【リスク】老後も家賃を払い続ける必要がある
- 【リターン】大きな負債(住宅ローン)を抱えずに済む
✅ 持ち家のリスクとリターン
- 【リスク】住宅ローンの負担・維持費がかかる
- 【リターン】ローン完済後は住居費の負担がなくなり、資産が残る
経済的な安定を考え、「住居費にいくらまで支払えるか?」をしっかり試算した上で判断しましょう。
3. 住みたいエリアと物件の選択肢
✅ 賃貸の強み → 駅近・都市部の人気エリアにも住みやすい
✅ 持ち家の強み → 長期的に住むなら郊外でもコスパが良い
例えば、都心の人気エリアでは購入価格が高すぎるため、賃貸の方がコストを抑えやすいですが、郊外では持ち家の方がメリットが大きくなることが多いです。
住みたいエリアの相場を調べ、賃貸と持ち家のコストを比較しながら最適な選択をすることが重要です。
4. 住宅ローンを組む際のリスクを理解する
✅ 安易に住宅ローンを組まない
- 収入の変動が大きい人は慎重に判断する
- 変動金利・固定金利の違いを理解して選ぶ
✅ ローンを組む場合の目安
- 年収の5~7倍までに抑える(例:年収500万円なら3,500万円以内)
- 毎月の返済額は手取り収入の25%以下が理想
住宅ローンの負担が大きすぎると、生活費や貯蓄に影響を及ぼすため、無理のない返済計画を立てることが重要です。
5. 老後の住まいを考える
✅ 持ち家の強み
- ローンを完済すれば住居費がほぼゼロになる
- 老後の住まいの確保がしやすい
✅ 賃貸の強み
- 維持費や修繕の手間がかからない
- 高齢者向けの住宅に住み替えやすい
老後の生活を考えると、持ち家を所有している方が経済的な安心感はあるものの、高齢になるとマンションの管理費や固定資産税が負担になる可能性もあるため、ライフプランに合わせた選択が重要です。
まとめ|賃貸と持ち家を選ぶポイント
| 項目 | 賃貸が向いている人 | 持ち家が向いている人 |
|---|---|---|
| ライフプラン | 転勤・住み替えの可能性がある | 長期的に同じ場所に住みたい |
| 経済的リスク | 家賃を払い続けるリスク | 住宅ローンの負担がある |
| エリア選択 | 都市部・駅近が多い | 郊外の選択肢も広がる |
| 住宅ローン | 大きな負債を抱えたくない | 老後の住居費を抑えたい |
| 老後の安心感 | 高齢になって借りづらくなる | 資産として残る |
どちらが正解というわけではなく、自分のライフスタイルや将来の計画に合った住まいを選ぶことが最も大切です。
「賃貸派 vs 持ち家派」実際の声を紹介
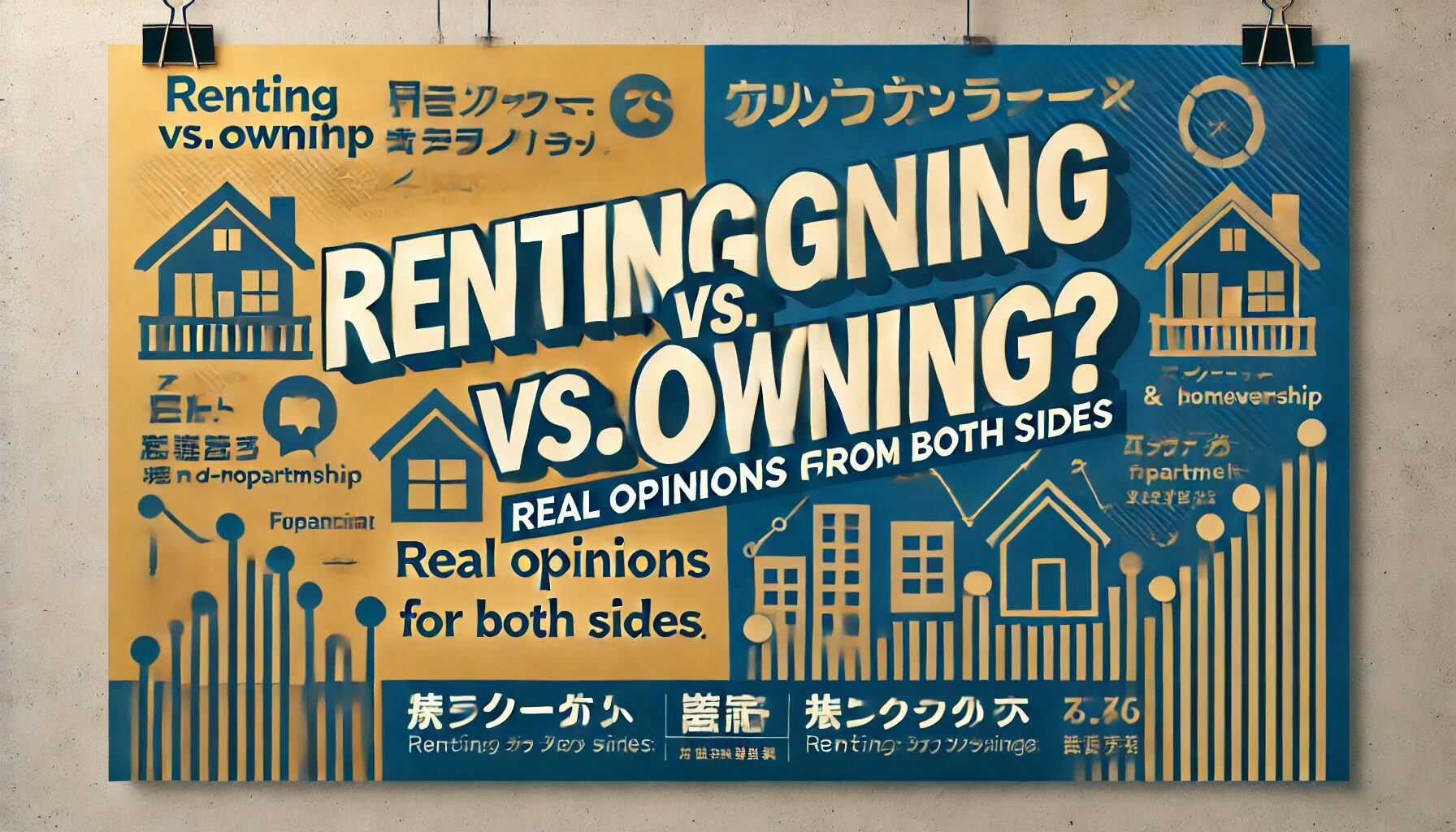
賃貸と持ち家にはそれぞれのメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかはライフスタイルや価値観によって異なります。
ここでは、実際に賃貸派と持ち家派の意見を紹介し、それぞれの考え方の特徴を解説します。
賃貸派の意見:自由とコスト重視
🔹 「転勤が多いので賃貸の方が便利」(30代・男性)
「仕事の関係で数年ごとに転勤があるため、持ち家を購入しても長く住める保証がありません。
賃貸なら、転勤のたびにスムーズに引っ越しができるので、今の生活スタイルには合っています。」
🔹 「住宅ローンを背負うのが怖い」(40代・女性)
「家を買うと住宅ローンを数十年払い続けることになります。それがプレッシャーになりそうなので、私は賃貸を選びました。
賃貸なら、万が一収入が減っても、家賃の安い物件に引っ越せる柔軟性があります。」
🔹 「修繕やメンテナンスの負担がないのが魅力」(50代・男性)
「友人が持ち家を購入しましたが、外壁の修繕や水回りのリフォームでかなりの費用がかかると聞きました。
賃貸ならそうした負担がないので、老後も楽に暮らせると思っています。」
📌 賃貸派の主な特徴
✅ 住み替えの自由度が高く、転勤やライフスタイルの変化に対応しやすい
✅ 住宅ローンの負担がなく、経済的なリスクを避けられる
✅ 修繕費や固定資産税の心配がない
持ち家派の意見:資産形成と安心感
🔹 「将来の家賃負担を考えて持ち家を選んだ」(30代・夫婦)
「賃貸は家賃を払い続けても何も残りませんが、持ち家ならローンを完済すれば住居費がほとんどかからなくなります。
老後の生活を考えると、持ち家の方が安心できると思いました。」
🔹 「自分好みにリフォームできるのが魅力」(40代・女性)
「賃貸では壁紙を変えるのもNGですが、持ち家なら自由にリフォームができます。
最近キッチンを最新の設備に変更しましたが、自分好みの家にできるのが一番のメリットです。」
🔹 「資産として残るので、万が一のときにも安心」(50代・男性)
「家を資産として持っていれば、将来的に売却や賃貸に出すこともできます。
万が一のときに売却してまとまったお金を確保できるのは、賃貸にはないメリットだと思います。」
📌 持ち家派の主な特徴
✅ ローン完済後は住居費の負担がほぼゼロになり、老後の安心感がある
✅ 自分の好きなようにリフォームやカスタマイズが可能
✅ 将来的に資産として売却・賃貸に出せる可能性がある
賃貸派 vs 持ち家派 どっちが多い?
実際の調査によると、20〜30代は賃貸派が多く、40〜50代以降になると持ち家派が増える傾向があります。
これは、若いうちは転職や結婚などライフスタイルの変化が多いため賃貸を選びやすく、40代以降になると老後の住居の安定を考えて持ち家を選ぶ人が増えるためです。
| 年代 | 賃貸派 | 持ち家派 |
|---|---|---|
| 20代 | 70% | 30% |
| 30代 | 60% | 40% |
| 40代 | 40% | 60% |
| 50代以上 | 30% | 70% |
このデータからも分かるように、若いうちは賃貸のメリットを活かし、年齢を重ねるにつれて持ち家を検討するのが一般的と言えます。
まとめ|あなたは賃貸派?持ち家派?
✅ 賃貸派に向いている人
- 住み替えの自由を重視したい
- 住宅ローンのリスクを避けたい
- 修繕や維持費の負担を減らしたい
✅ 持ち家派に向いている人
- 老後の住居費を抑えたい
- 自由にリフォームしたい
- 資産として家を残したい
賃貸と持ち家のどちらを選ぶべきかは、ライフスタイルや価値観、将来の計画によって異なります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮しながら、自分に合った住まいを選びましょう。
まとめ|自分に合った住まいを選ぶために大切なこと
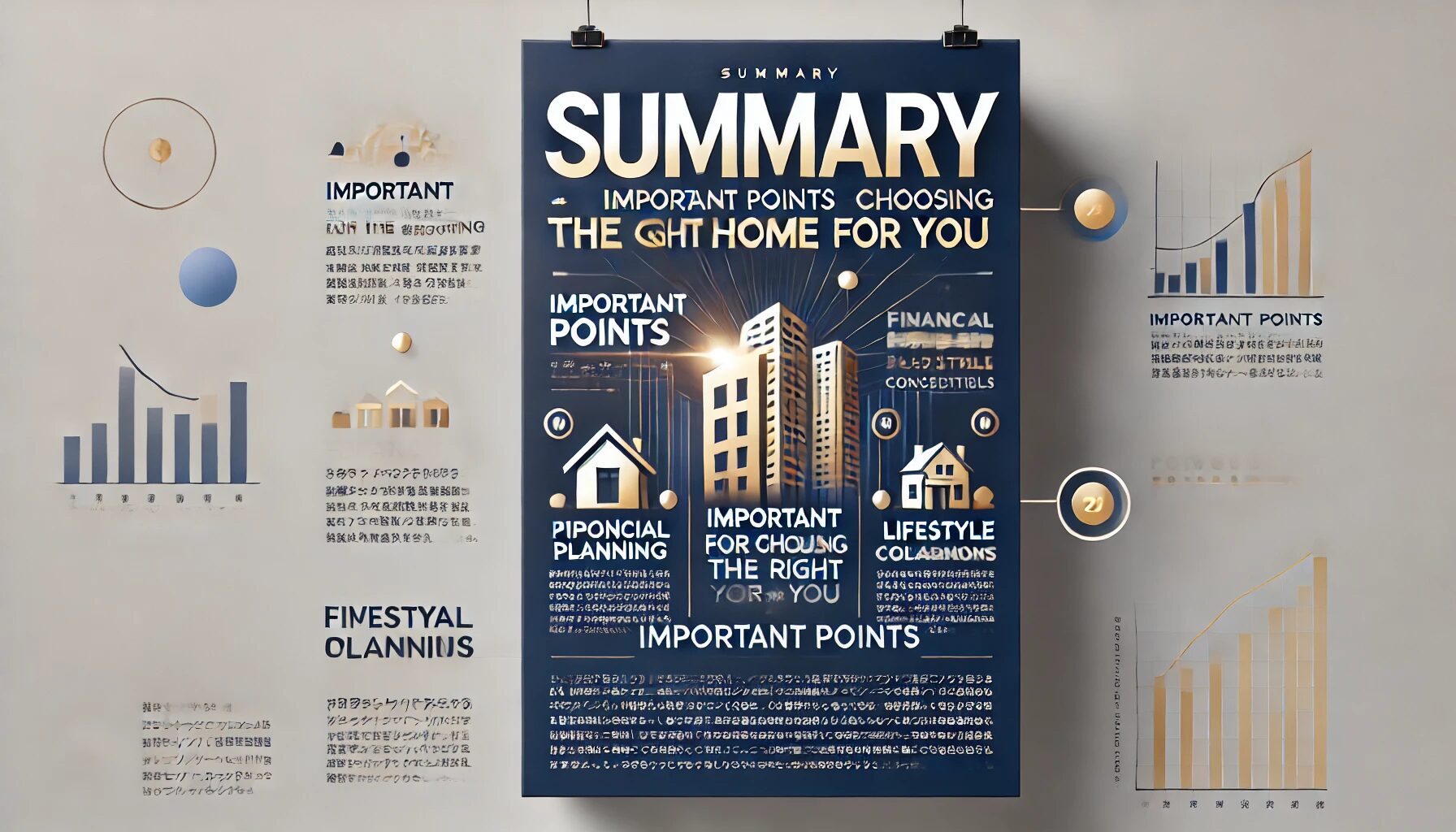
賃貸と持ち家の違いについて、メリット・デメリットやライフステージ別の住まいの選び方、費用シミュレーションを交えて詳しく解説しました。
どちらが正解というわけではなく、それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルや価値観に合った選択をすることが最も重要です。
賃貸と持ち家のメリット・デメリットの振り返り
✅ 賃貸のメリット
- 住み替えが自由で、ライフスタイルの変化に対応しやすい
- 初期費用が安く、住宅ローンのリスクを避けられる
- 修繕費や固定資産税の負担がない
✅ 賃貸のデメリット
- 家賃を払い続けても資産にはならない
- 高齢になると賃貸契約が難しくなることがある
- リフォームやカスタマイズができない
✅ 持ち家のメリット
- 住宅ローン完済後は住居費の負担がほぼゼロになる
- リフォームやカスタマイズが自由にできる
- 将来的に売却や賃貸に出すことで資産価値を活用できる
✅ 持ち家のデメリット
- 初期費用や維持費が高く、住宅ローンの負担がある
- 簡単に住み替えができない
- 災害リスクや市場価値の変動を考慮する必要がある
ライフステージ別の最適な選択肢
🏠 独身時代 → 賃貸が有利(自由なライフスタイルを維持できる)
🏠 結婚・子育て世代 → 持ち家が有利(家族の安定した住環境を確保しやすい)
🏠 老後 → 持ち家が有利(住宅ローンを完済すれば住居費の負担が減る)
特に、老後を考えたときに住居費をどうするかが大きなポイントになります。
賃貸派の人は、老後に備えて貯蓄をしっかり行う必要があり、持ち家派の人は、ローンの返済計画や将来の売却・活用方法を考えておく必要があります。
自分に合った住まいを選ぶためのポイント
✅ 将来のライフプランを考える(転勤や結婚、子育てなど)
✅ 経済的リスクとリターンを比較する(住宅ローン vs 家賃負担)
✅ 住みたいエリアと物件の選択肢を確認する
✅ 老後の住まいについて早めに計画を立てる
これらのポイントを押さえながら、自分の価値観やライフプランに合った住まいを選ぶことが大切です。
結論|賃貸と持ち家、どっちがいいのか?
🔹 短期的に住み替えの自由を重視するなら「賃貸」
🔹 長期的な資産形成と老後の安心を重視するなら「持ち家」
どちらの選択肢にもメリット・デメリットがあるため、「今の自分にとって最適な選択はどちらか?」を考えることが重要です。
この記事を参考に、後悔しない住まい選びをしてください!
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。