※本ページはプロモーションが含まれています。
第一章 金投資とは何か 仕組みと基本を知る

金投資とは、純金や金関連の金融商品に資金を投じ、長期的な資産保全と価値の安定を目的とする投資手法です。
通貨や株式とは異なり、金そのものには発行体が存在せず、世界共通の価値を持つ実物資産として古くから信頼を集めています。
金の価値が変わらない理由
金が投資対象として選ばれる最大の理由は、価値が「紙幣の信用」に依存しないことです。
各国の通貨は中央銀行や政府の政策に左右されますが、金はそれらの発行体を持たず、希少性と普遍的な需要によって価格が形成されます。
特に、金融危機・インフレ・通貨不安の際に価値が高まりやすく、投資家の間では「有事の金(Safe Haven Asset)」として位置づけられています。
金投資の基本構造
金投資には主に以下の4つの形態があります。
それぞれの特徴を理解することが、資産運用を成功させる第一歩です。
| 投資方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 現物(金地金・コイン) | 実際に金を所有する方法 | 手元に資産を保管できる | 保管・盗難リスクがある |
| 純金積立 | 毎月一定額で金を購入 | 少額から始められる | 手数料がかかる |
| 金ETF・投資信託 | 金価格に連動する金融商品 | 売買が容易で流動性が高い | 実物を手にできない |
| 金先物取引 | 将来の金価格を予測して取引 | 短期的な値動きで利益を狙える | ハイリスク・ハイリターン |
このように、目的とリスク許容度に応じて投資方法を選ぶことが重要です。
たとえば、安定的な資産保全を目的とするなら純金積立やETFが向いており、短期的な値動きを狙う場合は先物取引が適しています。
世界での金の役割と日本市場の位置づけ
金は世界中で「国際共通通貨」とも呼ばれ、各国の中央銀行も外貨準備の一部として保有しています。
特にアメリカ、中国、ロシアなどが大量の金を保有しており、国際的な金融バランスを保つ上で欠かせない存在です。
日本においても、金は1970年代の金本位制崩壊以降、投資・資産分散・インフレヘッジとして注目されてきました。
最近では、個人投資家の間で新NISAやiDeCoなどを通じて、金ETFを組み込む動きも加速しています。
金価格の決まり方
金の価格は、世界市場(ロンドン金市場やニューヨークCOMEX)を中心に形成されます。
主に次の3つの要因が金価格を左右します。
- ドルの為替動向
金はドル建てで取引されるため、ドル安になると金価格が上がりやすくなります。 - 金利の水準
金は利息を生まない資産のため、金利が低いときに人気が高まりやすい傾向があります。 - 地政学的リスクや経済不安
戦争・感染症・金融危機など、社会不安が高まると「安全資産」として金に資金が流入します。
このように、金の価格は「世界経済の体温計」とも呼ばれるほど、グローバルな要因で変動します。
金投資が注目される背景
近年、金投資が再び注目を集めている理由には、次のような環境要因があります。
- 各国の金融緩和と通貨価値の下落
- インフレ率の上昇と購買力の低下
- 株式や暗号資産のボラティリティ拡大
- 個人投資家の「資産防衛」意識の高まり
このような背景から、金は「守りの資産運用」として見直されています。
特に2020年代に入り、金価格は過去最高値を更新し続けており、ポートフォリオの一部として組み入れる投資家が急増しています。
まとめ
金投資は、短期的な利益を追うものではなく、資産価値を守り抜くための長期戦略です。
通貨や株式が不安定な時代において、金は「世界共通の信頼資産」としての存在感をますます強めています。
まずは金の性質を理解し、自分に合った投資方法を選ぶことが、資産形成の第一歩になります。
第二章 金投資のメリット インフレ対策・安全資産としての魅力

金投資が長年にわたり多くの投資家から支持されている理由は、その「価値の安定性」と「守りの強さ」にあります。
株や債券、通貨が市場の変動に大きく左右される一方で、金はそれらと異なる動きを見せる「独立した資産」として機能します。
インフレに強い資産としての金
金の最大の魅力の一つが、インフレ(物価上昇)に強い資産であるという点です。
紙幣は発行量が増えると価値が下がりますが、金は自然界での産出量が限られているため、供給が制御された希少資源です。
たとえば、1970年代のオイルショックや2008年のリーマンショックの際、各国で通貨価値が下落する中、金価格は上昇しました。
これは、インフレ局面で人々が「紙幣よりも実物資産を持ちたい」と考えるためです。
つまり、物価が上がり通貨の購買力が下がる時こそ、金の価値は相対的に上昇する仕組みになっています。
有事の際に強い「安全資産」
金は、地政学的リスクや金融危機時の避難先資産(セーフヘイブン)としても知られています。
戦争や感染症拡大、株式市場の暴落など、経済や社会が不安定になる局面で、投資家はリスク資産から金へ資金を移します。
2020年のコロナショックでも同様に、世界的に株価が急落した一方で、金価格は急騰しました。
これは「有事の金買い」と呼ばれる現象で、リスク分散の観点からも非常に重要です。
このため、投資家の多くはポートフォリオの中に金を数%〜10%程度組み込み、資産全体の防衛力を高める戦略をとっています。
世界共通の価値を持つ資産
金は、どの国でも同じ価値を持ち、通貨や国境に左右されない国際資産です。
円・ドル・ユーロなどの法定通貨は政治や金融政策に依存しますが、金にはそうした発行体が存在しません。
この「普遍的な交換価値」が、金を長期的な資産保全に適した存在にしています。
また、為替変動によるリスクも相対的に小さく、海外市場でも容易に換金できる流動性の高さも魅力です。
長期保有で安定したリターンを期待できる
金は短期的な値動きはあるものの、長期的には右肩上がりの推移を見せています。
特に2000年代以降、世界的な低金利政策や金融緩和によって、金の需要は急増。
2020年には1トロイオンスあたり2,000ドルを突破し、2024〜2025年も歴史的高値圏で推移しています。
金は株や不動産のように配当や家賃収入を生まない一方で、「保有することで価値を守る」という安定性があります。
つまり、成長を狙う資産ではなく、資産を守るための基盤として位置づけるのが正しい考え方です。
分散投資の一環としての価値
投資の基本原則は「リスクを分散すること」です。
株式・債券・不動産・現金などと並んで、金をポートフォリオに加えることで、全体の値動きを安定させることができます。
特に、株式市場が下落する局面では金が上昇する傾向があり、互いに逆の動きをすることでリスクヘッジ効果を発揮します。
このため、多くの機関投資家や富裕層は、金を「分散投資の中核」として組み込んでいます。
金投資が個人にも広がる理由
これまで金投資は一部の富裕層向けと思われていましたが、現在では少額から誰でも始められる時代になりました。
ネット証券やスマホアプリを通じて、純金積立・ETF・投資信託などを手軽に購入できるようになっています。
また、金を使ったジュエリーや小型バーなども人気があり、「楽しみながら資産形成する」というライフスタイル型投資としても注目されています。
まとめ
金投資のメリットは、
- インフレに強い
- 有事に価値が上がる
- 世界共通の資産
- 長期で安定した価値維持
- 分散投資の柱になる
という5つに集約されます。
不確実な時代において、金は単なる投資対象ではなく、「資産を守るための保険」としての役割を果たしています。
この理解を踏まえ、次章では逆に「金投資のリスクとデメリット」について、冷静に解説していきます。
第三章 金投資のリスクとデメリット

金投資は「安全資産」として高い人気を誇りますが、リスクがないわけではありません。
正しく理解せずに始めると、思わぬ損失や運用の失敗を招く可能性があります。
ここでは、金投資の主なリスクと注意すべきデメリットを整理して解説します。
価格変動リスクは常に存在する
金は「値下がりしない」と誤解されがちですが、実際には市場の需給や為替動向によって日々価格が変動します。
特に短期的には、ドル高や金利上昇の影響で価格が下落するケースもあります。
たとえば、2020年に過去最高値を記録した後、2021年には一時的に10%以上下落しました。
このように、タイミングによっては一時的な含み損を抱えるリスクもあるのです。
長期で保有すれば安定性は増しますが、「短期の値動きに強いメンタル」が求められます。
利息や配当が発生しない
株式や債券と異なり、金には利息や配当金がありません。
つまり、保有していてもインカムゲイン(定期収益)は得られないため、リターンは価格上昇によるキャピタルゲインのみです。
そのため、短期的な利益を狙う投資家にとっては「資産が眠る」状態になりやすく、
投資効率の観点から見ると機会損失につながる場合もあります。
特に金利上昇局面では、利息が得られる債券などに資金が流れやすく、金の価格が下がる傾向があります。
為替変動の影響を受ける
日本国内で取引される金の価格は、ドル建ての国際価格 × 円ドル相場で決まります。
そのため、金の国際価格が変わらなくても、円高が進むと日本円での金価格は下落します。
たとえば、ドル建て金価格が横ばいでも、1ドル=150円から140円に円高が進めば、
日本円での金価格は約7%も下落する計算になります。
つまり、金投資には「金価格リスク」に加え、「為替リスク」も存在することを理解しておく必要があります。
保管や管理にコストがかかる
現物の金を購入する場合、保管コストや盗難リスクも無視できません。
自宅で保管する場合は耐火金庫などが必要ですし、盗難や紛失のリスクも伴います。
また、販売店の金庫保管サービスを利用する場合は、年間数千円〜数万円の保管料が発生します。
純金積立やETFであれば保管の手間は省けますが、これらも購入・売却・管理に手数料がかかります。
「安全な資産」だからこそ、コスト管理を怠ると長期運用での利益を圧迫します。
現物の換金性に制約がある
金は世界共通の価値を持ちますが、現金化までに時間がかかるというデメリットがあります。
特に地金や金貨を持っている場合、売却の際には買取店への持ち込みや査定が必要で、
価格もタイミングによって変動します。
一方、金ETFや純金積立なら比較的スムーズに売買できますが、市場が閉まっている時間帯は取引できません。
つまり、いざというときにすぐ換金できないケースもあることを想定しておく必要があります。
詐欺や偽物のリスク
金の人気上昇とともに、偽物の金地金や詐欺まがいの投資話も増えています。
実際、近年では「金コーティングされたニセ地金」や「高額での押し売りトラブル」が報告されています。
信頼できる業者や大手金融機関を通じて取引することが、リスク回避の基本です。
デメリットを理解してこそ“本当の安全資産”
金投資は決して「リスクゼロの資産」ではありません。
しかし、デメリットを正しく理解し、目的に応じて保有量と期間を調整すれば、
ポートフォリオ全体の安定性を高める有効な手段になります。
短期利益を狙うよりも、長期的な資産防衛の観点で「時間を味方につける投資」と考えることが大切です。
第四章 金への投資方法 現物・純金積立・ETF・投資信託

金投資と一口にいっても、その手段はさまざまです。
投資スタイルやリスク許容度によって、最適な方法は異なります。
ここでは、代表的な4つの投資方法について、特徴・メリット・注意点を分かりやすく比較していきます。
1. 現物投資(金地金・金貨)
「実物を手にする」最も伝統的な投資スタイル
現物の金を購入して保有する方法は、最もシンプルかつ歴史のある金投資です。
田中貴金属や三菱マテリアルなど、国内大手の地金商から購入することができます。
メリット
- 自分の手元に「実物の資産」が残る安心感
- 世界中どこでも換金可能
- 相続や贈与にも活用しやすい
デメリット
- 保管リスク(盗難・火災など)
- 売買手数料(約3〜5%)が発生
- 小口での取引が難しく、まとまった資金が必要
また、1kgバー(約1,000万円相当)だけでなく、10gや20gといった少額バー、金貨タイプも登場しており、
初心者でも購入しやすい小口現物投資が広がっています。
2. 純金積立
毎月コツコツ買い増す「長期積立型」投資
純金積立は、証券会社や貴金属販売会社を通じて、毎月一定額の金を自動購入する方法です。
SBI証券・楽天証券・田中貴金属などが代表的な提供先です。
メリット
- 1,000円程度から始められる少額投資
- 毎月の積立で平均購入価格を平準化(ドルコスト平均法)
- 現物引き出しも可能(業者による)
デメリット
- 買付・保管・売却に手数料がかかる
- 現物を引き出す場合は別途コストが発生
純金積立は、「貯金感覚で始められる金投資」として人気があり、初心者や長期保有目的の投資家に向いています。
一方で、短期売買には不向きな点を理解しておきましょう。
3. 金ETF(上場投資信託)
証券口座で取引できる「手軽な金融商品」
金ETFは、東京証券取引所などに上場している「金価格に連動する金融商品」です。
たとえば、「SPDRゴールドシェア(GLD)」や「純金上場信託(1540)」が代表例です。
メリット
- 株式と同じように売買可能(流動性が高い)
- 少額でも金価格に連動した運用ができる
- 保管や輸送の手間が不要
デメリット
- 実際の金を手にできない(現物保有ではない)
- 為替変動リスクがある(外国ETFの場合)
- 信託報酬(年率0.3〜0.5%)がかかる
ETFは、効率的かつ透明性の高い金投資として、個人投資家・機関投資家の双方に利用されています。
短期取引やリバランス目的にも活用しやすい点が強みです。
4. 金投資信託
専門家が運用する「おまかせ型」投資
金投資信託は、投資家から集めた資金をプロのファンドマネージャーが金関連資産に投資する仕組みです。
金ETFや金鉱山株を組み合わせたファンドも多く、分散投資効果を狙うことができます。
メリット
- 専門家による運用で初心者でも始めやすい
- 金価格だけでなく、金関連株の成長も取り込める
- 積立NISA対応のファンドも存在
デメリット
- 信託報酬が高め(年率0.8〜1.5%)
- 金価格の動き以外の要因で値動きする場合もある
金投資信託は、「金を軸にしつつ成長性も狙いたい」という投資家におすすめです。
ただし、コストとリスクのバランスを見極めて選ぶ必要があります。
投資方法別の比較まとめ
| 投資方法 | 向いている人 | 特徴 | 初期費用 | 管理コスト |
|---|---|---|---|---|
| 現物(金地金・金貨) | 安全志向・資産保全重視 | 実物保有で安心感 | 高い(数十万円〜) | 保管料あり |
| 純金積立 | 長期積立型・初心者 | コツコツ買える | 低い(1,000円〜) | 低〜中 |
| 金ETF | 手軽に取引したい人 | 株式のように売買可能 | 中程度 | 低 |
| 金投資信託 | プロに任せたい人 | 分散運用・積立NISA対応 | 低〜中 | 中〜高 |
どの投資方法を選ぶべきか
- 安定重視なら → 現物・純金積立
- 流動性重視なら → 金ETF
- 分散・成長性重視なら → 金投資信託
目的と期間を明確にし、「自分のポートフォリオの中で金をどんな役割にするか」を決めることが成功の鍵です。
第五章 金価格の動向と2025年の見通し

金価格は、世界経済の不安定さを映す鏡のような存在です。
インフレ率、金利、ドル相場、地政学リスクといった複数の要因が複雑に絡み合いながら、価格は日々変動しています。
2025年現在、金は世界的に注目度が高く、「歴史的な高値圏」にある状態です。
世界の金価格の推移と背景
2020年以降の金価格は、以下のような流れで推移してきました。
| 年度 | 主な出来事 | 年平均価格(1トロイオンス) |
|---|---|---|
| 2020年 | コロナショックによる金融緩和 | 約1,770ドル |
| 2021年 | 経済再開・金利上昇で一時下落 | 約1,800ドル |
| 2022年 | ウクライナ危機・インフレ高進 | 約1,950ドル |
| 2023年 | FRB利上げ終了観測・ドル安進行 | 約2,000ドル |
| 2024年 | 中東情勢不安・AI関連需要増加 | 約2,250ドル |
| 2025年 | 各国の通貨安と実需拡大 | 約2,400ドル(史上最高圏) |
ここ数年、金価格を押し上げている最大の要因は、通貨価値の下落とインフレの持続です。
各国が金融緩和や財政出動を続けたことで、実質的な購買力が低下。
その結果、「紙幣の信用リスク」から資産を守る手段として、金への需要が高まりました。
金価格を動かす5つの要因
金の価格を決定づけるのは、主に次の5つのグローバル要因です。
- 米ドルの為替動向
金はドル建てで取引されるため、ドル安になると金価格は上がりやすくなります。
逆にドル高は金価格を抑制します。 - 各国の金利政策
金は利息を生まない資産のため、金利が下がる局面では投資妙味が増します。
特に2025年は、FRB(米連邦準備制度)が利下げに転じるとの見方が金相場を支えています。 - インフレ率の上昇
実質金利(名目金利−インフレ率)がマイナス圏に入ると、金は資産保全の手段として選ばれます。 - 地政学リスクの拡大
中東・ウクライナなどの不安定要因が続く中、安全資産としての金需要が根強いです。 - 中央銀行による金買い
新興国の中央銀行(特に中国・インド・ロシアなど)が金保有を増やしており、価格を下支えしています。
2025年の市場環境と金相場の位置づけ
2025年の国際市場では、以下の3つの構造変化が金価格を押し上げています。
- 「ドル離れ」の加速
各国がドル依存から脱却し、金やユーロ・人民元での取引を拡大。
これが金の国際的な価値をさらに押し上げています。 - 生成AI・半導体産業の金需要増加
高性能デバイスやAIサーバーには金を含む希少金属が欠かせず、実需面でも金の需要が高まっています。 - 個人投資家の参入増
日本を含む先進国では、インフレ対策として金ETFや純金積立を利用する個人投資家が増加。
「投資のサブ資産」として金が一般化しつつあります。
今後の見通しと注意点
アナリストの多くは、金価格の中長期的な上昇トレンドは継続すると見ています。
米国の利下げ局面が進行すれば、金利低下とドル安によって金は再び上値を試す展開が予想されます。
ただし短期的には、
- 利上げ再開の可能性
- 利益確定売り
- ドル高反転
といった要因で調整が入る可能性もあります。
したがって、長期保有を前提に分散投資として少しずつ買い増すのが現実的な戦略です。
日本市場での金価格動向
日本では円安が続く影響で、ドル建て価格の上昇に加えて円換算でも高値を更新しています。
2025年10月時点では、国内の金小売価格は1gあたり約13,000円前後と、史上最高水準です。
この円安環境では、海外要因以上に「為替」が金価格を押し上げているため、
投資の際は為替相場とのバランスを注視することが欠かせません。
まとめ
2025年の金市場は、
- 通貨安とインフレの長期化
- 地政学リスクの拡大
- 中央銀行・個人投資家の金買い
といった複合的な要因で支えられています。
短期の値動きに一喜一憂せず、世界経済の不確実性を見越した長期保有こそが金投資の本質です。
今後も金は、「紙幣では守れない価値を守る資産」として、投資ポートフォリオの中心的存在であり続けるでしょう。
第六章 金投資に向いている人と資産配分の考え方

金投資は、すべての人に同じように適しているわけではありません。
株や不動産のように「成長」を狙う投資ではなく、資産を守るための防御的な投資です。
ここでは、どんな人が金投資に向いているのか、そしてどのくらいの割合で保有すべきかを詳しく解説します。
金投資に向いている人の特徴
- リスクを取りすぎず、安定した運用を重視する人
金は「リスクを減らすための資産」です。株や暗号資産のような爆発的リターンはありませんが、
相場が荒れたときに損失を緩和する役割を果たします。 - 長期目線で資産形成を考えている人
短期的な売買で利益を狙うよりも、10年・20年単位で保有する人に向いています。
金は「時間をかけて価値を守る」性質があるため、老後資産や教育資金の分散先としても有効です。 - 円安・インフレに備えたい人
物価上昇や円安によって日本円の実質的な価値が下がるとき、金の価値は上がる傾向があります。
そのため、生活防衛資産として金を保有する人が増えています。 - 世界情勢や経済リスクに敏感な人
戦争・金融危機・感染症などの「不確実性の高い時代」では、金は強力なリスクヘッジ手段となります。
特に近年のように国際情勢が不安定なとき、金を持つ安心感は他の資産では代えがたいものです。
金投資に不向きな人の特徴
一方で、以下のようなタイプの人には金投資は向きません。
- 短期で大きな利益を求める人
- 毎月の収益(配当・利息)を重視する人
- 価格変動に一喜一憂しやすい人
金は「攻めの資産」ではなく、「守りの資産」です。
もし投資経験が浅く、利益追求を優先したい場合は、まず株式やインデックス投資で基盤を作ることをおすすめします。
理想的な資産配分の考え方
ポートフォリオを設計する上で、金は「リスクを吸収するバランサー」として機能します。
一般的に、次のような配分が現実的です。
| 投資スタイル | 金の割合 | 特徴 |
|---|---|---|
| 保守型(リスク低) | 15〜20% | 資産保全を重視。金を多めに配置し安定性を確保。 |
| バランス型 | 10〜15% | 株・債券とのバランスを取り、下落局面の損失を緩和。 |
| 成長型(リスク高) | 5〜10% | 株式中心の中でリスクヘッジ目的に少量保有。 |
たとえば、1,000万円の総資産がある場合、100万〜150万円を金に振り分けるのがバランスの取れた設計です。
これは、株価下落時に金が上昇する「逆相関効果」により、資産全体の変動を抑える狙いがあります。
投資タイミングと購入戦略
金はタイミングを測るよりも、定期的に買い増す積立戦略が有効です。
毎月一定額を購入することで、価格変動リスクを平準化し、
高値づかみを避けることができます(ドルコスト平均法)。
また、長期的に保有する前提であれば、価格が下がったときこそ買い増しのチャンスです。
「短期の値下がりは、長期の買い場」と捉える考え方が、金投資成功者の共通点です。
金以外との組み合わせが重要
金投資は単体で行うよりも、他の資産と組み合わせることで真価を発揮します。
たとえば次のような分散例が有効です。
- 株式(成長資産)……60%
- 債券(安定資産)……20%
- 金(守りの資産)……15%
- 現金・短期預金……5%
このように組み合わせることで、「株が下がっても資産全体が沈まない」安定した運用が可能になります。
特に2025年のようなインフレと金利変動が共存する相場環境では、金がポートフォリオの安定剤として機能します。
まとめ
金投資に向いているのは、
- 長期で資産を守りたい人
- インフレや円安に備えたい人
- 株価下落時のリスクヘッジを求める人
です。
理想の資産配分を意識しながら、「守りの資産」として金を戦略的に組み込むことが、これからの時代のスタンダードです。
市場の波に惑わされず、静かに価値を積み上げていく“金投資”の強さを、あなたのポートフォリオにも取り入れてみてください。
第七章 まとめ 金投資で資産を守りながら増やすために
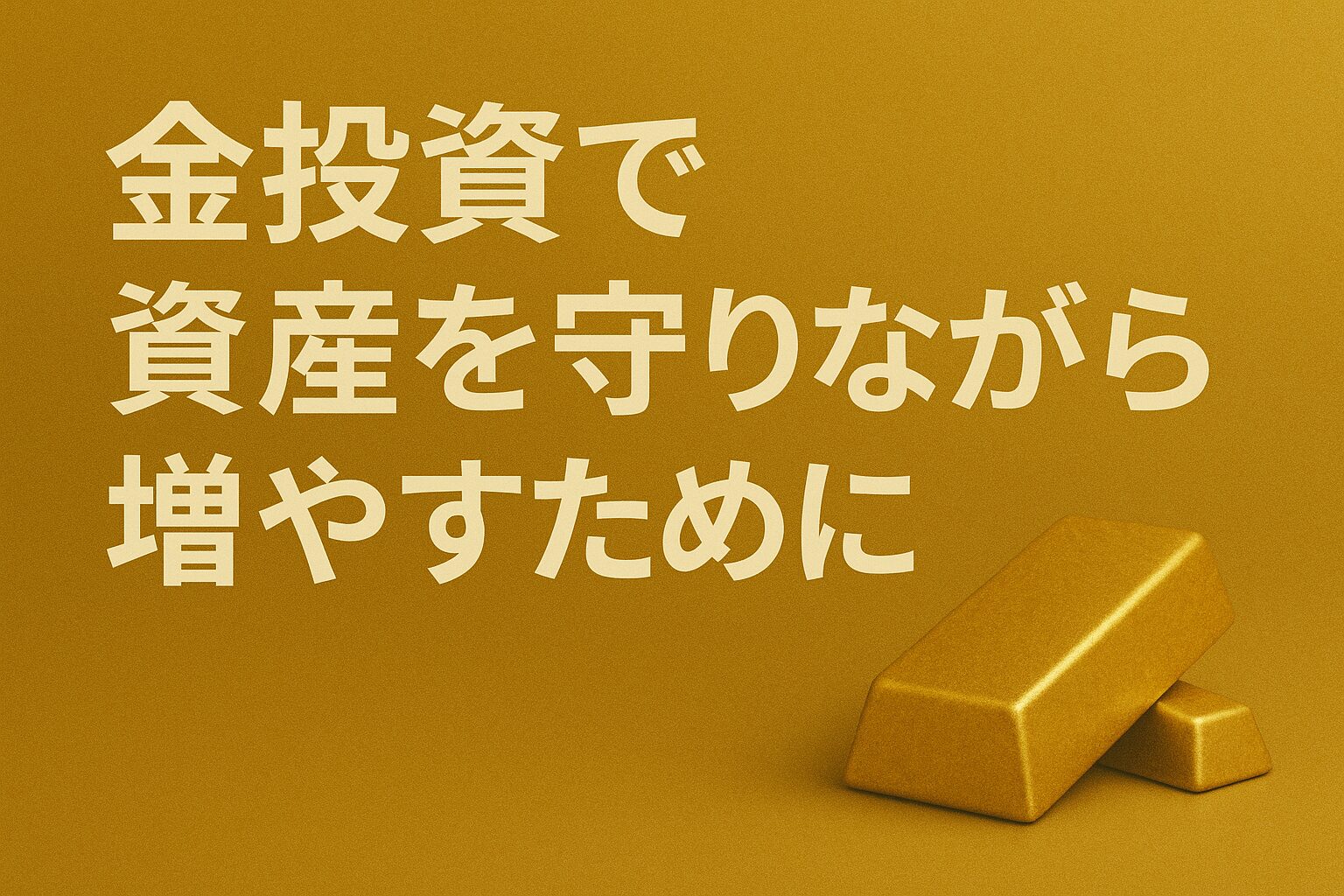
2025年の世界経済は、インフレ、金利変動、地政学リスクなど、あらゆる不確実性を抱えています。
その中で、「資産を増やす」だけでなく「資産を守る」ことの重要性が、これまで以上に高まっています。
金投資はまさにその「守りの資産運用」の中心に位置する存在です。
金投資の本質は“時間で勝つ投資”
金は短期的な値動きに一喜一憂するものではなく、長期的な時間を味方にする資産です。
現金がインフレで目減りしても、金はその価値を保ち続けます。
100年前の1万円と今の1万円の価値は全く違いますが、100年前の金の価値は今も通用するのです。
つまり、金投資とは「今の自分」だけでなく、「未来の自分」へのプレゼント。
長期目線で持ち続けることが最大のリターンを生む鍵になります。
金投資を始める前に押さえるべき3つのポイント
- 目的を明確にする
老後資産の守りなのか、インフレ対策なのか。目的によって最適な投資方法が異なります。 - 保有比率を決める
ポートフォリオの5〜15%を目安に、他の資産とのバランスを取ることが重要です。 - 積立・分散を徹底する
ドルコスト平均法で毎月一定額を買い続けることで、リスクを自然に平準化できます。
この3つを守るだけで、金投資は「難しい金融商品」ではなく、誰でも取り組める資産防衛術になります。
2025年以降、金投資が“常識”になる理由
- 世界的な通貨価値の低下(ドル・円安トレンド)
- 中央銀行による金買いの増加
- 投資アプリやネット証券の普及による参入ハードルの低下
- 富裕層だけでなく、一般家庭の「マネー防衛意識」の高まり
これらの流れは一時的なブームではなく、新しい金融常識の定着です。
「お金の価値を守る」という概念が浸透する中で、金はもはや“特別な投資”ではなく、“誰もが持つべき基盤資産”へと進化しています。
今すぐできる行動ステップ
- 証券口座を開設し、純金積立や金ETFをチェック
SBI証券、楽天証券、マネックス証券など、主要ネット証券で少額から始められます。 - 毎月の自動積立設定を行う
1,000円でも問題ありません。始めることが最も重要です。 - 価格変動を恐れず、継続を習慣化
金投資は「続けた人が勝つ」資産運用です。
まとめの結論
金投資は、「リスクを避けながら資産を守る」ための最もシンプルで確実な手段です。
- インフレに強く
- 通貨価値に左右されず
- 世界で共通の信頼を持ち
- 長期的に価値を維持する
という点で、他の資産にはない圧倒的な安定感があります。
将来の不確実性が増す時代だからこそ、“攻めの投資”と“守りの投資”の両輪を持つことが重要です。
そして、その「守りの軸」に最もふさわしいのが、金という資産なのです。
💡 行動の一歩
今日、金投資を始めるかどうかが、5年後・10年後のあなたの安心度を決めます。
1,000円からでも、1gからでも構いません。
「資産を守る」第一歩として、今すぐ金投資を始めてみましょう
ちなみにこれから資産運用を始めたい人、既存のポートフォリオを見直したい人にとって、ITトレンドMoneyは有力な選択肢となります。
安心できる環境で専門家に相談し、将来の資産設計を前向きに進めていきましょう。

\最短10秒で申込み/
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。