※本ページはプロモーションが含まれています。
1. 2025年の日産決算発表の概要
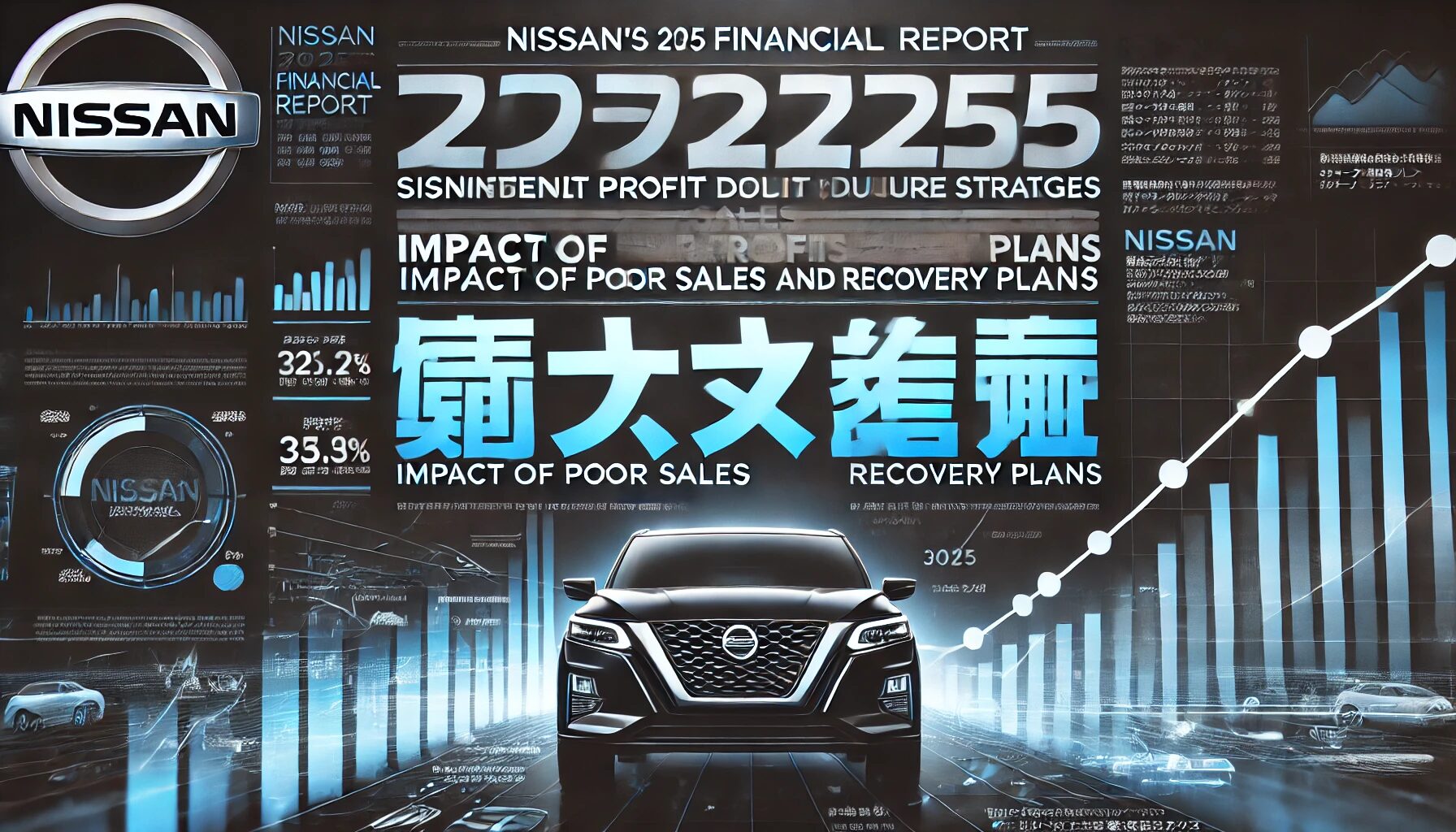
日産自動車は2025年2月13日に、2025年3月期第3四半期(4月~12月)の決算を発表しました。
その結果、連結営業利益は前年同期比86.6%減の640億円に落ち込みました。
この大幅な減益は、米国や中国市場での販売不振が主な要因とされています。
また、今回の決算発表に伴い、日産は業績目標を下方修正しました。
2024年4月から2025年3月までの純利益の見通しは、当初の2920億円から2000億円へ、営業利益は3350億円から2200億円へと大幅に引き下げられました。
さらに、世界販売台数の目標も650万台から620万台に縮小されることが決定しました。
この業績悪化の背景には、日産の主要市場である米国と中国における販売低迷が影響していると考えられています。
特に米国市場では、競争が激化する中で日産のシェアが低下し、新車販売が思うように伸びていません。
一方、中国市場ではEV(電気自動車)メーカーの台頭によって競争が激しくなり、日産の販売が振るわない状況が続いています。
こうした厳しい環境の中で、日産は業績回復に向けた新たな戦略を求められています。
特に、コスト削減の取り組みやEV戦略の見直しが今後の重要な課題となるでしょう。
2. 販売不振の要因と市場動向
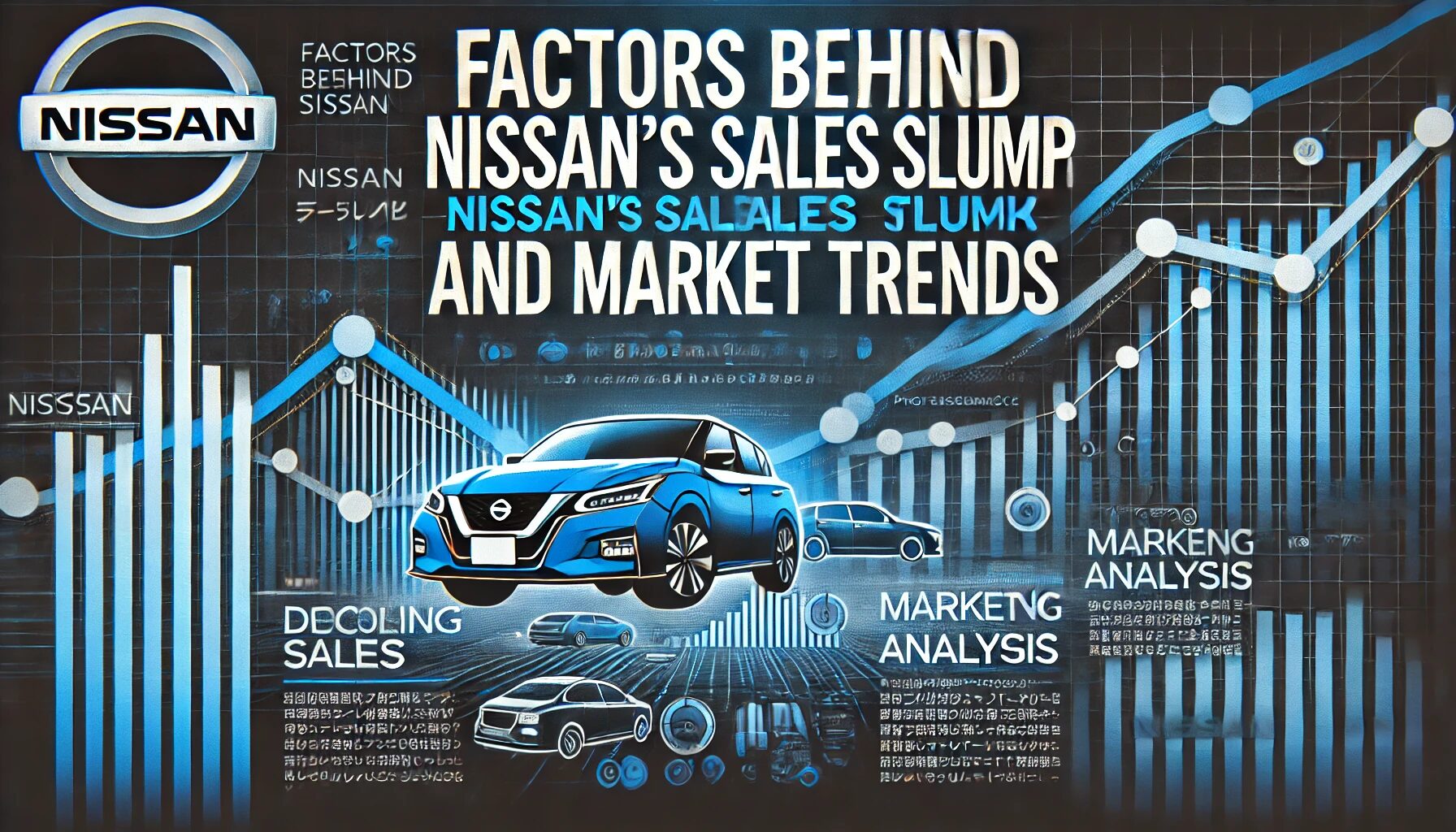
日産の大幅な業績悪化の背景には、主に米国市場と中国市場での販売不振があります。
これらの市場は日産にとって重要な収益源ですが、近年の競争環境の変化や市場の動向が厳しくなり、販売台数が思うように伸びていません。
米国市場での苦戦
米国市場では、SUVやピックアップトラックの需要が高まる中、日産の主要モデルが競争力を維持できていないことが問題視されています。
特に、「ローグ(エクストレイル)」や「アルティマ」などの主力車種の販売が低迷し、シェアの縮小が続いています。
また、米国ではEV(電気自動車)市場も急成長していますが、日産はこの分野での競争力強化が急務となっています。
かつて「リーフ」でEV市場をリードしていた日産ですが、現在はテスラやGM、フォードなどのメーカーが次々と新型EVを投入し、競争が激化しています。
日産の新型EV「アリア」も販売は伸び悩んでおり、EV戦略の見直しが必要な状況です。
中国市場での販売低迷
一方、中国市場では、新興EVメーカーの台頭が日産の業績に大きな影響を及ぼしています。
BYDやNIO(蔚来)、Xpeng(小鵬)などの中国メーカーが、競争力のあるEVを次々と投入し、国内市場でのシェアを急速に拡大しています。
その結果、従来の内燃機関(ガソリン車)を主力とする日産の販売は減少し、EV分野でも存在感を示せていない状況です。
また、中国政府はEV普及のための政策を積極的に進めており、EVに対する補助金や税制優遇が強化されています。
これにより、EV市場の成長スピードが加速する一方で、日産のように従来のガソリン車とEVの両方を展開する企業にとっては厳しい競争環境となっています。
競争環境の変化と他社の動き
日産は現在、グローバル市場での競争力を強化する必要があります。
特にEV市場では、テスラやBYDなどの専業メーカーに加え、トヨタやフォルクスワーゲンなどの大手メーカーも本格的にEV事業に参入しています。
トヨタは「プリウス」や「bZシリーズ」などのハイブリッド車(HEV)とEVを組み合わせた戦略を展開し、フォルクスワーゲンも「ID.シリーズ」でEV市場に本格参入しています。
これらの競合に対抗するためには、日産もEV戦略の見直しと販売網の強化が急務となります。
米国・中国市場での販売不振をどのように克服するのか、日産の今後の対応が注目されます。
3. ホンダとの経営統合協議の打ち切りと影響

日産は近年、経営の効率化と競争力強化を目的に、ホンダとの経営統合の可能性を模索していました。
しかし、2025年初めに両社の協議が打ち切られることが正式に発表され、業界に大きな波紋を広げました。
この決定は、日産の今後の成長戦略にどのような影響を与えるのでしょうか。
経営統合協議が行われた背景
日産とホンダは、共にグローバル市場での競争力強化を目指し、特にEV(電気自動車)分野での協力を検討していました。
・EV技術の開発には多額の投資が必要であり、企業単独での競争が困難になっている
・トヨタやフォルクスワーゲンなどの大手メーカーがEV開発を加速させており、対抗するためには規模の経済が必要
・日産とホンダはそれぞれ異なる強みを持っており、技術や生産面でのシナジー(相乗効果)が期待できる
このような理由から、日産とホンダがEVや自動運転技術の共同開発、プラットフォームの共通化、生産効率の向上を目的に協議を進めていたと考えられます。
経営統合協議が打ち切られた理由
しかし、最終的にこの協議は実現に至らず、2025年初めに打ち切られることが発表されました。
その理由として、以下の点が挙げられます。
・経営方針の違い:日産とホンダはそれぞれ独自の経営戦略を持ち、統合による方向性の調整が難しかった
・ブランドの独立性:統合によってブランド価値が損なわれる可能性があり、特にホンダ側が慎重になったとされる
・技術戦略の相違:ホンダは独自の水素燃料電池車(FCV)戦略を進めており、日産のEV中心の戦略と完全には一致しなかった
これらの要因が重なり、統合のメリットよりもリスクの方が大きいと判断され、協議は終了しました。
日産の今後への影響
ホンダとの統合が実現しなかったことで、日産は単独での競争力強化を図る必要があります。
特に、EV市場での競争が激化する中、技術開発やコスト削減を単独で進めなければならないという課題に直面しています。
・EV戦略の再構築:アリアや新型リーフの開発を加速し、EV市場での競争力を高める
・コスト削減の徹底:40%のコスト削減計画を実行し、利益率の向上を目指す
・新たなパートナーシップの模索:ホンダ以外の企業と新たな提携を模索し、技術や生産面での協力関係を築く可能性
日産は過去にも、ルノーや三菱自動車とのアライアンスを通じて成長してきました。
ホンダとの経営統合は実現しませんでしたが、今後は他の企業との提携や戦略的パートナーシップを活用しながら、EV市場での立ち位置を確立していくことが求められます。
4. 業績回復に向けた日産の対策

2025年の決算発表で明らかになった業績の大幅減益を受け、日産は今後の経営戦略を見直し、業績回復に向けたさまざまな対策を進めています。
その中でも、コスト削減、EV戦略の見直し、グローバル販売の強化が重要なポイントとなっています。
コスト削減40%達成に向けた取り組み
日産は現在、40%のコスト削減を達成するための計画を進めています。
この取り組みは、利益率の改善を目的としており、主に以下のような方法で実施される予定です。
・生産体制の最適化:工場の統廃合や生産ラインの効率化を進め、コストの削減を図る
・部品の共通化:異なる車種間で同じ部品を使用することで、調達コストを引き下げる
・固定費の削減:マーケティング費用の見直しや、事業のスリム化を実施
特に、ルノーや三菱自動車とのアライアンスを活用し、生産・調達の効率を高めることが期待されています。
これにより、単独での開発コストを抑えながら、新しい技術を迅速に市場に投入することが可能となります。
EV戦略の見直しと新モデル投入計画
EV市場での競争力を高めるため、日産はEV戦略の見直しを進めています。
かつて「リーフ」でEV市場をリードしていた日産ですが、現在はテスラやBYDなどの競合メーカーに対して遅れをとっています。
そこで、日産は以下のような施策を打ち出しています。
・新型EVの投入:「アリア」に続く新型EVの開発を加速し、競争力のある価格帯で市場に投入
・EV用バッテリーの開発強化:全固体電池の実用化を目指し、航続距離の向上や充電時間の短縮を実現
・EV販売地域の拡大:北米・欧州・中国市場だけでなく、東南アジアやインド市場にも本格的にEVを投入
また、EVの価格競争が激しくなっているため、日産は低価格帯のEVモデルの開発にも着手しています。
特に、コストパフォーマンスに優れたEVを市場に投入し、幅広いユーザー層にアピールすることを目指しています。
グローバル販売の強化策
日産は、販売不振が続く米国・中国市場でのシェア回復に加え、新興国市場への進出を強化する方針を示しています。
・米国市場の巻き返し:「ローグ(エクストレイル)」や「アルティマ」などの人気車種の改良版を投入し、ブランド力を再強化
・中国市場でのEV販売強化:BYDやNIOと競争するため、EVラインナップを拡充し、現地生産を強化
・東南アジア・インド市場の開拓:成長が期待される新興市場において、価格競争力のあるモデルを展開
特に東南アジアやインド市場では、EVの普及が進みつつあり、今後の成長が見込まれています。
日産はこれらの地域での販売戦略を強化し、新たな収益源を確保する考えです。
業績回復には時間がかかるかもしれませんが、日産が打ち出したこれらの戦略が実を結べば、再び競争力を取り戻す可能性があります。
5. 2025年度の見通しと投資家への影響

2025年の決算発表を受け、日産は業績の下方修正を発表しました。
これにより、投資家の間では今後の経営状況に対する懸念が高まっています。
純利益や営業利益の減少、世界販売台数の引き下げといった動きが、どのような影響を及ぼすのでしょうか。
純利益・営業利益の下方修正の詳細
日産は2025年度の業績見通しを以下のように修正しました。
・純利益:当初の2920億円から2000億円へ減少
・営業利益:3350億円から2200億円へ下方修正
・世界販売台数:650万台から620万台へ縮小
この修正は、主に米国と中国市場での販売不振によるものです。
特に、中国ではEV市場での競争が激化しており、日産の販売台数が伸び悩んでいます。
また、米国市場でもSUVやEVの販売が低調であり、業績回復には時間がかかる見通しです。
世界販売台数引き下げの影響
販売台数の引き下げは、日産の収益構造に大きな影響を及ぼします。
一般的に、自動車メーカーは一定の販売台数を確保することで生産コストを抑え、利益を確保しています。
そのため、販売目標が下方修正されることは、収益の減少に直結します。
特に、EV市場では価格競争が激しくなっており、日産が競争力のある価格帯で新型車を投入できるかどうかが重要なポイントとなります。
もし競争力のあるEVを市場に投入できなければ、さらに販売台数が落ち込む可能性もあります。
投資家・市場の反応と今後の焦点
日産の決算発表を受け、株式市場では同社の株価に対する不安が広がりました。
投資家は特に以下の点に注目しています。
・EV戦略の行方:アリアの販売不振を受け、新たなEVモデルの投入がどのように進められるのか
・コスト削減計画の進捗:40%のコスト削減が実現可能なのか、その効果がいつ現れるのか
・新市場開拓の成功可否:東南アジアやインド市場への進出が、どの程度業績回復につながるのか
また、投資家の間では、ホンダとの経営統合協議が打ち切られたことによる影響も注目されています。
統合によるシナジーが期待できなくなったため、日産が単独で成長戦略を推進する必要があり、今後の経営判断が市場に与える影響は大きいでしょう。
今後の展望
日産は今後、EV市場での競争力強化、コスト削減、グローバル販売の強化といった課題に取り組む必要があります。
2025年度の業績回復には時間がかかるかもしれませんが、適切な戦略を実行できれば、再び競争力を取り戻す可能性があります。
投資家や市場関係者は、日産が発表する今後の新戦略や経営計画に注目しており、特に新型EVの発表や収益改善の兆しが見えるかどうかが焦点となるでしょう。
2025年は、日産にとって大きな転換期となる1年になるかもしれません。
今後の動向もスマホでチェックしたい方は大人気の証券口座があるよ!
>僕が人気株が当たるキャンペーンに参加した結果を紹介しているので、よかったら見てみてください👇
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

