※本ページはプロモーションが含まれています。
はじめに|長く持つほど優待が良くなるって本当?

株主優待といえば、100株保有でお米やクオカード、食事券などがもらえる“お得な特典”というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
実際、日本企業の多くが個人株主を増やす目的で魅力的な優待制度を導入しており、節約やご褒美として役立てている人も少なくありません。
そんな中、近年注目されているのが「長期保有優遇型の株主優待」です。
これは、単に株を保有しているだけでなく、“何年持ち続けたか”によって優待内容がグレードアップする制度のことを指します。
たとえば、「1年保有で+1,000円分の優待券」「3年以上の保有でカタログギフトが2倍」など、“持ち続けた株主”への感謝を形にした特典が用意されています。
この仕組みにより、短期売買では得られない“じっくり育てる投資の楽しさ”が生まれます。
こうした長期保有優遇制度は、企業側にもメリットがあります。
安定した株主に支えられることで、株価の急落リスクを下げ、経営の安定化にもつながるため、株主と企業の信頼関係を深める仕組みとして注目が集まっています。
この記事では、そんな「長期保有で得られる株主優待」に焦点を当て、以下のような内容をわかりやすく解説していきます。
- 長期保有優遇型優待の仕組みと魅力
- 実際に長期保有でグレードアップする注目銘柄
- 保有年数や株数ごとの比較表
- 注意すべき落とし穴とよくある疑問
- じっくり投資を続けるメリットとは?
長く付き合うからこそ得られる、特別な優待の世界。
この記事を読めば、「ただ株を買って持つだけ」で終わらない、もう一歩先の株主優待投資が見えてくるはずです。
長期保有優遇型の株主優待とは?|仕組みとメリット

株主優待制度には、一定の株数を保有しているだけでもらえる“一律型”のものと、保有年数に応じて優待内容が変化する“長期保有優遇型”の2種類があります。
特に最近では、後者の長期保有型優待を導入する企業が増えており、投資家にとっては見逃せないポイントとなっています。
長期保有優遇型の定義とは?
長期保有優遇型とは、一定期間以上、継続して株式を保有している株主に対して、通常の優待よりも内容が充実した特典を提供する仕組みです。
企業によって「長期」の定義は異なりますが、一般的には以下のような条件が設けられています。
- 1年以上の継続保有(例:ビックカメラ)
- 3年以上の保有でグレードアップ(例:ヒューリック)
- 5年以上で最上級の優待に変化(例:NTT)
この「保有していた年数」は、証券会社を通じて管理されており、株主名簿に記載されている回数(年数)で判断されるケースが多いです。
企業が“長期保有”を重視する理由
企業が長期保有を優遇する背景には、以下のような意図があります。
- 株主の入れ替わりを減らし、安定株主を確保したい
- 短期的な株価変動に左右されにくい経営基盤を築きたい
- 株主との信頼関係を築くことで、IRコストを削減したい
そのため、長期保有優遇型の優待制度は、企業と投資家の“Win-Win”を実現する施策として評価されています。
長期保有で変わる優待内容の具体例
実際に、長期保有によって優待内容がどう変わるかの一例を紹介します。
- QUOカードの金額が増額(例:ビックカメラ)
- カタログギフトの内容が2倍に(例:ヒューリック)
- ポイント数が2倍にアップ(例:NTT)
- 商品券やギフトカードの追加贈呈(例:イオン)
これらはすべて、株数を買い増さなくても、「持ち続けるだけ」で優待がグレードアップする点が最大の魅力です。
投資家にとってのメリット
長期保有優遇型優待を活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 配当+優待でトータル利回りが向上
- 長期投資のモチベーションになる
- 実質的な“ホールドボーナス”としてお得感が強い
- 生活に密着した特典が増え、投資を実感しやすくなる
特に、日用品や食料品など実用性のある優待をグレードアップできれば、日々の暮らしに直接“投資の成果”を感じられるようになります。
長期保有でグレードアップする注目の優待銘柄5選

ここでは、実際に「長期保有優遇型の株主優待」を導入している企業の中から、特に人気・実用性・リターンのバランスに優れた注目の5銘柄を厳選してご紹介します。
保有年数に応じて優待がどう変化するかも含め、わかりやすく解説します。
ヒューリック(3003)|3年保有でカタログギフトが2倍に!

- 通常優待内容:3,000円相当のカタログギフト(グルメ・日用品など)
- 長期優遇条件:3年以上の継続保有で「カタログ2冊」にグレードアップ(6,000円相当)
- 魅力ポイント:
- 東証プライム上場の安定企業
- カタログ内容のクオリティが高く、毎年楽しみにしている株主も多数
- 100株保有だけでOKというハードルの低さも◎
ビックカメラ(3048)|1年保有で買物券が年+1,000円分増

- 通常優待内容:年2回、合計3,000円分の買物優待券(2月:2,000円、8月:1,000円)
- 長期優遇条件:1年以上保有で8月分に+1,000円(合計4,000円に)
- 魅力ポイント:
- 家電や日用品を割安で購入できるため実用性が高い
- ネット通販(ビックカメラ.com)でも利用可能
- 実店舗派にもEC派にもおすすめ
日本電信電話(9432)|5年保有でdポイントが2倍に
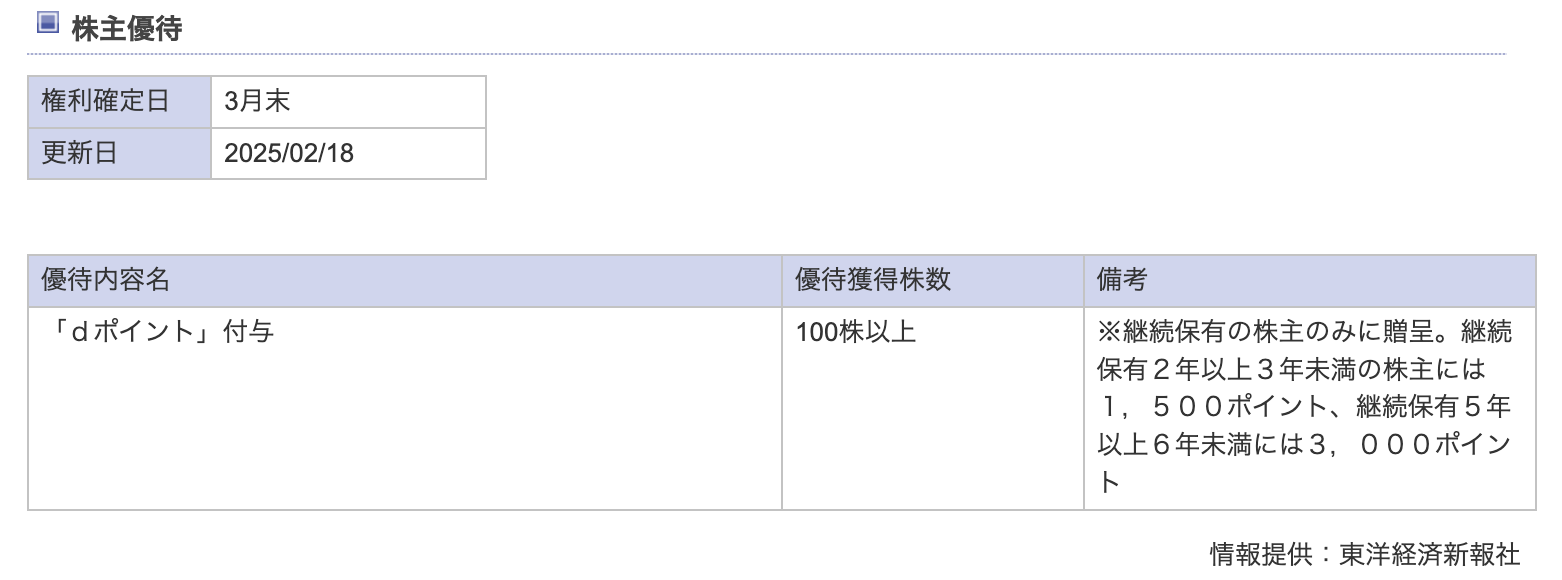
- 通常優待内容:1,500円相当のdポイント(年1回)
- 長期優遇条件:5年以上の継続保有で3,000ポイントにアップ
- 魅力ポイント:
- ドコモユーザーならポイントの汎用性が高く、ほぼ“現金感覚”で使える
- 通信インフラ系で業績も安定
- 高配当株としても評価が高く、優待+配当でダブルのお得感
イオン(8267)|3年保有でギフトカードの追加特典あり
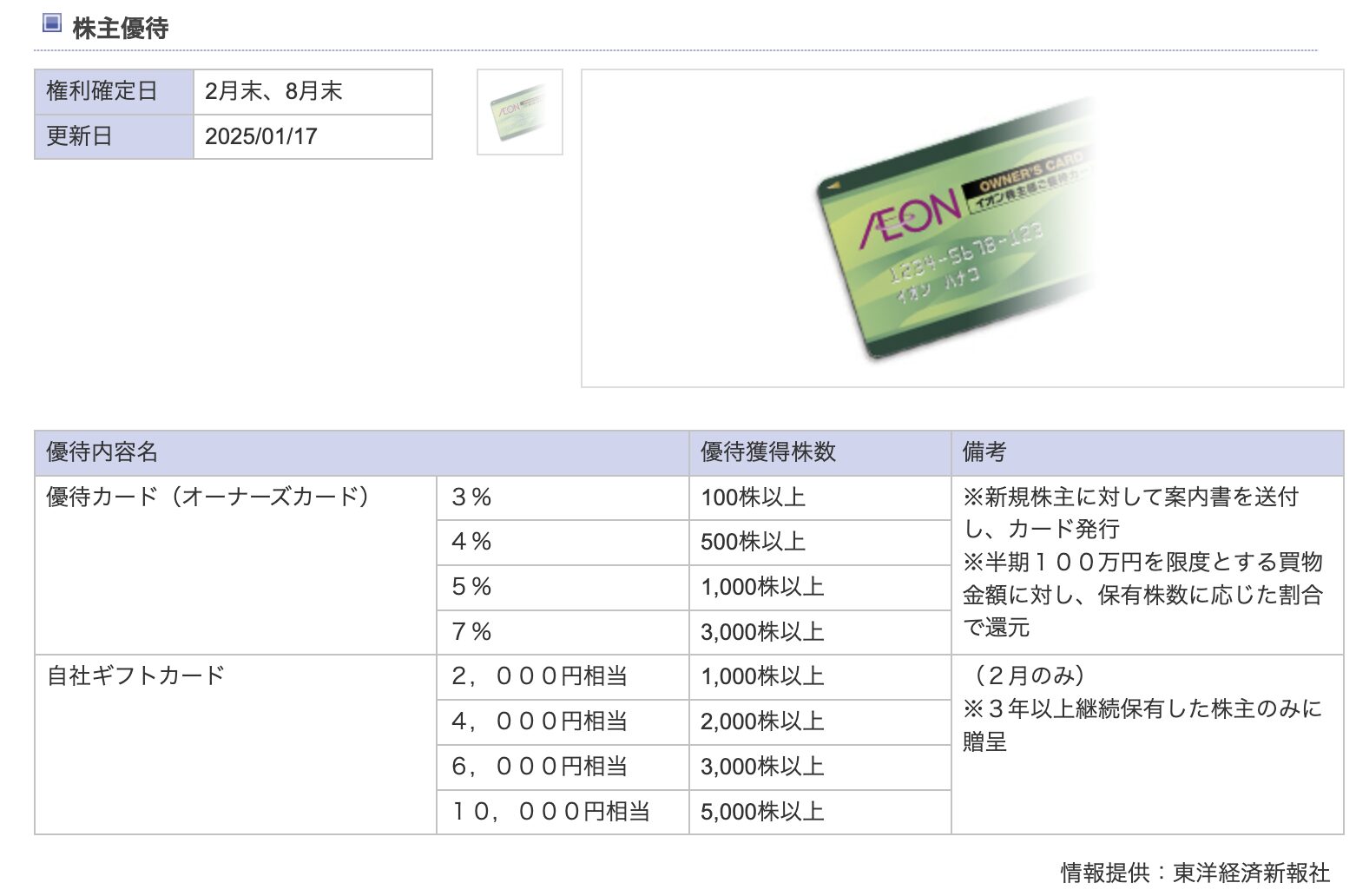
- 通常優待内容:オーナーズカードによる3〜7%の買物キャッシュバック(半年ごと)
- 長期優遇条件:3年以上保有でイオンギフトカード(3,000〜10,000円相当)を追加進呈
- 魅力ポイント:
- 普段からイオンを利用している方には“実質値引き”となる高還元制度
- 保有株数によってキャッシュバック率やギフトカード額が変動
- 全国どこでも使える利便性が抜群
ソフトバンク(9434)|1年以上の継続保有でPayPayポイント進呈
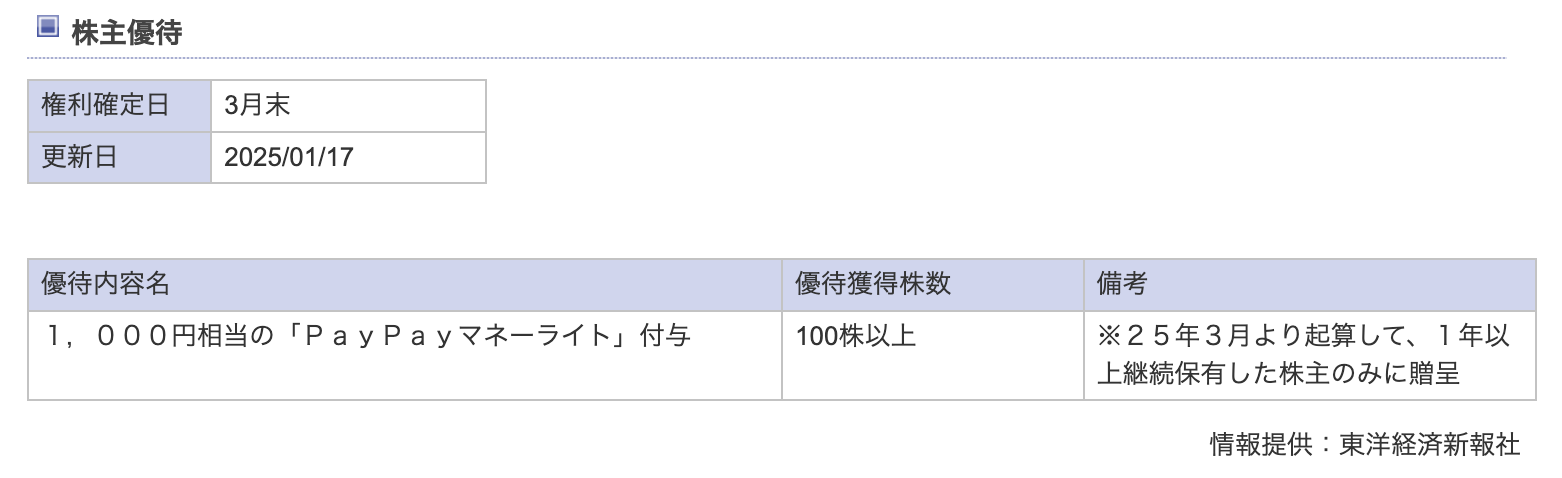
- 通常優待内容:条件を満たすとPayPayポイント(年1回)
- 長期優遇条件:1年以上の継続保有が必要。短期保有では付与対象外
- 魅力ポイント:
- 100株で権利対象になりやすく、初心者にも参入しやすい
- PayPayユーザーなら日常の支払いに使える汎用性が高いポイント
- 通信業界×キャッシュレスという相性の良い組み合わせ
これらの銘柄は、少額から投資できるうえに、優待+配当で長期的なリターンが期待できる点が大きな魅力です。
最近では、株主優待情報を簡単に管理できるアプリが多数登場しています。
その中でも特におすすめのアプリが「moomooアプリ」です。
このアプリは、様々な企業の株主優待情報を一元管理できるだけでなく、最新の優待情報もリアルタイムで配信してくれます。
テレビやYouTube広告でも話題のあのアプリだね!
使い方は非常にシンプルです。
moomooアプリをダウンロードし、気になる企業をお気に入りに登録するだけで、優待の内容や期限をすぐに確認できます。
長期保有優待の比較一覧|何年保有でどんな内容に変わる?

ここでは、前章で紹介した5社の長期保有優遇型株主優待を一目で比較できるよう、保有年数・必要株数・優待内容・年間総額などを表形式でまとめました。
どの企業が自分のライフスタイルに合っているか、選びやすくなっています。
長期保有優待 比較表(2025年版)
| 企業名 | 必要株数 | 通常優待内容 | 長期保有条件 | 長期保有時の優待内容 | 年間優待総額の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒューリック(3003) | 100株 | カタログギフト3,000円相当(年1回) | 3年以上 | カタログギフト2冊(6,000円相当) | 6,000円相当 |
| ビックカメラ(3048) | 100株 | 買物券3,000円分(年2回) | 1年以上 | 8月分に+1,000円加算(年4,000円) | 4,000円相当 |
| NTT(9432) | 100株 | dポイント1,500ポイント(年1回) | 5年以上 | dポイント3,000ポイント | 3,000円相当 |
| イオン(8267) | 100株〜 | オーナーズカード3%還元(買物額に応じて) | 3年以上 | ギフトカード3,000〜10,000円分追加 | 年数・株数により変動 |
| ソフトバンク(9434) | 100株 | PayPayポイント(年1回)※条件あり | 1年以上 | ポイント進呈確定(内容非公開) | 推定1,000円〜2,000円相当 |
注目ポイントまとめ
- ヒューリック:100株のまま3年以上持つだけで優待が2倍になるのは圧倒的コスパ。
- ビックカメラ:保有1年で+1,000円の追加は、初心者にもうれしい“短期長期の中間型”。
- NTT:5年という長期条件ながら、dポイントの利便性が高く、ドコモユーザーには実質現金級。
- イオン:普段からイオンで買い物するなら、キャッシュバック+ギフトカードの2段構えは魅力大。
- ソフトバンク:PayPayを使っている人には実用度が高く、生活費の節約にも直結。
長期保有優待は、株価の値上がりだけを目的とした短期売買では得られない“継続投資のリターン”を享受できる制度です。
少額でも長く保有することが、最終的に大きなメリットを生むという投資の本質を体感できる手段ともいえます。
なぜ企業は長期保有優遇を導入するのか?|企業側のメリット

株主優待は本来、企業が個人株主と良好な関係を築くための手段ですが、近年では“長期保有を条件とした優待制度”を導入する企業が急増しています。
その背景には、企業側にも大きなメリットがあるためです。ここでは、企業が長期保有優遇制度を採用する理由を深掘りしていきます。
株主の安定化で株価の急落リスクを抑制
株主の入れ替わりが激しいと、市場での売買が活発になりすぎ、株価が短期間で大きく変動するリスクが高まります。
そこで、長期保有を促すことで「売られにくい株主=安定株主」を増やし、株価の安定性を確保しようという狙いがあります。
短期売買を抑えて“投機”より“投資”の株主を増やす
優待目当ての短期保有(いわゆる“優待クロス”や“タダ取り”)が増えすぎると、企業にとっては実質的なコスト負担のみが残ってしまいます。
長期保有者に優待を手厚くすることで、一時的な優待目的の保有を抑え、本当に応援してくれる投資家を育てる意図があります。
IR(投資家向け広報)コストの削減
株主が頻繁に入れ替わると、そのたびに配当案内や招集通知、議決権行使の書類などを新たに発送しなければなりません。
しかし、長期で保有してくれる株主が増えれば、これらのIR関連コストの削減にもつながるのです。
信頼関係の構築とブランド価値の向上
「この企業は長く持ってくれる株主を大切にしてくれる」と投資家に認識されることで、企業ブランドの信頼性が高まる効果もあります。
優待を通じた企業との接点は、消費者でもあり株主でもある“ファン株主”の育成にも貢献します。
ESGやサステナビリティの観点からも評価
近年注目されているESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも、株主との中長期的な関係構築は重要視されています。
一過性の優待ではなく、持続的なメリットを提供することで、企業の社会的責任を果たす姿勢を示すことができるのです。
長期保有優待は、単なる“おまけ”の制度ではなく、企業が戦略的に設計する持続可能な経営の一環ともいえます。
次章では、実際に長期保有を目指す際に注意すべき点や、よくある勘違いについて詳しく解説していきます。
長期保有優待の注意点|誤解・勘違いに気をつけて

長期保有優遇型の株主優待は魅力的ですが、実際に制度を利用する際には注意すべき点や誤解しやすいポイントがあります。
知らずにうっかり条件を外れてしまうと、「長期保有したのに優待がもらえなかった…」という事態にもなりかねません。
ここでは、長期保有優待を賢く活用するために、ありがちな注意点とその対策を紹介します。
一度売却すると保有年数がリセットされる
多くの企業では、株主名簿に連続して記載されている回数で「長期保有」の判断がされます。
途中で株を売却し、再度買い直した場合は、保有年数がリセットされるケースがほとんどです。
対策:
「使わないから売る」「一時的に資金を引き出す」といった売買は避け、継続保有を前提に投資することが前提となります。
貸株サービスを利用すると“長期認定”されない場合がある
証券会社の「貸株サービス」は、保有株を貸し出すことで金利を得られる仕組みですが、多くの企業では、貸株中は名義上の保有者が変わるため、株主名簿に記載されなくなり、長期保有のカウント対象外となる可能性があります。
対策:
長期保有優待を目的とする場合は、貸株設定を解除しておくことが基本です。自動で貸株される証券会社もあるため、設定を確認しておきましょう。
株主名簿の基準日は“権利確定日”だけではない場合もある
企業によっては「3月末と9月末の両方で継続して名簿記載されていること」など、独自の条件を設定しているケースがあります。
「3年以上保有」と書かれていても、“何回連続で名簿に記載されたか”という形式でカウントされることがあるため、単純なカレンダー年数で判断してはいけません。
対策:
各企業のIRページや優待案内の「長期保有条件の詳細」をしっかり確認しましょう。
複数口座での分散保有はカウント対象外の可能性も
同じ名義であっても、異なる証券口座で保有している株は、企業側で一括して把握できない場合があります。
そのため、合計で100株持っていても、名簿上は50株×2と見なされてしまう可能性も。
対策:
できるだけ1つの証券口座でまとめて保有するのが確実です。
単元未満株(1株〜99株)は優待対象外のことが多い
長期保有戦略として1株投資を活用する人も増えていますが、多くの企業では優待の対象が「100株以上の保有者」に限定されています。
対策:
長期優待を狙うなら、まずは100株を基準に保有するようにしましょう。
長期保有優待は、制度の“表面だけ”を見ると簡単そうに見えますが、裏側には細かいルールや落とし穴が潜んでいます。
よくある疑問Q&A:優待の長期判定はどうされる?貸株はNG?

長期保有優遇型の株主優待は、条件やカウント方法が企業によって異なるため、初心者はもちろん中級者でも混乱することがあります。
ここでは、特に問い合わせや誤解が多い疑問をQ&A形式でまとめて解説します。
Q. どうやって“長期保有”が判定されるの?
A. 株主名簿に「連続して」記載されているかがカギです。
たとえば、「3年以上保有」が条件の場合、3月末や9月末などの基準日ごとに名簿に載っているかどうかが判断材料になります。
途中で株を売って買い直したり、貸株に出して名義が変わると、連続記載が途切れてリセットされる恐れがあります。
Q. 証券会社で株を買った日から年数をカウントするの?
A. いいえ、名簿に記載される“基準日”が起点です。
証券口座内で保有期間が1年以上あっても、企業の基準日に名簿に載っていなければ長期と見なされません。
たとえば、3月末基準の企業であれば、毎年3月末に保有しているかが重要です。
Q. 貸株サービスを使っていると長期保有扱いされないって本当?
A. 多くの場合、事実です。
貸株中は株の名義が証券会社側に移るため、企業の株主名簿にあなたの名前が載らず、「保有していない」と見なされることがあります。
特に長期保有優遇を狙う場合は、貸株サービスの自動設定をオフにしておくのが鉄則です。
Q. 複数の証券会社に分けて100株以上保有している場合は?
A. 長期保有の対象にならない可能性があります。
企業によっては、合算せずに口座ごとの記録として処理するため、どちらの証券会社でも「100株未満」と判断されることがあります。
確実に優待を受けるためには、1つの証券会社にまとめて保有するのが無難です。
Q. 同じ企業の株を途中で売って買い戻したらどうなる?
A. 一度でも売却すると、保有年数はリセットされます。
たとえ再度同じ企業の株を買っても、名簿への記載が途切れた時点で「新規」として扱われます。
長期優待を狙うなら、株価が下がっても“売らない覚悟”が必要です。
Q. 優待にカウントされるのは現物株だけ?つなぎ売りは?
A. 現物株の長期保有が前提です。
つなぎ売りやクロス取引は、短期での優待取得に有効ですが、名簿記載の“連続性”が必要な長期保有優遇には対応していません。
株主優待の世界は一見シンプルに見えて、制度の裏側には緻密な仕組みと条件が存在しています。
長期保有優待の恩恵をしっかり受け取るためには、こうした基本知識を押さえたうえで戦略的に投資を行うことが大切です。
まとめ|じっくり持ってじっくり得する投資を始めよう

株主優待は、「投資=難しい」「お金儲けの手段」というイメージを覆す、生活に役立つリアルなメリットが得られる投資手段です。
なかでも「長期保有優遇型の優待制度」は、単なる“お得”を超えて、投資を通じて企業との関係を築く楽しさや、継続することで生まれるリターンの奥深さを実感できる仕組みです。
長期保有優待の魅力を振り返ると…
- 時間をかけることで優待が“育つ”楽しみがある
- 安定株主として企業から信頼され、報われる仕組み
- 日用品・ポイント・買物券など、日常生活に密着したメリット
- インカムゲイン(配当)+優待で総合的なリターンを実現
短期的な値上がり益を追いかける投資では味わえない、「じっくり持つことで得られる充実感」がそこにはあります。
長く続けられる“堅実な投資スタイル”としておすすめ
初心者にとって、最初の投資はどうしても緊張や不安が付きまとうものです。
しかし、株主優待を目的にすれば、「応援したい企業の株を、生活の一部として持つ」という新しいスタイルの投資ができます。
特に長期保有型の優待は、株価の上下に一喜一憂せず、中長期的な視点で“楽しみながら資産を育てる”投資法として、非常に理にかなっています。
最後に|“優待を育てる”という考え方を持とう
株主優待は、株を買って終わりではありません。
とくに長期優遇制度がある銘柄では、「ただ持ち続けるだけで優待がグレードアップする」という“継続のご褒美”が用意されています。
あなたが日常で利用する企業の株を、数年単位でじっくり保有してみませんか?
配当+優待という着実なリターンを受け取りながら、“持ち続けることが正解になる”投資体験を、ぜひスタートしてみてください。
ちなみにこういった株をスマホで簡単に見つけられる神アプリがあるよ!
>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇
新NISA口座を開設できる証券会社はiDeCo口座も開設できる証券会社が多いです!
>おすすめ新NISAの証券口座が知りたい人は、こちらからご覧ください
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。



