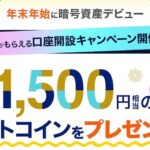※本ページはプロモーションが含まれています。
第1章:暗号資産投資はなぜ今注目されているのか?

2025年現在、暗号資産(仮想通貨)への注目は再び高まりを見せています。
特に投資家や資産運用に関心のある層の間で、「利回りの高さ」や「成長性」に着目した投資先として、ビットコインやイーサリアムといった代表的な暗号資産が再評価されています。
その背景にはいくつかの要因があります。まず、世界的に金利が頭打ちの状況にあり、従来の銀行預金では十分な利息が得られなくなってきています。
日本では依然として低金利が続いており、普通預金や定期預金では年0.01%〜0.2%程度の利息にとどまるのが現状です。
これに対して、暗号資産は「ステーキング」や「レンディング」などを活用することで、年数%〜十数%の利回りを得ることが可能です。
たとえば、2025年初頭のデータでは、イーサリアムのステーキング利回りは年4%前後、ソラナに至っては一時的に年利7%を超える場面も見られました。
これらの数値は、伝統的な資産運用に比べて非常に魅力的です。
また、政府発行の通貨(フィアット)に対する信頼が一部地域で揺らいでいることも、暗号資産の需要を後押ししています。
たとえば、トルコやアルゼンチンなどではインフレにより通貨価値が不安定になり、資産の一部を暗号資産で保有する動きが一般にも広がりつつあります。
さらに、ブロックチェーン技術そのものへの期待も根強く、金融・物流・エンタメ業界など幅広い分野での実用化が進んでいます。
これは、単なる投機対象ではなく、「次世代のインフラ技術」として暗号資産が注目されていることを意味します。
このように、低金利時代における資産形成の手段として、または通貨分散・インフレ対策として、暗号資産は多くの人々にとって魅力的な投資対象となっているのです。
第2章:暗号資産の年平均利回りを徹底比較(2025年版)

2025年現在、主要な暗号資産の年平均利回り(APY:Annual Percentage Yield)は、資産ごとに大きく異なります。
ここでは、投資家がよく利用する暗号資産の利回りを比較し、その仕組みや背景についても詳しく解説します。
主要な暗号資産のステーキング利回り(2025年4月時点)
| 暗号資産名 | 利回り(年率) | ステーキング対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イーサリアム(ETH) | 約4.0〜4.5% | Ethereum 2.0(PoS) | 長期保有向け。ロックアップ期間あり。 |
| ソラナ(SOL) | 約6.5〜7.2% | PoS | ステーキング解除までに数日必要。 |
| カルダノ(ADA) | 約3.5〜4.0% | PoS | ロックフリー型。比較的柔軟。 |
| ポルカドット(DOT) | 約13〜16% | Nominated PoS | 高利回りだが複雑な仕組み。 |
| テゾス(XTZ) | 約5.5〜6.5% | Liquid PoS | 委任型ステーキングが可能。 |
これらの利回りは、単純な保有ではなく「ステーキング」と呼ばれる仕組みを利用することで得られる報酬です。
ステーキングとは、暗号資産を一定期間ブロックチェーン上に預けることで、ネットワークの維持に貢献し、報酬を得る仕組みです。
これは、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)という合意アルゴリズムに基づいており、マイニングとは異なる低コストで環境に優しい方法とされています。
一方、レンディング(貸付)によって利息を得る方法もあります。
たとえば、BinanceやCoinbase、国内ではbitbankなどが提供している「貸暗号資産サービス」を利用すれば、ETHやUSDT(テザー)を貸し出すことで年利3〜10%の利息を得ることが可能です。
ただし、貸し倒れリスクや取引所の信用リスクがあるため、ステーキングに比べてややリスクが高い点に注意が必要です。
>貸暗号資産サービスって何?って思われた方は、こちらもご覧ください👇
利回りとリスクのバランスを見極める
利回りが高いほど魅力的に見える一方で、リスクも比例して高まります。たとえば、ポルカドットのように年利10%以上を提示しているプロジェクトは、ステーキングの仕組みが複雑であったり、価格変動リスクが大きかったりします。また、新興プロジェクトでは利回りが20%を超えることもありますが、詐欺的な案件や rug pull(資金持ち逃げ)といったリスクも存在します。
したがって、利回りだけでなく、「プロジェクトの信頼性」「ロック期間」「リスク分散」なども加味したうえで判断することが、暗号資産投資では非常に重要です。
第3章:暗号資産の利回りを得る4つの方法とは?

暗号資産から利回りを得る方法は、年々多様化しています。単に保有して値上がりを待つだけでなく、「運用して利益を生み出す」という考え方が主流になりつつあります。
ここでは、2025年時点で代表的な4つの運用方法を詳しく解説します。
1. ステーキング(Staking)
ステーキングとは、保有する暗号資産をブロックチェーンネットワークに預けて、ネットワークの運営やブロック生成に貢献することで報酬を得る仕組みです。
これは主にProof of Stake(PoS)型のブロックチェーンで採用されています。
例えば、イーサリアムやソラナ、カルダノなどが代表的です。
利回りは3〜10%程度が一般的で、ステーキング中は資産を自由に動かせない「ロック期間」がある場合もあります。
柔軟性が高いもの(例:カルダノ)もあれば、長期ロックが必要なもの(例:ETH)もあるため、自分の投資スタイルに合った選択が重要です。
2. レンディング(Lending)
レンディングとは、暗号資産を他者に貸し出すことで、利息を得る方法です。
個人間で行うこともありますが、通常は取引所やレンディングプラットフォームを通じて行います。
たとえば、Binance、bitbank、Coincheckなどがこのサービスを提供しています。
レンディングは利回りが比較的高く、USDTやBTC、ETHで5〜10%の利息を得られるケースもあります。
しかし、貸し出し先の信用リスクや取引所自体の経営リスクを考慮する必要があります。
個人的におすすめするレンディングサービスはこちら👇
3. イールドファーミング(Yield Farming)
イールドファーミングは、DeFi(分散型金融)における資産運用の一種で、複数のプロトコルに流動性を提供することで報酬を得る方法です。
資産を「流動性プール」に預け、その対価として手数料やガバナンストークンを受け取ります。
利回りは10%〜数百%と非常に高くなる可能性もありますが、リスクも非常に大きいです。
たとえば、流動性提供に伴う「インパーマネント・ロス(予期せぬ損失)」や、スマートコントラクトの脆弱性、rug pullなどの詐欺的な行為が起こる可能性があります。
経験者向けの手法といえるでしょう。
4. ノード運営やステーキング・プールの管理
これはより上級者向けの方法で、自らがノード(ネットワーク参加者)としてブロックチェーンの運営に関わることで報酬を得る方法です。
また、他者から資金を預かって「ステーキング・プール」を運営することでも利益を得られます。
この方法は技術的な知識が必要で、24時間ノードを稼働させるインフラの維持やセキュリティ対策も求められます。
その分、報酬率は高く、数十%の収益を得ることも可能です。
ただし、誤作動やセキュリティ侵害によってペナルティを受けることもあるため、注意が必要です。
このように、暗号資産の利回りを得る方法にはさまざまな選択肢があります。
それぞれの方法に特有のリスクと報酬構造があるため、投資家は自身のリスク許容度と目的に応じて使い分けることが重要です。
第4章:2025年の注目ステーキング銘柄ベスト5

ステーキングによって安定的な利回りを得る投資家が増える中、どの暗号資産を選ぶかは非常に重要なポイントとなります。
2025年の市場動向と技術的発展、そしてコミュニティの活発さを踏まえ、注目すべきステーキング対象銘柄を5つ厳選して紹介します。
1. イーサリアム(Ethereum:ETH)
2022年にPoSへ完全移行して以来、イーサリアムは最も注目されるステーキング対象資産の1つとなっています。
2025年現在もネットワークの拡張(Dankshardingの実装やL2エコシステムの成熟)により、ETHの需要は高まっています。
ステーキング報酬はネットワーク参加者数や取引量によって変動しますが、平均3〜5%前後。
流動性ステーキング(例:Lido)を活用することで、ETHをロックせずに利回りを得ることも可能です。
2. ソラナ(Solana:SOL)
ソラナは高速な処理能力と低い手数料で注目され、DeFiやNFTのプラットフォームとしても成長を続けています。
2024年にはネットワーク障害の改善が進み、2025年には安定運用が評価されて再注目されています。
ステーキング利回りは6〜8%と比較的高めで、ノード数も分散されており、セキュリティの面でも信頼性が増しています。
3. カルダノ(Cardano:ADA)
カルダノは、科学的アプローチと学術的な開発体制で知られるプロジェクトです。
独自のステーキングシステムにより、資産をロックせずに報酬を得ることができるという大きな特徴があります。
利回りは4〜6%程度で、ADAをダイダロスやヨロイといった公式ウォレットに預けて簡単にステーキングが可能。
コミュニティの熱量も高く、長期ホルダーが多いのも特徴です。
4. アバランチ(Avalanche:AVAX)
アバランチは「サブネット」と呼ばれる独自のスケーリング技術により、高速かつ柔軟なブロックチェーン構築を可能にするプロジェクトです。
2025年には、多くの機関投資家やWeb3企業がアバランチ上にdAppsを展開しています。
ステーキング利回りは約7〜10%と高水準であり、今後のエコシステム拡大によりさらなる需要増が期待されています。
5. セレニティ・チェーン(Serenity Chain:SNC)【新興プロジェクト】
SNCは2024年後半にローンチされた新興ブロックチェーンプロジェクトで、「カーボンニュートラルなブロックチェーン」を掲げており、欧州を中心に注目されています。
まだ知名度は高くないものの、ステーキング報酬が10%以上と高利回りであり、環境対応型のPoSとして関心を集めています。
もちろん新興銘柄ゆえにボラティリティや技術的な不確実性もありますが、ハイリスク・ハイリターンを狙う投資家には面白い選択肢です。
これらの銘柄は、それぞれ異なる強みと将来性を持っています。
利回りだけでなく、プロジェクトの信頼性や開発の継続性にも注目して、ステーキング対象を選ぶことが大切です。
第5章:ステーキングのリスクと注意点

ステーキングは、暗号資産を保有しながら報酬を得られる魅力的な手法ですが、リスクが存在することも忘れてはなりません。
ここでは、ステーキングに関わる主なリスクと、事前に確認しておくべき注意点を詳しく解説します。
1. プロトコルリスク(ネットワークや設計の問題)
ステーキングはPoSブロックチェーンの信頼性に依存しています。
ネットワークのバグやセキュリティ上の問題が発生すると、トークン価格の下落や報酬の減少だけでなく、資産のロック解除が困難になるケースもあります。
特に新興プロジェクトでは、スマートコントラクトの脆弱性やハッキングのリスクも高いため、プロジェクトの開発状況や監査履歴の確認が重要です。
2. トークン価格の変動リスク
たとえ年利5%〜10%のステーキング報酬があっても、保有しているトークン価格がそれ以上に下落すれば、実質的には損失となります。
暗号資産市場は非常にボラティリティが高く、予測が困難であるため、価格変動に対する耐性も考慮すべきです。
3. ロックアップ期間と流動性リスク
多くのステーキングでは、一定期間資産がロックされる「アンボンディング期間」が存在します。
この間はトークンの売却ができないため、市場が急落した際に逃げ遅れる可能性があります。
たとえば、イーサリアムのステーキング解除には最大で数日〜数週間かかる場合があります。
流動性ステーキングを活用すればこのリスクは軽減できますが、代わりに別のリスク(プラットフォーム破綻など)を背負うことになります。
4. カストディ・リスク(第三者による管理)
取引所やステーキングサービスを利用する場合、自分の資産を第三者に預けることになります。
これにより、プラットフォームのハッキングや経営破綻といったリスクが発生します。
信頼できるサービスを選ぶと同時に、自身でノード運用するなど、セルフカストディの選択肢も検討する価値があります。
5. 手数料や報酬分配の仕組み
ステーキングプールに参加する場合、運営者が報酬の一部を手数料として差し引くことが一般的です。
この手数料はプロジェクトやサービスごとに異なるため、実質の利回りがどれくらいになるのかを事前に把握しておくことが大切です。
また、報酬の受け取りタイミングや分配方法が不明確なサービスもあり、トラブルを避けるためには、利用規約をしっかり読むようにしましょう。
ステーキングは「リスクゼロ」の投資手法ではありません。
しかし、これらのリスクを事前に理解し、戦略的に銘柄やサービスを選べば、安定したインカムを得られる有効な手段となります。
第6章:まとめと今後の展望

本記事では、暗号資産におけるステーキングの基本から、実際の方法、利回りや銘柄選び、そして注意すべきリスクまでを体系的に解説してきました。
最後に、これまでのポイントを振り返りつつ、今後のステーキング市場の動向について考察します。
1. ステーキングの魅力
ステーキングは、単に暗号資産を「保有する」だけでなく、「活用して増やす」ことを可能にする仕組みです。
特に、銀行の金利が低迷する中で、年利数%〜十数%の報酬が期待できる点は、大きな魅力となっています。
さらに、分散型金融(DeFi)やWeb3サービスとの連携によって、ステーキングの活用範囲は年々拡大しています。
2. リスク管理の重要性
一方で、価格変動やロックアップ、ハッキングなどのリスクも存在し、盲目的な参加は危険です。
リスクを軽減するためには、次のようなポイントを意識することが重要です:
- トークンの選定:時価総額、プロジェクトの信頼性、ユースケースを確認する。
- プラットフォームの選定:取引所、ウォレット、DeFiプロトコルなどの安全性と実績を比較する。
- 投資額の調整:リスク許容度に応じて分散投資を行う。
3. 今後の展望:「リキッドステーキング」と「マルチチェーン化」
今後のステーキング分野で注目されるのが、「リキッドステーキング」の進化です。
stETHやrETHのようなトークンを介して、ステーキング資産に流動性を持たせることで、より柔軟な運用が可能になります。
また、CosmosやPolkadotなど、異なるブロックチェーンが連携する「マルチチェーン環境」も、ステーキングの新たな活用方法を生み出しています。
複数のチェーンでステーキング報酬を得ることができる仕組みや、クロスチェーンの分散型アプリケーションとの統合が進むことで、さらに高度な戦略的運用が可能になるでしょう。
4. 個人投資家としての心構え
ステーキングは決して「簡単に儲かる手法」ではありません。
しかし、適切な知識と慎重な判断のもとに行えば、長期的な資産形成の一助となります。
特に、今後日本でもWeb3や暗号資産への関心が高まるにつれ、ステーキングが金融リテラシーの一環として認識される時代が来るかもしれません。
初心者の方も、まずは少額から実際に試し、仕組みを体験することが重要です。
ステーキングは、暗号資産の進化とともに成長を続ける分野です。
本記事を通じて、皆さまがステーキングに関する理解を深め、自分に合った投資戦略を見つける一助となれば幸いです。
でも初めて暗号資産はちょっとこわい...
初心者の方であれば、自己資本0でも1,500円分暗号資産をもらえる取引所もあるので、
リスクを最小限に抑えてビットコインを始めたい方は、ビットポイントがおすすめです!
>ビットポイントについては、こちらをご覧ください。