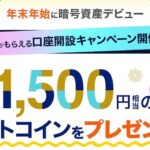第1章 暗号資産の暴落はなぜ起きるのか?市場特性と不安定さの背景を理解しよう

暗号資産(仮想通貨)の市場は、他の金融市場に比べて非常に価格変動が大きく、そのダイナミックな動きが魅力である一方、初心者にとっては大きなリスク要因にもなっています。
特に「暴落」は、短期間で資産価値が大幅に下落する現象で、多くの投資家を不安に陥れます。
まずは、なぜ暗号資産市場ではこのような暴落が繰り返し起きるのか、その根本的な背景を理解することが大切です。
第一に、暗号資産市場は成熟度が低く、参加者の多くが個人投資家で構成されているという特徴があります。
株式市場のような大口機関投資家による安定化が進んでおらず、個人の感情や群集心理によって大きく動きやすい構造です。
一部のニュースやSNSの情報が過剰に反応され、売りが売りを呼ぶ形で連鎖的に暴落が加速するケースも少なくありません。
次に、暗号資産には価値の裏付けが曖昧という特性があります。
ビットコインやイーサリアムのように一定の実用性や技術的基盤があるものでも、国家による法的保証がないため、「価値は市場がつけるもの」とされ、不安材料があると一気に価値が下がる傾向があります。
また、規制リスクも暴落の原因として無視できません。
国によって規制方針が異なり、例えば中国がICOを禁止したり、米国が証券としての扱いを強化したりするたびに、市場は敏感に反応します。
このような不透明な規制環境が投資家の不安を煽り、売却を促進する要因になります。
さらに、取引所のハッキングや破綻などの事件リスクも重要です。
中央集権型の取引所に資産を預けていたユーザーが、突如として出金できなくなるような事態が過去に何度も発生しています。
2022年のFTX破綻は記憶に新しく、信頼されていた大手取引所の崩壊が市場全体にパニックを引き起こしました。
最後に、暗号資産は24時間365日取引が可能という特徴があります。
これにより、株式市場のような休場時間がないため、何か重大なニュースが出た瞬間に一気に売りが殺到し、価格が急変することも日常茶飯事です。
この連続性が、冷静な判断を難しくさせてしまうのです。
このように、暗号資産市場の暴落には様々な要因が複雑に絡み合っています。
初心者の方は、「価格が下がるのは自分のせいではなく、市場の構造的な問題もある」と理解することがまず第一歩です。
その上で、次章からは過去に実際に起きた暴落事例を振り返り、そこから得られる教訓を学んでいきましょう。
第2章 過去に起きた代表的な暗号資産 暴落事例から学ぶ教訓

暗号資産市場では、過去に何度も大規模な暴落が発生してきました。
それらは一見予測不可能に思えるかもしれませんが、振り返ることで「何が起きたのか」「なぜ起きたのか」「どう対応すべきだったのか」といった貴重な学びを得ることができます。
本章では、特に影響が大きかった6つの暴落事例を時系列に沿って紹介し、それぞれの背景と教訓を解説します。
2017年9月:中国のICO禁止と取引所閉鎖による急落
2017年はビットコイン価格が1年で10倍以上に上昇した年でしたが、その裏で最初の大きな警告が鳴らされました。
中国政府が国内におけるICO(新規暗号資産公開)を全面禁止とし、さらに主要な仮想通貨取引所の閉鎖を命じたのです。
これにより、当時中国市場で活発だった取引が一気に冷え込み、ビットコイン価格はわずか3日間で約30%も下落しました。
この事件は、「政府規制が暗号資産市場にどれほどの影響を与えるか」を強く印象づけました。
投資家心理の脆さも明らかになり、制度的な安定性の欠如が価格急落を招く要因となることが示されました。
2018年11月:ビットコインキャッシュのハードフォーク混乱とSECの制裁
2018年は「暗号資産バブル崩壊の年」とも呼ばれますが、11月にはさらに大きな暴落が市場を襲いました。
主な要因は2つあり、ひとつはビットコインキャッシュ(BCH)のハードフォークによる内部対立と分裂騒動、もうひとつは米国証券取引委員会(SEC)が詐欺的ICOに対して制裁を発表したことです。
これらの出来事により市場に不信感が広がり、ビットコインは月間で約40%も下落しました。
この暴落の教訓は、「技術的分裂や規制強化は市場に深刻な不安を与える」という点にあります。
開発者や運営者間の不一致は、暗号資産の信用そのものを損なうことがあるのです。
2020年3月:新型コロナ・パンデミックによる世界的パニック
2020年3月には、WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスの世界的流行を「パンデミック」と宣言したことで、株式・債券・商品と共に暗号資産も一斉に暴落しました。
ビットコインは2日間で80万円台から50万円台へと急落し、他の多くの通貨も軒並み下落しました。
この時は暗号資産の固有リスクというより、「世界的な金融市場の混乱に連動するリスク」が浮き彫りとなりました。
暗号資産は“非中央集権型資産”という特徴がある一方で、市場全体のセンチメントには大きく左右されることが明確になりました。
2021年5月:テスラのビットコイン決済中止とマスク発言ショック
2021年5月、米テスラ社のCEOイーロン・マスク氏がビットコインによる決済を停止すると発表したことで市場に動揺が走りました。
理由は「ビットコインのマイニングが環境に与える影響」に対する懸念であり、発表後すぐにビットコイン価格は約10%下落し、540万円台まで値を下げました。
この出来事は、有名人や企業の発言ひとつで市場が揺れ動くことを象徴する例です。
特に初心者にとっては、「市場のファンダメンタルズだけでなく、ニュースや世論動向も重要な価格変動要因である」と学ぶきっかけとなりました。
2022年5月:USTとLUNAの崩壊によるステーブルコインショック
2022年5月には、アルゴリズム型ステーブルコインであるUST(TerraUSD)の価値が1ドルのペグを維持できず、関連トークンLUNAとともに崩壊するという前代未聞の事件が発生しました。
これにより暗号資産全体が連鎖的に売られ、ビットコインも約515万円から380万円まで下落しました。
この事例では、「技術的な仕組みが破綻した場合、市場全体に波及するリスクがある」という現実を突きつけられました。
特にステーブルコインの信頼性が崩れると、安全資産としての退避先が失われ、投資家心理の不安が一気に拡大するのです。
2022年11月:大手取引所FTXの経営破綻による信用崩壊
同年11月、世界最大級の取引所であるFTXが経営破綻し、数十億ドル規模の顧客資産が凍結される事態となりました。
ビットコイン価格は310万円台から230万円台へと急落し、市場の信用は大きく揺らぎました。
この暴落から得られる最大の教訓は、「いくら大手であっても、中央集権的な管理体制に依存した資産はリスクを伴う」ということです。
資産の保管場所や分散管理の重要性が再確認された事件でした。
過去の暴落はそれぞれ異なる原因によって引き起こされていますが、どれも市場に共通するリスク要因と構造的な課題が浮き彫りになっています。
次章では、こうした教訓を踏まえ、初心者でもできる暴落への備え方について具体的に解説していきます。
第3章 初心者でもできる!暗号資産 暴落に備える6つの安全対策

暗号資産の暴落は避けられない現象ですが、事前にしっかりと備えておくことで被害を最小限に抑えることができます。
ここでは、初心者でも実践しやすい6つの具体的な資産防衛策を紹介します。
これらの対策は、投資の失敗を防ぐだけでなく、暴落を乗り越えるための「投資体質」をつくる基礎になります。
1. 分散投資でリスクを分ける
暗号資産の投資では、ひとつの銘柄に全資金を集中させるのは非常に危険です。
特定の通貨が暴落すれば、それだけで資産全体が大きく目減りしてしまいます。
そこで有効なのが「分散投資」です。たとえば、ビットコインとイーサリアムなどの主力通貨だけでなく、価格変動の小さいステーブルコイン、さらに株式や現金といった伝統的資産もポートフォリオに加えることで、リスクを全体的に抑えることができます。
分散の基本は「値動きの異なる資産を組み合わせる」ことです。
ひとつが下がっても、他でカバーできるような構成にしておくことで、心理的にも安定した投資ができるようになります。
2. ドルコスト平均法で安定的に買い続ける
ドルコスト平均法とは、一定金額を定期的に投資し続ける方法です。
たとえば毎月1万円を決まった日に購入するなど、価格に関係なく機械的に買い増しをすることで、平均取得価格を平準化できます。
特に価格が下がったときにも購入を継続することで、将来の価格回復時により大きな利益を得られる可能性があります。
この方法は、感情的な判断を排除し、長期的な資産形成に向いています。
短期的な値動きに一喜一憂せず、「積立貯金のように暗号資産を買う」という感覚で取り組むことが、初心者にとっての安定投資への第一歩です。
3. ステーブルコインへの一時退避
暴落が始まりそうな兆候を感じた場合、一時的にステーブルコイン(USDT、USDCなど)に資金を避難させるのも有効な戦略です。
これらは価格が米ドルなどの法定通貨と連動しているため、相場全体が不安定なときにも価値を保ちやすいという特性があります。
特に短期的なリスクを回避したい場合、ステーブルコインに資産を移しておくことで冷静に次の投資タイミングをうかがう余裕ができます。
ただし、発行元の破綻や規制リスクもゼロではないため、ステーブルコインも複数種類に分散して保有するのが理想です。
4. 利益確定ルールを事前に決めておく
価格が大きく上昇したとき、つい「もっと上がるかも」と思って売却タイミングを逃してしまうことがあります。
しかし相場は永遠に上昇し続けることはありません。利益が出ているうちに一部を売却して現金化しておくことで、暴落時のショックを和らげることができます。
たとえば、「購入価格から20%上昇したら半分を売る」など、自分なりの利確ルールを事前に設定しておくと、感情に流されず冷静な行動ができます。
これは資産を守るだけでなく、精神的な余裕にもつながります。
5. 損切りルールを徹底する
暗号資産は価格の上昇と同様に下落も激しいため、損失が膨らむ前に撤退する「損切りライン」を明確に決めておくことが重要です。
たとえば「10%以上下落したら売却」といった具体的な基準をあらかじめ設定し、それを厳守することが大切です。
特に短期トレードでは、損切りを躊躇すると被害が拡大し、最終的に大きな損失を抱えてしまいます。
損切りは決して「失敗」ではなく、「リスクを制御するための行動」であるという意識を持つことが重要です。
6. レバレッジ取引を控えめに
暗号資産取引では、証拠金の数倍の取引ができる「レバレッジ取引」が利用可能ですが、暴落時には損失も何倍にも膨らむという大きなリスクがあります。
初心者の場合は、できるだけレバレッジ取引は避け、もし行う場合でも2倍以下の低倍率にとどめ、必ず損切り設定をしておくことが鉄則です。
レバレッジはリスクとリターンの両方を高めるため、資金管理のルールを厳格に守る必要があります。
安全な投資を目指すなら、まずは現物取引で基礎を固めましょう。
これら6つの対策は、暗号資産の暴落に備える「基本のき」とも言える内容です。
事前にルールを決めておけば、暴落が起きても慌てずに行動できるようになります。
次章では、実際に暴落が起きた際にどの銘柄に注目すべきか、将来性が期待される暗号資産を紹介していきます。
第4章 暴落時に注目すべき有望な暗号資産とその理由

暗号資産市場の暴落時、多くの通貨が大きく価格を下げますが、その中でも「回復が早い」「長期的に成長が見込める」銘柄が存在します。
こうした有望な暗号資産は、暴落局面においても投資家の関心を集めやすく、次の相場上昇時のリード役になる可能性があります。
この章では、暴落時に注目すべき代表的な暗号資産を3つ紹介し、それぞれの強みと投資価値について解説します。
ビットコイン(BTC)– 暗号資産の王者、信頼と実績の象徴
ビットコインは2009年に誕生した世界初の暗号資産であり、今なお時価総額ランキング1位を維持し続けています。
その最大の特徴は、分散型かつ発行上限が2,100万枚に設定されているという「デジタルゴールド」としての性質です。
過去の暴落でも、最終的にはビットコインが真っ先に価格を回復し、市場全体をけん引することが多くありました。
特に大口投資家や機関投資家からの信頼も厚く、暴落時には資金の「避難先」として再評価される傾向があります。
また、2025年現在も各国でETF(上場投資信託)や金融商品の基盤資産として採用が進んでおり、その流動性とグローバルな認知度は群を抜いています。
暴落時においても「最も安全性の高い暗号資産」としてのポジションを確保しています。
イーサリアム(ETH)– 実用性と進化を兼ね備えたスマートコントラクトの基盤
イーサリアムは「プログラム可能なお金」とも称され、スマートコントラクトを用いた分散型アプリケーション(DApps)の開発基盤として機能しています。
DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(分散型自律組織)など、多岐にわたる用途があるため、価格に反映される要素もビットコインより多様です。
特に2022年に実施された大型アップグレード「The Merge」により、イーサリアムは環境負荷の大きいPoW(プルーフ・オブ・ワーク)からPoS(プルーフ・オブ・ステーク)に移行し、環境面での評価も高まりました。
これにより、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する機関投資家の関心も集めています。
暴落時でもイーサリアムは技術基盤としての信頼感が強く、活発な開発コミュニティが支えているため、底堅い動きが期待できる銘柄のひとつです。
リップル(XRP)– 実需に支えられた国際送金のインフラ的存在
リップル(XRP)は、主に国際送金の分野に特化した暗号資産です。
リップル社の提供するRippleNetは、世界各国の銀行や決済機関と提携しており、既存の国際送金ネットワークよりも高速かつ低コストで送金を行えるインフラとして注目されています。
特筆すべきは、リップルが「現実社会でのユースケース(実需)」を持っている点です。
例えば、日本のSBIホールディングスなどと連携した実証実験が進んでおり、暗号資産の中でも特に実用性の高いプロジェクトといえます。
2020年以降、米SEC(証券取引委員会)との訴訟問題が価格を押し下げる要因となっていましたが、2023年以降は和解や規制明確化の流れもあり、市場からの信頼回復が進んでいます。
暴落局面では他の通貨と同様に下落しますが、その後の回復力が強い銘柄のひとつです。
その他の注目銘柄にも目を向けよう
2025年現在では、イーサリアムの競合として注目されているSolana(ソラナ)や、スケーラビリティの高いPolygon(ポリゴン)、さらにはバイナンスが提供するBNB(バイナンスコイン)なども市場の信頼を集めています。
これらの銘柄は、それぞれ独自の技術やエコシステムを持っており、特に暴落時に「次の主役候補」として資金が集まることもあります。
ただし、新興銘柄には開発スピードや資金調達の面での不安定要素もあるため、情報の信頼性やプロジェクトの透明性を重視した選別が求められます。
暴落局面は、多くの投資家が不安を抱えるタイミングですが、見方を変えれば「将来性のある銘柄を安く仕込むチャンス」でもあります。
次章では、暴落時に発生しやすい税制上のリスクと注意点について、具体的に解説していきます。
第5章 税制リスクにも注意!暗号資産 暴落時の損益と確定申告のポイント

暗号資産の投資で利益が出た場合はもちろん、暴落によって損失を被った場合でも、税制上の対応を誤ると余計な税負担が発生する恐れがあります。
日本の税法では、暗号資産取引に独特のルールが定められており、それを理解しないままでは「利益が出ていないのに税金がかかる」といった理不尽な状況に陥ることもあり得ます。
本章では、暗号資産の税制における基本的なルールと、暴落時に特に注意すべきポイントを解説します。
暗号資産の利益は「雑所得」として課税される
日本では、暗号資産の売却によって得た利益は雑所得に分類され、総合課税の対象となります。
これは、給与所得や事業所得などと合算されて年間の課税所得額が決定される方式で、所得が増えるほど税率も上がる「累進課税制度」が適用されます。
税率は住民税(10%)を含めると最大55%にも達する可能性があります。
たとえば、年収500万円の会社員が暗号資産取引で100万円の利益を得た場合、600万円の所得に対して税金が課される形になります。
たとえその後に価格が暴落しても、売却時点での利益があれば課税対象となる点に注意が必要です。
含み損は課税対象から除外される
暗号資産の価格が下落しても、保有しているだけでは「損失」として認められません。
つまり、含み損(まだ売却していない状態の損失)は税務上の損益に影響を与えないのです。
たとえば、ある暗号資産を100万円で購入し、その後70万円まで値下がりしたとしても、売却しなければその30万円の損失は「なかったもの」として扱われます。
逆に、含み益のある状態で一部売却した場合には、その利益分に対して税金がかかるため、暴落前に利確した分が翌年の税負担を大きくする可能性があります。
他の所得との損益通算ができない
暗号資産の損失は、給与所得や不動産所得、株式譲渡益などの他の所得と相殺することができません。
これは、雑所得が原則として「他の所得区分とは切り離される」ためです。
たとえ暗号資産で100万円の損失が出ても、給与や株式の利益からその損失を差し引くことはできず、税金を減らす効果は発生しません。
この点は、株式投資と大きく異なる部分であり、投資初心者が誤解しやすいポイントでもあります。
損失の繰越控除が認められていない
株式や先物取引では、損失が出た場合にそれを最大3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できる「損失繰越控除」という制度がありますが、暗号資産にはこの制度が適用されません。
つまり、その年に損失が出たら、翌年以降に持ち越すことはできないというルールです。
たとえば、2025年に100万円の損失が出た場合でも、2026年に利益が出てもその損失を使って税金を軽減することはできません。
これもまた、暗号資産特有の厳しい制度といえるでしょう。
同一年内の損益は相殺可能
一方で、同じ年内で発生した複数の暗号資産取引の損益は相殺が可能です。
たとえば、年の前半にビットコインで50万円の利益を確定させ、年末に別の通貨で50万円の損失を出して売却した場合、結果的に「利益ゼロ」として扱うことができます。
この制度を活用した「タックスロスセリング(節税のための損切り)」も、年末にかけて行われる戦略のひとつです。
ただし、形式的に損失を出して直後に同じ通貨を買い戻すような行為が税務上グレーとされる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
暴落時は取引記録の保存と計算ミスに注意
暴落時には売買が急増するため、取得価格と売却価格の正確な把握が難しくなり、損益計算に誤りが生じるリスクが高まります。
取引所が発行する年間取引報告書や、取引履歴を自動で整理してくれる損益計算ツールを活用して、記録を常に整備しておくことが重要です。
特に、複数の取引所を利用している場合は集計ミスが起きやすいため、Excelやクラウドツールなどで一元管理することをおすすめします。
税金は「利益を守るためのコスト」とも言えますが、制度を正しく理解していなければ、思わぬ損失につながりかねません。
暴落時だからこそ、冷静に制度を理解し、必要に応じて専門家のアドバイスも受けながら対策を講じることが大切です。
次章では、実際に暴落が起きたとき、初心者がパニックにならずに冷静に対応するための行動指針について解説していきます。
第6章 暴落が起きたらどうする?初心者が冷静に取るべき5つの行動
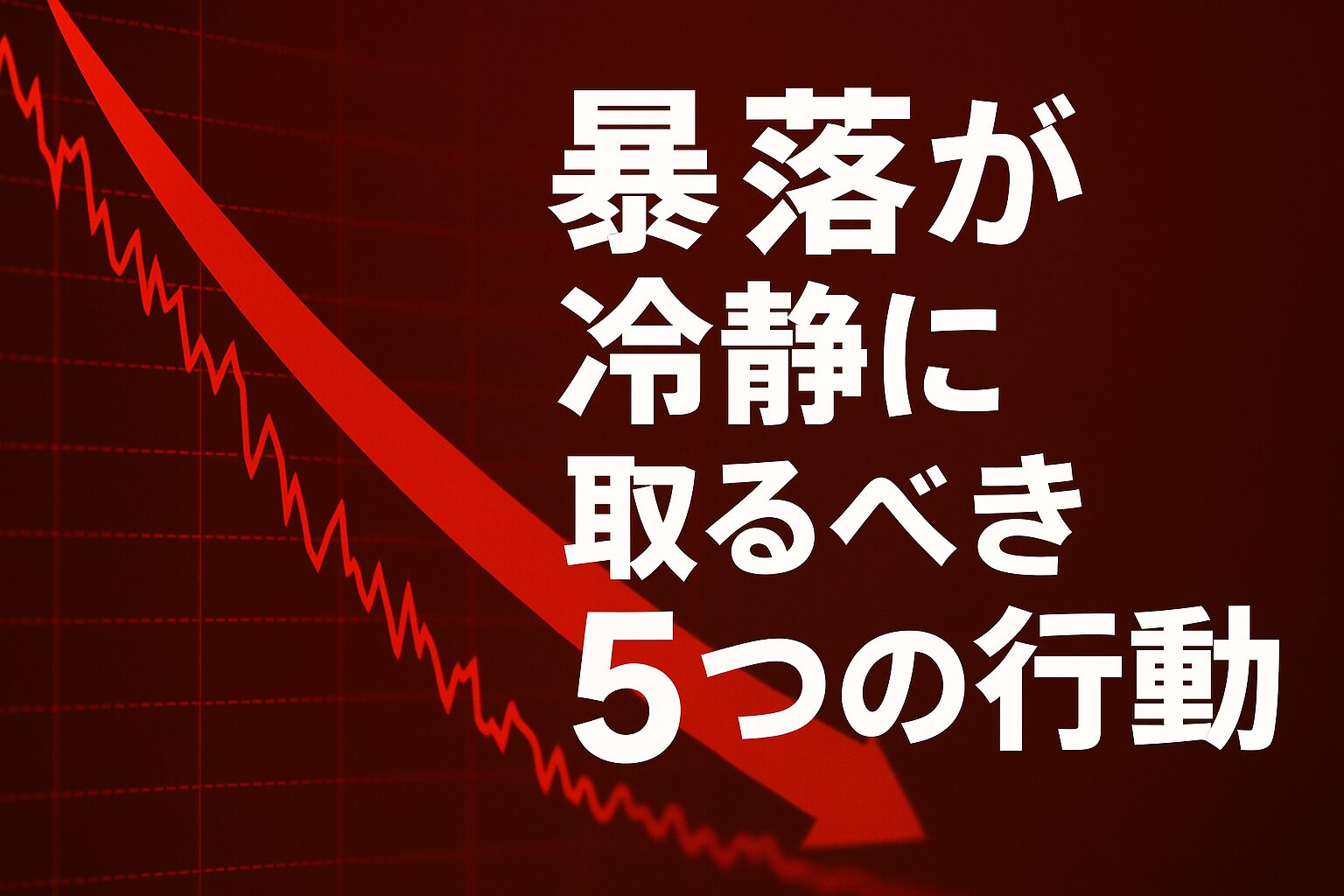
実際に暗号資産の暴落が起きたとき、多くの初心者は恐怖と不安に飲み込まれ、冷静な判断ができなくなりがちです。
しかし、暴落というのは「必ず起きるもの」であり、それを想定しておくことが投資家としての成熟につながります。
この章では、初心者が暴落時に取るべき具体的な5つの行動と、その考え方について詳しく解説します。
1. パニックによる「狼狽売り」を避ける
暴落時に最もやってはいけないのが、感情に流されて資産を売却してしまう「狼狽売り」です。
市場が急落した瞬間に「もうダメだ」と感じ、底値で資産を手放してしまうと、損失が確定するだけでなく、次の回復相場に乗れなくなるという機会損失も生まれます。
歴史的に見ても、暗号資産は幾度も暴落と回復を繰り返してきました。
感情ではなく、「これは一時的な下落か?」「ファンダメンタルズに変化はあるか?」といった視点で状況を捉えることが大切です。
焦って行動するよりも、まずは深呼吸をして冷静さを取り戻すことが最優先です。
2. 信頼できる情報源で状況を確認する
暴落時にはSNSや掲示板を中心に、さまざまな噂や不安を煽る情報が飛び交います。
こうした情報の多くは感情的・断片的で、真偽不明なものも少なくありません。
こうしたノイズに惑わされると、さらに混乱し判断を誤るリスクが高まります。
情報収集の際は、公式な発表、大手取引所の通知、信頼できるメディアやアナリストの解説を優先して確認しましょう。
「なぜ価格が下がっているのか」「本質的な原因は何か」を知ることが、適切な判断材料になります。
3. 暴落の原因を冷静に分析する
価格が急落した背景には必ず理由があります。
ハッキング、規制強化、企業の発言、経済危機など、その要因によって下落の深刻度や回復の見通しも異なります。
たとえば、「一時的なイベントによる売り」であれば、その後の回復が期待できますが、「プロジェクト自体の崩壊」であれば撤退を検討すべきかもしれません。
過去の暴落事例と比較しながら、「今回のケースはどういう位置づけか?」を冷静に分析することで、単なる恐怖ではなく合理的な行動が取れるようになります。
4. 事前に決めた投資ルールを守る
暴落時にもっとも力を発揮するのが、平時に決めたマイルールです。
たとえば「○%下落したら一部売却」「主要銘柄は長期保有を続ける」「積立は継続する」といった明確な戦略がある場合、それに忠実に従うことが肝心です。
感情が高ぶっているときこそ、ルールに基づいた機械的な判断が重要になります。
特に初心者は、事前に「どのような相場になっても続ける基本方針」を持っておくことで、いざという時にも迷わず行動できます。
5. 相場から一時的に距離を置く勇気も必要
暴落時はチャートを何度も見てしまい、気持ちが落ち着かなくなることが多いですが、過剰なチェックは逆効果になる場合があります。
特に、行動を起こす明確な基準がないままチャートを追い続けると、不安や焦りが増し、冷静な判断を妨げてしまいます。
そんなときは、あえて数時間〜1日程度相場を見ないという選択肢も有効です。
ストップロス(損切り注文)やアラート設定を活用して、一定の基準までは静観するという姿勢を持ちましょう。
心理的に余裕を保つことも、長期的に資産を守る上では重要なスキルです。
暗号資産の暴落は、どんな投資家にとっても避けて通れない試練です。
しかし、恐怖に支配されず冷静に行動することで、それを乗り越えるだけでなく、次のチャンスをつかむ準備にもなります。
次章では、暴落が終わった後にどのような視点を持ち、どう市場と向き合っていくべきかを前向きに考察していきます。
第7章 暗号資産の暴落は終わりではない!次の成長期に備えるための思考法

暗号資産市場における暴落は、決して「終わり」ではありません。むしろ、新たな成長サイクルの始まりであることが多いのです。
長期的に資産形成を考える上で、暴落時の行動だけでなく、その後の心構えや準備も極めて重要です。
本章では、暴落を乗り越えた先に待つチャンスを見据えて、どのような視点と戦略を持つべきかを解説します。
市場サイクルは繰り返される
暗号資産市場はこれまで、バブル的な上昇と大きな暴落を何度も繰り返してきました。
例えば、2017年末のビットコイン急騰と2018年の暴落、2020年末からの再上昇、そして2022年の大崩落など、市場は「上がっては下がり、また上がる」という波を描きながら成長してきました。
このような市場サイクルを理解していれば、暴落も「一時的な調整」や「健康的な市場の再構築」と捉えることができます。
過去のデータを振り返れば、暴落の後に大きな成長期が訪れていることが多く、それを待つ姿勢もまた立派な投資戦略です。
チャンスは「恐怖の中」にある
有名な投資の格言に、「人々が恐れているときに買い、強欲になっているときに売れ」という言葉があります。
暗号資産の暴落時こそ、資産価格が大きく割安になり、将来的なリターンが大きくなる可能性があるのです。
もちろん、ただ闇雲に買い増せばよいというわけではありませんが、「暴落=終わり」と思い込むのではなく、「暴落=準備のタイミング」と前向きに捉える思考法が、長期的な成功に近づく鍵となります。
情報収集と学びを継続する
暴落を経験したあとこそ、その原因や市場の変化を深く理解するチャンスです。
ただ価格を見るだけでなく、技術の進化、法規制の動向、プロジェクトの進展、開発者コミュニティの声など、より本質的な情報に目を向ける習慣を身につけましょう。
この「情報リテラシー」は、暴落からの回復局面や次の投資判断において大きな武器になります。
また、自分なりに記録をつけておくことで、次回の暴落時に冷静な判断がしやすくなります。
自分だけの投資哲学を持つ
短期的な値動きに一喜一憂せず、「なぜ自分はこの通貨に投資するのか」「どのような視点で長期的に資産を育てていくのか」といった、自分なりの投資哲学やビジョンを明確に持つことが大切です。
暴落を乗り越えるには、他人の意見ではなく、自分の価値観に基づいた意思決定が不可欠です。
そのためにも、日々の学びと経験を通じて「投資家としての軸」を築いていきましょう。
行動と反省を繰り返し、未来に備える
暴落を経験した際には、自分の取った行動を振り返り、何が良くて何が反省点だったのかを記録しておくことをおすすめします。
これにより、次の相場でより良い判断ができるようになり、着実にスキルと自信を積み上げていくことができます。
たとえば、「あのときパニック売りしてしまった」「損切りルールを守れなかった」など、実際の行動を分析することで、次回の暴落時には一段冷静に対応できるはずです。
まとめ:暴落は通過点、学びと成長のチャンス
暗号資産の暴落は恐怖と混乱をもたらしますが、それは同時に「市場に残る本物の投資家を選別する試練」でもあります。
冷静さと準備、そして前向きな視点を持ち続けることで、暴落を「投資人生の転機」として活かすことができるのです。
これまで解説してきた内容を実践しながら、暗号資産投資における心構えと行動力を磨き、次の成長期を迎える準備をしていきましょう。
この機会にぜひ仮想通貨を始めてみてください!
初心者の方であれば、自己資本0でも1,500円もらえる取引所もあるので、
リスクを最小限に抑えてビットコインを始めたい方は、ビットポイントもおすすめです!
>ビットポイントについては、こちらをご覧ください。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。