※本ページはプロモーションが含まれています。
第一章 退職給付金とは何かを正しく理解する
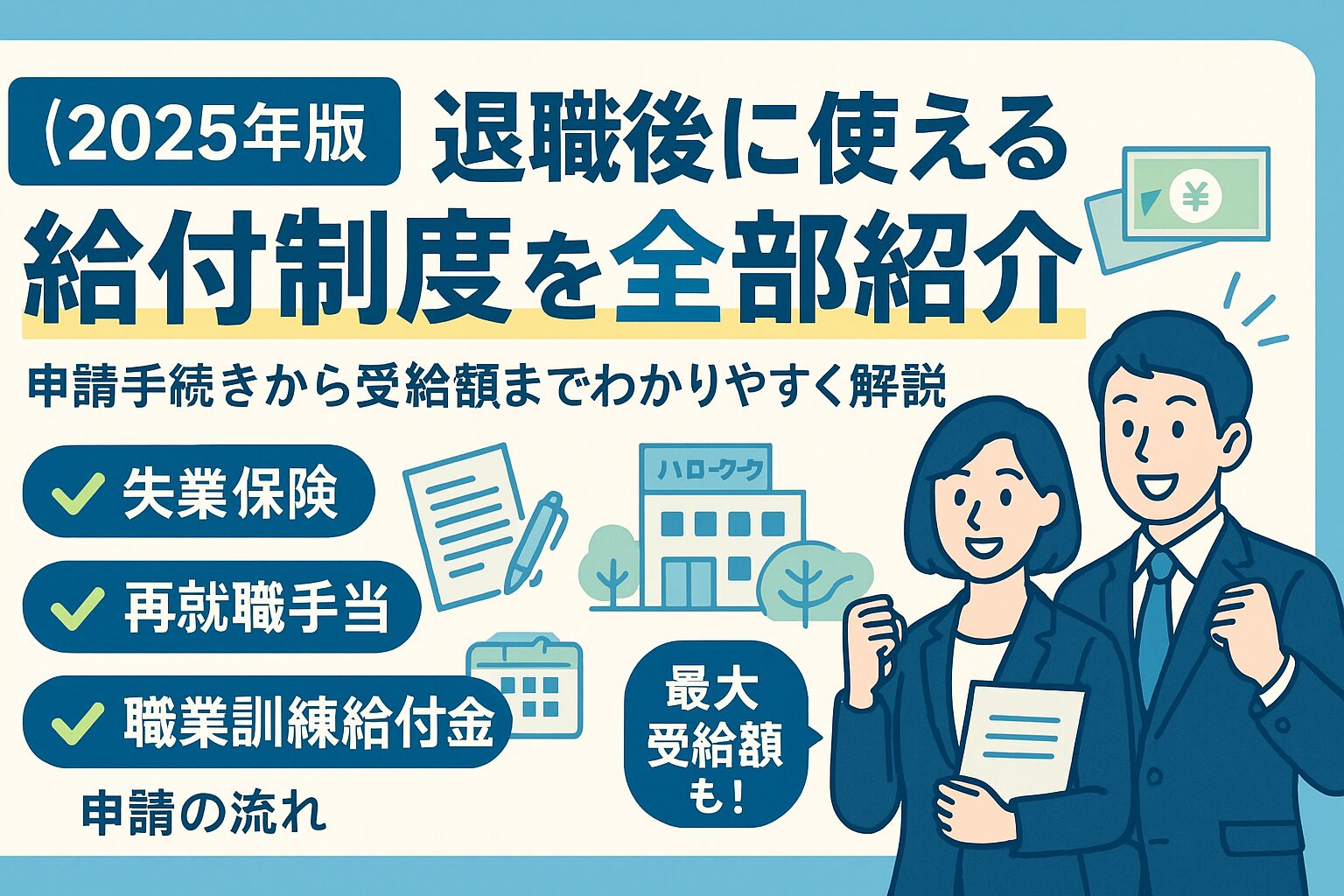
退職給付金とは、労働者が退職した際に受け取ることができる金銭的給付の総称です。
これは退職金や企業年金といった会社独自の制度だけでなく、雇用保険や健康保険など公的制度から支給される給付も含まれます。
つまり「退職後にもらえるお金」の全体像を指す広い概念です。
まずはこちらをご覧ください👇
一般的に退職給付金は、次の三つの大きな柱に分類できます。
- 雇用保険から支給される失業給付
退職後にハローワークで手続きを行い、一定の条件を満たすことで支給されます。
基本手当を中心に、早期に再就職した場合は再就職手当を受け取れる仕組みもあります。 - 企業から支給される退職金や企業年金
勤務先の就業規則や退職金規程に基づいて支払われるもので、金額は勤続年数や退職理由によって大きく変わります。
企業型確定拠出年金や確定給付企業年金が組み合わされるケースも増えています。 - 健康保険や年金制度による給付
退職後も病気やけがで働けない場合に継続して支給される傷病手当金、国民健康保険や任意継続制度による医療保障、そして外国籍の方に認められる脱退一時金などが該当します。
退職給付金は生活の安定を支える大切な資金源であり、制度ごとに申請の期限や条件が厳格に定められています。
受給漏れを防ぐためには、それぞれの仕組みを正しく理解し、必要な手続きを退職直後から計画的に進めることが欠かせません。
👉 次章では、退職給付金の中でも中心的な制度である「失業給付」の仕組みと受給条件について、時系列で詳しく解説していきます。
第二章 失業給付の仕組みと受給条件
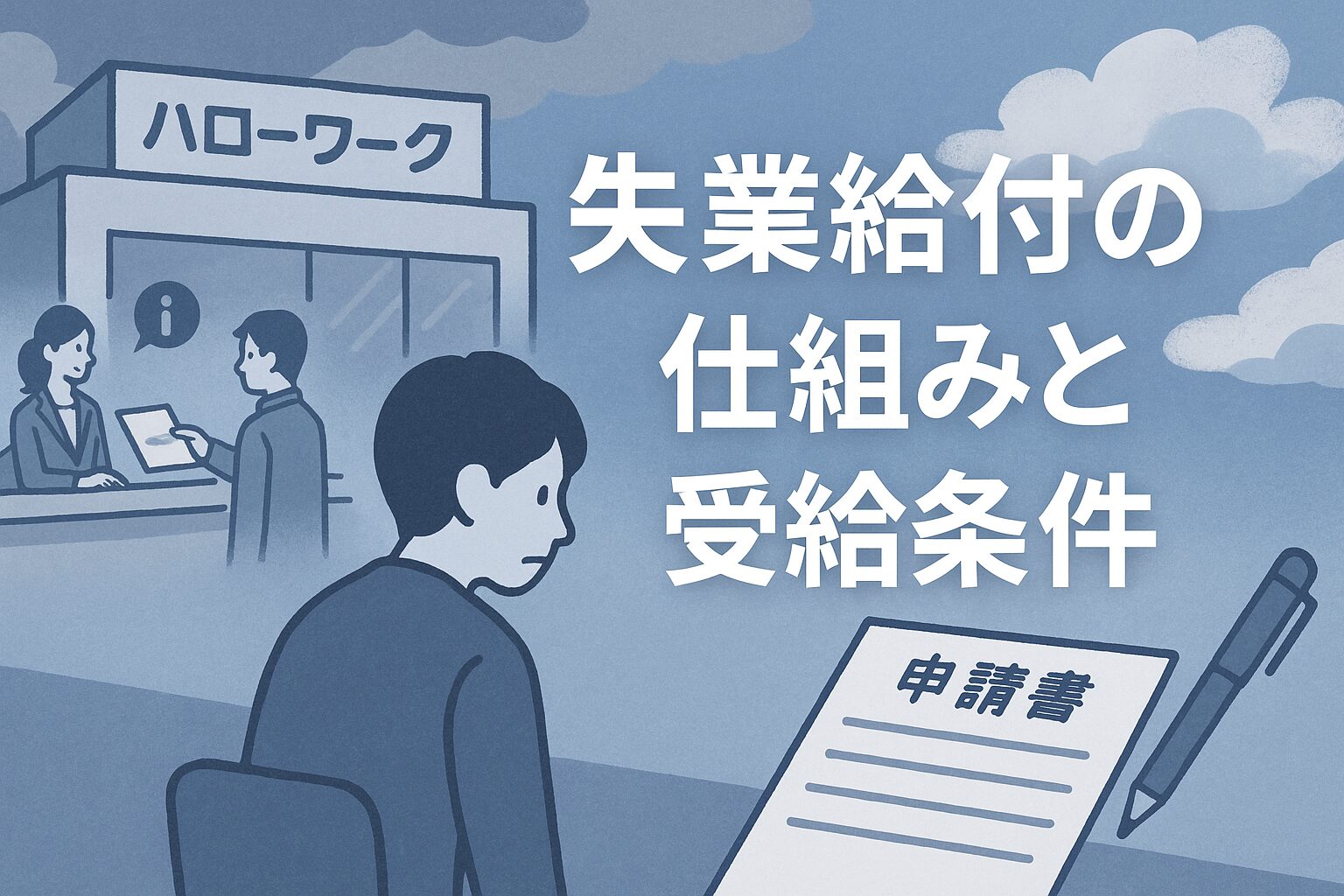
退職給付金の中でも中心的な存在が、雇用保険から支給される失業給付です。
これは、退職後に再就職活動を行う人の生活を支える制度であり、正しく理解することが重要です。
まずはこちらをご覧ください👇
失業給付を受けられる人の条件
失業給付は「働く意思と能力があるが、仕事が見つからない状態」にあることが前提です。
そのため、自ら進んで働く意思がない場合や病気・けがで働けない場合は対象外となります。
また、受給資格は退職日までに一定期間の雇用保険加入が必要で、原則として直近2年間で12か月以上の被保険者期間が求められます。
待機期間と給付制限
手続きを行ったとしても、すぐに給付金が支給されるわけではありません。
まず一律で7日間の待機期間があります。この間に働いて収入を得た場合は待機が成立せず、改めてやり直しになります。
さらに、自己都合退職の場合は追加で1か月の給付制限が設けられています。
一方、会社都合による退職であれば、この給付制限は発生せず、待機期間後すぐに支給対象となります。
所定給付日数
失業給付の支給日数は、退職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間によって決まります。
一般的には90日から150日程度が多いですが、長期勤続や高齢者、会社都合による離職の場合は最長330日まで延長されることもあります。
自分がどの区分に該当するかを把握することが、計画的な生活設計につながります。
手続きの流れ
失業給付を受けるには、退職後にハローワークで求職申込みと受給資格の確認を行います。
その際に離職票や本人確認書類、写真、印鑑、通帳などが必要です。
初回認定日には説明会が行われ、その後、4週間ごとの失業認定日に出席して求職活動実績を提出することで、給付が継続されます。
👉 次章では、失業給付の金額の計算方法や、実際にどれくらい受け取れるのかを具体的に解説していきます。
第三章 失業給付の金額と計算方法
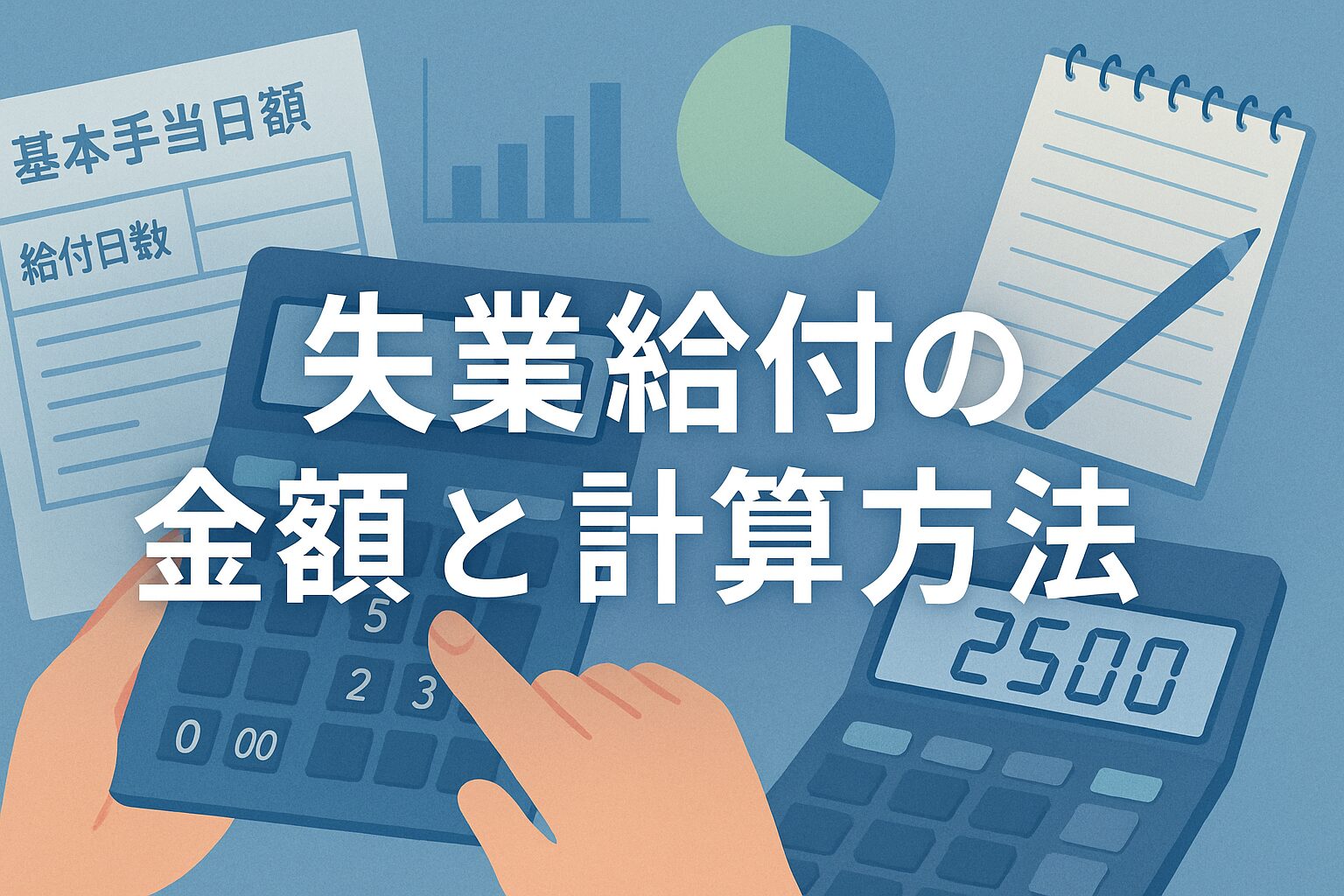
退職給付金の中心である失業給付は「いくらもらえるのか」が最も気になる点です。
給付額は人によって異なりますが、基本的な仕組みを理解すれば自分のおおよその受給額を把握できます。
基本手当日額の計算方法
失業給付の中心は「基本手当日額」です。
これは退職前6か月間の賃金総額を180で割り、その50%〜80%が基準となります。
賃金が低い人ほど高い給付率が適用され、逆に賃金が高い人は給付率が下がる仕組みです。
さらに、年齢区分ごとに上限額が設けられており、どんなに高い給与であっても支給額には限度があります。
所定給付日数との関係
実際の受給額は「基本手当日額×所定給付日数」で決まります。
所定給付日数は退職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって変わり、最短90日から最長330日まで幅があります。
例えば、自己都合退職で勤続10年未満の場合は90日、会社都合で勤続20年以上の45歳なら330日といった具合に大きな差が生じます。
計算例
仮に退職前6か月の賃金総額が180万円(1か月30万円)だった場合、1日あたりの賃金日額は1万円です。
この場合、給付率が60%とすると基本手当日額は6,000円となります。
所定給付日数が90日であれば、総額は54万円が目安となります。
もちろん実際には年齢や上限額が反映されるため、必ずハローワークで確認することが大切です。
正確な額を知るためのポイント
制度には上限・下限があり、また退職理由によっても条件が異なるため、計算はあくまで目安にすぎません。
正確な金額を知りたい場合は、離職票を持ってハローワークで試算してもらうことが最も確実です。
特に再就職手当や就業促進給付を考慮すると、実際に手にする額は大きく変動します。
👉 次章では、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」について、支給条件や受給額の目安を解説します。
第四章 早期再就職で受け取れる再就職手当

失業給付には、早期に再就職が決まった人に支給される「再就職手当」という制度があります。
これは失業状態が長引かないように支援するための仕組みであり、正しく理解すれば退職後の収入を大きく増やすことができます。
再就職手当の支給条件
再就職手当を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
- 受給資格決定を受けてから7日間の待機期間を満了していること
- 失業給付の所定給付日数が3分の1以上残っている時点で再就職すること
- 安定した雇用に就くこと(1年以上の雇用見込みがあること)
- 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
支給額の計算方法
再就職手当は「基本手当日額×残日数」に一定の割合をかけて計算されます。
- 所定給付日数の3分の2以上残して就職した場合 → 70%
- 所定給付日数の3分の1以上残して就職した場合 → 60%
例えば、基本手当日額が6,000円、残日数が100日あった場合、3分の2以上残して就職すれば「6,000円×100日×70%=42万円」が支給されます。
就業促進定着手当
再就職してから6か月以上働き続けた場合には「就業促進定着手当」が追加で支給されることがあります。
これは、再就職先での賃金が離職前に比べて低下した場合に差額を補う制度で、再就職後の生活安定をサポートします。
手続きの流れ
再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告し、再就職手当の申請書を提出する必要があります。
申請には雇用契約書や採用通知など、雇用の安定を証明できる書類が必要です。
申請が遅れると支給対象外となる場合があるため、必ず早めに手続きを行うことが大切です。
👉 次章では、企業から支払われる退職金と、その税金の仕組みについて詳しく解説していきます。
第五章 退職金と税金の仕組み
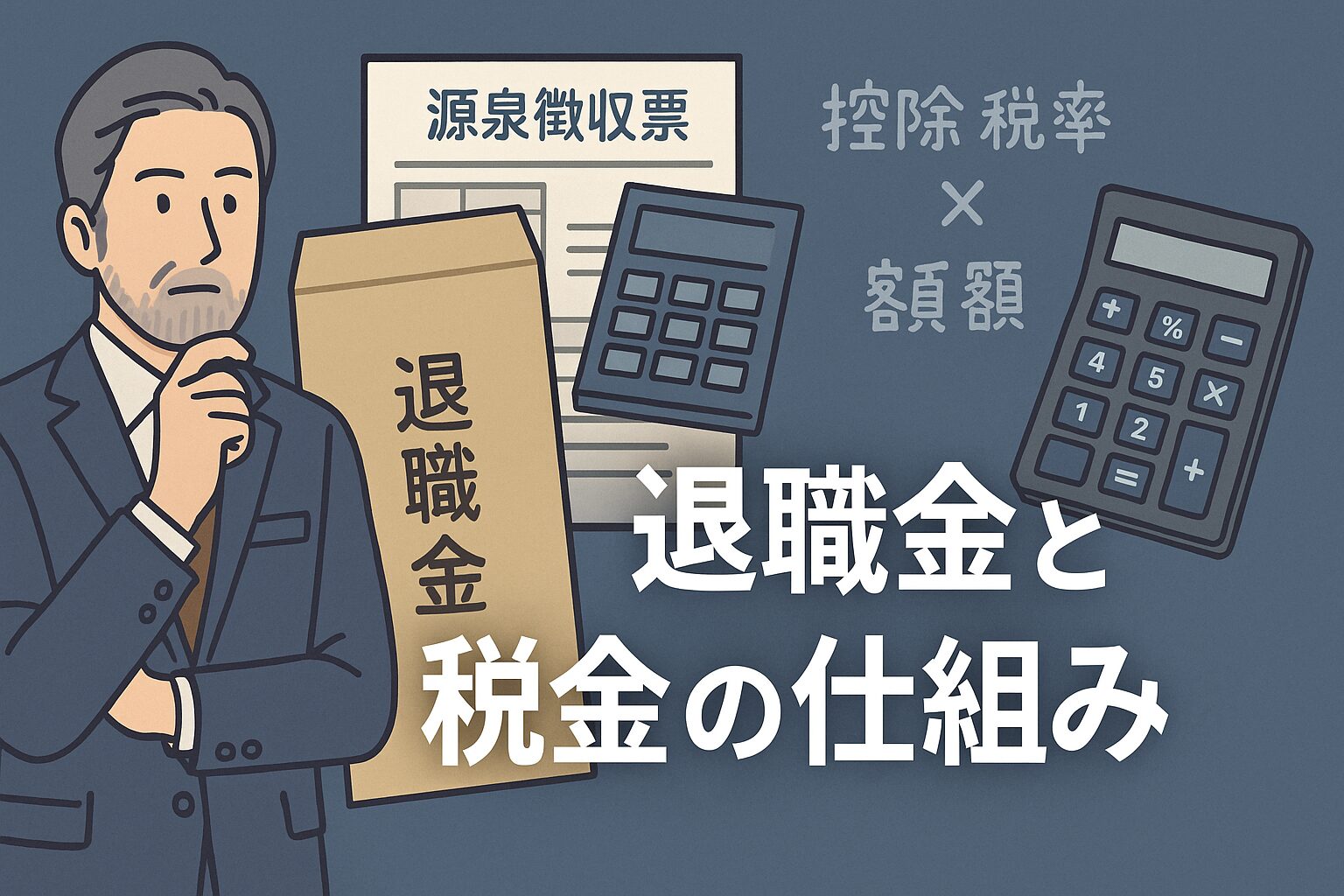
退職給付金の中でも大きな割合を占めるのが「退職金」です。
退職金は企業が独自に用意する制度であり、勤続年数や退職理由によって金額が変わります。
ここでは退職金にかかる税金の仕組みを整理します。
退職所得控除の考え方
退職金には「退職所得控除」という特別な制度があり、勤続年数に応じて大きな非課税枠が設けられています。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
例えば勤続25年の場合、控除額は800万円+70万円×5年=1150万円となります。
退職金がこの金額以下であれば課税対象にはなりません。
課税対象額の計算式
退職金の課税対象額は次の計算式で算出されます。
(退職金 − 退職所得控除)÷2
この「÷2」が大きな特徴であり、実際の課税額はさらに軽減されます。
つまり、同じ金額の給与と比べても退職金にかかる税負担は大幅に少なくなる仕組みです。
源泉徴収と確定申告
退職金は会社が支給時に源泉徴収を行います。
その際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、ほとんどの場合は源泉徴収で課税が完結し、確定申告を行う必要はありません。
ただし申告書を提出しなかった場合は、一律で高い税率で源泉徴収され、後で確定申告による精算が必要になります。
退職理由による差異
会社都合での退職や障害者となった場合には、さらに優遇措置があり、控除額が増えるケースもあります。
逆に自己都合退職の場合でも制度の基本は同じですが、企業の規程によって支給額が減額される場合があるため注意が必要です。
👉 次章では、退職後も継続して受け取れる可能性がある「傷病手当金」について、条件や申請方法を詳しく解説していきます。
第六章 傷病手当金を退職後も受け取るための条件

退職後に病気やけがで働けない場合、健康保険から「傷病手当金」を継続して受け取れる可能性があります。
生活を支える大切な給付の一つなので、条件を正しく理解しておくことが重要です。
支給を受けられる基本条件
退職後に傷病手当金を継続して受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 退職前に1年以上、同じ健康保険に継続して加入していたこと
- 退職日に出勤していないこと(有給消化中や欠勤中であることが求められる)
- 退職時点ですでに病気やけがで就労不能であること
- 医師による就労不能の証明があること
支給される金額
傷病手当金の金額は「退職前12か月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」で算出されます。
給与収入が途絶えても、一定期間は生活費を補うことができる仕組みです。
支給期間は最長で1年6か月とされており、退職後も継続されます。
他制度との調整
傷病手当金は他の給付と同時に受け取ることができない場合があります。
特に、老齢年金や障害年金などと重複する場合には、支給額が減額されるか不支給となるケースがあるため注意が必要です。
失業給付との同時受給もできないため、どちらを優先するか判断しなければなりません。
申請手続き
申請には、退職前の会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」、医師の診断書、本人確認書類などが必要です。
申請先は退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽです。
退職後は自分で申請を行う必要があるため、手続きの漏れに注意してください。
👉 次章では、退職後に選択する必要がある「健康保険の継続方法」について、任意継続・国民健康保険・扶養の比較を詳しく解説していきます。
第七章 退職後の健康保険の選び方
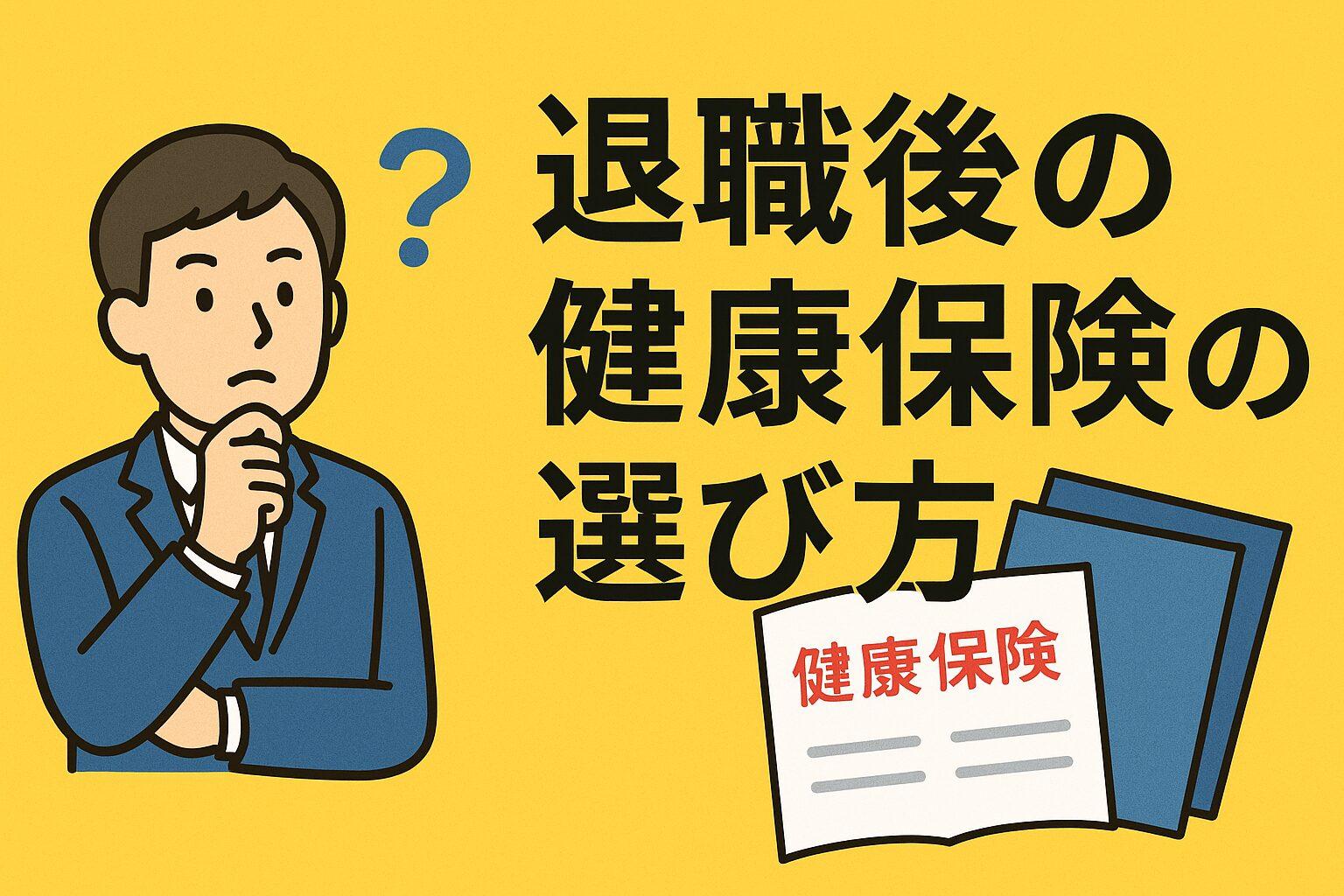
退職すると会社の健康保険の資格を失い、新しい制度に加入する必要があります。
大きく分けて「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」という三つの選択肢があります。
それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
任意継続被保険者制度
任意継続は、退職前に会社の健康保険に2か月以上加入していた人が対象です。
退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があり、期限を過ぎると加入できません。
保険料は全額自己負担になりますが、現役時代と同じ医療保障を2年間継続できるメリットがあります。
特に医療費がかかる予定がある人や家族の人数が多い人に適しています。
国民健康保険
国民健康保険は市区町村が運営する制度で、退職後の多くの人が加入する一般的な選択肢です。
保険料は前年の所得に応じて算出され、扶養という概念がないため家族ごとに計算されます。
ただし、非自発的失業(会社都合や倒産など)の場合は軽減措置が適用されるケースがあります。
保険料の見積もりは各自治体に確認する必要があります。
家族の扶養に入る
配偶者など家族が会社員として健康保険に加入している場合、その扶養に入る方法もあります。
収入要件を満たしていれば、追加の保険料負担なしで医療保障を受けられるため、最も経済的な選択肢となります。
ただし、扶養に入れるかどうかは収入基準や就労状況によって判断されるため、事前に確認が必要です。
比較と選び方のポイント
- 医療費の予定が多い → 任意継続
- 所得が少なく軽減措置を利用できる → 国民健康保険
- 配偶者の扶養に入れる → 家族の扶養
自分や家族の健康状態、今後の収入見込みを踏まえて、もっとも負担の少ない制度を選ぶことが大切です。
👉 次章では、60歳以降の人が対象となる「高年齢雇用継続給付」やその他の給付制度について解説します。
第八章 高年齢雇用継続給付とその他の制度
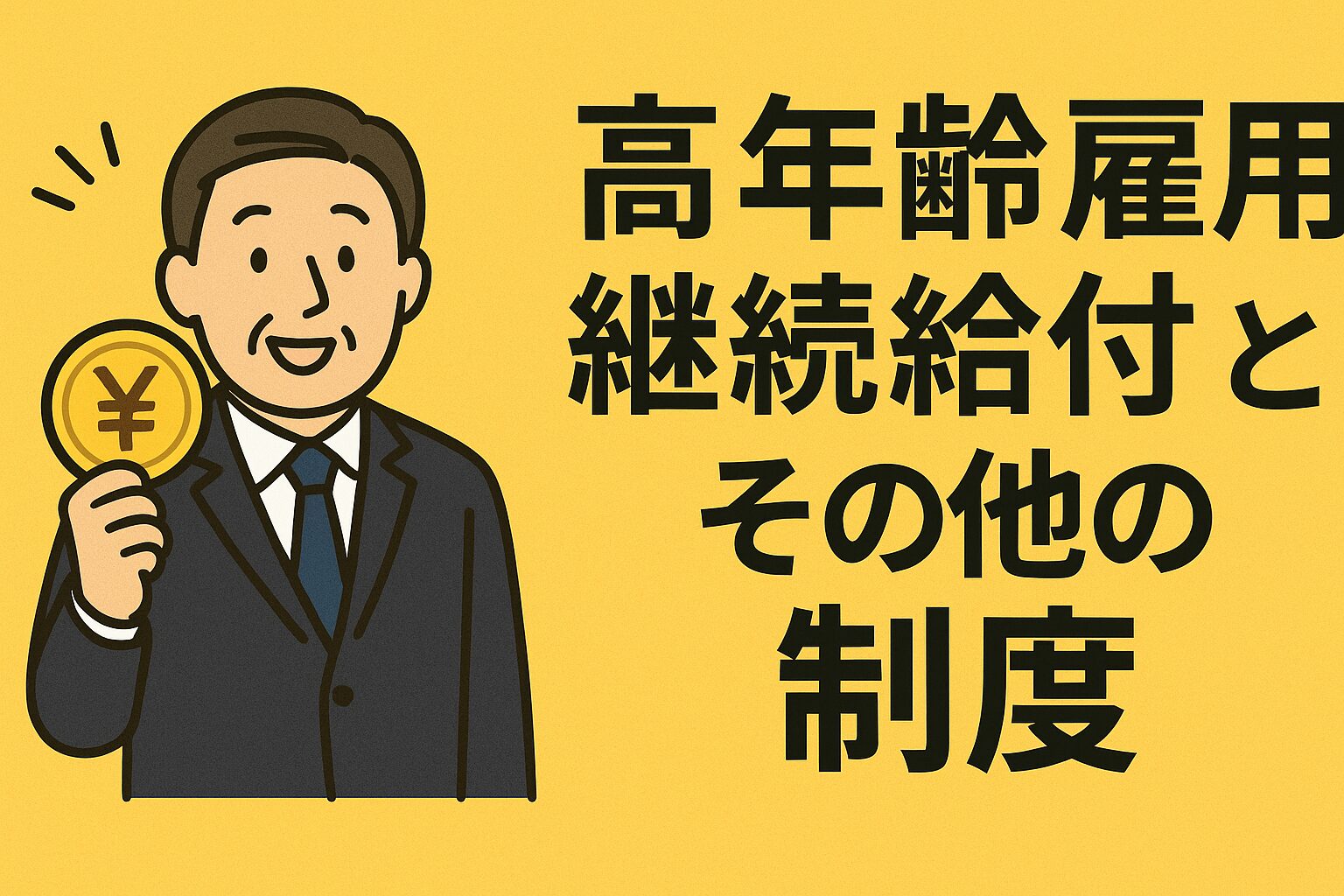
退職給付金とあわせて押さえておきたいのが、60歳以降の人を対象とした高年齢向けの給付制度です。
特に定年後も働き続ける人にとっては重要な収入の一部となります。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの間に賃金が大きく下がった場合に支給される制度です。
支給条件は以下の通りです。
- 雇用保険に5年以上加入していること
- 60歳以降も同じ事業所で雇用が継続されていること
- 60歳到達時点の賃金に比べて75%未満に下がっていること
支給額は賃金の低下率に応じて算定され、最大で賃金の15%程度が補填されます。
これにより、定年後に収入が減っても生活を安定させやすくなります。
高年齢再就職給付
定年前に退職し、新たに60歳以降で再就職した場合には「高年齢再就職給付」が対象となるケースもあります。
こちらも雇用保険の加入歴や賃金低下率が条件となり、60歳以降の再雇用者を支援する仕組みです。
外国籍労働者の脱退一時金
外国籍の労働者が日本の年金制度に加入していた場合、帰国時に「脱退一時金」を請求できることがあります。
これは国民年金・厚生年金に一定期間以上加入していた場合に支給され、申請期限は帰国から2年以内と定められています。
その他の関連制度
- 教育訓練給付金:新しいスキル習得のために指定講座を受講した際に費用の一部が支給される制度
- 求職者支援制度:失業給付を受けられない人が対象となる生活支援と職業訓練を組み合わせた仕組み
これらの制度を組み合わせることで、退職後の資金計画やキャリア形成をより安定させることができます。
👉 次章では、退職後にすぐ行うべき「7日間の行動計画リスト」を提示し、手続き漏れを防ぐための実践的なアクションを整理します。
第九章 退職後7日間の行動計画リスト
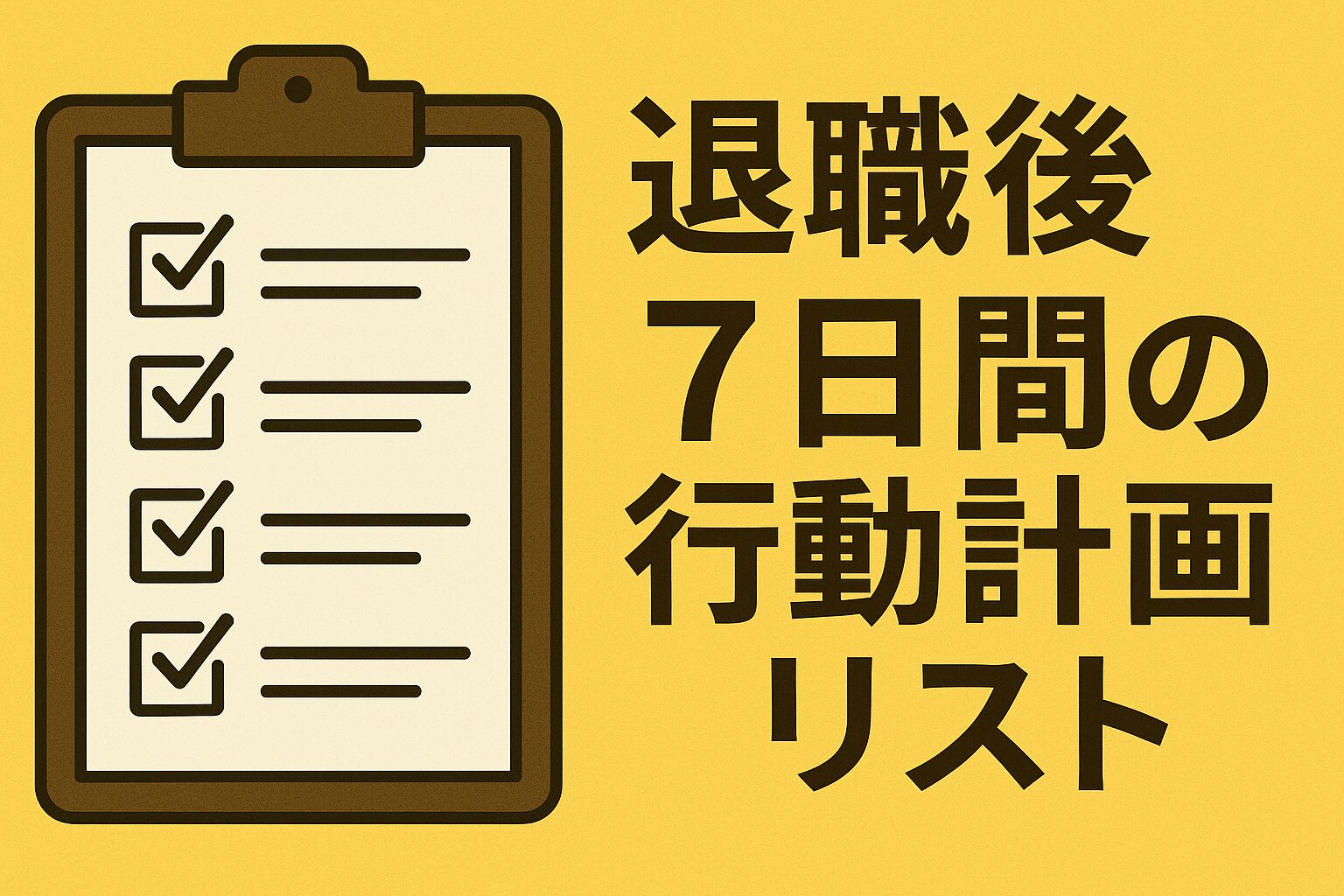
退職後は複数の給付金や制度を利用できますが、それぞれ申請期限や手続きの順序があります。
ここでは「退職直後の7日間でやるべきこと」を整理し、手続き漏れを防ぐための行動計画を提示します。
Day0(退職日までに準備しておくこと)
- 離職票や雇用保険被保険者証を会社から受け取る
- 退職金の源泉徴収票や退職所得申告書を確認
- 健康保険証を返却し、資格喪失日を把握
Day1〜Day3(失業給付の申請開始)
- ハローワークに行き、求職の申込みを行う
- 離職票、本人確認書類、証明写真、印鑑、通帳を提出
- 受給資格決定を受け、7日間の待機期間がスタート
- 初回説明会や認定日の案内を確認
Day4〜Day5(健康保険の手続き)
- 任意継続に加入する場合は、資格喪失日から20日以内に申請
- 国民健康保険に加入する場合は市区町村役所で手続きを行う
- 扶養に入る場合は配偶者の勤務先へ書類を提出
Day6(その他給付制度の確認)
- 傷病手当金を継続受給できる場合は、健康保険組合に必要書類を提出
- 外国籍の場合は脱退一時金の要件を確認し、帰国時に備えて資料を整理
Day7(全体のチェックと今後の計画)
- 提出書類の控えを整理し、次回認定日をカレンダーに記録
- 再就職手当を受けられる条件を確認し、転職活動の計画を立てる
- 教育訓練給付金や求職者支援制度など、追加で活用できる制度を調査
👉 次章では、退職給付金に関する「よくある質問と回答」をまとめ、読者が疑問をすぐに解消できるよう整理していきます。
第十章 退職給付金に関するよくある質問
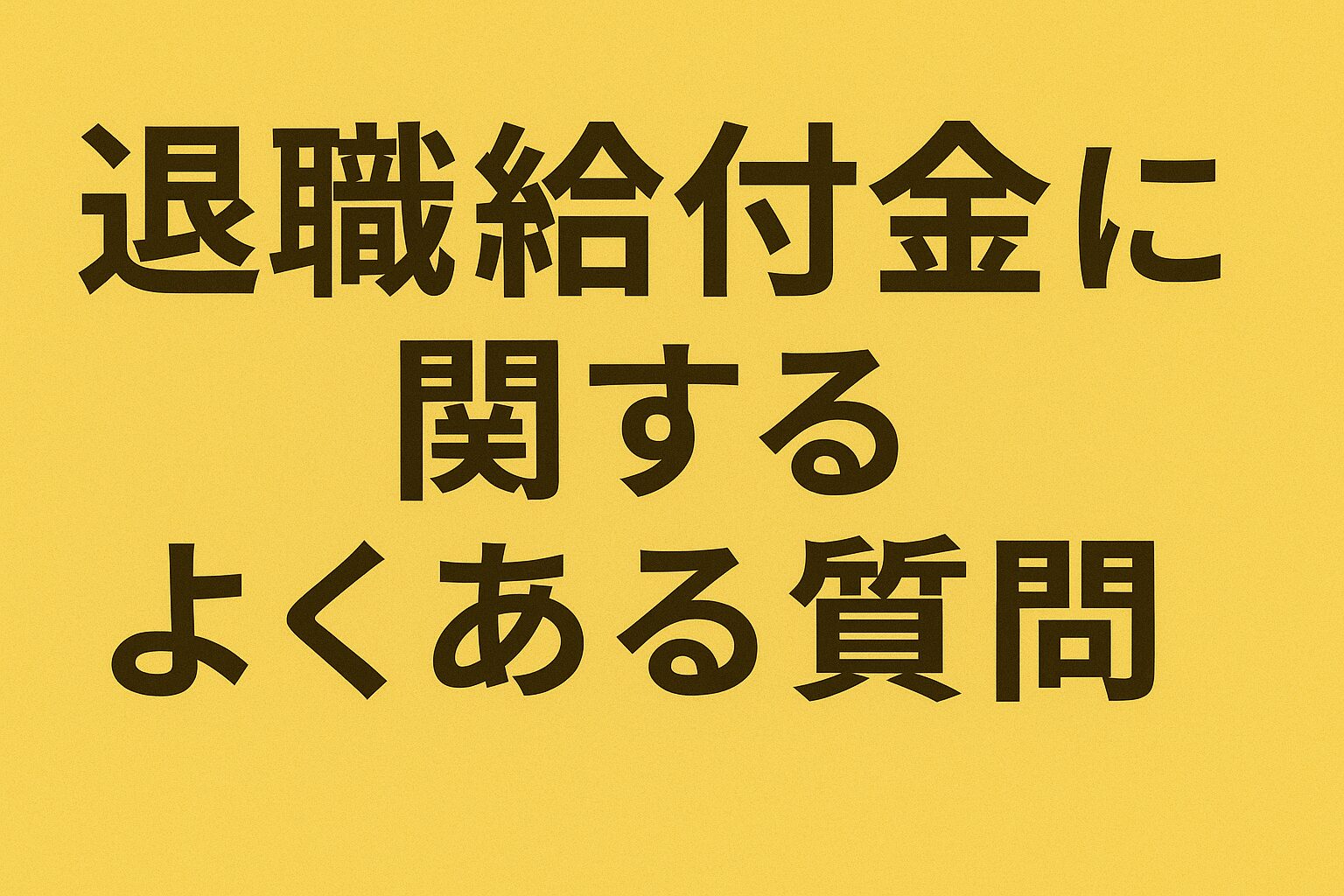
退職給付金は制度が複雑で、退職後に不安や疑問を抱く人が多い分野です。
ここでは、よく寄せられる質問を整理し、正確な回答を提示します。
自己都合退職でも失業給付はもらえますか
はい、自己都合退職でも失業給付を受けられます。
ただし7日間の待機期間に加えて、1か月の給付制限があるため、実際に支給が始まるまでに時間がかかります。
会社都合や倒産などの場合は給付制限がなく、待機後すぐに受給できます。
退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金は源泉徴収のみで課税が完結し、確定申告は不要です。
ただし申告書を提出しなかった場合や、複数の会社から退職金を受け取った場合には確定申告が必要になるケースがあります。
再就職手当と失業給付は両方もらえますか
両方を同時に受け取ることはできません。
再就職手当は、失業給付の残日数に応じて一括で支給される仕組みであり、再就職後は基本手当の支給は停止されます。
そのため、どちらかを選択する形になります。
傷病手当金と失業給付を同時に受け取れますか
傷病手当金と失業給付は同時には受け取れません。
病気やけがで働けない状態であれば失業給付の対象外となり、傷病手当金を優先して申請することになります。
回復して求職可能になった時点で、失業給付の手続きを開始できます。
退職後の健康保険はどれを選ぶべきですか
任意継続、国民健康保険、家族の扶養のいずれかを選びます。
医療費が多くかかる見込みがあるなら任意継続、収入が少なく軽減措置を利用できるなら国民健康保険、配偶者の扶養条件を満たせるなら扶養に入るのが有利です。
自分や家族の状況に合わせて検討することが必要です。
👉 次章では、これまでの内容を総まとめし、退職給付金を最大限活用するための実践的な最終アクションプランを提示します。
第十一章 退職給付金のまとめと最終アクションプラン
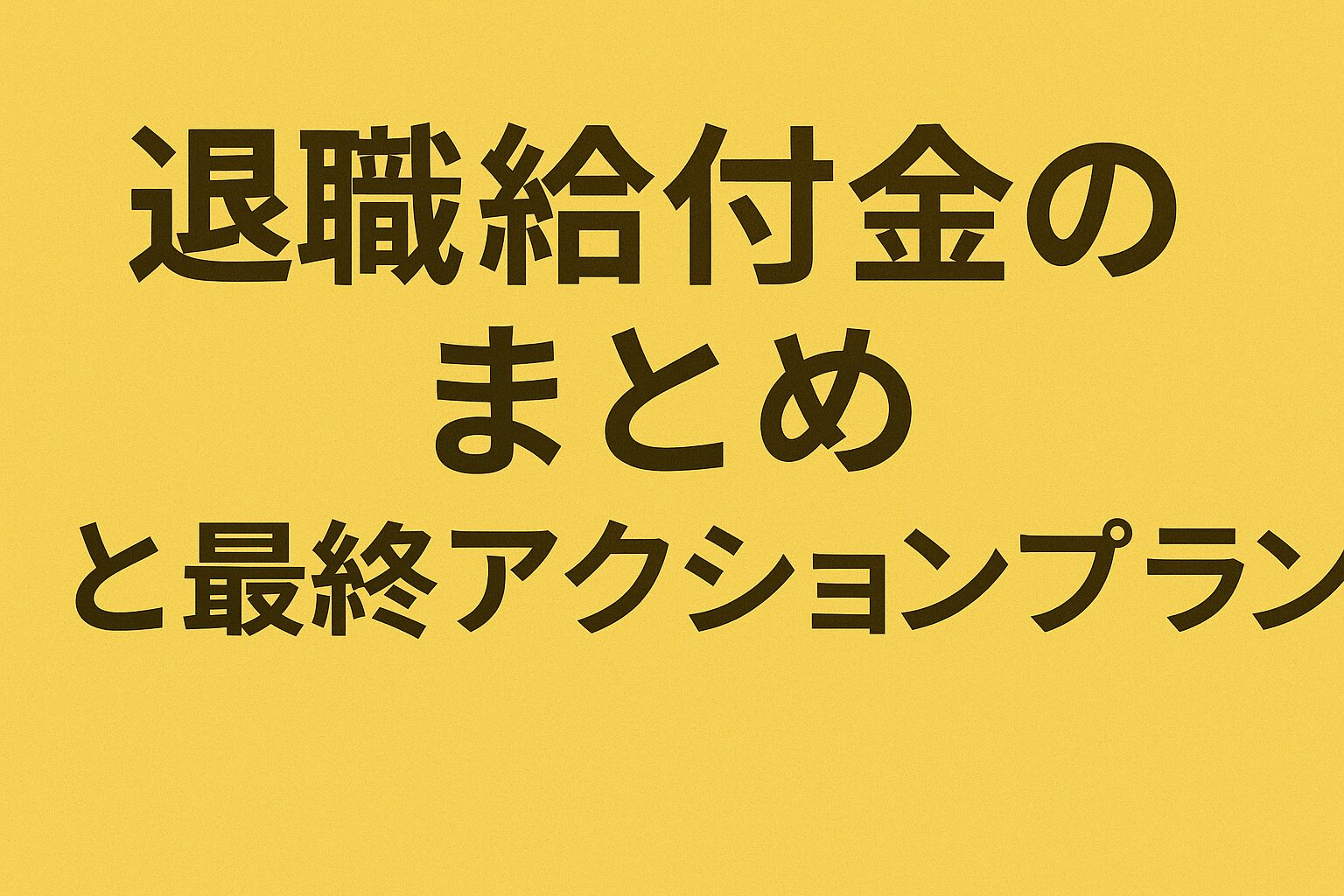
ここまで退職給付金の仕組みや種類を解説してきました。
最後に全体を整理し、実際に行動に移すためのアクションプランを提示します。
退職給付金の全体像の振り返り
- 失業給付:退職後の生活を支える基本的な給付。待機7日と給付制限の有無を確認することが重要。
- 再就職手当:早期に再就職した人を対象に、失業給付の一部をまとめて受け取れる制度。
- 退職金:企業から支給される給付で、退職所得控除により税負担が大きく軽減される。
- 傷病手当金:退職後も病気やけがで働けない場合に継続して支給されることがある。
- 健康保険制度:任意継続、国民健康保険、扶養の三つから選択可能。
- 高年齢向け制度やその他の給付:高年齢雇用継続給付、教育訓練給付金、外国人向け脱退一時金など。
叶えたい未来と避けたい未来
- 叶えたい未来:退職後も安定した収入を確保し、再就職や生活資金に不安を残さないこと。
- 避けたい未来:申請期限を逃して給付を受けられない、税金や社会保険で損をする、生活費が不足する。
最終アクションプラン
- 退職前
離職票や雇用保険被保険者証、退職所得申告書など必要書類を受け取る。 - 退職直後(7日以内)
ハローワークで失業給付の申請を行い、待機期間に入る。健康保険の任意継続を選ぶ場合は20日以内の手続きを忘れない。 - 1か月以内
再就職活動を開始し、再就職手当の条件を満たせるよう計画を立てる。傷病手当金の継続受給が必要な場合は医師の診断書を揃えて申請。 - 3か月以内
退職金に関して、税務処理が適正に行われているかを確認。必要に応じて確定申告を準備。 - 長期的視点
教育訓練給付金や求職者支援制度を活用し、再就職後もキャリアを安定させる。
退職給付金は種類ごとに条件や期限が異なるため、計画的に行動することが最大のポイントです。
本記事を参考に一つひとつ手続きを進めることで、退職後の生活を安定させ、再スタートを安心して切ることができます。
👉 まずは退職直後に必要な手続きをリスト化し、今日から動き出しましょう。
ちなみに退職後の生活を安心させたいなら、スグペイ退職が最適です。
専門家のサポートで申請の不安を解消し、最大310万円の失業保険を確実に受け取り。
さらに 最短1か月で給付開始、すべてオンラインで全国対応。
退職を控えている方や、生活資金を早く確保したい方にピッタリです。
👉 今すぐ詳細をチェックして、安心のスタートを切りましょう!