はじめに:ネタが被って伸びない…そんな悩みを解決します

・ショート動画を頑張って作って投稿しているのに、全然伸びない……
・自分のネタが他の人と被っていて、見てもらえない気がする
そんな悩みを抱えていませんか?
今、ショート動画市場は急激に拡大しており、参入者が増えたことでネタの競争も激化しています。
特にTikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsなどでは、似たようなフォーマットや流行に乗った動画が溢れています。
誰かがやっている「定番のネタ」をそのまま真似しても、目立つことができず、結果として埋もれてしまうのです。
しかし、安心してください。ネタが被る問題には、明確な原因と対処法があります。
本記事では、ネタが被る理由をアルゴリズムの視点からひも解いた上で、被らないネタを生み出す発想法、ジャンル別の差別化ネタ例、編集テクニック、そして日常的にアイデアを得る習慣化の方法までを網羅的に解説していきます。
また、「毎日投稿がキツい」「もうネタがない」と感じる方向けに、ストック術やメンタルの整え方も紹介していきます。
この記事を読むことで、ただバズるだけでなく、「自分らしいネタで見てもらえる」動画作りができるようになるはずです。
ショート動画はアイデア勝負。
でも、必要なのは特別なひらめきではなく、少しの工夫と視点の切り替えです。
それでは一緒に、ネタ被りから抜け出し、唯一無二の動画を作っていく準備を始めましょう。
なぜ「ネタ被り」が起きるのか?
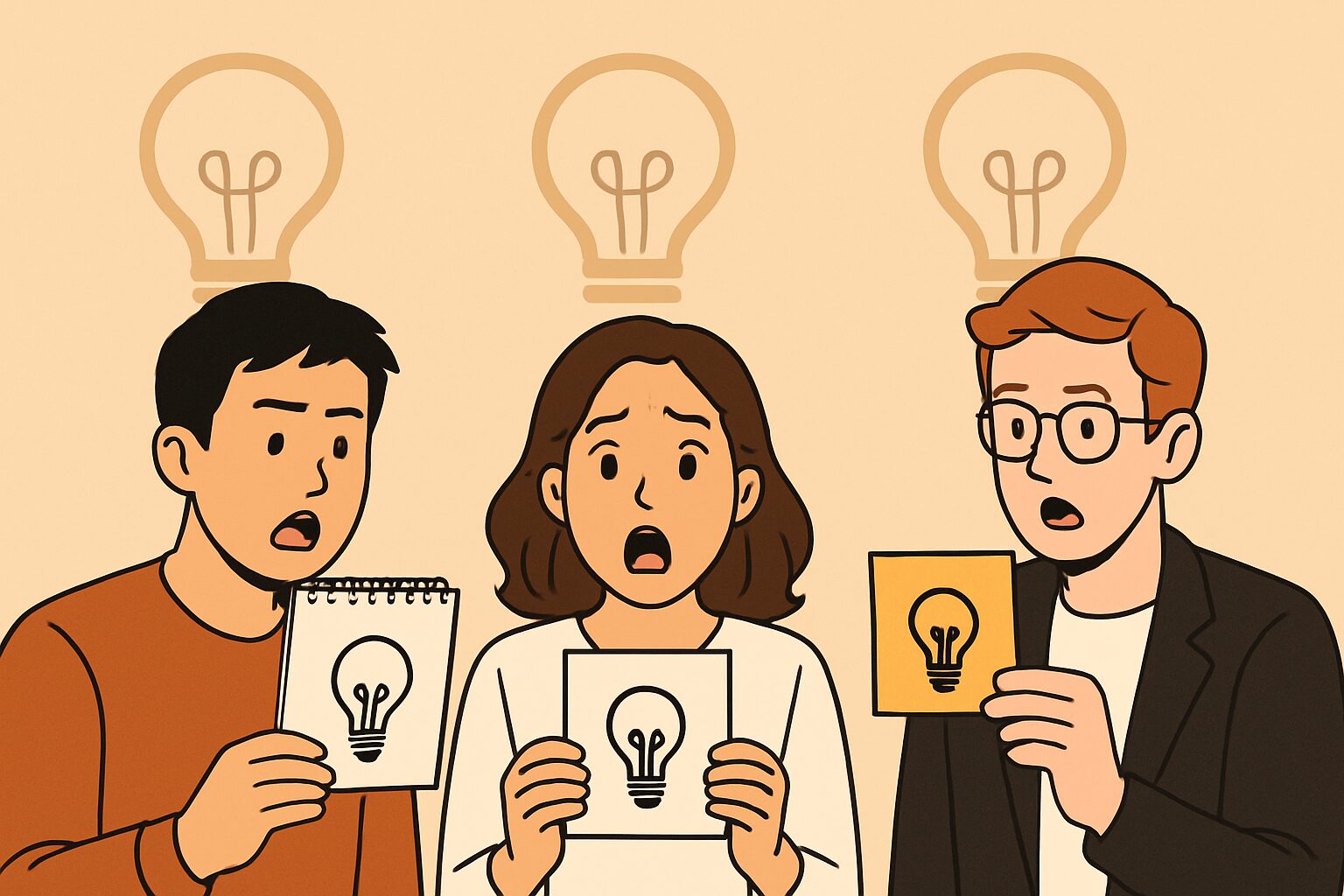
ショート動画を作っていると、多くの人が同じような内容を投稿しているのを目にすることがあります。
それもそのはず。ネタ被りは偶然ではなく、仕組みとして発生しやすい環境があるのです。
ここでは、なぜネタが被るのか、その背景をアルゴリズムとユーザー行動の両面から解説していきます。
トレンドを追う=競合も増える
SNSで「伸びる投稿」を目指すなら、トレンドを追うのは定番の戦略です。
しかし、ここに落とし穴があります。
みんなが同じハッシュタグ、同じ音源、同じチャレンジ系ネタに飛びつくため、投稿が“テンプレ化”してしまい、視聴者から見たときに「またこのパターンか」と飽きられる原因になるのです。
つまり、トレンドに乗るほど差別化が難しくなるという矛盾が起こります。
これは、初心者ほど陥りやすい罠の一つです。
アルゴリズムの性質上「似た動画」が拡散されやすい
InstagramやTikTokなどのSNSは、ユーザーの興味関心に合わせて動画を自動で推薦します。
この仕組みにより、「似た動画」が連続で表示される傾向があり、同じトピックや構成が並ぶことになります。
つまり、自分の動画が“似た系統の中の一つ”に過ぎないと、埋もれてしまう確率が高くなってしまうのです。
特にフック(冒頭)や展開が似ていると、最後まで見てもらえずスキップされる可能性が高まります。
無意識に「他人の真似」をしてしまう
ネタを考える際、参考にするために他の人気投稿を見ているうちに、無意識にその構成や表現を真似てしまうこともあります。
すると、自分では「工夫したつもり」でも、視聴者から見ると「また同じような動画」と映ってしまうのです。
アイデアのインスピレーションは重要ですが、それを「そのまま使う」ではなく、「自分なりの視点に置き換える」ことが必要です。
選ぶテーマが“競合の多い領域”である
美容、ライフハック、エンタメなど人気のジャンルは、常に大量の投稿が流れています。
特にフォーマットが定番化しているジャンルでは、わずかな違いでは差別化にならないことも多いです。
その結果、自分ではオリジナルと思っていても、すでに似たような投稿がたくさん存在してしまっていることになります。
このように、ネタ被りは自然発生的に起きてしまう現象であり、避けるには明確な「切り口」と「発想の転換」が必要になります。
次の章では、誰でも実践できる被らないネタ作りの考え方5つを紹介していきます。
視点を変えるだけで、同じテーマでも“唯一無二の動画”に生まれ変わります。
差がつく!被らないショート動画ネタの考え方5つ

ネタが被らずに伸びるショート動画を作るためには、「テーマ」ではなく「視点」を変えることが重要です。
同じ題材を扱っていても、切り口や伝え方が違えば、まったく新鮮な印象になります。
この章では、誰でも再現できる“被らないネタの考え方”を5つの視点から紹介します。
自分の失敗や黒歴史を活かす
「失敗談」や「黒歴史」は、あなただけのオリジナルコンテンツです。
これほど他人と被らないネタはありません。
しかも、視聴者の共感や笑いを引き出しやすく、感情的なつながりを生みやすいのが大きな強みです。
たとえば:
- 初めてバイトに行って全力でミスった話
- 恋愛でやらかした過去
- 服を裏表で着たまま出勤してしまった話
これらの体験をコミカルな演出で編集すれば、フォロワーとの距離が縮まり、ファン化にもつながります。
視点を変える:「裏側」や「知られざる一面」
よくあるネタでも、「裏側を見せる」ことで斬新さを出すことができます。
たとえば、料理の動画なら「失敗した時の裏側」や「撮影している風景」、美容なら「普段は見せないすっぴんからの変化」を映すことで、親近感やリアルさが増します。
視点の例:
- 「人気動画の裏側を公開」
- 「撮影している部屋、実はこんな状態です」
- 「編集している途中の画面を見せます」
こうした「ちょっとズラす」視点が、ネタ被りを防ぐ鍵になります。
専門知識や職業スキルを活かす
自分にとっては当たり前の知識でも、他の人にとっては「へぇ~!」という新鮮な情報になることがあります。
特に、専門的な職業やスキルを持っている方は、その強みを最大限活かしましょう。
業種別の活用例:
- 美容師:自宅でできるヘアセットの裏技
- 事務職:Excelの便利ショートカット集
- 看護師:知っておくと安心な応急処置方法
- 教師:生徒が言いそうな面白セリフあるある
“自分だけが知っていること”こそ、ネタの宝庫です。
地域×情報で独自性を出す
地元ネタ、方言、ローカル文化などは、「自分ごと」として受け取られやすく、バズりやすい傾向があります。
全国的には知られていないネタほど「新鮮」に映り、地域の共感も得やすくなります。
例:
- 「東京では通じない〇〇県の方言5選」
- 「地元あるあるに共感できたらいいね!」
- 「ご当地スーパーで売ってる謎グルメ紹介」
あなただけの“地元視点”を加えるだけで、動画の個性が一気に高まります。
日常×ハウツーで「保存される動画」に
日常生活の中にある“役立ち情報”を、短く簡潔にまとめた動画は「保存」されやすく、アルゴリズムにも好まれます。
特別なことではなく、ちょっとした豆知識や生活の工夫が、ネタとして機能するのです。
例:
- 「500mlペットボトルでできる筋トレ3選」
- 「朝の準備を10分短縮するルーティン」
- 「スマホの充電を長持ちさせる小技」
“これ、今度試してみよう”と思わせたら勝ちです。
ネタ作りで一番大切なのは、「どんな視点で語るか」です。
同じテーマでも、自分の体験や視点を重ねることで、誰とも被らないコンテンツに変えることができます。
ジャンル別|ネタが被りにくいショート動画アイデア

「ネタが被らないように」と意識しても、テーマの選び方がワンパターンだと、どうしても似たような投稿になってしまいがちです。
そこでこの章では、ジャンルごとに“ひと工夫加えるだけで差がつく”ショート動画のアイデアを紹介します。
どれも今すぐ取り入れやすく、ネタ切れ対策としても有効です。
ライフスタイル系
ライフスタイルジャンルは非常に人気が高く、競合も多いですが、切り口次第で十分に差別化が可能です。
ポイントは「逆張り」や「裏側の見せ方」です。
- 1日ルーティンの“逆再生”動画(起きる→寝るまでを逆順で紹介)
- 朝活 vs 夜型の生活を比較して見せる「二画面編集」
- ルーティンの「失敗版」や「現実版」などリアルさを見せる内容
生活感を前面に出すことで、共感と親近感を生み出せます。
教育・学習系
勉強法やスキル解説は、信頼性と差別化の両方が問われます。
特に“学校では教えてくれない”切り口が人気です。
- 難しい言葉を超かんたんに説明する「1分解説」シリーズ
- 歴史の“裏話”や“都市伝説”など、興味を引く切り口
- 本の要約×自分の意見を組み合わせたレビュー動画
「実用性+エンタメ性」のバランスがポイントです。
エンタメ系(お笑い・ドラマ・モノマネなど)
競争の激しいジャンルですが、創意工夫が活きる領域でもあります。
「架空設定」や「擬人化」が鉄板ネタとして活用できます。
- 架空ニュース「〇〇速報」シリーズ(例:冷蔵庫の中に閉じ込められたバナナ)
- 感情を擬人化してみた(例:やる気 vs 面倒くささ)
- AIや未来をテーマにした“ありそうでない日常”動画
ユニークな発想が光るネタが多く、バズる可能性も高いです。
美容・ファッション系
見た目に関するコンテンツは視覚的インパクトが大きい一方、プロセスや比較に焦点を当てると差が出ます。
- メイクの“やりすぎNG例”と“正解例”を比較する動画
- プチプラvsハイブランドの使用感・仕上がり比較
- 1つのアイテムで3通りのコーディネート紹介
「思ってたんと違う!」というギャップ要素が好反応を生みます。
ビジネス系
意外とネタが被りにくいのがビジネス系です。
リアルな職場の視点や考え方の紹介が求められています。
- デスクツアー:本当に使っているアイテム紹介
- 朝礼で使える一言ネタシリーズ
- 「1分で伝える」スライドプレゼン術
“役に立つ+共感できる”の両軸を意識するとヒットしやすくなります。
このように、ジャンルごとにネタの切り口を工夫することで、ネタ被りを避けつつ独自性を出すことができます。
大切なのは、「そのジャンルの中でどこに自分の個性を出せるか」を見極めることです。
ネタを差別化するための編集テク&演出アイデア

ショート動画のネタが他と被らないように工夫しても、編集や演出の違いがなければ“印象に残る動画”にはなりません。
同じテーマでも、演出が上手いだけで「この人、センスあるな」「プロっぽい」と感じさせることができます。
この章では、初心者でも取り入れやすい編集テクニックと演出アイデアを具体的にご紹介します。
テキストは“感情”で打つ
ただ情報を載せるだけのテキストよりも、「感情を表現する」言葉選びが大切です。
見た人の心に刺さるフレーズや言い回しは、共感・保存につながります。
例:
- 「マジでこれは人生変わった」
- 「知ってる人は意外と少ない裏技」
- 「〇〇するだけで、爆伸びします」
フォントや色も工夫して、“目に飛び込む”デザインを意識しましょう。
間(テンポ)を意識して“リズム感”を作る
編集のテンポ感は、動画の魅力に大きく関わります。
特にショート動画は一瞬で離脱されるため、「間延びした編集」は致命的です。
工夫例:
- 要点だけを1〜2秒ずつテンポよく配置
- 効果音やBGMのリズムに合わせてカット
- 一言ごとに場面を切り替えて緩急を出す
視聴者が“気持ちよく見られる”テンポが理想です。
音や効果音で印象操作する
音は視覚と同じくらい印象を左右します。効果音ひとつで、動画の空気感がガラッと変わります。
面白系なら笑い声やポップ音、感動系ならエモいピアノやストリングスなど、目的に応じた音選びが大切です。
おすすめの工夫:
- セリフの後に「チャーン」などインパクト音
- 無音→BGMスタートで一気にテンションアップ
- シーン転換時に「ポンッ」「シャキーン」などで印象付け
BGMだけでなく、“効果音の引き算”も効果的です。
あえて無音にする場面を作ると、集中力が高まり、次の演出が際立ちます。
「構成」でストーリー性を持たせる
1本の動画でも、「起承転結」を意識した構成にすると、見ごたえが大きく変わります。
構成例:
- 起:問題提起「〇〇に悩んでませんか?」
- 承:状況説明 or 自分の体験談
- 転:解決策・裏技・おすすめ
- 結:まとめ+次の行動を促す(保存・フォロー・シェア)
この型に沿って編集するだけで、内容がスッと頭に入り、行動を起こしてもらいやすくなります。
タイトル映像・カバーの工夫
視聴前に表示されるカバー画像(サムネ)や、動画の最初に出す「タイトル映像」も重要な差別化ポイントです。
工夫例:
- 動画タイトルを「白背景×黒字」でドンと表示
- イラストや図解でビジュアルに伝える
- 1秒だけ「完成形」を見せて興味を引く
これらの演出により、冒頭で“続きを見たい”と思わせることが可能になります。
編集はただの作業ではなく、「視聴者とのコミュニケーション」です。
演出を通して、どれだけ自分のネタを“魅せるか”を意識するだけで、同じテーマでも大きな違いを生み出せます。
ネタが被らない人の習慣|アイデアはこうして生まれる

ショート動画の世界で“常に新しいネタを出し続けている人”は、特別な才能があるわけではありません。
彼らは、日々のインプットとアイデアの記録を「習慣化」しているのです。
この章では、ネタが被らないクリエイターに共通する習慣と、誰でも今日から実践できるアイデア創出法を紹介します。
ネタ帳を作り、思いついたら即メモ
アイデアは思いついた瞬間にメモしないと、ほぼ100%忘れてしまいます。
プロのクリエイターは、思いついたネタを必ず“即記録”しています。
スマホのメモ帳、Notion、Google Keepなど、使いやすいツールでOKです。
記録するときは、「タイトル」や「ネタの種」だけでもOKですが、できれば下記のようなフォーマットにしておくと後で使いやすくなります:
- タイトル案
- どんな感情を伝えたいか
- 想定するターゲット
- 必要な素材(映像・音・構成)
これを毎日3〜5個書く習慣をつけると、ネタ切れに悩むことはなくなります。
ネタの種は日常に落ちている
ネタのヒントは、派手な出来事ではなく「日常の中の違和感」にこそ潜んでいます。
以下のような視点を持って生活するだけで、アイデアの幅がぐんと広がります。
- 「今の自分の行動、説明すると面白いかも?」
- 「なんでこれってこうなんだろう?」と疑問を持つ
- 他人の会話、SNSのコメントから“リアルな悩み”を拾う
日常にアンテナを立てることで、誰にも真似できないオリジナルのネタが自然と集まってきます。
インプットは「他ジャンル」から得る
ネタの差別化に最も効果的なのが、“自分が普段触れていない世界”からヒントを得ることです。
たとえば、美容ジャンルの投稿をしている人が、ビジネス書や科学番組からインスピレーションを得て構成を考えると、独自性のあるハイブリッドな動画が生まれます。
おすすめのインプット源:
- 他ジャンルのYouTube動画やショート
- 書籍や雑誌の見出し(タイトルにヒントが多い)
- 海外クリエイターのコンテンツ(視点が全く違う)
日常のインプットに「ひとひねり」加えることで、ネタは無限に湧いてきます。
SNSのコメント欄や質問箱は宝の山
視聴者のリアルな声ほど、次のネタづくりに活かせるものはありません。
自分の投稿だけでなく、他人の人気投稿のコメント欄をチェックすると、「こんなことが知りたい」「ここが分からなかった」などのニーズが見えてきます。
また、匿名で質問を受け付けられるサービス(例:Peing、質問箱など)を活用し、フォロワーの悩みや疑問を収集するのも効果的です。
ルールを決めて「自動化」する
ネタ出しを習慣化するには、自分ルールを決めると続けやすくなります。
- 通勤時間に必ず1ネタ考える
- 朝のコーヒータイムにネタ帳を開く
- 毎週日曜は「来週の投稿アイデアを5つ出す日」
こうしたルーチン化が、クリエイターとして“ネタに困らない脳”を作ってくれます。
アイデアは“ひらめき”ではなく“習慣”から生まれます。
今すぐ天才的なアイデアが浮かばなくても、日々の記録と観察を続けていけば、あなたにしか作れない動画ネタが自然と溜まっていくはずです。
「ショート動画 ネタ切れ」「毎日投稿がキツい」と感じた時の対処法

ショート動画を継続して投稿していると、多くの人がぶつかるのが「ネタ切れ」と「投稿疲れ」の壁です。
最初は勢いで毎日投稿できても、次第にアイデアが枯渇し、気力も続かなくなってしまうことはよくあります。
この章では、そんな時でも無理なく継続できるネタのストック法・再利用テク・メンタル維持術を具体的に紹介します。
アイデアのストックは「テーマ×視点」で無限化できる
ネタが出なくなる最大の原因は、「同じ考え方でしか探していない」ことにあります。
発想を広げるには、「テーマ」と「視点」を掛け合わせるのがコツです。
例えば:
- テーマ:節約術
- 視点①:一人暮らし向け
- 視点②:ファミリー層向け
- 視点③:ズボラさん向け
このように、1つのテーマでも視点を変えるだけで複数のネタに分裂させることができます。
ネタ帳をこの組み合わせで整理すると、常にアイデアが溜まる構造になります。
過去の投稿を再編集して“リバイバル”する
一度投稿したネタも、再編集・再構成することで新しい動画に生まれ変わります。
すべてを新しく考える必要はありません。
特に以下のような方法が有効です:
- 過去の動画を短く再編集してテンポを改善
- BGMや効果音を変えて“雰囲気チェンジ”
- 冒頭に「〇〇だった結果…」など新しいフックを追加
アルゴリズム的にも、新たな視聴者に再びリーチできる可能性があるため、定期的な再投稿は戦略的にアリです。
毎日投稿しないとダメ?→ペースを“再設計”しよう
「毎日投稿がきつい」と感じたら、無理に続けるのではなく、持続可能なペースに見直すことが大切です。
おすすめの投稿設計:
- 週3投稿+週1本は“再編集動画”で負担軽減
- ネタが豊富な時に“予約投稿”をしておく
- 投稿しない日は、ストーリーズやコメント返しでフォロワーと交流
大切なのは“習慣化”であり、“完璧主義”ではありません。
アイデアに困った時は「逆パターン」「否定ネタ」で突破口を
アイデアが浮かばない時は、「逆を考える」発想が効果的です。
例:
- 「やってはいけない〇〇術」
- 「〇〇しなかったらこうなった」
- 「失敗例から学ぶ〇〇」
王道をなぞるよりも、“逆張り”や“皮肉”を使った構成のほうが目を引きやすく、コメントもつきやすくなります。
メンタルの保ち方=完璧を求めすぎない
創作活動は、常に成果が見えるわけではありません。再生数が伸びない、反応が薄い…
そんなときこそ「焦らない・比べない・無理しない」が大切です。
- 再生数より「自分らしく出せたか」を評価軸に
- 目標は“完璧な動画”より“継続できたか”
- フォロワー10人でも反応があるなら“届いている証拠”
メンタルを安定させることは、クリエイターとして長く続けるための最重要ポイントです。
ネタ切れや疲労感は、どのクリエイターにも起きる自然なサイクルです。
大切なのは「ゼロから考え直さずに、工夫と工数を減らす仕組みを作ること」。
無理せず、継続できるスタイルを見つけていきましょう。
まとめ:被らないネタ作りは「自分らしさ×視点の切り口」から
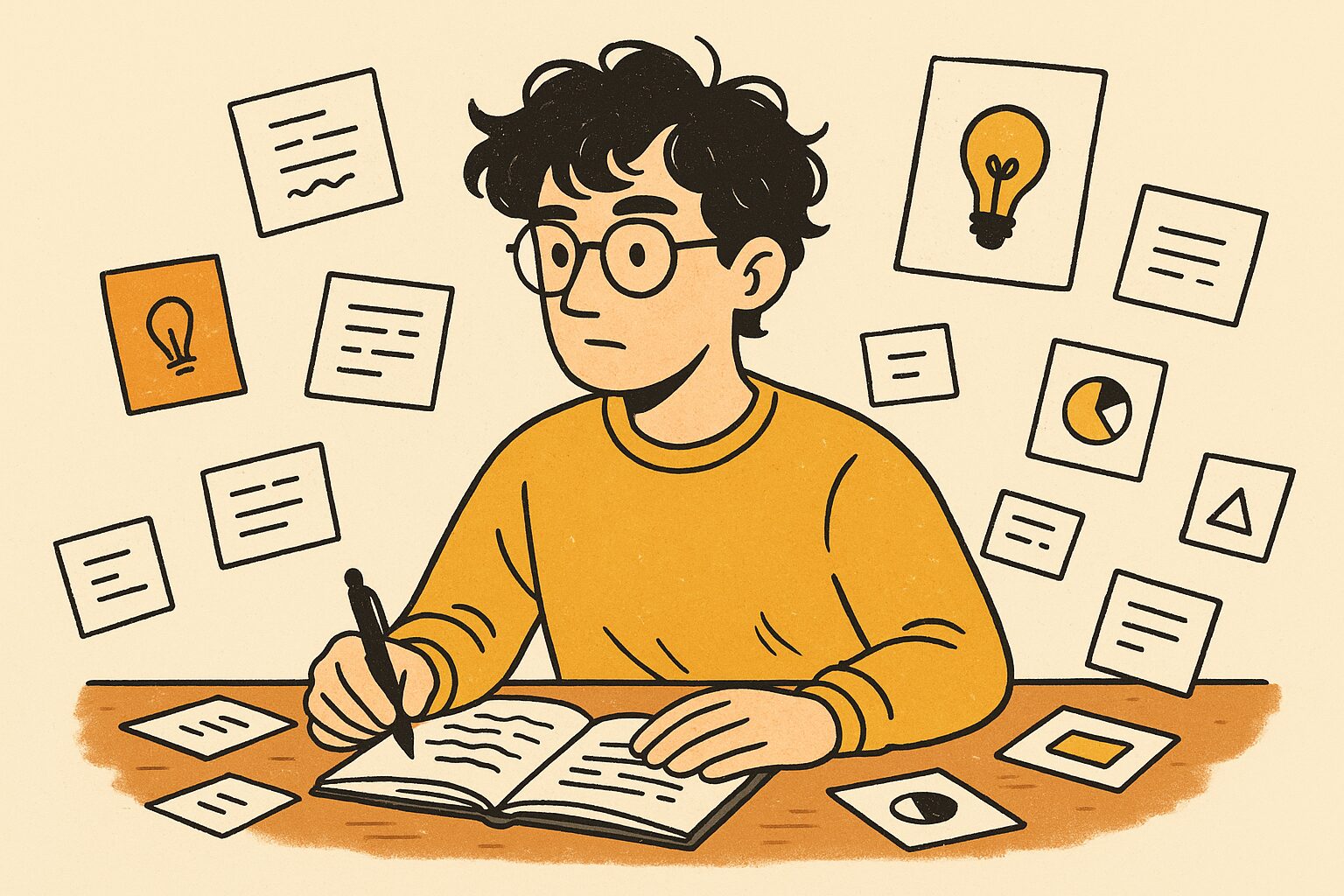
ショート動画の世界では、誰かと同じことをしていても“選ばれる理由”にはなりません。
ネタが被って伸びない…そんな悩みを抱える多くの人に共通するのは、「テーマは面白いけど、どこかで見たことがある」という印象を与えてしまっていることです。
しかし、本記事で解説してきたように、「視点を変える」「自分の体験を重ねる」「編集で差をつける」といった工夫をすることで、同じテーマでもまったく違う“自分だけのコンテンツ”に変えることができます。
被らないネタ作りとは、奇抜さや特別なセンスが必要なのではありません。必要なのは以下のようなシンプルな姿勢です。
- 自分の失敗や経験をネタにする勇気
- いつもと違う角度からテーマを見てみる発想力
- 小さな気づきをメモし続ける習慣
- 毎日続けるために仕組み化する工夫
誰かと違うものを作ろうと気負いすぎる必要はありません。
「自分の視点を活かして発信する」、それだけで自然とオリジナリティは生まれます。
ネタ切れに悩んだときは、過去の動画を振り返って“再構築”したり、コメント欄から新しいインスピレーションを得たり、日常の違和感にアンテナを立ててみてください。
ネタは外にあるのではなく、あなたの中にすでに眠っているのです。
さあ、今日からひとつだけ、この記事の中で「できそう」と思ったことを試してみてください。
完璧を求めず、積み重ねていくことで、あなたのショート動画は確実に“誰にも真似できないもの”になっていきます。
あなたの表現が、必要とする誰かに届きますように。
ただ・・・
まだまだSNSで収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。
じゅんの公式LINEでは、
- インスタアフィで稼ぐロードマップ
- 収益化に向けた詳しいノウハウ
- 各種テンプレート
などを中心に、
今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・
最高じゃありませんか…?
まずは僕の公式LINEを追加していただき、
ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
\無料!登録10秒/
公式LINEに登録するだけで
インスタ初心者でも月6桁目指せる
豪華17大特典配布中🎁
登録解除は、24時間いつでも出来ます