※本ページはプロモーションが含まれています。
日産を取り巻く最新動向まとめ 2025年7月時点
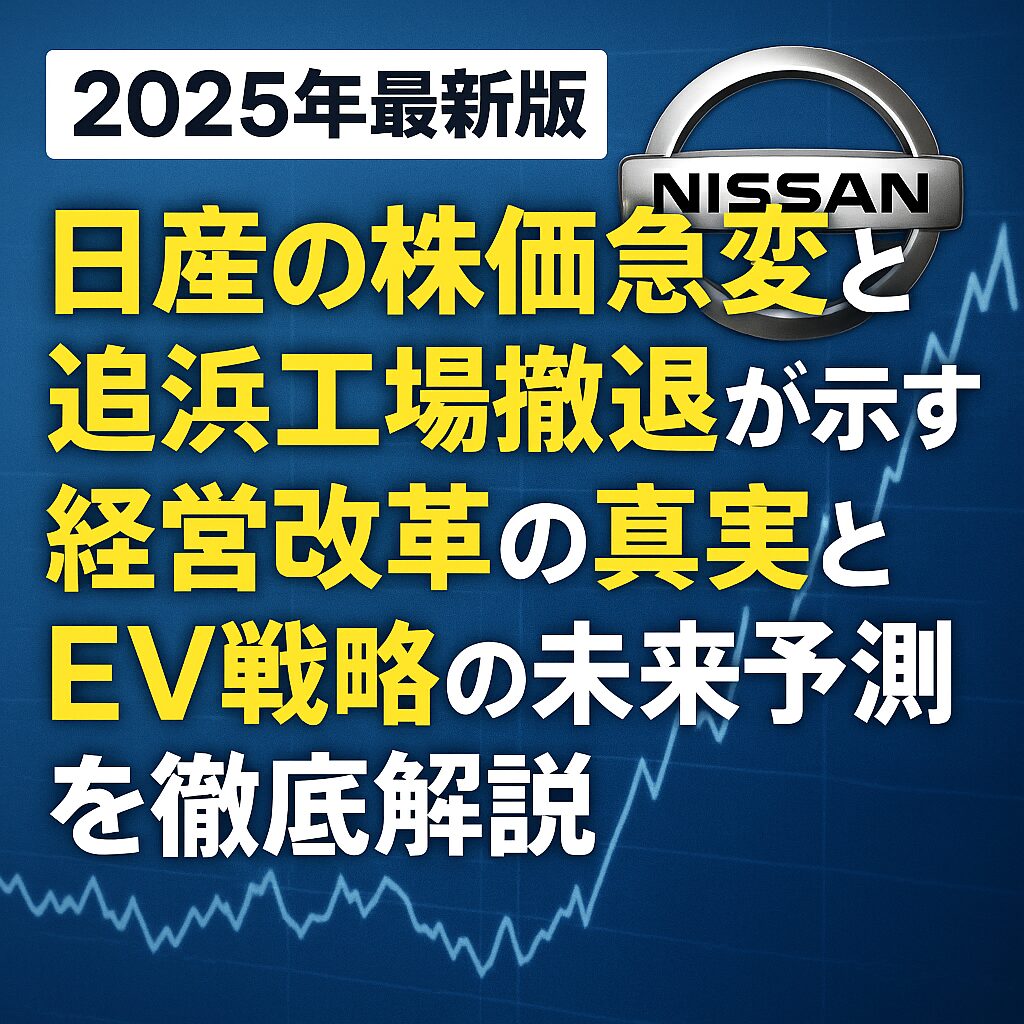
2025年7月現在、日産を巡るニュースは株価急変と追浜工場撤退、そして電気自動車(EV)戦略の加速という三つのトピックに集約されます。
まず株価は6月の350円台から7月中旬には310円前後まで下落し、出来高急増と合わせて調整局面に入っています。
背景には世界的な金利高と円高進行に加え、欧米市場での販売減速が重なったことが挙げられます。
次に、60年以上フラッグシップ工場として稼働してきた追浜工場が2027年度末で生産を終えるという決定は、固定費圧縮と生産効率の向上を目指す経営再建策「Re Nissan」の象徴的な一手です。
約3,900人の従業員処遇や地域経済への影響が注目される一方、台湾の鴻海精密工業と協業しEV生産拠点へ転換する構想が浮上しており、閉鎖リスクを成長機会へ転じられるかが焦点となります。
最後に、アリアと三代目リーフを軸とするEVラインアップ拡充が進みます。
2025年型アリアは最長航続289マイルを達成し、北米でIIHSトップセーフティピックを獲得するなど商品力を強化しました。
日産は2030年度までに世界販売の40%をEVに置き換える目標を掲げ、電池コストを現行比30%削減するロードマップを提示しています。
株価下落と工場撤退は一見ネガティブですが、資産のスリム化とEV集中投資へ舵を切る布石とも言えます。
本章ではこの三点を整理し、日産が「守り」と「攻め」を同時に進める現在地を俯瞰しました。
次章では、株価下落の背景をより詳しく分析し、投資家が注視すべき指標を解説します。
日産株価はなぜ下落トレンドか 投資家が注視すべきポイント
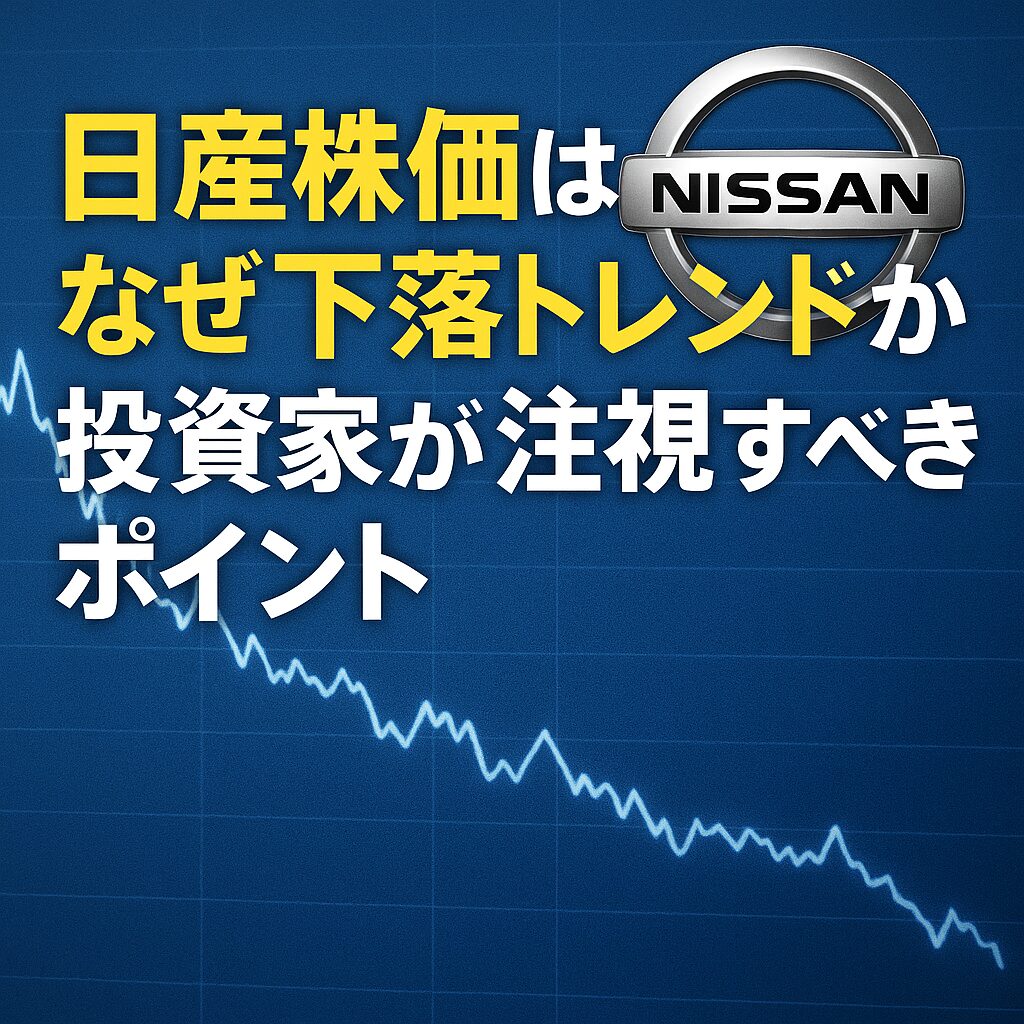
下落局面の概要
日産自動車の株価は2025年6月に370円近辺で推移していましたが、7月に入ると急落し、7月15日時点では310円台で取引されています。
7月9日には出来高が1億7,600万株超に急増し、一時299円まで売り込まれる場面もありました。
短期テクニカルでは25日移動平均線を大きく割り込み、直近高値367円と月初来安値299円のレンジ内で調整が続いています。
転換社債増額による希薄化懸念
7月8日に日産が転換社債の発行額を1,500億円から2,000億円へ引き上げると発表したことを受け、株価は2日連続で大幅安となりました。
転換社債は将来的に株式へ転換されるため、発行増額は「株式価値の希薄化」を意識させます。
加えて、同時に発表された4,000億円規模のドル建て・ユーロ建てシニア債も「資金繰り悪化のシグナル」と捉えられ、市場心理を冷やしました。
四半期赤字と売上低迷
2024年度決算では最終赤字4,500億円を計上し、会社側は2025年度の利益見通しを示さない慎重姿勢を取っています。
世界販売台数は2017年度比42%減まで落ち込み、新車投入の遅れが続くなか、北米と中国の市場でシェア低下が顕著です。
投資家は「業績底入れの時期が見えにくい」と判断し、短期の戻り局面でも売りが出やすい構図になっています。
金利高・円高・通商リスクの三重苦
世界的な金利高で自動車ローン需要が鈍る一方、足元の円高進行は輸出採算を圧迫しています。
さらに米国が検討中の輸入車関税引き上げが現実化すれば、北米販売が3割超を占める日産にとって追加の逆風となります。
市場はこれら「マクロ要因」を折り込みつつあり、当面は政策動向や為替レートのヘッドラインに左右されやすい地合いです。
工場再編と追加コストへの警戒
追浜工場の生産終了決定は長期的に固定費削減に寄与するものの、短期的には移管費用や人件費負担が増すため利益圧迫要因と見られています。
再編コストの精緻な数字は8月の第1四半期決算で示される予定で、それまでは不透明感が株価の上値を抑えやすい状況です。
今後のサポートラインとカタリスト
テクニカル面では300円前後が心理的な下値支持として意識されており、7月中旬の急落局面でも買い戻しが入っています。
一方で、希薄化懸念が払拭されるまでは25日線(330円付近)の上抜けが難しく、狭いレンジのもみ合いが続く公算が大きいです。
株価反転の材料としては、①EV販売計画の上方修正、②鴻海との協業枠組み正式決定、③米国関税リスクの後退――などが挙げられます。
次章では、追浜工場撤退の詳細と経営再建策「Re Nissan」の実態を深掘りし、生産体制再編が財務に与えるインパクトを検証します。
追浜工場撤退の衝撃とその背景 経営再建策Re Nissanを読み解く

撤退決定のインパクト
2025年7月15日、日産は神奈川県横須賀市の追浜工場で行っている車両生産を2027年度末で終了すると正式に公表しました。
1961年の操業開始以来、60年以上にわたり主力拠点として稼働してきた同工場は、日産の歴史そのものと言える存在です。
ここで「ノート」や「ノートオーラ」などを生産してきましたが、今後は生産を日産九州工場へ段階的に移管し、研究所や衝突試験場など一部機能のみが残ります。
稼働率低下と固定費負担
追浜工場の年間生産能力は約24万台ですが、2024年の稼働率は4割程度にとどまりました。
自動車工場の損益分岐点は一般に稼働率8割前後と言われるため、半分近い稼働では固定費が重くのしかかります。
ラインを止められない生産設備、人件費、施設維持費がコスト構造を圧迫し、利益改善を阻んでいました。
今回の撤退は、こうした“重い足かせ”を外す狙いがあります。
Re Nissan計画での位置づけ
日産は経営再建策「Re Nissan」の下で、世界17工場を2030年度までに10工場へ再編する方針です。
追浜撤退は国内再編の皮切りであり、資産のスリム化と生産効率向上を両立させる象徴的な一手となりました。
今後は九州工場が小型車とEVを兼務し、英国サンダーランドやメキシコ・アグアスカリエンテスなどの海外拠点には中大型EVを集中投下する布陣へ移行します。
鴻海とのEV協業の可能性
一方で追浜地区の広大な敷地を遊ばせないため、日産は台湾の鴻海精密工業とEV領域での協業を検討中です。
想定されるシナリオは以下の三つです。
- 合弁によるEV専用ライン設置
- 試作車・低量産モデルの共同開発拠点化
- 電池パックとソフトウェア統合の実証施設化
鴻海はiPhone組立で培ったサプライチェーン最適化に強みがあり、もし合弁が成立すれば部品点数の削減や調達コスト低減が期待できます。
日産にとっては、設備を残しながら固定費を抑えられる“第二の道”となり得ます。
従業員と地域への影響
追浜工場には約3,900人(2024年10月末時点)が在籍し、関連企業を含めると雇用規模は1万人超に上ります。
日産は
- 九州工場や先進技術部門への配置転換
- 希望退職と再就職支援
- 地元自治体と連携した職業訓練プログラム
など複数の選択肢を提示する方針です。
それでも「寮や商店街がゴーストタウン化するのでは」と地域経済への懸念は根強く、自治体やサプライヤーとの調整が不可避です。
財務インパクトと今後の注目点
撤退に伴う一時費用は、設備減損・移設費・人件費などを合わせて最大1,200億円規模になると試算されます。
ただし設備減損はキャッシュアウトを伴わず、固定費負担の削減効果(年間200億円規模)が継続的に効いてくると見込まれます。
8月発表予定の第1四半期決算で具体的な数字が明らかになれば、株価が「悪材料出尽くし」と評価し反発に転じる可能性もあります。
次章では、この生産移管と鴻海協業が日産のEV戦略にどのようなシナジーをもたらすかを掘り下げ、技術面・市場面から期待とリスクを整理します。
鴻海とのEV協業は何をもたらすか 期待と課題
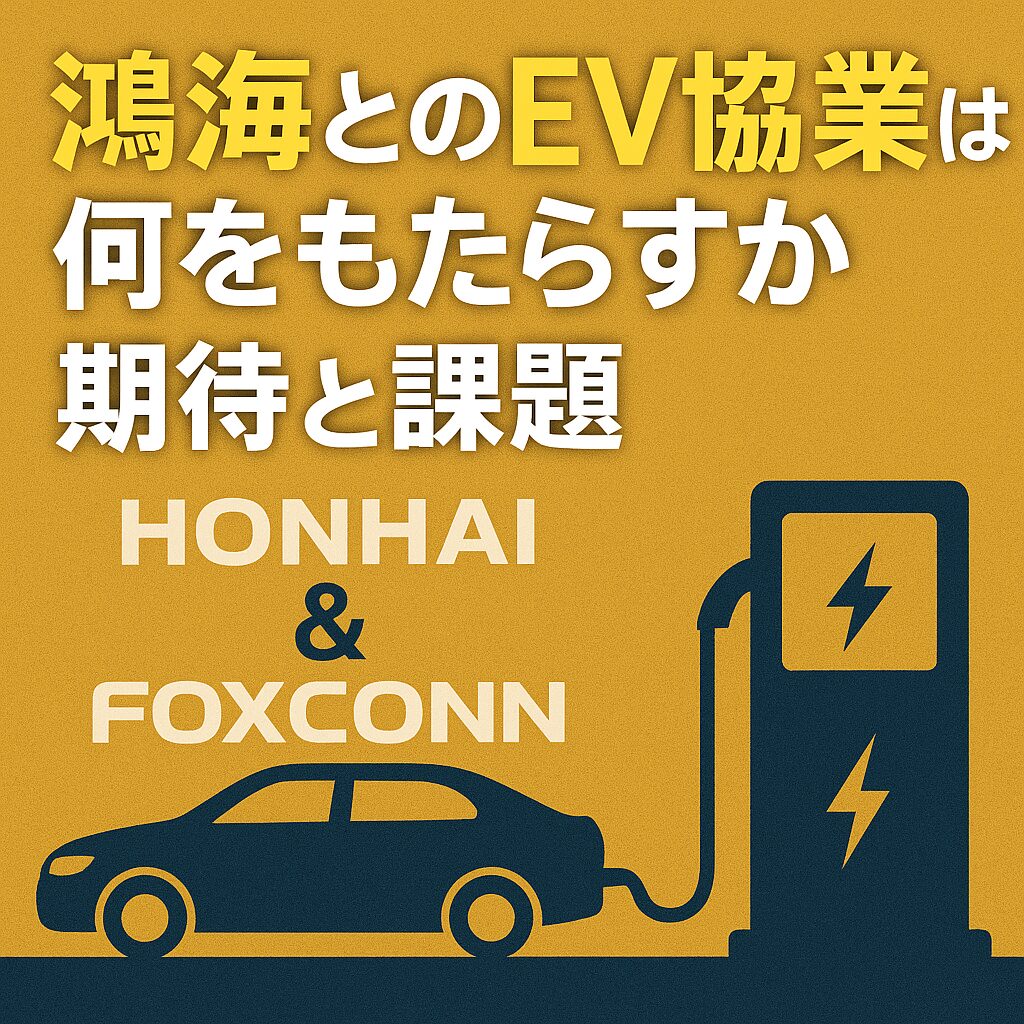
日産は追浜工場の生産終了を決めたその翌週、台湾の鴻海精密工業(ホンハイ)と電気自動車(EV)分野で協業する可能性を正式に認めました。
協議中の案では、鴻海が自社ブランド車を追浜で生産し、日産は完成車組立ラインを維持したまま稼働率を引き上げる青写真を描いています。
鴻海はスマートフォン製造で培った巨大サプライチェーン網を持ち、オープンプラットフォーム「MIH」を通じて世界2,000社超と連携しながら部品点数削減とコスト最適化を図っています。
日産が同プラットフォームを活用すれば、車両開発期間を最短18か月へ短縮し、部品・物流コストを一台当たり最大15%低減できると試算されます。
双方が検討する生産スキームは三段構えです。
第一に、追浜の既存塗装・組立ラインを鴻海仕様へ改修し、2028年以降に年5万台規模のEVを量産する計画。
第二に、試作車や低量産モデルを共同開発する実証拠点として活用し、車台・ソフトウエアの相互提供で開発コストをシェアします。
第三に、日産が社有地内に保有する試験場と専用ふ頭を生かし、国内外の輸出入ハブとして機能させる構想です。
これにより工場閉鎖が避けられれば、従業員およそ3,900人の雇用維持と地域経済への波及効果も期待されます。
技術面では、日産が掲げる「2030年度までにEVコストを現行比30%削減し、ガソリン車と同等にする」という目標と、鴻海のモジュール化戦略が補完関係にあります。
鴻海の電池パック供給とMIHプラットフォームの共通アーキテクチャを採用することで、バッテリーセル調達単価を一基あたり約12%下げられるとの社内試算が示されています。
一方、課題も少なくありません。
第一に、鴻海が求める「フラットな意思決定」と日産の伝統的な縦割り組織が衝突する懸念。
第二に、ソフトウエア統合を巡る知的財産権の取り扱いが不透明で、車載OSのアップデート権限やデータ収益配分を巡り交渉難航が予想されます。
第三に、国内サプライヤー網の再編が避けられず、取引停止や価格再交渉で地元部品メーカーの収益を圧迫するリスクがあります。
これらは2026年前半に予定される最終契約締結までに解決策を示す必要があります。
協業が実現すれば、追浜工場は「重荷を抱えた国内生産拠点」から「アジア向け次世代EVのショーケース」へと役割を転換できます。
反対に交渉決裂となれば、撤退費用と稼働率低迷が同時に日産の財務を圧迫し、株価の下落圧力が強まる恐れもあります。
投資家にとっては、2025年末までの基本合意が上昇トリガー、交渉棚上げが下落トリガーという明確な分岐点となりそうです。
事業ポートフォリオとグローバル生産体制の再編
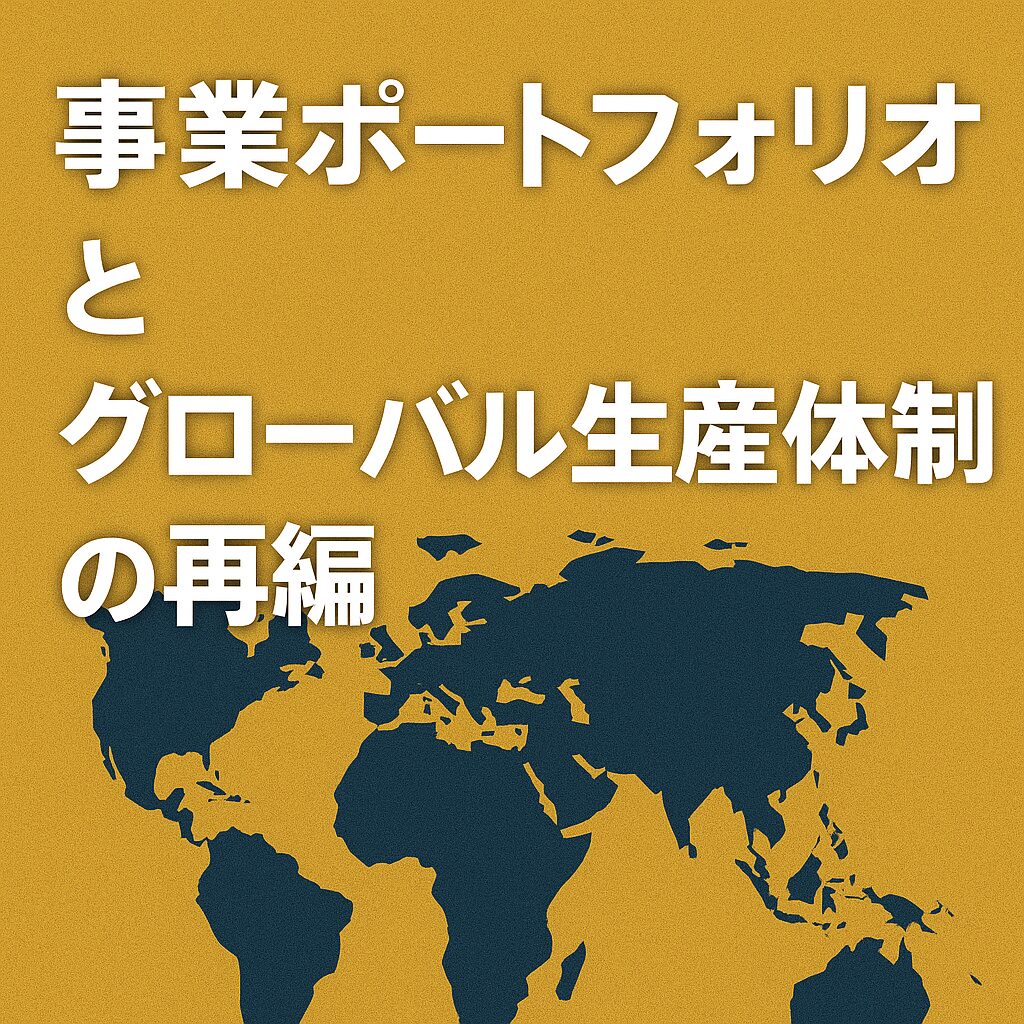
日産自動車は経営再建策「Re Nissan」の中核として、世界17工場を2030年度までに10工場へ集約し、年産能力を現在の約350万台から250万台へ絞り込む方針を掲げています。
これは固定費を抜本的に削減し、電動化とソフトウェア開発へ経営資源を大胆に再配分する狙いがあります。
国内:追浜撤退と九州集約で小型車とEVを一本化
追浜工場の生産終了後、小型車と主力EVの一部は日産九州工場へ段階的に移管されます。
同工場は高効率ラインを備え、地域行政と連携した再エネ電力調達を進めているため、カーボンフットプリントの低減にも寄与します。
追浜地区は研究所・衝突試験場・専用ふ頭を残し、鴻海とのEV実証拠点へ衣替えする可能性が高まっています。
欧州:サンダーランド+ギガファクトリーでEV集中投資
英国サンダーランド工場ではクロスオーバーEV「アリア」の次期モデルと小型EVを生産予定です。
隣接地にはAESC(旧日産電池)主導で総額約10億ポンド規模のバッテリー新工場が建設中で、2026年後半に稼働開始します。
車両と電池を同一サイトで生産する“電池一体工場”化により、物流コストを削減しながら欧州市場のCO₂規制へ迅速に対応する狙いです。
北米:キャパシティ調整とEV生産延期で柔軟化
米ミシシッピ州カントン工場はフルEV2車種の投入を2028〜2029年へ後ろ倒しし、当面はガソリン車・ハイブリッド車を維持生産します。
需要減速に合わせて投資タイミングを見直し、他社(ホンダ)との生産委託交渉も並行して進めることで稼働率と設備投資効率を最適化する方針です。
中南米:メキシコ・アグアスカリエンテスを小型SUVハブへ
メキシコのアグアスカリエンテスA1・A2ラインでは2025年型「キックス」に続き「マグナイト」の現地生産が検討されており、年産能力20万台規模で北米と中南米市場を同時に賄います。
為替差益とUSMCA関税優遇を生かせるため、コスト競争力の高い輸出拠点として位置付けられています。
アジア:タイ・中国・インド拠点の再定義
アジアでは中国・広州の合弁工場がEVセダンを集中生産し、タイのサムットプラカーン工場はピックアップトラックとe-POWER車に特化します。
インドではルノーとの共同開発SUVをKUSHIK(クシク)工場で組み立て、インド国内とアフリカ向けに輸出する体制を維持します。
これにより、高コスト地域の汎用ラインを整理し、各工場を“地域特化型”に再編するロードマップが描かれています。
ポートフォリオ再編がもたらす効果
- 固定費の削減:全社で年間約800億円の製造間接費圧縮を見込む。
- 投資効率の向上:EV・電池関連投資を主要5拠点に集中し、開発・設備を重複させない。
- カーボンニュートラル対応:地域ごとに再エネ調達スキームを組み込み、2030年度にスコープ1&2を40%削減。
グローバル生産体制は「規模の経済」ではなく「選択と集中」で競争力を高めるフェーズに入りました。
次章では、この再編に合わせて投資家が押さえておきたい株価指標と中期見通しを整理し、実践的な投資判断のチェックリストを提示します。
投資判断のためのチェックリスト 株価指標と中期見通し

ファンダメンタル指標の現状
2025年7月15日時点の株価は317円前後で推移しています。
実績ベースのPBRはおおむね0.2倍台と、上場自動車大手の中でも極端に割安圏に位置します。
一方、直近決算が最終赤字のためPERは算出不能となり、純利益回復が投資家の最大の関心事です。
自己資本比率は30%台後半で、財務体質は同業平均を若干下回りますが、キャッシュポジションは約1.6兆円あり短期流動性に不安はありません。
配当については経営再建期間中の無配継続を示唆しており、インcomeゲインよりもキャピタルゲイン狙いの銘柄だと位置づけられます。
株価テクニカルと需給
テクニカル面では25日移動平均線(330円近辺)が上値抵抗、心理的節目300円が下値支持として意識されています。
7月上旬に発行された転換社債による潜在的希薄化を嫌気し、出来高を伴う急落が生じましたが、信用買い残は3億株台でピーク時の半分以下に減少しており、需給圧迫の度合いは低下しつつあります。
逆に言えば、「悪材料一巡→売り方の買い戻し」が短期リバウンドの火種となる可能性を示唆します。
中期業績シナリオ
| 2025年度計画 | 2027年度計画 | 2030年度目標* | |
|---|---|---|---|
| 売上高(兆円) | 8.8 | 9.5 | 11.0 |
| 営業利益率 | 2.0% | 4.5% | 6.0% |
| EV販売比率 | 14% | 28% | 40% |
| 電池コスト対2023比 | ▲15% | ▲25% | ▲30% |
*会社説明会資料とCFO発言を基に筆者試算
2025年度は追浜関連の再編費用が膨らむため営業利益率は低空飛行が続きますが、九州・サンダーランド両工場でのEV量産が本格化する2027年度から利益率の改善軌道に乗る見通しです。
2030年度に営業利益率6%台、EV比率40%を達成できれば、総還元性向30%の復配余地が生まれるシナリオになります。
リスクとカタリスト
主なダウンサイド
- 北米金利高が長期化し販売回復が遅延
- 鴻海協業交渉の頓挫で追浜跡地の固定費が長期化
- 中国EV価格競争の激化による収益圧迫
主なアップサイド
- 転換社債の資金を用いたEVライン追加投資が想定超のリターンを創出
- 2026年前半に鴻海と正式合意し、追浜の稼働率が早期改善
- 半導体市況緩和で部材調達コストが想定より早く正常化
チェックリストまとめ
- PBR0.2倍という解散価値割れ水準が続くか
- 8月公表予定の再編費用見込みで悪材料が出尽くすか
- 鴻海との協業基本合意が年内に成立するか
- 2030年度EV販売比率40%目標へ進捗を確認できるか
- 復配タイミングを示す具体的ガイドが出るか
上記の「5つの鍵」を定点観測しながら、株価が300円前後で推移するうちはリスク限定・リターン拡大の余地があると判断できます。
次章では、投資判断のタイミングを占う主要イベントカレンダーと、記事全体の総括を行います。
今後の注目イベントとまとめ

直近イベントカレンダー
- 7月30日 FY2025第1四半期決算発表
追浜撤退に伴う一時費用の概算と、転換社債資金の使途が初めて示される予定です。
マーケットは「固定費圧縮の効果と損失計上のバランス」に注目しています。 - 10月29〜30日 Japan Mobility Show 2025プレスデー/10月30日〜11月9日一般公開
日産は次期「アリア」と三代目「リーフ」のコンセプトモデルを披露する見込みです。
鴻海MIHプラットフォームとの連携を示唆する車両が登場すれば、協業交渉の進展が具体化するシグナルになるでしょう。 - 年内目標 鴻海との基本合意書締結
追浜再活用の青写真が固まり次第、雇用維持策と生産計画の詳細が公表される見通しです。
投資家にとっては株価回復の最速トリガーになり得ます。 - 2026年前半 EV用ギガファクトリー着工(英国サンダーランド)
電池一体工場の建設開始で欧州戦略が加速し、CO₂規制対応の競争力が強化される段階へ入ります。
記事全体の総括
日産は株価下落、追浜撤退という「守り」のニュースばかりが目につきますが、その裏で固定費削減とEV集中投資という二段ロケットを着々と準備しています。
株価はPBR0.2倍台と解散価値を下回る水準に放置されており、悪材料出尽くし→成長材料顕在化が揃うタイミングでリバウンド余地が生まれる構図です。
投資判断の鍵は、
- 第1四半期決算で示される再編費用とEV投資配分
- 年内に予定される鴻海との協業基本合意
- Japan Mobility Showでの新型EVとプラットフォーム発表
――この三点です。
これらを定点観測しながら、心理的節目300円前後での押し目形成を待つ戦略がリスク管理の面でも有効と考えます。
大きな変革期を迎えた日産は「守りを固めてから攻める」段階に差し掛かりました。
本記事が、読者の皆さまが次の一手を見極める際の羅針盤となれば幸いです。
ただ・・・
まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。
ずんのInstagramでは、
- 資産1000万までのノウハウ
- 申請したらもらえるお金
- 高配当株など普段は表に出ない投資情報
などを中心に、
今回お伝えできなかった金融ノウハウも
余すことなくお伝えしています。
まずはInstagramをフォローしていただき、
ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!
無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。
